5 / 28
5
しおりを挟む
「……ふむ」
私は腕組みをして、眉間に深い皺を寄せた。
私の目の前には、専属メイドに任命されたばかりのロッテが、直立不動で震えている。
「あ、あの……エマール様? ボタンの付け替えは終わりましたけど……な、何か不備がございましたでしょうかぁ……?」
「ロッテ。この部屋の『備品管理リスト』と、現物の照合が終わりました」
私はサイドテーブルに置いてあった、革表紙の台帳を指差した。
休息を取れとクラウス様に言われたが、ベッドでただ横になっているなど、時間の浪費以外の何物でもない。
私は部屋にあった備品リストを見つけ出し、この一時間、棚卸し作業を行っていたのだ。
「け、結果は……?」
「最悪です」
私が低く告げると、ロッテが「ひいぃっ!」と悲鳴を上げた。
「ご、ごめんなさいぃ! 掃除が行き届いていないのは私の責任ですぅ! 窓の桟(さん)の埃ですよね? それともカーペットの染みですか? お許しください、お許しくださいぃ!」
ロッテは床に額を擦り付けて謝罪を始めた。
王都の噂では、私が「部屋に埃が一つあっただけでメイドの髪を切り落とした」ことになっているらしい。
なんて非効率な体罰だろうか。髪を切ったところで埃はなくならないし、メイドのモチベーションが下がるだけだ。
「顔をお上げなさい、ロッテ。私は埃や染みの話などしていません」
「へ……?」
ロッテが恐る恐る顔を上げる。
「確かに、窓の桟には三日分ほどの埃が堆積していますし、カーペットの染みは紅茶をこぼしてから迅速な処理を怠った証拠です。これらは美観を損ね、衛生環境を悪化させる『マイナス要因』ですが……」
私は一拍置き、台帳をバンッ!と叩いた。
「私が許せないのは、こちらの『数字のズレ』です!」
「す、数字……?」
「見てください。このリストには『クリスタル製の花瓶:2個』と記載されています。しかし、室内には1個しかありません。残り1個はどこへ?」
「え、えっと……それは……以前、掃除の際に割れてしまったと聞いております……」
「割れた? ならば『破損廃棄届』が出され、リストから削除されているはずです。なぜ残っているのですか? これでは資産価値が過大計上されたままです!」
私は赤ペンを取り出し、該当箇所を二重線で抹消した。
「いいですか、ロッテ。埃は掃除すれば消えます。しかし、帳簿のズレは放置すればするほど、組織の信用という根幹を腐らせるのです。物理的な汚れよりも、データの汚れの方が罪深いと知りなさい!」
「は、はいぃっ! 勉強になりますぅ!」
ロッテが目を輝かせて(涙目だが)頷く。
どうやら彼女は、私が理不尽な暴力で支配するタイプではなく、理屈っぽいだけの数字オタクだと薄々気づき始めたようだ。
その時、コンコン、とドアがノックされた。
「入るぞ」
返事をする間もなく、クラウス様が入室してくる。
彼は軍服から、リラックスした夜会服に着替えていた。その姿もまた絵になりすぎていて、目の保養……いや、視覚情報の過剰摂取で目がくらむ。
「……やはり、寝ていなかったか」
クラウス様は、私が広げた台帳と赤ペンを見て、呆れたように、しかしどこか嬉しそうに口角を上げた。
「休息も業務命令だと言ったはずだが?」
「頭脳労働は私にとっての休息です。それに、この部屋の棚卸しだけで三箇所もの記載ミスが見つかりました。これを放置して眠ることなど、生理的に不可能です」
私が胸を張って答えると、クラウス様はクスクスと笑った。
「君は本当に、数字の番人だな。……まあいい。夕食の準備が整った。食堂へ行こう」
クラウス様が腕を差し出す。
私はその腕に手を添え、部屋を出た。
ロッテが慌てて後ろをついてくる。
「ところで閣下。この屋敷の『メイド長』はどなたですか?」
廊下を歩きながら、私は尋ねた。
先ほどの部屋の管理不備。あれは末端のメイドの責任ではない。管理者の怠慢だ。
「メイド長か? ミセス・マーガレットだ。古株で、私の乳母代わりでもあった。……少々、頭の固いところがあるが」
「頭が固いのは構いません。数字にルーズなのが問題です」
「何かあったのか?」
「部屋の備品管理が杜撰(ずさん)です。おそらく、屋敷全体で相当数の『行方不明資産』があるはずです。早急に是正勧告を行う必要があります」
私が眼鏡の位置を直す仕草(伊達眼鏡ではないが、心の目で装着している)をすると、クラウス様は苦笑した。
「お手柔らかに頼むよ。彼女はプライドが高い」
「プライドで赤字は埋まりません」
バッサリと切り捨てると、私たちは一階の食堂に到着した。
重厚な両開きの扉が開かれる。
「お待ちしておりました、旦那様。そして……エマール様」
出迎えたのは、五十代半ばと思われる、恰幅の良い女性だった。
ひっつめ髪に、糊の効いたメイド服。その目つきは鋭く、私を見る視線には明らかな敵意――あるいは「値踏み」の色が浮かんでいる。
彼女が、メイド長のマーガレットだろう。
「ようこそ、辺境伯邸へ。メイド長のマーガレットでございます。……噂に名高い『悪役令嬢』様をお迎えできて、身の引き締まる思いですわ」
丁寧な言葉遣いだが、語尾にトゲがある。
「噂に名高い」という部分を強調したあたり、嫌味のセンスはなかなかだ。
周囲に控えるメイドたちが、ピリピリとした空気に飲まれて震えている。
これは、いわゆる「新参者の女主人」に対する、古株使用人による洗礼(マウンティング)というやつだろう。
通常なら、ここで萎縮するか、あるいは権力を笠に着て怒鳴り散らすのがセオリーだ。
だが、私はエマール。
感情バトルには興味がない。
「ご丁寧にありがとうございます、マーガレットさん。……ところで」
私は彼女の挨拶をスルーして、食堂のテーブルへと歩み寄った。
そこには、二人分とは思えない量の料理が並べられている。
前菜だけで五種類。スープ、魚料理、肉料理は大皿で三つ。デザートのタワーまである。
「これは、歓迎会用の特別メニューですか?」
私が尋ねると、マーガレットは鼻を鳴らした。
「いいえ。旦那様の普段のお食事ですわ。当家は武門の家柄。体力を使う旦那様のために、常に最高かつ豊富な種類の料理を用意するのが、代々の習わしとなっております」
彼女は胸を張った。
「王都の貧弱な令嬢様には、少々刺激が強すぎるかもしれませんが? お口に合わなければ、お粥でもご用意させますが」
挑発だ。
「田舎の料理だと馬鹿にするなよ」という牽制と、「お前ごときに当家の伝統が分かるか」というプライドが見え隠れする。
クラウス様が何か言いかけようとするのを、私は手で制した。
そして、静かに告げた。
「……廃棄率は、何パーセントですか?」
「は?」
マーガレットの眉が跳ね上がった。
「これだけの量、成人男性一人で食べきれるはずがありません。残った料理はどうしているのですか? 使用人の賄(まかな)いに回すとしても、高級食材をそのまま出すわけにはいかないでしょう。衛生管理上、保存も難しい。つまり、大半を捨てているのではありませんか?」
「そ、それは……! 当家の品格を保つためには、必要なゆとりです! 食べ残しが出るほど用意するのが、貴族の豊かさの証明……」
「それは一昔前の価値観です」
私はテーブルの上のローストビーフを指差した。
「この肉は、領内産の『スノー・バイソン』の希少部位ですね? 市場価格でキロあたり金貨二枚。それを毎日、廃棄前提で並べるなど、生産者への冒涜であり、経済合理性を欠いた愚行です」
「ぐ……っ!」
「さらに言えば、メニュー構成がタンパク質に偏りすぎています。これでは痛風のリスクが高まるだけです。医療費という将来的なコスト増大を招くつもりですか?」
私はマーガレットに向き直り、ニッコリと微笑んだ。
「品格とは、皿の数ではありません。素材を活かし、食べる人の健康を考え、無駄を出さない『知性』にこそ宿るものです」
食堂が、水を打ったように静まり返った。
マーガレットの顔が、怒りで赤くなり、次に青くなり、最後には真っ白になった。
彼女が最も誇りに思っていた「旦那様への献身」の方向性が、間違っていると指摘されたのだ。しかも、ド正論で。
「……ふっ、くくっ……!」
沈黙を破ったのは、またしてもクラウス様の笑い声だった。
「ははは! 痛風のリスクか! 確かに、最近少し胃が重いと思っていたんだ」
彼は椅子に座り、私に手招きをした。
「座りたまえ、エマール。君の言う通りだ。だが、作ってしまったものを捨てるのは、それこそ無駄だ。まずはいただこう。……改善策は、食べながら聞かせてもらえるか?」
「ええ、喜んで。まずはこの過剰なメニューの見直しと、食材の発注サイクルの最適化について提案があります」
私は席に着き、ナプキンを広げた。
マーガレットは呆然と立ち尽くしていたが、私が「スープが冷めますよ。給仕をお願いします」と声をかけると、ハッとして動き出した。
その手つきは先ほどまでの尊大さが消え、どこか私の顔色を窺うような、慎重なものに変わっていた。
(……ふむ。まずはジャブ程度ね)
私は絶品のスープを口に運びながら、心の中で計算した。
この屋敷の改革、想定よりもやりがいがありそうだ。
「美味しい」
私が素直に感想を漏らすと、マーガレットの肩がビクリと跳ねた。
「味は一流です。シェフの腕は確かですね。……だからこそ、その腕を『捨てる料理』を作るために使わせるのは、人件費の最大の無駄遣いだと思いますわ」
私の言葉に、奥の厨房への扉がわずかに開いた気がした。
聞き耳を立てていたシェフたちが、震え上がっているのか、それとも感動しているのか。
それは、明日の厨房視察で明らかになるだろう。
私は腕組みをして、眉間に深い皺を寄せた。
私の目の前には、専属メイドに任命されたばかりのロッテが、直立不動で震えている。
「あ、あの……エマール様? ボタンの付け替えは終わりましたけど……な、何か不備がございましたでしょうかぁ……?」
「ロッテ。この部屋の『備品管理リスト』と、現物の照合が終わりました」
私はサイドテーブルに置いてあった、革表紙の台帳を指差した。
休息を取れとクラウス様に言われたが、ベッドでただ横になっているなど、時間の浪費以外の何物でもない。
私は部屋にあった備品リストを見つけ出し、この一時間、棚卸し作業を行っていたのだ。
「け、結果は……?」
「最悪です」
私が低く告げると、ロッテが「ひいぃっ!」と悲鳴を上げた。
「ご、ごめんなさいぃ! 掃除が行き届いていないのは私の責任ですぅ! 窓の桟(さん)の埃ですよね? それともカーペットの染みですか? お許しください、お許しくださいぃ!」
ロッテは床に額を擦り付けて謝罪を始めた。
王都の噂では、私が「部屋に埃が一つあっただけでメイドの髪を切り落とした」ことになっているらしい。
なんて非効率な体罰だろうか。髪を切ったところで埃はなくならないし、メイドのモチベーションが下がるだけだ。
「顔をお上げなさい、ロッテ。私は埃や染みの話などしていません」
「へ……?」
ロッテが恐る恐る顔を上げる。
「確かに、窓の桟には三日分ほどの埃が堆積していますし、カーペットの染みは紅茶をこぼしてから迅速な処理を怠った証拠です。これらは美観を損ね、衛生環境を悪化させる『マイナス要因』ですが……」
私は一拍置き、台帳をバンッ!と叩いた。
「私が許せないのは、こちらの『数字のズレ』です!」
「す、数字……?」
「見てください。このリストには『クリスタル製の花瓶:2個』と記載されています。しかし、室内には1個しかありません。残り1個はどこへ?」
「え、えっと……それは……以前、掃除の際に割れてしまったと聞いております……」
「割れた? ならば『破損廃棄届』が出され、リストから削除されているはずです。なぜ残っているのですか? これでは資産価値が過大計上されたままです!」
私は赤ペンを取り出し、該当箇所を二重線で抹消した。
「いいですか、ロッテ。埃は掃除すれば消えます。しかし、帳簿のズレは放置すればするほど、組織の信用という根幹を腐らせるのです。物理的な汚れよりも、データの汚れの方が罪深いと知りなさい!」
「は、はいぃっ! 勉強になりますぅ!」
ロッテが目を輝かせて(涙目だが)頷く。
どうやら彼女は、私が理不尽な暴力で支配するタイプではなく、理屈っぽいだけの数字オタクだと薄々気づき始めたようだ。
その時、コンコン、とドアがノックされた。
「入るぞ」
返事をする間もなく、クラウス様が入室してくる。
彼は軍服から、リラックスした夜会服に着替えていた。その姿もまた絵になりすぎていて、目の保養……いや、視覚情報の過剰摂取で目がくらむ。
「……やはり、寝ていなかったか」
クラウス様は、私が広げた台帳と赤ペンを見て、呆れたように、しかしどこか嬉しそうに口角を上げた。
「休息も業務命令だと言ったはずだが?」
「頭脳労働は私にとっての休息です。それに、この部屋の棚卸しだけで三箇所もの記載ミスが見つかりました。これを放置して眠ることなど、生理的に不可能です」
私が胸を張って答えると、クラウス様はクスクスと笑った。
「君は本当に、数字の番人だな。……まあいい。夕食の準備が整った。食堂へ行こう」
クラウス様が腕を差し出す。
私はその腕に手を添え、部屋を出た。
ロッテが慌てて後ろをついてくる。
「ところで閣下。この屋敷の『メイド長』はどなたですか?」
廊下を歩きながら、私は尋ねた。
先ほどの部屋の管理不備。あれは末端のメイドの責任ではない。管理者の怠慢だ。
「メイド長か? ミセス・マーガレットだ。古株で、私の乳母代わりでもあった。……少々、頭の固いところがあるが」
「頭が固いのは構いません。数字にルーズなのが問題です」
「何かあったのか?」
「部屋の備品管理が杜撰(ずさん)です。おそらく、屋敷全体で相当数の『行方不明資産』があるはずです。早急に是正勧告を行う必要があります」
私が眼鏡の位置を直す仕草(伊達眼鏡ではないが、心の目で装着している)をすると、クラウス様は苦笑した。
「お手柔らかに頼むよ。彼女はプライドが高い」
「プライドで赤字は埋まりません」
バッサリと切り捨てると、私たちは一階の食堂に到着した。
重厚な両開きの扉が開かれる。
「お待ちしておりました、旦那様。そして……エマール様」
出迎えたのは、五十代半ばと思われる、恰幅の良い女性だった。
ひっつめ髪に、糊の効いたメイド服。その目つきは鋭く、私を見る視線には明らかな敵意――あるいは「値踏み」の色が浮かんでいる。
彼女が、メイド長のマーガレットだろう。
「ようこそ、辺境伯邸へ。メイド長のマーガレットでございます。……噂に名高い『悪役令嬢』様をお迎えできて、身の引き締まる思いですわ」
丁寧な言葉遣いだが、語尾にトゲがある。
「噂に名高い」という部分を強調したあたり、嫌味のセンスはなかなかだ。
周囲に控えるメイドたちが、ピリピリとした空気に飲まれて震えている。
これは、いわゆる「新参者の女主人」に対する、古株使用人による洗礼(マウンティング)というやつだろう。
通常なら、ここで萎縮するか、あるいは権力を笠に着て怒鳴り散らすのがセオリーだ。
だが、私はエマール。
感情バトルには興味がない。
「ご丁寧にありがとうございます、マーガレットさん。……ところで」
私は彼女の挨拶をスルーして、食堂のテーブルへと歩み寄った。
そこには、二人分とは思えない量の料理が並べられている。
前菜だけで五種類。スープ、魚料理、肉料理は大皿で三つ。デザートのタワーまである。
「これは、歓迎会用の特別メニューですか?」
私が尋ねると、マーガレットは鼻を鳴らした。
「いいえ。旦那様の普段のお食事ですわ。当家は武門の家柄。体力を使う旦那様のために、常に最高かつ豊富な種類の料理を用意するのが、代々の習わしとなっております」
彼女は胸を張った。
「王都の貧弱な令嬢様には、少々刺激が強すぎるかもしれませんが? お口に合わなければ、お粥でもご用意させますが」
挑発だ。
「田舎の料理だと馬鹿にするなよ」という牽制と、「お前ごときに当家の伝統が分かるか」というプライドが見え隠れする。
クラウス様が何か言いかけようとするのを、私は手で制した。
そして、静かに告げた。
「……廃棄率は、何パーセントですか?」
「は?」
マーガレットの眉が跳ね上がった。
「これだけの量、成人男性一人で食べきれるはずがありません。残った料理はどうしているのですか? 使用人の賄(まかな)いに回すとしても、高級食材をそのまま出すわけにはいかないでしょう。衛生管理上、保存も難しい。つまり、大半を捨てているのではありませんか?」
「そ、それは……! 当家の品格を保つためには、必要なゆとりです! 食べ残しが出るほど用意するのが、貴族の豊かさの証明……」
「それは一昔前の価値観です」
私はテーブルの上のローストビーフを指差した。
「この肉は、領内産の『スノー・バイソン』の希少部位ですね? 市場価格でキロあたり金貨二枚。それを毎日、廃棄前提で並べるなど、生産者への冒涜であり、経済合理性を欠いた愚行です」
「ぐ……っ!」
「さらに言えば、メニュー構成がタンパク質に偏りすぎています。これでは痛風のリスクが高まるだけです。医療費という将来的なコスト増大を招くつもりですか?」
私はマーガレットに向き直り、ニッコリと微笑んだ。
「品格とは、皿の数ではありません。素材を活かし、食べる人の健康を考え、無駄を出さない『知性』にこそ宿るものです」
食堂が、水を打ったように静まり返った。
マーガレットの顔が、怒りで赤くなり、次に青くなり、最後には真っ白になった。
彼女が最も誇りに思っていた「旦那様への献身」の方向性が、間違っていると指摘されたのだ。しかも、ド正論で。
「……ふっ、くくっ……!」
沈黙を破ったのは、またしてもクラウス様の笑い声だった。
「ははは! 痛風のリスクか! 確かに、最近少し胃が重いと思っていたんだ」
彼は椅子に座り、私に手招きをした。
「座りたまえ、エマール。君の言う通りだ。だが、作ってしまったものを捨てるのは、それこそ無駄だ。まずはいただこう。……改善策は、食べながら聞かせてもらえるか?」
「ええ、喜んで。まずはこの過剰なメニューの見直しと、食材の発注サイクルの最適化について提案があります」
私は席に着き、ナプキンを広げた。
マーガレットは呆然と立ち尽くしていたが、私が「スープが冷めますよ。給仕をお願いします」と声をかけると、ハッとして動き出した。
その手つきは先ほどまでの尊大さが消え、どこか私の顔色を窺うような、慎重なものに変わっていた。
(……ふむ。まずはジャブ程度ね)
私は絶品のスープを口に運びながら、心の中で計算した。
この屋敷の改革、想定よりもやりがいがありそうだ。
「美味しい」
私が素直に感想を漏らすと、マーガレットの肩がビクリと跳ねた。
「味は一流です。シェフの腕は確かですね。……だからこそ、その腕を『捨てる料理』を作るために使わせるのは、人件費の最大の無駄遣いだと思いますわ」
私の言葉に、奥の厨房への扉がわずかに開いた気がした。
聞き耳を立てていたシェフたちが、震え上がっているのか、それとも感動しているのか。
それは、明日の厨房視察で明らかになるだろう。
11
あなたにおすすめの小説


白い結婚で結構ですわ。愛人持ちの夫に興味はありません
鍛高譚
恋愛
公爵令嬢ルチアーナは、王太子アルベルトとの政略結婚を命じられた。だが彼にはすでに愛する女性がいた。そこでルチアーナは、夫婦の義務を果たさない“白い結婚”を提案し、お互いに干渉しない関係を築くことに成功する。
「夫婦としての役目を求めないでくださいませ。その代わり、わたくしも自由にさせていただきますわ」
そうして始まった王太子妃としての優雅な生活。社交界では完璧な妃を演じつつ、裏では趣味の読書やお茶会を存分に楽しみ、面倒ごととは距離を置くつもりだった。
——だが、夫は次第にルチアーナを気にし始める。
「最近、おまえが気になるんだ」
「もっと夫婦としての時間を持たないか?」
今さらそんなことを言われても、もう遅いのですわ。
愛人を優先しておいて、後になって本妻に興味を持つなんて、そんな都合の良い話はお断り。
わたくしは、自由を守るために、今日も紅茶を嗜みながら優雅に過ごしますわ——。
政略結婚から始まる痛快ざまぁ! 夫の後悔なんて知りませんわ
“白い結婚”を謳歌する令嬢の、自由気ままなラブ&ざまぁストーリー!

何も決めなかった王国は、静かに席を失う』
ふわふわ
恋愛
王太子の婚約者として、
表には立たず、裏で国を支えてきた公爵令嬢ネフェリア。
だが――
彼女が追い出されたのは、嫉妬でも陰謀でもなかった。
ただ一つ、「決める役割」を、国が彼女一人に押しつけていたからだ。
婚約破棄の後、ネフェリアを失った王国は変わろうとする。
制度を整え、会議を重ね、慎重に、正しく――
けれどその“正しさ”は、何一つ決断を生まなかった。
一方、帝国は違った。
完璧ではなくとも、期限内に返事をする。
責任を分け、判断を止めない。
その差は、やがて「呼ばれない会議」「残らない席」「知らされない決定」となって現れる。
王国は滅びない。
だが、何も決めない国は、静かに舞台の外へ追いやられていく。
――そして迎える、最後の選択。
これは、
剣も魔法も振るわない“静かなざまぁ”。
何も決めなかった過去に、国そのものが向き合う物語。
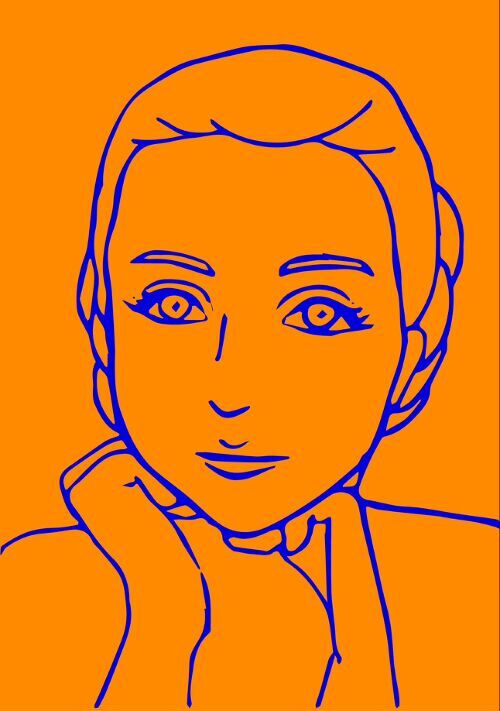
【完結】婚約破棄と言われても個人の意思では出来ません
狸田 真 (たぬきだ まこと)
恋愛
【あらすじ】
第一王子ヴィルヘルムに婚約破棄を宣言された公爵令嬢クリスチナ。しかし、2人の婚約は国のため、人民のためにする政略結婚を目的としたもの。
個人の意思で婚約破棄は出来ませんよ?
【楽しみ方】
笑い有り、ラブロマンス有りの勘違いコメディ作品です。ボケキャラが多数登場しますので、是非、突っ込みを入れながらお楽しみ下さい。感想欄でもお待ちしております! 突っ込み以外の真面目な感想や一言感想などもお気軽にお寄せ下さい。
【注意事項】
安心安全健全をモットーに、子供でも読める作品を目指しておりますが、物語の後半で、大人のロマンスが描写される予定です。直接的な表現は省き、詩的な表現に変換しておりますが、苦手な方はご注意頂ければと思います。
また、愛の伝道師・狸田真は、感想欄のお返事が初対面でも親友みたいな馴れ馴れしいコメントになる事がございます。ご容赦頂けると幸いです。

断罪の準備は完璧です!国外追放が楽しみすぎてボロが出る
黒猫かの
恋愛
「ミモリ・フォン・ラングレイ! 貴様との婚約を破棄し、国外追放に処す!」
パルマ王国の卒業パーティー。第一王子アリオスから突きつけられた非情な断罪に、公爵令嬢ミモリは……内心でガッツポーズを決めていた。
(ついにきたわ! これで堅苦しい王妃教育も、無能な婚約者の世話も、全部おさらばですわ!)

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
私は、夫にも子供にも選ばれなかった。
その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。
そこで待っていたのは、最悪の出来事――
けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。
夫は愛人と共に好きに生きればいい。
今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。
でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。
妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。
過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――

どうやら婚約者の隣は私のものではなくなってしまったようなので、その場所、全てお譲りします。
皇 翼
恋愛
侯爵令嬢という何でも買ってもらえてどんな教育でも施してもらえる恵まれた立場、王太子という立場に恥じない、童話の王子様のように顔の整った婚約者。そして自分自身は最高の教育を施され、侯爵令嬢としてどこに出されても恥ずかしくない教養を身につけていて、顔が綺麗な両親に似たのだろう容姿は綺麗な方だと思う。
完璧……そう、完璧だと思っていた。自身の婚約者が、中庭で公爵令嬢とキスをしているのを見てしまうまでは――。

挙式後すぐに離婚届を手渡された私は、この結婚は予め捨てられることが確定していた事実を知らされました
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
【結婚した日に、「君にこれを預けておく」と離婚届を手渡されました】
今日、私は子供の頃からずっと大好きだった人と結婚した。しかし、式の後に絶望的な事を彼に言われた。
「ごめん、本当は君とは結婚したくなかったんだ。これを預けておくから、その気になったら提出してくれ」
そう言って手渡されたのは何と離婚届けだった。
そしてどこまでも冷たい態度の夫の行動に傷つけられていく私。
けれどその裏には私の知らない、ある深い事情が隠されていた。
その真意を知った時、私は―。
※暫く鬱展開が続きます
※他サイトでも投稿中
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















