7 / 28
7
しおりを挟む
「……それで、これがその手紙ですか?」
私は執務机の上にある、毒々しいほど派手な封蝋(ふうろう)が押された手紙を見下ろした。
執事のハンスが、まるで爆発物を扱うかのように身を縮めている。
「は、はい。王都からの急使が届けてまいりました。『至急、エマールに読ませろ』とのことです」
「開封します。ペーパーナイフを」
「お、お気をつけて……毒が入っているかもしれません」
「レイド殿下にそんな知能はありません。あるとすれば、香水による嗅覚へのテロ行為くらいでしょう」
私は手際よく封筒を切り裂いた。
案の定、封筒からはムッとするような薔薇の香りが漂い出た。
(……香水代の無駄遣いね。この濃度、瓶の半分は使っているわ)
私は鼻をつまみながら、手紙を広げた。
そこには、ミミズがのたうち回ったような文字で、こう書かれていた。
『エマールへ。僕だ、レイドだ。
今すぐ王都へ戻ってこい。
シルフィが新しいドレスを欲しがっているんだが、王家の財務官がうるさくて買えない。
お前の実家の金で何とかしろ。
あと、僕の部屋の掃除もしてくれ。
戻ってきたら、側室にしてやらなくもないぞ。
感謝しろ。愛をこめて。レイド』
「……」
私は無言で、手紙を机の上に置いた。
ハンスが恐る恐る尋ねる。
「あ、あの……なんと書いてありましたか? やはり、脅迫状……?」
「いいえ。ただの『知性欠如証明書』です」
私は即座に、手元の『保留』トレイ……ではなく、『要・添削』トレイに手紙を放り込んだ。
「ハンス、後で赤ペンと辞書を用意してください。誤字脱字が十七箇所、文法の間違いが五箇所、論理的破綻が全行にあります。添削して突き返します」
「て、添削ですか……?」
「ええ。元婚約者としての、最後の手向け(教育的指導)です」
私が淡々と告げると、ハンスはポカンとした後、吹き出しそうになるのを必死で堪えていた。
「かしこまりました。……あ、それとエマール様。旦那様がお呼びです」
「閣下が? こんな夜更けに?」
時計を見ると、もう夜の十時を回っていた。
就業規則的には残業時間だ。超過勤務手当を請求せねばならない。
「はい。『私の部屋に来るように』とのことです」
「……分かりました」
私は少し身構えた。
夜に寝室へ呼び出し。
契約上の「白い結婚(書類上の夫婦)」とはいえ、相手はあの美貌の辺境伯だ。
もしや、大人の駆け引き(ロマンス)が始まるのだろうか?
(……いや、ないわね。きっと明日の予算会議の予習でしょう)
私は手帳と筆記用具を携え、クラウス様の私室へと向かった。
◇
「失礼します」
重厚な扉をノックして中に入ると、クラウス様はソファに座り、月明かりの下でグラスを傾けていた。
その姿があまりにも絵になりすぎていて、私は一瞬、息を呑んだ。
(……この方の顔面偏差値は、インフレを起こしているわね)
「来たか、エマール。座ってくれ」
クラウス様が向かいの席を勧める。
テーブルの上には、書類も計算機もない。
あるのは、豪奢なベルベットの小箱が一つだけ。
「……お話とは、なんでしょうか? 明日の視察ルートの変更ですか? それとも、レイド殿下からの手紙の件?」
私が尋ねると、クラウス様は首を横に振った。
「いや、仕事の話ではない。……約束の品が届いたんだ」
「約束?」
「忘れたのか? 昨日の夜、君が『欲しい』と言ったものだ」
クラウス様は、テーブルの上の小箱を、指先ですっと私の方へ押し出した。
「開けてみてくれ」
私はゴクリと喉を鳴らし、箱に手を伸ばした。
(まさか、本当に……?)
震える手で蓋を開ける。
そこには、黒いベルベットの海に沈むように、一本の万年筆が鎮座していた。
「っ……!!」
私は思わず声を上げた。
それは、単なる筆記具の域を超えていた。
軸は漆黒のエボナイト製で、手に吸い付くような艶がある。
キャップのリング部分には、ヴァイサリウス家の紋章である「氷狼」が精緻な彫金で施され、その目には極小のサファイアが埋め込まれている。
そして何より、ペン先。
18金の大型ニブが、黄金の輝きを放っている。
「こ、これは……王都の老舗『モンブラン・ロイヤル』の限定モデル、マイスター・シュテュックの特注品……!?」
「ああ。君の手に合うように、重心バランスを調整させた。インクフローも、君の計算速度に追いつけるよう、潤沢に出る設定にしてある」
「す、すごいです……!」
私は箱から万年筆を取り出した。
手に持った瞬間、その完璧な重量バランスに鳥肌が立った。
重すぎず、軽すぎず。まるで指の一部になったかのような一体感。
「試し書きをしても?」
「もちろん」
私は持参していた手帳を開き、サラサラと数字を書き連ねた。
『1,234,567,890...』
「……!!」
滑らかだ。
氷の上を滑るスケートのように、ペン先が紙の上を走る。
カリカリという不快な摩擦音は皆無。ただ、インクが紙に染み込む心地よい感触だけがある。
「素晴らしいです! これなら、決算処理のスピードが通常の1.5倍は向上します! 複利計算も微分積分も、ストレスなく行えます!」
私は興奮のあまり、頬を紅潮させて叫んだ。
「見てください、閣下! このインクの濃淡! 払いと止めの美しさ! 最高です! どんな宝石よりも価値があります!」
私は万年筆を両手で包み込み、うっとりと頬ずりをした。
「ありがとう、万年筆さん。これから私の相棒として、共に赤字を殲滅しましょうね……」
「……」
ふと気配を感じて顔を上げると、クラウス様が口元を手で覆い、肩を震わせていた。
「か、閣下?」
「……いや、すまない。君がそこまで喜ぶとは」
クラウス様は顔を上げ、優しく目を細めた。
「普通の令嬢なら、『綺麗な宝石!』とか『素敵なドレス!』と喜ぶ場面なんだが……君は、『インクの濃淡』と『計算速度』に感動するんだな」
「当然です。宝石は眺めるだけですが、この万年筆は『価値を生み出す』道具ですから。投資対効果(ROI)が段違いです」
「ふっ……。本当に、君はブレないな」
クラウス様は立ち上がり、私の隣に座った。
そして、私の手にある万年筆を、私ごと包み込むように手を重ねた。
「っ!?」
温かい体温が伝わってくる。
「気に入ってくれてよかった。……だが、エマール」
「は、はい」
「その万年筆にばかり頬ずりされると、贈り主としては少々、嫉妬するのだが」
クラウス様の顔が近い。
アイスブルーの瞳が、熱を帯びて私を見つめている。
「え、あ、その……」
「私にも、感謝の言葉以上の『報酬』はないのか?」
「ほ、報酬……?」
私は混乱した頭で計算を試みた。
(高価なプレゼントに対する対価。通常であれば、同等額の返礼品。しかし、私の現在の資産ではこの万年筆に見合うものは用意できない。となると、労働力での提供か、あるいは……)
「計算しなくていい」
クラウス様が、私の思考を遮るように囁く。
「答えは、感情で出すものだ」
彼は私の顎をそっと持ち上げた。
唇が、触れるか触れないかの距離まで近づく。
「……っ」
私は思わず目を閉じた。
(これは……キスされる!? ファーストキスが、計算機も帳簿もない、こんなロマンチックなシチュエーションで!?)
心臓が早鐘を打つ。
しかし。
「……今日は、勘弁してやろう」
ふわり、と。
額(ひたい)に、柔らかい感触が落ちただけだった。
目を開けると、クラウス様がいたずらっ子のように笑っていた。
「緊張で気絶されては困るからな。……それに、今日はその万年筆とイチャイチャしたいのだろう?」
「うっ……! 否定できません……」
「大事に使えよ、私の『最強の経理担当』」
クラウス様は私の頭をポンポンと撫でると、ソファから立ち上がった。
「もう遅い。部屋に戻って休め。……あ、そうそう。レイドからの手紙だが」
「はい」
「添削が終わったら、私にも見せてくれ。王家への『抗議文』として、正式に送り返してやるから」
「ふふ、承知いたしました。徹底的に赤を入れたものを提出します」
「楽しみにしている」
部屋を出る際、私はもう一度振り返った。
クラウス様はグラスを片手に、優しい眼差しで私を見送ってくれていた。
廊下に出た私は、胸に抱いた万年筆をギュッと握りしめた。
「……計算外だわ」
万年筆の冷たい感触とは裏腹に、私の顔は火が出るほど熱かった。
「この胸の高鳴り……。不整脈でも、カフェインの過剰摂取でもないとしたら……」
私は首を振り、早足で自室へと向かった。
認めてしまえば、きっと私の「鉄壁の理性」が崩壊してしまう。
今はまだ、このドキドキは「新しい文房具を手に入れた興奮」という項目で計上しておこう。
そう、自分に言い聞かせながら。
◇
翌日。
私は早朝から執務室に籠り、鬼の形相でペンを走らせていた。
昨夜の甘い余韻?
そんなものは、朝のコーヒーと共に胃の中に流し込んだ。
今の私の目の前にあるのは、レイド殿下からの「ゴミ手紙」だ。
「……ここも違う! 『愛』のスペルが間違っている! 『I』じゃなくて『Ai』と書くなんて、どこの田舎の方言ですか!?」
昨夜もらった万年筆の滑らかな書き心地を堪能しながら、私はレイド殿下の手紙を真っ赤に染め上げていく。
「ハンス! 辞書を持ってきて! あと、王家への請求書ドラフトも!」
「は、はいっ! ただいま!」
執務室に、私の怒号と、ハンスの悲鳴と、そして万年筆が走る軽快な音が響き渡る。
ここから、私とクラウス様による、元婚約者と王家への「倍返し」……いいえ、「正当なる債権回収」が始まるのである。
私は執務机の上にある、毒々しいほど派手な封蝋(ふうろう)が押された手紙を見下ろした。
執事のハンスが、まるで爆発物を扱うかのように身を縮めている。
「は、はい。王都からの急使が届けてまいりました。『至急、エマールに読ませろ』とのことです」
「開封します。ペーパーナイフを」
「お、お気をつけて……毒が入っているかもしれません」
「レイド殿下にそんな知能はありません。あるとすれば、香水による嗅覚へのテロ行為くらいでしょう」
私は手際よく封筒を切り裂いた。
案の定、封筒からはムッとするような薔薇の香りが漂い出た。
(……香水代の無駄遣いね。この濃度、瓶の半分は使っているわ)
私は鼻をつまみながら、手紙を広げた。
そこには、ミミズがのたうち回ったような文字で、こう書かれていた。
『エマールへ。僕だ、レイドだ。
今すぐ王都へ戻ってこい。
シルフィが新しいドレスを欲しがっているんだが、王家の財務官がうるさくて買えない。
お前の実家の金で何とかしろ。
あと、僕の部屋の掃除もしてくれ。
戻ってきたら、側室にしてやらなくもないぞ。
感謝しろ。愛をこめて。レイド』
「……」
私は無言で、手紙を机の上に置いた。
ハンスが恐る恐る尋ねる。
「あ、あの……なんと書いてありましたか? やはり、脅迫状……?」
「いいえ。ただの『知性欠如証明書』です」
私は即座に、手元の『保留』トレイ……ではなく、『要・添削』トレイに手紙を放り込んだ。
「ハンス、後で赤ペンと辞書を用意してください。誤字脱字が十七箇所、文法の間違いが五箇所、論理的破綻が全行にあります。添削して突き返します」
「て、添削ですか……?」
「ええ。元婚約者としての、最後の手向け(教育的指導)です」
私が淡々と告げると、ハンスはポカンとした後、吹き出しそうになるのを必死で堪えていた。
「かしこまりました。……あ、それとエマール様。旦那様がお呼びです」
「閣下が? こんな夜更けに?」
時計を見ると、もう夜の十時を回っていた。
就業規則的には残業時間だ。超過勤務手当を請求せねばならない。
「はい。『私の部屋に来るように』とのことです」
「……分かりました」
私は少し身構えた。
夜に寝室へ呼び出し。
契約上の「白い結婚(書類上の夫婦)」とはいえ、相手はあの美貌の辺境伯だ。
もしや、大人の駆け引き(ロマンス)が始まるのだろうか?
(……いや、ないわね。きっと明日の予算会議の予習でしょう)
私は手帳と筆記用具を携え、クラウス様の私室へと向かった。
◇
「失礼します」
重厚な扉をノックして中に入ると、クラウス様はソファに座り、月明かりの下でグラスを傾けていた。
その姿があまりにも絵になりすぎていて、私は一瞬、息を呑んだ。
(……この方の顔面偏差値は、インフレを起こしているわね)
「来たか、エマール。座ってくれ」
クラウス様が向かいの席を勧める。
テーブルの上には、書類も計算機もない。
あるのは、豪奢なベルベットの小箱が一つだけ。
「……お話とは、なんでしょうか? 明日の視察ルートの変更ですか? それとも、レイド殿下からの手紙の件?」
私が尋ねると、クラウス様は首を横に振った。
「いや、仕事の話ではない。……約束の品が届いたんだ」
「約束?」
「忘れたのか? 昨日の夜、君が『欲しい』と言ったものだ」
クラウス様は、テーブルの上の小箱を、指先ですっと私の方へ押し出した。
「開けてみてくれ」
私はゴクリと喉を鳴らし、箱に手を伸ばした。
(まさか、本当に……?)
震える手で蓋を開ける。
そこには、黒いベルベットの海に沈むように、一本の万年筆が鎮座していた。
「っ……!!」
私は思わず声を上げた。
それは、単なる筆記具の域を超えていた。
軸は漆黒のエボナイト製で、手に吸い付くような艶がある。
キャップのリング部分には、ヴァイサリウス家の紋章である「氷狼」が精緻な彫金で施され、その目には極小のサファイアが埋め込まれている。
そして何より、ペン先。
18金の大型ニブが、黄金の輝きを放っている。
「こ、これは……王都の老舗『モンブラン・ロイヤル』の限定モデル、マイスター・シュテュックの特注品……!?」
「ああ。君の手に合うように、重心バランスを調整させた。インクフローも、君の計算速度に追いつけるよう、潤沢に出る設定にしてある」
「す、すごいです……!」
私は箱から万年筆を取り出した。
手に持った瞬間、その完璧な重量バランスに鳥肌が立った。
重すぎず、軽すぎず。まるで指の一部になったかのような一体感。
「試し書きをしても?」
「もちろん」
私は持参していた手帳を開き、サラサラと数字を書き連ねた。
『1,234,567,890...』
「……!!」
滑らかだ。
氷の上を滑るスケートのように、ペン先が紙の上を走る。
カリカリという不快な摩擦音は皆無。ただ、インクが紙に染み込む心地よい感触だけがある。
「素晴らしいです! これなら、決算処理のスピードが通常の1.5倍は向上します! 複利計算も微分積分も、ストレスなく行えます!」
私は興奮のあまり、頬を紅潮させて叫んだ。
「見てください、閣下! このインクの濃淡! 払いと止めの美しさ! 最高です! どんな宝石よりも価値があります!」
私は万年筆を両手で包み込み、うっとりと頬ずりをした。
「ありがとう、万年筆さん。これから私の相棒として、共に赤字を殲滅しましょうね……」
「……」
ふと気配を感じて顔を上げると、クラウス様が口元を手で覆い、肩を震わせていた。
「か、閣下?」
「……いや、すまない。君がそこまで喜ぶとは」
クラウス様は顔を上げ、優しく目を細めた。
「普通の令嬢なら、『綺麗な宝石!』とか『素敵なドレス!』と喜ぶ場面なんだが……君は、『インクの濃淡』と『計算速度』に感動するんだな」
「当然です。宝石は眺めるだけですが、この万年筆は『価値を生み出す』道具ですから。投資対効果(ROI)が段違いです」
「ふっ……。本当に、君はブレないな」
クラウス様は立ち上がり、私の隣に座った。
そして、私の手にある万年筆を、私ごと包み込むように手を重ねた。
「っ!?」
温かい体温が伝わってくる。
「気に入ってくれてよかった。……だが、エマール」
「は、はい」
「その万年筆にばかり頬ずりされると、贈り主としては少々、嫉妬するのだが」
クラウス様の顔が近い。
アイスブルーの瞳が、熱を帯びて私を見つめている。
「え、あ、その……」
「私にも、感謝の言葉以上の『報酬』はないのか?」
「ほ、報酬……?」
私は混乱した頭で計算を試みた。
(高価なプレゼントに対する対価。通常であれば、同等額の返礼品。しかし、私の現在の資産ではこの万年筆に見合うものは用意できない。となると、労働力での提供か、あるいは……)
「計算しなくていい」
クラウス様が、私の思考を遮るように囁く。
「答えは、感情で出すものだ」
彼は私の顎をそっと持ち上げた。
唇が、触れるか触れないかの距離まで近づく。
「……っ」
私は思わず目を閉じた。
(これは……キスされる!? ファーストキスが、計算機も帳簿もない、こんなロマンチックなシチュエーションで!?)
心臓が早鐘を打つ。
しかし。
「……今日は、勘弁してやろう」
ふわり、と。
額(ひたい)に、柔らかい感触が落ちただけだった。
目を開けると、クラウス様がいたずらっ子のように笑っていた。
「緊張で気絶されては困るからな。……それに、今日はその万年筆とイチャイチャしたいのだろう?」
「うっ……! 否定できません……」
「大事に使えよ、私の『最強の経理担当』」
クラウス様は私の頭をポンポンと撫でると、ソファから立ち上がった。
「もう遅い。部屋に戻って休め。……あ、そうそう。レイドからの手紙だが」
「はい」
「添削が終わったら、私にも見せてくれ。王家への『抗議文』として、正式に送り返してやるから」
「ふふ、承知いたしました。徹底的に赤を入れたものを提出します」
「楽しみにしている」
部屋を出る際、私はもう一度振り返った。
クラウス様はグラスを片手に、優しい眼差しで私を見送ってくれていた。
廊下に出た私は、胸に抱いた万年筆をギュッと握りしめた。
「……計算外だわ」
万年筆の冷たい感触とは裏腹に、私の顔は火が出るほど熱かった。
「この胸の高鳴り……。不整脈でも、カフェインの過剰摂取でもないとしたら……」
私は首を振り、早足で自室へと向かった。
認めてしまえば、きっと私の「鉄壁の理性」が崩壊してしまう。
今はまだ、このドキドキは「新しい文房具を手に入れた興奮」という項目で計上しておこう。
そう、自分に言い聞かせながら。
◇
翌日。
私は早朝から執務室に籠り、鬼の形相でペンを走らせていた。
昨夜の甘い余韻?
そんなものは、朝のコーヒーと共に胃の中に流し込んだ。
今の私の目の前にあるのは、レイド殿下からの「ゴミ手紙」だ。
「……ここも違う! 『愛』のスペルが間違っている! 『I』じゃなくて『Ai』と書くなんて、どこの田舎の方言ですか!?」
昨夜もらった万年筆の滑らかな書き心地を堪能しながら、私はレイド殿下の手紙を真っ赤に染め上げていく。
「ハンス! 辞書を持ってきて! あと、王家への請求書ドラフトも!」
「は、はいっ! ただいま!」
執務室に、私の怒号と、ハンスの悲鳴と、そして万年筆が走る軽快な音が響き渡る。
ここから、私とクラウス様による、元婚約者と王家への「倍返し」……いいえ、「正当なる債権回収」が始まるのである。
13
あなたにおすすめの小説


白い結婚で結構ですわ。愛人持ちの夫に興味はありません
鍛高譚
恋愛
公爵令嬢ルチアーナは、王太子アルベルトとの政略結婚を命じられた。だが彼にはすでに愛する女性がいた。そこでルチアーナは、夫婦の義務を果たさない“白い結婚”を提案し、お互いに干渉しない関係を築くことに成功する。
「夫婦としての役目を求めないでくださいませ。その代わり、わたくしも自由にさせていただきますわ」
そうして始まった王太子妃としての優雅な生活。社交界では完璧な妃を演じつつ、裏では趣味の読書やお茶会を存分に楽しみ、面倒ごととは距離を置くつもりだった。
——だが、夫は次第にルチアーナを気にし始める。
「最近、おまえが気になるんだ」
「もっと夫婦としての時間を持たないか?」
今さらそんなことを言われても、もう遅いのですわ。
愛人を優先しておいて、後になって本妻に興味を持つなんて、そんな都合の良い話はお断り。
わたくしは、自由を守るために、今日も紅茶を嗜みながら優雅に過ごしますわ——。
政略結婚から始まる痛快ざまぁ! 夫の後悔なんて知りませんわ
“白い結婚”を謳歌する令嬢の、自由気ままなラブ&ざまぁストーリー!

何も決めなかった王国は、静かに席を失う』
ふわふわ
恋愛
王太子の婚約者として、
表には立たず、裏で国を支えてきた公爵令嬢ネフェリア。
だが――
彼女が追い出されたのは、嫉妬でも陰謀でもなかった。
ただ一つ、「決める役割」を、国が彼女一人に押しつけていたからだ。
婚約破棄の後、ネフェリアを失った王国は変わろうとする。
制度を整え、会議を重ね、慎重に、正しく――
けれどその“正しさ”は、何一つ決断を生まなかった。
一方、帝国は違った。
完璧ではなくとも、期限内に返事をする。
責任を分け、判断を止めない。
その差は、やがて「呼ばれない会議」「残らない席」「知らされない決定」となって現れる。
王国は滅びない。
だが、何も決めない国は、静かに舞台の外へ追いやられていく。
――そして迎える、最後の選択。
これは、
剣も魔法も振るわない“静かなざまぁ”。
何も決めなかった過去に、国そのものが向き合う物語。

断罪の準備は完璧です!国外追放が楽しみすぎてボロが出る
黒猫かの
恋愛
「ミモリ・フォン・ラングレイ! 貴様との婚約を破棄し、国外追放に処す!」
パルマ王国の卒業パーティー。第一王子アリオスから突きつけられた非情な断罪に、公爵令嬢ミモリは……内心でガッツポーズを決めていた。
(ついにきたわ! これで堅苦しい王妃教育も、無能な婚約者の世話も、全部おさらばですわ!)
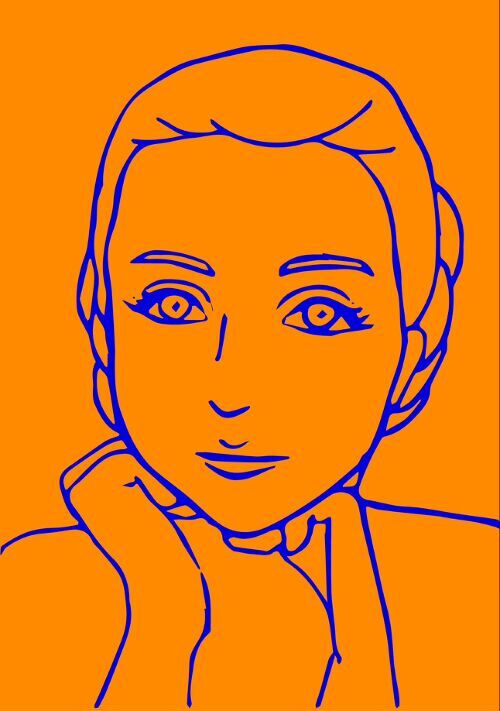
【完結】婚約破棄と言われても個人の意思では出来ません
狸田 真 (たぬきだ まこと)
恋愛
【あらすじ】
第一王子ヴィルヘルムに婚約破棄を宣言された公爵令嬢クリスチナ。しかし、2人の婚約は国のため、人民のためにする政略結婚を目的としたもの。
個人の意思で婚約破棄は出来ませんよ?
【楽しみ方】
笑い有り、ラブロマンス有りの勘違いコメディ作品です。ボケキャラが多数登場しますので、是非、突っ込みを入れながらお楽しみ下さい。感想欄でもお待ちしております! 突っ込み以外の真面目な感想や一言感想などもお気軽にお寄せ下さい。
【注意事項】
安心安全健全をモットーに、子供でも読める作品を目指しておりますが、物語の後半で、大人のロマンスが描写される予定です。直接的な表現は省き、詩的な表現に変換しておりますが、苦手な方はご注意頂ければと思います。
また、愛の伝道師・狸田真は、感想欄のお返事が初対面でも親友みたいな馴れ馴れしいコメントになる事がございます。ご容赦頂けると幸いです。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
私は、夫にも子供にも選ばれなかった。
その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。
そこで待っていたのは、最悪の出来事――
けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。
夫は愛人と共に好きに生きればいい。
今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。
でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。
妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。
過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――

どうやら婚約者の隣は私のものではなくなってしまったようなので、その場所、全てお譲りします。
皇 翼
恋愛
侯爵令嬢という何でも買ってもらえてどんな教育でも施してもらえる恵まれた立場、王太子という立場に恥じない、童話の王子様のように顔の整った婚約者。そして自分自身は最高の教育を施され、侯爵令嬢としてどこに出されても恥ずかしくない教養を身につけていて、顔が綺麗な両親に似たのだろう容姿は綺麗な方だと思う。
完璧……そう、完璧だと思っていた。自身の婚約者が、中庭で公爵令嬢とキスをしているのを見てしまうまでは――。

挙式後すぐに離婚届を手渡された私は、この結婚は予め捨てられることが確定していた事実を知らされました
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
【結婚した日に、「君にこれを預けておく」と離婚届を手渡されました】
今日、私は子供の頃からずっと大好きだった人と結婚した。しかし、式の後に絶望的な事を彼に言われた。
「ごめん、本当は君とは結婚したくなかったんだ。これを預けておくから、その気になったら提出してくれ」
そう言って手渡されたのは何と離婚届けだった。
そしてどこまでも冷たい態度の夫の行動に傷つけられていく私。
けれどその裏には私の知らない、ある深い事情が隠されていた。
その真意を知った時、私は―。
※暫く鬱展開が続きます
※他サイトでも投稿中
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















