4 / 6
第4章
別れたぬいぐるみ
しおりを挟む
ペーシェとバラばあさんは町の中心地に行くために、森を抜けようとしていた。
「ねえバラばあさん。今日はどんな用事なの?」
「なんだかお魚が食べたくてね。中心地に行ったほうが新鮮でおいしいお魚が食べられるのよ」
「どんなお魚を買うの?」
「そうねえ……」
バラばあさんが献立に悩んでいると、ペーシェの耳に小さく「助けてー」という声が聞こえた。
「バラばあさん、誰かが助けてって言ってる」
「えっ?」
ペーシェは耳をすます。同じ声で「だれかー」と叫んでいた。
「あっちから声がする」
ペーシェは声がする方向を指した。
「ぼく、行ってくるっ」
しかしそんなペーシェの体は、バラばあさんに持ち上げられてしまった。
「待ってペーシェ君。そっちは普通の靴じゃ歩けないの。大きな板があればいいんだけれど」
そのときペーシェはひらめいた。
「ねえバラばあさん、ぼくのお風呂代わりにしてくれたおけ、あるでしょう? あれを船にできないかな? ぼくが先に様子を見てくるよ」
「そうね。表面に蝋を塗って滑りやすくしましょう。オール代わりの棒もいるわね。とってくるから、ペーシェ君はここで待っていてくれる?」
「うん、わかった」
ペーシェは板の道でバラばあさんを待つことにした。ペーシェは声がしたほうに向かって叫んだ。
「だいじょうぶだよーっ。用意ができたらすぐに助けに行くからねーっ」
ペーシェの声が届いたのか、声の主は「わかったー」と答えた。ペーシェは声の主に尋ねた。
「今どんな風になってるのー?」
「体が埋まってるー。動けないのー」
「体が埋まってる……」
ペーシェは考えた。
「声の子がぼくより大きかったら、ぼくひとりじゃ助けられない。バラばあさんにも頼まなくっちゃ」
ペーシェがそんな風に思っていると、バラばあさんがおけと棒、それから縄を持ってきた。
「ペーシェ君、念のために体にくくっておくわね」
そう言ってバラばあさんはペーシェの胴体に縄をくくりつけた。
「ペーシェ君、お願いできる?」
「まかせてっ」
ペーシェはおけに乗りこみ、ボートを漕ぐように進んだ。しばらくすると、泥だらけになったうさぎのぬいぐるみに出会った。
「も、もしかして助けにきてくれたの?」
うさぎのぬいぐるみは言った。腕から下はぬかるみにはまっている。顔や耳のあちこちに泥が跳ねて白い体が汚れていた。
「もしかして、ずっと助けてって言ってたのはきみ?」
「そう、そうなのっ。おねがい、助けて」
「もうだいじょうぶだよ。さあ、この棒につかまって」
ペーシェはオール代わりに使っていた棒を、うさぎのぬいぐるみに差し出した。うさぎのぬいぐるみが掴まったところでペーシェは思いきり引っ張った。しかしびくともしない。
「どうすればいいだろう。……そうだっ」
ペーシェは棒が倒れないようにおけに立てかけ、自身の胴体とバラばあさんを繋いでいる縄の一部をおけのふちにある穴に結びつけた。ほどけないか確かめると、ペーシェは大きな声でバラばあさんに話しかけた。
「バラばあさーんっ。ぼくが合図をしたら、縄をひっぱってくれるー?」
「わかったわー」
ペーシェは再び棒を持った。
「しっかりつかまっててね」
うさぎのぬいぐるみは頷いた。ペーシェはバラばあさんに「いいよー」と合図をした。するとおけが来た方向へずるずると動き、うさぎのぬいぐるみの体が引き上げられていく。
「はなしちゃだめだよ」
「うん」
うさぎのぬいぐるみの体はぬかるみを滑る。そしてバラばあさんの姿を再び見たとき、うさぎのぬいぐるみはようやく自身の足で地面を踏むことができた。
「二人とも、助けてくれてありがとう。お礼をちゃんとしなくっちゃいけないんだけど、あたし行かなくっちゃ。もうずっと待たせてるから」
ペーシェはうさぎのぬいぐるみに尋ねた。
「待たせてるってだれを?」
ペーシェは尋ねた。
「エリカちゃん」
「エリカちゃんって、あなたの持ち主?」
今度はバラばあさんが尋ねた。うさぎのぬいぐるみは頷いた。
「エリカちゃんね、遠くに引っ越すからもうあたしといっしょにいられないって言ってたの。でもエリカちゃん、とってもさみしがりなの。だからエリカちゃんのところに行かなくちゃ」
「まあまあ、お待ちなさい。せっかく会うんなら、体をきれいにしたほうがいいわ。私の家がすぐそこにあるから、よかったら来ない?」
うさぎのぬいぐるみは自分の体を見た。そしてこくんと頷いた。バラばあさんはうさぎのぬいぐるみを抱き上げた。
「お、おばあさん、汚れちゃうよ」
「汚れたら洗えばいいのよ。そうだわ、自己紹介がまだだったわね。私の名前はアキノ」
「バラばあさんって呼ばれてるんだって。だからぼくもそう呼んでるんだ。それから、ぼくの名前はペーシェ」
「あたし、スノウ」
うさぎのぬいぐるみは名乗った。
「じゃあスノウちゃん、いっしょにお風呂に入りましょうか」
「うん」
ペーシェとバラばあさんは中心地に行くのをやめ、家に戻った。
スノウはバラばあさんの手によって、きれいにされた。その名前のとおり、雪のように真っ白な体になった。
「はい、きれいになりましたよ」
「ありがとう。バラばあさん」
スノウはバラばあさんにお礼を言った。スノウからは石鹸のいい香りがした。
「ねえ、エリカちゃんってどこに行ったの?」
ペーシェは尋ねた。
「あのね、リュックに住所入れてたの」
ペーシェはスノウがリュックを背負っていたという事実を初めて知った。バラばあさんはテーブルの上に置いてある、一枚の紙を手にとった。それは透明なビニール袋に入れられている封筒だった。
「これね。見ていい?」
「うん」
バラばあさんは紙を見た。そして驚きの声を上げた。
「まあ、まだここから電車で半日もあるじゃない」
「どこからきたの?」
ペーシェはスノウに聞いた。
「ずーっとずーっと遠いところだよ。毎日毎日歩いたの」
「封筒の表の住所……あなた隣の国から来たのね。疲れたでしょう」
「だいじょうぶ、あたしつかれないんだ」
「ぼくもだよ」
「でも危ない目にも遭ったでしょうに」
バラばあさんの言葉にスノウは斜め上の方向を見ながら思い出していた。
「犬に追いかけられたときは、こわかったかな。あれきっと、あたしのことオモチャだと思ったんだわ」
「ぼくもあるよ。ねこもこわいよね」
「うんうん」
そんな話を聞いたバラばあさんは、スノウにある申し出をした。
「よかったら一緒に汽車に乗って、エリカちゃんのところに行かない? 私もちょうど遠出がしたいなあって思っていたところなの」
「ほんとう? あたし、汽車って乗ったことないんだ」
「ぼくあるよ。景色がばーって流れていって、風が気持ちいいんだ」
「そうなの? 乗りたくなってきちゃった」
「じゃあ、決まりね」
その日は、スノウも一緒にバラばあさんのベッドで寝た。
次の日、ペーシェ、スノウ、バラばあさんは汽車に乗るために駅を目指した。二人とも籐のかごに入れられ、バラばあさんに運ばれた。いつもより目線が高いことに、ペーシェもスノウもはしゃいでいた。
まずは汽車の駅に向かうために、バスに乗った。
「バスはエリカちゃんと乗ったことあるよ」
スノウはそんな風に言った。スノウはエリカちゃんのことをたくさん話した。出会いはエリカちゃんが五歳のときでおもちゃ屋さんだったこと、すぐに友達になったこと。エリカちゃんは寂しがり屋で照れ屋なこと。少し泣き虫なこと。小学校で初めて友達ができたのを嬉しそうに話していたことなど。バスに乗っているあいだ、スノウはずっとエリカちゃんのことを話していた。
汽車の駅には大きな旅行カバンを持った人や、待ち合わせをしているらしき人、駅員さんなどがいた。駅の頭上にはステンドガラスがはめ込まれている。
「わあ、とっても広いねっ」
「すごいねっ」
かごの中で興奮しているスノウとペーシェに相槌を打ちながら、駅員さんに尋ねた。
「この子たち、人形師が作ったぬいぐるみなんですけれど、切符はどうすればいいでしょう?」
「切符ってなあに?」
「汽車に乗るためにいる紙のことだよ」
ペーシェはスノウに教えた。駅員さんはペーシェとスノウを見た。
「こんにちはっ」
ペーシェは駅員さんに元気よく挨拶をした。スノウも「こんにちは」と続いた。駅員さんはにこりと笑った。
「はい、こんにちは。
そうですね、この子たちは持ち込み料金をお支払いいただければ大丈夫です」
「わかりました」
バラばあさんは駅員さんに料金を支払っていた。
「ぼく、お金持ってるよ」
「あ……あたし、お金ない……」
それぞれの反応にバラばあさんはにっこり笑った。
「今回は私も日帰り旅行をする気で一緒に行くから、私に出させてちょうだい」
「で、でも……」
スノウがそう言いながらペーシェを見た。
「ぼくのお父さんが言ってたんだ。人の好意は素直に受け取ったらいいって。
ありがとう、バラばあさん」
「ありがとう」
ペーシェとスノウはバラばあさんに甘えることにした。バラばあさんはにこにこ笑いながら「いえいえ」と言った。
改札の内側に入ると、すぐに汽車がやってきた。汽車がまるでため息を吐くかのように煙を吐き出すと、乗客がちらほらと降りてきた。
「わあ……汽車って大きいのね」
スノウは汽車を上から下まで眺めていた。
「さあ、乗りましょう」
ペーシェとスノウはバラばあさんと一緒に汽車に乗りこんだ。四人掛けで、赤いベルベッド調の席が並んでいる。
「せっかくだから、窓際が空いているところにしましょうか」
バラばあさんはそう言って、窓際に誰も座っていない席を選んだ。
「はい。しばらく汽車の中だからこの席にいてね。あと、静かにね」
「うん、わかった。スノウ、いっしょに景色見よう」
「うん」
ペーシェとスノウはかごから出た。バラばあさんに窓にある、ちょっとしたものを置けるスペースの上に乗せてもらい、外の景色を眺めはじめた。
「汽車が出発するときと、止まるときは座ってたほうがいいよ。立ってると落ちちゃうから」
ペーシェはスノウにそうアドバイスした。
そのとき汽笛が鳴った。そして汽車が発車した。
半日もの長い汽車の旅は、ペーシェにとっても、スノウにとっても楽しい旅になった。途中で出会う人との会話、入れ替わる乗客。すぐに降りる人もいれば、しばらく乗っている人もいた。外の景色は川の流れにように変わっていった。緑が多いところ、町、山。移り変わる景色はどこも美しかった。バラばあさんは途中で車内販売のお弁当を買って食べていた。
汽車の終点に来るころには、空は青くありつつも、太陽の位置がずいぶん西に傾いていた。
「スノウちゃん、封筒を貸してくれる?」
「うん、いいよ」
スノウはかばんから、封筒を取り出しバラばあさんに渡した。バラばあさんは駅員さんに道を尋ねていた。駅員さんに言われたとおり、バスに乗る。
「すごく時間がかかるんだね」
「歩いたらもっと大変だったよ。
バラばあさん、ありがとう」
「いえいえ、気にしないで。おかけで楽しませてもらってるわ」
バスを降りると、バラばあさんは時折人に道を尋ねながら進んだ。ペーシェは通り過ぎる人に手を振った。ふとスノウを見ると、早くエリカちゃんに会いたいのか、そわそわしていた。
人の多いところに着くと、バラばあさんはまた人に「この住所に行きたいんですが、道をご存知でしょうか?」と尋ねた。そして一軒のハイツに辿り着いた。階段を上がり、七号室の前で、バラばあさんは立ち止まった。そしてドアチャイムを鳴らした。出てきたのは女性だった。髪はボブカットで、タレ目だ。
「あの……どなたでしょうか?」
女性はいぶかしげに尋ねた。そのときスノウがかごから飛び出し、女性に抱きついた。
「エリカちゃんっ」
「え、スノウっ?」
女性、エリカちゃんは混乱しているようだった。
「なんでスノウがここにいるの?」
「バラばあさんに連れてきてもらったの」
エリカちゃんは改めてバラばあさんを見た。バラばあさんはにっこり笑った。
「あ、あの、どうぞ上がってください。なにもありませんが……」
「まあ、気を遣わなくっていいですよ」
「けれど、その……」
エリカちゃんはなにか言いたそうだった。ペーシェはそれに気がついた。バラばあさんもそうなのか、「それじゃあ、少しだけ」とエリカちゃんの家に上がった。
「エリカちゃんっ、会いたかったよ。ねえ、なんであたしを置いていったの?」
「え、えっとねスノウ……」
エリカちゃんはなにか言おうとした。しかし再会に心が昂っているスノウはエリカに抱きついたまま言葉を続けた。
「でも、また一緒にいられるよねっ」
エリカちゃんはなにも言わなかった。そんなエリカちゃんを見つめながら、スノウは首を傾げた。エリカちゃんはぎこちない笑顔でスノウを床に下ろした。
「スノウ、この方にお礼をするから、別の部屋で遊んでてくれる?」
「バラばあさんに? あたしも一緒にお礼するっ」
しかしエリカちゃんはそれを許さなかった。
「この家、探検していいから」
ペーシェは助け舟を出すことにした。
「ねえ、スノウ。ここでかくれんぼしようよ。とってもかくれがいがありそうなおうちだよ」
しかしスノウは嫌がった。
「エリカちゃんといっしょにいるっ」
「スノウちゃん……」
バラばあさんが屈んでスノウに話しかけようとしたときだった。
「しんどいのよ」
エリカちゃんがそう言うと、場がしんと静まった。ペーシェは心がざわざわした。
「スノウといると、しんどいの」
「え……?」
スノウはつぶらな瞳でエリカちゃんを見上げた。ペーシェも見た。ペーシェたちぬいぐるみよりずっと大きな体は、上のほうが陰っていて表情が見えない。
「私だってしなくちゃいけないことだってあるし、独りでいたいときもある。用事だってあるし、休みたいときもある。でもスノウがいると『遊ぼう』『どこ行くの?』『なにしてるの?』ずっとひっついてくる。私はもう寂しがりで意気地なしの私じゃないのっ。もうスノウがいなくっても、私は生きていけるのっ」
スノウは石のように固まっていた。バラばあさんはエリカちゃんの背中をさすりながらペーシェに言った。
「ペーシェ君、スノウちゃんのこと、お願いしていい?」
「うん」
バラばあさんはエリカちゃんと一緒に別の部屋へ姿を消した。
ペーシェはスノウの手をとった。スノウは俯いた。
「あたし……エリカちゃんがあんな風に思ってるだなんて、知らなかった……」
ペーシェたちぬいぐるみは涙を流さない。けれどもしも流すことができたなら、スノウはきっと泣いているだろう。
「エリカちゃん、きっとひとりでさみしいだろうなって思ってた。だから何日も何日も歩き続けた。エリカちゃんが泣いてるかもしれないって思ったら、急がなくっちゃって思った。でも、エリカちゃんは……あたしがいないほうがよかったんだ」
ペーシェは悲しむスノウをただ抱きしめることしかできなかった。
しばらくすると、バラばあさんが部屋から出てきた。
「バラばあさん……」
ペーシェはバラばあさんを見た。バラばあさんは静かに首を横に振った。バラばあさんはそっとスノウとペーシェを抱き上げた。そして静かにエリカちゃんの家を出た。
帰りの汽車の中はとても静かで、行きのにぎやかさが嘘のようだった。スノウはかごの中で目を閉じて横になっていた。ペーシェやバラばあさんに背を向けている。
「バラばあさん、なんでエリカちゃんはあんなことを言ったの?」
ペーシェはバラばあさんの膝の上に移動して、小声で尋ねた。バラばあさんはエリカちゃんからの話を短くまとめてくれた。
「エリカちゃんはね、お仕事でもいろいろ聞かれる立場なんですって。それでちょっと疲れてるみたい。……心の病気だって、お医者さんに言われたんですって」
「エリカちゃん、病気なの?」
スノウがいつの間にか起き上がっていた。バラばあさんはうなずいた。
「仕事もやめて、遠く離れたところに行ったほうがいいって言われたそうなの。だから今エリカちゃんはあの家に引っ越したそうなの。……今のエリカちゃんに必要なのは、静かな時間。なにをしても、なにもしなくてもいいっていう環境。
でもね、スノウちゃんのことが嫌いになったわけではないの」
「え……?」
それはペーシェも意外に思った。バラばあさんは言葉を続けた。
「スノウちゃんには何度も助けられたって。とても大切な友達ではある、ってエリカちゃんは言っていたわ。でも、いろいろ聞かれるのが辛いから、独りでいたいんですって。だから……スノウちゃんをおうちに置いて引っ越した」
「だったらそう言えばよかったのに」
ペーシェは言った。スノウも頷いた。
「きっと、そんな余裕もなかったのね。説明する力も、質問に答えるエネルギーも」
バラばあさんはスノウの頭を撫でた。
「エリカちゃんの病気はね、治るのにとても時間がかかるんですって。それにいつ治るかもわからない。だからスノウちゃん、うちに来ない?」
「え……?」
「もちろんあなたがおうちに帰りたいなら、送っていくわ。でも私は夫が亡くなってからずっと独りなの。あなたみたいな明るい子がいてくれると、きっと毎日が楽しいわ」
「でも、ペーシェがいるんじゃ……」
スノウはペーシェを見た。ペーシェは首を横に振った。
「今はたまたまバラばあさんの家にお世話になっているだけで、ぼくはいろんなところを旅しているんだ。だからそのうちバイバイするよ」
「そうなんだ」
ペーシェの言葉を聞いたスノウは俯いた。
「あたし、いろいろ聞いちゃうかも」
「じゃあいろんなおしゃべりができるわね」
「バラばあさんのあと、ひっついてきちゃうかも」
「それなら一緒に色んなところに行けるわね」
「あ、あたしといっしょにいるの、つかれちゃうかもしれない……」
スノウは下唇を噛んだ。そんなスノウにバラばあさんは微笑んだ。
「むしろ私がごめんなさいね。もっと若かったらスノウちゃんといろんな遊びができるんでしょうけれど。
ねえ、スノウちゃん。まだ会って少ししか経っていないけれど、私はスノウちゃんのこと、大好きよ。私の生活は静かだけれど、少し寂しいの。だから、エリカちゃんの病気が治るまで一緒にいてくれないかしら?」
スノウはしばらく固まっていた。ペーシェとバラばあさんはスノウが口を開くのを待った。スノウはぽつりと尋ねた。
「あたしで、いいの……?」
「スノウちゃんがいいのよ」
スノウは俯き、尋ねた。
「もしもエリカちゃんが、あたしのこといらないって言ったら?」
「そうなったらうちにずっといてちょうだいな」
スノウはかごから出て、バラばあさんにぎゅっと抱きついた。
「あたし、バラばあさんのところに行っていいの?」
「もちろんよ」
「……あたし、バラばあさんのところに行く」
「ありがとう、スノウちゃん」
バラばあさんはスノウを抱きしめ返した。ペーシェはそんなスノウの頭を撫でた。
「ねえバラばあさん。今日はどんな用事なの?」
「なんだかお魚が食べたくてね。中心地に行ったほうが新鮮でおいしいお魚が食べられるのよ」
「どんなお魚を買うの?」
「そうねえ……」
バラばあさんが献立に悩んでいると、ペーシェの耳に小さく「助けてー」という声が聞こえた。
「バラばあさん、誰かが助けてって言ってる」
「えっ?」
ペーシェは耳をすます。同じ声で「だれかー」と叫んでいた。
「あっちから声がする」
ペーシェは声がする方向を指した。
「ぼく、行ってくるっ」
しかしそんなペーシェの体は、バラばあさんに持ち上げられてしまった。
「待ってペーシェ君。そっちは普通の靴じゃ歩けないの。大きな板があればいいんだけれど」
そのときペーシェはひらめいた。
「ねえバラばあさん、ぼくのお風呂代わりにしてくれたおけ、あるでしょう? あれを船にできないかな? ぼくが先に様子を見てくるよ」
「そうね。表面に蝋を塗って滑りやすくしましょう。オール代わりの棒もいるわね。とってくるから、ペーシェ君はここで待っていてくれる?」
「うん、わかった」
ペーシェは板の道でバラばあさんを待つことにした。ペーシェは声がしたほうに向かって叫んだ。
「だいじょうぶだよーっ。用意ができたらすぐに助けに行くからねーっ」
ペーシェの声が届いたのか、声の主は「わかったー」と答えた。ペーシェは声の主に尋ねた。
「今どんな風になってるのー?」
「体が埋まってるー。動けないのー」
「体が埋まってる……」
ペーシェは考えた。
「声の子がぼくより大きかったら、ぼくひとりじゃ助けられない。バラばあさんにも頼まなくっちゃ」
ペーシェがそんな風に思っていると、バラばあさんがおけと棒、それから縄を持ってきた。
「ペーシェ君、念のために体にくくっておくわね」
そう言ってバラばあさんはペーシェの胴体に縄をくくりつけた。
「ペーシェ君、お願いできる?」
「まかせてっ」
ペーシェはおけに乗りこみ、ボートを漕ぐように進んだ。しばらくすると、泥だらけになったうさぎのぬいぐるみに出会った。
「も、もしかして助けにきてくれたの?」
うさぎのぬいぐるみは言った。腕から下はぬかるみにはまっている。顔や耳のあちこちに泥が跳ねて白い体が汚れていた。
「もしかして、ずっと助けてって言ってたのはきみ?」
「そう、そうなのっ。おねがい、助けて」
「もうだいじょうぶだよ。さあ、この棒につかまって」
ペーシェはオール代わりに使っていた棒を、うさぎのぬいぐるみに差し出した。うさぎのぬいぐるみが掴まったところでペーシェは思いきり引っ張った。しかしびくともしない。
「どうすればいいだろう。……そうだっ」
ペーシェは棒が倒れないようにおけに立てかけ、自身の胴体とバラばあさんを繋いでいる縄の一部をおけのふちにある穴に結びつけた。ほどけないか確かめると、ペーシェは大きな声でバラばあさんに話しかけた。
「バラばあさーんっ。ぼくが合図をしたら、縄をひっぱってくれるー?」
「わかったわー」
ペーシェは再び棒を持った。
「しっかりつかまっててね」
うさぎのぬいぐるみは頷いた。ペーシェはバラばあさんに「いいよー」と合図をした。するとおけが来た方向へずるずると動き、うさぎのぬいぐるみの体が引き上げられていく。
「はなしちゃだめだよ」
「うん」
うさぎのぬいぐるみの体はぬかるみを滑る。そしてバラばあさんの姿を再び見たとき、うさぎのぬいぐるみはようやく自身の足で地面を踏むことができた。
「二人とも、助けてくれてありがとう。お礼をちゃんとしなくっちゃいけないんだけど、あたし行かなくっちゃ。もうずっと待たせてるから」
ペーシェはうさぎのぬいぐるみに尋ねた。
「待たせてるってだれを?」
ペーシェは尋ねた。
「エリカちゃん」
「エリカちゃんって、あなたの持ち主?」
今度はバラばあさんが尋ねた。うさぎのぬいぐるみは頷いた。
「エリカちゃんね、遠くに引っ越すからもうあたしといっしょにいられないって言ってたの。でもエリカちゃん、とってもさみしがりなの。だからエリカちゃんのところに行かなくちゃ」
「まあまあ、お待ちなさい。せっかく会うんなら、体をきれいにしたほうがいいわ。私の家がすぐそこにあるから、よかったら来ない?」
うさぎのぬいぐるみは自分の体を見た。そしてこくんと頷いた。バラばあさんはうさぎのぬいぐるみを抱き上げた。
「お、おばあさん、汚れちゃうよ」
「汚れたら洗えばいいのよ。そうだわ、自己紹介がまだだったわね。私の名前はアキノ」
「バラばあさんって呼ばれてるんだって。だからぼくもそう呼んでるんだ。それから、ぼくの名前はペーシェ」
「あたし、スノウ」
うさぎのぬいぐるみは名乗った。
「じゃあスノウちゃん、いっしょにお風呂に入りましょうか」
「うん」
ペーシェとバラばあさんは中心地に行くのをやめ、家に戻った。
スノウはバラばあさんの手によって、きれいにされた。その名前のとおり、雪のように真っ白な体になった。
「はい、きれいになりましたよ」
「ありがとう。バラばあさん」
スノウはバラばあさんにお礼を言った。スノウからは石鹸のいい香りがした。
「ねえ、エリカちゃんってどこに行ったの?」
ペーシェは尋ねた。
「あのね、リュックに住所入れてたの」
ペーシェはスノウがリュックを背負っていたという事実を初めて知った。バラばあさんはテーブルの上に置いてある、一枚の紙を手にとった。それは透明なビニール袋に入れられている封筒だった。
「これね。見ていい?」
「うん」
バラばあさんは紙を見た。そして驚きの声を上げた。
「まあ、まだここから電車で半日もあるじゃない」
「どこからきたの?」
ペーシェはスノウに聞いた。
「ずーっとずーっと遠いところだよ。毎日毎日歩いたの」
「封筒の表の住所……あなた隣の国から来たのね。疲れたでしょう」
「だいじょうぶ、あたしつかれないんだ」
「ぼくもだよ」
「でも危ない目にも遭ったでしょうに」
バラばあさんの言葉にスノウは斜め上の方向を見ながら思い出していた。
「犬に追いかけられたときは、こわかったかな。あれきっと、あたしのことオモチャだと思ったんだわ」
「ぼくもあるよ。ねこもこわいよね」
「うんうん」
そんな話を聞いたバラばあさんは、スノウにある申し出をした。
「よかったら一緒に汽車に乗って、エリカちゃんのところに行かない? 私もちょうど遠出がしたいなあって思っていたところなの」
「ほんとう? あたし、汽車って乗ったことないんだ」
「ぼくあるよ。景色がばーって流れていって、風が気持ちいいんだ」
「そうなの? 乗りたくなってきちゃった」
「じゃあ、決まりね」
その日は、スノウも一緒にバラばあさんのベッドで寝た。
次の日、ペーシェ、スノウ、バラばあさんは汽車に乗るために駅を目指した。二人とも籐のかごに入れられ、バラばあさんに運ばれた。いつもより目線が高いことに、ペーシェもスノウもはしゃいでいた。
まずは汽車の駅に向かうために、バスに乗った。
「バスはエリカちゃんと乗ったことあるよ」
スノウはそんな風に言った。スノウはエリカちゃんのことをたくさん話した。出会いはエリカちゃんが五歳のときでおもちゃ屋さんだったこと、すぐに友達になったこと。エリカちゃんは寂しがり屋で照れ屋なこと。少し泣き虫なこと。小学校で初めて友達ができたのを嬉しそうに話していたことなど。バスに乗っているあいだ、スノウはずっとエリカちゃんのことを話していた。
汽車の駅には大きな旅行カバンを持った人や、待ち合わせをしているらしき人、駅員さんなどがいた。駅の頭上にはステンドガラスがはめ込まれている。
「わあ、とっても広いねっ」
「すごいねっ」
かごの中で興奮しているスノウとペーシェに相槌を打ちながら、駅員さんに尋ねた。
「この子たち、人形師が作ったぬいぐるみなんですけれど、切符はどうすればいいでしょう?」
「切符ってなあに?」
「汽車に乗るためにいる紙のことだよ」
ペーシェはスノウに教えた。駅員さんはペーシェとスノウを見た。
「こんにちはっ」
ペーシェは駅員さんに元気よく挨拶をした。スノウも「こんにちは」と続いた。駅員さんはにこりと笑った。
「はい、こんにちは。
そうですね、この子たちは持ち込み料金をお支払いいただければ大丈夫です」
「わかりました」
バラばあさんは駅員さんに料金を支払っていた。
「ぼく、お金持ってるよ」
「あ……あたし、お金ない……」
それぞれの反応にバラばあさんはにっこり笑った。
「今回は私も日帰り旅行をする気で一緒に行くから、私に出させてちょうだい」
「で、でも……」
スノウがそう言いながらペーシェを見た。
「ぼくのお父さんが言ってたんだ。人の好意は素直に受け取ったらいいって。
ありがとう、バラばあさん」
「ありがとう」
ペーシェとスノウはバラばあさんに甘えることにした。バラばあさんはにこにこ笑いながら「いえいえ」と言った。
改札の内側に入ると、すぐに汽車がやってきた。汽車がまるでため息を吐くかのように煙を吐き出すと、乗客がちらほらと降りてきた。
「わあ……汽車って大きいのね」
スノウは汽車を上から下まで眺めていた。
「さあ、乗りましょう」
ペーシェとスノウはバラばあさんと一緒に汽車に乗りこんだ。四人掛けで、赤いベルベッド調の席が並んでいる。
「せっかくだから、窓際が空いているところにしましょうか」
バラばあさんはそう言って、窓際に誰も座っていない席を選んだ。
「はい。しばらく汽車の中だからこの席にいてね。あと、静かにね」
「うん、わかった。スノウ、いっしょに景色見よう」
「うん」
ペーシェとスノウはかごから出た。バラばあさんに窓にある、ちょっとしたものを置けるスペースの上に乗せてもらい、外の景色を眺めはじめた。
「汽車が出発するときと、止まるときは座ってたほうがいいよ。立ってると落ちちゃうから」
ペーシェはスノウにそうアドバイスした。
そのとき汽笛が鳴った。そして汽車が発車した。
半日もの長い汽車の旅は、ペーシェにとっても、スノウにとっても楽しい旅になった。途中で出会う人との会話、入れ替わる乗客。すぐに降りる人もいれば、しばらく乗っている人もいた。外の景色は川の流れにように変わっていった。緑が多いところ、町、山。移り変わる景色はどこも美しかった。バラばあさんは途中で車内販売のお弁当を買って食べていた。
汽車の終点に来るころには、空は青くありつつも、太陽の位置がずいぶん西に傾いていた。
「スノウちゃん、封筒を貸してくれる?」
「うん、いいよ」
スノウはかばんから、封筒を取り出しバラばあさんに渡した。バラばあさんは駅員さんに道を尋ねていた。駅員さんに言われたとおり、バスに乗る。
「すごく時間がかかるんだね」
「歩いたらもっと大変だったよ。
バラばあさん、ありがとう」
「いえいえ、気にしないで。おかけで楽しませてもらってるわ」
バスを降りると、バラばあさんは時折人に道を尋ねながら進んだ。ペーシェは通り過ぎる人に手を振った。ふとスノウを見ると、早くエリカちゃんに会いたいのか、そわそわしていた。
人の多いところに着くと、バラばあさんはまた人に「この住所に行きたいんですが、道をご存知でしょうか?」と尋ねた。そして一軒のハイツに辿り着いた。階段を上がり、七号室の前で、バラばあさんは立ち止まった。そしてドアチャイムを鳴らした。出てきたのは女性だった。髪はボブカットで、タレ目だ。
「あの……どなたでしょうか?」
女性はいぶかしげに尋ねた。そのときスノウがかごから飛び出し、女性に抱きついた。
「エリカちゃんっ」
「え、スノウっ?」
女性、エリカちゃんは混乱しているようだった。
「なんでスノウがここにいるの?」
「バラばあさんに連れてきてもらったの」
エリカちゃんは改めてバラばあさんを見た。バラばあさんはにっこり笑った。
「あ、あの、どうぞ上がってください。なにもありませんが……」
「まあ、気を遣わなくっていいですよ」
「けれど、その……」
エリカちゃんはなにか言いたそうだった。ペーシェはそれに気がついた。バラばあさんもそうなのか、「それじゃあ、少しだけ」とエリカちゃんの家に上がった。
「エリカちゃんっ、会いたかったよ。ねえ、なんであたしを置いていったの?」
「え、えっとねスノウ……」
エリカちゃんはなにか言おうとした。しかし再会に心が昂っているスノウはエリカに抱きついたまま言葉を続けた。
「でも、また一緒にいられるよねっ」
エリカちゃんはなにも言わなかった。そんなエリカちゃんを見つめながら、スノウは首を傾げた。エリカちゃんはぎこちない笑顔でスノウを床に下ろした。
「スノウ、この方にお礼をするから、別の部屋で遊んでてくれる?」
「バラばあさんに? あたしも一緒にお礼するっ」
しかしエリカちゃんはそれを許さなかった。
「この家、探検していいから」
ペーシェは助け舟を出すことにした。
「ねえ、スノウ。ここでかくれんぼしようよ。とってもかくれがいがありそうなおうちだよ」
しかしスノウは嫌がった。
「エリカちゃんといっしょにいるっ」
「スノウちゃん……」
バラばあさんが屈んでスノウに話しかけようとしたときだった。
「しんどいのよ」
エリカちゃんがそう言うと、場がしんと静まった。ペーシェは心がざわざわした。
「スノウといると、しんどいの」
「え……?」
スノウはつぶらな瞳でエリカちゃんを見上げた。ペーシェも見た。ペーシェたちぬいぐるみよりずっと大きな体は、上のほうが陰っていて表情が見えない。
「私だってしなくちゃいけないことだってあるし、独りでいたいときもある。用事だってあるし、休みたいときもある。でもスノウがいると『遊ぼう』『どこ行くの?』『なにしてるの?』ずっとひっついてくる。私はもう寂しがりで意気地なしの私じゃないのっ。もうスノウがいなくっても、私は生きていけるのっ」
スノウは石のように固まっていた。バラばあさんはエリカちゃんの背中をさすりながらペーシェに言った。
「ペーシェ君、スノウちゃんのこと、お願いしていい?」
「うん」
バラばあさんはエリカちゃんと一緒に別の部屋へ姿を消した。
ペーシェはスノウの手をとった。スノウは俯いた。
「あたし……エリカちゃんがあんな風に思ってるだなんて、知らなかった……」
ペーシェたちぬいぐるみは涙を流さない。けれどもしも流すことができたなら、スノウはきっと泣いているだろう。
「エリカちゃん、きっとひとりでさみしいだろうなって思ってた。だから何日も何日も歩き続けた。エリカちゃんが泣いてるかもしれないって思ったら、急がなくっちゃって思った。でも、エリカちゃんは……あたしがいないほうがよかったんだ」
ペーシェは悲しむスノウをただ抱きしめることしかできなかった。
しばらくすると、バラばあさんが部屋から出てきた。
「バラばあさん……」
ペーシェはバラばあさんを見た。バラばあさんは静かに首を横に振った。バラばあさんはそっとスノウとペーシェを抱き上げた。そして静かにエリカちゃんの家を出た。
帰りの汽車の中はとても静かで、行きのにぎやかさが嘘のようだった。スノウはかごの中で目を閉じて横になっていた。ペーシェやバラばあさんに背を向けている。
「バラばあさん、なんでエリカちゃんはあんなことを言ったの?」
ペーシェはバラばあさんの膝の上に移動して、小声で尋ねた。バラばあさんはエリカちゃんからの話を短くまとめてくれた。
「エリカちゃんはね、お仕事でもいろいろ聞かれる立場なんですって。それでちょっと疲れてるみたい。……心の病気だって、お医者さんに言われたんですって」
「エリカちゃん、病気なの?」
スノウがいつの間にか起き上がっていた。バラばあさんはうなずいた。
「仕事もやめて、遠く離れたところに行ったほうがいいって言われたそうなの。だから今エリカちゃんはあの家に引っ越したそうなの。……今のエリカちゃんに必要なのは、静かな時間。なにをしても、なにもしなくてもいいっていう環境。
でもね、スノウちゃんのことが嫌いになったわけではないの」
「え……?」
それはペーシェも意外に思った。バラばあさんは言葉を続けた。
「スノウちゃんには何度も助けられたって。とても大切な友達ではある、ってエリカちゃんは言っていたわ。でも、いろいろ聞かれるのが辛いから、独りでいたいんですって。だから……スノウちゃんをおうちに置いて引っ越した」
「だったらそう言えばよかったのに」
ペーシェは言った。スノウも頷いた。
「きっと、そんな余裕もなかったのね。説明する力も、質問に答えるエネルギーも」
バラばあさんはスノウの頭を撫でた。
「エリカちゃんの病気はね、治るのにとても時間がかかるんですって。それにいつ治るかもわからない。だからスノウちゃん、うちに来ない?」
「え……?」
「もちろんあなたがおうちに帰りたいなら、送っていくわ。でも私は夫が亡くなってからずっと独りなの。あなたみたいな明るい子がいてくれると、きっと毎日が楽しいわ」
「でも、ペーシェがいるんじゃ……」
スノウはペーシェを見た。ペーシェは首を横に振った。
「今はたまたまバラばあさんの家にお世話になっているだけで、ぼくはいろんなところを旅しているんだ。だからそのうちバイバイするよ」
「そうなんだ」
ペーシェの言葉を聞いたスノウは俯いた。
「あたし、いろいろ聞いちゃうかも」
「じゃあいろんなおしゃべりができるわね」
「バラばあさんのあと、ひっついてきちゃうかも」
「それなら一緒に色んなところに行けるわね」
「あ、あたしといっしょにいるの、つかれちゃうかもしれない……」
スノウは下唇を噛んだ。そんなスノウにバラばあさんは微笑んだ。
「むしろ私がごめんなさいね。もっと若かったらスノウちゃんといろんな遊びができるんでしょうけれど。
ねえ、スノウちゃん。まだ会って少ししか経っていないけれど、私はスノウちゃんのこと、大好きよ。私の生活は静かだけれど、少し寂しいの。だから、エリカちゃんの病気が治るまで一緒にいてくれないかしら?」
スノウはしばらく固まっていた。ペーシェとバラばあさんはスノウが口を開くのを待った。スノウはぽつりと尋ねた。
「あたしで、いいの……?」
「スノウちゃんがいいのよ」
スノウは俯き、尋ねた。
「もしもエリカちゃんが、あたしのこといらないって言ったら?」
「そうなったらうちにずっといてちょうだいな」
スノウはかごから出て、バラばあさんにぎゅっと抱きついた。
「あたし、バラばあさんのところに行っていいの?」
「もちろんよ」
「……あたし、バラばあさんのところに行く」
「ありがとう、スノウちゃん」
バラばあさんはスノウを抱きしめ返した。ペーシェはそんなスノウの頭を撫でた。
0
あなたにおすすめの小説
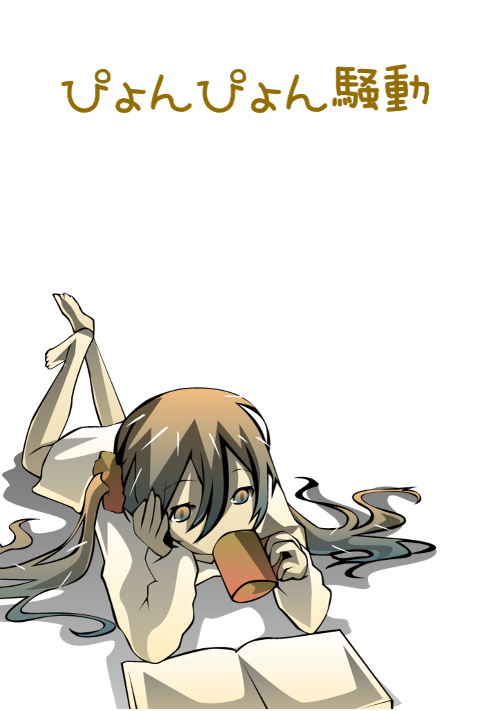
ぴょんぴょん騒動
はまだかよこ
児童書・童話
「ぴょんぴょん」という少女向け漫画雑誌がありました 1988年からわずか5年だけの短い命でした その「ぴょんぴょん」が大好きだった女の子のお話です ちょっと聞いてくださいませ

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394


未来スコープ ―キスした相手がわからないって、どういうこと!?―
米田悠由
児童書・童話
「あのね、すごいもの見つけちゃったの!」
平凡な女子高生・月島彩奈が偶然手にした謎の道具「未来スコープ」。
それは、未来を“見る”だけでなく、“課題を通して導く”装置だった。
恋の予感、見知らぬ男子とのキス、そして次々に提示される不可解な課題──
彩奈は、未来スコープを通して、自分の運命に深く関わる人物と出会っていく。
未来スコープが映し出すのは、甘いだけではない未来。
誰かを想う気持ち、誰かに選ばれない痛み、そしてそれでも誰かを支えたいという願い。
夢と現実が交錯する中で、彩奈は「自分の気持ちを信じること」の意味を知っていく。
この物語は、恋と選択、そしてすれ違う想いの中で、自分の軸を見つけていく少女たちの記録です。
感情の揺らぎと、未来への確信が交錯するSFラブストーリー、シリーズ第2作。
読後、きっと「誰かを想うとはどういうことか」を考えたくなる一冊です。


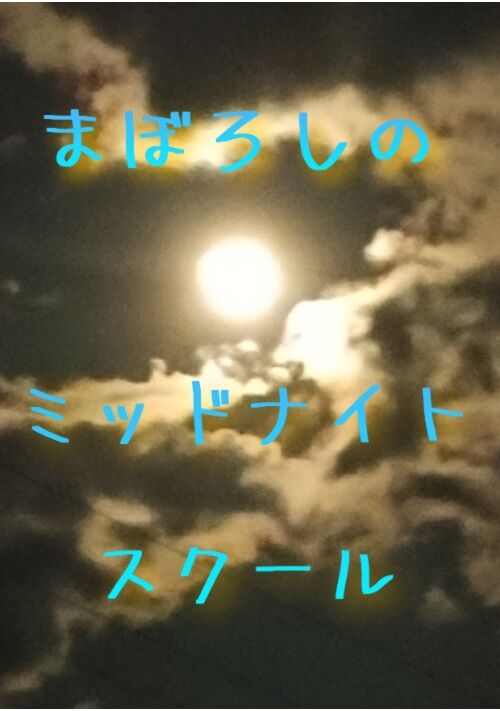
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

【親子おはなし絵本】ドングリさんいっぱい(2~4歳向け(漢字えほん):いろいろできたね!)
天渡 香
絵本
「ごちそうさま。ドングリさんをちょうだい」ママは、さっちゃんの小さな手に、ドングリさんをのせます。
+:-:+:-:+
ドングリさんが大好きな我が子ために作った絵本です。
+:-:+:-:+
「ひとりでトイレに行けたね!」とほめながら、おててにドングリさんを渡すような話しかけをしています(親子のコミュニケーションを目的にしています)。
+:-:+:-:+
「ドングリさんをちょうだい」のフレーズを繰り返しているうちに、子供の方から「ドングリさんはどうしたらもらえるの?」とたずねてくれたので、「ひとりでお着がえできたら、ドングリさんをもらえるよ~」と、我が家では親子の会話がはずみました。
+:-:+:-:+
寝る前に、今日の「いろいろできたね!」をお話しするのにもぴったりです!
+:-:+:-:+
2歳の頃から、園で『漢字えほん(漢字が含まれている童話の本)』に親しんでいる我が子。出版数の少ない、低年齢向けの『漢字えほん』を自分で作ってみました。漢字がまじる事で、大人もスラスラ読み聞かせができます。『友達』という漢字を見つけて、子供が喜ぶなど、ひらがなだけの絵本にはない発見の楽しさがあるようです。
+:-:+:-:+
未満児(1~3歳頃)に漢字のまじった絵本を渡すというのには最初驚きましたが、『街中の看板』『広告』の一つ一つも子供にとっては楽しい童話に見えるようです。漢字の成り立ちなどの『漢字えほん』は多数ありますが、童話に『漢字とひらがなとカタカナ』を含む事で、自然と興味を持って『文字が好き』になったみたいです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















