11 / 21
さよなら
第二話
しおりを挟む
「俺のことはもういいよ。自業自得だし、自分でなんとかする。それより一日でいいから家に顔出してくれよ。兄貴の気持ちもわかるけど、大学に入ってから一回も帰ってないだろう。お袋のやつ、婆ちゃんを施設に入れるって言ってるんだ」
祖母の名前が出たことに、ようやく陸の視線が佳の方に向けられた。複雑そうに揺らぐ黒い瞳に、佳はもう一度とにかく顔を見せてやれと繰り返す。
母親が入所させるつもりの介護施設は、風光明媚な場所を謳い文句にした県境の山間にあるホームだ。一度入ってしまえば、両親が厄介払いができたと面会にもいかず放置するとは目に見えている。
「そんなに悪いのか」
「うん、まあ……ね、家族の顔も名前も分かんなくなっちまって。俺がこっちに来てから徘徊も始まったみたいで、もう限界だってお袋が。近場ですぐに受け入れてくれる所はないから、なんかすげぇ山奥の施設に入れることになるって」
母と祖母の確執は、自分たち兄弟にはあずかり知らぬ所だ。むしろ彼女たちのせいで、トバッチリを喰らったと佳は思っている。
絵に描いたようなとまではいかずとも、せめて平均的の家族であったなら兄との関係はどんなものだったのだろう。子は親を選べない。何不自由なく大学にまで行かせてくれ、むしろ愛を過剰に与えられてきた自覚はあるが、歪なそれは結果的に毒と同じだ。
「そうか。なら、最後に会いに行くことにする」
夕暮れのアスファルトから発せられる熱のせいか、兄の声をぼんやりと遠く聞こえた。
「……最後とか、そんな言い方すんなよ」
心細げに響いた声に、少し前を歩いていた兄の足が止まった。残暑という言葉が空々しいほどの気温だが、太陽が顔を出している時間は確実に短くなっている。ようやく沈んだ夕日に、僅かに残っている蝉たちが最後の鳴き声をあげている。
「来月カナダに行くことになった。教授が無理をして作ってくれた、最初で最後のチャンスだ。暫くはこっちに帰るつもりはない」
「カナダ?」
「お前の新しい下宿先もついでに頼んでおく。俺が留学するせいで同居解消ならおかしくはないだろう。バイトで勉学を疎かにするな。俺の話はそれだけだ、お前もその件だけならもう帰るぞ」
「まって、兄貴!」
慌てて駆け寄って腕をつかむと、ぎょっとしたように陸が目を見開く。年頃になってから、佳は極力兄に触れないようにしてきた。伝わる体温に胸の奥がつきりと痛む。
「っんで、なんでそんな大事なこと、一人で決めちまうんだよ。俺が兄貴の先輩に伝言頼まなかったら、家族に黙ったまま行くつもりだったのかよッ」
「そんなの、今までと同じだろう?」
掴んでいた手を振り払われると、もう一度つかむだけの勇気は出ない。陸は受験も大学も一人で決め、実家に頼ることなく奨学金とおそらく梶聡介の援助を受けてここまでやってきた。
日帰りで通えないこともない距離であるにも関わらず、お互いにこの四年半一度も顔を見せず。電話の一本すら交わさない。陸にとって家族は、とっくの昔に家族では無くなっていたのかもしれない。
どこかで分かっていた筈なのに、改めて突きつけられた現実に打ちのめされる。そしてそこまで擦り切れた絆であっても、自分たちが兄弟であるという呪いは永遠に消えることはないのだ。
「次の日曜だろう。俺も、一緒に行っていいかな。最後なんだろう」
「勝手にしろ」
昼頃に着くように出るとだけ言って、陸は今度こそ佳を待つことなく歩き出す。遠ざかる背中に何も言えず、ただ俯いて痛いほど手を握りしめた。
追いかける佳を待ってくれた兄は、この手を引いてくれた人はもう居ないのだと、痛いほどに思い知らされた。
数年ぶりになる地元の駅に降り立つと、焼かれたコンクリートの熱気にむせ返りそうになる。
ちょうど正午前という時間もあって、太陽の光は皮膚にあたると痛いほどだ。ここから実家まではさらにバスで二十分かかる。先に昼食を済ませておこうと、涼を求めて駅前にあるファーストフード店に足を向ける。
食欲があるわけでもなかったので、適当に一番量の少ないセットをドリンクだけ大きくして注文する。日差しの届かない奥の席に着くと、陸はこの後のことを考えて憂うつになった。
大学に入学して五回目の夏。ここには二度と帰らないつもりで家を出た。留学の件がなければ、祖母が施設に入るからといって顔を見せたりはしなかっただろう。冷たいと世間に非難されようと、それが幼い頃からの積み重ねで作られた家族と自分の関係の答えなのだと思っている。
窓から見えた昔なじみの洋菓子店に、いつだったか土産を買ったことを思い出した。少ない学生の小遣いで買った、ふわふわとした可愛らしいパステルカラーの洋菓子。あの頃の自分は、十年以上も忌々しそうにこちらを見る母親に、まだ何かを期待していたのだろうか。
昼時を過ぎたのを確認してから、陸はバスに乗り実家へと向かった。ほんの数キロの距離だというのに、緑はどんどん増えて山の色合いが濃くなっていく。途中、遠くに梶家の屋敷がちらりと見えた。ここからは分からないが、本宅へと続く正面玄関とは逆の方向にある細い山道を歩いていくとも、あの離れがひっそりと佇んでいるはずだ。
そちらの方にむしろ懐かしさを覚えながら、聞こえてきた停留所の名前に降車ボタンを押す。たいして乗客のいない車内で、次に降りるのは自分だけのようだ。
昔からある古い家と、広い土地を売った後に建てられた似たような雰囲気の複数の家。どこにでもある平凡な住宅街の一画に、陸の実家は二軒並んで立っている。
古い日本家屋の方が代々住んできた祖母の家で、敷地内の畑を潰して建てられた少し前の流行を感じさせる戸建てが両親の家。鹿嶋は父方の姓だが、まさに名前だけというのが家を見ただけで伝わってくる。
鍵が付け替えられている可能性も考えて、先にインターフォンのボタンを押した。応答したのは先に着いていたらしい佳で、すぐに走ってくる音がしてドアが開けられる。
「お帰り、遅いから心配したじゃん」
「婆ちゃんはあっち?」
「いや。一人にはしておけねぇから、一階の和室使ってるよ。別人みてぇに愛想のいいお婆ちゃんになってるから、扱いやすいのは助かるんだけどな」
違和感がなぁと独りごちる佳の後について中に入ると、居間に続くドアから母が顔を見せていた。長らく見なかったその顔は、介護の疲れもあってか随分と老けている。
「帰ったの」
「婆ちゃんの顔見に来た。これお土産、好きでしょう」
「え、そんなこと言ったかしら?」
戸惑っている母の手に押し付けたのは、あの店で買ったカラフルなマカロンだ。クラスの女子がやたらと美味しい可愛いともてはやす菓子を、気まぐれで買って帰った中学生の頃。
もしかしたら喜ぶだろうかという期待は、こんな物にお小遣いを使ってと面倒臭そうに吐き出された言葉によって消えた。並べれば些細なこと。けれどこの家で陸に与えられるのは常にマイナスの言葉と感情ばかりで、ここに居ると息苦しさしか感じなかった。
「婆ちゃん、兄貴が来てくれたぜ」
奥にある和室に入ると、介護用ベッドに座っている老女が佳の声にうんうんと頷いていた。好きだった薄紫のワンピースを着て、腕には子ども用の人形を抱いた祖母は、陸の記憶とは違う柔和な笑みを浮かべている。
「ほら、兄貴」
「あ、ああ。婆ちゃん、久しぶり」
「あら、新しい方かしら。ずいぶんとお若い先生ねぇ。初めまして、東百合子です」
「違うって婆ちゃん、兄貴だよ。婆ちゃんの孫の、りーく」
「陸先生とおっしゃるの。そう、良いお名前ねぇ」
「ありがとうございます。百合子さん、お加減はいかがですか?」
「はい先生、お陰さまで健康だけが取り柄です。うちは主人が早くに亡くなりましたでしょう。だから私が元気でしっかりしなくちゃ」
にこにこと笑いながら腕の中の人形をあやす女性は、陸の知る厳格で隙のない祖母とは別人だった。
彼女は確かに陸を目にかけてくれたが、それは理想を押しつける対象としての一方的な愛情だった。祖母の望む何処に出しても恥ずかしくない良い子であるよう、行儀作法から勉強に運動と、ときには長い定規で叩かれながら、あらゆることを詰め込まれた。
それはおそらく母が幼い日に歩いてきた道であり、お眼鏡に敵わなかった彼女は失敗品として放逐され、祖母の期待は生まれた孫にかけられることになった。
「さあ、まーちゃんネンネの時間ですよ」
「あ、ごめん。これ言い出すと、眠いってことみたいなんだ。婆ちゃんほら、お昼寝はトイレ行ってからな。俺がやっとくから、兄貴はあっちでお茶でも飲んでてよ」
「ああ」
慣れた様子で介助する佳は、惚けた祖母を相手に冗談を言いながら廊下を歩いていく。一人になった空間を改めて見回すと、対して物を置いていなかった和室は、すっかり介護用の部屋へと改造されている。
もう必要ないと背を向けて、無いものとして扱ってきたかつての家。過ぎた歳月は両者の間に積もっていく。
「陸、こっちに来てなさい。お婆ちゃん、慣れない人が居ると寝ないのよ」
「ああ、ごめん」
相変わらずのしかめ面をした母に促されてリビングに移動すると、テーブルの上にはアイスコーヒーと先ほど渡したマカロンが置かれている。
「ホームに移るのは、来月からだってきいたけど」
「ええ。正直、昔のお婆ちゃんよりはよっぽど扱いやすいんだけどね。夜はなかなか寝ないし、家に帰るって徘徊したりするものだから、流石にお母さん一人じゃ無理になった。言っとくけど、反対したって母さんの気持ちは変わらないから」
「反対したりしないよ」
祖母の名前が出たことに、ようやく陸の視線が佳の方に向けられた。複雑そうに揺らぐ黒い瞳に、佳はもう一度とにかく顔を見せてやれと繰り返す。
母親が入所させるつもりの介護施設は、風光明媚な場所を謳い文句にした県境の山間にあるホームだ。一度入ってしまえば、両親が厄介払いができたと面会にもいかず放置するとは目に見えている。
「そんなに悪いのか」
「うん、まあ……ね、家族の顔も名前も分かんなくなっちまって。俺がこっちに来てから徘徊も始まったみたいで、もう限界だってお袋が。近場ですぐに受け入れてくれる所はないから、なんかすげぇ山奥の施設に入れることになるって」
母と祖母の確執は、自分たち兄弟にはあずかり知らぬ所だ。むしろ彼女たちのせいで、トバッチリを喰らったと佳は思っている。
絵に描いたようなとまではいかずとも、せめて平均的の家族であったなら兄との関係はどんなものだったのだろう。子は親を選べない。何不自由なく大学にまで行かせてくれ、むしろ愛を過剰に与えられてきた自覚はあるが、歪なそれは結果的に毒と同じだ。
「そうか。なら、最後に会いに行くことにする」
夕暮れのアスファルトから発せられる熱のせいか、兄の声をぼんやりと遠く聞こえた。
「……最後とか、そんな言い方すんなよ」
心細げに響いた声に、少し前を歩いていた兄の足が止まった。残暑という言葉が空々しいほどの気温だが、太陽が顔を出している時間は確実に短くなっている。ようやく沈んだ夕日に、僅かに残っている蝉たちが最後の鳴き声をあげている。
「来月カナダに行くことになった。教授が無理をして作ってくれた、最初で最後のチャンスだ。暫くはこっちに帰るつもりはない」
「カナダ?」
「お前の新しい下宿先もついでに頼んでおく。俺が留学するせいで同居解消ならおかしくはないだろう。バイトで勉学を疎かにするな。俺の話はそれだけだ、お前もその件だけならもう帰るぞ」
「まって、兄貴!」
慌てて駆け寄って腕をつかむと、ぎょっとしたように陸が目を見開く。年頃になってから、佳は極力兄に触れないようにしてきた。伝わる体温に胸の奥がつきりと痛む。
「っんで、なんでそんな大事なこと、一人で決めちまうんだよ。俺が兄貴の先輩に伝言頼まなかったら、家族に黙ったまま行くつもりだったのかよッ」
「そんなの、今までと同じだろう?」
掴んでいた手を振り払われると、もう一度つかむだけの勇気は出ない。陸は受験も大学も一人で決め、実家に頼ることなく奨学金とおそらく梶聡介の援助を受けてここまでやってきた。
日帰りで通えないこともない距離であるにも関わらず、お互いにこの四年半一度も顔を見せず。電話の一本すら交わさない。陸にとって家族は、とっくの昔に家族では無くなっていたのかもしれない。
どこかで分かっていた筈なのに、改めて突きつけられた現実に打ちのめされる。そしてそこまで擦り切れた絆であっても、自分たちが兄弟であるという呪いは永遠に消えることはないのだ。
「次の日曜だろう。俺も、一緒に行っていいかな。最後なんだろう」
「勝手にしろ」
昼頃に着くように出るとだけ言って、陸は今度こそ佳を待つことなく歩き出す。遠ざかる背中に何も言えず、ただ俯いて痛いほど手を握りしめた。
追いかける佳を待ってくれた兄は、この手を引いてくれた人はもう居ないのだと、痛いほどに思い知らされた。
数年ぶりになる地元の駅に降り立つと、焼かれたコンクリートの熱気にむせ返りそうになる。
ちょうど正午前という時間もあって、太陽の光は皮膚にあたると痛いほどだ。ここから実家まではさらにバスで二十分かかる。先に昼食を済ませておこうと、涼を求めて駅前にあるファーストフード店に足を向ける。
食欲があるわけでもなかったので、適当に一番量の少ないセットをドリンクだけ大きくして注文する。日差しの届かない奥の席に着くと、陸はこの後のことを考えて憂うつになった。
大学に入学して五回目の夏。ここには二度と帰らないつもりで家を出た。留学の件がなければ、祖母が施設に入るからといって顔を見せたりはしなかっただろう。冷たいと世間に非難されようと、それが幼い頃からの積み重ねで作られた家族と自分の関係の答えなのだと思っている。
窓から見えた昔なじみの洋菓子店に、いつだったか土産を買ったことを思い出した。少ない学生の小遣いで買った、ふわふわとした可愛らしいパステルカラーの洋菓子。あの頃の自分は、十年以上も忌々しそうにこちらを見る母親に、まだ何かを期待していたのだろうか。
昼時を過ぎたのを確認してから、陸はバスに乗り実家へと向かった。ほんの数キロの距離だというのに、緑はどんどん増えて山の色合いが濃くなっていく。途中、遠くに梶家の屋敷がちらりと見えた。ここからは分からないが、本宅へと続く正面玄関とは逆の方向にある細い山道を歩いていくとも、あの離れがひっそりと佇んでいるはずだ。
そちらの方にむしろ懐かしさを覚えながら、聞こえてきた停留所の名前に降車ボタンを押す。たいして乗客のいない車内で、次に降りるのは自分だけのようだ。
昔からある古い家と、広い土地を売った後に建てられた似たような雰囲気の複数の家。どこにでもある平凡な住宅街の一画に、陸の実家は二軒並んで立っている。
古い日本家屋の方が代々住んできた祖母の家で、敷地内の畑を潰して建てられた少し前の流行を感じさせる戸建てが両親の家。鹿嶋は父方の姓だが、まさに名前だけというのが家を見ただけで伝わってくる。
鍵が付け替えられている可能性も考えて、先にインターフォンのボタンを押した。応答したのは先に着いていたらしい佳で、すぐに走ってくる音がしてドアが開けられる。
「お帰り、遅いから心配したじゃん」
「婆ちゃんはあっち?」
「いや。一人にはしておけねぇから、一階の和室使ってるよ。別人みてぇに愛想のいいお婆ちゃんになってるから、扱いやすいのは助かるんだけどな」
違和感がなぁと独りごちる佳の後について中に入ると、居間に続くドアから母が顔を見せていた。長らく見なかったその顔は、介護の疲れもあってか随分と老けている。
「帰ったの」
「婆ちゃんの顔見に来た。これお土産、好きでしょう」
「え、そんなこと言ったかしら?」
戸惑っている母の手に押し付けたのは、あの店で買ったカラフルなマカロンだ。クラスの女子がやたらと美味しい可愛いともてはやす菓子を、気まぐれで買って帰った中学生の頃。
もしかしたら喜ぶだろうかという期待は、こんな物にお小遣いを使ってと面倒臭そうに吐き出された言葉によって消えた。並べれば些細なこと。けれどこの家で陸に与えられるのは常にマイナスの言葉と感情ばかりで、ここに居ると息苦しさしか感じなかった。
「婆ちゃん、兄貴が来てくれたぜ」
奥にある和室に入ると、介護用ベッドに座っている老女が佳の声にうんうんと頷いていた。好きだった薄紫のワンピースを着て、腕には子ども用の人形を抱いた祖母は、陸の記憶とは違う柔和な笑みを浮かべている。
「ほら、兄貴」
「あ、ああ。婆ちゃん、久しぶり」
「あら、新しい方かしら。ずいぶんとお若い先生ねぇ。初めまして、東百合子です」
「違うって婆ちゃん、兄貴だよ。婆ちゃんの孫の、りーく」
「陸先生とおっしゃるの。そう、良いお名前ねぇ」
「ありがとうございます。百合子さん、お加減はいかがですか?」
「はい先生、お陰さまで健康だけが取り柄です。うちは主人が早くに亡くなりましたでしょう。だから私が元気でしっかりしなくちゃ」
にこにこと笑いながら腕の中の人形をあやす女性は、陸の知る厳格で隙のない祖母とは別人だった。
彼女は確かに陸を目にかけてくれたが、それは理想を押しつける対象としての一方的な愛情だった。祖母の望む何処に出しても恥ずかしくない良い子であるよう、行儀作法から勉強に運動と、ときには長い定規で叩かれながら、あらゆることを詰め込まれた。
それはおそらく母が幼い日に歩いてきた道であり、お眼鏡に敵わなかった彼女は失敗品として放逐され、祖母の期待は生まれた孫にかけられることになった。
「さあ、まーちゃんネンネの時間ですよ」
「あ、ごめん。これ言い出すと、眠いってことみたいなんだ。婆ちゃんほら、お昼寝はトイレ行ってからな。俺がやっとくから、兄貴はあっちでお茶でも飲んでてよ」
「ああ」
慣れた様子で介助する佳は、惚けた祖母を相手に冗談を言いながら廊下を歩いていく。一人になった空間を改めて見回すと、対して物を置いていなかった和室は、すっかり介護用の部屋へと改造されている。
もう必要ないと背を向けて、無いものとして扱ってきたかつての家。過ぎた歳月は両者の間に積もっていく。
「陸、こっちに来てなさい。お婆ちゃん、慣れない人が居ると寝ないのよ」
「ああ、ごめん」
相変わらずのしかめ面をした母に促されてリビングに移動すると、テーブルの上にはアイスコーヒーと先ほど渡したマカロンが置かれている。
「ホームに移るのは、来月からだってきいたけど」
「ええ。正直、昔のお婆ちゃんよりはよっぽど扱いやすいんだけどね。夜はなかなか寝ないし、家に帰るって徘徊したりするものだから、流石にお母さん一人じゃ無理になった。言っとくけど、反対したって母さんの気持ちは変わらないから」
「反対したりしないよ」
20
あなたにおすすめの小説

夢の続きの話をしよう
木原あざみ
BL
歯止めのきかなくなる前に離れようと思った。
隣になんていたくないと思った。
**
サッカー選手×大学生。すれ違い過多の両方向片思いなお話です。他サイトにて完結済みの作品を転載しています。本編総文字数25万字強。
表紙は同人誌にした際に木久劇美和さまに描いていただいたものを使用しています(※こちらに載せている本文は同人誌用に改稿する前のものになります)。

シスルの花束を
碧月 晶
BL
年下俺様モデル×年上訳あり青年
~人物紹介~
○氷室 三門(ひむろ みかど)
・攻め(主人公)
・23歳、身長178cm
・モデル
・俺様な性格、短気
・訳あって、雨月の所に転がり込んだ
○寒河江 雨月(さがえ うげつ)
・受け
・26歳、身長170cm
・常に無表情で、人形のように顔が整っている
・童顔
※作中に英会話が出てきますが、翻訳アプリで訳したため正しいとは限りません。
※濡れ場があるシーンはタイトルに*マークが付きます。
※基本、三門視点で進みます。
※表紙絵は作者が生成AIで試しに作ってみたものです。

【第一部完結】カフェと雪の女王と、多分、恋の話
凍星
BL
親の店を継ぎ、運河沿いのカフェで見習店長をつとめる高槻泉水には、人に言えない悩みがあった。
誰かを好きになっても、踏み込んだ関係になれない。つまり、SEXが苦手で体の関係にまで進めないこと。
それは過去の手酷い失恋によるものなのだが、それをどうしたら解消できるのか分からなくて……
呪いのような心の傷と、二人の男性との出会い。自分を変えたい泉水の葛藤と、彼を好きになった年下ホスト蓮のもだもだした両片想いの物語。BLです。
「*」マーク付きの話は、性的描写ありです。閲覧にご注意ください。
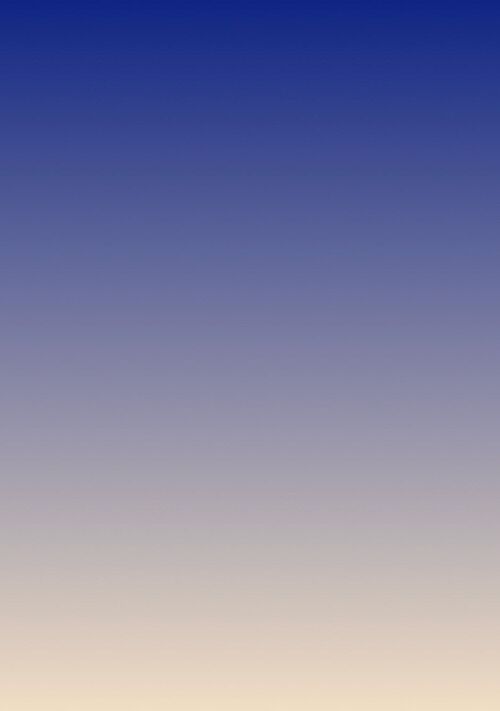
あの部屋でまだ待ってる
名雪
BL
アパートの一室。
どんなに遅くなっても、帰りを待つ習慣だけが残っている。
始まりは、ほんの気まぐれ。
終わる理由もないまま、十年が過ぎた。
与え続けることも、受け取るだけでいることも、いつしか当たり前になっていく。
――あの部屋で、まだ待ってる。

ヤンキーDKの献身
ナムラケイ
BL
スパダリ高校生×こじらせ公務員のBLです。
ケンカ上等、金髪ヤンキー高校生の三沢空乃は、築51年のオンボロアパートで一人暮らしを始めることに。隣人の近間行人は、お堅い公務員かと思いきや、夜な夜な違う男と寝ているビッチ系ネコで…。
性描写があるものには、タイトルに★をつけています。
行人の兄が主人公の「戦闘機乗りの劣情」(完結済み)も掲載しています。

この胸の高鳴りは・・・
暁エネル
BL
電車に乗りいつも通り大学へと向かう途中 気になる人と出会う男性なのか女性なのかわからないまま 電車を降りその人をなぜか追いかけてしまった 初めての出来事に驚き その人に声をかけ自分のした事に 優しく笑うその人に今まで経験した事のない感情が・・・

Take On Me
マン太
BL
親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。
初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。
岳とも次第に打ち解ける様になり…。
軽いノリのお話しを目指しています。
※BLに分類していますが軽めです。
※他サイトへも掲載しています。

箱入りオメガの受難
おもちDX
BL
社会人の瑠璃は突然の発情期を知らないアルファの男と過ごしてしまう。記憶にないが瑠璃は大学生の地味系男子、琥珀と致してしまったらしい。
元の生活に戻ろうとするも、琥珀はストーカーのように付きまといだし、なぜか瑠璃はだんだん絆されていってしまう。
ある日瑠璃は、発情期を見知らぬイケメンと過ごす夢を見て混乱に陥る。これはあの日の記憶?知らない相手は誰?
不器用なアルファとオメガのドタバタ勘違いラブストーリー。
現代オメガバース ※R要素は限りなく薄いです。
この作品は『KADOKAWA×pixiv ノベル大賞2024』の「BL部門」お題イラストから着想し、創作したものです。ありがたいことに、グローバルコミック賞をいただきました。
https://www.pixiv.net/novel/contest/kadokawapixivnovel24
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















