6 / 12
06. 果樹園にて
しおりを挟む
「それで、今年の聖レオーナの日は、どうするんだ?」
狩猟小屋でクレメントが尋ねてきた。シャツとトラウザーズにブーツといういでたちは、相変わらず貴族らしくない。
十七歳のクレメントは、精悍な青年に成長していた。
「ジャムもクッキーも煮林檎も、全部美味かった。味見役なら、まかせとけよ」
「もう、クレムは食いしん坊ね」
クスクスとセシリアが笑みを零す。塞いでいた気持ちが、瞬く間に晴れていった。
聖レオーナの祭日が近付くと、不安でたまらなくなり、毎年クレメントに味見をして貰っている。
「今年こそ、サイラス様と話し合いたいと思っているの。だから、そのきっかけになるものを贈りたいんだけど、なかなか思いつかなくて」
「ああ、そうか。来年には、もう結婚だもんな」
複雑な表情で、二人は口をつぐんだ。セシリアの結婚は、かけがえのないこの友情の、最終期限である。
すでに二人とも成人済みのため、会う頻度は減らしていた。けれど、庭師を介した手紙のやり取りは、定期的に続けている。
内容は近況報告や相談など、健全なものばかりである。
セシリアにとって、クレメントとの交流は、唯一の心の拠り所だった。
彼がいなければ、とっくに気がおかしくなっていたに違いない。
けれど、あくまで独身だから続けられたことだ。夫のある身で他の男性と会い、秘密の手紙をやり取りするなど、非常識な行為である。
勇気が無いセシリアを追い詰めず、ずっと支えてくれた大切な友達。彼と会えなくなると想像しただけで、胸が痛くてたまらなくなる。
結婚してからの自分が、どうなってしまうのかを、セシリアはなるべく考えないようにしていた。
「……なあ、シシー。うちの果樹農園に来てみないか」
「果樹園って、林檎の?」
「うん。これまで料理を出して文句をつけられたわけだろ。だったら、原点に返って、林檎をそのまま贈ったらいい。それが、今の君の心境と、一番近いんじゃないか? 」
「林檎を、サイラス様に……」
この国には、こんな神話がある。
飢饉に喘ぐ貧しい土地。ぼろを纏った旅の老婆が、痩せこけた男に、小さな果実をひとつ与えた。男はそれを持ち帰り、愛する女にそっくり差し出す。女もまた、受け取るのを拒んで、男が食べるよう促した。
結局、男と女は、その果実を二つに切って、共に分かち合ったという。
老婆の正体は、愛の女神レオーナファウラ。
本来の姿を顕現させた女神は、この男女を祝福し、様々な果実や穀物で、豊かに地上を満たしたという。
そのときの果実が、林檎だと言われている。聖レオーナの日には、大切な人へ林檎料理を贈る。
けれど、もっと正確には、林檎を分かち合って食べる風習なのだ。神話に倣い、そのまま贈る人も多く、失礼にはあたらない。
「沢山、摘んでいくといい。俺からのはなむけだ。サイラスのために、自分で採ってきたって教えてやれよ。それで、あの神話みたいな夫婦になりたいって、ちゃんと説明するんだ」
訥々と、クレメントが言葉を紡ぐ。離別の辛さを押し隠した、切ない微笑みを浮かべながら。
「もし、そいつも君と同じ意見なら……これまでの嫌な態度は、ガキが突っ張って、素直になれなかっただけだろう。五年分のわだかまりはあるだろうが、そのときはもう、許しちまえよ。だって、夫婦になるんだからさ。君が婚約者としたいのは、そういう話し合いなんだろ?」
「ええ。そうよ、クレム」
責めたいわけでも、謝って欲しいわけでもない。たとえ女として愛してくれなくても、かまわなかった。
ただ、結婚するしか道が無い以上、家族として信頼関係を築きたい。今のままでは、名目上の夫婦としてさえ、共に行動できるか怪しいだろう。
「たとえ、相手が誰だろうと……君が幸せになれるのなら、できる限り協力するよ」
「ありがとう、クレム……」
「礼なんかいいって。週末は時間あるかい?」
こうして、セシリアはオルグレン伯爵家が所有する果樹農園へ招待されたのだった。
裕福な商家の娘といった装いのセシリアが、丘の上から果樹園を見渡した。
クレメントと一緒に、馬に乗っている。横乗りしているセシリアが落ちないよう、彼が背後から手綱を握っていた。
「わあ、ずいぶん広いのね」
「君の領地の小麦畑と同じだよ。うちは果樹が主力ってだけだ」
今日は、ウィンクル家の令嬢だとバレないよう、平民のふりをしている。農夫たちは貴族について、自分たちの領主くらいしか知らないのだと、事前に説明を受けていた。
いつもの待ち合わせ場所へ、クレメントは馬で現れた。一頭の馬に相乗りし、目的地へ連れてきてもらったのだ。
農園に到着すると、セシリアは農夫たちに歓迎された。祭日用の林檎の収穫で忙しいだろうに、不思議なほど迷惑がる素振りは無い。
むしろ社交辞令抜きで、本心から喜んでくれていた。
「若様が恋人を連れてこられたぞ」
「ははぁ、あの御方が『林檎の君』か。初々しいねえ」
「ようこそ、若様の大事な『林檎の君』」
和やかに声をかけてくる農夫たちに、セシリアは目を瞬いた。
「林檎の君?」
焦った様子のクレメントが、耳を赤くして止めに入る。
「こ、こら! みんな仕事に戻れよ。このお嬢さんは、なんというか、俺の、とっ、友達だ!」
「ですが若様。お小さい頃から、聖レオーナの日に林檎を贈ってきたのは、この御方なんでしょう?」
「特別な子と一緒に食べるんだっておっしゃられて、毎年、手ずから収穫して行かれるじゃないですか」
「見合いもなさらず、縁談を遠ざけていらっしゃるのだって、きっと……」
「わーっ! わーっ!」
農夫たちを追い払い、ばつの悪い顔をしたクレメントに、手を取られた。
「行こうぜ、シシー。あいつらのことは気にしないで」
「……え、ええ」
頬が熱い。胸の奥が甘く痺れていた。その意味を考えてはいけないと、セシリアは目を伏せる。
婚約者がいる身だ。サイラスと向き合う準備をするために、ここへ来たのだ。本来の目的を、忘れてはいけない。
そういえば、こうしてクレメントと手をつなぐのは、何年ぶりだろう。おそらく、これが最後になる。
骨ばった大きな手を、セシリアはキュッと握り返した。この先、辛いときに思い出せるよう、その感触と温もりを心に刻みつけていた。
セシリアが持参した籠へ、クレメントが林檎を入れていく。セシリアもハサミを借りて、いくつか林檎を収穫していた。
「これくらいあれば、足りるだろ」
「うん、十分よ」
この農園は特別なのだと、クレメントが教えてくれる。品種改良した果樹や、国外から取り寄せた苗の試験生産を行っているのだ。
オルグレン伯爵と嫡男のクレメントは、この農園へ足を運び、生産にも積極的に関わっている。また、この農園では、信用できる者だけを働かせているという。
あの親しげなやり取りは、長年培った信頼からくるのだろう。
籠には、沢山の赤い果実。市場にはまだ出回っていない、味が良い品種の林檎を分けてもらった。
「いつもごめんね」
「急にどうした?」
「私、あなたに迷惑ばかりかけているわ……」
これだけ親切にしてもらって、心苦しい。厄介なお荷物に過ぎないセシリアを、ずっと支えてくれた。その優しさにつけこんで、甘えるだけ甘えたあげく、結婚という自分の都合で放り出すことになる。
「迷惑だなんて、勝手に決めつけないでくれないか」
「…………」
「俺は、自分がしたいように行動してる。端からどう見えるかなんて関係ない。だからさ、謝らないで」
クレメントの凛々しい顔に、笑みが滲む。痛みと幸福が入り交じった淡い表情に、ギュッと胸を塞がれた。
「クレム、わたし……」
息をつめたセシリアに何も言わず、クレメントはハサミをあてて林檎をひとつパチリと採った。
「まだ、少し早いけど……聖レオーナの日、おめでとう」
差し出された林檎。それを受け取ったセシリアを、目に焼き付けるように、じっと見つめてくる。
「……きっと、これが俺への罰なんだろうな」
「え?」
「いや、なんでもないよ」
誤魔化すように、クレメントは首を横に振った。
「話し合いの結果は、手紙で教えてくれ。もし、サイラスと上手くいきそうなら、その手紙で最後にしよう。俺たちは、もう関わるべきじゃない」
彼の言う通りだった。もう、接触してはいけない。不適切な感情を、きっと無視できなくなる。
「ねえ、クレム。私に出来ることは、ある? あなたのために、何か、できることは……?」
「あるよ」
クレメントはセシリアにきっぱり言った。
「幸せになれ、シシー。君の幸せが、俺の望みだ」
愛を象徴する赤い果実。
セシリアがクレメントから受け取った林檎は、これが最後になるというのに、燃えるような赤い色で瑞々しく彩られていた。
狩猟小屋でクレメントが尋ねてきた。シャツとトラウザーズにブーツといういでたちは、相変わらず貴族らしくない。
十七歳のクレメントは、精悍な青年に成長していた。
「ジャムもクッキーも煮林檎も、全部美味かった。味見役なら、まかせとけよ」
「もう、クレムは食いしん坊ね」
クスクスとセシリアが笑みを零す。塞いでいた気持ちが、瞬く間に晴れていった。
聖レオーナの祭日が近付くと、不安でたまらなくなり、毎年クレメントに味見をして貰っている。
「今年こそ、サイラス様と話し合いたいと思っているの。だから、そのきっかけになるものを贈りたいんだけど、なかなか思いつかなくて」
「ああ、そうか。来年には、もう結婚だもんな」
複雑な表情で、二人は口をつぐんだ。セシリアの結婚は、かけがえのないこの友情の、最終期限である。
すでに二人とも成人済みのため、会う頻度は減らしていた。けれど、庭師を介した手紙のやり取りは、定期的に続けている。
内容は近況報告や相談など、健全なものばかりである。
セシリアにとって、クレメントとの交流は、唯一の心の拠り所だった。
彼がいなければ、とっくに気がおかしくなっていたに違いない。
けれど、あくまで独身だから続けられたことだ。夫のある身で他の男性と会い、秘密の手紙をやり取りするなど、非常識な行為である。
勇気が無いセシリアを追い詰めず、ずっと支えてくれた大切な友達。彼と会えなくなると想像しただけで、胸が痛くてたまらなくなる。
結婚してからの自分が、どうなってしまうのかを、セシリアはなるべく考えないようにしていた。
「……なあ、シシー。うちの果樹農園に来てみないか」
「果樹園って、林檎の?」
「うん。これまで料理を出して文句をつけられたわけだろ。だったら、原点に返って、林檎をそのまま贈ったらいい。それが、今の君の心境と、一番近いんじゃないか? 」
「林檎を、サイラス様に……」
この国には、こんな神話がある。
飢饉に喘ぐ貧しい土地。ぼろを纏った旅の老婆が、痩せこけた男に、小さな果実をひとつ与えた。男はそれを持ち帰り、愛する女にそっくり差し出す。女もまた、受け取るのを拒んで、男が食べるよう促した。
結局、男と女は、その果実を二つに切って、共に分かち合ったという。
老婆の正体は、愛の女神レオーナファウラ。
本来の姿を顕現させた女神は、この男女を祝福し、様々な果実や穀物で、豊かに地上を満たしたという。
そのときの果実が、林檎だと言われている。聖レオーナの日には、大切な人へ林檎料理を贈る。
けれど、もっと正確には、林檎を分かち合って食べる風習なのだ。神話に倣い、そのまま贈る人も多く、失礼にはあたらない。
「沢山、摘んでいくといい。俺からのはなむけだ。サイラスのために、自分で採ってきたって教えてやれよ。それで、あの神話みたいな夫婦になりたいって、ちゃんと説明するんだ」
訥々と、クレメントが言葉を紡ぐ。離別の辛さを押し隠した、切ない微笑みを浮かべながら。
「もし、そいつも君と同じ意見なら……これまでの嫌な態度は、ガキが突っ張って、素直になれなかっただけだろう。五年分のわだかまりはあるだろうが、そのときはもう、許しちまえよ。だって、夫婦になるんだからさ。君が婚約者としたいのは、そういう話し合いなんだろ?」
「ええ。そうよ、クレム」
責めたいわけでも、謝って欲しいわけでもない。たとえ女として愛してくれなくても、かまわなかった。
ただ、結婚するしか道が無い以上、家族として信頼関係を築きたい。今のままでは、名目上の夫婦としてさえ、共に行動できるか怪しいだろう。
「たとえ、相手が誰だろうと……君が幸せになれるのなら、できる限り協力するよ」
「ありがとう、クレム……」
「礼なんかいいって。週末は時間あるかい?」
こうして、セシリアはオルグレン伯爵家が所有する果樹農園へ招待されたのだった。
裕福な商家の娘といった装いのセシリアが、丘の上から果樹園を見渡した。
クレメントと一緒に、馬に乗っている。横乗りしているセシリアが落ちないよう、彼が背後から手綱を握っていた。
「わあ、ずいぶん広いのね」
「君の領地の小麦畑と同じだよ。うちは果樹が主力ってだけだ」
今日は、ウィンクル家の令嬢だとバレないよう、平民のふりをしている。農夫たちは貴族について、自分たちの領主くらいしか知らないのだと、事前に説明を受けていた。
いつもの待ち合わせ場所へ、クレメントは馬で現れた。一頭の馬に相乗りし、目的地へ連れてきてもらったのだ。
農園に到着すると、セシリアは農夫たちに歓迎された。祭日用の林檎の収穫で忙しいだろうに、不思議なほど迷惑がる素振りは無い。
むしろ社交辞令抜きで、本心から喜んでくれていた。
「若様が恋人を連れてこられたぞ」
「ははぁ、あの御方が『林檎の君』か。初々しいねえ」
「ようこそ、若様の大事な『林檎の君』」
和やかに声をかけてくる農夫たちに、セシリアは目を瞬いた。
「林檎の君?」
焦った様子のクレメントが、耳を赤くして止めに入る。
「こ、こら! みんな仕事に戻れよ。このお嬢さんは、なんというか、俺の、とっ、友達だ!」
「ですが若様。お小さい頃から、聖レオーナの日に林檎を贈ってきたのは、この御方なんでしょう?」
「特別な子と一緒に食べるんだっておっしゃられて、毎年、手ずから収穫して行かれるじゃないですか」
「見合いもなさらず、縁談を遠ざけていらっしゃるのだって、きっと……」
「わーっ! わーっ!」
農夫たちを追い払い、ばつの悪い顔をしたクレメントに、手を取られた。
「行こうぜ、シシー。あいつらのことは気にしないで」
「……え、ええ」
頬が熱い。胸の奥が甘く痺れていた。その意味を考えてはいけないと、セシリアは目を伏せる。
婚約者がいる身だ。サイラスと向き合う準備をするために、ここへ来たのだ。本来の目的を、忘れてはいけない。
そういえば、こうしてクレメントと手をつなぐのは、何年ぶりだろう。おそらく、これが最後になる。
骨ばった大きな手を、セシリアはキュッと握り返した。この先、辛いときに思い出せるよう、その感触と温もりを心に刻みつけていた。
セシリアが持参した籠へ、クレメントが林檎を入れていく。セシリアもハサミを借りて、いくつか林檎を収穫していた。
「これくらいあれば、足りるだろ」
「うん、十分よ」
この農園は特別なのだと、クレメントが教えてくれる。品種改良した果樹や、国外から取り寄せた苗の試験生産を行っているのだ。
オルグレン伯爵と嫡男のクレメントは、この農園へ足を運び、生産にも積極的に関わっている。また、この農園では、信用できる者だけを働かせているという。
あの親しげなやり取りは、長年培った信頼からくるのだろう。
籠には、沢山の赤い果実。市場にはまだ出回っていない、味が良い品種の林檎を分けてもらった。
「いつもごめんね」
「急にどうした?」
「私、あなたに迷惑ばかりかけているわ……」
これだけ親切にしてもらって、心苦しい。厄介なお荷物に過ぎないセシリアを、ずっと支えてくれた。その優しさにつけこんで、甘えるだけ甘えたあげく、結婚という自分の都合で放り出すことになる。
「迷惑だなんて、勝手に決めつけないでくれないか」
「…………」
「俺は、自分がしたいように行動してる。端からどう見えるかなんて関係ない。だからさ、謝らないで」
クレメントの凛々しい顔に、笑みが滲む。痛みと幸福が入り交じった淡い表情に、ギュッと胸を塞がれた。
「クレム、わたし……」
息をつめたセシリアに何も言わず、クレメントはハサミをあてて林檎をひとつパチリと採った。
「まだ、少し早いけど……聖レオーナの日、おめでとう」
差し出された林檎。それを受け取ったセシリアを、目に焼き付けるように、じっと見つめてくる。
「……きっと、これが俺への罰なんだろうな」
「え?」
「いや、なんでもないよ」
誤魔化すように、クレメントは首を横に振った。
「話し合いの結果は、手紙で教えてくれ。もし、サイラスと上手くいきそうなら、その手紙で最後にしよう。俺たちは、もう関わるべきじゃない」
彼の言う通りだった。もう、接触してはいけない。不適切な感情を、きっと無視できなくなる。
「ねえ、クレム。私に出来ることは、ある? あなたのために、何か、できることは……?」
「あるよ」
クレメントはセシリアにきっぱり言った。
「幸せになれ、シシー。君の幸せが、俺の望みだ」
愛を象徴する赤い果実。
セシリアがクレメントから受け取った林檎は、これが最後になるというのに、燃えるような赤い色で瑞々しく彩られていた。
0
あなたにおすすめの小説

溺愛王子の甘すぎる花嫁~悪役令嬢を追放したら、毎日が新婚初夜になりました~
紅葉山参
恋愛
侯爵令嬢リーシャは、婚約者である第一王子ビヨンド様との結婚を心から待ち望んでいた。けれど、その幸福な未来を妬む者もいた。それが、リーシャの控えめな立場を馬鹿にし、王子を我が物にしようと画策した悪役令嬢ユーリーだった。
ある夜会で、ユーリーはビヨンド様の気を引こうと、リーシャを罠にかける。しかし、あなたの王子は、そんなつまらない小細工に騙されるほど愚かではなかった。愛するリーシャを信じ、王子はユーリーを即座に糾弾し、国外追放という厳しい処分を下す。
邪魔者が消え去った後、リーシャとビヨンド様の甘美な新婚生活が始まる。彼は、人前では厳格な王子として振る舞うけれど、私と二人きりになると、とろけるような甘さでリーシャを愛し尽くしてくれるの。
「私の可愛い妻よ、きみなしの人生なんて考えられない」
そう囁くビヨンド様に、私リーシャもまた、心も身体も預けてしまう。これは、障害が取り除かれたことで、むしろ加速度的に深まる、世界一甘くて幸せな夫婦の溺愛物語。新婚の王子妃として、私は彼の、そして王国の「最愛」として、毎日を幸福に満たされて生きていきます。

世界観制約で罵倒しかできない悪役令嬢なのに、なぜか婚約者が溺愛してくる
杓子ねこ
恋愛
前世の記憶を取り戻した悪役令嬢ヴェスカは、王太子との婚約を回避し、学園でもおとなしくすごすつもりだった。
なのに聖女セノリィの入学とともに口からは罵倒の言葉しか出なくなり、周囲からは冷たい目で見られる――ただ一人を除いては。
なぜか婚約者に収まっている侯爵令息ロアン。
彼だけはヴェスカの言動にひるまない。むしろ溺愛してくる。本当になんで?
「ヴェスカ嬢、君は美しいな」
「ロアン様はお可哀想に。今さら気づくなんて、目がお悪いのね」
「そうかもしれない、本当の君はもっと輝いているのかも」
これは侯爵令息が一途に悪役令嬢を思い、ついでにざまあするお話。
悪役令嬢が意外と無自覚にシナリオ改変を起こしまくっていた話でもある。
※小説家になろうで先行掲載中

「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある
柴田はつみ
恋愛
妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった
王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。
リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。
「わかりました。あなたには、がっかりです」
微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。

元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。

公爵令嬢の異世界旅行記 ―婚約破棄されたので旅に出ます。何があっても呼び戻さないでください
ふわふわ
恋愛
大公爵家の令嬢――オルフェアは、婚約者である王子から突然、婚約破棄を言い渡される。
その瞬間、彼女の人生は静かな終わりではなく、新たな旅の始まりとなった。
“ここに留まってはいけない。”
そう直感した彼女は、広大な領地でただ形式だけに触れてきた日常から抜け出し、外の世界へと足を踏み出す。
護衛の騎士と忠実なメイドを従え、覚悟も目的もないまま始まった旅は、やがて異世界の光景――青に染まる夜空、風に揺れる草原、川辺のささやき、森の静けさ――そのすべてを五感で刻む旅へと変わっていく。
王都で巻き起こる噂や騒動は、彼女には遠い世界の出来事に過ぎない。
『戻れ』という声を受け取らず、ただ彼女は歩き続ける。丘を越え、森を抜け、名もない村の空気に触れ、知らない人々の生活を垣間見ながら――。
彼女は知る。
世界は広く、日常は多層的であり、
旅は目的地ではなく、問いを生み、心を形づくるものなのだと。 �
Reddit
領都へ一度戻った後も、再び世界へ歩を進める決意を固めた令嬢の心境の変化は、他者との関わり、内面の成長、そして自分だけの色で描かれる恋と日常の交錯として深く紡がれる。
戦いや陰謀ではなく、風と色と音と空気を感じる旅の物語。
これは、異世界を巡りながら真実の自分を見つけていく、一人の令嬢の恋愛旅記である。

偽りの愛の終焉〜サレ妻アイナの冷徹な断罪〜
紅葉山参
恋愛
貧しいけれど、愛と笑顔に満ちた生活。それが、私(アイナ)が夫と築き上げた全てだと思っていた。築40年のボロアパートの一室。安いスーパーの食材。それでも、あの人の「愛してる」の言葉一つで、アイナは満たされていた。
しかし、些細な変化が、穏やかな日々にヒビを入れる。
私の配偶者の帰宅時間が遅くなった。仕事のメールだと誤魔化す、頻繁に確認されるスマートフォン。その違和感の正体が、アイナのすぐそばにいた。
近所に住むシンママのユリエ。彼女の愛らしい笑顔の裏に、私の全てを奪う魔女の顔が隠されていた。夫とユリエの、不貞の証拠を握ったアイナの心は、凍てつく怒りに支配される。
泣き崩れるだけの弱々しい妻は、もういない。
私は、彼と彼女が築いた「偽りの愛」を、社会的な地獄へと突き落とす、冷徹な復讐を誓う。一歩ずつ、緻密に、二人からすべてを奪い尽くす、断罪の物語。

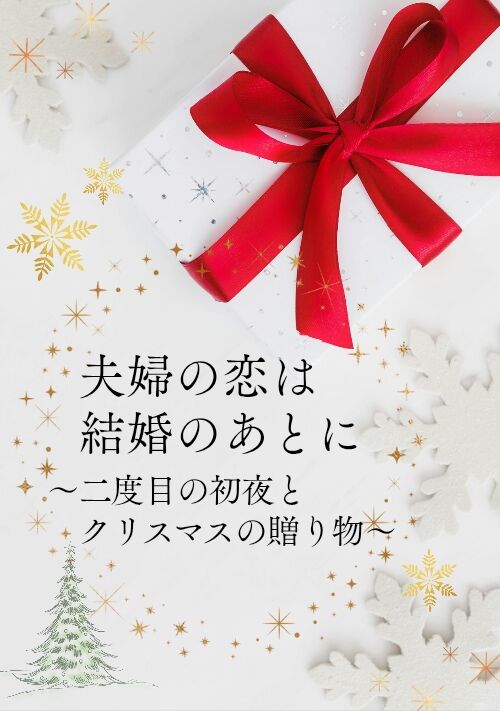
夫婦の恋は結婚のあとに 〜二度目の初夜とクリスマスの贈り物〜
出 万璃玲
恋愛
「エーミル、今年はサンタさんに何をお願いするの?」
「あのね、僕、弟か妹が欲しい!」
四歳の息子の純真無垢な願いを聞いて、アマーリアは固まった。愛のない結婚をした夫と関係を持ったのは、初夜の一度きり。弟か妹が生まれる可能性は皆無。だが、彼女は息子を何よりも愛していた。
「愛するエーミルの願いを無下にするなんてできない」。そう決意したアマーリアは、サンタ……もとい、夫ヴィンフリートに直談判する。
仕事人間でほとんど家にいない無愛想な夫ヴィンフリート、はじめから結婚に期待のなかった妻アマーリア。
不器用な夫婦それぞれの想いの行方は、果たして……?
――政略結婚からすれ違い続けた夫婦の、静かな「恋のやり直し」。
しっとりとした大人の恋愛と、あたたかな家族愛の物語です。
(おまけSS含め、約10000字の短編です。他サイト掲載あり。表紙はcanvaを使用。)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















