2 / 28
2
しおりを挟む
夜会から帰宅する馬車の中、アムリーは死んだ魚のような目をしていた。
ガタゴトと揺れる振動が、疲れた脳みそに響く。
「……解せぬ」
ぽつりと呟いた言葉は、虚空に消えた。
つい数時間前まで、彼女は自由の翼を手に入れたはずだった。
ブラックな王妃教育からの解放。
慰謝料という名の退職金。
これからは毎朝十時まで寝て、趣味の編み物(ストレス解消用のわら人形作り)に没頭するはずだったのだ。
なのに。
「なんで……なんで借金が五億もあるんですか……!」
アムリーは手元の羊皮紙を握りつぶした。
ギルバートから渡された債務明細書。
そこには、父親の署名と、吐き気を催すような数字が並んでいる。
馬車がベルンシュタイン公爵邸の前に止まった。
アムリーは扉が開くのも待たずに飛び出し、屋敷の玄関ホールを風のように駆け抜けた。
「お父様! お父様はいらっしゃいますか!?」
深夜の屋敷に、アムリーの怒号が響き渡る。
パジャマ姿の使用人たちが驚いて顔を出す中、階段の上からのんきな声が降ってきた。
「やあ、おかえりアムリー。今日の夜会はどうだった? カイル殿下とは仲良く……」
「正座してください」
「え?」
「いいから、そこで正座をしてください」
アムリーの剣幕に押され、ベルンシュタイン公爵――アムリーの父であるロベルトは、廊下の真ん中で素直に膝を折った。
この父親、人はいいのだが、致命的に危機管理能力が欠如している。
アムリーは仁王立ちで、しわくちゃになった明細書を突きつけた。
「これは何ですか」
ロベルトは紙を覗き込み、「あー」と間の抜けた声を上げた。
「ライオット公爵から渡されたのかい? 仕事が早いねえ、彼は」
「感心している場合ですか! 連帯保証人!? しかも事業投資詐欺!? この『永久機関開発プロジェクト』って何ですか! 熱力学第二法則をご存知ないんですか!?」
「いやあ、友人の男爵がね、どうしても資金が足りないって泣きついてきて……。夢がある話じゃないか」
「夢でお腹は膨れません! で、その男爵は?」
「先週から連絡が取れないんだ。きっと研究に没頭しているんだろう」
「夜逃げです! それは夜逃げと言うんです!」
アムリーは頭を抱えてその場にしゃがみ込んだ。
終わった。
完全に終わった。
公爵家の資産を洗いざらい売却しても、この額には届かない。
「アムリー、怒らないでおくれよ。なんとかなるさ」
「なりません。明日から私たちは路頭に迷うんです。屋敷は差し押さえ、お父様はタコ部屋行き、私は……」
アムリーの脳裏に、あの冷徹な男の顔が浮かんだ。
『私の元で働かないか?』
甘い誘惑のように聞こえるが、その実態は「借金をカタに取った強制労働」だ。
王妃教育以上のブラック職場が待っているに違いない。
「……いや、待てよ」
アムリーはむくりと顔を上げた。
瞳に、計算高い光が戻ってくる。
「相手はあのギルバート・フォン・ライオット……。合理主義の塊のような男」
「アムリーちゃん?」
「彼が私を欲しがった理由は『有能な手駒』としての能力と、『防波堤』としての役割。つまり、私には五億の借金をチャラにするだけの市場価値があるということ」
アムリーはぶつぶつと独り言を呟きながら、指先で空中に計算式を描き始めた。
ロベルトがおっかなびっくり声をかける。
「あ、あの、アムリー? ひょっとして、ライオット公爵と結婚するのかい?」
「結婚ではありません。業務提携です」
アムリーはきっぱりと言い放った。
「いいですか、お父様。この借金がある以上、私に選択肢はありません。しかし、ただ言いなりになるつもりもありません」
彼女は立ち上がり、自室へと向かう。
「今から契約書の草案を作成します。明日の朝までに、あの冷徹公爵からふんだくれるだけの労働条件を叩き出しますから!」
「ひえっ、あのアムリーが本気モードだ……」
「お父様は反省文を原稿用紙五十枚書いておいてください! テーマは『美味しい話には裏がある』です!」
バタン! と扉が閉まる音が屋敷に響いた。
◇
翌朝。
王城にある宰相執務室の前には、異様な空気が漂っていた。
衛兵たちが緊張した面持ちで直立不動の姿勢を取っている。
その理由は、部屋の中にいる主(あるじ)ではなく、今まさに廊下を歩いてくる一人の令嬢にあった。
カツ、カツ、カツ。
規則正しいヒールの音が近づいてくる。
アムリー・ベルンシュタイン。
昨夜の「婚約破棄騒動」の主役であり、一夜にして「王城で最も敵に回してはいけない女」として名を上げた人物である。
彼女の目の下には、うっすらとクマができていた。
だが、その瞳は爛々と輝き、殺気すら帯びている。
「失礼いたします。ベルンシュタインでございます」
アムリーは衛兵に会釈すらせず、重厚な扉をノックした。
「入れ」
中から短い応答がある。
アムリーは深呼吸を一つし、気合を入れて扉を開けた。
「おはようございます、ライオット公爵閣下」
「早いな。約束の時間より十分早い」
執務机の奥で、ギルバートが書類から顔を上げた。
朝の光を浴びたその姿は、絵画のように美しい。
だが、アムリーにとってそれは「敵将」の姿でしかなかった。
「時間は金(カネ)なり、ですので」
アムリーは許可も待たずにソファへ向かい、持参した鞄から分厚い書類の束を取り出した。
ドサッ。
重たい音がテーブルにする。
ギルバートが眉をひそめた。
「……それは?」
「私からの『逆提案書』です」
アムリーは不敵に笑んだ。
「閣下、昨夜のお話、謹んでお受けいたします。ただし、労働条件に関してこちらの要望をすべて飲んでいただけるならば、ですが」
「ほう」
ギルバートは面白そうに口角を上げた。
彼は立ち上がり、ゆったりとした足取りでソファの対面へと座る。
「借金を肩代わりしてもらう立場で、条件をつけると?」
「借金を肩代わり『させる』だけの価値が私にあると、閣下が判断されたのでは?」
「……口が減らないな」
「お褒めに預かり光栄です。では、第一項から説明させていただきます」
アムリーは指示棒(どこから出したのか)を取り出し、書類を叩いた。
「まず、勤務時間について。基本は九時から十七時。いかなる場合も残業は認めません。もし緊急事態で残業が発生した場合、基本給の五割増しでの支給を求めます」
「五割? 法廷基準は二割五分だ」
「私のストレス対価が含まれております」
「……続けて」
「次に休日。土日祝日は完全休養。さらに、月に三日の『生理休暇』および『メンタルケア休暇』の取得を権利として明記してください」
「王城の文官ですら、そこまで休んでいないぞ」
「彼らが働きすぎなのです。生産性を上げるには休養が不可欠。閣下もご存知でしょう?」
ギルバートは苦笑した。
「いいだろう。他には?」
「ここからが重要です」
アムリーは身を乗り出した。
「業務内容は『宰相補佐』および『婚約者のふり』に限定します。それ以外の、たとえば『夜のお相手』や『後継者作り』といった業務は、契約外事項として一切拒否させていただきます」
執務室の空気が、ピクリと震えた。
ギルバートのアイスブルーの瞳が、すっと細められる。
「……それは、私との結婚生活において、白い結婚を望むということか?」
「ビジネスパートナーですから当然です。愛のない行為は時間の無駄。非生産的です」
アムリーは真顔で言い切った。
ギルバートはしばらくアムリーの顔をじっと見つめ――。
突然、肩を震わせて笑い出した。
「く、くく……! ははははは!」
「……何がおかしいのですか」
「いや、失礼。ここまで清々しい女性は初めてだ」
ギルバートは目尻の涙を指で拭った。
その表情は、先ほどまでの冷徹な仮面が外れ、年相応の青年のように見えた。
「気に入った。その条件、すべて飲もう」
「本当ですか!?」
「ああ。ただし、私からも一つだけ条件がある」
ギルバートはテーブルの上に肘をつき、アムリーの顔を覗き込んだ。
肉食獣のような瞳が、獲物を射抜く。
「契約期間は『終身』とする。……逃がさないよ、アムリー」
アムリーはその言葉の意味を吟味し――。
(終身雇用!? つまり定年まで安泰!?)
「喜んで!」
即答だった。
アムリーは満面の笑みで右手を差し出した。
「契約成立ですね、閣下! いや、旦那様(ボス)!」
「ああ、成立だ。……私の妻(部下)」
二人はガッチリと握手を交わした。
その握手の意味が、互いに微妙に食い違っていることに、まだ誰も気づいていなかった。
◇
一方その頃、王太子の執務室では。
「ふん、アムリーのやつ、きっと今頃泣いて詫び状を書いているに違いない」
カイル王太子は、書類の山(アムリーがいなくなったせいで処理されていない)を前に現実逃避をしていた。
隣にいるミナが、おっとりと首を傾げる。
「そうですわねぇ。きっと強がっていただけですわ。だって、カイル様ほど素敵な殿方を振るなんて、ありえませんもの」
「だろう? まあ、三日もすれば泣いて戻ってくるさ。『無給でいいから働かせてください』とな!」
「さすがカイル様! 慈悲深いですぅ!」
二人は高笑いをした。
その足元で、崩れた書類の山が静かに音を立てて雪崩を起こしていたことを、彼らはまだ知らない。
ガタゴトと揺れる振動が、疲れた脳みそに響く。
「……解せぬ」
ぽつりと呟いた言葉は、虚空に消えた。
つい数時間前まで、彼女は自由の翼を手に入れたはずだった。
ブラックな王妃教育からの解放。
慰謝料という名の退職金。
これからは毎朝十時まで寝て、趣味の編み物(ストレス解消用のわら人形作り)に没頭するはずだったのだ。
なのに。
「なんで……なんで借金が五億もあるんですか……!」
アムリーは手元の羊皮紙を握りつぶした。
ギルバートから渡された債務明細書。
そこには、父親の署名と、吐き気を催すような数字が並んでいる。
馬車がベルンシュタイン公爵邸の前に止まった。
アムリーは扉が開くのも待たずに飛び出し、屋敷の玄関ホールを風のように駆け抜けた。
「お父様! お父様はいらっしゃいますか!?」
深夜の屋敷に、アムリーの怒号が響き渡る。
パジャマ姿の使用人たちが驚いて顔を出す中、階段の上からのんきな声が降ってきた。
「やあ、おかえりアムリー。今日の夜会はどうだった? カイル殿下とは仲良く……」
「正座してください」
「え?」
「いいから、そこで正座をしてください」
アムリーの剣幕に押され、ベルンシュタイン公爵――アムリーの父であるロベルトは、廊下の真ん中で素直に膝を折った。
この父親、人はいいのだが、致命的に危機管理能力が欠如している。
アムリーは仁王立ちで、しわくちゃになった明細書を突きつけた。
「これは何ですか」
ロベルトは紙を覗き込み、「あー」と間の抜けた声を上げた。
「ライオット公爵から渡されたのかい? 仕事が早いねえ、彼は」
「感心している場合ですか! 連帯保証人!? しかも事業投資詐欺!? この『永久機関開発プロジェクト』って何ですか! 熱力学第二法則をご存知ないんですか!?」
「いやあ、友人の男爵がね、どうしても資金が足りないって泣きついてきて……。夢がある話じゃないか」
「夢でお腹は膨れません! で、その男爵は?」
「先週から連絡が取れないんだ。きっと研究に没頭しているんだろう」
「夜逃げです! それは夜逃げと言うんです!」
アムリーは頭を抱えてその場にしゃがみ込んだ。
終わった。
完全に終わった。
公爵家の資産を洗いざらい売却しても、この額には届かない。
「アムリー、怒らないでおくれよ。なんとかなるさ」
「なりません。明日から私たちは路頭に迷うんです。屋敷は差し押さえ、お父様はタコ部屋行き、私は……」
アムリーの脳裏に、あの冷徹な男の顔が浮かんだ。
『私の元で働かないか?』
甘い誘惑のように聞こえるが、その実態は「借金をカタに取った強制労働」だ。
王妃教育以上のブラック職場が待っているに違いない。
「……いや、待てよ」
アムリーはむくりと顔を上げた。
瞳に、計算高い光が戻ってくる。
「相手はあのギルバート・フォン・ライオット……。合理主義の塊のような男」
「アムリーちゃん?」
「彼が私を欲しがった理由は『有能な手駒』としての能力と、『防波堤』としての役割。つまり、私には五億の借金をチャラにするだけの市場価値があるということ」
アムリーはぶつぶつと独り言を呟きながら、指先で空中に計算式を描き始めた。
ロベルトがおっかなびっくり声をかける。
「あ、あの、アムリー? ひょっとして、ライオット公爵と結婚するのかい?」
「結婚ではありません。業務提携です」
アムリーはきっぱりと言い放った。
「いいですか、お父様。この借金がある以上、私に選択肢はありません。しかし、ただ言いなりになるつもりもありません」
彼女は立ち上がり、自室へと向かう。
「今から契約書の草案を作成します。明日の朝までに、あの冷徹公爵からふんだくれるだけの労働条件を叩き出しますから!」
「ひえっ、あのアムリーが本気モードだ……」
「お父様は反省文を原稿用紙五十枚書いておいてください! テーマは『美味しい話には裏がある』です!」
バタン! と扉が閉まる音が屋敷に響いた。
◇
翌朝。
王城にある宰相執務室の前には、異様な空気が漂っていた。
衛兵たちが緊張した面持ちで直立不動の姿勢を取っている。
その理由は、部屋の中にいる主(あるじ)ではなく、今まさに廊下を歩いてくる一人の令嬢にあった。
カツ、カツ、カツ。
規則正しいヒールの音が近づいてくる。
アムリー・ベルンシュタイン。
昨夜の「婚約破棄騒動」の主役であり、一夜にして「王城で最も敵に回してはいけない女」として名を上げた人物である。
彼女の目の下には、うっすらとクマができていた。
だが、その瞳は爛々と輝き、殺気すら帯びている。
「失礼いたします。ベルンシュタインでございます」
アムリーは衛兵に会釈すらせず、重厚な扉をノックした。
「入れ」
中から短い応答がある。
アムリーは深呼吸を一つし、気合を入れて扉を開けた。
「おはようございます、ライオット公爵閣下」
「早いな。約束の時間より十分早い」
執務机の奥で、ギルバートが書類から顔を上げた。
朝の光を浴びたその姿は、絵画のように美しい。
だが、アムリーにとってそれは「敵将」の姿でしかなかった。
「時間は金(カネ)なり、ですので」
アムリーは許可も待たずにソファへ向かい、持参した鞄から分厚い書類の束を取り出した。
ドサッ。
重たい音がテーブルにする。
ギルバートが眉をひそめた。
「……それは?」
「私からの『逆提案書』です」
アムリーは不敵に笑んだ。
「閣下、昨夜のお話、謹んでお受けいたします。ただし、労働条件に関してこちらの要望をすべて飲んでいただけるならば、ですが」
「ほう」
ギルバートは面白そうに口角を上げた。
彼は立ち上がり、ゆったりとした足取りでソファの対面へと座る。
「借金を肩代わりしてもらう立場で、条件をつけると?」
「借金を肩代わり『させる』だけの価値が私にあると、閣下が判断されたのでは?」
「……口が減らないな」
「お褒めに預かり光栄です。では、第一項から説明させていただきます」
アムリーは指示棒(どこから出したのか)を取り出し、書類を叩いた。
「まず、勤務時間について。基本は九時から十七時。いかなる場合も残業は認めません。もし緊急事態で残業が発生した場合、基本給の五割増しでの支給を求めます」
「五割? 法廷基準は二割五分だ」
「私のストレス対価が含まれております」
「……続けて」
「次に休日。土日祝日は完全休養。さらに、月に三日の『生理休暇』および『メンタルケア休暇』の取得を権利として明記してください」
「王城の文官ですら、そこまで休んでいないぞ」
「彼らが働きすぎなのです。生産性を上げるには休養が不可欠。閣下もご存知でしょう?」
ギルバートは苦笑した。
「いいだろう。他には?」
「ここからが重要です」
アムリーは身を乗り出した。
「業務内容は『宰相補佐』および『婚約者のふり』に限定します。それ以外の、たとえば『夜のお相手』や『後継者作り』といった業務は、契約外事項として一切拒否させていただきます」
執務室の空気が、ピクリと震えた。
ギルバートのアイスブルーの瞳が、すっと細められる。
「……それは、私との結婚生活において、白い結婚を望むということか?」
「ビジネスパートナーですから当然です。愛のない行為は時間の無駄。非生産的です」
アムリーは真顔で言い切った。
ギルバートはしばらくアムリーの顔をじっと見つめ――。
突然、肩を震わせて笑い出した。
「く、くく……! ははははは!」
「……何がおかしいのですか」
「いや、失礼。ここまで清々しい女性は初めてだ」
ギルバートは目尻の涙を指で拭った。
その表情は、先ほどまでの冷徹な仮面が外れ、年相応の青年のように見えた。
「気に入った。その条件、すべて飲もう」
「本当ですか!?」
「ああ。ただし、私からも一つだけ条件がある」
ギルバートはテーブルの上に肘をつき、アムリーの顔を覗き込んだ。
肉食獣のような瞳が、獲物を射抜く。
「契約期間は『終身』とする。……逃がさないよ、アムリー」
アムリーはその言葉の意味を吟味し――。
(終身雇用!? つまり定年まで安泰!?)
「喜んで!」
即答だった。
アムリーは満面の笑みで右手を差し出した。
「契約成立ですね、閣下! いや、旦那様(ボス)!」
「ああ、成立だ。……私の妻(部下)」
二人はガッチリと握手を交わした。
その握手の意味が、互いに微妙に食い違っていることに、まだ誰も気づいていなかった。
◇
一方その頃、王太子の執務室では。
「ふん、アムリーのやつ、きっと今頃泣いて詫び状を書いているに違いない」
カイル王太子は、書類の山(アムリーがいなくなったせいで処理されていない)を前に現実逃避をしていた。
隣にいるミナが、おっとりと首を傾げる。
「そうですわねぇ。きっと強がっていただけですわ。だって、カイル様ほど素敵な殿方を振るなんて、ありえませんもの」
「だろう? まあ、三日もすれば泣いて戻ってくるさ。『無給でいいから働かせてください』とな!」
「さすがカイル様! 慈悲深いですぅ!」
二人は高笑いをした。
その足元で、崩れた書類の山が静かに音を立てて雪崩を起こしていたことを、彼らはまだ知らない。
15
あなたにおすすめの小説

『婚約破棄された悪役令嬢ですが、嫁ぎ先で“連れ子三人”の母になりました ~三人の「ママ」が聞けるまで、私は絶対に逃げません~』
放浪人
恋愛
「母はいりません」と拒絶された悪役令嬢が、最強の“ママ”になるまでの物語。
「君のような可愛げのない女は、王妃にふさわしくない」
身に覚えのない罪で婚約破棄され、“悪役令嬢”の汚名を着せられたクラリス。 彼女が新たに嫁いだのは、北方の辺境を守る「氷の公爵」ことレオンハルト・フォン・グレイフだった。
冷え切った屋敷で彼女を待っていたのは、無表情な夫と、心に傷を負った三人の連れ子たち。 「僕たちに、母はいりません」 初対面で突きつけられた三つの拒絶。しかし、クラリスは諦めなかった。
「称号はいりません。私が欲しいのは――あなたたち三人の『ママ』になれる日だけです」
得意の生活魔法『灯(ともしび)』で凍えた部屋を温め、『鎮(しずめ)』の歌で夜泣きを癒やし、家政手腕で荒れた食卓を立て直す。 クラリスの献身的な愛情は、頑なだった子供たちの心を解きほぐし、やがて不器用な夫の氷の心さえも熱く溶かしていく。
これは、不遇な悪役令嬢が「最強の母」となり、家族を脅かす元婚約者や魔獣たちを華麗に撃退し、最愛の家族から「ママ」と呼ばれるその日までを綴った物語。
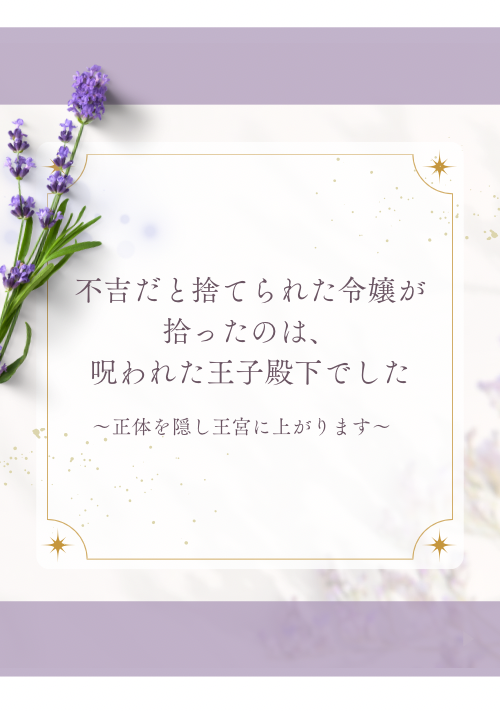
不吉だと捨てられた令嬢が拾ったのは、呪われた王子殿下でした ~正体を隠し王宮に上がります~
長井よる
恋愛
フローレス侯爵家の次女のレティシアは、この国で忌み嫌われる紫の髪と瞳を持って生まれたため、父親から疎まれ、ついには十歳の時に捨てられてしまう。
孤児となり、死にかけていたレティシアは、この国の高名な魔法使いに拾われ、彼の弟子として新たな人生を歩むことになる。
レティシアが十七歳になったある日、事故に遭い瀕死の王子アンドレアスを介抱する。アンドレアスの体には呪いがかけられており、成人まで生きられないという運命が待ち受けていた。レティシアは試行錯誤の末、何とか呪いの進行を止めることに成功する。
アンドレアスから、王宮に来てほしいと懇願されたレティシアは、正体を隠し王宮に上がることを決意するが……。
呪われた王子×秘密を抱えた令嬢(魔法使いの弟子)のラブストーリーです。
※残酷な描写注意
10/30:主要登場人物•事件設定をUPしました。

悪役令嬢まさかの『家出』
にとこん。
恋愛
王国の侯爵令嬢ルゥナ=フェリシェは、些細なすれ違いから突発的に家出をする。本人にとっては軽いお散歩のつもりだったが、方向音痴の彼女はそのまま隣国の帝国に迷い込み、なぜか牢獄に収監される羽目に。しかし無自覚な怪力と天然ぶりで脱獄してしまい、道に迷うたびに騒動を巻き起こす。
一方、婚約破棄を告げようとした王子レオニスは、当日にルゥナが失踪したことで騒然。王宮も侯爵家も大混乱となり、レオニス自身が捜索に出るが、恐らく最後まで彼女とは一度も出会えない。
ルゥナは道に迷っただけなのに、なぜか人助けを繰り返し、帝国の各地で英雄視されていく。そして気づけば彼女を慕う男たちが集まり始め、逆ハーレムの中心に。だが本人は一切自覚がなく、むしろ全員の好意に対して煙たがっている。
帰るつもりもなく、目的もなく、ただ好奇心のままに彷徨う“無害で最強な天然令嬢”による、帝国大騒動ギャグ恋愛コメディ、ここに開幕!


【完結】メルティは諦めない~立派なレディになったなら
すみ 小桜(sumitan)
恋愛
レドゼンツ伯爵家の次女メルティは、水面に映る未来を見る(予言)事ができた。ある日、父親が事故に遭う事を知りそれを止めた事によって、聖女となり第二王子と婚約する事になるが、なぜか姉であるクラリサがそれらを手にする事に――。51話で完結です。

働かないつもりでしたのに、気づけば全部うまくいっていました ――自由に生きる貴族夫人と溺愛旦那様』
鷹 綾
恋愛
前世では、仕事に追われるだけの人生を送り、恋も自由も知らないまま終わった私。
だからこそ転生後に誓った――
「今度こそ、働かずに優雅に生きる!」 と。
気づけば貴族夫人、しかも結婚相手は冷静沈着な名門貴族リチャード様。
「君は何もしなくていい。自由に過ごしてくれ」
――理想的すぎる条件に、これは勝ち確人生だと思ったのに。
なぜか気づけば、
・屋敷の管理を改善して使用人の待遇が激変
・夫の仕事を手伝ったら経理改革が大成功
・興味本位で教えた簿記と珠算が商業界に革命を起こす
・商人ギルドの顧問にまで祭り上げられる始末
「あれ? 私、働かない予定でしたよね???」
自分から出世街道を爆走するつもりはなかったはずなのに、
“やりたいことをやっていただけ”で、世界のほうが勝手に変わっていく。
一方、そんな彼女を静かに見守り続けていた夫・リチャードは、
実は昔から彼女を想い続けていた溺愛系旦那様で――。
「君が選ぶなら、私はずっとそばにいる」
働かないつもりだった貴族夫人が、
自由・仕事・愛情のすべてを“自分で選ぶ”人生に辿り着く物語。
これは、
何もしないはずだったのに、幸せだけは全部手に入れてしまった女性の物語。

一夜限りの関係だったはずなのに、責任を取れと迫られてます。
甘寧
恋愛
魔女であるシャルロッテは、偉才と呼ばれる魔導師ルイースとひょんなことから身体の関係を持ってしまう。
だがそれはお互いに同意の上で一夜限りという約束だった。
それなのに、ルイースはシャルロッテの元を訪れ「責任を取ってもらう」と言い出した。
後腐れのない関係を好むシャルロッテは、何とかして逃げようと考える。しかし、逃げれば逃げるだけ愛が重くなっていくルイース…
身体から始まる恋愛模様◎
※タイトル一部変更しました。

5分前契約した没落令嬢は、辺境伯の花嫁暮らしを楽しむうちに大国の皇帝の妻になる
西野歌夏
恋愛
ロザーラ・アリーシャ・エヴルーは、美しい顔と妖艶な体を誇る没落令嬢であった。お家の窮状は深刻だ。そこに半年前に陛下から連絡があってー
私の本当の人生は大陸を横断して、辺境の伯爵家に嫁ぐところから始まる。ただ、その前に最初の契約について語らなければならない。没落令嬢のロザーラには、秘密があった。陛下との契約の背景には、秘密の契約が存在した。やがて、ロザーラは花嫁となりながらも、大国ジークベインリードハルトの皇帝選抜に巻き込まれ、陰謀と暗号にまみれた旅路を駆け抜けることになる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















