6 / 28
6
しおりを挟む
王都の一等地に店を構える、高級ブティック『ローズ・マリー』。
王侯貴族御用達のこの店に、アムリーはギルバートと共に足を踏み入れた。
「いらっしゃいませ、ライオット公爵閣下! お待ちしておりましたわ!」
店主のマダムが、揉み手をして出迎える。
店内には、宝石を散りばめたような煌びやかなドレスがずらりと並んでいた。
「アムリー。今日は貸切にしてある。好きなものを選ぶといい」
ギルバートが鷹揚に言う。
アムリーは並べられたドレス群を、在庫管理表を見るような目でスキャンした。
「……閣下。質問しても?」
「なんだ?」
「今回の舞踏会における、私の『役割(ロール)』は?」
アムリーが真顔で尋ねる。
ギルバートは少し考え、答えた。
「『私の最愛の婚約者』としての威厳を示し、周囲の雑音を黙らせること。そして何より、君自身がその美しさを自覚することだ」
「了解しました。つまり、敵(カイル殿下たち)への威嚇と、対外的なプレゼンスの向上ですね」
アムリーは頷くと、一着のパステルピンクのドレスを指先で摘んだ。
「まず、これは却下です」
「なぜだ? 可愛らしいと思うが」
「フリルが多すぎます。これでは他者と接触した際、破損するリスクが高い。それに、ワインなどをかけられた場合の防汚性が著しく低い色です」
「……防汚性?」
「次に、あの純白のドレス。あれも却下です。膨張色は威圧感に欠けます。舐められたら終わりの交渉の場において、白旗を上げているようなものです」
アムリーは次々とドレスを却下していく。
「このマーメイドラインは動きにくいので却下(緊急時の逃走に支障が出ます)。この総レースは引っかかり係数が高すぎるので却下」
マダムの顔が引きつり始めた。
「あ、あの、お嬢様……? デザインや流行については……?」
「機能美こそが至高です。戦場(舞踏会)に、飾りだけの鎧を着ていく騎士はいません」
アムリーは断言した。
彼女にとって舞踏会とは、優雅に踊る場所ではない。
情報収集と人脈形成、そして敵対勢力との腹の探り合いを行う『戦場』なのだ。
「……ははは!」
ギルバートが吹き出した。
「戦場か。違いない」
彼は楽しそうに笑うと、ラックの奥から一着のドレスを引き出した。
それは、深い夜の色――ミッドナイトブルーの生地に、銀糸の刺繍が施されたシックなドレスだった。
露出は控えめだが、背中のラインが大胆に開いている。
「これならどうだ? 汚れも目立たないし、威厳もある」
アムリーは生地を触り、縫製を確認し、裏地をチェックした。
「……シルクサテンの厚手生地。耐久性は合格。色味も、私の肌色とのコントラスト比において最適解かと。何より、足捌きが良さそうです」
「気に入ったか?」
「はい。この装備なら、カイル殿下にワインをかけられても、即座に回し蹴りで応戦できます」
「応戦はしなくていい。避けてくれ」
ギルバートは苦笑しつつ、マダムに合図を送った。
「これを頼む。あと、これに合う宝石もだ。予算は無制限でいい」
「かしこまりましたわ!」
マダムの目が金貨の色に輝いた。
◇
数十分後。
試着室のカーテンが開かれた。
「……いかがでしょうか」
アムリーが少し照れくさそうに姿を現す。
店内の空気が、一変した。
深い青のドレスは、アムリーの冷ややかな美貌を極限まで引き立てていた。
アップに結い上げられた銀髪。
露わになった白磁の背中。
そして首元には、ギルバートの瞳と同じアイスブルーのサファイアが輝いている。
それはもはや『悪役令嬢』というより、『氷の女王』と呼ぶにふさわしい気品と迫力だった。
「……」
ギルバートは言葉を失っていた。
いつもの皮肉な笑みも、冷徹な仮面も消え失せ、ただ呆然とアムリーを見つめている。
「閣下? 変でしょうか? やはり機能性を重視しすぎて、華やかさに欠けるのでは……」
アムリーが不安げに尋ねる。
ギルバートはハッと我に返り、ゆっくりと歩み寄った。
「……いや。訂正が必要だ」
「訂正?」
「『美しい』という言葉では足りない。……君は、恐ろしいほどに魅力的だ」
ギルバートの手が、アムリーの頬に触れる。
その指先がわずかに熱いことに、アムリーは驚いた。
「この姿を会場で見せれば、誰もがひれ伏すだろう。カイル殿下が泡を吹いて倒れる姿が目に浮かぶよ」
「それは効果絶大ですね。コストパフォーマンス最高の投資です」
アムリーは照れ隠しにそう言ったが、心臓の鼓動は早鐘を打っていた。
(おかしいわね……。コルセットの締め付けがきついのかしら? 酸素供給量が低下している気がする)
顔が熱い。
鏡に映る自分は、いつもの冷静な顔をしているはずなのに、耳まで赤い気がする。
「さあ、次は靴を選ぼう。君が『逃走』にも『追跡』にも使える、最強のヒールを」
「はい! ヒールの高さは七センチが限界です。それ以上は機動力が三〇%低下します!」
「了解した。……本当に、君は面白いな」
ギルバートは愛おしそうにアムリーの手を取り、エスコートした。
その様子を、店の外から恨めしそうに見つめる影があったことに、二人はまだ気づいていなかった。
◇
一方、その頃。
王都の裏通りにある質屋『強欲の壺』。
そこに、帽子を目深に被った男と、フードを被った小柄な女の姿があった。
「お、おい、本当にこれを売るのか? これは王家伝来の……」
「カイル様ぁ、仕方ないですぅ。だってお金がないと、ミナのドレスが買えないじゃないですかぁ」
カイルとミナである。
カイルの手には、小さな宝飾品が握られていた。
それは王太子の私物ではなく、王家の倉庫からこっそり持ち出したアンティークのブローチだった。
「でも、バレたら父上に殺される……」
「バレませんよぉ! それに、アムリーお姉様に勝つためです! ミナが一番可愛くなって、あのお姉様をギャフンと言わせるんです!」
ミナは拳を握りしめた。
あの日、宰相執務室から追い出された屈辱。
そして実家に届いた高額な請求書。
それらがミナの(歪んだ)対抗心に火をつけていた。
「そうだな……。あいつを見返してやらねば! 俺を振ったことを後悔させてやる!」
カイルは意を決して、質屋のカウンターにブローチを置いた。
「これを頼む! 最高級のドレスが買えるだけの金をくれ!」
質屋の親父が、ギロリと目を光らせた。
「……へいへい。出所は聞かねえことにしてやるよ」
ジャラジャラと硬貨の音が響く。
その金を手にした二人は、歪んだ笑みを浮かべた。
「見てろよアムリー! 今度の舞踏会が貴様の処刑場だ!」
「ミナの可愛さで、ギルバート様を奪っちゃいますぅ!」
二人の復讐計画(という名の自爆特攻準備)は、着々と進行していた。
◇
翌日。
宰相邸のダンスホールにて。
「ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー」
機械的なカウントが響いていた。
アムリーである。
彼女は真剣な顔で、ギルバートと組みながらステップを踏んでいた。
「アムリー。もう少し力を抜いて」
「無理です。重心移動のベクトル計算に集中しています」
アムリーの体は、木の棒のように硬い。
「ダンスは計算じゃない。相手に身を委ねるものだ」
「身を委ねる=転倒リスクの増加です。私は自分の足で立ちます」
「……はは、頑固だな」
ギルバートは苦笑しながら、ぐっとアムリーを引き寄せた。
「っ!?」
距離がゼロになる。
互いの呼吸がかかるほどの密着度。
「私を信じろ。絶対に転ばせないし、君を傷つけさせない」
ギルバートの低音が、鼓膜を震わせる。
「君はただ、私のリードに従って、優雅に微笑んでいればいい。……全ての面倒ごとは、私が処理する」
その言葉は、アムリーが今まで一人で背負ってきた重荷を、ふわりと持ち上げてくれるようだった。
王妃教育のプレッシャーも。
実家の借金も。
周囲の悪意も。
「……好条件すぎますね」
アムリーは小さく呟いた。
「そんなに甘やかされると、勘違いしてしまいそうです」
「勘違いすればいい。……私は本気だと言っているだろう?」
ギルバートはアムリーの額に、唇を寄せた。
チュッ。
軽い音とともに、アムリーの思考回路がショートした。
「~~~~っ!?」
「本番を楽しみにしているよ、私の可愛いアムリー」
真っ赤になって固まるアムリーを見て、ギルバートは満足げに笑った。
舞踏会まで、あと三日。
最強の装備と、最強のパートナーを得たアムリーの進撃が始まる。
王侯貴族御用達のこの店に、アムリーはギルバートと共に足を踏み入れた。
「いらっしゃいませ、ライオット公爵閣下! お待ちしておりましたわ!」
店主のマダムが、揉み手をして出迎える。
店内には、宝石を散りばめたような煌びやかなドレスがずらりと並んでいた。
「アムリー。今日は貸切にしてある。好きなものを選ぶといい」
ギルバートが鷹揚に言う。
アムリーは並べられたドレス群を、在庫管理表を見るような目でスキャンした。
「……閣下。質問しても?」
「なんだ?」
「今回の舞踏会における、私の『役割(ロール)』は?」
アムリーが真顔で尋ねる。
ギルバートは少し考え、答えた。
「『私の最愛の婚約者』としての威厳を示し、周囲の雑音を黙らせること。そして何より、君自身がその美しさを自覚することだ」
「了解しました。つまり、敵(カイル殿下たち)への威嚇と、対外的なプレゼンスの向上ですね」
アムリーは頷くと、一着のパステルピンクのドレスを指先で摘んだ。
「まず、これは却下です」
「なぜだ? 可愛らしいと思うが」
「フリルが多すぎます。これでは他者と接触した際、破損するリスクが高い。それに、ワインなどをかけられた場合の防汚性が著しく低い色です」
「……防汚性?」
「次に、あの純白のドレス。あれも却下です。膨張色は威圧感に欠けます。舐められたら終わりの交渉の場において、白旗を上げているようなものです」
アムリーは次々とドレスを却下していく。
「このマーメイドラインは動きにくいので却下(緊急時の逃走に支障が出ます)。この総レースは引っかかり係数が高すぎるので却下」
マダムの顔が引きつり始めた。
「あ、あの、お嬢様……? デザインや流行については……?」
「機能美こそが至高です。戦場(舞踏会)に、飾りだけの鎧を着ていく騎士はいません」
アムリーは断言した。
彼女にとって舞踏会とは、優雅に踊る場所ではない。
情報収集と人脈形成、そして敵対勢力との腹の探り合いを行う『戦場』なのだ。
「……ははは!」
ギルバートが吹き出した。
「戦場か。違いない」
彼は楽しそうに笑うと、ラックの奥から一着のドレスを引き出した。
それは、深い夜の色――ミッドナイトブルーの生地に、銀糸の刺繍が施されたシックなドレスだった。
露出は控えめだが、背中のラインが大胆に開いている。
「これならどうだ? 汚れも目立たないし、威厳もある」
アムリーは生地を触り、縫製を確認し、裏地をチェックした。
「……シルクサテンの厚手生地。耐久性は合格。色味も、私の肌色とのコントラスト比において最適解かと。何より、足捌きが良さそうです」
「気に入ったか?」
「はい。この装備なら、カイル殿下にワインをかけられても、即座に回し蹴りで応戦できます」
「応戦はしなくていい。避けてくれ」
ギルバートは苦笑しつつ、マダムに合図を送った。
「これを頼む。あと、これに合う宝石もだ。予算は無制限でいい」
「かしこまりましたわ!」
マダムの目が金貨の色に輝いた。
◇
数十分後。
試着室のカーテンが開かれた。
「……いかがでしょうか」
アムリーが少し照れくさそうに姿を現す。
店内の空気が、一変した。
深い青のドレスは、アムリーの冷ややかな美貌を極限まで引き立てていた。
アップに結い上げられた銀髪。
露わになった白磁の背中。
そして首元には、ギルバートの瞳と同じアイスブルーのサファイアが輝いている。
それはもはや『悪役令嬢』というより、『氷の女王』と呼ぶにふさわしい気品と迫力だった。
「……」
ギルバートは言葉を失っていた。
いつもの皮肉な笑みも、冷徹な仮面も消え失せ、ただ呆然とアムリーを見つめている。
「閣下? 変でしょうか? やはり機能性を重視しすぎて、華やかさに欠けるのでは……」
アムリーが不安げに尋ねる。
ギルバートはハッと我に返り、ゆっくりと歩み寄った。
「……いや。訂正が必要だ」
「訂正?」
「『美しい』という言葉では足りない。……君は、恐ろしいほどに魅力的だ」
ギルバートの手が、アムリーの頬に触れる。
その指先がわずかに熱いことに、アムリーは驚いた。
「この姿を会場で見せれば、誰もがひれ伏すだろう。カイル殿下が泡を吹いて倒れる姿が目に浮かぶよ」
「それは効果絶大ですね。コストパフォーマンス最高の投資です」
アムリーは照れ隠しにそう言ったが、心臓の鼓動は早鐘を打っていた。
(おかしいわね……。コルセットの締め付けがきついのかしら? 酸素供給量が低下している気がする)
顔が熱い。
鏡に映る自分は、いつもの冷静な顔をしているはずなのに、耳まで赤い気がする。
「さあ、次は靴を選ぼう。君が『逃走』にも『追跡』にも使える、最強のヒールを」
「はい! ヒールの高さは七センチが限界です。それ以上は機動力が三〇%低下します!」
「了解した。……本当に、君は面白いな」
ギルバートは愛おしそうにアムリーの手を取り、エスコートした。
その様子を、店の外から恨めしそうに見つめる影があったことに、二人はまだ気づいていなかった。
◇
一方、その頃。
王都の裏通りにある質屋『強欲の壺』。
そこに、帽子を目深に被った男と、フードを被った小柄な女の姿があった。
「お、おい、本当にこれを売るのか? これは王家伝来の……」
「カイル様ぁ、仕方ないですぅ。だってお金がないと、ミナのドレスが買えないじゃないですかぁ」
カイルとミナである。
カイルの手には、小さな宝飾品が握られていた。
それは王太子の私物ではなく、王家の倉庫からこっそり持ち出したアンティークのブローチだった。
「でも、バレたら父上に殺される……」
「バレませんよぉ! それに、アムリーお姉様に勝つためです! ミナが一番可愛くなって、あのお姉様をギャフンと言わせるんです!」
ミナは拳を握りしめた。
あの日、宰相執務室から追い出された屈辱。
そして実家に届いた高額な請求書。
それらがミナの(歪んだ)対抗心に火をつけていた。
「そうだな……。あいつを見返してやらねば! 俺を振ったことを後悔させてやる!」
カイルは意を決して、質屋のカウンターにブローチを置いた。
「これを頼む! 最高級のドレスが買えるだけの金をくれ!」
質屋の親父が、ギロリと目を光らせた。
「……へいへい。出所は聞かねえことにしてやるよ」
ジャラジャラと硬貨の音が響く。
その金を手にした二人は、歪んだ笑みを浮かべた。
「見てろよアムリー! 今度の舞踏会が貴様の処刑場だ!」
「ミナの可愛さで、ギルバート様を奪っちゃいますぅ!」
二人の復讐計画(という名の自爆特攻準備)は、着々と進行していた。
◇
翌日。
宰相邸のダンスホールにて。
「ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー」
機械的なカウントが響いていた。
アムリーである。
彼女は真剣な顔で、ギルバートと組みながらステップを踏んでいた。
「アムリー。もう少し力を抜いて」
「無理です。重心移動のベクトル計算に集中しています」
アムリーの体は、木の棒のように硬い。
「ダンスは計算じゃない。相手に身を委ねるものだ」
「身を委ねる=転倒リスクの増加です。私は自分の足で立ちます」
「……はは、頑固だな」
ギルバートは苦笑しながら、ぐっとアムリーを引き寄せた。
「っ!?」
距離がゼロになる。
互いの呼吸がかかるほどの密着度。
「私を信じろ。絶対に転ばせないし、君を傷つけさせない」
ギルバートの低音が、鼓膜を震わせる。
「君はただ、私のリードに従って、優雅に微笑んでいればいい。……全ての面倒ごとは、私が処理する」
その言葉は、アムリーが今まで一人で背負ってきた重荷を、ふわりと持ち上げてくれるようだった。
王妃教育のプレッシャーも。
実家の借金も。
周囲の悪意も。
「……好条件すぎますね」
アムリーは小さく呟いた。
「そんなに甘やかされると、勘違いしてしまいそうです」
「勘違いすればいい。……私は本気だと言っているだろう?」
ギルバートはアムリーの額に、唇を寄せた。
チュッ。
軽い音とともに、アムリーの思考回路がショートした。
「~~~~っ!?」
「本番を楽しみにしているよ、私の可愛いアムリー」
真っ赤になって固まるアムリーを見て、ギルバートは満足げに笑った。
舞踏会まで、あと三日。
最強の装備と、最強のパートナーを得たアムリーの進撃が始まる。
6
あなたにおすすめの小説

『婚約破棄された悪役令嬢ですが、嫁ぎ先で“連れ子三人”の母になりました ~三人の「ママ」が聞けるまで、私は絶対に逃げません~』
放浪人
恋愛
「母はいりません」と拒絶された悪役令嬢が、最強の“ママ”になるまでの物語。
「君のような可愛げのない女は、王妃にふさわしくない」
身に覚えのない罪で婚約破棄され、“悪役令嬢”の汚名を着せられたクラリス。 彼女が新たに嫁いだのは、北方の辺境を守る「氷の公爵」ことレオンハルト・フォン・グレイフだった。
冷え切った屋敷で彼女を待っていたのは、無表情な夫と、心に傷を負った三人の連れ子たち。 「僕たちに、母はいりません」 初対面で突きつけられた三つの拒絶。しかし、クラリスは諦めなかった。
「称号はいりません。私が欲しいのは――あなたたち三人の『ママ』になれる日だけです」
得意の生活魔法『灯(ともしび)』で凍えた部屋を温め、『鎮(しずめ)』の歌で夜泣きを癒やし、家政手腕で荒れた食卓を立て直す。 クラリスの献身的な愛情は、頑なだった子供たちの心を解きほぐし、やがて不器用な夫の氷の心さえも熱く溶かしていく。
これは、不遇な悪役令嬢が「最強の母」となり、家族を脅かす元婚約者や魔獣たちを華麗に撃退し、最愛の家族から「ママ」と呼ばれるその日までを綴った物語。
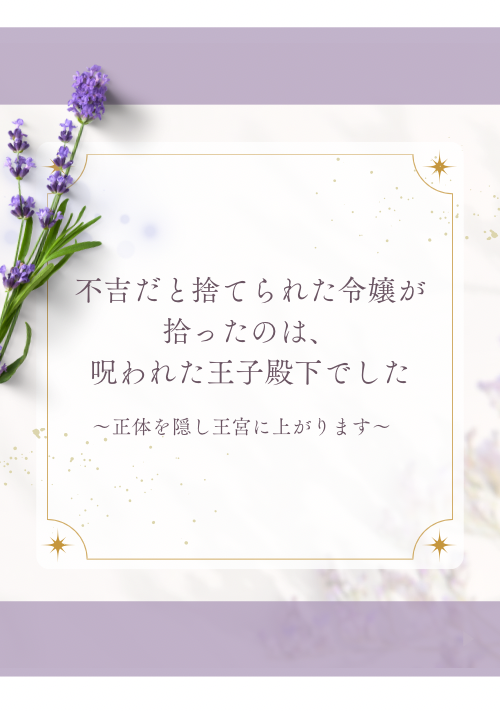
不吉だと捨てられた令嬢が拾ったのは、呪われた王子殿下でした ~正体を隠し王宮に上がります~
長井よる
恋愛
フローレス侯爵家の次女のレティシアは、この国で忌み嫌われる紫の髪と瞳を持って生まれたため、父親から疎まれ、ついには十歳の時に捨てられてしまう。
孤児となり、死にかけていたレティシアは、この国の高名な魔法使いに拾われ、彼の弟子として新たな人生を歩むことになる。
レティシアが十七歳になったある日、事故に遭い瀕死の王子アンドレアスを介抱する。アンドレアスの体には呪いがかけられており、成人まで生きられないという運命が待ち受けていた。レティシアは試行錯誤の末、何とか呪いの進行を止めることに成功する。
アンドレアスから、王宮に来てほしいと懇願されたレティシアは、正体を隠し王宮に上がることを決意するが……。
呪われた王子×秘密を抱えた令嬢(魔法使いの弟子)のラブストーリーです。
※残酷な描写注意
10/30:主要登場人物•事件設定をUPしました。

悪役令嬢まさかの『家出』
にとこん。
恋愛
王国の侯爵令嬢ルゥナ=フェリシェは、些細なすれ違いから突発的に家出をする。本人にとっては軽いお散歩のつもりだったが、方向音痴の彼女はそのまま隣国の帝国に迷い込み、なぜか牢獄に収監される羽目に。しかし無自覚な怪力と天然ぶりで脱獄してしまい、道に迷うたびに騒動を巻き起こす。
一方、婚約破棄を告げようとした王子レオニスは、当日にルゥナが失踪したことで騒然。王宮も侯爵家も大混乱となり、レオニス自身が捜索に出るが、恐らく最後まで彼女とは一度も出会えない。
ルゥナは道に迷っただけなのに、なぜか人助けを繰り返し、帝国の各地で英雄視されていく。そして気づけば彼女を慕う男たちが集まり始め、逆ハーレムの中心に。だが本人は一切自覚がなく、むしろ全員の好意に対して煙たがっている。
帰るつもりもなく、目的もなく、ただ好奇心のままに彷徨う“無害で最強な天然令嬢”による、帝国大騒動ギャグ恋愛コメディ、ここに開幕!


【完結】メルティは諦めない~立派なレディになったなら
すみ 小桜(sumitan)
恋愛
レドゼンツ伯爵家の次女メルティは、水面に映る未来を見る(予言)事ができた。ある日、父親が事故に遭う事を知りそれを止めた事によって、聖女となり第二王子と婚約する事になるが、なぜか姉であるクラリサがそれらを手にする事に――。51話で完結です。

働かないつもりでしたのに、気づけば全部うまくいっていました ――自由に生きる貴族夫人と溺愛旦那様』
鷹 綾
恋愛
前世では、仕事に追われるだけの人生を送り、恋も自由も知らないまま終わった私。
だからこそ転生後に誓った――
「今度こそ、働かずに優雅に生きる!」 と。
気づけば貴族夫人、しかも結婚相手は冷静沈着な名門貴族リチャード様。
「君は何もしなくていい。自由に過ごしてくれ」
――理想的すぎる条件に、これは勝ち確人生だと思ったのに。
なぜか気づけば、
・屋敷の管理を改善して使用人の待遇が激変
・夫の仕事を手伝ったら経理改革が大成功
・興味本位で教えた簿記と珠算が商業界に革命を起こす
・商人ギルドの顧問にまで祭り上げられる始末
「あれ? 私、働かない予定でしたよね???」
自分から出世街道を爆走するつもりはなかったはずなのに、
“やりたいことをやっていただけ”で、世界のほうが勝手に変わっていく。
一方、そんな彼女を静かに見守り続けていた夫・リチャードは、
実は昔から彼女を想い続けていた溺愛系旦那様で――。
「君が選ぶなら、私はずっとそばにいる」
働かないつもりだった貴族夫人が、
自由・仕事・愛情のすべてを“自分で選ぶ”人生に辿り着く物語。
これは、
何もしないはずだったのに、幸せだけは全部手に入れてしまった女性の物語。

一夜限りの関係だったはずなのに、責任を取れと迫られてます。
甘寧
恋愛
魔女であるシャルロッテは、偉才と呼ばれる魔導師ルイースとひょんなことから身体の関係を持ってしまう。
だがそれはお互いに同意の上で一夜限りという約束だった。
それなのに、ルイースはシャルロッテの元を訪れ「責任を取ってもらう」と言い出した。
後腐れのない関係を好むシャルロッテは、何とかして逃げようと考える。しかし、逃げれば逃げるだけ愛が重くなっていくルイース…
身体から始まる恋愛模様◎
※タイトル一部変更しました。

5分前契約した没落令嬢は、辺境伯の花嫁暮らしを楽しむうちに大国の皇帝の妻になる
西野歌夏
恋愛
ロザーラ・アリーシャ・エヴルーは、美しい顔と妖艶な体を誇る没落令嬢であった。お家の窮状は深刻だ。そこに半年前に陛下から連絡があってー
私の本当の人生は大陸を横断して、辺境の伯爵家に嫁ぐところから始まる。ただ、その前に最初の契約について語らなければならない。没落令嬢のロザーラには、秘密があった。陛下との契約の背景には、秘密の契約が存在した。やがて、ロザーラは花嫁となりながらも、大国ジークベインリードハルトの皇帝選抜に巻き込まれ、陰謀と暗号にまみれた旅路を駆け抜けることになる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















