あなたにおすすめの小説

愛してやまなかった婚約者は俺に興味がない
了承
BL
卒業パーティー。
皇子は婚約者に破棄を告げ、左腕には新しい恋人を抱いていた。
青年はただ微笑み、一枚の紙を手渡す。
皇子が目を向けた、その瞬間——。
「この瞬間だと思った。」
すべてを愛で終わらせた、沈黙の恋の物語。
IFストーリーあり
誤字あれば報告お願いします!

【完結】伯爵家当主になりますので、お飾りの婚約者の僕は早く捨てて下さいね?
MEIKO
BL
【完結】伯爵家次男のマリンは、公爵家嫡男のミシェルの婚約者として一緒に過ごしているが実際はお飾りの存在だ。そんなマリンは池に落ちたショックで前世は日本人の男子で今この世界が小説の中なんだと気付いた。マズい!このままだとミシェルから婚約破棄されて路頭に迷う未来しか見えない!
僕はそこから前世の特技を活かしてお金を貯め、ミシェルに愛する人が現れるその日に備えだす。2年後、万全の備えと新たな朗報を得た僕は、もう婚約破棄してもらっていいんですけど?ってミシェルに告げる。なのに対象外のはずの僕に未練たらたらなのどうして?
※R対象話には『*』マーク付けます。

婚約破棄させた愛し合う2人にザマァされた俺。とその後
結人
BL
王太子妃になるために頑張ってた公爵家の三男アランが愛する2人の愛でザマァされ…溺愛される話。
※男しかいない世界で男同士でも結婚できます。子供はなんかしたら作ることができます。きっと…。
全5話完結。予約更新します。

転生したら同性の婚約者に毛嫌いされていた俺の話
鳴海
BL
前世を思い出した俺には、驚くことに同性の婚約者がいた。
この世界では同性同士での恋愛や結婚は普通に認められていて、なんと出産だってできるという。
俺は婚約者に毛嫌いされているけれど、それは前世を思い出す前の俺の性格が最悪だったからだ。
我儘で傲慢な俺は、学園でも嫌われ者。
そんな主人公が前世を思い出したことで自分の行動を反省し、行動を改め、友達を作り、婚約者とも仲直りして愛されて幸せになるまでの話。

転生したら、主人公の宿敵(でも俺の推し)の側近でした
リリーブルー
BL
「しごとより、いのち」厚労省の過労死等防止対策のスローガンです。過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ。この小説の主人公は、仕事依存で過労死し異世界転生します。
仕事依存だった主人公(20代社畜)は、過労で倒れた拍子に異世界へ転生。目を覚ますと、そこは剣と魔法の世界——。愛読していた小説のラスボス貴族、すなわち原作主人公の宿敵(ライバル)レオナルト公爵に仕える側近の美青年貴族・シリル(20代)になっていた!
原作小説では悪役のレオナルト公爵。でも主人公はレオナルトに感情移入して読んでおり彼が推しだった! なので嬉しい!
だが問題は、そのラスボス貴族・レオナルト公爵(30代)が、物語の中では原作主人公にとっての宿敵ゆえに、原作小説では彼の冷酷な策略によって国家間の戦争へと突き進み、最終的にレオナルトと側近のシリルは処刑される運命だったことだ。
「俺、このままだと死ぬやつじゃん……」
死を回避するために、主人公、すなわち転生先の新しいシリルは、レオナルト公爵の信頼を得て歴史を変えようと決意。しかし、レオナルトは原作とは違い、どこか寂しげで孤独を抱えている様子。さらに、主人公が意外な才覚を発揮するたびに、公爵の態度が甘くなり、なぜか距離が近くなっていく。主人公は気づく。レオナルト公爵が悪に染まる原因は、彼の孤独と裏切られ続けた過去にあるのではないかと。そして彼を救おうと奔走するが、それは同時に、公爵からの執着を招くことになり——!?
原作主人公ラセル王太子も出てきて話は複雑に!
見どころ
・転生
・主従
・推しである原作悪役に溺愛される
・前世の経験と知識を活かす
・政治的な駆け引きとバトル要素(少し)
・ダークヒーロー(攻め)の変化(冷酷な公爵が愛を知り、主人公に執着・溺愛する過程)
・黒猫もふもふ
番外編では。
・もふもふ獣人化
・切ない裏側
・少年時代
などなど
最初は、推しの信頼を得るために、ほのぼの日常スローライフ、かわいい黒猫が出てきます。中盤にバトルがあって、解決、という流れ。後日譚は、ほのぼのに戻るかも。本編は完結しましたが、後日譚や番外編、ifルートなど、続々更新中。
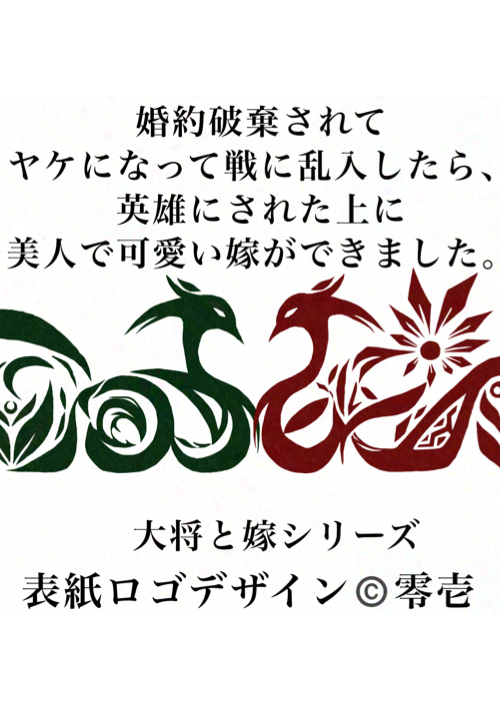
婚約破棄されてヤケになって戦に乱入したら、英雄にされた上に美人で可愛い嫁ができました。
零壱
BL
自己肯定感ゼロ×圧倒的王太子───美形スパダリ同士の成長と恋のファンタジーBL。
鎖国国家クルシュの第三王子アースィムは、結婚式目前にして長年の婚約を一方的に破棄される。
ヤケになり、賑やかな幼馴染み達を引き連れ無関係の戦場に乗り込んだ結果───何故か英雄に祭り上げられ、なぜか嫁(男)まで手に入れてしまう。
「自分なんかがこんなどちゃくそ美人(男)を……」と悩むアースィム(攻)と、
「この私に不満があるのか」と詰め寄る王太子セオドア(受)。
互いを想い合う二人が紡ぐ、恋と成長の物語。
他にも幼馴染み達の一抹の寂寥を切り取った短篇や、
両想いなのに攻めの鈍感さで拗れる二人の恋を含む全四篇。
フッと笑えて、ギュッと胸が詰まる。
丁寧に読みたい、大人のためのファンタジーBL。
他サイトでも公開しております。
表紙ロゴは零壱の著作物です。

【完結】家も家族もなくし婚約者にも捨てられた僕だけど、隣国の宰相を助けたら囲われて大切にされています。
cyan
BL
留学中に実家が潰れて家族を失くし、婚約者にも捨てられ、どこにも行く宛てがなく彷徨っていた僕を助けてくれたのは隣国の宰相だった。
家が潰れた僕は平民。彼は宰相様、それなのに僕は恐れ多くも彼に恋をした。

あなたと過ごせた日々は幸せでした
蒸しケーキ
BL
結婚から五年後、幸せな日々を過ごしていたシューン・トアは、突然義父に「息子と別れてやってくれ」と冷酷に告げられる。そんな言葉にシューンは、何一つ言い返せず、飲み込むしかなかった。そして、夫であるアインス・キールに離婚を切り出すが、アインスがそう簡単にシューンを手離す訳もなく......。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















