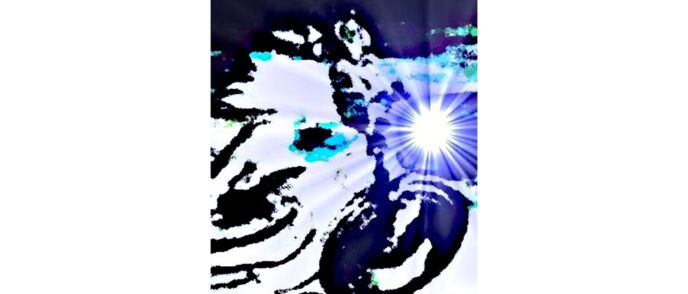1 / 9
あいつのGTサンパチ
しおりを挟む
(まったくあの女、私に勉強教えに来てるのかね。それとも性格の悪い女のやり方を教えに来てるのかね。医学部かなんか知らないけど、あんたはアタマいいだろうけどさ。私はあんたと違うから。微分積分も、アボガドロの法則も、解の公式も分かんないよ。それで私が分かんないでいると、『は~』とため息ついて、『あなたねえ、高校二年生の夏休みで解の公式なんかやってる場合じゃないのよ。いったいどうするつもり?』とか言ってさあ。また『は~』とかため息ついてから教え始める。あ~やだやだ。もうやってらんない!)
ハナは家庭教師の「お勉強」が終わった後、部屋で一人、鬱々としていた。ハナ。鈴木ハナ。
一七歳。
父は医者で「ご立派」な人物。運転が超下手くそなくせに、医者たちの間で見栄を張ってGTRなんかに乗っている。スポーツカー?オートマじゃん。
母はこれまた見栄っ張りで、アルファロメオに乗って、ブランド品の時計、バッグ、アクセサリーなんかで身を固め、授業参観だのPTAだの。
そして極めつけはハナの担任! 毎日毎日狂ったように恐ろしく大量の宿題を出す。とにかく、宿題をたくさん出せば生徒が勉強するとでも思っているアタマ悪い男。宿題なんか、どうせみんな移し合いっこしてるだけなのに。
それでもってハナの母の口癖は、
「ハナちゃん宿題は?」
それからハナが一人、部屋で愚痴っていると、ピアノの先生がピンポーンとやってきた。それから弾きたくもないピアノを二時間、ばっちり弾かされた。メヌエットにアラベスク。
「はいそこはテンポよく。スタッカートでしょ!」
「そこはもっと丁寧に。そこはデクレッセント…」
それからスイミングと英会話にバレエ。
オリンピックで水泳に出るわけじゃなし。外国留学するわけじゃなし。バレリーナになるわけじゃなし。とにかく一週間に七回の「習い事」!
遊びたい年頃なのに、遊ぶ暇なんてありはしない。
ハナには二人の姉がいる。二人ともお習い事、お勉強、宿題を立派に両立させ、今は立派に医学部へ行っていた。それにひきかえ自分は…
だから両親は自分のことを少しも愛していないと、ハナはいつも思っていた。
そもそも自分は両親にとって、単なる「見栄」の道具ではないのか…
だけど自分の出来が悪くて見栄を張れない。見栄っ張り!
何でGTRなの? 何でアルファロメオなの?
スズキのアルトくらいじゃダメなの?
私は鈴木ハナ。見栄張りの道具になんか、なれないよ。
それからハナの心の中で、「嫌な気持ち」がどんどん膨らんでいった。
(もういや。こんな家、出てってやる。もう、死んでやる!)
そして深夜。
ハナはパジャマのまま、二階の自分の部屋の窓を開け、一回の屋根の上に降り、それから何とか地面にたどりついた。実はこれは計画的犯行だった。
ハナの家には、これまた両親が見栄を張るために、立派な「お庭」があり、植木の手入れのための梯子もあった。ハナはその日の夕方、その梯子を自分の部屋からの「脱出」のために、雨どいの辺りに掛けておいたのだ。
そして無事脱出に成功したハナは、それから裸足でふらふらと道を歩き、大通りに出た。
深夜で車はほとんど走っていなかった。
だけどしばらくして、一つのヘッドライトが見え、ぐんぐん近づいてきた。そしてハナの目の前にそのヘッドライトが迫り、クオ~ンクオ~ンと、心地よいエンジンの音が聞こえた。
(あのオートバイにひかれよう)
そう思ったハナは道路に飛び出し、目をつぶった…
バンバンバンバンというシフトダウンの音と、キーっというブレーキの音。
オートバイはハナの目前で止まった。焼けたエンジンオイルの匂いがした。
それからライダーはエンジンを止め、サイドスタンドを出し、ハナに歩み寄り言った。
「お前、死にたいのか?」
「そうよ。死にたいのよ」
「ふざけるな。そしたら俺、加害者じゃないか!」
「ごめん」
「意外と素直だな。ところでおまえ、花山手なんかに住んで、いいところの御嬢さんに見えるけど、こんな時間に裸足でパジャマなんか着て、一体何やってんだ?」
「だから死のうと思ってたの」
「パジャマを着てか?」
「そうよ」
「いいかげんにしろ!」
「ねえ、オートバイ、乗せて。事故って私を殺してよ」
「乗せるのはいいが、俺は簡単には事故らないぞ」
「じゃ、海のきれいなとこ、連れてって」
「パジャマを着てか?」
「まあいいじゃない。夜だから見えやしないよ」
「だけど夜なら海も見えないぞ」
「今夜は月が出てるでしょ」
「おまえ理屈こねるな」
「いいじゃん」
「じゃ乗れ」
それからオートバイは「クオーンクオーン」という独特の音をたて、深夜の街を疾走した。真夏の夜風がビュービューと心地よい。ハナのパジャマがその風にバタバタと揺れ、そしてその風は、ハナの鬱々とした心を、少しずつ吹き飛ばした。
そしてオートバイは走り続け、スリリングに車体を傾け、カーブを曲がり、堀切峠を越え、イルカ岬に着いた。
そしてそこにあるイカした岩に二人で並んで座った。オートバイから焼けたオイルの匂いがした。
二人の座った岩からは、月に照らされた海がきれいに見えた。
「ねえ、これ、何ていうオートバイ?」
「スズキのGTサンパチ」
「サンパチ? 変な名前」
「乗せてもらったのに文句言うな!」
「ごめん。だけど、スズキはアルトじゃないの?」
「それは四つ輪だろう」
「ヨツワって?」
「クルマのこと。俺はクルマは嫌いだね」
「何となく分かる。でもかっこいいね。サンパチって」
「サンパチの前はハスラーに乗ってたんだ」
「だけどハスラーって、クルマでしょ?」
「バカヤロウ。ハスラーはバイクに決まってるだろう。オフロードの」
「オフロードって?」
「おまえ、何にも分かってねえな」
「分かってるよ。お父さんのGTRも、お母さんのアルファロメオも、私、嫌いだもん」
「おまえん家、凄いんだな」
「凄くないよ。見栄張ってるだけだよ。GTRも、アルファロメオも、見栄張るための道具だよ。どっちも威張った顔してさ。ブランド物のバッグと一緒だよ」
「なかなかいいこと言うじゃねえか。ところでおまえ、名前は?」
「ハナ。鈴木ハナ」
「鈴木アルトじゃねえんだな」
「あたりまえでしょ。で、あんたは?」
「コウヘイ」
「苗字は」
「まあいいじゃんか」
「いいよ。で、コウヘイ君って、どんな字書くの?」
「俺、漢字、大っ嫌いだから、カタカナたくさんだ」
「わかったわ。じゃカタカナで、コウヘイ君ね」
「ああ、そうしなよ。ところでおまえ、ええと、ハナちゃん。どうしてこんな夜中に通りを歩いてたんだ? しかも俺のバイクの前に飛び出したりしてさ」
「だから私、死のうと思っていたのよ」
「死ぬ?」
「そうよ」
「バカヤロウ。死ぬんだったらタマゴくらい産んでから死ねよ」
「タマゴ?」
「そうだ。ニワトリはタマゴ産めなくなったら殺されるんだ」
「何の話?」
「俺、養鶏所で働いてるんだ。タマゴ産めなくなったニワトリは速攻で食鳥にされるんだ」
「え~! 可哀そう」
「現実は厳しいんだぞ!」
「そうなんだ。コウヘイ君、養鶏所で働いていたんだ」
「うん」
「ねえ、歳、いくつなの?」
「一七」
「じゃ、私と一緒じゃん。高校二年生?」
「高校は辞めた」
「どうして?」
「父ちゃん、死んじゃった。それで金、無くなって」
「そうなんだ…」
「母ちゃんも病気がちであまり無理出来ない。ときどきパートでレジ打ってるけど」
「それで高校、行けなくなっちゃったの?」
「そうだ。俺も働かなきゃいけなくなったんだ」
「ねえ、ところで養鶏所って、どんな仕事するの?」
「聞きたいか?」
「うん!」
「ええと、毎朝六時に鶏舎のカーテンを開ける」
「それから?」
「窓は金網が張ってあって、野鳥の進入を防いでるんだ。鳥インフルエンザがヤバいからさ」
「へぇ~」
「そしたら、卵がずらっとケージの卵受けに並んでる」
「凄い!」
「うちんとこみたいな零細だと、一つ一つ手で拾うんだ。結構重労働なんだぞ!」
「大変なんだね」
「それを出荷する。俺はまだクルマの免許ないから、社長が軽トラックでスーパーなんかを回るんだ。俺も一緒に行くこともあるけどね。だけど俺のいつもの仕事は配餌車という、なんていうか、カートみたいなので鶏に餌をやるんだ。そいつを押して、それで俺、毎日鶏に餌をあげてるんだ」
「何だか、楽しそう」
「バカヤロウ。大変なんだぞ!」
「そうか。そうだよね」
「あとはひよこ育てたり」
「ひよこって可愛いでしょ?」
「可愛いよ。だけどすぐにニワトリになって、ニワトリは物凄く糞をするし、それを処理するのも大変だぞ。臭いし」
「臭いの?」
「あたりまえだ。ばっちり服に臭い着くぞ」
「でもコウヘイ君、ちっとも臭わない」
「仕事終わってシャワー浴びて、着替えて、バイクで走るからさ」
「バイクで走るから?」
「風で臭いなんて飛んで行っちまうさ」
「ふーん。そうなんだ。そういえば私の嫌な気持もかなり吹き飛んだ!」
「それはよかった。だけどおまえ…、ええと、ハナちゃん。一体どうして死にたかったんだ?」
「死にたかった理由? そうね。家庭教師が嫌な女で、お父さんお母さんは見栄っ張りで、担任は気が狂ったように宿題ばっかし。ピアノの先生はごちゃごちゃうるさいし、バレエの練習まではじめちゃったし。それにスイミングに英会話に。だから私、自由な時間なんてありゃしない」
「そりゃ大変だね。俺、同情するよ」
「コウヘイ君はどうなの?」
「俺は朝六時から夜九時までばっちり仕事だ。日曜もほとんど休みないし。だからサンパチに乗れるのは夜中だけさ」
「え~! そうなんだ…」
「それに俺、高校行きたいよ。学校行ってるほうがずっと楽だぞ」
「嫌な担任でも?」
「ニワトリの糞まみれで一日働くより楽だろう」
「…」
「高校行ってる方が楽だって!」
「…そうだよね。うん。きっとそうだよ。コウヘイ君の方がずっと大変よ」
「まあそうでもねえけどさ」
「大変よ。だから私…、バカみたい。私、そんなことで死にたいだなんて」
「だけど死にたいなんて思うこと、誰にだってあるさ。俺にだってある」
「コウヘイ君も?」
「そうだ。誰にだってあるよ。俺だって、毎日鶏の糞にまみれて、いやになる時がある。だけどタマゴ産めなくなったニワトリは殺されるんだ。死にたくなくても」
「死にたくなくても…」
「だから生きていれるのは幸せなんだ」
「生きていれるのは幸せ?」
「そうだ!」
「…そうだよね。きっとそうだよね」
「だけどハナちゃんにはハナちゃんの悩みがあるんだろう?」
「うん。進学とか。それに、お姉ちゃんたち優秀だから、それにひきかえ私…」
「気にするな。みんな個性ってもんがあるんだから」
「個性?」
「そうだ。人間の価値なんて、ええと、お勉強なんかで決まってたまるか! そんなもので人間の価値決められたら、俺なんか核廃棄物だろうよ」
「え~、核廃棄物? コウヘイ君、そんなんじゃない。コウヘイ君は個性的な人だよ」
「だけど俺、毎日必死で生きてるだけだけどさ。でも、人それぞれさ。とにかくみんな大変なんだぜ」
「そうだよね。みんな結構大変なんだよね」
「だけどみんな個性があるんだ」
「個性?」
「そう。個性!」
「そうか。私、死のうと思ってたけど…」
「思ってたけど?」
「思ってたけど…」
「みんな個性があるから、だから死んではいけないんだ」
「個性があるから死んではいけない?」
「当たり前だろう」
「当たり前?」
「そうだ! 個性があるから、それって、オンリーワンっていうじゃないか」
「オンリーワン?」
「世界に一つの貴重な人間なんだ。だから死んではいけないんだ」
「世界に一つ…」
「そうだ!」
「…そうだよね。やっぱりそうかも」
「そうだ。世界に一つの個性だ」
「世界に一つの個性ね。大切なのね。死んではいけないのね。わかった!」
「よし!」
「私、今夜、コウヘイ君に逢えて良かったかも」
「良かったか?」
「うん」
「じゃ、もう死なないか?」
「うん!」
「約束するか?」
「約束する!」
それから赤色灯を点けた二台のパトカーが近づいてきた。
「やべえ。マッポだ!」
「マッポ?」
「警察」
「どうして?」
「お前、スマホ持って来てねえか?」
「あ、パジャマのポケットに入れて来た」
「GPSでここがばれたんだろうよ」
「スマホのGPS?」
「居場所がわかるんだ。きっとおまえの両親が警察に捜査願いでも出したんだろうよ」
それからパトカーが止まり、警察官が降りて来た。
「君はこの娘を誘拐したのかね?」
「お巡りさん、違います。私、コウヘイ君のサンパチに乗せてって、頼んだだけです」
「君のご両親が捜索願を出しているんだ」
「それに、コウヘイ君は私の命の恩人なんです!」
それから二人の警察官がコウヘイの両腕を掴んだ。
「お巡りさん、やめて下さい。私、死のうと思って、だけどコウヘイ君がサンパチに乗せてくれて、それでここまで来て、そして…、そしてコウヘイ君がいろんな話をしてくれて、だからコウヘイ君は、私の命の恩人なんです!」
「まあいい、とにかく署まで来てもらう。それから鈴木ハナちゃん。君はパトカーで家まで送ってあげよう。ご両親が心配しておられる」
「お巡りさん。コウヘイ君は何も悪いことしていません! 絶対に、絶対に、私を誘拐なんてしていません! それに命の恩人…」
「まあいい。とにかく署まで来てもらう」
そう言うと二人の警察官がコウヘイをパトカーに乗せようとした。
「やめて! コウヘイ君は何も悪いことしていません!」
「とにかく署まで…」
それからコウヘイは一度警察官の腕を振り払い、そして毅然とこう言った。
「お巡りさん。これだけは言わせてよ。ハナちゃんに」
「まあいい。それじゃ言いなさい」
「ハナちゃん、俺のことなら心配するな。自分のことは何とかするから。だけど俺…、俺、いつかきっと立派な社長になって、そしていつの日か…、いつの日か、きっと俺、ハナちゃんを迎えに行くからな!」
ハナは家庭教師の「お勉強」が終わった後、部屋で一人、鬱々としていた。ハナ。鈴木ハナ。
一七歳。
父は医者で「ご立派」な人物。運転が超下手くそなくせに、医者たちの間で見栄を張ってGTRなんかに乗っている。スポーツカー?オートマじゃん。
母はこれまた見栄っ張りで、アルファロメオに乗って、ブランド品の時計、バッグ、アクセサリーなんかで身を固め、授業参観だのPTAだの。
そして極めつけはハナの担任! 毎日毎日狂ったように恐ろしく大量の宿題を出す。とにかく、宿題をたくさん出せば生徒が勉強するとでも思っているアタマ悪い男。宿題なんか、どうせみんな移し合いっこしてるだけなのに。
それでもってハナの母の口癖は、
「ハナちゃん宿題は?」
それからハナが一人、部屋で愚痴っていると、ピアノの先生がピンポーンとやってきた。それから弾きたくもないピアノを二時間、ばっちり弾かされた。メヌエットにアラベスク。
「はいそこはテンポよく。スタッカートでしょ!」
「そこはもっと丁寧に。そこはデクレッセント…」
それからスイミングと英会話にバレエ。
オリンピックで水泳に出るわけじゃなし。外国留学するわけじゃなし。バレリーナになるわけじゃなし。とにかく一週間に七回の「習い事」!
遊びたい年頃なのに、遊ぶ暇なんてありはしない。
ハナには二人の姉がいる。二人ともお習い事、お勉強、宿題を立派に両立させ、今は立派に医学部へ行っていた。それにひきかえ自分は…
だから両親は自分のことを少しも愛していないと、ハナはいつも思っていた。
そもそも自分は両親にとって、単なる「見栄」の道具ではないのか…
だけど自分の出来が悪くて見栄を張れない。見栄っ張り!
何でGTRなの? 何でアルファロメオなの?
スズキのアルトくらいじゃダメなの?
私は鈴木ハナ。見栄張りの道具になんか、なれないよ。
それからハナの心の中で、「嫌な気持ち」がどんどん膨らんでいった。
(もういや。こんな家、出てってやる。もう、死んでやる!)
そして深夜。
ハナはパジャマのまま、二階の自分の部屋の窓を開け、一回の屋根の上に降り、それから何とか地面にたどりついた。実はこれは計画的犯行だった。
ハナの家には、これまた両親が見栄を張るために、立派な「お庭」があり、植木の手入れのための梯子もあった。ハナはその日の夕方、その梯子を自分の部屋からの「脱出」のために、雨どいの辺りに掛けておいたのだ。
そして無事脱出に成功したハナは、それから裸足でふらふらと道を歩き、大通りに出た。
深夜で車はほとんど走っていなかった。
だけどしばらくして、一つのヘッドライトが見え、ぐんぐん近づいてきた。そしてハナの目の前にそのヘッドライトが迫り、クオ~ンクオ~ンと、心地よいエンジンの音が聞こえた。
(あのオートバイにひかれよう)
そう思ったハナは道路に飛び出し、目をつぶった…
バンバンバンバンというシフトダウンの音と、キーっというブレーキの音。
オートバイはハナの目前で止まった。焼けたエンジンオイルの匂いがした。
それからライダーはエンジンを止め、サイドスタンドを出し、ハナに歩み寄り言った。
「お前、死にたいのか?」
「そうよ。死にたいのよ」
「ふざけるな。そしたら俺、加害者じゃないか!」
「ごめん」
「意外と素直だな。ところでおまえ、花山手なんかに住んで、いいところの御嬢さんに見えるけど、こんな時間に裸足でパジャマなんか着て、一体何やってんだ?」
「だから死のうと思ってたの」
「パジャマを着てか?」
「そうよ」
「いいかげんにしろ!」
「ねえ、オートバイ、乗せて。事故って私を殺してよ」
「乗せるのはいいが、俺は簡単には事故らないぞ」
「じゃ、海のきれいなとこ、連れてって」
「パジャマを着てか?」
「まあいいじゃない。夜だから見えやしないよ」
「だけど夜なら海も見えないぞ」
「今夜は月が出てるでしょ」
「おまえ理屈こねるな」
「いいじゃん」
「じゃ乗れ」
それからオートバイは「クオーンクオーン」という独特の音をたて、深夜の街を疾走した。真夏の夜風がビュービューと心地よい。ハナのパジャマがその風にバタバタと揺れ、そしてその風は、ハナの鬱々とした心を、少しずつ吹き飛ばした。
そしてオートバイは走り続け、スリリングに車体を傾け、カーブを曲がり、堀切峠を越え、イルカ岬に着いた。
そしてそこにあるイカした岩に二人で並んで座った。オートバイから焼けたオイルの匂いがした。
二人の座った岩からは、月に照らされた海がきれいに見えた。
「ねえ、これ、何ていうオートバイ?」
「スズキのGTサンパチ」
「サンパチ? 変な名前」
「乗せてもらったのに文句言うな!」
「ごめん。だけど、スズキはアルトじゃないの?」
「それは四つ輪だろう」
「ヨツワって?」
「クルマのこと。俺はクルマは嫌いだね」
「何となく分かる。でもかっこいいね。サンパチって」
「サンパチの前はハスラーに乗ってたんだ」
「だけどハスラーって、クルマでしょ?」
「バカヤロウ。ハスラーはバイクに決まってるだろう。オフロードの」
「オフロードって?」
「おまえ、何にも分かってねえな」
「分かってるよ。お父さんのGTRも、お母さんのアルファロメオも、私、嫌いだもん」
「おまえん家、凄いんだな」
「凄くないよ。見栄張ってるだけだよ。GTRも、アルファロメオも、見栄張るための道具だよ。どっちも威張った顔してさ。ブランド物のバッグと一緒だよ」
「なかなかいいこと言うじゃねえか。ところでおまえ、名前は?」
「ハナ。鈴木ハナ」
「鈴木アルトじゃねえんだな」
「あたりまえでしょ。で、あんたは?」
「コウヘイ」
「苗字は」
「まあいいじゃんか」
「いいよ。で、コウヘイ君って、どんな字書くの?」
「俺、漢字、大っ嫌いだから、カタカナたくさんだ」
「わかったわ。じゃカタカナで、コウヘイ君ね」
「ああ、そうしなよ。ところでおまえ、ええと、ハナちゃん。どうしてこんな夜中に通りを歩いてたんだ? しかも俺のバイクの前に飛び出したりしてさ」
「だから私、死のうと思っていたのよ」
「死ぬ?」
「そうよ」
「バカヤロウ。死ぬんだったらタマゴくらい産んでから死ねよ」
「タマゴ?」
「そうだ。ニワトリはタマゴ産めなくなったら殺されるんだ」
「何の話?」
「俺、養鶏所で働いてるんだ。タマゴ産めなくなったニワトリは速攻で食鳥にされるんだ」
「え~! 可哀そう」
「現実は厳しいんだぞ!」
「そうなんだ。コウヘイ君、養鶏所で働いていたんだ」
「うん」
「ねえ、歳、いくつなの?」
「一七」
「じゃ、私と一緒じゃん。高校二年生?」
「高校は辞めた」
「どうして?」
「父ちゃん、死んじゃった。それで金、無くなって」
「そうなんだ…」
「母ちゃんも病気がちであまり無理出来ない。ときどきパートでレジ打ってるけど」
「それで高校、行けなくなっちゃったの?」
「そうだ。俺も働かなきゃいけなくなったんだ」
「ねえ、ところで養鶏所って、どんな仕事するの?」
「聞きたいか?」
「うん!」
「ええと、毎朝六時に鶏舎のカーテンを開ける」
「それから?」
「窓は金網が張ってあって、野鳥の進入を防いでるんだ。鳥インフルエンザがヤバいからさ」
「へぇ~」
「そしたら、卵がずらっとケージの卵受けに並んでる」
「凄い!」
「うちんとこみたいな零細だと、一つ一つ手で拾うんだ。結構重労働なんだぞ!」
「大変なんだね」
「それを出荷する。俺はまだクルマの免許ないから、社長が軽トラックでスーパーなんかを回るんだ。俺も一緒に行くこともあるけどね。だけど俺のいつもの仕事は配餌車という、なんていうか、カートみたいなので鶏に餌をやるんだ。そいつを押して、それで俺、毎日鶏に餌をあげてるんだ」
「何だか、楽しそう」
「バカヤロウ。大変なんだぞ!」
「そうか。そうだよね」
「あとはひよこ育てたり」
「ひよこって可愛いでしょ?」
「可愛いよ。だけどすぐにニワトリになって、ニワトリは物凄く糞をするし、それを処理するのも大変だぞ。臭いし」
「臭いの?」
「あたりまえだ。ばっちり服に臭い着くぞ」
「でもコウヘイ君、ちっとも臭わない」
「仕事終わってシャワー浴びて、着替えて、バイクで走るからさ」
「バイクで走るから?」
「風で臭いなんて飛んで行っちまうさ」
「ふーん。そうなんだ。そういえば私の嫌な気持もかなり吹き飛んだ!」
「それはよかった。だけどおまえ…、ええと、ハナちゃん。一体どうして死にたかったんだ?」
「死にたかった理由? そうね。家庭教師が嫌な女で、お父さんお母さんは見栄っ張りで、担任は気が狂ったように宿題ばっかし。ピアノの先生はごちゃごちゃうるさいし、バレエの練習まではじめちゃったし。それにスイミングに英会話に。だから私、自由な時間なんてありゃしない」
「そりゃ大変だね。俺、同情するよ」
「コウヘイ君はどうなの?」
「俺は朝六時から夜九時までばっちり仕事だ。日曜もほとんど休みないし。だからサンパチに乗れるのは夜中だけさ」
「え~! そうなんだ…」
「それに俺、高校行きたいよ。学校行ってるほうがずっと楽だぞ」
「嫌な担任でも?」
「ニワトリの糞まみれで一日働くより楽だろう」
「…」
「高校行ってる方が楽だって!」
「…そうだよね。うん。きっとそうだよ。コウヘイ君の方がずっと大変よ」
「まあそうでもねえけどさ」
「大変よ。だから私…、バカみたい。私、そんなことで死にたいだなんて」
「だけど死にたいなんて思うこと、誰にだってあるさ。俺にだってある」
「コウヘイ君も?」
「そうだ。誰にだってあるよ。俺だって、毎日鶏の糞にまみれて、いやになる時がある。だけどタマゴ産めなくなったニワトリは殺されるんだ。死にたくなくても」
「死にたくなくても…」
「だから生きていれるのは幸せなんだ」
「生きていれるのは幸せ?」
「そうだ!」
「…そうだよね。きっとそうだよね」
「だけどハナちゃんにはハナちゃんの悩みがあるんだろう?」
「うん。進学とか。それに、お姉ちゃんたち優秀だから、それにひきかえ私…」
「気にするな。みんな個性ってもんがあるんだから」
「個性?」
「そうだ。人間の価値なんて、ええと、お勉強なんかで決まってたまるか! そんなもので人間の価値決められたら、俺なんか核廃棄物だろうよ」
「え~、核廃棄物? コウヘイ君、そんなんじゃない。コウヘイ君は個性的な人だよ」
「だけど俺、毎日必死で生きてるだけだけどさ。でも、人それぞれさ。とにかくみんな大変なんだぜ」
「そうだよね。みんな結構大変なんだよね」
「だけどみんな個性があるんだ」
「個性?」
「そう。個性!」
「そうか。私、死のうと思ってたけど…」
「思ってたけど?」
「思ってたけど…」
「みんな個性があるから、だから死んではいけないんだ」
「個性があるから死んではいけない?」
「当たり前だろう」
「当たり前?」
「そうだ! 個性があるから、それって、オンリーワンっていうじゃないか」
「オンリーワン?」
「世界に一つの貴重な人間なんだ。だから死んではいけないんだ」
「世界に一つ…」
「そうだ!」
「…そうだよね。やっぱりそうかも」
「そうだ。世界に一つの個性だ」
「世界に一つの個性ね。大切なのね。死んではいけないのね。わかった!」
「よし!」
「私、今夜、コウヘイ君に逢えて良かったかも」
「良かったか?」
「うん」
「じゃ、もう死なないか?」
「うん!」
「約束するか?」
「約束する!」
それから赤色灯を点けた二台のパトカーが近づいてきた。
「やべえ。マッポだ!」
「マッポ?」
「警察」
「どうして?」
「お前、スマホ持って来てねえか?」
「あ、パジャマのポケットに入れて来た」
「GPSでここがばれたんだろうよ」
「スマホのGPS?」
「居場所がわかるんだ。きっとおまえの両親が警察に捜査願いでも出したんだろうよ」
それからパトカーが止まり、警察官が降りて来た。
「君はこの娘を誘拐したのかね?」
「お巡りさん、違います。私、コウヘイ君のサンパチに乗せてって、頼んだだけです」
「君のご両親が捜索願を出しているんだ」
「それに、コウヘイ君は私の命の恩人なんです!」
それから二人の警察官がコウヘイの両腕を掴んだ。
「お巡りさん、やめて下さい。私、死のうと思って、だけどコウヘイ君がサンパチに乗せてくれて、それでここまで来て、そして…、そしてコウヘイ君がいろんな話をしてくれて、だからコウヘイ君は、私の命の恩人なんです!」
「まあいい、とにかく署まで来てもらう。それから鈴木ハナちゃん。君はパトカーで家まで送ってあげよう。ご両親が心配しておられる」
「お巡りさん。コウヘイ君は何も悪いことしていません! 絶対に、絶対に、私を誘拐なんてしていません! それに命の恩人…」
「まあいい。とにかく署まで来てもらう」
そう言うと二人の警察官がコウヘイをパトカーに乗せようとした。
「やめて! コウヘイ君は何も悪いことしていません!」
「とにかく署まで…」
それからコウヘイは一度警察官の腕を振り払い、そして毅然とこう言った。
「お巡りさん。これだけは言わせてよ。ハナちゃんに」
「まあいい。それじゃ言いなさい」
「ハナちゃん、俺のことなら心配するな。自分のことは何とかするから。だけど俺…、俺、いつかきっと立派な社長になって、そしていつの日か…、いつの日か、きっと俺、ハナちゃんを迎えに行くからな!」
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる