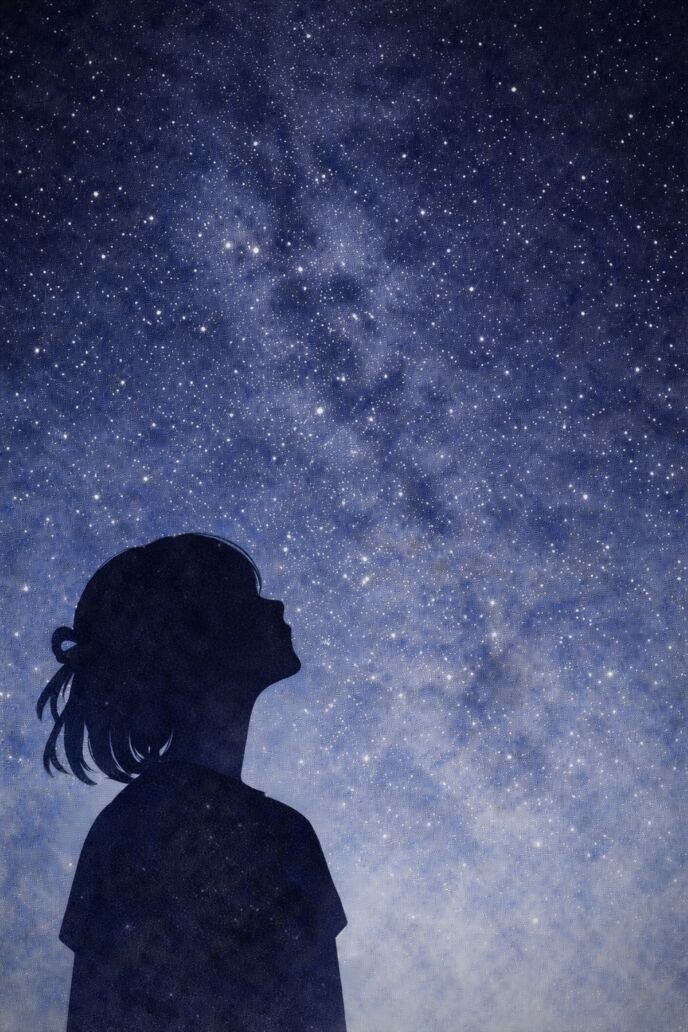2 / 3
後編
しおりを挟む今日は満月だね。
暁ひかりは空を見上げる。
今日という「約束の日」まで、ひかりは太陽が沈む瞬間を数え続けた。
満月だった日も、三日月だった日も、雲で月が見えない日も、全てを数えた。
雨と風が舞い、散ってゆく花びらの枚数も、一枚一枚、ひかりは数えた。
そして、数えた数をひかりは覚えている。
だから、控えめに歩いてくる足音に心が跳ねた。
ゆっくりと振り向くと、日枯 が花束を持ちながら、悲しそうに笑う。
「お久しぶりです」
暁ひかりは、ゆっくりと笑ってみせる。
「こんばんは」
日枯 は、暁ひかりの足元に花束を置いた。
花の色は赤、オレンジ、黄色、黄緑。
全て、ひかりが好きな色だった。
「ありがとう」
ひかりの言葉に、日枯 の目が少し潤む。
「今日までの僕の思い出、聞いてくれますか?」
日枯 の言葉にひかりは頷く。
「聞きたいな」
「僕、高校生になりました」
「そうだね」
「制服、似合っていないですよね」
「ううん。とてもかっこいいな」
橙色のブレザーを1ミリのズレもなく、しっかりと着ている。小学生の頃から、変わらないなぁ。
「髪も短くしたんだね」
「はい」
「でも、目の色は黄色のままだね」
「はい。生まれつきなので……」
「うん。知ってる。私が一番好きな色」
日枯 が顔をあげる。
「僕の顔、変わりましたか?」
「むー君の顔、全然、変わっていないね。私が小学生の頃から知っている顔」
「でも……」
日枯 は言葉を飲み込む。
「そうだね。でも、もう、私より年上になっちゃったね」
立派な高校生になったんだね。
嬉しいな。
暁ひかりは、ふたたび空を見上げる。
「今日は花火大会らしいね」
「はい」
「せっかくなら、この橋からも見えたらよかったのにね」
「そうですね……」
狼煙の音がした。
そして、夜空が青く光り出す。
「ひかりさんに見てほしいんです」
日枯 は携帯電話を取り出して、画面を見せる。
紺色と茜色が重なる夕焼け空の写真に、ひかりの目が輝く。
「とても綺麗な空の色。とても綺麗な写真だね」
「この空の色、教室の窓から見えるんです」
だから、僕、夕陽に見惚れて部活に遅刻しちゃうんです。
日枯 の言葉にひかりは「むー君らしいね」と笑った。
「でも、僕、しっかりとフルートを練習しているんですよ」
「そうなんだ。私のお母さん、とても厳しいでしょ」
「はい。今年も毎日、怒られっぱなしです」
「よく続けられているね。偉いよ」
「だって楽しいんです。どうしようもなく楽しいんです」
日枯 が泣きそうな声で笑う。
「ひかりさんにフルートの吹き方を教えてもらえた日のこと、僕の人生の中で、一番楽しい思い出だったから……」
ひかりは、日枯 の言葉を待つ。
焦らなくていい。
「今日」という日はまだ終わらないのだから。
「自分の中で演奏できる楽器は、ピアノだけだと思っていました」
「うん、それが、すごく微笑ましくて、今でも笑っちゃうの」
「僕もです」
やっと二人で同時に笑えた。
日枯 の笑顔が本物に近づいたように見えた。
「実は、僕、新しい楽器に挑戦しているんです」
「そうなんだ。すごいね」
また、演奏できる楽器が増えたんだね。
ひかりの言葉に日枯 は、照れくさそうに俯く。
「僕、マンドリンって楽器を始めたんです」
「マンドリンって、どんな楽器なの?」
「イタリア発祥の弦楽器なんです。音がきらきらしているんです。まるで星空みたいに」
日枯 は、携帯電話を出して、マンドリンの音を流す。
「これ、僕たちの……マンドリン部としての初めての合奏なんです」
「すごいね。たしかにお星様みたいな音」
日枯 の肩から、少し力が抜けたように見えた。
「私の知らない場所で、知らない楽器に挑戦して、知らない音楽を奏でる。むー君が楽しそうで嬉しいな」
でも……と日枯 は唇を噛む。
「みんなと合奏して、新しい曲に挑戦して、うまく行かないこともあって、それでも楽しくて」
ひかりは静かに、日枯 の言葉を聞き続ける。
「みんなで笑い合って、みんなで校舎を出たときに、やっぱり思っちゃうんです。この中に、ひかりさんがいたら『もっと毎日が楽しくなるのに』って」
日枯 の語気が強くなってゆく。
「夜に一番、明るい星が見えたとき、思ってしまうんです。
ひかりさんの世界で生きて、ひかりさんと同じ時間を過ごして、ひかりさんと同じ景色を見る。そういう道を選ぶのも悪くないかもしれないって」
日枯 はまた俯いてしまう。
ひかりは星の数を数えるふりをする。
彼は何かを言いたげに時々、顔を上げようとする。
でも、顔を上げきることができないのは、きっと彼の中で、言葉が選べないからだろう。
口に出したい感情がある。
でも、その感情を表現する言葉が見つからない。
きっと、その感情そのものに、まだ、誰も名前をつけていない。
数秒の沈黙が流れた。
流れ星が見えた。
そして、ひかりは息を吸い、日枯 の顔を見つめた。
「私ね、ずっとこの橋にいて、気がついたことがあるの」
日枯 が顔を上げた。
彼の目はやっぱり綺麗な黄色の目。
でも、その目には星の光が届いてはいない。
「この橋にはね、たくさんの人が私に逢いに来てくれるの」
「僕みたいに?」
「そう」
ひかりはにこりと笑ってみせる。
「お母さんやお父さん、ピアノの先生とか、クラスで一緒だったみんながね。逢いに来てくれるの」
日枯 は黙って、ひかりの顔を見つめ続けていた。
ひかりはもう一度、笑ってみせてから、そっと口を開く。
「私に逢いに来てくれる人たちはね、みんな優しい顔をしているの。でも、みんなの声はいつも悲しそうなの」
「……僕の声も、悲しそうに聞こえているんですか?」
日枯 の問いに、ひかりは答えなかった。
「私ね、思ったんだ。自ら命を断つ人の選択を、私は責めることができない。自ら命を断つ人の価値観を否定することはできない。その人たちの人生を私は非難することができないの」
でもね。
ひかりはゆっくりと目を閉じた。
「人が自ら命を絶ったとき、必ず誰かが悲しむ。誰からも悲しまれない人なんていない。必ず誰かは悲しむ。それがたとえ一人であっても、必ず悲しむ人がいるの」
ひかりは目を開けて、今度こそ、しっかりと、まっすぐに日枯 の目を見つめる。
「自らの命を手放す選択を、私は否定することができない。けれどね、誰かが一人でも悲しむのなら、その行いは、きっと、正しくないんだって。ようやく気がついたの」
風が吹いた。
気持ちの良い夏の香りの風が。
ひかりの髪がゆらりとなびいた。
「今日の風の香り。一緒に帰ったあの日と同じだね」
「……はい。本当に、同じです……」
「あの日ね、むー君に楽譜を渡せて良かったって、今でも思っているの」
日枯 が顔を上げて尋ねる。「本当に、僕で良かったのですか?」
「私の譜面、今日も持ってきてくれたんでしょ」
「はい。もちろんです」
「私、実はね、むー君がずっと大切に持ち歩いてくれているのを知っているんだ」
「……どうしてですか?」
「だってそれは」
夜空の星を眺めながら、ひかりは優しく微笑んだ。
「むー君が『むー君』だから。そういう『人』だって知っているから」
日枯 は悲しそうに「嬉しいです」と声を絞り出す。
「僕と愛さんで、約束したんです。今日という日、『約束の日』以外は、ひかりさんに会わないって。だから、ひかりさんに会えるのがこれからは少なくなってしまって……でも、やっぱり……やっぱり、それが苦しくて……」
ひかりは何も言わずに、日枯 の言葉の続きを待つ。
風がまた静かに二人の顔を掠める。
「愛さんとの約束を破ることは、僕という『人間』が許してくれないんです。でも、ひかりさんの世界に行くことは、愛さんからは禁じられていないんです。だから、ひかりさんの世界に行くことを選んでも、約束を破ったことにはならないと思うんです」
満月を眺めながら、日枯 が口から息を吸った。
「けれど、その選択をすることは、僕の『倫理』に反するんです。決められていないから選ぶことはできる。でも、それを選んでしまうことは、きっと愛さんの信頼を、『心』を踏み躙るって、分かるんです。彼女が誠実であればあるほど、僕もそれに応えて、誠実でなければならない。それが僕の中での結論でした。僕の中の『僕が自分に課した倫理』でした」
日枯 の言葉をひかりは抱きしめる。
今のひかりにできるのは、それしかなかったから。
日枯 はひかりの横に立ち、一緒に星を眺める。
どちらが先に「右から二番目の星」を探せるか。
ひかりと日枯 の二人で勝負をして、ひかりが負けたことは一度もなかった。
でも、今日は負けちゃうかもなぁ。
二人で一緒に、「一番明るい星」を探し始める。
「ひかりさんの作った曲……『星空マーチ』を僕、編曲しているんです」
「とても嬉しいな。でも、大変じゃない? あの曲は未完成のまま、むー君に託しちゃったし」
「大変じゃないです。むしろ、楽しいというか、生き甲斐というか」
生き甲斐。
その言葉に、ひかりの心が締め付けられる。
この世に存在しない「人間」の遺産を、彼の生き甲斐にはしてほしくなかった。
ひかりは目を伏せる。
「ごめんね。私が未熟だったばかりに」
「そういう意味じゃないんです」
日枯 が初めて笑顔を見せた。
偽物ではない、本物の笑顔を。
「ひかりさんの曲に縛られているって意味じゃないんです。ひかりさんの曲を僕が演奏すると、部のみんなが明るくなるんです。みんなが楽しそうに笑うんです」
日枯 は嬉しそうに星の数を数える。
「みんなが喜んでくれる。だから、僕、大変じゃないんです。「星空マーチ」は「みんな」で作っているんです」
日枯 が「一等星を見つけた!」とはしゃいだ。
そっか。
君の出会った人たちは、きっと、優しい人たちだったんだね。
君は、これから、私が知らない曲をたくさん演奏していくんだね。
君は、私の知らない音が溢れる世界に踏み出そうとしているんだね。
それなら、私がすることはただ一つ。
ひかりは目を閉じて心を決めた。
その瞬間だった。
聞き慣れた軽快な足音が聞こえてきた。
ひかりが振り向くと、桜雫愛が、息を切らしながら、立っていた。
履き慣れないサンダルで必死に歩いて来たのだろう。
足が弱々しく震えていた。
橋の街灯と星の光で、橋と道に綺麗な影の線ができていた。
愛は、その線の前で立ち止まる。
日枯 は彼女に向かって、ゆっくりと笑う。
「ごめん。僕は今日、行けない」
「知っているよ」
「なら、どうしてここに?」
愛は橋の前で立ち尽くすだけ。
あと、一歩。
どうしても、愛は前に進めない。
日枯 はただ、静かに笑ってから謝る。
「ごめんね。みんなには、そう伝えてくれるかな」
日枯 が造花のように笑ったとき、彼の背中を誰かがふわりと優しく押し、日枯 が前に一歩を踏み出してしまう。
日枯 は驚いて振り返った。
暁ひかりが笑っていた。
彼女の目に、月と星が反射している。
ひかりの目を見ながら、日枯 は目で問いかける。
「あなたは、僕が生み出した幻だったはず」
ひかりもゆっくりと目を見て答える。
「前に進む日が来ただけだよ」
あと数歩だけ進めば、愛の小さな手に、日枯 の指が届くだろう。
それでも、日枯 は前には進まない。
ひかりはゆっくりと、彼に手を振った。
「大丈夫。『暁ひかり』という『人間』は、いつもここにいるから。私という『心』は必ずここにいるから」
その言葉を聞き、日枯 が瞳で問いかける。
「もし、ひかりさんが……ひかりさんの『心』がずっと待っていてくれるのなら、ひかりさんの曲を必ず……きっと、必ず完成させるので……そのときは……」
日枯 とひかりは一緒に笑い合った。
お互いに笑顔で、お互いの心を伝え合う。
そして、心で約束を交わした。
前に踏み出した日枯 の手を愛が掴もうとする。
しかし、愛は躊躇ったかのように、一度、手を自分の方に戻してしまう。
だから、日枯 の方から彼女の指を取って、笑顔を見せる。
星の光が反射した、黄色の目が静かにゆらめいた。「花火、まだ間に合うかな?」
日枯 が聞いた。
「うん。きっと、間に合う」
愛の言葉とともに、二人で一緒に歩き始める。
日枯 は、もう、橋の方を振り向かなかった。
二人が遠ざかるにつれ、花火の音が大きくなってゆく。
ひかりは一人で手すりに寄りかかり、目を閉じ、風の香りをたどる。
ようやく、ひとりぼっちになっちゃった。
ひかりは嬉しかった。
日枯 が無闇に走る時間を終わらせることができたから。
ひかりは微笑んだ。
日枯 の幸せを願って。
ひかりは微笑んだ。
自分の幸せを抱きしめながら。
0
あなたにおすすめの小説

母の下着 タンスと洗濯籠の秘密
MisakiNonagase
青春
この物語は、思春期という複雑で繊細な時期を生きる少年の内面と、彼を取り巻く家族の静かなる絆を描いた作品です。
颯真(そうま)という一人の高校生の、ある「秘密」を通して、私たちは成長の過程で誰もが抱くかもしれない戸惑い、罪悪感、そしてそれらを包み込む家族の無言の理解に触れます。
物語は、現在の颯真と恋人・彩花との関係から、中学時代にさかのぼる形で展開されます。そこで明らかになるのは、彼がかつて母親の下着に対して抱いた抑えがたい好奇心と、それに伴う一連の行為です。それは彼自身が「歪んだ」と感じる過去の断片であり、深い恥ずかしさと自己嫌悪を伴う記憶です。
しかし、この物語の核心は、単なる過去の告白にはありません。むしろ、その行為に「気づいていたはず」の母親が、なぜ一言も問い詰めず、誰にも告げず、ただ静かに見守り続けたのか——という問いにこそあります。そこには、親子という関係を超えた、深い人間理解と、言葉にされない優しさが横たわっています。
センシティブな題材を、露骨な描写や扇情的な表現に頼ることなく、あくまで颯真の内省的な視点から丁寧に紡ぎ出しています。読者は、主人公の痛みと恥ずかしさを共有しながら、同時に、彼を破綻から救った「沈黙の救済」の重みと温かさを感じ取ることでしょう。
これは、一つの過ちと、その赦しについての物語です。また、成長とは時に恥ずかしい過去を背負いながら、他者の無償の寛容さによって初めて前を向けるようになる過程であること、そして家族の愛が最も深く現れるのは、時に何も言わない瞬間であることを、静かにしかし確かに伝える物語です。
どうか、登場人物たちの静かなる心の襞に寄り添いながら、ページをめくってください。




春に狂(くる)う
転生新語
恋愛
先輩と後輩、というだけの関係。後輩の少女の体を、私はホテルで時間を掛けて味わう。
小説家になろう、カクヨムに投稿しています。
小説家になろう→https://ncode.syosetu.com/n5251id/
カクヨム→https://kakuyomu.jp/works/16817330654752443761


ワシの子を産んでくれんか
KOU/Vami
ライト文芸
妻に先立たれ、息子まで亡くした老人は、息子の妻である若い未亡人と二人きりで古い家に残された。
「まだ若い、アンタは出て行って生き直せ」――そう言い続けるのは、彼女の未来を守りたい善意であり、同時に、自分の寂しさが露見するのを恐れる防波堤でもあった。
しかし彼女は去らない。義父を一人にできないという情と、家に残る最後の温もりを手放せない心が、彼女の足を止めていた。
昼はいつも通り、義父と嫁として食卓を囲む。けれど夜になると、喪失の闇と孤独が、二人の境界を静かに溶かしていく。
ある夜を境に、彼女は“何事もない”顔で日々を回し始め、老人だけが遺影を直視できなくなる。
救いのような笑顔と、罪のような温もり。
二人はやがて、外の世界から少しずつ音を失い、互いだけを必要とする狭い家の中へ沈んでいく――。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる