11 / 39
×生贄
しおりを挟む
一歩。足を前に出す。
――村を守ることができるのなら、これほど喜ばしいことはない。
また一歩、歩みを進める。
――家族のため、村の仲間のため、これから生まれてくる命のために。
まるで『花嫁のための通路』を歩くように、一歩。
――これで村は救われる。要求された命は一つ。醜い感情など押し殺して、この身を捧げる喜びを。
まるで『死地に赴く戦士』のように、気高く前へ。
――それでも浅ましい心は叫んでる。まだ
「死にたくない」
音にした言葉のなんと浅ましいことだろう。
自分は産まれてからこれまで、このために生きてきたのに。
この地を守る主にこの身を捧げ、生涯お仕えすることが義務なのに。
父と母は誇らしげに笑顔で見送ってくれた。僕もそれに答えるために笑顔で村を出てきた。こんなに綺麗な『花嫁衣装』は他にないだろう。
「……しにたくない」
それでも言葉も涙も勝手に出てくる。ここには誰もいないんだ。少しくらい、いいじゃないか。自分のために泣いたって。
主の家に続くと言われる一本道。暗い夜道を一人で歩く。
どうせ辿り着けば化け物に頭からぱくりと食われるか、遊びみたいに嬲り殺しにされるんだ。声を上げながらわんわん泣いた。それでも歩みは止めない。
ふと道の先に目を向けると、ランタンのような灯りが近づいてくる。怖くなって立ち止まった。ここで死んでは意味がない。灯りはどんどん大きくなって、僕の心臓もばくばくと音を立てる。相手もこちらを認識したのか、明るい大人の男性の声が聞こえた。
「こんばんは」
「……こんばんは」
「こんなところでどうしたの?」
「これから、主様のところに行くの」
「主様?」
男性はこの辺りの人ではないらしい。小首を傾げながら問うてくる。僕は拙い言葉で主様の説明をした。
「ふぅん。君はそうしたいの?」
「本当は、嫌だ」
「うん」
「死にたくなんてない」
「わかるよ」
嗚咽混じりの酷い言葉でも、見ず知らずの男性は頷きながら聞いてくれる。もっとたくさん言葉を知っていればよかった。必要ないと捻くれて学ばなかったのは僕だ。なんて愚かだったんだろう。
「ところで、その主様というのは本当に必要なのかな?」
男性は空中に答えを探すようにどこかを見ている。僕は素直に「わからない」と答えた。男性は嬉しそうに笑って「それじゃあ見に行こう」と『歌を奏でる者』のように弾む声で僕の手を引いて、長い道を彼が来た方角へ歩きだした。
グラディウスと名乗った彼は色々なことを話してくれた。これまでに行った場所や見てきたもの、その全てが輝いているようで、僕は素直に羨ましくなった。彼はそんな僕を素直でいいと言ってくれた。僕も色んなことを話したかったけれど、言いたいことが見つからなかった。
やがて少し開けた場所に出る。
彼とはここでお別れだ。
主に挨拶をしなければと、俯いた顔を上げる。
そこには、何もなかった。
「……え?」
「あぁ、やっぱりここか」
「あの、これは? 主様は……」
「ここの"主様"と呼ばれていたあれは、本当は良くないものだったんだ」
「よくないもの……」
グラディウスは僕の頭を軽く撫でながら話を続ける。
「国から討伐命令が出たから、勇者である俺がアレを倒しちゃった」
「じゃあ、その……僕は、もう、必要ない?」
「ダガーがお嫁に行っちゃう前でよかった」
彼はいたずらっぽく笑うとギュッと僕を抱きしめた。にこにこと機嫌よく僕を抱き上げて、そのまま村への道を取って返した。
夜が明けるよりも早く村に戻った僕を、両親は驚きながらも歓迎してくれた。けれど村人たちの視線は冷たい。彼らには僕が出戻りのように見えているのだろうか。役目のない僕なんてカカシより役に立たない。
こっそり村を抜け出して、秘密の祠までやってきた。空気が澄んでいてとても落ち着く。心がざわざわしたときは、ここでもやもやを吐き出すんだ。
「ダガー」
「グラディウス……」
誰も知らない場所に現れた彼に目を見開く。特別な場所に彼がいる。ただそれだけで足元がもぞもぞする。
「さっき村長と話をしたんだ」
グラディウスは優しく笑いながら、僕の頬に触れた。宝物を扱うようなその触り方に、背中がぞくぞくする。でもきっと、彼がこうするのは僕だけじゃない。
「君の、これからについて」
「……え?」
「実は、本当に由々しき事態で、下劣で最低なことなんだけど」
「……」
「君は村には居られない」
「なん、で……」
「古い風習だ。ありえないほど悍ましい、憎むべき悪習なのだけど、出戻った『花嫁』は殺される」
「どうして?」
「主様と呼ぶアレが、もういないと説明したけどあいつらは受け入れようとしなくて、とにかくアレが怒るから、らしい。怒りを買う前に殺して、代わりを捧げるんだと。全く解せない」
「僕、やっぱり死ぬんだ」
「そんなことさせないよ」
グラディウスは昨晩そうしたようにまた僕を抱きしめた。僕はなんだか悲しくなって、子どものように彼に縋った。
「こんなところ、捨てちゃおう。いっそ俺のところにお嫁においで」
「なんで僕なんかに」
「なんかって言わないで? 俺の一目惚れってやつかなぁ。花嫁衣装の君は本当に素敵だった」
くすくすと笑って少し僕の体を離すと手を取り指先口づける。
「結婚しよ? それで、色んなものを見に行こう」
僕は真っ赤になってしまって、誤魔化すように彼に抱きついた。
その後、彼は僕を村には返さず、文字通り攫ってしまった。
――村を守ることができるのなら、これほど喜ばしいことはない。
また一歩、歩みを進める。
――家族のため、村の仲間のため、これから生まれてくる命のために。
まるで『花嫁のための通路』を歩くように、一歩。
――これで村は救われる。要求された命は一つ。醜い感情など押し殺して、この身を捧げる喜びを。
まるで『死地に赴く戦士』のように、気高く前へ。
――それでも浅ましい心は叫んでる。まだ
「死にたくない」
音にした言葉のなんと浅ましいことだろう。
自分は産まれてからこれまで、このために生きてきたのに。
この地を守る主にこの身を捧げ、生涯お仕えすることが義務なのに。
父と母は誇らしげに笑顔で見送ってくれた。僕もそれに答えるために笑顔で村を出てきた。こんなに綺麗な『花嫁衣装』は他にないだろう。
「……しにたくない」
それでも言葉も涙も勝手に出てくる。ここには誰もいないんだ。少しくらい、いいじゃないか。自分のために泣いたって。
主の家に続くと言われる一本道。暗い夜道を一人で歩く。
どうせ辿り着けば化け物に頭からぱくりと食われるか、遊びみたいに嬲り殺しにされるんだ。声を上げながらわんわん泣いた。それでも歩みは止めない。
ふと道の先に目を向けると、ランタンのような灯りが近づいてくる。怖くなって立ち止まった。ここで死んでは意味がない。灯りはどんどん大きくなって、僕の心臓もばくばくと音を立てる。相手もこちらを認識したのか、明るい大人の男性の声が聞こえた。
「こんばんは」
「……こんばんは」
「こんなところでどうしたの?」
「これから、主様のところに行くの」
「主様?」
男性はこの辺りの人ではないらしい。小首を傾げながら問うてくる。僕は拙い言葉で主様の説明をした。
「ふぅん。君はそうしたいの?」
「本当は、嫌だ」
「うん」
「死にたくなんてない」
「わかるよ」
嗚咽混じりの酷い言葉でも、見ず知らずの男性は頷きながら聞いてくれる。もっとたくさん言葉を知っていればよかった。必要ないと捻くれて学ばなかったのは僕だ。なんて愚かだったんだろう。
「ところで、その主様というのは本当に必要なのかな?」
男性は空中に答えを探すようにどこかを見ている。僕は素直に「わからない」と答えた。男性は嬉しそうに笑って「それじゃあ見に行こう」と『歌を奏でる者』のように弾む声で僕の手を引いて、長い道を彼が来た方角へ歩きだした。
グラディウスと名乗った彼は色々なことを話してくれた。これまでに行った場所や見てきたもの、その全てが輝いているようで、僕は素直に羨ましくなった。彼はそんな僕を素直でいいと言ってくれた。僕も色んなことを話したかったけれど、言いたいことが見つからなかった。
やがて少し開けた場所に出る。
彼とはここでお別れだ。
主に挨拶をしなければと、俯いた顔を上げる。
そこには、何もなかった。
「……え?」
「あぁ、やっぱりここか」
「あの、これは? 主様は……」
「ここの"主様"と呼ばれていたあれは、本当は良くないものだったんだ」
「よくないもの……」
グラディウスは僕の頭を軽く撫でながら話を続ける。
「国から討伐命令が出たから、勇者である俺がアレを倒しちゃった」
「じゃあ、その……僕は、もう、必要ない?」
「ダガーがお嫁に行っちゃう前でよかった」
彼はいたずらっぽく笑うとギュッと僕を抱きしめた。にこにこと機嫌よく僕を抱き上げて、そのまま村への道を取って返した。
夜が明けるよりも早く村に戻った僕を、両親は驚きながらも歓迎してくれた。けれど村人たちの視線は冷たい。彼らには僕が出戻りのように見えているのだろうか。役目のない僕なんてカカシより役に立たない。
こっそり村を抜け出して、秘密の祠までやってきた。空気が澄んでいてとても落ち着く。心がざわざわしたときは、ここでもやもやを吐き出すんだ。
「ダガー」
「グラディウス……」
誰も知らない場所に現れた彼に目を見開く。特別な場所に彼がいる。ただそれだけで足元がもぞもぞする。
「さっき村長と話をしたんだ」
グラディウスは優しく笑いながら、僕の頬に触れた。宝物を扱うようなその触り方に、背中がぞくぞくする。でもきっと、彼がこうするのは僕だけじゃない。
「君の、これからについて」
「……え?」
「実は、本当に由々しき事態で、下劣で最低なことなんだけど」
「……」
「君は村には居られない」
「なん、で……」
「古い風習だ。ありえないほど悍ましい、憎むべき悪習なのだけど、出戻った『花嫁』は殺される」
「どうして?」
「主様と呼ぶアレが、もういないと説明したけどあいつらは受け入れようとしなくて、とにかくアレが怒るから、らしい。怒りを買う前に殺して、代わりを捧げるんだと。全く解せない」
「僕、やっぱり死ぬんだ」
「そんなことさせないよ」
グラディウスは昨晩そうしたようにまた僕を抱きしめた。僕はなんだか悲しくなって、子どものように彼に縋った。
「こんなところ、捨てちゃおう。いっそ俺のところにお嫁においで」
「なんで僕なんかに」
「なんかって言わないで? 俺の一目惚れってやつかなぁ。花嫁衣装の君は本当に素敵だった」
くすくすと笑って少し僕の体を離すと手を取り指先口づける。
「結婚しよ? それで、色んなものを見に行こう」
僕は真っ赤になってしまって、誤魔化すように彼に抱きついた。
その後、彼は僕を村には返さず、文字通り攫ってしまった。
0
あなたにおすすめの小説

【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。

逃げた弟のかわりに溺愛アルファに差し出されました。抱かれたら身代わりがばれてしまうので初夜は断固拒否します!
雪代鞠絵/15分で萌えるBL小説
BL
隣国の国王キリアン(アルファ)に嫁がされたオメガの王子リュカ。
しかし実は、結婚から逃げ出した双子の弟セラの身代わりなのです…
本当の花嫁じゃないとばれたら大変!
だから何としても初夜は回避しなければと思うのですが、
だんだんキリアンに惹かれてしまい、苦しくなる…という
お話です。よろしくお願いします<(_ _)>
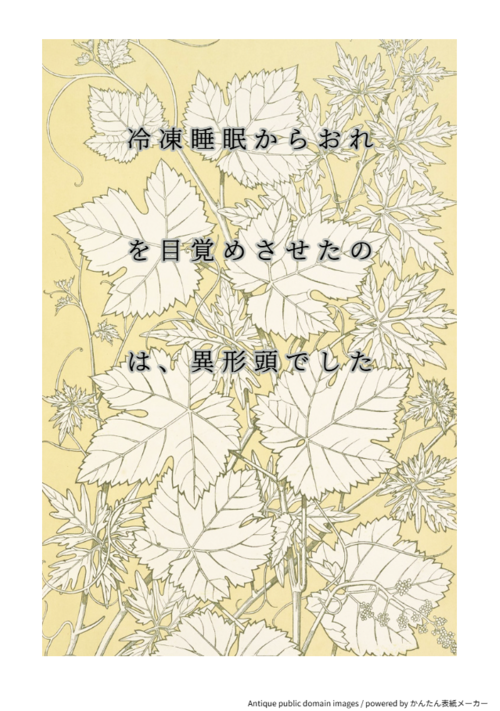
冷凍睡眠からおれを目覚めさせたのは、異形頭でした
秋山龍央
BL
2412年。冷凍睡眠から目覚めたら、地球上に残っている人間はおれひとりになっていた。
三百年の眠りのあいだに、未知のウイルスと戦争により人類は宇宙シェルターへと避難していたのだ。
そんな荒廃した世界で、おれを目覚めさせたのは―― 黒い頭部に青白い光を灯す、異形頭の男だった。
人工機械生命体である彼は、この星における変異体と環境変化の記録のため地球上に残され、二百年以上も一人きりで任務を続けているという。
そんな彼と、行動を共にすることになった人間の話。
※異形頭BLアンソロ本に寄稿した小説に加筆修正をくわえたものになります

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。



冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















