5 / 6
5
しおりを挟む
王都セイクリアに到着してから一週間。
メアリーは王妃に付き添われ、少しずつ新しい生活に慣れていった。
朝は礼儀作法の講義、昼は服飾の打ち合わせ、夜はリアンと共に食卓を囲む。
まるで夢のような日々――けれど、どこか現実味がなかった。
彼の視線はいつも優しくて、けれど深すぎて、逃げ場がない。
笑顔の裏にある感情が見えないからこそ、怖い。
愛されることが、こんなに息苦しいなんて知らなかった。
「メアリー」
リアンが声をかける。
夜の部屋には月光が差し込み、彼の白金の髪が光を受けて輝いていた。
「明日の夜会のことですが……準備は順調ですか?」
「ええ。王妃様からもご指導をいただいています。……でも」
「でも?」
「出席者の中に、アレクシス王太子もいると聞きました」
その名を口にした瞬間、空気がわずかに変わった。
リアンは笑った。けれどその微笑みは、氷のように冷たい。
「そうですよ。外交上、避けられませんからね。彼の視線の先に、あなたがいるのは当然でしょう」
「……リアン様」
「怖いですか?」
「少しだけ。でも……あなたがそばにいてくだされば」
そう言った瞬間、リアンがメアリーの手を取り、指先に軽く唇を触れさせた。
「どんな場所でも、あなたは僕の隣に立つ。それを忘れないで」
低く囁く声に、背筋がぞくりと震える。
まるでその言葉そのものが鎖のように感じた。
夜会の日は、驚くほど華やかだった。
大理石の広間に、百を超える貴族が集まっている。
煌びやかなシャンデリアの光が揺れ、音楽が優雅に流れる。
メアリーは深紅のドレスを身にまとい、リアンの腕に手を添えた。
周囲の視線が、彼女に集まる。
――好奇、嫉妬、軽蔑、そして憧れ。
さまざまな感情が混ざり合った視線を、彼女は静かに受け止めた。
「堂々としていて、素敵ですよ」
リアンの声が耳に届く。
その優しさに、メアリーはかすかに笑みを返した。
けれど、視線の端に見えたひとりの男に、心臓が跳ねた。
――アレクシス王太子。
以前より少し痩せたように見える。
けれど、その瞳には強い焦燥と悔恨が宿っていた。
彼の視線がまっすぐにメアリーを射抜いた。
「……メアリー」
人々のざわめきの中、彼の唇がそう動いた。
メアリーは目をそらそうとしたが、リアンの指が彼女の腰を軽く引き寄せる。
「見なくていい。あなたが見るべきのは、僕だけです」
「……っ」
「ねぇ、メアリー。笑って」
リアンが優しく言い、彼女の頬に手を添えた。
人々の前で――まるで恋人を慈しむように。
その行為は明らかな宣言だった。
『彼女は僕のものだ』という、誰もが理解する愛の示威。
アレクシスが苦しげに拳を握るのが見えた。
ざまぁ、と思う自分がいた。
けれど同時に、胸の奥で小さな痛みが芽生える。
(私は……こんな復讐を、望んでいたの?)
リアンが微笑み、耳元で囁く。
「ほら、見て。あの男、あなたを手放したことを今さら後悔してる。
でももう遅い。あなたは、僕と踊る」
リアンが手を取り、ダンスの輪へと導く。
音楽が流れ、二人は優雅に回る。
その動きは完璧で、まるで絵画のようだった。
「リアン様……人々が見ています」
「いいじゃないですか。僕は見せびらかしたいんです」
リアンが囁く。
「あなたを奪ったことを、世界中に」
その言葉が甘く響くほどに、心が締め付けられた。
彼の愛が深ければ深いほど、逃げ場がなくなる。
曲が終わり、拍手が広がる。
リアンはメアリーの手を握ったまま、アレクシスの前に歩み寄った。
「久しぶりですね、アレクシス殿下。外交の場で会うとは思いませんでした」
「……リアン王子。彼女を――メアリーを、どうするつもりだ」
「どうするつもり? 僕の婚約者として、迎えるだけですよ」
「彼女は――っ!」
アレクシスが声を荒げる。
その瞬間、周囲の空気が張り詰めた。
リアンの笑みが静かに消える。
「彼女は、あなたのものではない。
あなたが踏みにじった愛を、今さら拾い直せると思っているんですか?」
「違う……あの時は、そうするしかなかったんだ……っ! 父上に逆らえなかった!」
「言い訳ですね」
リアンの声は低く冷たい。
「どんな理由があっても、彼女を泣かせた事実は変わらない。あなたの“愛”は、彼女を守れなかった」
メアリーの胸がざわつく。
リアンの正義が、あまりに鋭くて――誰も反論できない。
「リアン様、もう……」
彼の袖をそっと引いた。
けれどリアンは、アレクシスを見据えたまま続ける。
「僕はあなたに感謝してるんですよ」
「……感謝?」
「あなたが彼女を手放してくれたおかげで、僕は人生で初めて“欲しい”と思うものに出会えた。
だから、せいぜい後悔し続けてください。自分が何を失ったのか、理解できるまで」
アレクシスの表情が崩れる。
まるで全ての希望を奪われたように。
その姿を見た瞬間、メアリーの胸が痛んだ。
リアンの言葉は間違っていない。けれど――あまりにも残酷だった。
夜会のあと。
メアリーは一人、バルコニーに出て冷たい風に当たっていた。
遠くで笑い声と音楽がまだ続いている。
けれど心の中は静まり返っていた。
(私は、何をしてるの……?)
アレクシスが苦しむ姿を見て、少しだけ胸がすっとした。
でもその直後、空っぽになった。
ざまぁを果たしても、心は軽くならない。
むしろ――リアンに縛られていく感覚が強くなる。
「メアリー」
背後から声がした。
振り向くと、リアンが立っていた。
金色の瞳が月光を映し、静かに輝いている。
「……逃げたくなりましたか?」
その問いに、息を呑む。
まるで心を読まれたようだった。
「私は……ただ、少し疲れただけです」
「そうですか。なら、もう少しだけこの腕の中で休んでください」
リアンがそっと抱き寄せる。
その抱擁は温かいのに、どこか息苦しい。
逃げられない、と本能が告げていた。
「あなたがいれば、僕は何もいらない。
でも――あなたが僕から離れようとするなら、きっと、僕は壊れる」
その言葉が、優しさに包まれた警告のように響いた。
メアリーの心が凍りつく。
(この人は……どこまで私を愛しているの? それとも、支配しているの?)
リアンの指が彼女の頬をなぞり、唇に触れる寸前で止まる。
「あなたは僕のものだ。それを、もう一度、言ってください」
メアリーは震えながら目を閉じた。
彼の瞳の奥にある“愛”が、少しずつ狂気に変わっていくのを感じながら。
遠くで、アレクシスの馬車が夜の闇に消えていった。
――彼もまた、あきらめてはいなかった。
この恋はまだ終わらない。
誰の愛が真実で、誰の愛が呪いなのか――
メアリーは王妃に付き添われ、少しずつ新しい生活に慣れていった。
朝は礼儀作法の講義、昼は服飾の打ち合わせ、夜はリアンと共に食卓を囲む。
まるで夢のような日々――けれど、どこか現実味がなかった。
彼の視線はいつも優しくて、けれど深すぎて、逃げ場がない。
笑顔の裏にある感情が見えないからこそ、怖い。
愛されることが、こんなに息苦しいなんて知らなかった。
「メアリー」
リアンが声をかける。
夜の部屋には月光が差し込み、彼の白金の髪が光を受けて輝いていた。
「明日の夜会のことですが……準備は順調ですか?」
「ええ。王妃様からもご指導をいただいています。……でも」
「でも?」
「出席者の中に、アレクシス王太子もいると聞きました」
その名を口にした瞬間、空気がわずかに変わった。
リアンは笑った。けれどその微笑みは、氷のように冷たい。
「そうですよ。外交上、避けられませんからね。彼の視線の先に、あなたがいるのは当然でしょう」
「……リアン様」
「怖いですか?」
「少しだけ。でも……あなたがそばにいてくだされば」
そう言った瞬間、リアンがメアリーの手を取り、指先に軽く唇を触れさせた。
「どんな場所でも、あなたは僕の隣に立つ。それを忘れないで」
低く囁く声に、背筋がぞくりと震える。
まるでその言葉そのものが鎖のように感じた。
夜会の日は、驚くほど華やかだった。
大理石の広間に、百を超える貴族が集まっている。
煌びやかなシャンデリアの光が揺れ、音楽が優雅に流れる。
メアリーは深紅のドレスを身にまとい、リアンの腕に手を添えた。
周囲の視線が、彼女に集まる。
――好奇、嫉妬、軽蔑、そして憧れ。
さまざまな感情が混ざり合った視線を、彼女は静かに受け止めた。
「堂々としていて、素敵ですよ」
リアンの声が耳に届く。
その優しさに、メアリーはかすかに笑みを返した。
けれど、視線の端に見えたひとりの男に、心臓が跳ねた。
――アレクシス王太子。
以前より少し痩せたように見える。
けれど、その瞳には強い焦燥と悔恨が宿っていた。
彼の視線がまっすぐにメアリーを射抜いた。
「……メアリー」
人々のざわめきの中、彼の唇がそう動いた。
メアリーは目をそらそうとしたが、リアンの指が彼女の腰を軽く引き寄せる。
「見なくていい。あなたが見るべきのは、僕だけです」
「……っ」
「ねぇ、メアリー。笑って」
リアンが優しく言い、彼女の頬に手を添えた。
人々の前で――まるで恋人を慈しむように。
その行為は明らかな宣言だった。
『彼女は僕のものだ』という、誰もが理解する愛の示威。
アレクシスが苦しげに拳を握るのが見えた。
ざまぁ、と思う自分がいた。
けれど同時に、胸の奥で小さな痛みが芽生える。
(私は……こんな復讐を、望んでいたの?)
リアンが微笑み、耳元で囁く。
「ほら、見て。あの男、あなたを手放したことを今さら後悔してる。
でももう遅い。あなたは、僕と踊る」
リアンが手を取り、ダンスの輪へと導く。
音楽が流れ、二人は優雅に回る。
その動きは完璧で、まるで絵画のようだった。
「リアン様……人々が見ています」
「いいじゃないですか。僕は見せびらかしたいんです」
リアンが囁く。
「あなたを奪ったことを、世界中に」
その言葉が甘く響くほどに、心が締め付けられた。
彼の愛が深ければ深いほど、逃げ場がなくなる。
曲が終わり、拍手が広がる。
リアンはメアリーの手を握ったまま、アレクシスの前に歩み寄った。
「久しぶりですね、アレクシス殿下。外交の場で会うとは思いませんでした」
「……リアン王子。彼女を――メアリーを、どうするつもりだ」
「どうするつもり? 僕の婚約者として、迎えるだけですよ」
「彼女は――っ!」
アレクシスが声を荒げる。
その瞬間、周囲の空気が張り詰めた。
リアンの笑みが静かに消える。
「彼女は、あなたのものではない。
あなたが踏みにじった愛を、今さら拾い直せると思っているんですか?」
「違う……あの時は、そうするしかなかったんだ……っ! 父上に逆らえなかった!」
「言い訳ですね」
リアンの声は低く冷たい。
「どんな理由があっても、彼女を泣かせた事実は変わらない。あなたの“愛”は、彼女を守れなかった」
メアリーの胸がざわつく。
リアンの正義が、あまりに鋭くて――誰も反論できない。
「リアン様、もう……」
彼の袖をそっと引いた。
けれどリアンは、アレクシスを見据えたまま続ける。
「僕はあなたに感謝してるんですよ」
「……感謝?」
「あなたが彼女を手放してくれたおかげで、僕は人生で初めて“欲しい”と思うものに出会えた。
だから、せいぜい後悔し続けてください。自分が何を失ったのか、理解できるまで」
アレクシスの表情が崩れる。
まるで全ての希望を奪われたように。
その姿を見た瞬間、メアリーの胸が痛んだ。
リアンの言葉は間違っていない。けれど――あまりにも残酷だった。
夜会のあと。
メアリーは一人、バルコニーに出て冷たい風に当たっていた。
遠くで笑い声と音楽がまだ続いている。
けれど心の中は静まり返っていた。
(私は、何をしてるの……?)
アレクシスが苦しむ姿を見て、少しだけ胸がすっとした。
でもその直後、空っぽになった。
ざまぁを果たしても、心は軽くならない。
むしろ――リアンに縛られていく感覚が強くなる。
「メアリー」
背後から声がした。
振り向くと、リアンが立っていた。
金色の瞳が月光を映し、静かに輝いている。
「……逃げたくなりましたか?」
その問いに、息を呑む。
まるで心を読まれたようだった。
「私は……ただ、少し疲れただけです」
「そうですか。なら、もう少しだけこの腕の中で休んでください」
リアンがそっと抱き寄せる。
その抱擁は温かいのに、どこか息苦しい。
逃げられない、と本能が告げていた。
「あなたがいれば、僕は何もいらない。
でも――あなたが僕から離れようとするなら、きっと、僕は壊れる」
その言葉が、優しさに包まれた警告のように響いた。
メアリーの心が凍りつく。
(この人は……どこまで私を愛しているの? それとも、支配しているの?)
リアンの指が彼女の頬をなぞり、唇に触れる寸前で止まる。
「あなたは僕のものだ。それを、もう一度、言ってください」
メアリーは震えながら目を閉じた。
彼の瞳の奥にある“愛”が、少しずつ狂気に変わっていくのを感じながら。
遠くで、アレクシスの馬車が夜の闇に消えていった。
――彼もまた、あきらめてはいなかった。
この恋はまだ終わらない。
誰の愛が真実で、誰の愛が呪いなのか――
25
あなたにおすすめの小説

「誰もお前なんか愛さない」と笑われたけど、隣国の王が即プロポーズしてきました
ゆっこ
恋愛
「アンナ・リヴィエール、貴様との婚約は、今日をもって破棄する!」
王城の大広間に響いた声を、私は冷静に見つめていた。
誰よりも愛していた婚約者、レオンハルト王太子が、冷たい笑みを浮かべて私を断罪する。
「お前は地味で、つまらなくて、礼儀ばかりの女だ。華もない。……誰もお前なんか愛さないさ」
笑い声が響く。
取り巻きの令嬢たちが、まるで待っていたかのように口元を隠して嘲笑した。
胸が痛んだ。
けれど涙は出なかった。もう、心が乾いていたからだ。

婚約破棄された傷心令嬢です。
あんど もあ
ファンタジー
王立学園に在学するコレットは、友人のマデリーヌが退学になった事を知る。マデリーヌは、コレットと親しくしつつコレットの婚約者のフランツを狙っていたのだが……。そして今、フランツの横にはカタリナが。
したたかでたくましいコレットの話。

〖完結〗容姿しか取り柄のない殿下を、愛することはありません。
藍川みいな
恋愛
幼い頃から、完璧な王妃になるよう教育を受けて来たエリアーナ。エリアーナは、無能な王太子の代わりに公務を行う為に選ばれた。
婚約者である王太子ラクセルは初対面で、 「ずいぶん、平凡な顔だな。美しい女なら沢山居るだろうに、なぜおまえが婚約者なのだ……」と言った。
それ以来、結婚式まで二人は会うことがなかった。
結婚式の日も、不機嫌な顔でエリアーナを侮辱するラクセル。それどころか、初夜だというのに 「おまえを抱くなど、ありえない! おまえは、次期国王の私の子が欲しいのだろう? 残念だったな。まあ、私に跪いて抱いてくださいと頼めば、考えてやらんこともないが?」と言い放つ始末。
更にラクセルは側妃を迎え、エリアーナを自室に軟禁すると言い出した。
設定ゆるゆるの、架空の世界のお話です。
架空の世界ですので、王太子妃が摂政である王太子の仕事を行っていることもサラッと流してください。

平民出身の地味令嬢ですが、論文が王子の目に留まりました
有賀冬馬
恋愛
貴族に拾われ、必死に努力して婚約者の隣に立とうとしたのに――「やっぱり貴族の娘がいい」と言われて、あっさり捨てられました。
でもその直後、学者として発表した論文が王子の目に止まり、まさかの求婚!?
「君の知性と誠実さに惹かれた。どうか、私の隣に来てほしい」
今では愛され、甘やかされ、未来の王妃。
……そして元婚約者は、落ちぶれて、泣きながらわたしに縋ってくる。
「あなたには、わたしの価値が見えなかっただけです」

【完結】従姉妹と婚約者と叔父さんがグルになり私を当主の座から追放し婚約破棄されましたが密かに嬉しいのは内緒です!
ジャン・幸田
恋愛
私マリーは伯爵当主の臨時代理をしていたけど、欲に駆られた叔父さんが、娘を使い婚約者を奪い婚約破棄と伯爵家からの追放を決行した!
でも私はそれでよかったのよ! なぜなら・・・家を守るよりも彼との愛を選んだから。
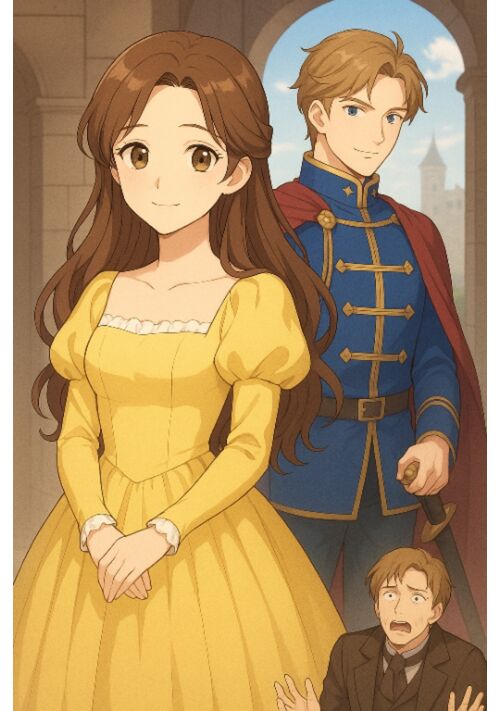
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……


裏切られ追放されたけど…精霊様がついてきました。
京月
恋愛
精霊の力を宿したペンダント。
アンネは婚約者のジーク、商人のカマダル、友人のパナに裏切られ、ペンダントを奪われ、追放されてしまった。
1人で泣いているアンネ。
「どうして泣いているの?」
あれ?何でここに精霊様がいるの?
※5話完結です。(もう書き終わってます)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















