171 / 336
第二部 四季姫進化の巻
第十三章 秋姫進化 12
しおりを挟む
十二
妖気を辿って走っていくと、湖の畔に赤尾がいた。
さっき、榎を撮影したカメラを、難しい顔をして弄っていた。
部下の狐たちが足止めしてくれていると信じているのか、周囲を警戒している素振りはない。
楸は気配を殺して木の影に隠れ、静かに弓の弦を引いた。
矢を放った瞬間、殺気が漏れたのか、気付かれた。
赤尾は素早く、飛び退いて矢を躱した。矢は外れ、赤尾が座っていた地面に突き刺さった。
楸は舌を打つ。もう、奇襲は通用しない。ゆっくりと、赤尾の前に姿を現した。
「しつこいねぇ。おちおち、調べ物もできやしない」
鬱陶しそうに、赤尾は楸を睨みつける。
「当然どす。私から逃げ切れると思うたら、大間違いどす」
楸が殺気を放ち返すと、赤尾も楸の本気を察した。
今までの、逃げ腰の飄々とした態度を切り替え、楸に真正面から、殺気を飛ばしてきた。
「そんなに死にたきゃ、相手になってやるよ」
赤尾はカメラを頭上に放り投げた。直後、どこからか木葉がたくさん飛んできて、カメラを包みこんだ。葉っぱの塊は、危険から逃れるみたいに、カメラを連れてどこか遠くへと飛んで行った。
赤尾の周囲に、青白い炎が大量に揺らめいた。炎はじんわりと形を歪め、姿を変えていく。
やがて、炎一つ一つが赤尾の姿に変身した。分身、とでも呼ぶのだろうか。どれが本体か、全く区別がつかなかった。
大勢の赤尾たちが、嫌味な表情を浮かべてきた。楸の全身に、悪寒が走る。
相変わらず、対象の弱点を巧みに突いた、嫌な戦い方をしてくる。楸の武器が弓矢しかなく、接近戦や大勢を相手にした戦闘が苦手だと確信した上での戦略だった。
もし、この絶体絶命の状況で、赤尾に勝つ方法があるとすれば、大量の偽物たちの中から本物の赤尾を見つけ出し、一撃の元に仕留めるしかないだろう。
理論上は、不可能ではなかった。だが、標的を見定めるために集中する時間が必要だし、その間、赤尾がじっと待ってくれているはずもない。
楸は、単独で妖怪と戦うには、本当に適していない四季姫だ。一番、欲しいと思っていた、榎や柊の持つ強靭な力を備えていない。己の無力さに、情けなさまで感じた。
別の作戦を考えている暇も、与えてはくれなかった。
統率した動きで、赤尾たちは一斉に飛び掛かってきた。
逃げる暇もない。楸は微動だにできないまま、迫ってくる狐の群れを凝視していた。
狐たちの波に飲まれかけた刹那。突然、体を強く押し飛ばされた。
側の、つつじの繁みに突っ込む形で、倒れ込む。
何が起こったか分からなかったが、赤尾の攻撃からは逃れられた。
素早く体を起こし、隣を見ると、一緒に垣根に突っ込んで倒れている宵の姿があった。木の枝に切り裂かれた頬や腕から、血が滲んでいる。楸の頭から、血の気が引いていく感覚がした。
「宵はん、ついてきたら、あかんどす!」
お礼よりも先に、命にかかわる危険な行為を叱る言葉が出てきた。
「俺には、赤尾を呼び出した責任がある。今更、お前を一人で行かせられるかよ!」
「せやかて、まだ、力は戻っておらんでしょう。生身の人間の体で、何ができるんどすか!」
宵の性格はよく分かっているから、頑固な行動は理解できる。
だが、無茶が過ぎる。
楸一人でもどうにもならない事態なのに、宵を助けながら戦うなんて、絶対に無理だ。
「体一つあれば、何なりとできる。囮でも盾でも、好きに使え」
楸の訴えを押し退け、宵は楸を庇って立ち上がり、大量の狐たちに向きあった。
力が及ばない分、宵は全てを懸けて、赤尾に立ちはだかるつもりだ。己の、命さえも賭して。
そんな強行策が、許されるはずがない。少なくとも、楸は絶対に、許さない。
楸は宵の腕にしがみつき、全力で引き止めた。
「私はもう、大切な人が危険な目に遭うなんて、嫌なんどす! 誰にも、傷付いて欲しくない……」
行かせまいと、力を込めれば込めるだけ、手が震えた。
「俺だって、同じだ。楸を一人で危険な目に遭わせるくらいなら、死んだほうがましだ」
必死で腕を掴む楸の頭を、宵は空いた手で、優しく撫でてきた。
顔をあげると、微笑む宵の顔が、涙で滲む視界に入り込んできた。
どうして、宵はいつも、穏やかな顔をしていられるのだろう。死ぬかもしれない厳しい状況に直面して、恐怖を感じないのだろうか。
楸のためなら、なんて犠牲精神は感心できない。楸みたいなどうしようもない人間のために、失われていい命なんて、ない。
楸は強い気持ちを込めて、宵の腕を掴み続けた。
「人間なんかとイチャイチャして、気持ちが悪いねぇ。流石は、半端者の不吉鳥」
庇い合う楸と宵の姿を見て、分身の群れに隠れた赤尾が、嫌らしく笑った。続けて、分身たちの笑いの波が押し寄せる。
宵が目を細めて、赤尾を睨みつけた。
半端者の不吉鳥。妖怪と人間、さらに悪鬼の血まで引き継ぐ宵や朝を、象徴する呼び名だろうか。
宵の反応から察するに、決して良い意味を持つ名前ではなさそうだ。
「千年前は、そう呼ばれて、人からも妖怪からも嫌われていらっしゃいましたねぇ」
やっぱり宵たちを嘲り、差別するための名前らしい。妖怪としての宵たちの地位はそれなりに高く、みんなから敬われる存在なのかと思っていたが、違うらしい。
妖怪とも人間とも違う存在だから、双方から忌み嫌われてきたのだろう。だから、分け隔てなく接してくれた千年前の四季姫たちを慕い、必要としてくれた下等妖怪たちを助け続けてきた。
さらに今は、楸を――。
宵の、大切な者を守ろうとする、共に近しい存在であろうとする執念の断片を、垣間見た気がした。
「嫌われ者だから、親切にされると、すぐに騙されちまうんだ。あんたみたいな気味の悪い生き物に、誰が本気で構うっていうのかね。馬鹿馬鹿しい」
赤尾の言葉に、宵が微かに反応していた。
「ただの挑発どす、まともに聞かんでもよろしい」
宵の手を強く握り締め、楸は宵の隣に立った。動揺した視線を向けてきた宵に、楸は微笑みかけた。
「あなたが何者かなんて、今更、愚問でしょう? 考える必要もありまへん。宵はんの価値は、そんな括りで決め付けられるもんではないどす」
完全な妖怪ではないから、人間ではないからと、虐げられる道理なんてない。妖怪や人間に合わせようと、焦らなくてもいい。
宵は宵なのだから、ありのままでいればいい。
強い視線を向けると、宵の泳いでいた瞳も、次第に焦点が定まってきた。
握り返してくる宵の手に、力強さを感じる。もう、迷いはなかった。
「あんたも、変な人間だね。執拗に妖怪を恨んで、倒そうと追いかけ回していると思いきや、訳の分からない妖怪の肩を持つなんてさ」
赤尾の不愉快そうな声が、狐の群れの中から聞こえてくる。
くだらない問い掛けだ。楸は鼻で笑った。
「簡単な理屈どす。私が倒したい相手はあなたであって、妖怪ではない。私が側におりたい相手も、宵月夜はんであって、妖怪ではないんどす」
赤尾は、よく分かっていない様子だった。妖怪は妖怪、人間は人間と分けてしか考えられない狐には、理解できなくて当然だ。
「別に、どうでもいいけどね。餓鬼のお飯事に付き合うつもりはないよ。そんなに一緒にいたいなら、二人揃って、さっさと死にな!」
目の前に群がる狐たちが、一斉に身構えた。黒い前足を前方に突き出し、念を込め始める。細長い肉球から、炎の塊が放たれた。
一つならば、掻き消すくらいはできたかもしれない。だが、迫りくる炎の数は、赤尾の分身の数と同じだけ。
数えられないほどの炎の乱舞が、襲い掛かってきた。
啖呵を切ったところで、敵に打ち勝つ方法を見つけたわけではない。
命の危険を悟った瞬間、楸の体は、宵を庇おうと腕を広げていた。
炎が、楸めがけて飛んでくる。
その直後。激しい風が辺りを包み込み、炎を吹き飛ばした。
赤尾の分身たちは、強風に煽られながら、飛ばされまいと必死で踏ん張っていた。
楸は、風に巻かれながら、人の腕に抱きかかえられる感触を覚えた。急に地面から足が離れ、一気に上空に浮かび上がる。
驚いて顔を上げた。すぐ傍に、宵の笑顔があった。楸は、宵に抱きしめられていた。
宵の姿は、人間からは少し、かけ離れたものになっていた。獣にも似た、鋭い眼光。髪は長く伸び、楸を包み込む手には、長い爪が伸びている。
極めつけは、服を突き破って背中から飛び出した、大きな漆黒の翼。
初めて出会った時と同じ、宵月夜の姿に戻っていた。
同時に、楸は宵と一緒に空を飛んでいるのだと気付いた。
かなり高くまで上昇している。下を見ると、地上が遠くて眩暈がした。楸は慌てて、宵に強くしがみついた。
「力が、戻ったんどすな」
少し落ち着いてきた楸は、宵の耳元で囁いた。
四季姫が施した封印が、完全に解けた。宵が少し遠い存在になった気がして、残念さが脳裏を過った。
でも同時に、生命力溢れる宵の本来の姿を見ていると、どこか安心した気持ちにも包まれた。
「間一髪だったな。――ようやく、楸の力になれる」
宵は久しぶりに空を飛ぶ感覚を思い出そうと、嬉しそうに激しく、翼を羽ばたかせた。
「やっぱり、空はいいな! 心が軽くなる」
宵は楽しそうに笑っているが、楸には真似できそうにない。空中を自在に飛び回る感覚は、どんな遊園地の絶叫アトラクションよりも激しく、怖かった。
世界が回る。地上を見下ろすと、四季ヶ丘の町並みや京都の山々、遥か遠くに日本海まで見渡せた。目まぐるしく角度を変えながら、視界に入り込んでくる。
この景色が、いつも宵が見ていたものなのか。日本が、とってもちっぽけな島国に感じる。以前、名古屋までひとっ飛びだと言っていた意味が、ようやく分かった。
楸は恐怖に負けて、悲鳴を上げながら宵にしがみつくだけで精一杯だった。
馴らしを終えた宵は、ゆっくりと下降して、楸を地上に降ろしてくれた。腰が抜けそうになっていたが、楸は何とか力を入れて、しっかりと足を踏ん張った。
「俺が赤尾の動きを止める。楸は落ち着いて、急所を狙え」
力強い表情で、宵が指示を送ってくる。自身に満ち溢れた、頼もしい姿だった。
宵は楸と赤尾たちの間に立ち塞がり、両手を前に突き出した。
「久しぶりだからな。手加減とかできねえぞ。歯ぁ食いしばれよ」
宵が両手で印を結ぶと同時に、激しい竜巻が起こり、赤尾の分身たちを取り囲む。
身動きが取れなくなった赤尾は、渦の中心に纏まって、警戒心を露わにしていた。
竜巻は徐々に黒い渦に変わり始め、電流を帯び始めた。稲光を明滅させながら、徐々に赤尾を追い詰めていく。
激しい音と共に、雷が渦の中心に落ちた。狐たちの悲鳴が響き渡る。
竜巻が治まると、雷に打たれて倒れた、大量の狐たちが視界に入ってきた。
楸は標的に向かって弓の弦を引き、術を発動する。赤い二重丸の形をした的が浮かび上がり、狐たちを順番に探っていく。
「――〝千里の的〟。……急所、見えたどす!」
急所とは、分身の中に隠れた赤尾の本体そのものだ。実体は、一番奥の端のほうで、縮こまって身を隠していた。
楸は狙いを定めて、素早く矢を放つ。赤尾は、すぐ傍にいた分身を盾にして、攻撃を防いだ。心臓を射抜かれた分身は、断末魔の悲鳴を上げて粉塵と化した。
すかさず、二投目を放った。だが、赤尾は矢を避けて逃げた。他の分身たちも散り散りに分散し、周囲一帯に広がった。
宵が風を操って捕えようとしてくれるが、数が多すぎて捕まえきれない。
「弓なんて、いやらしい武器だねぇ。けど、あっしも、ただではやられんよ」
赤尾たちは後ろ足に力を込め、楸たちの周りを物凄い速さで飛び回り始めた。辺りの木を蹴り飛ばしては方向転換し、延々と高速移動を続けながら、楸たちを翻弄してくる。
「相変わらず、逃げ足だけは逸品だな」
宵は悪態を吐くが、赤尾のスピードには追いついていけない。風の塊を放つが当たらず、苛立って、舌打ちをしていた。
赤尾は、単純に逃げ回るだけではなかった。高速で飛び回りながら、隙あらば炎の欠片を飛ばして攻撃してくる。小さな火の玉が顔や腕を掠めるたびに、肌に焼け付く痛みが走った。
「狙いが、定まらんどす……!」
本体の場所は分かっているが、弓を構えている暇がない。このままでは一方的に弄られるだけだ。楸は現状に苛立っていた。
何とか、赤尾を仕留める方法はないか。まだ、楸が把握していない秋姫の力があるかもしれない。
楸は目を閉じて、精神を集中させた。
手元に、熱が集まっていく感覚がした。指先が、妙に熱い。
新しい力が湧いてくる。楸はその瞬間を、しっかりと自覚した。
ゆっくりと目を開くと、握りしめていた弓の形状が、大きく変化していた。
竹のしなりが特徴の、漆塗りの梓弓が、強固な木製の弧を描く弓になった。中仕掛けの部分に、番えるべき矢の代わりに、同様の木の棒があてがわれ、固定されていた。木の棒には深い溝があり、細い矢が何本も束ねて収蔵されていた。
「クロスボウ、どすか……?」
本でしか見た覚えがないが、西洋で発明されて進化してきた、自動式の弓矢によく似た形状だった。威力や飛距離は通常の弓矢より劣るものの、精度が高く、素人でも容易に扱える代物だ。
弓の装填と、的を絞り込むための時間が、大幅に短縮される。現状を打開するには、もってこいの武器といえた。
楸は本能のままに、進化を遂げた弓を構える。力を込めると、大量の赤い的が出現し、飛び回る赤尾の分身たちを残らず捉えた。
木の棒で設えられた台座の底部にある、引き金を引く。
直後、ものすごい勢いで、針みたいな矢が連射され、次々と飛んで行った。矢は的確に分身に突き刺さり、あっという間に消滅させていった。
「オート連射どすか……。便利になりましたなぁ」
唖然と、自動射撃の威力を実感していた。楸自身は、しっかりとした和弓を使って、じっくりと標的を射るほうが好みだが、多勢に無勢の時には、こんな武器のほうが有り難い。
赤尾の分身たちが消滅すると共に、楸の弓も元の形に戻った。自在に形状を変えられるらしい。
嵐が過ぎ去ったかと思えるほど、周囲は静寂に包まれていた。最後に、背中に矢を突き刺された赤尾の本体が、目の前で倒れこんで体を震わせていた。
「狡いぞ、いきなり強くなりやがってぇ!」
涙目になりながら、赤尾が怒鳴りつけてくる。
確かに、反則技かもしれない。だが、狡いなんて、この狐だけには、いわれたくない。
「狡賢い狐を倒すための力なら、妥当なところでしょう」
一匹になってしまえば、矢で射倒すなんて容易な作業だ。楸はゆっくりと弦を引き、狙いを定めた。
やっと、仇が討てる。心臓が、激しく高鳴った。
何とか興奮を抑えて精神統一し、腕に力を込める。
突然、体の奥から、熱い気の流れが込み上げてくる。鼓動が焼け付きそうなほど、激しく熱を帯びた。
あまりの熱さに息苦しさを覚え、楸は胸に手を当てて蹲った。
「楸、しっかりしろ!」
宵が慌てて駆け寄ってくる。手を差し伸べてくれるが、楸の肩に触れた瞬間、指先に炎が迸った。
「宵はん、近づいたら駄目どす。力が、制御できへん……」
反射的に手を引っ込めた宵から、楸は四つん這いになって距離を置いた。
激しく高鳴る鼓動が、苦しい。体中を、炎で焼かれている感覚に陥った。
もう一息なのに、体がいうことを聞かない。最後の一矢が、放てない。
楸が自由に動けないと気付いた赤尾は、背中の矢を引き抜いて、へっぴり腰で逃げようとした。
また、奴を逃してしまう。せっかく、最後まで追い詰めたのに。
運命なのだろうか。楸は一生、家族の無念を晴らせないのだろうか。
絶望に襲われそうになっていると、急に、楸の体が引っ張り上げられた。
宵が、楸を引き起こして、まっすぐ立てるように支えてくれた。
楸が放つ熱い力が宵に移り、腕や顔の皮膚が爛れ、煙が上がっている。
傍にいては駄目だ。宵まで、炎に焼かれる。
楸は宵を振り解こうとした。だが、宵の力は強く、楸の体を支えて、放さない。
「俺に構うな、早く討て!」
宵の張り上げた声が、楸の中で躊躇を生み出していた大きな枷を、弾き飛ばした。
気付けば、腕が勝手に動き、素早く弓を構えていた。
頭の中から、鮮明な言葉が浮かび上がってくる。
「焦熱にて灰となれ。――〝朱雀の炎翔〟!」
全力を振り絞って、矢を放つ。矢は炎を纏って、逃げる狐の足元めがけて飛んだ。
だが、赤尾に当たることなく、地面を抉った。
外した。狙いが定まらなかった。楸は脱力した。
その直後。矢が突き刺さった地面が激しく爆発した。地中から炎の柱が伸び、はるか上空まで突き上がった。その炎の中から、巨大な炎の鳥が飛び出し、空を舞っていた。
優雅に羽ばたく炎の鳥は、ゆったりとした動きで、地上めがけて滑空した。――赤尾に狙いを定めて。
必死で逃げようとする赤尾に、鳥は勢いよく体当たりした。赤尾は炎に飲まれ、おぞましい悲鳴を上げた。
炎の鳥は地面に潜り、姿を消した。立ち上っていた炎も消え、楸の体の熱も治まった。
眼前では、真っ黒焦げになった赤尾が、煙を立ち上らせながら倒れていた。
まだ息があるらしく、ピクピクと前足を動かしている。
「こんな、化け物に、育っちまうとは……」
震える首を回し、楸を睨み付けてくる。弱々しい声で、恨み辛みを吐き出した。
「あんたの魂、さっさと食っとけば、よかった、ね」
最期の言葉を残し、赤尾は力尽きた。黒焦げの体は炭と化し、風に吹かれて粉々に吹き飛んでいった。
倒した。ついに、念願の敵を討てた。
体から、一気に力が抜けていく。足腰に、力が全く入らない。楸は膝を折って、倒れこんだ。
地面に倒れこむ直前に、体を抱きとめられた。閉じそうな瞼を懸命に開くと、不安そうな宵の表情が霞んで見えた。
「倒せたんどすな。私の手で……」
消え入りそうな声で、楸は訊ねていた。宵は泣きそうな顔で、必死に笑おうとしていた。
「そうだ、楸が、倒したんだ。凄い技だった」
震える声で伝え、楸の頭を、優しく撫でてくれた。
「力を使い果たしたんだな。待ってろ、四季姫たちを、呼んでくる」
「待って。もう少し、今のままで……」
楸から手を放し、榎たちのところに行こうとした宵を、力なく引き留めた。宵も無理に振り解こうとはせず、楸の傍にいてくれた。
心身共に限界だったが、心は晴れやかで、清々しかった。
この強い余韻を、まだ掻き消したくない。叶うなら、何よりも大切な人の元で、感じていたい。
宵の腕に顔を埋めながら、楸の意識は、深い、温かい場所へと落ちていった。
妖気を辿って走っていくと、湖の畔に赤尾がいた。
さっき、榎を撮影したカメラを、難しい顔をして弄っていた。
部下の狐たちが足止めしてくれていると信じているのか、周囲を警戒している素振りはない。
楸は気配を殺して木の影に隠れ、静かに弓の弦を引いた。
矢を放った瞬間、殺気が漏れたのか、気付かれた。
赤尾は素早く、飛び退いて矢を躱した。矢は外れ、赤尾が座っていた地面に突き刺さった。
楸は舌を打つ。もう、奇襲は通用しない。ゆっくりと、赤尾の前に姿を現した。
「しつこいねぇ。おちおち、調べ物もできやしない」
鬱陶しそうに、赤尾は楸を睨みつける。
「当然どす。私から逃げ切れると思うたら、大間違いどす」
楸が殺気を放ち返すと、赤尾も楸の本気を察した。
今までの、逃げ腰の飄々とした態度を切り替え、楸に真正面から、殺気を飛ばしてきた。
「そんなに死にたきゃ、相手になってやるよ」
赤尾はカメラを頭上に放り投げた。直後、どこからか木葉がたくさん飛んできて、カメラを包みこんだ。葉っぱの塊は、危険から逃れるみたいに、カメラを連れてどこか遠くへと飛んで行った。
赤尾の周囲に、青白い炎が大量に揺らめいた。炎はじんわりと形を歪め、姿を変えていく。
やがて、炎一つ一つが赤尾の姿に変身した。分身、とでも呼ぶのだろうか。どれが本体か、全く区別がつかなかった。
大勢の赤尾たちが、嫌味な表情を浮かべてきた。楸の全身に、悪寒が走る。
相変わらず、対象の弱点を巧みに突いた、嫌な戦い方をしてくる。楸の武器が弓矢しかなく、接近戦や大勢を相手にした戦闘が苦手だと確信した上での戦略だった。
もし、この絶体絶命の状況で、赤尾に勝つ方法があるとすれば、大量の偽物たちの中から本物の赤尾を見つけ出し、一撃の元に仕留めるしかないだろう。
理論上は、不可能ではなかった。だが、標的を見定めるために集中する時間が必要だし、その間、赤尾がじっと待ってくれているはずもない。
楸は、単独で妖怪と戦うには、本当に適していない四季姫だ。一番、欲しいと思っていた、榎や柊の持つ強靭な力を備えていない。己の無力さに、情けなさまで感じた。
別の作戦を考えている暇も、与えてはくれなかった。
統率した動きで、赤尾たちは一斉に飛び掛かってきた。
逃げる暇もない。楸は微動だにできないまま、迫ってくる狐の群れを凝視していた。
狐たちの波に飲まれかけた刹那。突然、体を強く押し飛ばされた。
側の、つつじの繁みに突っ込む形で、倒れ込む。
何が起こったか分からなかったが、赤尾の攻撃からは逃れられた。
素早く体を起こし、隣を見ると、一緒に垣根に突っ込んで倒れている宵の姿があった。木の枝に切り裂かれた頬や腕から、血が滲んでいる。楸の頭から、血の気が引いていく感覚がした。
「宵はん、ついてきたら、あかんどす!」
お礼よりも先に、命にかかわる危険な行為を叱る言葉が出てきた。
「俺には、赤尾を呼び出した責任がある。今更、お前を一人で行かせられるかよ!」
「せやかて、まだ、力は戻っておらんでしょう。生身の人間の体で、何ができるんどすか!」
宵の性格はよく分かっているから、頑固な行動は理解できる。
だが、無茶が過ぎる。
楸一人でもどうにもならない事態なのに、宵を助けながら戦うなんて、絶対に無理だ。
「体一つあれば、何なりとできる。囮でも盾でも、好きに使え」
楸の訴えを押し退け、宵は楸を庇って立ち上がり、大量の狐たちに向きあった。
力が及ばない分、宵は全てを懸けて、赤尾に立ちはだかるつもりだ。己の、命さえも賭して。
そんな強行策が、許されるはずがない。少なくとも、楸は絶対に、許さない。
楸は宵の腕にしがみつき、全力で引き止めた。
「私はもう、大切な人が危険な目に遭うなんて、嫌なんどす! 誰にも、傷付いて欲しくない……」
行かせまいと、力を込めれば込めるだけ、手が震えた。
「俺だって、同じだ。楸を一人で危険な目に遭わせるくらいなら、死んだほうがましだ」
必死で腕を掴む楸の頭を、宵は空いた手で、優しく撫でてきた。
顔をあげると、微笑む宵の顔が、涙で滲む視界に入り込んできた。
どうして、宵はいつも、穏やかな顔をしていられるのだろう。死ぬかもしれない厳しい状況に直面して、恐怖を感じないのだろうか。
楸のためなら、なんて犠牲精神は感心できない。楸みたいなどうしようもない人間のために、失われていい命なんて、ない。
楸は強い気持ちを込めて、宵の腕を掴み続けた。
「人間なんかとイチャイチャして、気持ちが悪いねぇ。流石は、半端者の不吉鳥」
庇い合う楸と宵の姿を見て、分身の群れに隠れた赤尾が、嫌らしく笑った。続けて、分身たちの笑いの波が押し寄せる。
宵が目を細めて、赤尾を睨みつけた。
半端者の不吉鳥。妖怪と人間、さらに悪鬼の血まで引き継ぐ宵や朝を、象徴する呼び名だろうか。
宵の反応から察するに、決して良い意味を持つ名前ではなさそうだ。
「千年前は、そう呼ばれて、人からも妖怪からも嫌われていらっしゃいましたねぇ」
やっぱり宵たちを嘲り、差別するための名前らしい。妖怪としての宵たちの地位はそれなりに高く、みんなから敬われる存在なのかと思っていたが、違うらしい。
妖怪とも人間とも違う存在だから、双方から忌み嫌われてきたのだろう。だから、分け隔てなく接してくれた千年前の四季姫たちを慕い、必要としてくれた下等妖怪たちを助け続けてきた。
さらに今は、楸を――。
宵の、大切な者を守ろうとする、共に近しい存在であろうとする執念の断片を、垣間見た気がした。
「嫌われ者だから、親切にされると、すぐに騙されちまうんだ。あんたみたいな気味の悪い生き物に、誰が本気で構うっていうのかね。馬鹿馬鹿しい」
赤尾の言葉に、宵が微かに反応していた。
「ただの挑発どす、まともに聞かんでもよろしい」
宵の手を強く握り締め、楸は宵の隣に立った。動揺した視線を向けてきた宵に、楸は微笑みかけた。
「あなたが何者かなんて、今更、愚問でしょう? 考える必要もありまへん。宵はんの価値は、そんな括りで決め付けられるもんではないどす」
完全な妖怪ではないから、人間ではないからと、虐げられる道理なんてない。妖怪や人間に合わせようと、焦らなくてもいい。
宵は宵なのだから、ありのままでいればいい。
強い視線を向けると、宵の泳いでいた瞳も、次第に焦点が定まってきた。
握り返してくる宵の手に、力強さを感じる。もう、迷いはなかった。
「あんたも、変な人間だね。執拗に妖怪を恨んで、倒そうと追いかけ回していると思いきや、訳の分からない妖怪の肩を持つなんてさ」
赤尾の不愉快そうな声が、狐の群れの中から聞こえてくる。
くだらない問い掛けだ。楸は鼻で笑った。
「簡単な理屈どす。私が倒したい相手はあなたであって、妖怪ではない。私が側におりたい相手も、宵月夜はんであって、妖怪ではないんどす」
赤尾は、よく分かっていない様子だった。妖怪は妖怪、人間は人間と分けてしか考えられない狐には、理解できなくて当然だ。
「別に、どうでもいいけどね。餓鬼のお飯事に付き合うつもりはないよ。そんなに一緒にいたいなら、二人揃って、さっさと死にな!」
目の前に群がる狐たちが、一斉に身構えた。黒い前足を前方に突き出し、念を込め始める。細長い肉球から、炎の塊が放たれた。
一つならば、掻き消すくらいはできたかもしれない。だが、迫りくる炎の数は、赤尾の分身の数と同じだけ。
数えられないほどの炎の乱舞が、襲い掛かってきた。
啖呵を切ったところで、敵に打ち勝つ方法を見つけたわけではない。
命の危険を悟った瞬間、楸の体は、宵を庇おうと腕を広げていた。
炎が、楸めがけて飛んでくる。
その直後。激しい風が辺りを包み込み、炎を吹き飛ばした。
赤尾の分身たちは、強風に煽られながら、飛ばされまいと必死で踏ん張っていた。
楸は、風に巻かれながら、人の腕に抱きかかえられる感触を覚えた。急に地面から足が離れ、一気に上空に浮かび上がる。
驚いて顔を上げた。すぐ傍に、宵の笑顔があった。楸は、宵に抱きしめられていた。
宵の姿は、人間からは少し、かけ離れたものになっていた。獣にも似た、鋭い眼光。髪は長く伸び、楸を包み込む手には、長い爪が伸びている。
極めつけは、服を突き破って背中から飛び出した、大きな漆黒の翼。
初めて出会った時と同じ、宵月夜の姿に戻っていた。
同時に、楸は宵と一緒に空を飛んでいるのだと気付いた。
かなり高くまで上昇している。下を見ると、地上が遠くて眩暈がした。楸は慌てて、宵に強くしがみついた。
「力が、戻ったんどすな」
少し落ち着いてきた楸は、宵の耳元で囁いた。
四季姫が施した封印が、完全に解けた。宵が少し遠い存在になった気がして、残念さが脳裏を過った。
でも同時に、生命力溢れる宵の本来の姿を見ていると、どこか安心した気持ちにも包まれた。
「間一髪だったな。――ようやく、楸の力になれる」
宵は久しぶりに空を飛ぶ感覚を思い出そうと、嬉しそうに激しく、翼を羽ばたかせた。
「やっぱり、空はいいな! 心が軽くなる」
宵は楽しそうに笑っているが、楸には真似できそうにない。空中を自在に飛び回る感覚は、どんな遊園地の絶叫アトラクションよりも激しく、怖かった。
世界が回る。地上を見下ろすと、四季ヶ丘の町並みや京都の山々、遥か遠くに日本海まで見渡せた。目まぐるしく角度を変えながら、視界に入り込んでくる。
この景色が、いつも宵が見ていたものなのか。日本が、とってもちっぽけな島国に感じる。以前、名古屋までひとっ飛びだと言っていた意味が、ようやく分かった。
楸は恐怖に負けて、悲鳴を上げながら宵にしがみつくだけで精一杯だった。
馴らしを終えた宵は、ゆっくりと下降して、楸を地上に降ろしてくれた。腰が抜けそうになっていたが、楸は何とか力を入れて、しっかりと足を踏ん張った。
「俺が赤尾の動きを止める。楸は落ち着いて、急所を狙え」
力強い表情で、宵が指示を送ってくる。自身に満ち溢れた、頼もしい姿だった。
宵は楸と赤尾たちの間に立ち塞がり、両手を前に突き出した。
「久しぶりだからな。手加減とかできねえぞ。歯ぁ食いしばれよ」
宵が両手で印を結ぶと同時に、激しい竜巻が起こり、赤尾の分身たちを取り囲む。
身動きが取れなくなった赤尾は、渦の中心に纏まって、警戒心を露わにしていた。
竜巻は徐々に黒い渦に変わり始め、電流を帯び始めた。稲光を明滅させながら、徐々に赤尾を追い詰めていく。
激しい音と共に、雷が渦の中心に落ちた。狐たちの悲鳴が響き渡る。
竜巻が治まると、雷に打たれて倒れた、大量の狐たちが視界に入ってきた。
楸は標的に向かって弓の弦を引き、術を発動する。赤い二重丸の形をした的が浮かび上がり、狐たちを順番に探っていく。
「――〝千里の的〟。……急所、見えたどす!」
急所とは、分身の中に隠れた赤尾の本体そのものだ。実体は、一番奥の端のほうで、縮こまって身を隠していた。
楸は狙いを定めて、素早く矢を放つ。赤尾は、すぐ傍にいた分身を盾にして、攻撃を防いだ。心臓を射抜かれた分身は、断末魔の悲鳴を上げて粉塵と化した。
すかさず、二投目を放った。だが、赤尾は矢を避けて逃げた。他の分身たちも散り散りに分散し、周囲一帯に広がった。
宵が風を操って捕えようとしてくれるが、数が多すぎて捕まえきれない。
「弓なんて、いやらしい武器だねぇ。けど、あっしも、ただではやられんよ」
赤尾たちは後ろ足に力を込め、楸たちの周りを物凄い速さで飛び回り始めた。辺りの木を蹴り飛ばしては方向転換し、延々と高速移動を続けながら、楸たちを翻弄してくる。
「相変わらず、逃げ足だけは逸品だな」
宵は悪態を吐くが、赤尾のスピードには追いついていけない。風の塊を放つが当たらず、苛立って、舌打ちをしていた。
赤尾は、単純に逃げ回るだけではなかった。高速で飛び回りながら、隙あらば炎の欠片を飛ばして攻撃してくる。小さな火の玉が顔や腕を掠めるたびに、肌に焼け付く痛みが走った。
「狙いが、定まらんどす……!」
本体の場所は分かっているが、弓を構えている暇がない。このままでは一方的に弄られるだけだ。楸は現状に苛立っていた。
何とか、赤尾を仕留める方法はないか。まだ、楸が把握していない秋姫の力があるかもしれない。
楸は目を閉じて、精神を集中させた。
手元に、熱が集まっていく感覚がした。指先が、妙に熱い。
新しい力が湧いてくる。楸はその瞬間を、しっかりと自覚した。
ゆっくりと目を開くと、握りしめていた弓の形状が、大きく変化していた。
竹のしなりが特徴の、漆塗りの梓弓が、強固な木製の弧を描く弓になった。中仕掛けの部分に、番えるべき矢の代わりに、同様の木の棒があてがわれ、固定されていた。木の棒には深い溝があり、細い矢が何本も束ねて収蔵されていた。
「クロスボウ、どすか……?」
本でしか見た覚えがないが、西洋で発明されて進化してきた、自動式の弓矢によく似た形状だった。威力や飛距離は通常の弓矢より劣るものの、精度が高く、素人でも容易に扱える代物だ。
弓の装填と、的を絞り込むための時間が、大幅に短縮される。現状を打開するには、もってこいの武器といえた。
楸は本能のままに、進化を遂げた弓を構える。力を込めると、大量の赤い的が出現し、飛び回る赤尾の分身たちを残らず捉えた。
木の棒で設えられた台座の底部にある、引き金を引く。
直後、ものすごい勢いで、針みたいな矢が連射され、次々と飛んで行った。矢は的確に分身に突き刺さり、あっという間に消滅させていった。
「オート連射どすか……。便利になりましたなぁ」
唖然と、自動射撃の威力を実感していた。楸自身は、しっかりとした和弓を使って、じっくりと標的を射るほうが好みだが、多勢に無勢の時には、こんな武器のほうが有り難い。
赤尾の分身たちが消滅すると共に、楸の弓も元の形に戻った。自在に形状を変えられるらしい。
嵐が過ぎ去ったかと思えるほど、周囲は静寂に包まれていた。最後に、背中に矢を突き刺された赤尾の本体が、目の前で倒れこんで体を震わせていた。
「狡いぞ、いきなり強くなりやがってぇ!」
涙目になりながら、赤尾が怒鳴りつけてくる。
確かに、反則技かもしれない。だが、狡いなんて、この狐だけには、いわれたくない。
「狡賢い狐を倒すための力なら、妥当なところでしょう」
一匹になってしまえば、矢で射倒すなんて容易な作業だ。楸はゆっくりと弦を引き、狙いを定めた。
やっと、仇が討てる。心臓が、激しく高鳴った。
何とか興奮を抑えて精神統一し、腕に力を込める。
突然、体の奥から、熱い気の流れが込み上げてくる。鼓動が焼け付きそうなほど、激しく熱を帯びた。
あまりの熱さに息苦しさを覚え、楸は胸に手を当てて蹲った。
「楸、しっかりしろ!」
宵が慌てて駆け寄ってくる。手を差し伸べてくれるが、楸の肩に触れた瞬間、指先に炎が迸った。
「宵はん、近づいたら駄目どす。力が、制御できへん……」
反射的に手を引っ込めた宵から、楸は四つん這いになって距離を置いた。
激しく高鳴る鼓動が、苦しい。体中を、炎で焼かれている感覚に陥った。
もう一息なのに、体がいうことを聞かない。最後の一矢が、放てない。
楸が自由に動けないと気付いた赤尾は、背中の矢を引き抜いて、へっぴり腰で逃げようとした。
また、奴を逃してしまう。せっかく、最後まで追い詰めたのに。
運命なのだろうか。楸は一生、家族の無念を晴らせないのだろうか。
絶望に襲われそうになっていると、急に、楸の体が引っ張り上げられた。
宵が、楸を引き起こして、まっすぐ立てるように支えてくれた。
楸が放つ熱い力が宵に移り、腕や顔の皮膚が爛れ、煙が上がっている。
傍にいては駄目だ。宵まで、炎に焼かれる。
楸は宵を振り解こうとした。だが、宵の力は強く、楸の体を支えて、放さない。
「俺に構うな、早く討て!」
宵の張り上げた声が、楸の中で躊躇を生み出していた大きな枷を、弾き飛ばした。
気付けば、腕が勝手に動き、素早く弓を構えていた。
頭の中から、鮮明な言葉が浮かび上がってくる。
「焦熱にて灰となれ。――〝朱雀の炎翔〟!」
全力を振り絞って、矢を放つ。矢は炎を纏って、逃げる狐の足元めがけて飛んだ。
だが、赤尾に当たることなく、地面を抉った。
外した。狙いが定まらなかった。楸は脱力した。
その直後。矢が突き刺さった地面が激しく爆発した。地中から炎の柱が伸び、はるか上空まで突き上がった。その炎の中から、巨大な炎の鳥が飛び出し、空を舞っていた。
優雅に羽ばたく炎の鳥は、ゆったりとした動きで、地上めがけて滑空した。――赤尾に狙いを定めて。
必死で逃げようとする赤尾に、鳥は勢いよく体当たりした。赤尾は炎に飲まれ、おぞましい悲鳴を上げた。
炎の鳥は地面に潜り、姿を消した。立ち上っていた炎も消え、楸の体の熱も治まった。
眼前では、真っ黒焦げになった赤尾が、煙を立ち上らせながら倒れていた。
まだ息があるらしく、ピクピクと前足を動かしている。
「こんな、化け物に、育っちまうとは……」
震える首を回し、楸を睨み付けてくる。弱々しい声で、恨み辛みを吐き出した。
「あんたの魂、さっさと食っとけば、よかった、ね」
最期の言葉を残し、赤尾は力尽きた。黒焦げの体は炭と化し、風に吹かれて粉々に吹き飛んでいった。
倒した。ついに、念願の敵を討てた。
体から、一気に力が抜けていく。足腰に、力が全く入らない。楸は膝を折って、倒れこんだ。
地面に倒れこむ直前に、体を抱きとめられた。閉じそうな瞼を懸命に開くと、不安そうな宵の表情が霞んで見えた。
「倒せたんどすな。私の手で……」
消え入りそうな声で、楸は訊ねていた。宵は泣きそうな顔で、必死に笑おうとしていた。
「そうだ、楸が、倒したんだ。凄い技だった」
震える声で伝え、楸の頭を、優しく撫でてくれた。
「力を使い果たしたんだな。待ってろ、四季姫たちを、呼んでくる」
「待って。もう少し、今のままで……」
楸から手を放し、榎たちのところに行こうとした宵を、力なく引き留めた。宵も無理に振り解こうとはせず、楸の傍にいてくれた。
心身共に限界だったが、心は晴れやかで、清々しかった。
この強い余韻を、まだ掻き消したくない。叶うなら、何よりも大切な人の元で、感じていたい。
宵の腕に顔を埋めながら、楸の意識は、深い、温かい場所へと落ちていった。
0
あなたにおすすめの小説
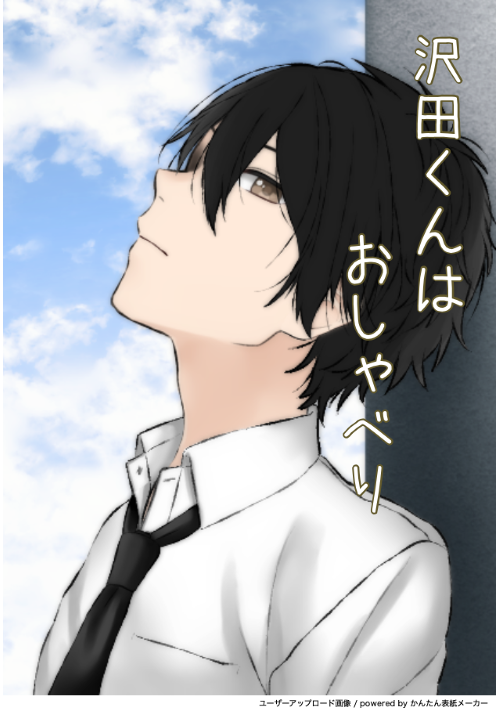
沢田くんはおしゃべり
ゆづ
青春
第13回ドリーム大賞奨励賞受賞✨ありがとうございました!!
【あらすじ】
空気を読む力が高まりすぎて、他人の心の声が聞こえるようになってしまった普通の女の子、佐藤景子。
友達から地味だのモブだの心の中で言いたい放題言われているのに言い返せない悔しさの日々の中、景子の唯一の癒しは隣の席の男子、沢田空の心の声だった。
【佐藤さん、マジ天使】(心の声)
無口でほとんどしゃべらない沢田くんの心の声が、まさかの愛と笑いを巻き起こす!
めちゃコミ女性向け漫画原作賞の優秀作品にノミネートされました✨
エブリスタでコメディートレンドランキング年間1位(ただし完結作品に限るッ!)
エブリスタ→https://estar.jp/novels/25774848

攻撃魔法を使えないヒーラーの俺が、回復魔法で最強でした。 -俺は何度でも救うとそう決めた-【[完]】
水無月いい人(minazuki)
ファンタジー
【HOTランキング一位獲得作品】
【一次選考通過作品】
---
とある剣と魔法の世界で、
ある男女の間に赤ん坊が生まれた。
名をアスフィ・シーネット。
才能が無ければ魔法が使えない、そんな世界で彼は運良く魔法の才能を持って産まれた。
だが、使用できるのは攻撃魔法ではなく回復魔法のみだった。
攻撃魔法を一切使えない彼は、冒険者達からも距離を置かれていた。
彼は誓う、俺は回復魔法で最強になると。
---------
もし気に入っていただけたら、ブクマや評価、感想をいただけると大変励みになります!
#ヒラ俺
この度ついに完結しました。
1年以上書き続けた作品です。
途中迷走してました……。
今までありがとうございました!
---
追記:2025/09/20
再編、あるいは続編を書くか迷ってます。
もし気になる方は、
コメント頂けるとするかもしれないです。

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました
蒼羽咲
ファンタジー
つまらなかった乙女ゲームに転生⁈
絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。
絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!
聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!
ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!
+++++
・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

荷物持ちチート(倉庫、翻訳、環境適用)から始める異世界物流革命
ニャルC
ファンタジー
事務屋の僕が授かったのは、勇者の「荷物持ち用」と揶揄される地味なスキルセット(倉庫・翻訳・適応)だった。神には「魔王は倒せない」と笑われ、商業ギルドには「実績不足」と門前払い。算盤一つで砂漠に水道橋を架け、「砂漠の水道王」になる。神のシナリオを越えた、持たざる者の「逆襲」。痛快な異世界インフラ革命!

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

下宿屋 東風荘 7
浅井 ことは
キャラ文芸
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆*:..☆
四つの巻物と本の解読で段々と力を身につけだした雪翔。
狐の国で保護されながら、五つ目の巻物を持つ九堂の居所をつかみ、自身を鍵とする場所に辿り着けるのか!
四社の狐に天狐が大集結。
第七弾始動!
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆*:..☆
表紙の無断使用は固くお断りさせて頂いております。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















