3 / 9
その3
しおりを挟む
◇
下山した粟島は、ひとまず事務所に戻り依頼人に連絡を取った。一刻も早く猫を届けるべきだとは思ったが、相手の都合もあるし、なによりそのまま訪問するには粟島の服装に問題があった。
粟島の着ている服は泥だらけなうえあちこちが擦り切れていて、いかにも遭難しましたと言わんばかりの状態だった。ズボンの左裾は治療のために膝上まで切り裂かれている。仮縫いはしてもらったが、事務所に戻るまでの道で誰とも会わずにすんだのは幸運だった。
そういえば、マシロの家で床を借りていたとき、アウターは脱いでいたがズボンはそのままだった。本当に申し訳ないことをしたと思う。布団は必ず弁償しよう。
数コールの後、依頼人が電話口に出た。猫が見つかった旨を伝え、引き渡しについて相談する。怪我もしているし、医者に診せた方がいいのは間違いない。
町の動物病院は、粟島の事務所と依頼人の家のちょうど間にあった。そこを受け渡し場所に指定し、時間は少女の下校時刻に合わせることになった。
小学校の下校時刻まであと一時間弱。粟島はそれまでに風呂を済ませ、なるべく傷が見えない服を選んで身支度を整えた。
◇
「ベンケルハイト!」
猫はするりと粟島の腕から抜け出すと、腕を広げて駆け寄る少女に飛びついた。
少女の目からぼろぼろと安堵の涙がこぼれ落ちる。猫は自身の毛が濡れるのも構わず少女の頬に擦り寄り、その涙を舐め取った。
「本当に、ありがとうございました」
「いえ。無事に見つかってよかったです」
少女は涙を拭って粟島に近付き、ありがとう、と涙声で言いながら手を差し出した。
「これ、お礼」
粟島が両手で受け取る。小さな貝殻と、つるつるの石だった。
「ベンケルハイトとね、いっしょに見つけたの」
「きれいだね。もらっていいの?」
少女はこくりとうなずいた。粟島が母親に確認を取れば、迷惑でなければ受け取ってやってほしいとのことだった。
「ありがとう。大事にするね」
少女がにこりと笑う。けれどその表情はすぐに曇った。
「ツチノコは?」
「…………まだなんだ。ごめんね」
できれば忘れていてほしかった。
粟島は屈んで、少女に視線を合わせた。
「ツチノコっていうのはみんなには内緒の生き物だから、退治しても証拠は持ってこれないんだ。でも倒したらちゃんと君に報告するから。危ないことはせずに、ベンケルハイトと待っててくれるかな?」
少女が何か言うより先に、猫がにゃおんと返事をした。少女が猫に視線をやれば、猫は少女の顔をぺろりと舐める。
少女は粟島の目を見て、こくりとうなずいた。どうやら信用は得られたらしい。
追加資料として、少女は以前の絵より禍々しさが増したツチノコの絵を二枚粟島に渡した。絵を指差しながら「このへんの模様が気持ち悪かった」と解説まで入れてくれる。ツチノコの背中には動物の目のような模様が大小いくつか描かれていた。たしかにこれは粟島でも気持ち悪いと思う。
母親が申し訳なさそうな顔で粟島を見た。さすがに未確認生物の捜索と退治を料金に含めることはできない。ここから先はタダ働きだ。
もちろん適当なことを言って切り上げたってよかった。実際ツチノコなどいないのだから、どのみち退治譚はでっちあげるしかない。ただ粟島が、少女の不安を雑にあしらいたくなかっただけだ。つまりは自己満足だった。
猫を医者に診せるため、その日はそこで別れた。報酬は後日あらためて依頼人が事務所まで払いに来てくれることになった。
少女たちが病院に入ったのを見送って、粟島は帰路につく。
猫を見つけたのも、治療して保護したのも、粟島ではなくマシロだ。この貝殻も、石も、マシロが受け取るべき報酬だった。
けれどマシロは、自分のことはあまり人に話さないでほしいと粟島に頼んだ。理由を聞いたが、困った顔をするだけで答えてはくれなかった。
恩人の唯一の頼みを無下にもできない。粟島が誰にも話さないと約束すれば、マシロは安心したように笑った。
◇
事務所に戻り、報告書の準備をしていたところで粟島のスマホに着信がきた。画面には、最近猫探しについてアドバイスを求めた探偵の名前が表示されている。粟島は通話ボタンを押した。
「もしもし……」
『粟島ァ!』
電話口からの大音声に、思わず耳を離す。
「え、なに、うるさ……。どうかした?」
『貴様……山へ行くと言って一晩連絡が取れなかったくせになんだその態度は』
探偵は不機嫌そうに粟島をなじる。先日の電話でたしかに山の話をした気はするが、一度も山へ行くとは言っていなかったはずだ。そうでなくとも、お互いに連絡がつかないことなどよくあった。
「ごめん。もしかして心配してくれた?」
『違う』
食い気味に否定された。
『貴様のことだ。軽い気持ちで山に臨みはせんだろうが、猫が崖から落ちかけていれば迷わず飛び込むお人好しだからな。一応確認したまでだ』
「つまり心配してくれたんじゃないか」
『してない』
悪かったよ、と謝れば、探偵はふんと鼻を鳴らした。
「お前はそう言ってくれるけど、俺だってさすがに自分の身の方がかわいいよ」
『どうだか』
訝しむ探偵に、話題を変えようと猫が見つかったことを伝えれば、そうか、とだけ返ってきた。しばらく間を開けて、よかったな、という小さな呟きが聞こえた。この探偵は優秀だったが、迷い猫が無事に見つかることは少なかった。
粟島は書類を机に置いて冷蔵庫へ向かう。中にはゼリーが数個と炭酸飲料が二本入っていた。小さい方の缶を取り出して、粟島はソファに腰かけるとタブに指を掛ける。
『酒か?』
「エナドリ」
『今すぐ寝ろ』
電話口から舌打ちが聞こえて、粟島は笑いを噛み殺す。彼はわかりやすく人の心配をして、わかりやすく優しさを表現するのが下手だった。いわゆる“根はいいやつ”なのだ。
「せっかくだからもう少し怒ってほしいんだけど」
『なんだ』
「昨日、猫とは関係なく山で足を滑らせたんだ」
『馬鹿め』
「それで……詳しくは言えないんだけど、当分山には通うと思う」
探偵は長めのため息をついた。
『俺を保険にしてくれるな。他を当たれ』
「町内会長には伝えるつもりだよ」
探偵はもう一度、盛大にため息をつく。肺の空気を出し切らんばかりのそれには、粟島への抗議と諦めが多分に含まれていた。
『……山の名前は?』
なんだかんだ言いながら面倒見のいい男だった。お人好しというなら彼の方だと常々思う。
「あさぎ。植物の麻に、建物の城って書いて、麻城山」
察しのいい探偵は、それ以上の詳細を訊ねることはしなかった。
それからしばらく雑談を交わし、通話を終える。スマホを操作して確認すれば、たしかに探偵からの着信履歴が数件あった。山は圏外だったため気付かなかった。
粟島はソファに身を沈め、天井を眺める。
こうして粟島の身を案じてくれる人は多い。家族も、友人も、町の人々も。粟島の周りにいるのは気のいい人たちばかりだった。
マシロはどうだろう。彼にも気が置けない友人はいるのだろうか。いつからあの山で暮らしているのだろう。誰かと共に生きたことは、あるのだろうか。
粟島は今、踏みとどまるべき境界に立っている。今ならまだ引き返せる。
けれど。
無理はするなと言った粟島の言葉に、マシロが笑う前に一瞬見せたあの泣きそうな顔が、どうしても頭から離れなかった。
◆
初めて訪れた町であったはずなのに、粟島は何故か懐かしいと感じた。きっと町の人々のあたたかい人柄がそう思わせたのだろう。
これまで各地を転々としてきたが、ここを永住の地とするのも悪くない選択に思えた。
「ここのやつらは、みんなおしゃべりが好きなんだ」
粟島に町を案内しながら、町内会長の日ノ池が言った。
「捕まったら三時間は帰れないと思った方がいい」
実際、日ノ池は五時間ほど案内を続け、そのあいだずっと話し続けていた。そのあとも、歓迎会だと言って中央会館へ連れて行かれた。滅多に人が越してこないから、新住民が増えるたびお祭り騒ぎになるらしい。
ずっとにぎやかで、粟島はひとりになる暇がなかった。
「そこの山に展望台がある。何もないところだが眺めはいいから、いつか行ってみるといい」
歓迎会の帰り道、山があるであろう方向を指差しながら日ノ池が言った。もうすっかり日は沈んでいて、粟島には何も見えない。
春になればタケノコを掘りに行くし、秋になれば狩猟もできる。行く機会ならいくらでもあるだろう。そう笑う日ノ池に、粟島も笑顔で返した。
だが想定していた以上に日々が忙しくて、結局展望台には一度も行けないままだった。
◇
マシロに助けられてから約一ヶ月後。
約束を果たすべく、粟島は再び山に登っていた。
前回の最低限装備とは違い、しっかりと準備を整え、登山の講習も受け直した。粟島は地図を見ながら山道を進む。
鳥のさえずり、風が木々を揺らす音、川のせせらぎ。土や草のにおい。岩場や樹木に生えた苔、可憐な花や小さな木の実。前回は意識を向ける余裕のなかったそれらも、今は少しだけ楽しめた。相変わらず薄暗いので、落ち着くかといわれたら微妙だったが。
一時間ほど登ったところで、粟島はようやく一番の問題に気が付いた。
「マシロさんの家って、どこにあるんだ……?」
前回マシロが粟島を麓まで送ってくれた道は、どうも地図には載っていないようだった。
あのとき通った道には標識の類いが見当たらなかったから、あれはマシロが個人的に使っているもので登山道ではないのだろう。それにしたって、同じ入り口から入ったはずなのに、粟島はそれらしき道を見つけることすらできなかった。
下手にルートを外れてしまえば、また遭難することになる。粟島は現在地を確認しながら慎重に山頂を目指していた。
何故だか粟島は、山頂へ向かえばマシロに会えると、根拠もなくそう思っていたのだ。
周りの風景に目を向けながら歩いていると、緑や茶色が多い景色の中、ひときわ目立つ色が視界に入った。
木の根元の地面から、何かが生えている。薄紅色をした棒状のものが数本枝分かれし、上に向かって伸びていた。
どこかで見たことのある光景だった。そうだ、最近観たホラー映画に、ちょうどこんなシーンがあった。土の中から、ゾンビが土をかき分けて出てくる場面だ。
粟島は地図を投げ出して走り寄った。現実にはゾンビなんて存在しない。いたとしても火葬が主な日本ではまずお目にかかれないだろう。
近付けば近付くほど、それは人間の手に見えた。
粟島は手を伸ばしたが、それには届かず空を切った。誰かが後ろから粟島の腕を掴んで止めたのだ。
「触らないで」
聞き覚えのある声がした。
「触れると皮膚が爛れます。食用には不向きかと」
「食……っ⁉」
「茸でしたら、あちらで採れますよ」
「…………キノコ?」
よく見れば、手のように見えたそれはたしかに人の質感とは異なった。
人間が埋まっているわけではなかったのだとわかって、粟島はほっと息をついた。おかげで不名誉な勘違いをされていることには気付いていない。
「傷の具合は如何ですか?」
「……おかげさまで、すっかりよくなりました」
粟島が振り返った先にいたのは、先日と変わらぬ着流し姿の男だった。
◇
粟島が人間の手だと誤認したのは、カエンタケというキノコらしかった。
「有毒ですから、決して口になさらないでくださいね」
マシロは見える範囲にあるキノコや草花の食用に関する可不可について説明をはじめた。
こう何度も助けられては頭が上がらない。なんとなく誤解もあるような気はしたが、粟島は素直に「はい」と返事をした。
マシロは相変わらず着流しの軽装で、足元は黒い足袋に雪駄という格好だった。
粟島も、雪駄は一度だけ履いたことがある。かかとを出して履くのが正しい履き方らしく、知らなかった粟島は素足で挑んで砂利を踏み、かかとは血塗れになった。それ以来、草履も下駄も怖くて履いていない。
「以前粟島さんが遭遇された物怪ですが」
食用講義は終わったらしい。粟島はマシロの足元から視線を上げる。
「証拠というものをお見せすることはできませんが、退治は致しました。あれから何度か見回っておりますが登山道付近で目撃したことはございません。これで当面はご安心いただけるかと」
粟島の錯覚でなければ、あの獣は三メートル近い大きさであったはずだ。下山してから熊について調べたが、あの獣が熊と同等のスペックを有していたとすれば丸腰の人間に勝ち目はない。マシロは猟銃を所持しているようだったが、銃弾が外れれば数秒で距離を詰められ反撃される可能性もある。狩りや駆除というものは、粟島が想像していた以上に危険と隣り合わせにあるものだった。
粟島が見る限り、マシロの体に目立った傷は見当たらなかった。歩く様子にも異常はない。きっと大きな怪我はしていないのだろう。
『必ず仕留めます。ですからどうか、このことはご内密に』
別れる前に告げられたその言葉は、町の人々への配慮だったのか、粟島にはわからない。ただマシロのことは信じてもいいと、あのときの粟島はそう思った。
マシロは粟島が落とした地図を拾い上げ、くるくると回しながら「今の地図は色彩豊かですね」と楽しそうに笑っていた。ひとしきり眺めたあと、はっとした様子で地図を畳み粟島に手渡した。
「申し訳ありません、断りもせずに不躾な真似を」
「いえ、そんな。地図くらいいくらでも見てください」
多少の書き込みはあったが、見られて困るようなことは書いていない。粟島は地図を受け取って、拾ってもらった礼を告げる。マシロは少し眉を下げ、もう一度謝罪を口にした。
「あ、予備ありますけど、よかったらいりますか?」
粟島は胸ポケットから予備の地図を取り出した。こちらは購入時に確認のため一度開いただけなので、新品といっていいだろう。大人用の登山地図と、子ども向けのポップでかわいらしい簡略地図のセットで、マシロが見ていたのは子ども向けの方だった。
マシロは一瞬目を輝かせたが、すぐに首を横に振った。
「たいへん有り難い申し出ですが、残念ながら通貨の持ち合わせがございません」
「お金はいりませんよ。そんなつもりで出したんじゃありませんし」
もしかすると今見えている面だけでは、さきほどマシロが見ていたのと同じ地図だと認識できていないのかもしれない。粟島は地図を広げてみせた。デフォルメされた動物が描かれたカラフルな面をマシロに向ける。
それでもマシロは首を縦には振らなかった。
表情を見る限り、不要というわけではなさそうなのだ。こういう場合は、受け取るための正当な理由さえ用意できればいい。
粟島はもう一度、マシロが楽しそうにする姿を見たかった。
「あ、さっきの講習料ってことならどうですか?」
食べるかは置いておいて、有毒か否かの知識は非常に役立つものだった。キノコも木の実も、見れば見るほど似ている気がして、安易に口にするのはやめておこうと心に誓う。
マシロは地図と粟島を交互に見て、少し迷った様子を見せながらも両手で地図を受け取った。
「……ありがとうございます」
マシロはふっと眉を下げて笑った。「大事にします」と言って、しばらく眺めたあと、丁寧に地図を畳んだ。
彼は、ああいうかわいいものが好きなのだろうか。粟島は麓の商店で見たファンシーグッズを思い出そうとした。けれど興味がなかったせいか、記憶の輪郭は朧げだ。
マシロは地図を懐にしまうと、粟島に向き直った。
「それで、本日のご予定はつちのこ退治でよろしいでしょうか?」
みなツチノコに積極的すぎやしないだろうか。
たしかに今回の目的はツチノコ狩りだし、ツチノコの生息域はすでにマシロが把握しているようだが、粟島にも準備というものが必要なのだ。主に、心の。
「それもありますけど、まずは先日のお礼とお詫びを……」
粟島はリュックから菓子折りを取り出した。日持ちした方がいいかと思い干菓子の詰め合わせにしたが、マシロは気に入ってくれるだろうか。
手渡そうとして「あ、今じゃないな」と思った。
「ではいつがよろしいですか?」
口にも出ていた。
「いえ、違……すみません。山の中で渡すものじゃなかったな、と。マシロさんの家に伺ってから渡そうと思ってたんですが、道がわからなくて」
「ああ、たしかに登山道からは外れていますからね。見通しも悪いので、無理もないことです」
マシロは粟島が登ってきた道を少し引き返して、脇にある藪のトンネルをくぐっていった。
「どうかお気を付けて」
頭上に注意しながら、粟島もトンネルをくぐる。
しばらく進めばマシロの家に辿り着いた。簡素ながらしっかりとした造りの古民家で、昔話といえばこんな家だろうという風情が漂っていた。
「茅葺き屋根……」
粟島はぽそりと呟いた。前回は余裕がなかったとはいえ、気付かなかったことが悔やまれる。
粟島は子どものころから、茅葺き屋根と囲炉裏のある家に憧れていた。大人になったらこんな家に住む、と何枚も設計図を描いていたらしい。どれを見ても台所だけは現代式のハイテク仕様だったと、両親は酔うたびにそんな話をした。粟島も、大人になってからそれらの絵を何枚か見たことがあった。囲炉裏のそばではたいてい山姥が包丁を研いでいた。
あの日は使われていなかったが、マシロの家にはたしか囲炉裏もあったはずだ。台所だって、冬の底冷えというデメリットさえどうにかできれば、他の不便さには目を瞑るつもりでいたのだ。
マシロの家には、粟島の理想の大半が詰まっていた。
「粟島さん?」
マシロの声に、粟島は自身の足が止まっていたことに気付いた。粟島は慌てて視線を逸らす。さきほどのマシロの気持ちが、少しだけわかった気がした。たしかにひとりで内心盛り上がっているのを人に見られるのは気恥ずかしい。
「せっかくですから、お茶にしましょうか」
マシロはにこりと微笑んだ。
「外の食べ物なんて何年振りでしょう。とても楽しみです」
下山した粟島は、ひとまず事務所に戻り依頼人に連絡を取った。一刻も早く猫を届けるべきだとは思ったが、相手の都合もあるし、なによりそのまま訪問するには粟島の服装に問題があった。
粟島の着ている服は泥だらけなうえあちこちが擦り切れていて、いかにも遭難しましたと言わんばかりの状態だった。ズボンの左裾は治療のために膝上まで切り裂かれている。仮縫いはしてもらったが、事務所に戻るまでの道で誰とも会わずにすんだのは幸運だった。
そういえば、マシロの家で床を借りていたとき、アウターは脱いでいたがズボンはそのままだった。本当に申し訳ないことをしたと思う。布団は必ず弁償しよう。
数コールの後、依頼人が電話口に出た。猫が見つかった旨を伝え、引き渡しについて相談する。怪我もしているし、医者に診せた方がいいのは間違いない。
町の動物病院は、粟島の事務所と依頼人の家のちょうど間にあった。そこを受け渡し場所に指定し、時間は少女の下校時刻に合わせることになった。
小学校の下校時刻まであと一時間弱。粟島はそれまでに風呂を済ませ、なるべく傷が見えない服を選んで身支度を整えた。
◇
「ベンケルハイト!」
猫はするりと粟島の腕から抜け出すと、腕を広げて駆け寄る少女に飛びついた。
少女の目からぼろぼろと安堵の涙がこぼれ落ちる。猫は自身の毛が濡れるのも構わず少女の頬に擦り寄り、その涙を舐め取った。
「本当に、ありがとうございました」
「いえ。無事に見つかってよかったです」
少女は涙を拭って粟島に近付き、ありがとう、と涙声で言いながら手を差し出した。
「これ、お礼」
粟島が両手で受け取る。小さな貝殻と、つるつるの石だった。
「ベンケルハイトとね、いっしょに見つけたの」
「きれいだね。もらっていいの?」
少女はこくりとうなずいた。粟島が母親に確認を取れば、迷惑でなければ受け取ってやってほしいとのことだった。
「ありがとう。大事にするね」
少女がにこりと笑う。けれどその表情はすぐに曇った。
「ツチノコは?」
「…………まだなんだ。ごめんね」
できれば忘れていてほしかった。
粟島は屈んで、少女に視線を合わせた。
「ツチノコっていうのはみんなには内緒の生き物だから、退治しても証拠は持ってこれないんだ。でも倒したらちゃんと君に報告するから。危ないことはせずに、ベンケルハイトと待っててくれるかな?」
少女が何か言うより先に、猫がにゃおんと返事をした。少女が猫に視線をやれば、猫は少女の顔をぺろりと舐める。
少女は粟島の目を見て、こくりとうなずいた。どうやら信用は得られたらしい。
追加資料として、少女は以前の絵より禍々しさが増したツチノコの絵を二枚粟島に渡した。絵を指差しながら「このへんの模様が気持ち悪かった」と解説まで入れてくれる。ツチノコの背中には動物の目のような模様が大小いくつか描かれていた。たしかにこれは粟島でも気持ち悪いと思う。
母親が申し訳なさそうな顔で粟島を見た。さすがに未確認生物の捜索と退治を料金に含めることはできない。ここから先はタダ働きだ。
もちろん適当なことを言って切り上げたってよかった。実際ツチノコなどいないのだから、どのみち退治譚はでっちあげるしかない。ただ粟島が、少女の不安を雑にあしらいたくなかっただけだ。つまりは自己満足だった。
猫を医者に診せるため、その日はそこで別れた。報酬は後日あらためて依頼人が事務所まで払いに来てくれることになった。
少女たちが病院に入ったのを見送って、粟島は帰路につく。
猫を見つけたのも、治療して保護したのも、粟島ではなくマシロだ。この貝殻も、石も、マシロが受け取るべき報酬だった。
けれどマシロは、自分のことはあまり人に話さないでほしいと粟島に頼んだ。理由を聞いたが、困った顔をするだけで答えてはくれなかった。
恩人の唯一の頼みを無下にもできない。粟島が誰にも話さないと約束すれば、マシロは安心したように笑った。
◇
事務所に戻り、報告書の準備をしていたところで粟島のスマホに着信がきた。画面には、最近猫探しについてアドバイスを求めた探偵の名前が表示されている。粟島は通話ボタンを押した。
「もしもし……」
『粟島ァ!』
電話口からの大音声に、思わず耳を離す。
「え、なに、うるさ……。どうかした?」
『貴様……山へ行くと言って一晩連絡が取れなかったくせになんだその態度は』
探偵は不機嫌そうに粟島をなじる。先日の電話でたしかに山の話をした気はするが、一度も山へ行くとは言っていなかったはずだ。そうでなくとも、お互いに連絡がつかないことなどよくあった。
「ごめん。もしかして心配してくれた?」
『違う』
食い気味に否定された。
『貴様のことだ。軽い気持ちで山に臨みはせんだろうが、猫が崖から落ちかけていれば迷わず飛び込むお人好しだからな。一応確認したまでだ』
「つまり心配してくれたんじゃないか」
『してない』
悪かったよ、と謝れば、探偵はふんと鼻を鳴らした。
「お前はそう言ってくれるけど、俺だってさすがに自分の身の方がかわいいよ」
『どうだか』
訝しむ探偵に、話題を変えようと猫が見つかったことを伝えれば、そうか、とだけ返ってきた。しばらく間を開けて、よかったな、という小さな呟きが聞こえた。この探偵は優秀だったが、迷い猫が無事に見つかることは少なかった。
粟島は書類を机に置いて冷蔵庫へ向かう。中にはゼリーが数個と炭酸飲料が二本入っていた。小さい方の缶を取り出して、粟島はソファに腰かけるとタブに指を掛ける。
『酒か?』
「エナドリ」
『今すぐ寝ろ』
電話口から舌打ちが聞こえて、粟島は笑いを噛み殺す。彼はわかりやすく人の心配をして、わかりやすく優しさを表現するのが下手だった。いわゆる“根はいいやつ”なのだ。
「せっかくだからもう少し怒ってほしいんだけど」
『なんだ』
「昨日、猫とは関係なく山で足を滑らせたんだ」
『馬鹿め』
「それで……詳しくは言えないんだけど、当分山には通うと思う」
探偵は長めのため息をついた。
『俺を保険にしてくれるな。他を当たれ』
「町内会長には伝えるつもりだよ」
探偵はもう一度、盛大にため息をつく。肺の空気を出し切らんばかりのそれには、粟島への抗議と諦めが多分に含まれていた。
『……山の名前は?』
なんだかんだ言いながら面倒見のいい男だった。お人好しというなら彼の方だと常々思う。
「あさぎ。植物の麻に、建物の城って書いて、麻城山」
察しのいい探偵は、それ以上の詳細を訊ねることはしなかった。
それからしばらく雑談を交わし、通話を終える。スマホを操作して確認すれば、たしかに探偵からの着信履歴が数件あった。山は圏外だったため気付かなかった。
粟島はソファに身を沈め、天井を眺める。
こうして粟島の身を案じてくれる人は多い。家族も、友人も、町の人々も。粟島の周りにいるのは気のいい人たちばかりだった。
マシロはどうだろう。彼にも気が置けない友人はいるのだろうか。いつからあの山で暮らしているのだろう。誰かと共に生きたことは、あるのだろうか。
粟島は今、踏みとどまるべき境界に立っている。今ならまだ引き返せる。
けれど。
無理はするなと言った粟島の言葉に、マシロが笑う前に一瞬見せたあの泣きそうな顔が、どうしても頭から離れなかった。
◆
初めて訪れた町であったはずなのに、粟島は何故か懐かしいと感じた。きっと町の人々のあたたかい人柄がそう思わせたのだろう。
これまで各地を転々としてきたが、ここを永住の地とするのも悪くない選択に思えた。
「ここのやつらは、みんなおしゃべりが好きなんだ」
粟島に町を案内しながら、町内会長の日ノ池が言った。
「捕まったら三時間は帰れないと思った方がいい」
実際、日ノ池は五時間ほど案内を続け、そのあいだずっと話し続けていた。そのあとも、歓迎会だと言って中央会館へ連れて行かれた。滅多に人が越してこないから、新住民が増えるたびお祭り騒ぎになるらしい。
ずっとにぎやかで、粟島はひとりになる暇がなかった。
「そこの山に展望台がある。何もないところだが眺めはいいから、いつか行ってみるといい」
歓迎会の帰り道、山があるであろう方向を指差しながら日ノ池が言った。もうすっかり日は沈んでいて、粟島には何も見えない。
春になればタケノコを掘りに行くし、秋になれば狩猟もできる。行く機会ならいくらでもあるだろう。そう笑う日ノ池に、粟島も笑顔で返した。
だが想定していた以上に日々が忙しくて、結局展望台には一度も行けないままだった。
◇
マシロに助けられてから約一ヶ月後。
約束を果たすべく、粟島は再び山に登っていた。
前回の最低限装備とは違い、しっかりと準備を整え、登山の講習も受け直した。粟島は地図を見ながら山道を進む。
鳥のさえずり、風が木々を揺らす音、川のせせらぎ。土や草のにおい。岩場や樹木に生えた苔、可憐な花や小さな木の実。前回は意識を向ける余裕のなかったそれらも、今は少しだけ楽しめた。相変わらず薄暗いので、落ち着くかといわれたら微妙だったが。
一時間ほど登ったところで、粟島はようやく一番の問題に気が付いた。
「マシロさんの家って、どこにあるんだ……?」
前回マシロが粟島を麓まで送ってくれた道は、どうも地図には載っていないようだった。
あのとき通った道には標識の類いが見当たらなかったから、あれはマシロが個人的に使っているもので登山道ではないのだろう。それにしたって、同じ入り口から入ったはずなのに、粟島はそれらしき道を見つけることすらできなかった。
下手にルートを外れてしまえば、また遭難することになる。粟島は現在地を確認しながら慎重に山頂を目指していた。
何故だか粟島は、山頂へ向かえばマシロに会えると、根拠もなくそう思っていたのだ。
周りの風景に目を向けながら歩いていると、緑や茶色が多い景色の中、ひときわ目立つ色が視界に入った。
木の根元の地面から、何かが生えている。薄紅色をした棒状のものが数本枝分かれし、上に向かって伸びていた。
どこかで見たことのある光景だった。そうだ、最近観たホラー映画に、ちょうどこんなシーンがあった。土の中から、ゾンビが土をかき分けて出てくる場面だ。
粟島は地図を投げ出して走り寄った。現実にはゾンビなんて存在しない。いたとしても火葬が主な日本ではまずお目にかかれないだろう。
近付けば近付くほど、それは人間の手に見えた。
粟島は手を伸ばしたが、それには届かず空を切った。誰かが後ろから粟島の腕を掴んで止めたのだ。
「触らないで」
聞き覚えのある声がした。
「触れると皮膚が爛れます。食用には不向きかと」
「食……っ⁉」
「茸でしたら、あちらで採れますよ」
「…………キノコ?」
よく見れば、手のように見えたそれはたしかに人の質感とは異なった。
人間が埋まっているわけではなかったのだとわかって、粟島はほっと息をついた。おかげで不名誉な勘違いをされていることには気付いていない。
「傷の具合は如何ですか?」
「……おかげさまで、すっかりよくなりました」
粟島が振り返った先にいたのは、先日と変わらぬ着流し姿の男だった。
◇
粟島が人間の手だと誤認したのは、カエンタケというキノコらしかった。
「有毒ですから、決して口になさらないでくださいね」
マシロは見える範囲にあるキノコや草花の食用に関する可不可について説明をはじめた。
こう何度も助けられては頭が上がらない。なんとなく誤解もあるような気はしたが、粟島は素直に「はい」と返事をした。
マシロは相変わらず着流しの軽装で、足元は黒い足袋に雪駄という格好だった。
粟島も、雪駄は一度だけ履いたことがある。かかとを出して履くのが正しい履き方らしく、知らなかった粟島は素足で挑んで砂利を踏み、かかとは血塗れになった。それ以来、草履も下駄も怖くて履いていない。
「以前粟島さんが遭遇された物怪ですが」
食用講義は終わったらしい。粟島はマシロの足元から視線を上げる。
「証拠というものをお見せすることはできませんが、退治は致しました。あれから何度か見回っておりますが登山道付近で目撃したことはございません。これで当面はご安心いただけるかと」
粟島の錯覚でなければ、あの獣は三メートル近い大きさであったはずだ。下山してから熊について調べたが、あの獣が熊と同等のスペックを有していたとすれば丸腰の人間に勝ち目はない。マシロは猟銃を所持しているようだったが、銃弾が外れれば数秒で距離を詰められ反撃される可能性もある。狩りや駆除というものは、粟島が想像していた以上に危険と隣り合わせにあるものだった。
粟島が見る限り、マシロの体に目立った傷は見当たらなかった。歩く様子にも異常はない。きっと大きな怪我はしていないのだろう。
『必ず仕留めます。ですからどうか、このことはご内密に』
別れる前に告げられたその言葉は、町の人々への配慮だったのか、粟島にはわからない。ただマシロのことは信じてもいいと、あのときの粟島はそう思った。
マシロは粟島が落とした地図を拾い上げ、くるくると回しながら「今の地図は色彩豊かですね」と楽しそうに笑っていた。ひとしきり眺めたあと、はっとした様子で地図を畳み粟島に手渡した。
「申し訳ありません、断りもせずに不躾な真似を」
「いえ、そんな。地図くらいいくらでも見てください」
多少の書き込みはあったが、見られて困るようなことは書いていない。粟島は地図を受け取って、拾ってもらった礼を告げる。マシロは少し眉を下げ、もう一度謝罪を口にした。
「あ、予備ありますけど、よかったらいりますか?」
粟島は胸ポケットから予備の地図を取り出した。こちらは購入時に確認のため一度開いただけなので、新品といっていいだろう。大人用の登山地図と、子ども向けのポップでかわいらしい簡略地図のセットで、マシロが見ていたのは子ども向けの方だった。
マシロは一瞬目を輝かせたが、すぐに首を横に振った。
「たいへん有り難い申し出ですが、残念ながら通貨の持ち合わせがございません」
「お金はいりませんよ。そんなつもりで出したんじゃありませんし」
もしかすると今見えている面だけでは、さきほどマシロが見ていたのと同じ地図だと認識できていないのかもしれない。粟島は地図を広げてみせた。デフォルメされた動物が描かれたカラフルな面をマシロに向ける。
それでもマシロは首を縦には振らなかった。
表情を見る限り、不要というわけではなさそうなのだ。こういう場合は、受け取るための正当な理由さえ用意できればいい。
粟島はもう一度、マシロが楽しそうにする姿を見たかった。
「あ、さっきの講習料ってことならどうですか?」
食べるかは置いておいて、有毒か否かの知識は非常に役立つものだった。キノコも木の実も、見れば見るほど似ている気がして、安易に口にするのはやめておこうと心に誓う。
マシロは地図と粟島を交互に見て、少し迷った様子を見せながらも両手で地図を受け取った。
「……ありがとうございます」
マシロはふっと眉を下げて笑った。「大事にします」と言って、しばらく眺めたあと、丁寧に地図を畳んだ。
彼は、ああいうかわいいものが好きなのだろうか。粟島は麓の商店で見たファンシーグッズを思い出そうとした。けれど興味がなかったせいか、記憶の輪郭は朧げだ。
マシロは地図を懐にしまうと、粟島に向き直った。
「それで、本日のご予定はつちのこ退治でよろしいでしょうか?」
みなツチノコに積極的すぎやしないだろうか。
たしかに今回の目的はツチノコ狩りだし、ツチノコの生息域はすでにマシロが把握しているようだが、粟島にも準備というものが必要なのだ。主に、心の。
「それもありますけど、まずは先日のお礼とお詫びを……」
粟島はリュックから菓子折りを取り出した。日持ちした方がいいかと思い干菓子の詰め合わせにしたが、マシロは気に入ってくれるだろうか。
手渡そうとして「あ、今じゃないな」と思った。
「ではいつがよろしいですか?」
口にも出ていた。
「いえ、違……すみません。山の中で渡すものじゃなかったな、と。マシロさんの家に伺ってから渡そうと思ってたんですが、道がわからなくて」
「ああ、たしかに登山道からは外れていますからね。見通しも悪いので、無理もないことです」
マシロは粟島が登ってきた道を少し引き返して、脇にある藪のトンネルをくぐっていった。
「どうかお気を付けて」
頭上に注意しながら、粟島もトンネルをくぐる。
しばらく進めばマシロの家に辿り着いた。簡素ながらしっかりとした造りの古民家で、昔話といえばこんな家だろうという風情が漂っていた。
「茅葺き屋根……」
粟島はぽそりと呟いた。前回は余裕がなかったとはいえ、気付かなかったことが悔やまれる。
粟島は子どものころから、茅葺き屋根と囲炉裏のある家に憧れていた。大人になったらこんな家に住む、と何枚も設計図を描いていたらしい。どれを見ても台所だけは現代式のハイテク仕様だったと、両親は酔うたびにそんな話をした。粟島も、大人になってからそれらの絵を何枚か見たことがあった。囲炉裏のそばではたいてい山姥が包丁を研いでいた。
あの日は使われていなかったが、マシロの家にはたしか囲炉裏もあったはずだ。台所だって、冬の底冷えというデメリットさえどうにかできれば、他の不便さには目を瞑るつもりでいたのだ。
マシロの家には、粟島の理想の大半が詰まっていた。
「粟島さん?」
マシロの声に、粟島は自身の足が止まっていたことに気付いた。粟島は慌てて視線を逸らす。さきほどのマシロの気持ちが、少しだけわかった気がした。たしかにひとりで内心盛り上がっているのを人に見られるのは気恥ずかしい。
「せっかくですから、お茶にしましょうか」
マシロはにこりと微笑んだ。
「外の食べ物なんて何年振りでしょう。とても楽しみです」
2
あなたにおすすめの小説
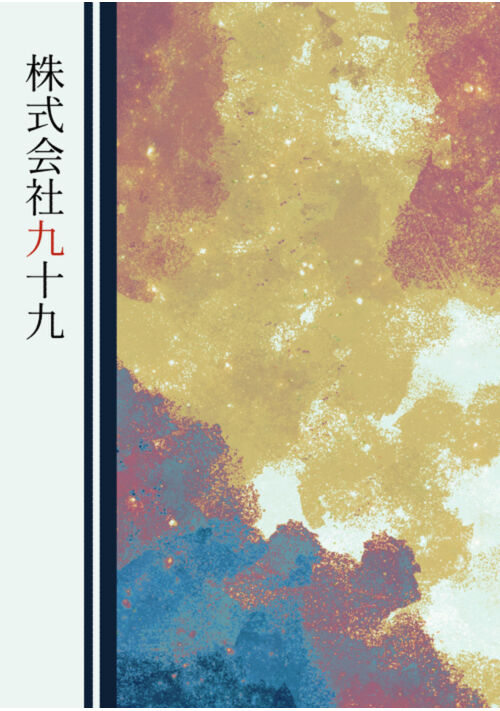
株式会社九十九
煤原
キャラ文芸
呪いに怯える人々が持ち込んだ品々を呪物と呼んで、依頼人から買い取ったり預かったりするのが、この会社の主な仕事内容だ。実際に持ち込まれる物はただの骨董品や古いだけのガラクタであることがほとんどだけれど、会社の倉庫にはそれらの呪物がずらりと並んでいる。本当に呪われているかどうかなんて、依頼人には関係がない。彼らはただ不安なのだ。その不安を手放したいのだ。
これは、人の不安を預かって安心させる仕事だった。
◇ ◆ ◇
ホラー要素と、痛々しい描写を含みます。人面瘡や異食、カニバリズム等が苦手な方はご注意ください。
◇ ◆ ◇
漫画の短編集(https://www.alphapolis.co.jp/manga/173302362/376868016)に4ページほどの小ネタを掲載しています。

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。


怪奇蒐集帳(短編集)
naomikoryo
ホラー
この世には、知ってはいけない話がある。
怪談、都市伝説、語り継がれる呪い——
どれもがただの作り話かもしれない。
だが、それでも時々、**「本物」**が紛れ込むことがある。
本書は、そんな“見つけてしまった”怪異を集めた一冊である。
最後のページを閉じるとき、あなたは“何か”に気づくことになるだろう——。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

【完結】百怪
アンミン
ホラー
【PV数100万突破】
第9回ネット小説大賞、一次選考通過、
第11回ネット小説大賞、一次選考通過、
マンガBANG×エイベックス・ピクチャーズ
第一回WEB小説大賞一次選考通過作品です。
百物語系のお話。
怖くない話の短編がメインです。


意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















