2 / 9
その2
しおりを挟む
◇
猫が見つかった安堵からか、粟島はマシロの家で目覚める前に起きた出来事を思い出した。
しかし獣の姿に関しては、あまりにも非現実的だった。まだ頭が混乱しているのか、はたまた夢と混同しているのか。
「あの、この山で熊って見たことありますか?」
粟島はマシロに訊ねた。猫を土間に戻したマシロは、ここ数年は見ていないと答えた。粟島も、近年ここらで熊が目撃されたという話は聞いていない。そもそもマシロは、粟島が倒れていた付近に獣の形跡はなかったと言っていた。
では、粟島が見たあれはいったいなんだったのか。最有力候補であった熊はマシロの証言で消えた。犬や猪にしては大きすぎる。しかし、山への恐怖が実物以上に獣を大きく見せた可能性も否定はできない。人間の脳というのは案外馬鹿なのだ。
とにかく、本命である猫は無事に見つかった。これで少女の笑顔も戻るだろう。あとは粟島が猫を連れて下山すればいいだけだ。
「ところで、つちのこ……とはどのような生き物なのでしょうか?」
どうやら聞き流してくれたわけではなかったらしい。
マシロは純粋な目を粟島に向けた。茶化しているわけでないことだけはわかったので、粟島はどう伝えたものかと言葉を選ぶ。この歳でツチノコを信じていると思われたくないのが半分、少女の不安を笑われたくないのが半分だ。
「えっと……UMAってわかります?」
「ゆーま?」
「未確認生物っていって……まあ簡単に言えば、実在が確認されてない生き物です」
蛇のような姿で、胴体は太く短い。体長は五十センチ前後で、驚異のジャンプ力を誇る。粟島が知るツチノコはその程度だった。
目撃情報はあるものの、どちらかといえばオカルトに分類され、バラエティで人気を博す架空の生物。子どものころはとてもロマン溢れる存在に思えていたが、発見された時点で“未確認”ではなくなってしまう事実に気付いてからは探すのをやめた。夢は夢のままの方が魅力的だ。
マシロは口元に手を添え、視線を下げる。あれは考えごとをするときの癖なのかもしれない。
「多少形は異なりますが、腕のようなものが生えた個体なら見たことがあります」
「おてて」
思わず漏れた呟きに、粟島は慌てて口を塞いだ。幸いマシロには聞こえていなかったようだ。
「なるほど。あれは今ゆーまと呼ばれているのですね」
マシロは何かに納得した様子だった。粟島は置いてけぼりだ。
粟島が教えたのは一般的なツチノコの形状だけで、少女が見た姿は伝えていない。粟島が寝ている間に、マシロが少女の描いた絵を見た可能性もあるが、あれがツチノコの絵であったと判断するのは難しいだろう。それくらい少女の絵は独特だった。
「ずんぐりとした見た目の割に存外素早く、しかし飛び跳ねるばかりで何かを襲う気配もなかったので後回しにしてしまいました。不徳の致すところです」
粟島は開いた口が塞がらなかった。マシロの態度は真剣そのもので、申し訳なさそうに頭を下げる。自分を助けてくれた親切な人は、案外電波なのかもしれないと失礼なことを考えた。しかしマシロはツチノコを知らなかったのだから、似たような生き物の話をしている可能性もまだあった。腕の生えた蛇の存在を、粟島が知らないだけかもしれないのだ。やたらとデカいトカゲの話をしている可能性だって捨てきれない。
「粟島さんの目的は猫の捜索とつちのこの退治、でしたよね?」
マシロの問いに、粟島は頷いた。単純に声が出せなかった。
「つちのこの件は、どうか私にお任せください。主な出没地点はすでに把握しております」
マシロは立ち上がって、部屋の隅に置かれていた細長い包みを取り出した。布の中から現れたのはずいぶんと古い単発銃だ。マシロはそのまま板戸を開けて出て行こうとする。
「ま、待って!」
粟島は慌てて引き留めた。マシロは立ち止まって振り返る。
「俺も、行きます」
これは粟島が受けた依頼だ。ならば最後まで粟島がやらねばならない。
マシロは困ったように眉を下げた。粟島は今、足に怪我を負っている。粟島とてこの状態で山を歩き回れるとは思っていなかった。
「昨日今日会ったばかりの私を信用できないのはもっともです。けれど今の貴方は……」
「違……っ、そうじゃなくて」
粟島は必死になって頭を回した。とにかく今はこの電波なのか天然なのかわからない命の恩人を止めねばならない。今の時期は狩猟期間外だし、ツチノコの駆除なんてどこになんの申請を出せばいいのかもわからない。いや、そもそも未確認生物は保護法で守られてはいないのではないか。そうでなくてもトカゲに銃はやりすぎだろう。そういえば猪や粟島に振る舞われた鹿は彼が仕留めたものなのだろうか。あの鹿おいしかったな。違う、そうじゃない。思考がぐるぐる回ってまとまらない。
何かないかと辺りを見回す。少女と猫の写真が目に入った。粟島は写真を手に取りマシロの前にかざす。
「一応、仕事なので! 報告義務があるんです。もし貴方に仕留めてもらうとしても、俺も、同行したい、な……と」
義務、あるかなぁ。粟島は遠い目をした。そもそもツチノコの退治をどう証明すればいいのだろう。
粟島の言い分に納得したのか、マシロは銃を戻し、再び粟島の前に座った。
「承知いたしました。しかし、つちのこ退治は貴方の傷が治ってからにいたしましょう。それまでは監視に留めます」
やはりマシロは真剣そのものだった。粟島の話に悪ノリしているようには見えない。これが演技なら、きっといい役者になれる。
なんというか、どっと疲れた。粟島は布団に倒れ込む。
いつまでも他人の家の布団を占領しているのも悪いからと、粟島は朝食前に一度布団を畳んだのだが、マシロは安静を言い渡して再び粟島を布団に押し込んだ。でも、と食い下がる粟島に対して、マシロはまるで赤子にするように粟島をあやし始めたものだから、粟島はいろいろと諦めて今に至る。
急ぎの予定がないのであれば好きなだけここで療養すればいいと、マシロは言った。どこまでが社交辞令なのか判断しかねたが、足が痛むのも事実なので、厚かましくはあるがせめて昼くらいまでは世話になろうと思った。
「……あの熊みたいな犬も、俺の幻覚かなぁ……」
粟島はぽつりと呟いた。
人の脳は騙されやすい。ほんの些細なエラーでまぼろしを見るのだ。ストレスや恐怖は視覚的錯覚を引き起こしやすいと聞く。ツチノコなんて話を聞いて、少なからず期待や不安があったのかもしれない。きっと茂みや木立ちを獣と見間違えたのだ。たしかそういう専門用語があった気がする。パレイドリア現象とか。
「……今、なんとおっしゃいましたか?」
視線を上げれば、マシロが目を見開いて粟島を見ていた。どうやら今度の独り言は聞かれていたらしい。
「あ、すみません。たぶん俺の気のせいなんで、気にしないで……」
「他に特徴は?」
「えっと、他……?」
マシロは栗島の話を遮って、ずいと身を乗り出した。
「先程熊について訊ねられた際に気付くべきでした」
マシロは自身の失態を嘆く。粟島の体には、滑落によって負った傷以外見当たらなかった。それ故考えが及ばなかったのだと。
粟島が見た獣について、マシロは何か知っているのかもしれなかった。ここまでくれば今更恥も外聞もない。粟島は自身が足を滑らせた原因について話した。
マシロは神妙な顔で粟島の話を聞き終えると、何やら支度を始めた。
「事情が変わりました。申し訳ありませんが、下山の準備を」
土間の猫を抱き上げて、粟島の荷物もまとめて背負う。
「貴方の傷が癒えるまでには終わらせます」
何をだ。
ぽかんとマシロを見上げる粟島に対して、マシロは「気が利かずに申し訳ありません」と手を差し出した。
「ご安心ください。貴方を背負って山を降りる程度であれば可能です」
「いえ、ダイジョウブ。自分で歩けます」
粟島は急いで立ち上がった。事態はまったく飲み込めていないが、ここで時間をかけては成人男性のプライド的によろしくないことが起きそうな気がした。山で足を滑らせ遭難した時点でもはや手遅れではあるのだが。
マシロが布団を畳んで端に寄せる。そこで粟島はようやく気付いた。
この家に、布団は一組しかなかった。
◇
マシロは長年この山住んでいるらしく、粟島の足でも帰れそうな道を教えてくれた。いつか使うかもしれないと自作していた簡易の松葉杖を粟島に持たせ、そのうえ麓まで送ってくれる親切振りである。足が治ったら必ず礼をしに来ようと粟島は誓った。
「すみません、荷物全部持っていただいて……」
「いえ。急かしてしまったのは私ですから」
マシロは粟島の荷物と猫を抱え、粟島を気遣いながら山道を歩いていく。粟島が僅かによろめくたびに、マシロは「抱えましょうか?」と提案してきた。もちろん粟島は断った。
マシロに案内されたのは、これまで粟島が山に入った中で、一番明るい道だった。歩きやすいく、かつ植生が損なわれないよう適度に草木が払われている。よく整備されているが、道標の類いは見当たらなかった。
「貴方が見たのは、かつて麓の村人が『物怪』と呼んだものかと」
「もののけ?」
下山しながら、マシロは粟島が見た獣について説明しはじめた。
「呼び方にさほど意味はありません。つちのこでも、ゆーまでも、妖怪でも。名は形を与えるものですが、どのように呼ばれようと“あれ”の本質が変わることはありませんでした」
その昔、山の麓にあったのがまだ小さな集落だったころ。村人たちはこの山そのものを神として崇めていた。山で獲れるものはそのすべてが神から与えられた恵みであり、村人たちは感謝と畏怖の念を心に留め、山を敬い大切に守ってきた。
しかし、ある日を境に村人の態度は一変する。山に入った村の男が、化け物を見たと言ったのだ。
それはゆうに一丈(約三メートル)を超える大きさで、闇夜でも赤々と燃えるような目はしっかりと村人を捉えていた。大きなかぎ爪、立派な牙、毛皮に覆われてさえそうとわかる筋肉質な大柄の体躯。どれを取っても人間が敵うような相手ではなかった。
山の神が怒っているのだと、村人たちは考えた。あの化け物は、神の怒りの姿だと。
そうして村人たちは、山の頂上に神の世話係を置くことにした。神を宥め、その怒りを鎮めることが世話係の役目だった。
「世話係とはいっても、村人が山頂に住み、物怪が村を襲う前に仕留めるのがその仕事でした」
マシロが指差した先を見れば、木々の隙間から山頂が見えた。
「故に村の若い男が選ばれ、十年に一度交代の儀が執り行われました」
「十年って、その間ずっと一人で山頂に住むんですか?」
「神を生活の第一に置くため、人との交流は最小限に留めるしきたりであったと聞いています」
村のためとはいえ、十年も一人で孤独な生活を送るなど、粟島には想像もできなかった。
マシロの話を聞く限り、世話係は山の獣を駆除する猟師であったのだろう。最低限の交流は、麓の村人や商人から衣服や薬をもらうために許されていた。その際も、あまり言葉を交わしてはならない決まりであったらしい。
二年ほど前にこの町に越してきたばかりの粟島は、まだこの土地の伝承や風習に疎かった。昔話や言い伝えを好んで話す老人たちからも、そんな話は聞いたことがない。
「儀式を行っていた村は飢饉で滅んだと聞いております。現在麓にお住まいの方々がご存知ないのも、無理のない話かと」
そう話すマシロは、少し寂しそうな、それでいて安心したような顔をしていた。出会ったばかりの粟島には、その心情を推しはかることはできない。
「今回、猫や貴方に傷を負わせてしまったことは、まこと私の不徳の致すところです」
あ、なんかちょっと話が戻ってきた気がする。
「あの大柄の物怪は、何故かぬかるみにさえ足跡を残さないのです」
これまで、粟島が見た獣──マシロが言うには物怪──が山奥から出てくることはなかったらしい。凶暴ではあるが人間が縄張りに侵入してこない限り、あの獣から手を出したことはなかったのだという。
しかし粟島が獣に遭遇したのは、ほとんど山の入り口と言ってもいい場所だった。
町でも毎年、春先にはタケノコを取りに山へ入る人もいる。粟島も誘われてついていったことがあった。それほど知名度も人気もあるとは言えないものの、ときどき登山客も来る。あまり整備はされずとも人の出入りはそれなりにあった。ウワサ程度であろうと化け物を見たという話が出たことはない。
物怪かどうかは置いておくとして、本当に獣がいるなら役所に連絡するべきだ。
「七日……いえ、三日で仕留めます」
どう答えるのが正解か、粟島にはわからなかった。彼が害獣駆除の許可をもらっているのなら、わざわざ粟島が気を揉む必要はないのかもしれない。とりあえず今は当たり障りのないことを言っておくことにした。
「えっと……無理はしないでくださいね?」
その言葉に、マシロは足を止めた。目を瞠って粟島を見る。
ふと、大学時代の友人の顔が脳裏をよぎった。少々過激なその友人は、酒の席であったとはいえ「侮辱には血をもって償わせる!」などと物騒なことを叫んでいた。本当に物騒だが彼の専門が神話研究であったため、まあそういうこともあるだろうとその場にいた誰もが聞き流した。もちろん彼は今も元気に資料を睨みつけ研究に勤しんでいる。酒癖の悪さだけが彼の欠点だった。
侮辱とまではいかずとも、マシロもまた猟師であったなら、今の発言は失礼に当たるのだろうか。粟島はおそるおそるマシロの顔色をうかがった。
「お気遣い痛み入ります」
マシロはふっと笑って、再び歩き始めた。粟島は何も言わずについていく。
マシロは、一人でこの山に住んでいるのだろうか。先程聞いた昔話の猟師のように。
聞きたいことはたくさんあった。けれど聞いてしまえばもう後戻りはできないと、頭の中で警鐘が鳴り響く。
「近ごろは物怪の発生も少なく、その気性も穏やかなものばかりでした。人どころか木の根を齧ることもなく、草花の上で午睡を楽しむ姿は微笑ましくさえありました」
マシロは口元をゆるめて、そっと猫を撫でた。猫は気持ちよさそうに喉を鳴らす。どこか浮世離れした雰囲気はあるものの、やはりマシロは善良な人間なのだと思う。
粟島はオカルトや超常現象の類いを信じてはいなかった。
サンタクロースが実在しないことは、その存在を教えられた日に知った。粟島家にサンタがやってきたことはない。そういう教育方針だった。
だからといって人の夢を壊すようなことはしたくないし、個人的に信じるぶんには良い趣味だとも思っている。粟島だって、いまだUMAにロマンを感じているのだ。もちろん、きちんと現実と区別したえ上での話ではあるが。
果たしてマシロのそれが信仰であるのか趣味であるのか、粟島には判断できなかった。
◇
歩き続けていると、鳥のさえずりの他に、車の走行音が聞こえてきた。どうやら出口が近いらしい。
マシロは立ち止まって、持っていた荷物や猫を粟島に手渡した。
「申し訳ありませんが、ここから先はお一人でお願いいたします」
マシロは明るく日が差し込む山道の入り口を指し示す。粟島はそれを目で追った。
「どうか迷わずお進みください」
礼を言おうと粟島が振り返った先に、マシロの姿はなかった。ざあっと風が通り過ぎて、木々を揺らしていく。
「……マシロさん?」
にゃおん、と猫が鳴いた。それ以外、粟島の声に応えるものはなかった。
猫が見つかった安堵からか、粟島はマシロの家で目覚める前に起きた出来事を思い出した。
しかし獣の姿に関しては、あまりにも非現実的だった。まだ頭が混乱しているのか、はたまた夢と混同しているのか。
「あの、この山で熊って見たことありますか?」
粟島はマシロに訊ねた。猫を土間に戻したマシロは、ここ数年は見ていないと答えた。粟島も、近年ここらで熊が目撃されたという話は聞いていない。そもそもマシロは、粟島が倒れていた付近に獣の形跡はなかったと言っていた。
では、粟島が見たあれはいったいなんだったのか。最有力候補であった熊はマシロの証言で消えた。犬や猪にしては大きすぎる。しかし、山への恐怖が実物以上に獣を大きく見せた可能性も否定はできない。人間の脳というのは案外馬鹿なのだ。
とにかく、本命である猫は無事に見つかった。これで少女の笑顔も戻るだろう。あとは粟島が猫を連れて下山すればいいだけだ。
「ところで、つちのこ……とはどのような生き物なのでしょうか?」
どうやら聞き流してくれたわけではなかったらしい。
マシロは純粋な目を粟島に向けた。茶化しているわけでないことだけはわかったので、粟島はどう伝えたものかと言葉を選ぶ。この歳でツチノコを信じていると思われたくないのが半分、少女の不安を笑われたくないのが半分だ。
「えっと……UMAってわかります?」
「ゆーま?」
「未確認生物っていって……まあ簡単に言えば、実在が確認されてない生き物です」
蛇のような姿で、胴体は太く短い。体長は五十センチ前後で、驚異のジャンプ力を誇る。粟島が知るツチノコはその程度だった。
目撃情報はあるものの、どちらかといえばオカルトに分類され、バラエティで人気を博す架空の生物。子どものころはとてもロマン溢れる存在に思えていたが、発見された時点で“未確認”ではなくなってしまう事実に気付いてからは探すのをやめた。夢は夢のままの方が魅力的だ。
マシロは口元に手を添え、視線を下げる。あれは考えごとをするときの癖なのかもしれない。
「多少形は異なりますが、腕のようなものが生えた個体なら見たことがあります」
「おてて」
思わず漏れた呟きに、粟島は慌てて口を塞いだ。幸いマシロには聞こえていなかったようだ。
「なるほど。あれは今ゆーまと呼ばれているのですね」
マシロは何かに納得した様子だった。粟島は置いてけぼりだ。
粟島が教えたのは一般的なツチノコの形状だけで、少女が見た姿は伝えていない。粟島が寝ている間に、マシロが少女の描いた絵を見た可能性もあるが、あれがツチノコの絵であったと判断するのは難しいだろう。それくらい少女の絵は独特だった。
「ずんぐりとした見た目の割に存外素早く、しかし飛び跳ねるばかりで何かを襲う気配もなかったので後回しにしてしまいました。不徳の致すところです」
粟島は開いた口が塞がらなかった。マシロの態度は真剣そのもので、申し訳なさそうに頭を下げる。自分を助けてくれた親切な人は、案外電波なのかもしれないと失礼なことを考えた。しかしマシロはツチノコを知らなかったのだから、似たような生き物の話をしている可能性もまだあった。腕の生えた蛇の存在を、粟島が知らないだけかもしれないのだ。やたらとデカいトカゲの話をしている可能性だって捨てきれない。
「粟島さんの目的は猫の捜索とつちのこの退治、でしたよね?」
マシロの問いに、粟島は頷いた。単純に声が出せなかった。
「つちのこの件は、どうか私にお任せください。主な出没地点はすでに把握しております」
マシロは立ち上がって、部屋の隅に置かれていた細長い包みを取り出した。布の中から現れたのはずいぶんと古い単発銃だ。マシロはそのまま板戸を開けて出て行こうとする。
「ま、待って!」
粟島は慌てて引き留めた。マシロは立ち止まって振り返る。
「俺も、行きます」
これは粟島が受けた依頼だ。ならば最後まで粟島がやらねばならない。
マシロは困ったように眉を下げた。粟島は今、足に怪我を負っている。粟島とてこの状態で山を歩き回れるとは思っていなかった。
「昨日今日会ったばかりの私を信用できないのはもっともです。けれど今の貴方は……」
「違……っ、そうじゃなくて」
粟島は必死になって頭を回した。とにかく今はこの電波なのか天然なのかわからない命の恩人を止めねばならない。今の時期は狩猟期間外だし、ツチノコの駆除なんてどこになんの申請を出せばいいのかもわからない。いや、そもそも未確認生物は保護法で守られてはいないのではないか。そうでなくてもトカゲに銃はやりすぎだろう。そういえば猪や粟島に振る舞われた鹿は彼が仕留めたものなのだろうか。あの鹿おいしかったな。違う、そうじゃない。思考がぐるぐる回ってまとまらない。
何かないかと辺りを見回す。少女と猫の写真が目に入った。粟島は写真を手に取りマシロの前にかざす。
「一応、仕事なので! 報告義務があるんです。もし貴方に仕留めてもらうとしても、俺も、同行したい、な……と」
義務、あるかなぁ。粟島は遠い目をした。そもそもツチノコの退治をどう証明すればいいのだろう。
粟島の言い分に納得したのか、マシロは銃を戻し、再び粟島の前に座った。
「承知いたしました。しかし、つちのこ退治は貴方の傷が治ってからにいたしましょう。それまでは監視に留めます」
やはりマシロは真剣そのものだった。粟島の話に悪ノリしているようには見えない。これが演技なら、きっといい役者になれる。
なんというか、どっと疲れた。粟島は布団に倒れ込む。
いつまでも他人の家の布団を占領しているのも悪いからと、粟島は朝食前に一度布団を畳んだのだが、マシロは安静を言い渡して再び粟島を布団に押し込んだ。でも、と食い下がる粟島に対して、マシロはまるで赤子にするように粟島をあやし始めたものだから、粟島はいろいろと諦めて今に至る。
急ぎの予定がないのであれば好きなだけここで療養すればいいと、マシロは言った。どこまでが社交辞令なのか判断しかねたが、足が痛むのも事実なので、厚かましくはあるがせめて昼くらいまでは世話になろうと思った。
「……あの熊みたいな犬も、俺の幻覚かなぁ……」
粟島はぽつりと呟いた。
人の脳は騙されやすい。ほんの些細なエラーでまぼろしを見るのだ。ストレスや恐怖は視覚的錯覚を引き起こしやすいと聞く。ツチノコなんて話を聞いて、少なからず期待や不安があったのかもしれない。きっと茂みや木立ちを獣と見間違えたのだ。たしかそういう専門用語があった気がする。パレイドリア現象とか。
「……今、なんとおっしゃいましたか?」
視線を上げれば、マシロが目を見開いて粟島を見ていた。どうやら今度の独り言は聞かれていたらしい。
「あ、すみません。たぶん俺の気のせいなんで、気にしないで……」
「他に特徴は?」
「えっと、他……?」
マシロは栗島の話を遮って、ずいと身を乗り出した。
「先程熊について訊ねられた際に気付くべきでした」
マシロは自身の失態を嘆く。粟島の体には、滑落によって負った傷以外見当たらなかった。それ故考えが及ばなかったのだと。
粟島が見た獣について、マシロは何か知っているのかもしれなかった。ここまでくれば今更恥も外聞もない。粟島は自身が足を滑らせた原因について話した。
マシロは神妙な顔で粟島の話を聞き終えると、何やら支度を始めた。
「事情が変わりました。申し訳ありませんが、下山の準備を」
土間の猫を抱き上げて、粟島の荷物もまとめて背負う。
「貴方の傷が癒えるまでには終わらせます」
何をだ。
ぽかんとマシロを見上げる粟島に対して、マシロは「気が利かずに申し訳ありません」と手を差し出した。
「ご安心ください。貴方を背負って山を降りる程度であれば可能です」
「いえ、ダイジョウブ。自分で歩けます」
粟島は急いで立ち上がった。事態はまったく飲み込めていないが、ここで時間をかけては成人男性のプライド的によろしくないことが起きそうな気がした。山で足を滑らせ遭難した時点でもはや手遅れではあるのだが。
マシロが布団を畳んで端に寄せる。そこで粟島はようやく気付いた。
この家に、布団は一組しかなかった。
◇
マシロは長年この山住んでいるらしく、粟島の足でも帰れそうな道を教えてくれた。いつか使うかもしれないと自作していた簡易の松葉杖を粟島に持たせ、そのうえ麓まで送ってくれる親切振りである。足が治ったら必ず礼をしに来ようと粟島は誓った。
「すみません、荷物全部持っていただいて……」
「いえ。急かしてしまったのは私ですから」
マシロは粟島の荷物と猫を抱え、粟島を気遣いながら山道を歩いていく。粟島が僅かによろめくたびに、マシロは「抱えましょうか?」と提案してきた。もちろん粟島は断った。
マシロに案内されたのは、これまで粟島が山に入った中で、一番明るい道だった。歩きやすいく、かつ植生が損なわれないよう適度に草木が払われている。よく整備されているが、道標の類いは見当たらなかった。
「貴方が見たのは、かつて麓の村人が『物怪』と呼んだものかと」
「もののけ?」
下山しながら、マシロは粟島が見た獣について説明しはじめた。
「呼び方にさほど意味はありません。つちのこでも、ゆーまでも、妖怪でも。名は形を与えるものですが、どのように呼ばれようと“あれ”の本質が変わることはありませんでした」
その昔、山の麓にあったのがまだ小さな集落だったころ。村人たちはこの山そのものを神として崇めていた。山で獲れるものはそのすべてが神から与えられた恵みであり、村人たちは感謝と畏怖の念を心に留め、山を敬い大切に守ってきた。
しかし、ある日を境に村人の態度は一変する。山に入った村の男が、化け物を見たと言ったのだ。
それはゆうに一丈(約三メートル)を超える大きさで、闇夜でも赤々と燃えるような目はしっかりと村人を捉えていた。大きなかぎ爪、立派な牙、毛皮に覆われてさえそうとわかる筋肉質な大柄の体躯。どれを取っても人間が敵うような相手ではなかった。
山の神が怒っているのだと、村人たちは考えた。あの化け物は、神の怒りの姿だと。
そうして村人たちは、山の頂上に神の世話係を置くことにした。神を宥め、その怒りを鎮めることが世話係の役目だった。
「世話係とはいっても、村人が山頂に住み、物怪が村を襲う前に仕留めるのがその仕事でした」
マシロが指差した先を見れば、木々の隙間から山頂が見えた。
「故に村の若い男が選ばれ、十年に一度交代の儀が執り行われました」
「十年って、その間ずっと一人で山頂に住むんですか?」
「神を生活の第一に置くため、人との交流は最小限に留めるしきたりであったと聞いています」
村のためとはいえ、十年も一人で孤独な生活を送るなど、粟島には想像もできなかった。
マシロの話を聞く限り、世話係は山の獣を駆除する猟師であったのだろう。最低限の交流は、麓の村人や商人から衣服や薬をもらうために許されていた。その際も、あまり言葉を交わしてはならない決まりであったらしい。
二年ほど前にこの町に越してきたばかりの粟島は、まだこの土地の伝承や風習に疎かった。昔話や言い伝えを好んで話す老人たちからも、そんな話は聞いたことがない。
「儀式を行っていた村は飢饉で滅んだと聞いております。現在麓にお住まいの方々がご存知ないのも、無理のない話かと」
そう話すマシロは、少し寂しそうな、それでいて安心したような顔をしていた。出会ったばかりの粟島には、その心情を推しはかることはできない。
「今回、猫や貴方に傷を負わせてしまったことは、まこと私の不徳の致すところです」
あ、なんかちょっと話が戻ってきた気がする。
「あの大柄の物怪は、何故かぬかるみにさえ足跡を残さないのです」
これまで、粟島が見た獣──マシロが言うには物怪──が山奥から出てくることはなかったらしい。凶暴ではあるが人間が縄張りに侵入してこない限り、あの獣から手を出したことはなかったのだという。
しかし粟島が獣に遭遇したのは、ほとんど山の入り口と言ってもいい場所だった。
町でも毎年、春先にはタケノコを取りに山へ入る人もいる。粟島も誘われてついていったことがあった。それほど知名度も人気もあるとは言えないものの、ときどき登山客も来る。あまり整備はされずとも人の出入りはそれなりにあった。ウワサ程度であろうと化け物を見たという話が出たことはない。
物怪かどうかは置いておくとして、本当に獣がいるなら役所に連絡するべきだ。
「七日……いえ、三日で仕留めます」
どう答えるのが正解か、粟島にはわからなかった。彼が害獣駆除の許可をもらっているのなら、わざわざ粟島が気を揉む必要はないのかもしれない。とりあえず今は当たり障りのないことを言っておくことにした。
「えっと……無理はしないでくださいね?」
その言葉に、マシロは足を止めた。目を瞠って粟島を見る。
ふと、大学時代の友人の顔が脳裏をよぎった。少々過激なその友人は、酒の席であったとはいえ「侮辱には血をもって償わせる!」などと物騒なことを叫んでいた。本当に物騒だが彼の専門が神話研究であったため、まあそういうこともあるだろうとその場にいた誰もが聞き流した。もちろん彼は今も元気に資料を睨みつけ研究に勤しんでいる。酒癖の悪さだけが彼の欠点だった。
侮辱とまではいかずとも、マシロもまた猟師であったなら、今の発言は失礼に当たるのだろうか。粟島はおそるおそるマシロの顔色をうかがった。
「お気遣い痛み入ります」
マシロはふっと笑って、再び歩き始めた。粟島は何も言わずについていく。
マシロは、一人でこの山に住んでいるのだろうか。先程聞いた昔話の猟師のように。
聞きたいことはたくさんあった。けれど聞いてしまえばもう後戻りはできないと、頭の中で警鐘が鳴り響く。
「近ごろは物怪の発生も少なく、その気性も穏やかなものばかりでした。人どころか木の根を齧ることもなく、草花の上で午睡を楽しむ姿は微笑ましくさえありました」
マシロは口元をゆるめて、そっと猫を撫でた。猫は気持ちよさそうに喉を鳴らす。どこか浮世離れした雰囲気はあるものの、やはりマシロは善良な人間なのだと思う。
粟島はオカルトや超常現象の類いを信じてはいなかった。
サンタクロースが実在しないことは、その存在を教えられた日に知った。粟島家にサンタがやってきたことはない。そういう教育方針だった。
だからといって人の夢を壊すようなことはしたくないし、個人的に信じるぶんには良い趣味だとも思っている。粟島だって、いまだUMAにロマンを感じているのだ。もちろん、きちんと現実と区別したえ上での話ではあるが。
果たしてマシロのそれが信仰であるのか趣味であるのか、粟島には判断できなかった。
◇
歩き続けていると、鳥のさえずりの他に、車の走行音が聞こえてきた。どうやら出口が近いらしい。
マシロは立ち止まって、持っていた荷物や猫を粟島に手渡した。
「申し訳ありませんが、ここから先はお一人でお願いいたします」
マシロは明るく日が差し込む山道の入り口を指し示す。粟島はそれを目で追った。
「どうか迷わずお進みください」
礼を言おうと粟島が振り返った先に、マシロの姿はなかった。ざあっと風が通り過ぎて、木々を揺らしていく。
「……マシロさん?」
にゃおん、と猫が鳴いた。それ以外、粟島の声に応えるものはなかった。
1
あなたにおすすめの小説
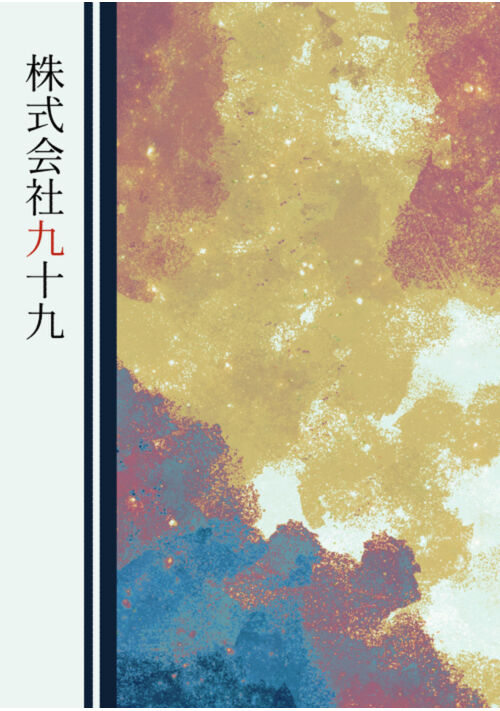
株式会社九十九
煤原
キャラ文芸
呪いに怯える人々が持ち込んだ品々を呪物と呼んで、依頼人から買い取ったり預かったりするのが、この会社の主な仕事内容だ。実際に持ち込まれる物はただの骨董品や古いだけのガラクタであることがほとんどだけれど、会社の倉庫にはそれらの呪物がずらりと並んでいる。本当に呪われているかどうかなんて、依頼人には関係がない。彼らはただ不安なのだ。その不安を手放したいのだ。
これは、人の不安を預かって安心させる仕事だった。
◇ ◆ ◇
ホラー要素と、痛々しい描写を含みます。人面瘡や異食、カニバリズム等が苦手な方はご注意ください。
◇ ◆ ◇
漫画の短編集(https://www.alphapolis.co.jp/manga/173302362/376868016)に4ページほどの小ネタを掲載しています。

怪奇蒐集帳(短編集)
naomikoryo
ホラー
この世には、知ってはいけない話がある。
怪談、都市伝説、語り継がれる呪い——
どれもがただの作り話かもしれない。
だが、それでも時々、**「本物」**が紛れ込むことがある。
本書は、そんな“見つけてしまった”怪異を集めた一冊である。
最後のページを閉じるとき、あなたは“何か”に気づくことになるだろう——。


彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

視える僕らのシェアハウス
橘しづき
ホラー
安藤花音は、ごく普通のOLだった。だが25歳の誕生日を境に、急におかしなものが見え始める。
電車に飛び込んでバラバラになる男性、やせ細った子供の姿、どれもこの世のものではない者たち。家の中にまで入ってくるそれらに、花音は仕事にも行けず追い詰められていた。
ある日、駅のホームで電車を待っていると、霊に引き込まれそうになってしまう。そこを、見知らぬ男性が間一髪で救ってくれる。彼は花音の話を聞いて名刺を一枚手渡す。
『月乃庭 管理人 竜崎奏多』
不思議なルームシェアが、始まる。

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド
まみ夜
ホラー
ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。
事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。
一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。
その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。
そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。
ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。
そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。
第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。
表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















