4 / 9
その4
しおりを挟む◇
「粗茶ですが」
ドラマでは聞いたことのある表現だったが、実際に聞くのは初めてだった。
「ありがとうございます」
湯呑みからゆらゆらと湯気がのぼり、琥珀色の水面が揺れる。以前世話になったときにも出されたお茶だ。香ばしい香りとすっきりとした味わいで、粟島でも飲みやすいと思ったお茶だった。
「開けても?」
どうぞと粟島が答えると、マシロは丁寧に菓子折りの包みを開けていく。
マシロの好みを聞きそびれた粟島が用意したのは、和三盆と金平糖の詰め合わせだった。マシロの装いから、なんとなく和風の物がいいだろうという安直な考えと、甘党の粟島が選んだ結果だ。
「ずいぶんとかわいらしい見た目のお菓子ですね」
色とりどりの金平糖は丸い小瓶に詰められている。和三盆は季節の花々をかたどったもので、見た目にも華やかだ。
マシロは小瓶に詰められた金平糖を手に取って眺めた。陽に透かせばきらきらと光るそれはマシロの目を楽しませる。
「気に入ってもらえてよかったです」
マシロの様子に、粟島はほっと胸を撫で下ろした。粟島には信じられないことだが、この世には甘いものが苦手な人も存在するのだ。マシロがそうかもしれない可能性を考慮していなかったことに気付いたのは、菓子折りをリュックから取り出した後だった。
「こちらはそのまま食してもよろしいのですか?」
「はい。お茶請けにもちょうどいいですけど、俺はそのまま食べるのも好きです」
マシロは小瓶の蓋を開け、金平糖を一粒取り出した。しばらく眺めたあと、淡い色合いの星がマシロの口に消えていく。それから少しの間をおいて、マシロの顔がぱっと明るくなった。
「甘い……」
マシロは目を輝かせて金平糖の小瓶を見た。それから和三盆に伸ばしかけた手を一度引っ込めて、申し訳さなそうな顔を粟島に向ける。
「こんぺいとう、でしたか? こんな貴重な物、私がいただいてもよろしいのでしょうか?」
「……? はい。全部マシロさんの分です」
よくわからない聞き方だった。粟島が用意したのはよくある贈答用の菓子で、スーパーで買うよりは少々お高い程度の物だ。特別高級な品ではない。
菓子といえば基本甘いものを指す言葉だと思っていたが、それは粟島が甘党だからであって、全人類共通の認識ではない。サルミアッキだって菓子なのだ。どうもマシロは金平糖を知らなかったようだし、見た目からアラレのようなものだと思っていたのかもしれない。遠回しに甘いものが苦手だと言われている可能性も否定できなかった。しかし直前の反応を見る限りは、甘味が嫌いなわけではないはずだ。さきほどの地図もそうだったが、マシロは自分が珍しいと思った物はなかなか受け取ってくれないらしい。
粟島としては、マシロが甘味好きであってくれたらうれしいな、と思う。同性で甘いものの話ができる人は貴重だった。
とりあえず自分の願望は置いておいて、いったいどう言えばマシロに気を遣わせずに済むだろうか。
「えっと……金平糖も和三盆も甘いお菓子なんですけど、マシロさんは甘いの大丈夫ですか?」
「……そう、ですね。甘いものは、好きです」
マシロは和三盆に視線をやった。その控えめでやさしい上品な甘さは、マシロによく似合うだろうと思った。
もしかすると、山暮らしでは砂糖が貴重品なのかもしれない。山でも甘味は味わえるだろうが、砂糖の甘さはハチミツや木の実とはおもむきが異なる。
マシロがここでどのような生活を送っているのか、粟島は知らない。見た限り、この家には電気も水道も通ってはいなさそうなのだ。お茶を淹れてくれたときも、水は家の外から持ってきていた。ずいぶんと古風な生き方をしていることは間違いないだろう。
粟島にとっても、砂糖は貴重だと考えたのだろうか。
今思えば、あの日粟島に振る舞われた鹿肉だって、マシロにとっては貴重な食料だったはずだ。マシロは罠の見回りの際に粟島を見つけたと言っていた。罠猟は毎日確認して回らなければならないが、毎日確実に獲物が掛かるわけではない。
「貴方へのお礼に持ってきたんです。受けた恩に比べたら、全然足りないんですけど」
マシロは手元の菓子を見つめて、そっと粟島をうかがった。きっと粟島より年下だろうに、粟島よりずっと大人びていた彼が見せた幼さの滲む顔に、ふっと笑みがこぼれる。マシロのために用意したものだ。マシロが喜んでくれるなら、持ってきた甲斐がある。
「お口に合いました?」
「……はい。とても、おいしいです」
マシロは視線を下げて、きゅっと小瓶を握り込んだ。なんとか受け取ってもらえたようだ。
「あの、よければ粟島さんも、ご一緒にいかがですか? 一人で食べるのは、その……もったいなくて」
マシロは小瓶の蓋を開け、粟島に向かって傾ける。中で金平糖がころりと転がった。
粟島は馬鹿みたいに甘いチョコレートが一等好きだが、ラムネのような素朴な甘さも好きだった。これが『命の恩人に対するお礼の品』でなければ喜んで手を出していただろう。あと相手が年上だったら。
いろいろ考えて、粟島も一緒に食べることにした。マシロが地図のときと同じように笑ったので、きっとこの選択は正解だったのだと思う。
しばらくは他愛もない話をしながらお茶を楽しんだ。本当に取るに足りないような話でも、マシロは楽しそうに聞いてくれた。
「それで、俺は日本酒とチョコの組み合わせが好きなんですけど、そのとき賛同してくれる人は一人もいなかったんですよね」
マシロが口を挟むのは、知らない単語が出てきたときくらいだった。気付けば粟島ばかりが話していて、しまいには愚痴をこぼしていた。
「俺の知り合いは辛党の方が多くて。金平糖でさえ甘くて無理って言うんですよ」
だからといって甘さ控えめのものを用意しても、今度は刺激が足りないのか、やはり反応は悪かった。嗜好は人それぞれなので無理強いするつもりはないが、騙し討ちのようにキャロライナ・リーパーを食べさせてきた友人の口には輸入チョコをねじ込んだ。
「あ、金平糖が甘すぎるんだったら、次はお茶に入れてみるのもいいかもしれないですね。俺はやったことないんですけど、紅茶に溶かして飲む人もいるらしいし」
「紅茶、ですか?」
マシロが久方振りに口を開く。
粟島にとって紅茶というのは、ダージリンだとかアールグレイだとかいう横文字の名前がついた外国のお茶だった。きっとマシロには馴染みがないのだろう。粟島は紅茶を説明しようとして、UMAのとき以上に困った。まったくもって紅茶に対する知識がない。
どうしたものかと思案する粟島をよそに、「少々お待ちください」と言ってマシロは立ち上がると戸棚を開け、茶筒を取り出した。茶器を用意し、土間におりて湯を沸かす。
見ているぶんには憧れるが、現代の便利さに慣れた粟島にこの生活は送れそうにない。やはり台所はシステムキッチンにするしかなさそうだ。
そんなことを考えている間に、マシロは茶器を持って戻ってきた。
「粟島さんがご存知のものとは異なるかもしれませんが」
ことりと目の前に置かれたお茶は、さきほどとは違い透き通った紅色をしていた。いかにも紅茶といえば、といった色合いだ。日本茶しかなさそうな家で紅茶を出されるとは思ってもみなかった。なによりマシロが紅茶を知っていることが意外だった。
さて、どうしたものだろう。粟島は渋みのある飲み物が苦手だった。紅茶はもちろん、緑茶にさえこっそりと加糖して飲んでいたくらいだ。金平糖を溶かす話から出されたものだが、やはり最初はストレートで飲むのが礼儀だろうか。
粟島はためらいながら湯呑みに手を伸ばす。思っていたほど熱くはなかった。
まずはひと口。それから加糖。粟島はそっと紅茶に口をつける。
「……おいしい」
優しい香りに、渋みは少なくすっきりとした後味で、ほのかに甘みがある。粟島がこれまでに飲んだ紅茶とは異なるものだった。
マシロは自身の湯呑みに金平糖をぽちゃりと落とし、箸をマドラー代わりにしてかき混ぜた。
「ああ。たしかに、これはいいですね」
粟島も同じように金平糖を入れる。ひと口啜れば、紅茶の香りと金平糖の甘さが口いっぱいに広がった。金平糖はじわじわとゆっくり溶けて、時間と共に味も変化していく。
たしかにいい。とてもいい。だがストレートも悪くなかった。
「すごくおいしいです。飲みやすいし、これ、なんて名前の紅茶ですか?」
「裏の庭で栽培したものです」
「ウラノニワ?」
言葉の意味を理解するのに数秒かかった。お茶って自作できるんだ。
「何年か前に、苗木を譲り受けまして。お茶の苗としか聞いていなかったので、品種まではわかりません」
マシロは懐かしむように目を閉じた。
「発酵の度合いによって味が変わるのだと、ずいぶんと楽しそうに話してくださったのをよく覚えています」
その客人は茶葉の作り方を何時間も熱弁し、苗を残して去っていった。おいしくできたら、いつか振る舞ってくれと言いながら。
マシロはゆっくりと紅茶を飲み干した。彼の昔話はこれで終わりらしい。
狩りをして、料理をして、お茶まで自分で作って、マシロはこの山で暮らしている。
「マシロさんってできないことあるの?」
思わず口をついて出た言葉だった。
「……ありますよ。たくさん」
そのときの寂しそうな顔を見て、粟島は自分の発言を後悔した。
◇
結局覚悟は決まらなかったが、いつまでも先延ばしにはできない。粟島たちはついにツチノコ退治に出かけることになった。
マシロの後に続いて獣道を登っていく。
ツチノコは人が立ち入らない山奥を棲家としているらしい。マシロは比較的歩きやすい地面を選んでくれているようだったが、粟島はついていくのがやっとだった。粟島に合わせてゆっくりと斜面を登っていくマシロは粟島を振り返ることはしなかったが、気にかけてくれているのはよくわかった。粟島はこれ以上マシロに気を遣わせまいと慎重に後を追う。
マシロはツチノコを仕留めるための小刀と、万が一のときに備えて猟銃を背負っていた。粟島も念のため、捕獲用の網を持ってきたが、果たしてこれがどれほどの役に立つだろう。
「物怪がどのように発生しているのか、私も直接見たことはありません」
気付いたら山を徘徊しているため、見つけ次第仕留めているのだと、マシロは言った。
「昔話にもあるように、物怪は赤い目が特徴で、暗闇でも一目でそれとわかります」
粟島は例の、熊のような犬のような獣を思い出した。たしかにあれも、暗がりで目だけが赤々と光っていた。
「物怪は仕留めると黒い灰となり、その原型を留めません。ゆえに、世話係は自身の功績を証明することが困難でした」
被害が出る前に退治しても、それを証明できなければ初めから『なかった』ものとして扱われる。そのシビアさはどの時代でも同じだった。ヒーローというものは、敵が暴れてからしか認知も賞賛もされない。
「それでも村のためという大義名分のもと、世話係はその役目を果たしてきました」
町の老人たちより詳しい解説を、マシロは淀みなく続けていく。
物怪という神の怒りを宥める世話係の制度。とうの昔に廃れてしまった非科学的な慣習。それらはここで暮らしていた村人たちの信仰心と未知への恐怖心が作り上げたものだ。
マシロがやっている物怪退治は、その延長上にあるのだろうか。
「効果はありました。けれどこの世に完璧はありません」
今、マシロがどんな顔をしているのか、粟島に知る術はない。
「何事にも、終わりはあるものです」
◇
しばらく登り続けると、開けた場所に出た。
マシロはしゃがんで茂みの陰に身を隠す。粟島もそれに倣った。
木々の隙間から太陽が降り注ぎ、草花が風にそよぐ。絵になりそうな風景の中で、依頼されたのと同じ特徴を備えた“何か”が眺ねていた。
「あれが……ツチノコ?」
少女の絵は独特であったが、その観察眼には目を見張るものがあった。動物の目のような模様も、ずんぐりとした体躯も、生えている手の形も、よく特徴を捉えている。
ツチノコ──であろう何か──はぴょんぴょんと地面の上を飛び跳ねて、ときどき草の上を転がってはまた跳ねる。たしかに微笑ましいと表現できる情景だった。目の前にいる生き物がUMAでなかったなら、の話だが。
「基本的にはあのように、生き物を襲うことも木々を齧ることもせずに跳ねて過ごしております」
朝と夜は跳ね回り、昼には草の上で微睡む。無害と判断されても仕方がない。今もツチノコはのんきに地面を転がっている。
それでも物怪は例外なく退治しなければならない。発見してから何度も退治しようと試みたが、あのツチノコは罠にも掛からず、そっと背後から忍び寄っても素早く転がって逃げてしまうらしい。
「どうやって捕まえるんですか?」
マシロは銃をおろして粟島に預けた。
「粟島さんはここにいてください」
茂みから出ると、マシロは音を消すこともなくツチノコに近付いていった。足音に気付いたツチノコが跳ねるのをやめ、近くで立ち止まったマシロを見上げる。マシロは膝を折って、目線をツチノコに合わせた。目を見てにこりと微笑めば、ツチノコもまた目を細めた。
「失礼」
マシロはツチノコの背に、ドスッと小刀を突き刺した。逃げようとするツチノコの尻尾を掴んで、刃を頭の方へ滑らせる。小刀がツチノコの頭を二つに割ると、ツチノコだったものは黒い塵となった。風が吹いて、塵は跡形もなく消えていった。
背後から近付けば逃げるが、正面からであればその場に留まる。粟島と別れてからひと月、マシロは安全な退治方法を探していた。粟島と共に来る約束がなければ、この方法は見つけられなかっただろう。のちにマシロは、粟島にそう説明した。それを聞いて粟島は、少しばかりマシロのことが心配になった。退治にしろ狩猟にしろ、普段の彼は自身の安全を二の次にしているのだろうか。
マシロは立ち上がって膝の土を払う。
「最近はあのような害のない物怪が増えております」
戻ってきたマシロは粟島から荷物を受け取ると、ツチノコが跳ねていた場所を見ながらそう言った。
「かといって放置すればいたずらに増えるばかりです」
マシロにとって、物怪退治は草むしりと同列のようだった。道端に咲いた花を愛ではするが、伸びるままにもしておけない。草も獣も、増えすぎては山の営みに影響が出る。山の食べ物が少なくなれば、獣は飢えて死ぬか、餌を求めて人里に降りてくる。適度に間引かなければどこかに被害が出る。それが山か、動物か、人間か。結果が出てからでは遅いのだ。
「……いえ、たしか猫を連れ去ったのはあの物怪でしたか。このひと月、ここから動いた様子はありませんでしたし、いったい何が……」
マシロは口元に手を当てて独り言を呟いている。
以前、彼はあの物怪を『後回しにした』と言っていた。だからといって少女の猫が攫われた原因がマシロにあるとは思わない。そもそも、ツチノコが猫を攫った証拠はないのだ。
マシロの話では、物怪が自分の住処から出ることはまずなかったらしい。出てくるのは他の生き物が縄張りに侵入したときか、天災によって住処が失われたときだったという。今回の件は、そのどちらにも当てはまらない。
邪魔をするのも悪いと思って、粟島はマシロの考えがまとまるのを待つことにした。少なくとも粟島の頭はそのつもりだった。
ぐう。
粟島の腹の虫が鳴り響いた。バサバサと鳥が飛び立っていく。何故今飛ぶんだ。そこまで大きな音じゃなかっただろ。
マシロがじっと粟島を見る。粟島は地面に視線を落とした。
「粟島さん」
粟島が口を開く前に、腹がぐう、と返事をした。粟島はそっと両手で腹を押さえる。
「……違う。違うの、待って」
「たいしたものはご用意できませんが、何かお食べになりますか?」
マシロはくすくすと笑っている。それは揶揄いを含んだものではなく、小さな子どもに向けるような慈愛に満ちたものだった。粟島は余計に居た堪れなくなる。
「ああ、ですが今からでは日が暮れてしまいますね」
「あ、それは大丈夫です。今日は寝袋も持ってきたので」
マシロがぱちぱちと目を瞬かせる。しばらくして「寝具ですか?」と問われた。
「はい。俺が子どものころの寝袋って普通に薄いし寒かったんですけど、最近のはけっこうあたたかいんですよ」
前回汚してしまった布団の代わりにと持ってきた。もちろん最終的には布団を弁償するつもりだ。
「布団はちゃんと好みを聞いてから用意した方がいいと思って」
「……数は」
「え?」
「その寝具は、粟島さんの分もあるんですか?」
もちろん、と答えかけて、粟島は首を捻った。
今回粟島は寝袋をふたつ持ってきている。ひとつはマシロに渡すためのものだ。では、もうひとつはなんだというのだろう。決してマシロの家で寝ることを前提に持ってきたわけではないと言い訳したかったが、残念ながらテントは持ってきていなかった。
「あー……えっと、その……」
粟島が返答に詰まっていると、またしても腹の音が鳴り響いた。
「ふふ。ええ、ご期待に添えるよう努力いたします」
マシロは粟島の腹のあたりに視線を向けて微笑んだ。
「夜の山は危険です。おつかれでしょうし、どうぞ遠慮なくお泊まりになってください」
「……………………よろしくお願いします」
粟島は顔を真っ赤に染めながら、ぎゅうっと腹部を押さえ込む。マシロの家に着くまで、腹からの催促が止むことはなかった。
◇
家に着くとマシロは「すぐにご用意いたします」と言って、棚からフライパンを取り出した。ずいぶんと使い込まれてはいるが、歴史を感じさせるほど古い品ではなさそうに見える。
一応客人である粟島は居間で待つよう言われた。しかしそわそわと落ち着きなく台所を見つめる粟島に、マシロはくふくふと笑みをこぼした。調理器具を置いて、マシロはゆっくりと粟島を振り返る。
「申し訳ありませんが、手が足りなくて。お手伝いしていただけますか?」
またしても子ども扱いされてしまった。
土間へおりると、皿と調味料を出してほしいと頼まれた。きっと自分でやった方が早いだろうに、マシロは丁寧に場所を伝えていく。そのときのマシロがとても楽しそうに見えたので、粟島はあとで目いっぱい感謝を告げようと思った。
まな板の上には赤身の肉が置かれている。なんの肉かと問えば、猪だと返ってきた。
「猪……ってことは、牡丹鍋ですか?」
「いえ。この時期の猪はあまり脂肪がありませんから、別のものを」
マシロは薄く切った肉に、粟島が取り出した調味料で下味を付けていく。
「粟島さんは、牡丹鍋がお好きなんですか?」
作業の手を止めずに、マシロは会話を続けた。
「いえ、まだ食べたことはないんです。ここの町内会長がおいしいって言ってたから、ちょっと気になって」
「かいちょう?」
「日ノ池さんっていって、俺がこの町に越してきたときによくお世話になった人で。まあ、今もなんですけど」
日ノ池は齢八十を過ぎても溌剌とした好好爺で、「暇な老人の話し相手になってくれ」などと言いながら、粟島に町のことをいろいろと教えてくれた。先日も、趣味の海釣りで得た釣果を分けてもらった。粟島よりもずっとタフで行動力のある人だ。
「……そうですか」
マシロの手が一瞬止まる。けれどすぐに調理を再開した。
「お元気そうで何よりです」
その懐かしむような穏やかな表情の理由を、粟島は尋ねることができなかった。
粟島はオカルトを信じていない。
正確には、信じたくなかった。
1
あなたにおすすめの小説
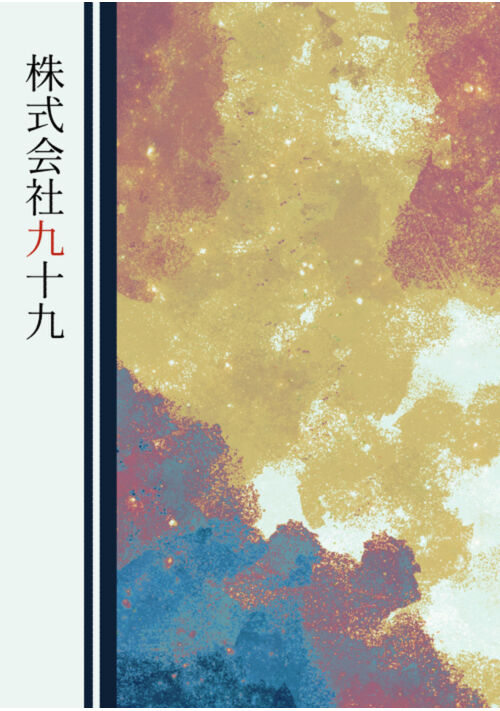
株式会社九十九
煤原
キャラ文芸
呪いに怯える人々が持ち込んだ品々を呪物と呼んで、依頼人から買い取ったり預かったりするのが、この会社の主な仕事内容だ。実際に持ち込まれる物はただの骨董品や古いだけのガラクタであることがほとんどだけれど、会社の倉庫にはそれらの呪物がずらりと並んでいる。本当に呪われているかどうかなんて、依頼人には関係がない。彼らはただ不安なのだ。その不安を手放したいのだ。
これは、人の不安を預かって安心させる仕事だった。
◇ ◆ ◇
ホラー要素と、痛々しい描写を含みます。人面瘡や異食、カニバリズム等が苦手な方はご注意ください。
◇ ◆ ◇
漫画の短編集(https://www.alphapolis.co.jp/manga/173302362/376868016)に4ページほどの小ネタを掲載しています。

怪奇蒐集帳(短編集)
naomikoryo
ホラー
この世には、知ってはいけない話がある。
怪談、都市伝説、語り継がれる呪い——
どれもがただの作り話かもしれない。
だが、それでも時々、**「本物」**が紛れ込むことがある。
本書は、そんな“見つけてしまった”怪異を集めた一冊である。
最後のページを閉じるとき、あなたは“何か”に気づくことになるだろう——。


彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

視える僕らのシェアハウス
橘しづき
ホラー
安藤花音は、ごく普通のOLだった。だが25歳の誕生日を境に、急におかしなものが見え始める。
電車に飛び込んでバラバラになる男性、やせ細った子供の姿、どれもこの世のものではない者たち。家の中にまで入ってくるそれらに、花音は仕事にも行けず追い詰められていた。
ある日、駅のホームで電車を待っていると、霊に引き込まれそうになってしまう。そこを、見知らぬ男性が間一髪で救ってくれる。彼は花音の話を聞いて名刺を一枚手渡す。
『月乃庭 管理人 竜崎奏多』
不思議なルームシェアが、始まる。

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド
まみ夜
ホラー
ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。
事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。
一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。
その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。
そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。
ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。
そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。
第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。
表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















