あなたにおすすめの小説

目覚めたら公爵夫人でしたが夫に冷遇されているようです
MIRICO
恋愛
フィオナは没落寸前のブルイエ家の長女。体調が悪く早めに眠ったら、目が覚めた時、夫のいる公爵夫人セレスティーヌになっていた。
しかし、夫のクラウディオは、妻に冷たく視線を合わせようともしない。
フィオナはセレスティーヌの体を乗っ取ったことをクラウディオに気付かれまいと会う回数を減らし、セレスティーヌの体に入ってしまった原因を探そうとするが、原因が分からぬままセレスティーヌの姉の子がやってきて世話をすることに。
クラウディオはいつもと違う様子のセレスティーヌが気になり始めて……。
ざまあ系ではありません。恋愛中心でもないです。事件中心軽く恋愛くらいです。
番外編は暗い話がありますので、苦手な方はお気を付けください。
ご感想ありがとうございます!!
誤字脱字等もお知らせくださりありがとうございます。順次修正させていただきます。
小説家になろう様に掲載済みです。

私を見下していた婚約者が破滅する未来が見えましたので、静かに離縁いたします
ほーみ
恋愛
その日、私は十六歳の誕生日を迎えた。
そして目を覚ました瞬間――未来の記憶を手に入れていた。
冷たい床に倒れ込んでいる私の姿。
誰にも手を差し伸べられることなく、泥水をすするように生きる未来。
それだけなら、まだ耐えられたかもしれない。
だが、彼の言葉は、決定的だった。
「――君のような役立たずが、僕の婚約者だったことが恥ずかしい」
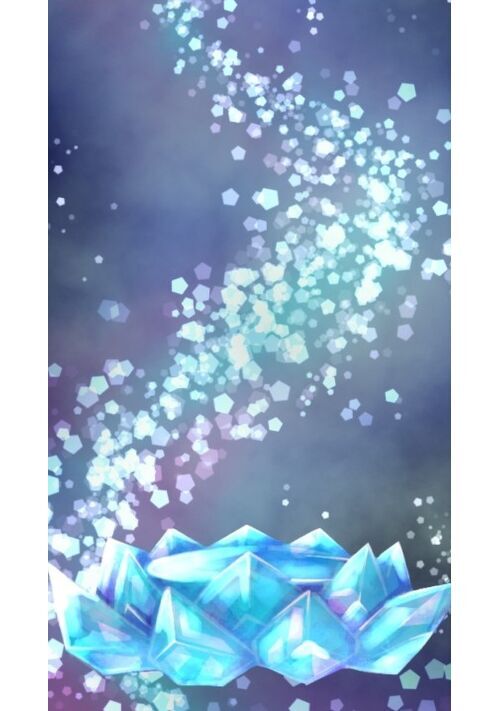
【完結】無罪なのに断罪されたモブ令嬢ですが、神に物申したら上手くいった話
もわゆぬ
恋愛
この世は可笑しい。
本当にしたかも分からない罪で”悪役”が作り上げられ断罪される。
そんな世界にむしゃくしゃしながらも、何も出来ないで居たサラ。
しかし、平凡な自分も婚約者から突然婚約破棄をされる。
隣国へと逃亡したが、よく分からないこんな世界に怒りが収まらず神に一言物申してやろうと教会へと向かうのだった…
【短編です、物語7話+αで終わります】

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

辺境の侯爵令嬢、婚約破棄された夜に最強薬師スキルでざまぁします。
コテット
恋愛
侯爵令嬢リーナは、王子からの婚約破棄と義妹の策略により、社交界での地位も誇りも奪われた。
だが、彼女には誰も知らない“前世の記憶”がある。現代薬剤師として培った知識と、辺境で拾った“魔草”の力。
それらを駆使して、貴族社会の裏を暴き、裏切った者たちに“真実の薬”を処方する。
ざまぁの宴の先に待つのは、異国の王子との出会い、平穏な薬草庵の日々、そして新たな愛。
これは、捨てられた令嬢が世界を変える、痛快で甘くてスカッとする逆転恋愛譚。

わたくしがお父様に疎まれている?いいえ、目に入れても痛くない程溺愛されております。
織り子
ファンタジー
王国貴族院の卒業記念パーティーの場で、大公家の令嬢ルクレツィア・アーヴェントは王太子エドワードから突然の婚約破棄を告げられる。
父であるアーヴェント大公に疎まれている――
噂を知った王太子は、彼女を公衆の面前で侮辱する。

『婚約もしていないのに婚約破棄ですか? 〜岩塩で殴れば目が覚めます?〜』
しおしお
恋愛
「岩を売る田舎娘と婚約?そんなもの破棄だ!」
――そう言い放ったのは、まだ婚約すら成立していないのに“婚約破棄”を宣言した内陸王国の王太子。
塩は海から来るもの。
白く精製された粉こそ本物。
岩塩など不純物の塊に過ぎない。
そう思い込んだ彼は、ハライト公国公爵令嬢ヴィエリチカを侮辱し、交易を軽んじた。
だが――
王都に届くその“白い粉”は、すべてハライト産の岩塩から精製されたものだった。
供給が止まった瞬間、王国は気づく。
塩は保存であり、兵站であり、治療であり、冬越しの生命線であったことを。
謝罪の席で提示された条件はただ一つ。
民への販売価格は据え置き。
だが国家は十倍で買い取ること。
誇りを守るために契約を受け入れた王太子。
守られたのは民。
削られたのは国家。
やがて赤字は膨らみ、担保は差し出され、王国は静かに編入されていく。
処刑はない。
復讐もない。
あるのは――帰結。
「塩は、穢れを流すためのものです」
笑顔で告げるヴィエリチカと、
王宮衛生管理局へ配属された元王太子。
これは、岩塩を侮った物語の、静かな終着点。
---
もしアルファポリス向けにもう少し軽くする版も欲しければ、作ります。
それとも、
・タグもまとめる?
・もっと煽る版にする?
・文学寄りにする?
どの方向で仕上げますか?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















