23 / 28
23
しおりを挟む
王宮は、かつてないほどの混乱と、冷え切った沈黙に包まれていた。
リリアナが公衆の面前で引き起こした、あの常軌を逸した自作自演の毒殺未遂騒ぎ。
その醜聞は、瞬く間に王都中を駆け巡り、すでに地に落ちかけていた王家の威信に、とどめの一撃を突き刺した。
「この愚か者めが!」
国王陛下の雷のような怒声が、玉座の間に響き渡る。
その前に、エドワードは、ただ、頭を垂れることしかできなかった。
「貴様の甘さが、あの小娘を増長させ、王家の顔に、取り返しのつかぬ泥を塗ったのだ! 分かっているのか!」
「…申し訳、ございません」
リリアナは、王太子妃候補の資格を、即日、剥奪された。
すべての貴族の称号も取り上げられ、平民同然の身分で、泣きながら実家の男爵家へと送り返されていった。
彼女が最後に、エドワードに「見捨てないで」とみっともなく縋り付いてきた時、彼の心には、哀れみなど、一欠片も湧いてはこなかった。
ただ、自分の人生をここまでめちゃくちゃにした、この愚かな女への、激しい嫌悪と憎しみがあるだけだった。
しかし、リリアナを断罪したところで、何も解決はしない。
貴族たちの、自分を見る目は、日に日に冷たくなっていく。
国政は、シュヴァルツ公爵家という大きな歯車を失ったことで、完全に停滞し、問題は山積みになる一方だ。
一人、がらんとした執務室で、エドワードは、その高く積み上げられた書類の山を前に、途方に暮れていた。
(なぜだ…なぜ、こうなった…)
真実の愛を選び、悪役令嬢を追放した、正しい王子。
物語の筋書きは、完璧だったはずだ。
それなのに、なぜ、自分は、こんなにも孤立し、追い詰められているのだろう。
ふと、机の隅に置かれたティーカップに、目が留まった。
侍女が淹れてくれた、いつもの紅茶。
しかし、今日のそれは、ひどく、不味く感じられた。
その時、エドワードの脳裏に、ふと、ある記憶が蘇った。
(…サーシャの淹れる紅茶は、いつも完璧な濃さだったな…)
そうだ。彼女は、自分が執務で疲れている時、少し濃いめに。
会議で神経を使った後には、安らぐ香りのハーブを少しだけ加えたものを。
何も言わなくても、いつも、完璧なタイミングで、完璧な一杯を、彼の前に差し出してくれた。
そんなことは、当たり前すぎて、今まで、気に留めたことすらなかったのに。
一つ思い出すと、次から次へと、忘れていたはずの記憶が、洪水のように押し寄せてくる。
あれは、隣国との、難解な交易協定の書類を前に、自分が頭を抱えていた時のこと。
「殿下、少しよろしいですわね」と、サーシャは、分厚い書類の束を、一晩で、完璧な要約と、問題点のリストにまとめてきてくれた。
そのおかげで、自分は、どれほど会議を有利に進めることができたことか。
あれは、頑固な大臣たちとの会議で、自分が立ち往生してしまっていた時のこと。
自分の隣に座っていたサーシャが、そっと、「あちらの大臣は、孫娘の誕生を心待ちにしていますわ。そのお話をされてみては?」と囁いてくれた。
その一言の助言で、どれほど、場の空気が和み、物事が円滑に進んだことか。
財力。家柄。影響力。
自分が、サーシャに求めていたのは、そんな、シュヴァルヴァルツ家の背景だけだと思っていた。
だが、違ったのだ。
自分は、何よりもまず、「サーシャ・フォン・シュヴァルツ」という、一人の、あまりにも有能で、聡明で、そして、誰よりも自分のことを理解してくれていた、唯一無二のパートナーを、失ってしまったのだ。
愛や、恋といった、甘い感情ではない。
もっと、深く、根源的なレベルで、自分は、彼女に支えられ、彼女に依存し、そして、彼女に生かされていた。
その事実に、エドワードは、すべてを失った今になって、ようやく、骨身にしみて、気づいたのだった。
「…私が、間違っていたと、いうのか…?」
生まれて初めて、自分の判断を、心の底から後悔した。
もし、あの時、卒業パーティーで、あんな愚かな真似をしなければ。
もし、彼女の本当の価値に、もっと早く気づいてさえいれば。
今頃、自分は、彼女という最高の伴侶と共に、この国の未来を、明るく照らしていたかもしれないのに。
だが、そんな後悔は、あまりにも、遅すぎた。
その時、執務室の扉が、勢いよく開かれた。
側近の一人が、息を切らし、蒼白な顔で駆け込んでくる。
「で、殿下…! 大変な、情報が…!」
「なんだ、騒々しい」
「アシュフォード辺境伯領に放っていた、諜報員からの、確かな筋による、報告でございます…!」
側近は、ごくり、と唾を飲み込むと、エドワードにとって、最後の希望を無慈悲に打ち砕く、決定的な言葉を、口にした。
「アシュフォード辺境伯様と、かの、シュヴァルヴァルツ公爵家のサーシャ様が…近々、両家の間で、正式に、婚約を発表される見込み、とのことです…!」
その報せは、まるで、死刑宣告のように、エドワードの頭上で響き渡った。
サーシャは、もう、決して、自分の手の届くところにはいない。
彼女は、自分よりも、遥かに器が大きく、優れた男の隣で、この国の、新しい未来を、作り上げていくのだ。
自分という、愚かな王子を踏み台にして。
自分に残されたのは、傾きかけた国と、地に落ちた信頼、そして、もはや、どうすることもできない、永遠の後悔だけ。
がくん、と、膝の力が抜けた。
エドワードは、王太子の威厳も何もかも失い、まるで糸が切れた人形のように、その場に崩れ落ちた。
窓の外は、彼をあざ笑うかのように、どこまでも美しい、皮肉なほどの夕焼けに染まっている。
「…サーシャ…」
絞り出した声は、誰の耳にも届くことなく、がらんとした執務室に、空しく、そして、虚しく響き渡った。
リリアナが公衆の面前で引き起こした、あの常軌を逸した自作自演の毒殺未遂騒ぎ。
その醜聞は、瞬く間に王都中を駆け巡り、すでに地に落ちかけていた王家の威信に、とどめの一撃を突き刺した。
「この愚か者めが!」
国王陛下の雷のような怒声が、玉座の間に響き渡る。
その前に、エドワードは、ただ、頭を垂れることしかできなかった。
「貴様の甘さが、あの小娘を増長させ、王家の顔に、取り返しのつかぬ泥を塗ったのだ! 分かっているのか!」
「…申し訳、ございません」
リリアナは、王太子妃候補の資格を、即日、剥奪された。
すべての貴族の称号も取り上げられ、平民同然の身分で、泣きながら実家の男爵家へと送り返されていった。
彼女が最後に、エドワードに「見捨てないで」とみっともなく縋り付いてきた時、彼の心には、哀れみなど、一欠片も湧いてはこなかった。
ただ、自分の人生をここまでめちゃくちゃにした、この愚かな女への、激しい嫌悪と憎しみがあるだけだった。
しかし、リリアナを断罪したところで、何も解決はしない。
貴族たちの、自分を見る目は、日に日に冷たくなっていく。
国政は、シュヴァルツ公爵家という大きな歯車を失ったことで、完全に停滞し、問題は山積みになる一方だ。
一人、がらんとした執務室で、エドワードは、その高く積み上げられた書類の山を前に、途方に暮れていた。
(なぜだ…なぜ、こうなった…)
真実の愛を選び、悪役令嬢を追放した、正しい王子。
物語の筋書きは、完璧だったはずだ。
それなのに、なぜ、自分は、こんなにも孤立し、追い詰められているのだろう。
ふと、机の隅に置かれたティーカップに、目が留まった。
侍女が淹れてくれた、いつもの紅茶。
しかし、今日のそれは、ひどく、不味く感じられた。
その時、エドワードの脳裏に、ふと、ある記憶が蘇った。
(…サーシャの淹れる紅茶は、いつも完璧な濃さだったな…)
そうだ。彼女は、自分が執務で疲れている時、少し濃いめに。
会議で神経を使った後には、安らぐ香りのハーブを少しだけ加えたものを。
何も言わなくても、いつも、完璧なタイミングで、完璧な一杯を、彼の前に差し出してくれた。
そんなことは、当たり前すぎて、今まで、気に留めたことすらなかったのに。
一つ思い出すと、次から次へと、忘れていたはずの記憶が、洪水のように押し寄せてくる。
あれは、隣国との、難解な交易協定の書類を前に、自分が頭を抱えていた時のこと。
「殿下、少しよろしいですわね」と、サーシャは、分厚い書類の束を、一晩で、完璧な要約と、問題点のリストにまとめてきてくれた。
そのおかげで、自分は、どれほど会議を有利に進めることができたことか。
あれは、頑固な大臣たちとの会議で、自分が立ち往生してしまっていた時のこと。
自分の隣に座っていたサーシャが、そっと、「あちらの大臣は、孫娘の誕生を心待ちにしていますわ。そのお話をされてみては?」と囁いてくれた。
その一言の助言で、どれほど、場の空気が和み、物事が円滑に進んだことか。
財力。家柄。影響力。
自分が、サーシャに求めていたのは、そんな、シュヴァルヴァルツ家の背景だけだと思っていた。
だが、違ったのだ。
自分は、何よりもまず、「サーシャ・フォン・シュヴァルツ」という、一人の、あまりにも有能で、聡明で、そして、誰よりも自分のことを理解してくれていた、唯一無二のパートナーを、失ってしまったのだ。
愛や、恋といった、甘い感情ではない。
もっと、深く、根源的なレベルで、自分は、彼女に支えられ、彼女に依存し、そして、彼女に生かされていた。
その事実に、エドワードは、すべてを失った今になって、ようやく、骨身にしみて、気づいたのだった。
「…私が、間違っていたと、いうのか…?」
生まれて初めて、自分の判断を、心の底から後悔した。
もし、あの時、卒業パーティーで、あんな愚かな真似をしなければ。
もし、彼女の本当の価値に、もっと早く気づいてさえいれば。
今頃、自分は、彼女という最高の伴侶と共に、この国の未来を、明るく照らしていたかもしれないのに。
だが、そんな後悔は、あまりにも、遅すぎた。
その時、執務室の扉が、勢いよく開かれた。
側近の一人が、息を切らし、蒼白な顔で駆け込んでくる。
「で、殿下…! 大変な、情報が…!」
「なんだ、騒々しい」
「アシュフォード辺境伯領に放っていた、諜報員からの、確かな筋による、報告でございます…!」
側近は、ごくり、と唾を飲み込むと、エドワードにとって、最後の希望を無慈悲に打ち砕く、決定的な言葉を、口にした。
「アシュフォード辺境伯様と、かの、シュヴァルヴァルツ公爵家のサーシャ様が…近々、両家の間で、正式に、婚約を発表される見込み、とのことです…!」
その報せは、まるで、死刑宣告のように、エドワードの頭上で響き渡った。
サーシャは、もう、決して、自分の手の届くところにはいない。
彼女は、自分よりも、遥かに器が大きく、優れた男の隣で、この国の、新しい未来を、作り上げていくのだ。
自分という、愚かな王子を踏み台にして。
自分に残されたのは、傾きかけた国と、地に落ちた信頼、そして、もはや、どうすることもできない、永遠の後悔だけ。
がくん、と、膝の力が抜けた。
エドワードは、王太子の威厳も何もかも失い、まるで糸が切れた人形のように、その場に崩れ落ちた。
窓の外は、彼をあざ笑うかのように、どこまでも美しい、皮肉なほどの夕焼けに染まっている。
「…サーシャ…」
絞り出した声は、誰の耳にも届くことなく、がらんとした執務室に、空しく、そして、虚しく響き渡った。
528
あなたにおすすめの小説

政略結婚の指南書
編端みどり
恋愛
【完結しました。ありがとうございました】
貴族なのだから、政略結婚は当たり前。両親のように愛がなくても仕方ないと諦めて結婚式に臨んだマリア。母が持たせてくれたのは、政略結婚の指南書。夫に愛されなかった母は、指南書を頼りに自分の役目を果たし、マリア達を立派に育ててくれた。
母の背中を見て育ったマリアは、愛されなくても自分の役目を果たそうと覚悟を決めて嫁いだ。お相手は、女嫌いで有名な辺境伯。
愛されなくても良いと思っていたのに、マリアは結婚式で初めて会った夫に一目惚れしてしまう。
屈強な見た目で女性に怖がられる辺境伯も、小動物のようなマリアに一目惚れ。
惹かれ合うふたりを引き裂くように、結婚式直後に辺境伯は出陣する事になってしまう。
戻ってきた辺境伯は、上手く妻と距離を縮められない。みかねた使用人達の手配で、ふたりは視察という名のデートに赴く事に。そこで、事件に巻き込まれてしまい……
※R15は保険です
※別サイトにも掲載しています

【完結】姉に婚約者を奪われ、役立たずと言われ家からも追放されたので、隣国で幸せに生きます
よどら文鳥
恋愛
「リリーナ、俺はお前の姉と結婚することにした。だからお前との婚約は取り消しにさせろ」
婚約者だったザグローム様は婚約破棄が当然のように言ってきました。
「ようやくお前でも家のために役立つ日がきたかと思ったが、所詮は役立たずだったか……」
「リリーナは伯爵家にとって必要ない子なの」
両親からもゴミのように扱われています。そして役に立たないと、家から追放されることが決まりました。
お姉様からは用が済んだからと捨てられます。
「あなたの手柄は全部私が貰ってきたから、今回の婚約も私のもの。当然の流れよね。だから謝罪するつもりはないわよ」
「平民になっても公爵婦人になる私からは何の援助もしないけど、立派に生きて頂戴ね」
ですが、これでようやく理不尽な家からも解放されて自由になれました。
唯一の味方になってくれた執事の助言と支援によって、隣国の公爵家へ向かうことになりました。
ここから私の人生が大きく変わっていきます。

妹のために愛の無い結婚をすることになりました
バンブー竹田
恋愛
「エミリー、君との婚約は破棄することに決まった」
愛するラルフからの唐突な通告に私は言葉を失ってしまった。
婚約が破棄されたことはもちろんショックだけど、それだけじゃない。
私とラルフの結婚は妹のシエルの命がかかったものでもあったから・・・。
落ちこむ私のもとに『アレン』という大金持ちの平民からの縁談が舞い込んできた。
思い悩んだ末、私は会ったこともない殿方と結婚することに決めた。
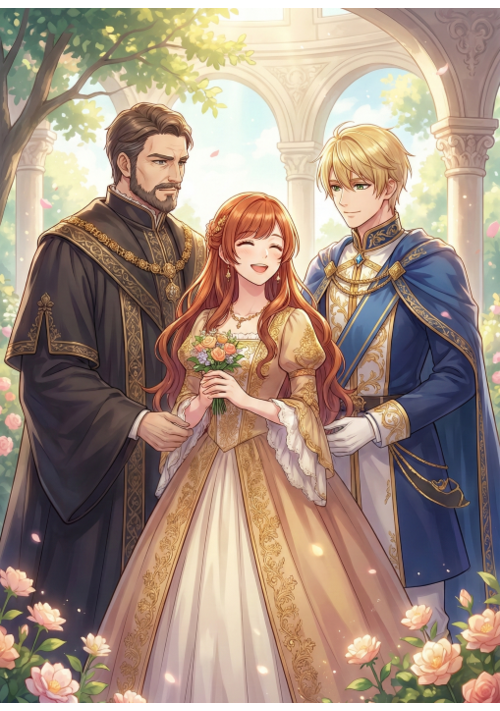
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

婚約者と王の座を捨てて、真実の愛を選んだ僕の結果
もふっとしたクリームパン
恋愛
タイトル通り、婚約者と王位を捨てた元第一王子様が過去と今を語る話です。ざまぁされる側のお話なので、明るい話ではありません。*書きたいとこだけ書いた小説なので、世界観などの設定はふんわりしてます。*文章の追加や修正を適時行います。*カクヨム様にも投稿しています。*本編十四話(幕間四話)+登場人物紹介+オマケ(四話:ざまぁする側の話)、で完結。

偽王を演じた侯爵令嬢は、名もなき人生を選ぶ」
鷹 綾
恋愛
内容紹介
王太子オレンに婚約破棄された侯爵令嬢ライアー・ユースティティア。
だが、それは彼女にとって「不幸の始まり」ではなかった。
国政を放棄し、重税と私欲に溺れる暴君ロネ国王。
その無責任さを補っていた宰相リシュリュー公爵が投獄されたことで、
国は静かに、しかし確実に崩壊へ向かい始める。
そんな中、変身魔法を使えるライアーは、
国王の身代わり――偽王として玉座に座ることを強要されてしまう。
「王太子妃には向いていなかったけれど……
どうやら、国王にも向いていなかったみたいですわね」
有能な宰相とともに国を立て直し、
理不尽な税を廃し、民の暮らしを取り戻した彼女は、
やがて本物の国王と王太子を“偽者”として流刑に処す。
そして最後に選んだのは、
王として君臨し続けることではなく――
偽王のまま退位し、名もなき人生を生きることだった。
これは、
婚約破棄から始まり、
偽王としてざまぁを成し遂げ、
それでも「王にならなかった」令嬢の物語。
玉座よりも遠く、
裁きよりも静かな場所で、
彼女はようやく“自分の人生”を歩き始める。

婚約破棄されましたが、私はもう必要ありませんので
ふわふわ
恋愛
「婚約破棄?
……そうですか。では、私の役目は終わりですね」
王太子ロイド・ヴァルシュタインの婚約者として、
国と王宮を“滞りなく回す存在”であり続けてきた令嬢
マルグリット・フォン・ルーヴェン。
感情を表に出さず、
功績を誇らず、
ただ淡々と、最善だけを積み重ねてきた彼女に突きつけられたのは――
偽りの奇跡を振りかざす“聖女”による、突然の婚約破棄だった。
だが、マルグリットは嘆かない。
怒りもしない。
復讐すら、望まない。
彼女が選んだのは、
すべてを「仕組み」と「基準」に引き渡し、静かに前線から降りること。
彼女がいなくなっても、領地は回る。
判断は滞らず、人々は困らない。
それこそが、彼女が築いた“完成形”だった。
一方で、
彼女を切り捨てた王太子と偽聖女は、
「彼女がいない世界」で初めて、自分たちの無力さと向き合うことになる。
――必要とされない価値。
――前に出ない強さ。
――名前を呼ばれない完成。
これは、
騒がず、縋らず、静かに去った令嬢が、
最後にすべてを置き去りにして手に入れる“自由”の物語。
ざまぁは静かに、
恋は後半に、
そして物語は、凛と終わる。
アルファポリス女子読者向け
「大人の婚約破棄ざまぁ恋愛」、ここに完結。

悪役令嬢が行方不明!?
mimiaizu
恋愛
乙女ゲームの設定では悪役令嬢だった公爵令嬢サエナリア・ヴァン・ソノーザ。そんな彼女が行方不明になるというゲームになかった事件(イベント)が起こる。彼女を見つけ出そうと捜索が始まる。そして、次々と明かされることになる真実に、妹が両親が、婚約者の王太子が、ヒロインの男爵令嬢が、皆が驚愕することになる。全てのカギを握るのは、一体誰なのだろう。
※初めての悪役令嬢物です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















