この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

大丈夫のその先は…
水姫
恋愛
実来はシングルマザーの母が再婚すると聞いた。母が嬉しそうにしているのを見るとこれまで苦労かけた分幸せになって欲しいと思う。
新しくできた父はよりにもよって医者だった。新しくできた兄たちも同様で…。
バレないように、バレないように。
「大丈夫だよ」
すいません。ゆっくりお待ち下さい。m(_ _)m

私に告白してきたはずの先輩が、私の友人とキスをしてました。黙って退散して食事をしていたら、ハイスペックなイケメン彼氏ができちゃったのですが。
石河 翠
恋愛
飲み会の最中に席を立った主人公。化粧室に向かった彼女は、自分に告白してきた先輩と自分の友人がキスをしている現場を目撃する。
自分への告白は、何だったのか。あまりの出来事に衝撃を受けた彼女は、そのまま行きつけの喫茶店に退散する。
そこでやけ食いをする予定が、美味しいものに満足してご機嫌に。ちょっとしてネタとして先ほどのできごとを話したところ、ずっと片想いをしていた相手に押し倒されて……。
好きなひとは高嶺の花だからと諦めつつそばにいたい主人公と、アピールし過ぎているせいで冗談だと思われている愛が重たいヒーローの恋物語。
この作品は、小説家になろう及びエブリスタでも投稿しております。
扉絵は、写真ACよりチョコラテさまの作品をお借りしております。

婚約者の心の声が聞こえるようになったが手遅れだった
神々廻
恋愛
《めんどー、何その嫌そうな顔。うっざ》
「殿下、ご機嫌麗しゅうございます」
婚約者の声が聞こえるようになったら.........婚約者に罵倒されてた.....怖い。
全3話完結
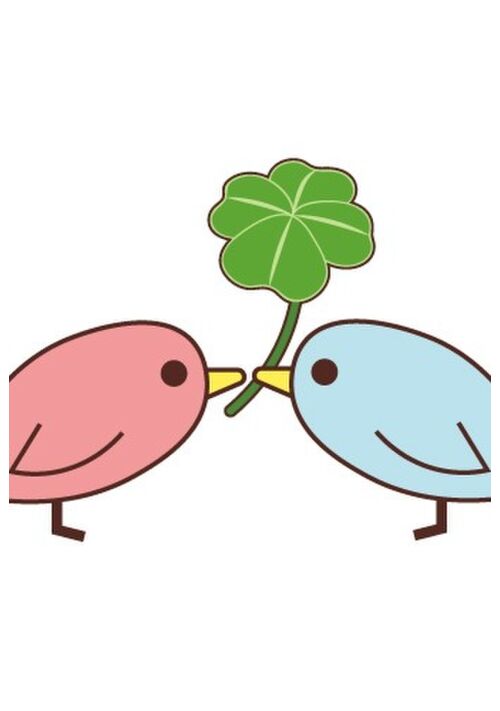
番が1人なんて…誰が決めたの?
月樹《つき》
恋愛
私達、鳥族では大抵一夫一妻で生涯を通して同じ伴侶と協力し、子育てをしてその生涯を終える。
雌はより優秀な遺伝子を持つ雄を伴侶とし、優秀な子を育てる。社交的で美しい夫と、家庭的で慎ましい妻。
夫はその美しい羽を見せびらかし、うっとりするような美声で社交界を飛び回る。
夫は『心配しないで…僕達は唯一無二の番だよ?』と言うけれど…
このお話は小説家になろう様でも掲載しております。




お腹の子と一緒に逃げたところ、結局お腹の子の父親に捕まりました。
下菊みこと
恋愛
逃げたけど逃げ切れなかったお話。
またはチャラ男だと思ってたらヤンデレだったお話。
あるいは今度こそ幸せ家族になるお話。
ご都合主義の多分ハッピーエンド?
小説家になろう様でも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















