2 / 5
2
しおりを挟む明くんは、ますます鏡について知りたくなり、おばあちゃんにお話の続きをせがみました。
「この鏡の中のあたしは、長い人生の中で生き方に迷いが生まれた時、あたしが選べなかった道を、それぞれ歩いています。学者さんになったあたしも、有名な作家になったあたしもいるわ」
「それ、凄い!」
「でしょう? この鏡を見ていると、たくさんの、違うあたし自身と出会えて、自分では気づけなかったくせや、可能性を知る事ができるの。もう楽しくて、寂しがってなんかいられません」
「でも……鏡の中の自分とは、お話できないんだよね」
おばあちゃんは、明くんのその言葉に悪戯っぽく笑いました。
「あ、もしかして、できちゃう?」
「我が家に伝わる秘伝の奥義には、合わせ鏡で扉を開く、と言うのがあってね」
「合わせ鏡って何さ?」
「それは……」
説明しようとしたけれど、途中でおばあちゃんは何かにためらい、人差し指を唇の前に置きました。
「やめておきます、それについて詳しい説明をするのは」
「どうして? ここまできて、ずるいよ」
「その奥義を使うと、もしかしたら、すごく危ない事になるかもしれないの。実はね、私も昔……」
「昔、何?」
「やっぱり言えません。その代わり、私が死んだら、この鏡はあなたに譲るわ。そう遺言書に書いておく」
「ホント?」
「ただ、一つだけ約束して」
おばあちゃんは姿勢を正し、正面から明くんを見詰めて、言いました。
「他の鏡がある所で、この古い鏡を見てはだめ。特に」
おばあちゃんの眼差しが、和室の隅に置かれた大きな鏡台へ向きます。
古い鏡と同じように栃木から引っ越してくる時、おばあちゃんが持ってきた品で、お嫁入りの道具だったそうです。
「古い鏡が外に出ている時、絶対にこの鏡台を開かないで。掛かっている布を外してもダメ」
「どうして?」
「どうしても! その約束を守れないなら、あなたに鏡はあげません」
そう言われ、慌てて明くんは約束を守ると誓いました。
でも、根が忘れっぽい明くんのこと。
その後、そんな約束をした事も、おばあちゃんが亡くなってしまうまで忘れていたのですが……
おばあちゃんが亡くなり、形見分けが始まった時、明くんは迷わず、銅の鏡を選びました。
そして、お父さんとお母さんが捨てようと相談していたあの大きな鏡台も自分の部屋へ置く事にしたのです。
お父さんは、何故そんな物を欲しがるか不思議そうでしたが、不思議な鏡と一緒に鏡台を開くな、とおばあちゃんに注意された事が、かえって明くんの印象に強く残っていました。
それに、何か言われたら、その反対をやってみたくなる悪い癖が、明くんにはあったのです。
それからというもの、学校が終わって部屋へ帰る度、明くんは一人で銅の鏡を眺めるようになりました。
「ん~、どうしたら、別の世界が見えるようになるんだろ?」
そうつぶやき、おばあちゃんの魔法みたいな手の動きをまねても、しばらくの間は景色が普通に映るだけでしたが……
ある日、自分の顔がぼやけ、別人のように見える角度をとうとう見つけ出しました。
「あ、もしかして、こんな風に揺らしながら覗くのがコツ?」
最初のおまじないもまねできるようになり、角度を微妙に調整すると、鏡に映る後ろの景色が変化して行きます。
最初に見つけた『魔法の角度』では、鏡の中の明くんの部屋に、算数の参考書や問題集、それに難しそうな本が沢山ありました。
本当の明くんの部屋には、教科書の他はマンガしかありません。
次に見つけた『魔法の角度』では、学校の校庭で走る明くんの姿が見えました。
それもクラスの誰よりぶっちぎりで早く、運動会の時はクラス代表の選手になっているみたいです。
ちなみに、本当の明くんは運動が嫌いで、体育の時間はさぼりっぱなし。競争をするといつもビリ。
ちょっとくやしい気がしたけれど、その分、むきになって明くんは鏡の研究へのめりこむようになりました。
その結果、毎日、少しずつ色んな魔法の角度を探しだし、本当の明くんとは少しずつ違う性格、特技の「明くん」を、たくさん鏡の中に見つける事ができたのです。
きっとおばあちゃんも、こんな風に沢山の自分と出会い、寂しさをまぎらわせていたに違いありません。
「ウン、可能性としてのボク、って所かなぁ。おばあちゃん流に言うと」
そう、鏡の中の「明くん」が示す力は、銅の鏡を持つ「元の世界の明くん」にも努力次第で手に入る物ばかり。もし、それをきっかけに、勉強へ打ち込んだり、運動したりすれば、未来の夢へ近づけていた事でしょう。
きっと、おばあちゃんが孫に鏡を残したのは、その願いからだったろうに……
でも明くんには悪い癖がありました。
頑張らなければならない時、いつも怠けたい気持ちが先に立つのです。努力なんて大嫌い。
結局、誰より早く逃げ出してしまう。
そんな孫の様子を心配していたのでしょうか?
時々、鏡を覗いていると、おばあちゃんに似た影がよぎる事がありました。
いつも穏やかに笑っていたおばあちゃんの瞳と違う、哀しそうな眼差しを鏡の向こう側から感じた時もあります。
でも、それが何を意味しているか、明くんは考えようとしませんでした。
目の前の、不思議な鏡が作り出す楽しい事しか、見えていなかった。いや、見たくなかったのです。
0
あなたにおすすめの小説

少年イシュタと夜空の少女 ~死なずの村 エリュシラーナ~
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
イシュタは病の妹のため、誰も死なない村・エリュシラーナへと旅立つ。そして、夜空のような美しい少女・フェルルと出会い……
「昔話をしてあげるわ――」
フェルルの口から語られる、村に隠された秘密とは……?
☆…☆…☆
※ 大人でも楽しめる児童文学として書きました。明確な記述は避けておりますので、大人になって読み返してみると、また違った風に感じられる……そんな物語かもしれません……♪
※ イラストは、親友の朝美智晴さまに描いていただきました。

童話絵本版 アリとキリギリス∞(インフィニティ)
カワカツ
絵本
その夜……僕は死んだ……
誰もいない野原のステージの上で……
アリの子「アントン」とキリギリスの「ギリィ」が奏でる 少し切ない ある野原の物語 ———
全16話+エピローグで紡ぐ「小さないのちの世界」を、どうぞお楽しみ下さい。
※高学年〜大人向き

隣のじいさん
kudamonokozou
児童書・童話
小学生の頃僕は祐介と友達だった。空き家だった隣にいつの間にか変なじいさんが住みついた。
祐介はじいさんと仲良しになる。
ところが、そのじいさんが色々な騒動を起こす。
でも祐介はじいさんを信頼しており、ある日遠い所へ二人で飛んで行ってしまった。

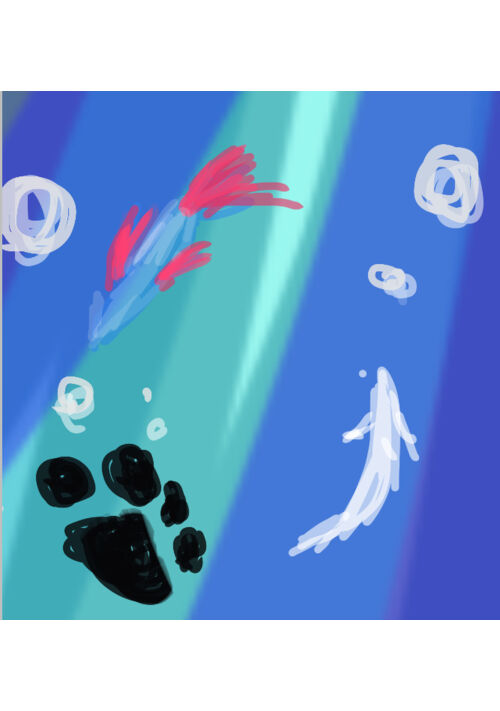
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎



ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















