3 / 6
3
しおりを挟む
今から山に登るのは、それこそ自殺行為だった。霊とは別の、もっと現実的な危険が夜の山にはある。猪と遭遇しようものなら、それこそ無事では済まない可能性が高い。猪に襲われて重傷を負った事例や、死亡した事例も現実としてある。そして、猪は夜になると活発になるのだ。無論、危険はそれだけではない。いるかどうかも分からない不確かな霊という存在よりも、Kさんはどちらかといえば現実として確実に在る危険の方を危惧していた。
「ライトとスマホのバッテリーがほとんど残ってない。家までまだ距離あるし、あまり上には登らない方がいいな。戻れなくなったらヤバいし、そんなに時間もないしな。どっかその辺で雰囲気のあるとこがあれば……」
見落としのないよう、再度慎重に辺りを見渡す。
「にゃあ~」
静寂を切り裂くその鳴き声はKさんのすぐ後ろから聞こえた。突然の鳴き声に驚き、肩を一瞬ビクッとさせてから慌てて振り返った。
やはり人影はなく、代わりに、少しぽっちゃりとした、一匹の可愛らしい茶白猫が目の前にちょこんと坐っていた。赤い首輪をしている。どうやら飼い猫のようだ。榛色の目で何かを訴えかけるかのように、じっと見ている。
「なんだ、猫か。首輪してるな。ってことは、近所の飼い猫か。こんな可愛い子にビビってるようじゃ、俺もまだまだだな。早く帰らないと飼い主さんが心配しちゃうぞ~」
撫でようとその場で屈むと、猫はくるりと背を向け、ゆっくりと歩を進めた。数歩ほど歩くと立ち止まって振り向く。Kさんの方を一瞥して「にゃあ~」と、また大きな声で鳴くと、駐車場の向かい側にある墓地に向かって歩き出した。それは「ついてこい」と言っているように、Kさんには聞こえた、という。
Kさんは、猫のその誘いに乗ることにした。それは単純に面白そうだったから、というのもあるが、Kさんは大の犬猫好きだった。先程、撫で損ねたことが心残りで、隙あらば撫でてやろう、と画策していたのだ。多少引っかかれたり、噛まれたりするのは覚悟の上。それで傷を負っても、彼にとってそれは名誉の負傷である。
時折、猫は立ち止まって、Kさんがついてきているか確認でもしているかのように振り向いた。そして、その姿を一瞥すると、また歩き出すのだ。Kさんは1mほど離れた後ろから、猫の小さくて愛らしい背中を追っていた。ストーカーのような熱視線を送り続ける。相手が人間だったらと思うと、違った意味で背筋が凍る話である。
「ライトとスマホのバッテリーがほとんど残ってない。家までまだ距離あるし、あまり上には登らない方がいいな。戻れなくなったらヤバいし、そんなに時間もないしな。どっかその辺で雰囲気のあるとこがあれば……」
見落としのないよう、再度慎重に辺りを見渡す。
「にゃあ~」
静寂を切り裂くその鳴き声はKさんのすぐ後ろから聞こえた。突然の鳴き声に驚き、肩を一瞬ビクッとさせてから慌てて振り返った。
やはり人影はなく、代わりに、少しぽっちゃりとした、一匹の可愛らしい茶白猫が目の前にちょこんと坐っていた。赤い首輪をしている。どうやら飼い猫のようだ。榛色の目で何かを訴えかけるかのように、じっと見ている。
「なんだ、猫か。首輪してるな。ってことは、近所の飼い猫か。こんな可愛い子にビビってるようじゃ、俺もまだまだだな。早く帰らないと飼い主さんが心配しちゃうぞ~」
撫でようとその場で屈むと、猫はくるりと背を向け、ゆっくりと歩を進めた。数歩ほど歩くと立ち止まって振り向く。Kさんの方を一瞥して「にゃあ~」と、また大きな声で鳴くと、駐車場の向かい側にある墓地に向かって歩き出した。それは「ついてこい」と言っているように、Kさんには聞こえた、という。
Kさんは、猫のその誘いに乗ることにした。それは単純に面白そうだったから、というのもあるが、Kさんは大の犬猫好きだった。先程、撫で損ねたことが心残りで、隙あらば撫でてやろう、と画策していたのだ。多少引っかかれたり、噛まれたりするのは覚悟の上。それで傷を負っても、彼にとってそれは名誉の負傷である。
時折、猫は立ち止まって、Kさんがついてきているか確認でもしているかのように振り向いた。そして、その姿を一瞥すると、また歩き出すのだ。Kさんは1mほど離れた後ろから、猫の小さくて愛らしい背中を追っていた。ストーカーのような熱視線を送り続ける。相手が人間だったらと思うと、違った意味で背筋が凍る話である。
0
あなたにおすすめの小説


意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

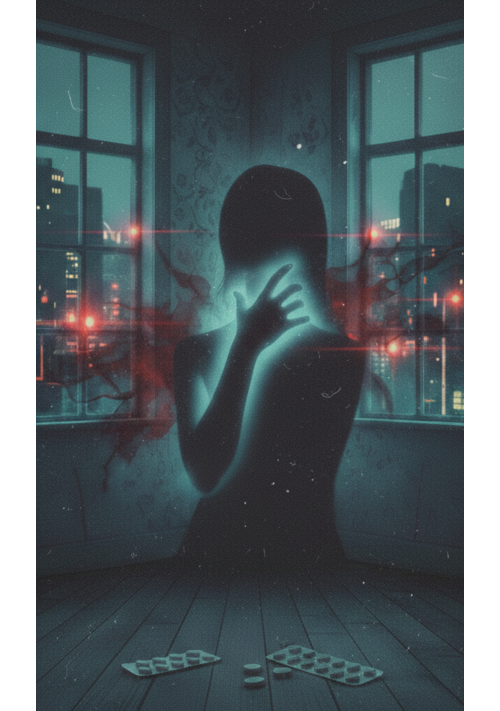
洒落にならない怖い話【短編集】
鍵谷端哉
ホラー
その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。
意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。
隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


意味がわかると怖い話
邪神 白猫
ホラー
【意味がわかると怖い話】解説付き
基本的には読めば誰でも分かるお話になっていますが、たまに激ムズが混ざっています。
※完結としますが、追加次第随時更新※
YouTubeにて、朗読始めました(*'ω'*)
お休み前や何かの作業のお供に、耳から読書はいかがですか?📕
https://youtube.com/@yuachanRio

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















