1 / 6
プロローグ
1
しおりを挟む
子供の頃、近所の汚れた川に落ちたことがある。ひどく濁った川で、緑色と灰色が混ざったみたいな色をした水の中に、お気に入りだった白いワンピースのまま沈んでいった。
一人ぼっちで川に落ちて、私に誰も気づいてくれなくて一人で川から這い上がった時、ワンピースがすっかり汚れていて、それが悲しくて一人きりで濡れたまま泣いていた。妙な生臭い匂いが全身からする中、汚れたワンピースと共に温い気持ちの悪い風に吹かれてひたすら泣いた。
濡れたまま家に帰ると私を見た母は血相を変え、心配してくれるのかと思いきや、いきなり頬を叩いてきた。そのワンピースはもう二度と手に入らないのに、一体なんてことをしてくれたの。母はそう言って怒りながら私のワンピースを玄関で脱がせ、下着姿の私を玄関に放置してワンピースを洗っていた。
結局、ワンピースは白に戻ることはなくて、私は薄汚れた色になって外に干されて揺れているワンピースを見た時思ったのだ。ああ、私もこのワンピースと同じだと。もう二度と前の私には戻れないのだと、その時ようやく実感した。
「へぇー大学一年生ね。勤務希望日数多いねぇ、まあ、香椎さんちょっと地味だけど若いし、採用かな。ところで経験人数何人?」
下卑た目でこちらを見てくる胡散臭い風貌をした男に、私はどうしたらいいのか戸惑うこともなく、処女です、とはっきり言う。
汚れた川に身を落として早十一年。これ以上その川に身を沈めることは出来ないと思っていた底の方まで落ちたはずだったのに、私はさらに底へ落ちていこうとしていた。
「マジで?なのに風俗?あーでも処女かぁ、フェラとかの技術もなんもないんだよね。なら少し練習しよっか、ちょっとこっちおいで。」
男の目に明確な、なんらかの感情が宿ったのが見えて、胃の中身をぐちゃぐちゃにかき乱されているような強烈な不快感を覚えた。目眩もしてきて、倒れそうになる中なんとか立ち上がる。
「ごめんなさい、やっぱりやめます。」
それだけ言い放ち、私は必要ないのにと笑われた履歴書を机の上から奪い取り、その場から走って逃げて外へ出た。薄灰色に汚れたコンクリートのビルから出てすぐ蹲る。堪えきれない吐き気を抑えるために座り込んだ地面には、誰かが踏みつけて火を消した吸殻が沢山あってまた吐き気が強くなる。
タバコは嫌いだ。臭いし、熱いし、痛いし。私にとってなんのいい思い出もないそれを見るのが苦しくて、目を開けられないまま汚いアスファルトの上についに座り込む。
どうやったって吐き気が止まらなくて動けないままでいると、急な雨が降ってきて座り込む私を容赦なく濡らしていく。着ていた服に染み込んだ雨水がぞっとするほど冷たくて、もともと冷たい体を余計に冷やしていった。慌てるように小走りになる足音が道の窪みに早くも溜まっているらしい水を弾いて、ぴちょんと音を鳴らす。傘が雨を弾く音もする中、みんな足早に私の前を去っていった。
「ねえ君、何してんの。」
雨が止んで、一つの足音が私の前に止まった。閉じた目を開けて顔を上げると、そこに居たのはくたびれたスーツ姿の髭を生やした男の人。その人が自分が濡れるのも厭わず、私に傘をさしてくれていた。
「なんでもないです……。」
「顔色悪いしなんでもないわけないだろ、近くに俺の店があるからおいで。」
男の人は私を引っ張って立ち上がらせ、そのままその店とやらに連れて行く。その間体濡れて冷えていく一方なのに、少しだけ胸が暖かくなった気がする。
「タオルあったっけな……あーないな。」
連れてこられた店の休憩室らしきところで私がずぶ濡れなことも厭わず、ビニール素材のソファーに座らせた男の人は今私を拭くためのタオルを探していた。
こんな真冬に寒いだろ、と休憩室に入った途端暖房の温度を一気にあげて私を温めようとしてくれたせいで、男の人はさっきから冬なのに汗をかいていた。
「あー……すまん、あんまり着たくはないだろうけどひとまずこれ着とけ。」
苦虫を噛み潰したような顔とは小説の中で多数出てくる表現ではあるけれど、私は今目の前でその顔を初めて見た。男の人が手に持っているのはかなり広めのVネックに、スリットが入った短い丈のタイトなワンピース。
ありがとうございます、と頭を下げて指をさされた更衣室に入り、雨水をたっぷり吸い込んで重たく、さらに冷たい服を脱ぎ捨てた。
べちょんと重さを持った音がした時、床を濡らしてしまったことに気づく。脱ぐ前から本来なら気づくはずが気づかないということは、幾分か頭が働いていない証拠だ。風邪、ひいたかも。
鼻腔をくすぐられているような感覚を堪えながら服を着替え、脱いだ服を床から掻き集めてから更衣室を出た。出るとすぐに男の人と目が合って、脱いだ服こっちに貸してくれ、とハンガー片手に言われる。
「お手数おかけします。」
男の人は私の言葉に驚いたような顔をして、そんな言葉初めて言われたと吐き出すように言った。別に普通のことだとは思うけれど、男の人にとっては初めてだったらしい。
ハンガーに服をいくつかかけてから、ハンガーラックに吊るしてそのハンガーラックを暖房の風がよく当たるのかソファーの前に置いた。ぴちょん、ぴちょんと水滴が落ちる音が微かに部屋の中へ響く。
「すみません、床濡らしてしまって。」
「ああ?別に気にすんな、それにしても金稼ぐならあそこのソープはやめとけよ。超悪徳って有名だからな。」
「えっ、そうなんですか。」
下手したらうちの最低賃金より下がるぞ、と男の人は笑いながらソファーから立ち上がり、ウォーターサーバーへ近づいていく。
高賃金保証!なんて書かれていたのにあの煽りは嘘だったのか。そしてそんなところで働こうとしていた自分にショックに近い感情を抱いていると、目の前にコトンと音を立ててマグカップが置かれた。マグカップの中には湯気を立ち上らせるコーヒーが。
「テレビで見たんだが、コーヒーは割と体を温めるらしい。まあ飲んどけ。」
そう言って笑った男の人を見た時、急に涙がにじんできて、急なことすぎて堪えることも出来ずに涙が溢れていた。咄嗟に顔を下げたものの、男の人は私が泣いていることに気づいたようで、少し離れた位置に座り、平気か?と聞いてくる。
「言える範囲でいいが、君みたいなタイプがこんなところに来るまで追い詰められてる理由はなんなんだ。」
服とコーヒー代だと思って話してみろ、と男の人に言われて、握りしめていた両手を見ながら黙り込んだ。右手の手首に巻き付けたガラス製のウサギのチャームがついたブレスレットと共に、左手で冷えた手首を握り込む。こうすると、少しだけ落ち着く。
しばらく黙ってから、意を決するように口を開いた。事の発端は数ヶ月前、大学入学の直前まで遡ることになる。
成績優秀者かつ家庭の経済的事情で大学側から入学費、そして授業料の免除を受けた上、給付型奨学金も最大まで貰えることになりなんとか大学入学をすることが出来ることになった。また、私は家庭事情によって一人暮らしをするための給付型奨学金まで申請し、受理されたこともあり家を出るための準備をしていた。
家を出るための準備とはいうがこの家に私の物はないに等しく、持っていくものが大きめのトートバッグに収まるほど物がない。
服以外に私が持っているものといえば、勉強道具と腕にいつも巻いているウサギのブレスレット、それと小学生の時仲良くなった金髪の男の子と作ったよく分からない工作くらいしかなくて、その事実に乾いた笑いが漏れそうになる。
「瑠璃、家を出るなら仕送り入れなさいよ。」
父と離婚して以来吸うようになったタバコを片手に、やつれた様子の母はそう言った。煙くさい室内の中で私は、分かっていますと頷いて準備を続けるふりをする。母と敬語で話すようになったのは一体いつからだったか。
準備のふりを終え、母がこちらに話しかけてくることもなく、視線を向けてくることもない時を狙って静かに家を出て行く。電車を乗り継ぎ、大学の女子寮へと向かう中、心の中は雲ひとつない空のように晴れ晴れとしていてなんの憂いもなかった。
夢にまで見た一人暮らしをしながら大学の勉強と、家に仕送りを送るためにアルバイトに身を費やしていたこともあってまともな友人は一人しかできなかったけれど、それでもあの家から逃げられただけで充分だった。
毎月膨れ上がっていく仕送りの請求額とヒステリックな母の電話に怯えながらも、一人で生活できているからそれでいいと、それ以上は望まないと思っていたのに現実は優しくない。到底今のアルバイトでは支払えない額の仕送りを請求され無視している中、寮に帰ると部屋の前には母と新しい男がいた。
「瑠璃!あんたどうしてお金を払わないのよ!」
母は廊下で騒ぎ立て、私の頬を思いっきり叩いてくる。痛む頬を抑えてごめんなさい、ごめんなさいと何度も謝るが母は許してくれる気配はなく、男と共にぎゃあぎゃあと声を上げた。
廊下という誰かがいつ通ってもおかしくない場所で騒がれることに恐怖を覚え、私はその場で正座……つまりは土下座の体制になりお金は払うから帰ってくれと何度も泣きながら繰り返し、ようやく母たちは黙ってくれた。
「早く支払いなさい、そうしないとまた来るから。」
母はそう言うと土下座して頭を下げたまま動けない私の頭を、ヒールの高い靴のつま先でぐりぐりと踏みつけて帰っていった。
「だから、お金が欲しくてここへ来ました。」
ここに至るまでの経緯をいくつか省略しながら話す。
「なるほどな、請求額いくらだ。」
なんの感傷もなさそうな声に、分かりきってはいたが肩を落とした自分が気持ち悪い。こんな事情がある人間なんか、この街には呆れるほど溢れているだろうし感傷的にならないのは当たり前だ。それなのにこの人に同情してもらおうとした自分があまりにも気持ち悪くて、なんだか惨めだった。
「30万です。」
「30万か……うちは基本給が2600円だけど、君は週何日、何時間いける?」
もしかして面接が始まっているのだろうか。鞄の中から偶然にも濡れていなかった履歴書を取り出して差し出せば、男の人は目を丸くしてから履歴書を見て笑う。
「お前ほんとに面白いな!えーと週五で、勤務可能時間が八時から二時までか。なら30万のノルマは達成だな。」
仕方ないから店のノルマはなしにしてやるよ、そう言った男の人にまた私は涙が出てきそうになる。沈みこんだ川の底で、思わぬ出会いをしたことへの涙だった。
一人ぼっちで川に落ちて、私に誰も気づいてくれなくて一人で川から這い上がった時、ワンピースがすっかり汚れていて、それが悲しくて一人きりで濡れたまま泣いていた。妙な生臭い匂いが全身からする中、汚れたワンピースと共に温い気持ちの悪い風に吹かれてひたすら泣いた。
濡れたまま家に帰ると私を見た母は血相を変え、心配してくれるのかと思いきや、いきなり頬を叩いてきた。そのワンピースはもう二度と手に入らないのに、一体なんてことをしてくれたの。母はそう言って怒りながら私のワンピースを玄関で脱がせ、下着姿の私を玄関に放置してワンピースを洗っていた。
結局、ワンピースは白に戻ることはなくて、私は薄汚れた色になって外に干されて揺れているワンピースを見た時思ったのだ。ああ、私もこのワンピースと同じだと。もう二度と前の私には戻れないのだと、その時ようやく実感した。
「へぇー大学一年生ね。勤務希望日数多いねぇ、まあ、香椎さんちょっと地味だけど若いし、採用かな。ところで経験人数何人?」
下卑た目でこちらを見てくる胡散臭い風貌をした男に、私はどうしたらいいのか戸惑うこともなく、処女です、とはっきり言う。
汚れた川に身を落として早十一年。これ以上その川に身を沈めることは出来ないと思っていた底の方まで落ちたはずだったのに、私はさらに底へ落ちていこうとしていた。
「マジで?なのに風俗?あーでも処女かぁ、フェラとかの技術もなんもないんだよね。なら少し練習しよっか、ちょっとこっちおいで。」
男の目に明確な、なんらかの感情が宿ったのが見えて、胃の中身をぐちゃぐちゃにかき乱されているような強烈な不快感を覚えた。目眩もしてきて、倒れそうになる中なんとか立ち上がる。
「ごめんなさい、やっぱりやめます。」
それだけ言い放ち、私は必要ないのにと笑われた履歴書を机の上から奪い取り、その場から走って逃げて外へ出た。薄灰色に汚れたコンクリートのビルから出てすぐ蹲る。堪えきれない吐き気を抑えるために座り込んだ地面には、誰かが踏みつけて火を消した吸殻が沢山あってまた吐き気が強くなる。
タバコは嫌いだ。臭いし、熱いし、痛いし。私にとってなんのいい思い出もないそれを見るのが苦しくて、目を開けられないまま汚いアスファルトの上についに座り込む。
どうやったって吐き気が止まらなくて動けないままでいると、急な雨が降ってきて座り込む私を容赦なく濡らしていく。着ていた服に染み込んだ雨水がぞっとするほど冷たくて、もともと冷たい体を余計に冷やしていった。慌てるように小走りになる足音が道の窪みに早くも溜まっているらしい水を弾いて、ぴちょんと音を鳴らす。傘が雨を弾く音もする中、みんな足早に私の前を去っていった。
「ねえ君、何してんの。」
雨が止んで、一つの足音が私の前に止まった。閉じた目を開けて顔を上げると、そこに居たのはくたびれたスーツ姿の髭を生やした男の人。その人が自分が濡れるのも厭わず、私に傘をさしてくれていた。
「なんでもないです……。」
「顔色悪いしなんでもないわけないだろ、近くに俺の店があるからおいで。」
男の人は私を引っ張って立ち上がらせ、そのままその店とやらに連れて行く。その間体濡れて冷えていく一方なのに、少しだけ胸が暖かくなった気がする。
「タオルあったっけな……あーないな。」
連れてこられた店の休憩室らしきところで私がずぶ濡れなことも厭わず、ビニール素材のソファーに座らせた男の人は今私を拭くためのタオルを探していた。
こんな真冬に寒いだろ、と休憩室に入った途端暖房の温度を一気にあげて私を温めようとしてくれたせいで、男の人はさっきから冬なのに汗をかいていた。
「あー……すまん、あんまり着たくはないだろうけどひとまずこれ着とけ。」
苦虫を噛み潰したような顔とは小説の中で多数出てくる表現ではあるけれど、私は今目の前でその顔を初めて見た。男の人が手に持っているのはかなり広めのVネックに、スリットが入った短い丈のタイトなワンピース。
ありがとうございます、と頭を下げて指をさされた更衣室に入り、雨水をたっぷり吸い込んで重たく、さらに冷たい服を脱ぎ捨てた。
べちょんと重さを持った音がした時、床を濡らしてしまったことに気づく。脱ぐ前から本来なら気づくはずが気づかないということは、幾分か頭が働いていない証拠だ。風邪、ひいたかも。
鼻腔をくすぐられているような感覚を堪えながら服を着替え、脱いだ服を床から掻き集めてから更衣室を出た。出るとすぐに男の人と目が合って、脱いだ服こっちに貸してくれ、とハンガー片手に言われる。
「お手数おかけします。」
男の人は私の言葉に驚いたような顔をして、そんな言葉初めて言われたと吐き出すように言った。別に普通のことだとは思うけれど、男の人にとっては初めてだったらしい。
ハンガーに服をいくつかかけてから、ハンガーラックに吊るしてそのハンガーラックを暖房の風がよく当たるのかソファーの前に置いた。ぴちょん、ぴちょんと水滴が落ちる音が微かに部屋の中へ響く。
「すみません、床濡らしてしまって。」
「ああ?別に気にすんな、それにしても金稼ぐならあそこのソープはやめとけよ。超悪徳って有名だからな。」
「えっ、そうなんですか。」
下手したらうちの最低賃金より下がるぞ、と男の人は笑いながらソファーから立ち上がり、ウォーターサーバーへ近づいていく。
高賃金保証!なんて書かれていたのにあの煽りは嘘だったのか。そしてそんなところで働こうとしていた自分にショックに近い感情を抱いていると、目の前にコトンと音を立ててマグカップが置かれた。マグカップの中には湯気を立ち上らせるコーヒーが。
「テレビで見たんだが、コーヒーは割と体を温めるらしい。まあ飲んどけ。」
そう言って笑った男の人を見た時、急に涙がにじんできて、急なことすぎて堪えることも出来ずに涙が溢れていた。咄嗟に顔を下げたものの、男の人は私が泣いていることに気づいたようで、少し離れた位置に座り、平気か?と聞いてくる。
「言える範囲でいいが、君みたいなタイプがこんなところに来るまで追い詰められてる理由はなんなんだ。」
服とコーヒー代だと思って話してみろ、と男の人に言われて、握りしめていた両手を見ながら黙り込んだ。右手の手首に巻き付けたガラス製のウサギのチャームがついたブレスレットと共に、左手で冷えた手首を握り込む。こうすると、少しだけ落ち着く。
しばらく黙ってから、意を決するように口を開いた。事の発端は数ヶ月前、大学入学の直前まで遡ることになる。
成績優秀者かつ家庭の経済的事情で大学側から入学費、そして授業料の免除を受けた上、給付型奨学金も最大まで貰えることになりなんとか大学入学をすることが出来ることになった。また、私は家庭事情によって一人暮らしをするための給付型奨学金まで申請し、受理されたこともあり家を出るための準備をしていた。
家を出るための準備とはいうがこの家に私の物はないに等しく、持っていくものが大きめのトートバッグに収まるほど物がない。
服以外に私が持っているものといえば、勉強道具と腕にいつも巻いているウサギのブレスレット、それと小学生の時仲良くなった金髪の男の子と作ったよく分からない工作くらいしかなくて、その事実に乾いた笑いが漏れそうになる。
「瑠璃、家を出るなら仕送り入れなさいよ。」
父と離婚して以来吸うようになったタバコを片手に、やつれた様子の母はそう言った。煙くさい室内の中で私は、分かっていますと頷いて準備を続けるふりをする。母と敬語で話すようになったのは一体いつからだったか。
準備のふりを終え、母がこちらに話しかけてくることもなく、視線を向けてくることもない時を狙って静かに家を出て行く。電車を乗り継ぎ、大学の女子寮へと向かう中、心の中は雲ひとつない空のように晴れ晴れとしていてなんの憂いもなかった。
夢にまで見た一人暮らしをしながら大学の勉強と、家に仕送りを送るためにアルバイトに身を費やしていたこともあってまともな友人は一人しかできなかったけれど、それでもあの家から逃げられただけで充分だった。
毎月膨れ上がっていく仕送りの請求額とヒステリックな母の電話に怯えながらも、一人で生活できているからそれでいいと、それ以上は望まないと思っていたのに現実は優しくない。到底今のアルバイトでは支払えない額の仕送りを請求され無視している中、寮に帰ると部屋の前には母と新しい男がいた。
「瑠璃!あんたどうしてお金を払わないのよ!」
母は廊下で騒ぎ立て、私の頬を思いっきり叩いてくる。痛む頬を抑えてごめんなさい、ごめんなさいと何度も謝るが母は許してくれる気配はなく、男と共にぎゃあぎゃあと声を上げた。
廊下という誰かがいつ通ってもおかしくない場所で騒がれることに恐怖を覚え、私はその場で正座……つまりは土下座の体制になりお金は払うから帰ってくれと何度も泣きながら繰り返し、ようやく母たちは黙ってくれた。
「早く支払いなさい、そうしないとまた来るから。」
母はそう言うと土下座して頭を下げたまま動けない私の頭を、ヒールの高い靴のつま先でぐりぐりと踏みつけて帰っていった。
「だから、お金が欲しくてここへ来ました。」
ここに至るまでの経緯をいくつか省略しながら話す。
「なるほどな、請求額いくらだ。」
なんの感傷もなさそうな声に、分かりきってはいたが肩を落とした自分が気持ち悪い。こんな事情がある人間なんか、この街には呆れるほど溢れているだろうし感傷的にならないのは当たり前だ。それなのにこの人に同情してもらおうとした自分があまりにも気持ち悪くて、なんだか惨めだった。
「30万です。」
「30万か……うちは基本給が2600円だけど、君は週何日、何時間いける?」
もしかして面接が始まっているのだろうか。鞄の中から偶然にも濡れていなかった履歴書を取り出して差し出せば、男の人は目を丸くしてから履歴書を見て笑う。
「お前ほんとに面白いな!えーと週五で、勤務可能時間が八時から二時までか。なら30万のノルマは達成だな。」
仕方ないから店のノルマはなしにしてやるよ、そう言った男の人にまた私は涙が出てきそうになる。沈みこんだ川の底で、思わぬ出会いをしたことへの涙だった。
0
あなたにおすすめの小説

同期に恋して
美希みなみ
恋愛
近藤 千夏 27歳 STI株式会社 国内営業部事務
高遠 涼真 27歳 STI株式会社 国内営業部
同期入社の2人。
千夏はもう何年も同期の涼真に片思いをしている。しかし今の仲の良い同期の関係を壊せずにいて。
平凡な千夏と、いつも女の子に囲まれている涼真。
千夏は同期の関係を壊せるの?
「甘い罠に溺れたら」の登場人物が少しだけでてきます。全くストーリには影響がないのでこちらのお話だけでも読んで頂けるとうれしいです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉
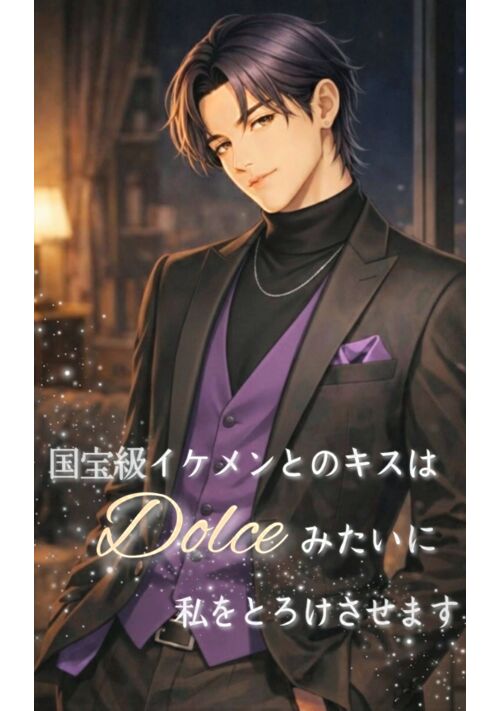
国宝級イケメンとのキスは、ドルチェみたいに私をとろけさせます♡ 〈Dulcisシリーズ〉
はなたろう
恋愛
人気アイドルとの秘密の恋愛♡コウキは俳優やモデルとしても活躍するアイドル。クールで優しいけど、ベッドでは少し意地悪でやきもちやき。彼女の美咲を溺愛し、他の男に取られないかと不安になることも。出会いから交際を経て、甘いキスで溶ける日々の物語。
★みなさまの心にいる、推しを思いながら読んでください
◆出会い編あらすじ
毎日同じ、変わらない。都会の片隅にある植物園で働く美咲。
そこに毎週やってくる、おしゃれで長身の男性。カメラが趣味らい。この日は初めて会話をしたけど、ちょっと変わった人だなーと思っていた。
まさか、その彼が人気アイドル、dulcis〈ドゥルキス〉のメンバーだとは気づきもしなかった。
毎日同じだと思っていた日常、ついに変わるときがきた。
◆登場人物
佐倉 美咲(25) 公園の管理運営企業に勤める。植物園のスタッフから本社の企画営業部へ異動
天見 光季(27) 人気アイドルグループ、dulcis(ドゥルキス)のメンバー。俳優業で活躍中、自然の写真を撮るのが趣味
お読みいただきありがとうございます!
★番外編はこちらに集約してます。
https://www.alphapolis.co.jp/novel/411579529/693947517
★最年少、甘えん坊ケイタとバツイチ×アラサーの恋愛はじめました。
https://www.alphapolis.co.jp/novel/411579529/408954279

カモフラ婚~CEOは溺愛したくてたまらない!~
伊吹美香
恋愛
ウエディングプランナーとして働く菱崎由華
結婚式当日に花嫁に逃げられた建築会社CEOの月城蒼空
幼馴染の二人が偶然再会し、花嫁に逃げられた蒼空のメンツのために、カモフラージュ婚をしてしまう二人。
割り切った結婚かと思いきや、小さいころからずっと由華のことを想っていた蒼空が、このチャンスを逃すはずがない。
思いっきり溺愛する蒼空に、由華は翻弄されまくりでパニック。
二人の結婚生活は一体どうなる?

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

我儘令嬢なんて無理だったので小心者令嬢になったらみんなに甘やかされました。
たぬきち25番
恋愛
「ここはどこですか?私はだれですか?」目を覚ましたら全く知らない場所にいました。
しかも以前の私は、かなり我儘令嬢だったそうです。
そんなマイナスからのスタートですが、文句はいえません。
ずっと冷たかった周りの目が、なんだか最近優しい気がします。
というか、甘やかされてません?
これって、どういうことでしょう?
※後日談は激甘です。
激甘が苦手な方は後日談以外をお楽しみ下さい。
※小説家になろう様にも公開させて頂いております。
ただあちらは、マルチエンディングではございませんので、その関係でこちらとは、内容が大幅に異なります。ご了承下さい。
タイトルも違います。タイトル:異世界、訳アリ令嬢の恋の行方は?!~あの時、もしあなたを選ばなければ~
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















