8 / 12
呪いの本、あるいは若気の至り
2
しおりを挟む
***
「それからずっと、毎晩毎晩それに襲われているらしくて」
渚さんはここ数週間で私の身に起きた出来事を簡単に説明した。学校近くの喫茶店で、私と渚さんの向かい側には緑川律樹という女性と、その助手の一倉景という大柄な男性が並んで座っている。緑川さんは渚さんの大学時代の同期で、霊的な現象に詳しいということで渚さんが呼んでくれたのだ。
私は半袖のセーラー服の下に黒いアームカバーをつけている。腕に残る赤い痕を隠すためだ。首にも痕があるので下に着るシャツもタートルネックのものに変えていた。夜毎襲いくる呪いに私は疲弊していた。縋れるものには何でも縋りたい。けれどそんな私の状態を知ってか知らずか、緑川さんは低い声で言う。
「言っておくけど、私は霊能者とかそういうのじゃないからね」
「わかってるわよ。表向きはオカルト雑誌のライターでしょ?」
緑川さんはオカルト雑誌のライターをする傍ら、怪現象に襲われている人の相談にも乗っているらしい。渚さん曰くかなり頼りになる人とのことだが、会ってみると普通の人に見える。雰囲気だけで言うならば、渚さんの方が余程怪異の専門家じみている。緑川さんは薄い青色のブラウスに黒のスカートを着て、長い髪を低いところで一つに縛っていた。どこかですれ違ってもあまり記憶に残らない、普通の会社員という印象だ。
「それに、私が解決できる範囲は狭いから」
「それは承知の上で、律樹が解決できる問題かどうかをまず判断して欲しいのよ」
「あなたはそれでいいの?」
急に水を向けられ、私は飛び上がりそうになった。緑川の目は特に鋭いわけでもないのに、何か自分の本心を覗かれているような気がする。
「私は……渚さんが、緑川さんはそういうことに強いって聞いて」
「いったいどんな説明をしたのやら……まあいいわ。とりあえず話だけでも聞きましょうか。響子はちょっと外してくれる?」
「え?」
渚さんが緑川さんの言葉に驚いたような声を上げる。渚さんには私の現状は全て話してある。いてもらっても差し障りはない、というか、状況は渚さんが先程話したのが全てで、私がこれ以上言うことはないのだ。それを緑川さんに伝えようと口を開いたそのとき、緑川さんが落ち着いた声で言った。
「響子がいると色々邪魔になって見えないのよ。今日はただでさえ景がいて見づらいから」
「そういえば近くにいると邪魔になる人がいるって言ってたわね。助手君はいいわけ?」
「景はいいの。それに……まあこれはいいや」
緑川さんが何を言おうとしたのかは気になったが、渚さんは不承不承という顔をしながらも店を出て行った。隠れ家風の喫茶店は隠れすぎていて、客は私たちしかいない。初老のマスターはカウンターの後ろで新聞を読み始めていた。
「さて、響子がいなくなったところで……もう一度説明してもらいましょうか。今度はあなた自身の口から」
「えっと……ほとんどさっき渚さんが言ったのと同じなんですが」
「繰り返しになったとしても、あなたが説明することに意味があるのよ。景もちゃんと見ててね」
私は首を傾げながらも順を追って説明した。これで何かがわかるのなら、逆らう意味はないと思ったからだ。図書館の除籍図書の棚から出て来た妙な本。そこに書かれていた意味のわからない言葉の羅列。そして渚さんに聞いた呪いの本の噂と、その通りに起きた怪現象。緑川さんは話を聞きながらも、私の目ではなく、その手前に焦点を合わせているように見えた。
話が終わると、緑川さんは溜息とともにコーヒーを飲み干した。そして私にも、目の前にある紅茶を飲むようにと言う。一息入れた方がいい、というのがその理由だった。私が紅茶を飲むと、緑川さんは静かに話し始める。
「呪いっていうのは、色々な種類があるの。強い思いが怪異になってしまったものだとか、人の思いが淀む場所で生まれてしまうものとか、あと、死んだ人間がその恨みから使うものとか。でもそれとは別に、自分で自分に呪いを掛けてしまうというものもある」
「自分で、自分に?」
「『自分は呪われてしまった』と思うことで、本当に呪われているような症状が出ることがある。例えば……こっくりさんが失敗したときの話とかは聞いたことある?」
「はい。狐に取り憑かれたみたいな行動を取ったりとか、体調を崩したりとか……」
「稀に本物の怪異を呼び寄せてしまっている場合もあるのだけど、大抵は儀式が中途半端で何も呼べていない。それなのに失敗したと思って、体調を崩してしまったり、奇行に走ってしまう人はいる。その原因は怪異ではなく、人間の感情が作り出してしまった何かなのよ。まあ怪異みたいなものではあるんだけど……バターとマーガリンくらいは違うわね」
同じように使うものだけれど、別物だ。たとえがそれでいいのかはわからなかったが、緑川さんが言いたいことは大体理解できた。
「それって、プラシーボ効果みたいなことですか?」
「そう。現代の呪いは大抵それだったりするのよ。だから、呪いをかけたのはあなた自身と言えなくもない。でも今回の場合は違うわね」
自分の思い込みからこんなことになっているのであれば、それが種明かしされてしまった以上は恐れるものではない。そう思ったのに、緑川はそれは違うと言う。緑川は鞄の中から小さなリングノートとペンを取り出し、何も書いていないページを開いた。
「『るばしをて』で始まる意味不明な言葉だけれど、あれはそのまま反対にすると、『手を縛る』になる。『手を縛る、歯を縛る、骨を縛る』から始まる呪文は、ネットで調べると沢山のページがヒットしてしまうくらいには有名なもの。言ってしまえば、それを逆にするという発想さえ浮かべば誰にだってあの言葉を書くことができる。その意味不明に見える言葉の中に、ランダムにキーワードをちりばめたのがあの本というわけ」
そういえば、夜に聞こえる声は確かにその呪文を口にしていた。それに私もその呪文自体は以前見たことがある。
「そういうわけで、あの本を作った人は、呪いに関しては素人と私は判断する。うちの雑誌には載せられないレベルの稚拙さね」
「十分不気味ではありましたけど……」
「そうね。不気味さの演出には成功している。そこに『呪いの本』の噂話が加われば、呪いとしてちゃんと完成するのよ。まあ受け手が『呪いの本』のことを全く気にしないような人間なら何の効果もないんだけどね。あとは本をよく読む人って言葉から何かを想像する力が強いから」
つまりは全て私の思い込みが原因だったということか。安堵すると同時に拍子抜けした。何日も苦しんだものなのに、それを作り出したのが他でもない自分自身なんて、そんな酷い話があるだろうか。呪いの本のことなんて気にしなければ良かったのだ。でもあのときはあの本そのものの不気味さもさることながら、渚さんに見せようとしたら忽然と姿を消していたことや、渚さんが教えてくれた噂話などが頭の中で絡み合って、ありもしない怪異を作り出してしまったのだ。
人騒がせだったと恥ずかしく思い俯いた私は、はたと気が付いた。
あの噂話を知らなければこんなことにはならなかった。そしてあのとき、書庫にいたのは私と渚さんだけだった。私はあの本を隠してはいない。隠したのが怪異の類でないのなら、それができるのはただ一人だ。
それで腑に落ちる。緑川さんが渚さんをこの場から追い出した理由、それは――。
「もうわかった? 誰がその呪いを仕掛けたか」
「……渚さんが、どうして私に」
「それは本人に聞いた方が早いわね。どうせその辺でソワソワしてると思うから呼んできて、景」
一倉さんは緑川さんの言葉に頷き、喫茶店を出て行った。けれど私はそれどころではなかった。渚さんは私を害そうとしていたのか。でも彼女に恨まれるようなことは何もしていない。それとも本を見つけた人間なら誰でも良かったのか。
「――結城さん」
私の思考を止めるように、緑川さんが言う。
「結論から言うと、響子にあなたを傷つけようという意図はなかったはず。ただ、まあ……聞くと幻滅するかもしれないくらい、しょうもない話が始まることは覚悟しておいて」
どういうことだろうかと首を傾げたそのとき、一倉さんが渚さんを連れて戻ってきた。渚さんの手にはあの「呪いの本」があった。あのときは不気味だと思ったそれは、正体を知った今ではただの古びた本にしか見えなかった。
***
「この本は、私が高校生のときに作って、こっそり蔵書印を押して図書館の棚に紛れ込ませたものなの。とっくに処分されたものだと思っていたけど、まさかここで出てくるとは……」
緑川さんに促され、渚さんは頭を抱えながらそう言った。確かにこの仕草からは悪意のようなものは読み取れない。犯人がトリックを暴かれたときというよりは、隠していた恥ずかしい過去を暴露されてしまったときのようだ。
「で、そもそもなんでこんなもの作ったのよ」
「当時、文芸部に所属してたんだけどね……ホラー小説が書きたいのにどうしても上手く書けなくて。だったら自分で都市伝説の類を作れないかと思ったのよ。本を作って、呪いの本の噂を流して……噂が噂を育てたら、上手く行くんじゃないかと思って」
緑川さんが溜息を吐く。やったことは言ってしまえば悪戯の範囲だ。高校生にもなってそんなことを、と思われる可能性はあるが、娯楽が少なかった女子校の中ではそれがいいスパイスになったのだろう。
「でも、あのときは噂は広まったけど、結局本を見つけて呪われた人もいなかったから……効果なんて出ないんだと思ってしまって。高校生のときのことは黒歴史だったから、思わず本も隠しちゃって、それで終わりだと思ったんだけど」
渚さんが俯く。嘘を言っているようには見えなかった。本当に渚さんには悪意はなかったのだ。実際に酷い目に遭った私からすれば迷惑な話ではあるものの、少なくとも私のことが嫌いだとか恨んでいるというわけではなかったから安心した。
「でも、私が作った本が原因になってるのは間違いないから……律樹なら何とか出来るかなと思ったの」
「おかげで黒歴史も暴かれちゃったけどね」
「それはまあ……結城さんの呪いが解決するなら、私の黒歴史くらい」
「……だそうだけど。正直、結城さんは響子をぶん殴っても許されると思うけど、どうする?」
渚さんに対する怒りはなかった。そもそも、自分がやったことが暴かれるということもわかっていて緑川さんを呼んだのだ。私は渚さんを安心させるために笑みを浮かべた。
「もう解決したなら、それでいいです。私も自分の本を図書館に紛れ込ませようとか、思ったことはあるし……」
「本当にごめんなさい。まさかこんなことになるとは思ってなかったの」
日が暮れて、外から差し込む光が暗くなっていく。そろそろこの喫茶店も閉店の時間が近づいているようだった。緑川さんは一倉さんを伴って立ち上がる。
「それじゃ、もう大丈夫みたいだから帰るわね。お金はもらったけど、東京からじゃさすがに遠すぎるわよ、ここ。記事にもならない事件だったし」
「ありがとう、律樹。お礼に今度いい資料紹介するわよ」
「大丈夫。編集長に『ついでに消えた村の取材してきて』って言われてるから」
「その村の資料だけど?」
緑川さんの顔色が変わる。すっかりオカルト雑誌のライターの顔になって渚さんに詰め寄る緑川さんと、緑川さんを宥めながら説明を始める渚さん。傍から見ていると愉快なやりとりだな、と思いながら、蚊帳の外の私と一倉さんは目を見合わせた。
***
「ごめんなさいね、本当に」
「だから大丈夫ですって、渚さん」
「この本はもう処分することにするわ。黒歴史だし……また同じようなことが起きても良くないし」
渚さんの手には、渚さんが作った呪いの本がある。確かに処分するのが妥当なのだろう。それこそ同じようなことが起きるのは良くないし、渚さんにとっては恥ずかしい過去だ。けれど私はその本を渚さんの手から奪い取った。
「本の形をしてるものが処分できない質なんですよ、私」
「結城さん……」
「渚さんがいらないなら、これは私がもらいます。折角綺麗に製本してるのに、捨てるなんてもったいない」
「でも、それのせいで大変なことになったのに」
確かにそうだ。でも正体を知ってしまった今となっては、もう不気味な本でも何でもなくなってしまっている。でも、どんな本であっても本は本だ。私が愛すべきものなのだ。
「もうこれで呪われる人が出ないように、私がしっかり管理します。それでいいじゃないですか」
「えっと……文句を言える立場ではないんだけど、ちょっと恥ずかしいというか何というか……。あの頃は、そうやって自分が作ったものが広がっていくのが楽しかったのよね。自分が何者かになれた気がして。でも……結局私は特別な誰かにはなれなかった。律樹が羨ましいことも、たまにあるのよ」
渚さんはどこか遠くを見つめている。同じような気持ちは私にもあった。自分が作ったものが広がっていくのを見るのは楽しいだろう。誰だって特別になりたい。それは渚さんだけが抱く感情ではないのだ。
「そういえば、緑川さんって……実際何者なんですか?」
「一応オカルト雑誌のライターが本業なんだけどね。でも、人間の心が作り出す怪異を専門に解決する仕事もしてるの」
今回のことは、緑川さんの専門分野だったらしい。渚さんはそれがわかっていたから、最初から緑川さんを呼んだのだ。
「あの人ね、他人の心が見えるのよ。といっても何を考えているかが全部わかるわけではなくて、その人の心の多くを占めるのが何なのか……心配だったり、恐怖だったり、欲望だったり……そういうのが、靄のように見えるんだって」
「オーラの発展系、みたいな感じなんですかね」
「さあ、私にははっきりとしたことはわからないけど……。律樹の力は生きている人間にしか使えないから、死んだ人間とか、本物の妖怪とかそういうものに対して何かが出来るわけじゃない。そのためにあの助手君がいるらしいんだけど……それでも、あんな風に特別な何かが出来るのは羨ましいわね」
高校生のときの渚さんは、自分の手で呪いの噂を作ろうとした。それはきっと、特別な何かになりたいという思春期の欲求もあったのだろう。そして大人になったとしても、それは簡単に消えるものではない。ただ、もう特別な何かにはなれないと諦めて、受け入れて生きていくことを選んでいるだけだ。
「私は……本のことなら何でも知ってる渚さんも特別だと思いますよ」
「え?」
「渚さんみたいに本に詳しい人になりたいって、ずっと思ってるので」
私には人の感情なんて見えなくてもいい。むしろ大好きな本のことをこの頭の中に沢山詰め込みたい。そんなものは機械に任せておけと言う人もいるかもしれないけれど、私がそうありたいと思うことを誰かにとやかく言われる筋合いはないのだ。
「結城さんって、本当に本が好きなのね」
「幼稚園の卒園文集の将来の夢に『世界一の図書館に住む』って書いたくらいですよ」
渚さんが安心したように笑った。私は渚さんからタイトルのない、渚さんが作った呪いの本を受け取る。これは今夜から私の本棚に加わる。どんな本でも本は本だ。一冊増える度に私の喜びも増えていく。
「それからずっと、毎晩毎晩それに襲われているらしくて」
渚さんはここ数週間で私の身に起きた出来事を簡単に説明した。学校近くの喫茶店で、私と渚さんの向かい側には緑川律樹という女性と、その助手の一倉景という大柄な男性が並んで座っている。緑川さんは渚さんの大学時代の同期で、霊的な現象に詳しいということで渚さんが呼んでくれたのだ。
私は半袖のセーラー服の下に黒いアームカバーをつけている。腕に残る赤い痕を隠すためだ。首にも痕があるので下に着るシャツもタートルネックのものに変えていた。夜毎襲いくる呪いに私は疲弊していた。縋れるものには何でも縋りたい。けれどそんな私の状態を知ってか知らずか、緑川さんは低い声で言う。
「言っておくけど、私は霊能者とかそういうのじゃないからね」
「わかってるわよ。表向きはオカルト雑誌のライターでしょ?」
緑川さんはオカルト雑誌のライターをする傍ら、怪現象に襲われている人の相談にも乗っているらしい。渚さん曰くかなり頼りになる人とのことだが、会ってみると普通の人に見える。雰囲気だけで言うならば、渚さんの方が余程怪異の専門家じみている。緑川さんは薄い青色のブラウスに黒のスカートを着て、長い髪を低いところで一つに縛っていた。どこかですれ違ってもあまり記憶に残らない、普通の会社員という印象だ。
「それに、私が解決できる範囲は狭いから」
「それは承知の上で、律樹が解決できる問題かどうかをまず判断して欲しいのよ」
「あなたはそれでいいの?」
急に水を向けられ、私は飛び上がりそうになった。緑川の目は特に鋭いわけでもないのに、何か自分の本心を覗かれているような気がする。
「私は……渚さんが、緑川さんはそういうことに強いって聞いて」
「いったいどんな説明をしたのやら……まあいいわ。とりあえず話だけでも聞きましょうか。響子はちょっと外してくれる?」
「え?」
渚さんが緑川さんの言葉に驚いたような声を上げる。渚さんには私の現状は全て話してある。いてもらっても差し障りはない、というか、状況は渚さんが先程話したのが全てで、私がこれ以上言うことはないのだ。それを緑川さんに伝えようと口を開いたそのとき、緑川さんが落ち着いた声で言った。
「響子がいると色々邪魔になって見えないのよ。今日はただでさえ景がいて見づらいから」
「そういえば近くにいると邪魔になる人がいるって言ってたわね。助手君はいいわけ?」
「景はいいの。それに……まあこれはいいや」
緑川さんが何を言おうとしたのかは気になったが、渚さんは不承不承という顔をしながらも店を出て行った。隠れ家風の喫茶店は隠れすぎていて、客は私たちしかいない。初老のマスターはカウンターの後ろで新聞を読み始めていた。
「さて、響子がいなくなったところで……もう一度説明してもらいましょうか。今度はあなた自身の口から」
「えっと……ほとんどさっき渚さんが言ったのと同じなんですが」
「繰り返しになったとしても、あなたが説明することに意味があるのよ。景もちゃんと見ててね」
私は首を傾げながらも順を追って説明した。これで何かがわかるのなら、逆らう意味はないと思ったからだ。図書館の除籍図書の棚から出て来た妙な本。そこに書かれていた意味のわからない言葉の羅列。そして渚さんに聞いた呪いの本の噂と、その通りに起きた怪現象。緑川さんは話を聞きながらも、私の目ではなく、その手前に焦点を合わせているように見えた。
話が終わると、緑川さんは溜息とともにコーヒーを飲み干した。そして私にも、目の前にある紅茶を飲むようにと言う。一息入れた方がいい、というのがその理由だった。私が紅茶を飲むと、緑川さんは静かに話し始める。
「呪いっていうのは、色々な種類があるの。強い思いが怪異になってしまったものだとか、人の思いが淀む場所で生まれてしまうものとか、あと、死んだ人間がその恨みから使うものとか。でもそれとは別に、自分で自分に呪いを掛けてしまうというものもある」
「自分で、自分に?」
「『自分は呪われてしまった』と思うことで、本当に呪われているような症状が出ることがある。例えば……こっくりさんが失敗したときの話とかは聞いたことある?」
「はい。狐に取り憑かれたみたいな行動を取ったりとか、体調を崩したりとか……」
「稀に本物の怪異を呼び寄せてしまっている場合もあるのだけど、大抵は儀式が中途半端で何も呼べていない。それなのに失敗したと思って、体調を崩してしまったり、奇行に走ってしまう人はいる。その原因は怪異ではなく、人間の感情が作り出してしまった何かなのよ。まあ怪異みたいなものではあるんだけど……バターとマーガリンくらいは違うわね」
同じように使うものだけれど、別物だ。たとえがそれでいいのかはわからなかったが、緑川さんが言いたいことは大体理解できた。
「それって、プラシーボ効果みたいなことですか?」
「そう。現代の呪いは大抵それだったりするのよ。だから、呪いをかけたのはあなた自身と言えなくもない。でも今回の場合は違うわね」
自分の思い込みからこんなことになっているのであれば、それが種明かしされてしまった以上は恐れるものではない。そう思ったのに、緑川はそれは違うと言う。緑川は鞄の中から小さなリングノートとペンを取り出し、何も書いていないページを開いた。
「『るばしをて』で始まる意味不明な言葉だけれど、あれはそのまま反対にすると、『手を縛る』になる。『手を縛る、歯を縛る、骨を縛る』から始まる呪文は、ネットで調べると沢山のページがヒットしてしまうくらいには有名なもの。言ってしまえば、それを逆にするという発想さえ浮かべば誰にだってあの言葉を書くことができる。その意味不明に見える言葉の中に、ランダムにキーワードをちりばめたのがあの本というわけ」
そういえば、夜に聞こえる声は確かにその呪文を口にしていた。それに私もその呪文自体は以前見たことがある。
「そういうわけで、あの本を作った人は、呪いに関しては素人と私は判断する。うちの雑誌には載せられないレベルの稚拙さね」
「十分不気味ではありましたけど……」
「そうね。不気味さの演出には成功している。そこに『呪いの本』の噂話が加われば、呪いとしてちゃんと完成するのよ。まあ受け手が『呪いの本』のことを全く気にしないような人間なら何の効果もないんだけどね。あとは本をよく読む人って言葉から何かを想像する力が強いから」
つまりは全て私の思い込みが原因だったということか。安堵すると同時に拍子抜けした。何日も苦しんだものなのに、それを作り出したのが他でもない自分自身なんて、そんな酷い話があるだろうか。呪いの本のことなんて気にしなければ良かったのだ。でもあのときはあの本そのものの不気味さもさることながら、渚さんに見せようとしたら忽然と姿を消していたことや、渚さんが教えてくれた噂話などが頭の中で絡み合って、ありもしない怪異を作り出してしまったのだ。
人騒がせだったと恥ずかしく思い俯いた私は、はたと気が付いた。
あの噂話を知らなければこんなことにはならなかった。そしてあのとき、書庫にいたのは私と渚さんだけだった。私はあの本を隠してはいない。隠したのが怪異の類でないのなら、それができるのはただ一人だ。
それで腑に落ちる。緑川さんが渚さんをこの場から追い出した理由、それは――。
「もうわかった? 誰がその呪いを仕掛けたか」
「……渚さんが、どうして私に」
「それは本人に聞いた方が早いわね。どうせその辺でソワソワしてると思うから呼んできて、景」
一倉さんは緑川さんの言葉に頷き、喫茶店を出て行った。けれど私はそれどころではなかった。渚さんは私を害そうとしていたのか。でも彼女に恨まれるようなことは何もしていない。それとも本を見つけた人間なら誰でも良かったのか。
「――結城さん」
私の思考を止めるように、緑川さんが言う。
「結論から言うと、響子にあなたを傷つけようという意図はなかったはず。ただ、まあ……聞くと幻滅するかもしれないくらい、しょうもない話が始まることは覚悟しておいて」
どういうことだろうかと首を傾げたそのとき、一倉さんが渚さんを連れて戻ってきた。渚さんの手にはあの「呪いの本」があった。あのときは不気味だと思ったそれは、正体を知った今ではただの古びた本にしか見えなかった。
***
「この本は、私が高校生のときに作って、こっそり蔵書印を押して図書館の棚に紛れ込ませたものなの。とっくに処分されたものだと思っていたけど、まさかここで出てくるとは……」
緑川さんに促され、渚さんは頭を抱えながらそう言った。確かにこの仕草からは悪意のようなものは読み取れない。犯人がトリックを暴かれたときというよりは、隠していた恥ずかしい過去を暴露されてしまったときのようだ。
「で、そもそもなんでこんなもの作ったのよ」
「当時、文芸部に所属してたんだけどね……ホラー小説が書きたいのにどうしても上手く書けなくて。だったら自分で都市伝説の類を作れないかと思ったのよ。本を作って、呪いの本の噂を流して……噂が噂を育てたら、上手く行くんじゃないかと思って」
緑川さんが溜息を吐く。やったことは言ってしまえば悪戯の範囲だ。高校生にもなってそんなことを、と思われる可能性はあるが、娯楽が少なかった女子校の中ではそれがいいスパイスになったのだろう。
「でも、あのときは噂は広まったけど、結局本を見つけて呪われた人もいなかったから……効果なんて出ないんだと思ってしまって。高校生のときのことは黒歴史だったから、思わず本も隠しちゃって、それで終わりだと思ったんだけど」
渚さんが俯く。嘘を言っているようには見えなかった。本当に渚さんには悪意はなかったのだ。実際に酷い目に遭った私からすれば迷惑な話ではあるものの、少なくとも私のことが嫌いだとか恨んでいるというわけではなかったから安心した。
「でも、私が作った本が原因になってるのは間違いないから……律樹なら何とか出来るかなと思ったの」
「おかげで黒歴史も暴かれちゃったけどね」
「それはまあ……結城さんの呪いが解決するなら、私の黒歴史くらい」
「……だそうだけど。正直、結城さんは響子をぶん殴っても許されると思うけど、どうする?」
渚さんに対する怒りはなかった。そもそも、自分がやったことが暴かれるということもわかっていて緑川さんを呼んだのだ。私は渚さんを安心させるために笑みを浮かべた。
「もう解決したなら、それでいいです。私も自分の本を図書館に紛れ込ませようとか、思ったことはあるし……」
「本当にごめんなさい。まさかこんなことになるとは思ってなかったの」
日が暮れて、外から差し込む光が暗くなっていく。そろそろこの喫茶店も閉店の時間が近づいているようだった。緑川さんは一倉さんを伴って立ち上がる。
「それじゃ、もう大丈夫みたいだから帰るわね。お金はもらったけど、東京からじゃさすがに遠すぎるわよ、ここ。記事にもならない事件だったし」
「ありがとう、律樹。お礼に今度いい資料紹介するわよ」
「大丈夫。編集長に『ついでに消えた村の取材してきて』って言われてるから」
「その村の資料だけど?」
緑川さんの顔色が変わる。すっかりオカルト雑誌のライターの顔になって渚さんに詰め寄る緑川さんと、緑川さんを宥めながら説明を始める渚さん。傍から見ていると愉快なやりとりだな、と思いながら、蚊帳の外の私と一倉さんは目を見合わせた。
***
「ごめんなさいね、本当に」
「だから大丈夫ですって、渚さん」
「この本はもう処分することにするわ。黒歴史だし……また同じようなことが起きても良くないし」
渚さんの手には、渚さんが作った呪いの本がある。確かに処分するのが妥当なのだろう。それこそ同じようなことが起きるのは良くないし、渚さんにとっては恥ずかしい過去だ。けれど私はその本を渚さんの手から奪い取った。
「本の形をしてるものが処分できない質なんですよ、私」
「結城さん……」
「渚さんがいらないなら、これは私がもらいます。折角綺麗に製本してるのに、捨てるなんてもったいない」
「でも、それのせいで大変なことになったのに」
確かにそうだ。でも正体を知ってしまった今となっては、もう不気味な本でも何でもなくなってしまっている。でも、どんな本であっても本は本だ。私が愛すべきものなのだ。
「もうこれで呪われる人が出ないように、私がしっかり管理します。それでいいじゃないですか」
「えっと……文句を言える立場ではないんだけど、ちょっと恥ずかしいというか何というか……。あの頃は、そうやって自分が作ったものが広がっていくのが楽しかったのよね。自分が何者かになれた気がして。でも……結局私は特別な誰かにはなれなかった。律樹が羨ましいことも、たまにあるのよ」
渚さんはどこか遠くを見つめている。同じような気持ちは私にもあった。自分が作ったものが広がっていくのを見るのは楽しいだろう。誰だって特別になりたい。それは渚さんだけが抱く感情ではないのだ。
「そういえば、緑川さんって……実際何者なんですか?」
「一応オカルト雑誌のライターが本業なんだけどね。でも、人間の心が作り出す怪異を専門に解決する仕事もしてるの」
今回のことは、緑川さんの専門分野だったらしい。渚さんはそれがわかっていたから、最初から緑川さんを呼んだのだ。
「あの人ね、他人の心が見えるのよ。といっても何を考えているかが全部わかるわけではなくて、その人の心の多くを占めるのが何なのか……心配だったり、恐怖だったり、欲望だったり……そういうのが、靄のように見えるんだって」
「オーラの発展系、みたいな感じなんですかね」
「さあ、私にははっきりとしたことはわからないけど……。律樹の力は生きている人間にしか使えないから、死んだ人間とか、本物の妖怪とかそういうものに対して何かが出来るわけじゃない。そのためにあの助手君がいるらしいんだけど……それでも、あんな風に特別な何かが出来るのは羨ましいわね」
高校生のときの渚さんは、自分の手で呪いの噂を作ろうとした。それはきっと、特別な何かになりたいという思春期の欲求もあったのだろう。そして大人になったとしても、それは簡単に消えるものではない。ただ、もう特別な何かにはなれないと諦めて、受け入れて生きていくことを選んでいるだけだ。
「私は……本のことなら何でも知ってる渚さんも特別だと思いますよ」
「え?」
「渚さんみたいに本に詳しい人になりたいって、ずっと思ってるので」
私には人の感情なんて見えなくてもいい。むしろ大好きな本のことをこの頭の中に沢山詰め込みたい。そんなものは機械に任せておけと言う人もいるかもしれないけれど、私がそうありたいと思うことを誰かにとやかく言われる筋合いはないのだ。
「結城さんって、本当に本が好きなのね」
「幼稚園の卒園文集の将来の夢に『世界一の図書館に住む』って書いたくらいですよ」
渚さんが安心したように笑った。私は渚さんからタイトルのない、渚さんが作った呪いの本を受け取る。これは今夜から私の本棚に加わる。どんな本でも本は本だ。一冊増える度に私の喜びも増えていく。
0
あなたにおすすめの小説

それなりに怖い話。
只野誠
ホラー
これは創作です。
実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。
本当に、実際に起きた話ではございません。
なので、安心して読むことができます。
オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。
不定期に章を追加していきます。
2025/12/23:『みこし』の章を追加。2025/12/30の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/22:『かれんだー』の章を追加。2025/12/29の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/21:『おつきさまがみている』の章を追加。2025/12/28の朝8時頃より公開開始予定。
2025/12/20:『にんぎょう』の章を追加。2025/12/27の朝8時頃より公開開始予定。
2025/12/19:『ひるさがり』の章を追加。2025/12/26の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/18:『いるみねーしょん』の章を追加。2025/12/25の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/17:『まく』の章を追加。2025/12/24の朝4時頃より公開開始予定。
※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。


意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【1分読書】意味が分かると怖いおとぎばなし
響ぴあの
ホラー
【1分読書】
意味が分かるとこわいおとぎ話。
意外な事実や知らなかった裏話。
浦島太郎は神になった。桃太郎の闇。本当に怖いかちかち山。かぐや姫は宇宙人。白雪姫の王子の誤算。舌切りすずめは三角関係の話。早く人間になりたい人魚姫。本当は怖い眠り姫、シンデレラ、さるかに合戦、はなさかじいさん、犬の呪いなどなど面白い雑学と創作短編をお楽しみください。
どこから読んでも大丈夫です。1話完結ショートショート。
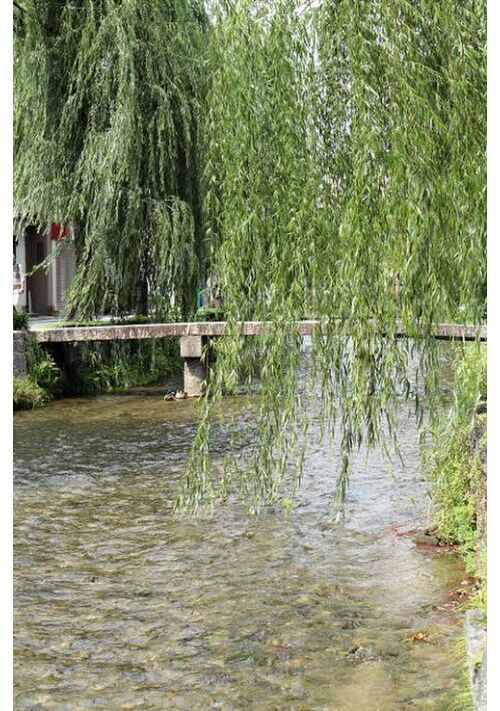

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】
絢郷水沙
ホラー
普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。
下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。
※全話オリジナル作品です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















