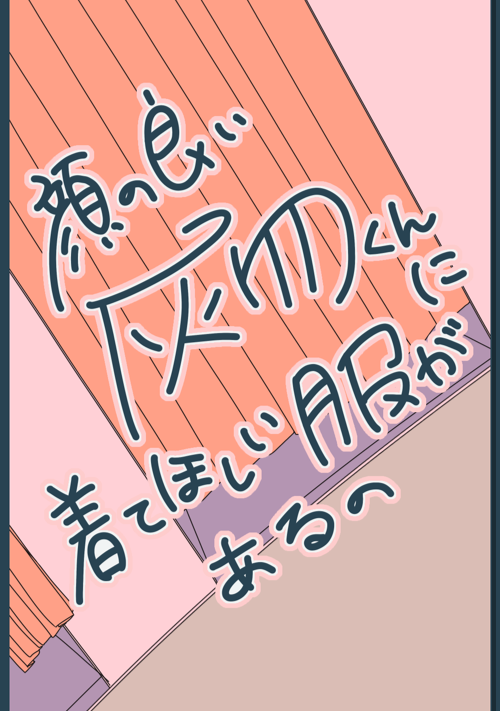64 / 122
第三章
いざ、出発
しおりを挟む
「姉上! 今日の姉上はとってもキレイです! もちろんいつもキレイですが、今日はすごくすごくキレイで、キラキラ輝いています! 女神様のようです!」
10歳男子の持っている全ての褒め言葉を繰り出し、全力で姉を褒め讃えるアルフォンス。
「髪型もステキだし、ドレスもステキで似合っているし、今日のパーティーでは、絶対姉上が一番ステキで注目されます!」
「ありがとう。アルフォンスに褒めてもらえて自信がついたわ」
エリザベートは微笑んでアルフォンスの頭を撫で、アルフォンスもニコニコだ。
「出来る事なら僕がエスコートしたいです。でもまだ子供だから……ルーク! ちゃんと姉上をお守りするんだぞ! 姉上の美しさに引き寄せられて集まって来る男共を近づけないように!」
「はいっ、アルフォンス様」
ピシッと姿勢を正して返事をするルークに、アルフォンスは『うんうん』と頷いている。
最近ルークは剣の腕前が上がり、アルフォンスに『まあまあだ』と一応認められた。
「じゃあ、そろそろ出ようかしら」
「はい、エリザベート様」
エスコートの仕方についてみっちり指導されたルークが手を差し出し、その上に手を重ねてエリザベートは部屋を出た。アルフォンス、アメリア、マダム・ポッピン、そして公爵家のお針子達や侍女達も見送りの為に後に続く。
「エリザベート様、お気をつけて」
「ええ。皆、朝からご苦労様。この後はゆっくり休んでね」
そしてエリザベートはルークと一緒に、公爵家で二番目に豪華な馬車に乗り込んだ。ちなみに、一番いい馬車は当主専用で、スピネル公爵と夫人を乗せて王城に向け出発済である。
「……朝早くからこの時間まで、磨かれて揉まれて塗られて着せられて……もう、パーティー前からヘトヘトだわ」
「私は、緊張で倒れそうです」
息苦しそうに言うルークに、エリザベートは思わず笑ってしまった。
「大丈夫よルーク。もっとリラックスしなさい。髪も耳もツヤツヤ輝いているし、お肌はツルツルだし、衣装がとっても似合っていて完璧よ。ダンスもマナーもあんなに一生懸命学んだのだから、自信をもって!」
「ですが、私の失態はエリザベート様の名誉に傷をつける事になります。絶対に失敗しないようにしなくちゃ……」
「いいのよ、そんなに気負わなくて」
向かいに座っているルークの、腿の上でギュッと握りしめている手に、自分の手をそっと重ねる。
「一人で出席するのが嫌で貴方を巻き込んでしまったわけだけれど、わたくしとしては、ルークと一緒にパーティーに出席する事をかなり楽しみにしているのよ。獣人を蔑視する人がいる事は確かだけれど、貴方が可愛くて、綺麗で、素敵な事も事実よ。そんな貴方とパーティーに出られる事は、わたくしにとって自慢できる事だわ。嫌な思いもするだろうけど、この王都で暮らしていくには表に出て認められることも必要だからね」
「はい!」
真剣な表情で、頷くルーク。
「わたくしは名ばかりの王太子婚約者で、貴方は獣人で、そしてこの衣装。もう、目立って注目を集める要素ばかりだけれど、だからこそ、顔を上げて胸を張って行きましょう」
「はいっ!」
敵地に乗り込むような気持ちで、二人は王城へ向かった。
「スピネル公爵令嬢エリザベート様、ようこそお越し、ください、ました……あの、こちらは……」
「わたくしのパートナーです」
「えー、しかしながら、エリザベート様、本日は王太子殿下の成年パーティーでして、その……こちらのパートナーの方との出席は、いかがなものかと……」
会場の前でさっそく足止めをくらってしまったが、想定内の事である。
「ルーク、あれを」
「はい」
エリザベートに指示され、ルークは一枚の紙を出す。
「これは、王太子殿下からいただいた許可証です。わたくしが、パートナーを伴ってパーティーに参加する事に対し、何も問題はないと書いてありますでしょう?」
「た、確かに……」
「と、言うことですので、早く案内していただけます?」
「はい、かしこまりました」
案内係は深くお辞儀をし、二人を会場内へと案内した。
(こうなる事は予想していたわ。後で問題にされるのは嫌だから、ちゃんと手を打っておいて良かった)
『わたくしを伴って入場する気がないのでしたら、わたくしが別のパートナーと出席する事を認め、許可するという証明書を頂きたく存じます。もしそれを頂けないのであれば、パーティーは欠席致します』
とても嫌だったが、レオンハルトに手紙を出し、手に入れた許可証だ。
(早く婚約破棄してくれれば、こんなものわざわざもらわなくてもよかったのに……結局、婚約破棄しないままパーティー当日になってしまったわ)
そんな事を思いながら会場に入ると、一気に視線が注がれるのを感じた。
「誰だ? あの二人」
「なに? あの変わったドレス」
「他国からの貴賓かしら」
「ちょっと、あれって、エリザベート様じゃない?」
「ええ? まあ! 本当だわ」
「そういえば、獣人の奴隷を買ったとの噂を聞いたわ。ペットを連れて来たわけ?」
「王太子殿下が男爵令嬢に夢中だからって、自暴自棄になっているのかしら」
「警護ならわかるが、招待客として獣人がこの場にいるっていうのが気に食わん」
そんな声が聞こえてきたが、二人は堂々と中へ進んだ。
『こういう事言われそうじゃない?』『きっとこんな事も』と、二人でシミュレーションし、直接言われない限り無視する事に決めている。もし直接言われたら、王太子の許可証と、公爵家の権威発動である。
「リザ! ずいぶん待ちましたわ!」
最初に話しかけてきたのは、ヴィクトリアだった。
胴の部分は紫、袖とスカートは明るいライラック色のドレス姿だ。白いレースとリボンで飾られ広めに開いた襟ぐり、キュッと絞ったウエストと大きく広がったスカート。可愛らしさと大人っぽさがあいまって、とてもよく似合っている。
「素敵なドレスね、ヴィヴィ。それにリアムくんも似合っているわ」
「ありがとうございます」
ヴィクトリアと同じライラック色のコートに、紫のウエストコートと半ズボン、白のソックスという姿で、ニッコリ笑うリアム。首元と袖口には大量のレースが見えるが、これもヴィクトリアと同じレースを使っている。
(最初マダム・ポッピンが作ろうとしたのは、こういう衣装だったのでしょうね。確かに、ルークの可愛さがよく引き立ちそうだけど、わたしと並んだら姉弟っぽかったかもしれないわ)
リアムを観察しながらそんな事を考えていると、
「それにしてもリザのドレス、変わってるわね」
しげしげと、エリザベートを見るヴィクトリア。
「スカートが全然膨らんでいないし、遠目ではちょっと地味に感じたけれど、近くで見ると、光沢のある生地に金糸の刺繍、ケープは総レースでしかもパール付きなんて、物凄く豪華だわ。このドレスの形も洗練されていて素敵。こんなの、初めて見たわ」
「ありがとう。今回は今までと違う仕立て屋に作ってもらったの。逸材を見つけてね」
「まあ! リザにはいつも驚かされるわ。ねえ、わたくしも作ってもらいたいんだけど、紹介してくださらない?」
「いいけど、この布、虫由来の布よ。ヴィヴィ、大丈夫?」
「ムシ?」
「……シルクか」
ギョッとしたように聞き返すヴィクトリアの背後からそう呟いたのは、ザカリー・オニキスだった。
10歳男子の持っている全ての褒め言葉を繰り出し、全力で姉を褒め讃えるアルフォンス。
「髪型もステキだし、ドレスもステキで似合っているし、今日のパーティーでは、絶対姉上が一番ステキで注目されます!」
「ありがとう。アルフォンスに褒めてもらえて自信がついたわ」
エリザベートは微笑んでアルフォンスの頭を撫で、アルフォンスもニコニコだ。
「出来る事なら僕がエスコートしたいです。でもまだ子供だから……ルーク! ちゃんと姉上をお守りするんだぞ! 姉上の美しさに引き寄せられて集まって来る男共を近づけないように!」
「はいっ、アルフォンス様」
ピシッと姿勢を正して返事をするルークに、アルフォンスは『うんうん』と頷いている。
最近ルークは剣の腕前が上がり、アルフォンスに『まあまあだ』と一応認められた。
「じゃあ、そろそろ出ようかしら」
「はい、エリザベート様」
エスコートの仕方についてみっちり指導されたルークが手を差し出し、その上に手を重ねてエリザベートは部屋を出た。アルフォンス、アメリア、マダム・ポッピン、そして公爵家のお針子達や侍女達も見送りの為に後に続く。
「エリザベート様、お気をつけて」
「ええ。皆、朝からご苦労様。この後はゆっくり休んでね」
そしてエリザベートはルークと一緒に、公爵家で二番目に豪華な馬車に乗り込んだ。ちなみに、一番いい馬車は当主専用で、スピネル公爵と夫人を乗せて王城に向け出発済である。
「……朝早くからこの時間まで、磨かれて揉まれて塗られて着せられて……もう、パーティー前からヘトヘトだわ」
「私は、緊張で倒れそうです」
息苦しそうに言うルークに、エリザベートは思わず笑ってしまった。
「大丈夫よルーク。もっとリラックスしなさい。髪も耳もツヤツヤ輝いているし、お肌はツルツルだし、衣装がとっても似合っていて完璧よ。ダンスもマナーもあんなに一生懸命学んだのだから、自信をもって!」
「ですが、私の失態はエリザベート様の名誉に傷をつける事になります。絶対に失敗しないようにしなくちゃ……」
「いいのよ、そんなに気負わなくて」
向かいに座っているルークの、腿の上でギュッと握りしめている手に、自分の手をそっと重ねる。
「一人で出席するのが嫌で貴方を巻き込んでしまったわけだけれど、わたくしとしては、ルークと一緒にパーティーに出席する事をかなり楽しみにしているのよ。獣人を蔑視する人がいる事は確かだけれど、貴方が可愛くて、綺麗で、素敵な事も事実よ。そんな貴方とパーティーに出られる事は、わたくしにとって自慢できる事だわ。嫌な思いもするだろうけど、この王都で暮らしていくには表に出て認められることも必要だからね」
「はい!」
真剣な表情で、頷くルーク。
「わたくしは名ばかりの王太子婚約者で、貴方は獣人で、そしてこの衣装。もう、目立って注目を集める要素ばかりだけれど、だからこそ、顔を上げて胸を張って行きましょう」
「はいっ!」
敵地に乗り込むような気持ちで、二人は王城へ向かった。
「スピネル公爵令嬢エリザベート様、ようこそお越し、ください、ました……あの、こちらは……」
「わたくしのパートナーです」
「えー、しかしながら、エリザベート様、本日は王太子殿下の成年パーティーでして、その……こちらのパートナーの方との出席は、いかがなものかと……」
会場の前でさっそく足止めをくらってしまったが、想定内の事である。
「ルーク、あれを」
「はい」
エリザベートに指示され、ルークは一枚の紙を出す。
「これは、王太子殿下からいただいた許可証です。わたくしが、パートナーを伴ってパーティーに参加する事に対し、何も問題はないと書いてありますでしょう?」
「た、確かに……」
「と、言うことですので、早く案内していただけます?」
「はい、かしこまりました」
案内係は深くお辞儀をし、二人を会場内へと案内した。
(こうなる事は予想していたわ。後で問題にされるのは嫌だから、ちゃんと手を打っておいて良かった)
『わたくしを伴って入場する気がないのでしたら、わたくしが別のパートナーと出席する事を認め、許可するという証明書を頂きたく存じます。もしそれを頂けないのであれば、パーティーは欠席致します』
とても嫌だったが、レオンハルトに手紙を出し、手に入れた許可証だ。
(早く婚約破棄してくれれば、こんなものわざわざもらわなくてもよかったのに……結局、婚約破棄しないままパーティー当日になってしまったわ)
そんな事を思いながら会場に入ると、一気に視線が注がれるのを感じた。
「誰だ? あの二人」
「なに? あの変わったドレス」
「他国からの貴賓かしら」
「ちょっと、あれって、エリザベート様じゃない?」
「ええ? まあ! 本当だわ」
「そういえば、獣人の奴隷を買ったとの噂を聞いたわ。ペットを連れて来たわけ?」
「王太子殿下が男爵令嬢に夢中だからって、自暴自棄になっているのかしら」
「警護ならわかるが、招待客として獣人がこの場にいるっていうのが気に食わん」
そんな声が聞こえてきたが、二人は堂々と中へ進んだ。
『こういう事言われそうじゃない?』『きっとこんな事も』と、二人でシミュレーションし、直接言われない限り無視する事に決めている。もし直接言われたら、王太子の許可証と、公爵家の権威発動である。
「リザ! ずいぶん待ちましたわ!」
最初に話しかけてきたのは、ヴィクトリアだった。
胴の部分は紫、袖とスカートは明るいライラック色のドレス姿だ。白いレースとリボンで飾られ広めに開いた襟ぐり、キュッと絞ったウエストと大きく広がったスカート。可愛らしさと大人っぽさがあいまって、とてもよく似合っている。
「素敵なドレスね、ヴィヴィ。それにリアムくんも似合っているわ」
「ありがとうございます」
ヴィクトリアと同じライラック色のコートに、紫のウエストコートと半ズボン、白のソックスという姿で、ニッコリ笑うリアム。首元と袖口には大量のレースが見えるが、これもヴィクトリアと同じレースを使っている。
(最初マダム・ポッピンが作ろうとしたのは、こういう衣装だったのでしょうね。確かに、ルークの可愛さがよく引き立ちそうだけど、わたしと並んだら姉弟っぽかったかもしれないわ)
リアムを観察しながらそんな事を考えていると、
「それにしてもリザのドレス、変わってるわね」
しげしげと、エリザベートを見るヴィクトリア。
「スカートが全然膨らんでいないし、遠目ではちょっと地味に感じたけれど、近くで見ると、光沢のある生地に金糸の刺繍、ケープは総レースでしかもパール付きなんて、物凄く豪華だわ。このドレスの形も洗練されていて素敵。こんなの、初めて見たわ」
「ありがとう。今回は今までと違う仕立て屋に作ってもらったの。逸材を見つけてね」
「まあ! リザにはいつも驚かされるわ。ねえ、わたくしも作ってもらいたいんだけど、紹介してくださらない?」
「いいけど、この布、虫由来の布よ。ヴィヴィ、大丈夫?」
「ムシ?」
「……シルクか」
ギョッとしたように聞き返すヴィクトリアの背後からそう呟いたのは、ザカリー・オニキスだった。
応援ありがとうございます!
31
お気に入りに追加
4,408
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる