4 / 28
第4章: 冷たい歓迎
しおりを挟む
ヴァルトハイムの王宮に到着した私は、あまりの豪華さに一瞬息を飲んだ。
けれど、その驚きはすぐに冷たく鋭い視線に押しつぶされることとなった。
王宮の使用人たちは皆、まるで私が見るからに怪しい者であるかのような目を向けてくる。
それもそのはずだ。
私は正式な王族ではない、いわば見知らぬ異国から送り込まれた花嫁もどきなのだから。
「ふぅ…まあ、予想通りの歓迎よね」
自嘲気味に呟いてみたものの、心の中はざわざわとして落ち着かない。
そんな私の不安をさらに煽るように、正面から歩いてきたのは彼――ヴァルトハイムの王太子、レオニードだった。
背が高くて、整った顔立ち。
そして何より目を引くのは、その鋭い青い瞳。
まるで氷のように冷たく、刺さるような視線だった。
「君が誰であれ、私にとってはただの取引だ」
彼が初めて発した言葉はこれだった。
一瞬、耳を疑った。
けれど、その冷たい声と無表情な顔を見た瞬間、すぐに理解した。
彼は本気だ。
本気で、私をただの道具としか見ていないのだと。
「……」
返す言葉が見つからず、ただその場に立ち尽くしてしまった。
「黙っていればいい。余計なことは何もするな。それが唯一の条件だ」
彼の冷ややかな声が突き刺さる。
その言葉のあと、彼は私に背を向け、その場を立ち去った。
その晩、私は広すぎる寝室にひとり置き去りにされた。
天井の高い部屋、絢爛豪華な調度品、ふかふかのベッド。
まるで夢のような空間のはずなのに、私は一歩も動けなかった。
「これが、私の居場所…?」
思わず呟いた言葉が、あまりにも空しく響く。
リヴィアから冷たく送り出され、ここでも冷たい目を向けられ、取引だと切り捨てられる。
「…何やってるんだろう、私」
気づけば、涙が頬を伝っていた。
それでも、私は自分に言い聞かせる。
「泣いてる場合じゃない」と。
「私には誇りがある。どんなに冷たく扱われても、私は…私は自分を見失わないから。」
口に出してみると、少しだけ心が軽くなった気がした。
そのときだった。
ドアが小さくノックされ、私は驚いて顔を上げた。
「失礼いたします、アリシア様」
現れたのは侍女のひとりだった。
彼女は緊張した面持ちで、何か言いたげに私の前に立つ。
「…どうかしました?」
「実は、レオニード殿下が…」
その名前を聞いた瞬間、心臓が跳ねる。
「殿下がどうされたの?」
「…いえ、あの、殿下は特に何も。ただ…」
侍女は言葉を濁したけれど、その表情から察するに、何かあるらしい。
「大丈夫です。話して」
「殿下はいつもそうなんです。冷たくて、無愛想で…でも、実はとても繊細なお方で…」
繊細?
あの冷たい目をした彼が?
「それはどういう意味?」
「…殿下はあまり人を信じられないのです。ですから、アリシア様もきっと、殿下にとってはまだ“未知”なのでしょう」
未知。
そう言われると、少しだけ彼に興味が湧いてきた。
「…ありがとう。話してくれて」
侍女に礼を言い、再びひとりきりになると、私はベッドに腰を下ろした。
彼が私をどう思っているのか、そんなことは分からない。
でも、彼が私を“未知”だと思っているのなら――私にも、彼を知るチャンスがあるのかもしれない。
「未知、ね」
そう呟いた瞬間、なぜか胸が少しだけ暖かくなった。
これから何が起こるのか分からないけれど、私は諦めない。
たとえ彼が冷たくても、私には自分の道を切り開く力があるのだと信じるしかないのだから。
けれど、その驚きはすぐに冷たく鋭い視線に押しつぶされることとなった。
王宮の使用人たちは皆、まるで私が見るからに怪しい者であるかのような目を向けてくる。
それもそのはずだ。
私は正式な王族ではない、いわば見知らぬ異国から送り込まれた花嫁もどきなのだから。
「ふぅ…まあ、予想通りの歓迎よね」
自嘲気味に呟いてみたものの、心の中はざわざわとして落ち着かない。
そんな私の不安をさらに煽るように、正面から歩いてきたのは彼――ヴァルトハイムの王太子、レオニードだった。
背が高くて、整った顔立ち。
そして何より目を引くのは、その鋭い青い瞳。
まるで氷のように冷たく、刺さるような視線だった。
「君が誰であれ、私にとってはただの取引だ」
彼が初めて発した言葉はこれだった。
一瞬、耳を疑った。
けれど、その冷たい声と無表情な顔を見た瞬間、すぐに理解した。
彼は本気だ。
本気で、私をただの道具としか見ていないのだと。
「……」
返す言葉が見つからず、ただその場に立ち尽くしてしまった。
「黙っていればいい。余計なことは何もするな。それが唯一の条件だ」
彼の冷ややかな声が突き刺さる。
その言葉のあと、彼は私に背を向け、その場を立ち去った。
その晩、私は広すぎる寝室にひとり置き去りにされた。
天井の高い部屋、絢爛豪華な調度品、ふかふかのベッド。
まるで夢のような空間のはずなのに、私は一歩も動けなかった。
「これが、私の居場所…?」
思わず呟いた言葉が、あまりにも空しく響く。
リヴィアから冷たく送り出され、ここでも冷たい目を向けられ、取引だと切り捨てられる。
「…何やってるんだろう、私」
気づけば、涙が頬を伝っていた。
それでも、私は自分に言い聞かせる。
「泣いてる場合じゃない」と。
「私には誇りがある。どんなに冷たく扱われても、私は…私は自分を見失わないから。」
口に出してみると、少しだけ心が軽くなった気がした。
そのときだった。
ドアが小さくノックされ、私は驚いて顔を上げた。
「失礼いたします、アリシア様」
現れたのは侍女のひとりだった。
彼女は緊張した面持ちで、何か言いたげに私の前に立つ。
「…どうかしました?」
「実は、レオニード殿下が…」
その名前を聞いた瞬間、心臓が跳ねる。
「殿下がどうされたの?」
「…いえ、あの、殿下は特に何も。ただ…」
侍女は言葉を濁したけれど、その表情から察するに、何かあるらしい。
「大丈夫です。話して」
「殿下はいつもそうなんです。冷たくて、無愛想で…でも、実はとても繊細なお方で…」
繊細?
あの冷たい目をした彼が?
「それはどういう意味?」
「…殿下はあまり人を信じられないのです。ですから、アリシア様もきっと、殿下にとってはまだ“未知”なのでしょう」
未知。
そう言われると、少しだけ彼に興味が湧いてきた。
「…ありがとう。話してくれて」
侍女に礼を言い、再びひとりきりになると、私はベッドに腰を下ろした。
彼が私をどう思っているのか、そんなことは分からない。
でも、彼が私を“未知”だと思っているのなら――私にも、彼を知るチャンスがあるのかもしれない。
「未知、ね」
そう呟いた瞬間、なぜか胸が少しだけ暖かくなった。
これから何が起こるのか分からないけれど、私は諦めない。
たとえ彼が冷たくても、私には自分の道を切り開く力があるのだと信じるしかないのだから。
0
あなたにおすすめの小説

つまらない妃と呼ばれた日
柴田はつみ
恋愛
公爵令嬢リーシャは政略結婚で王妃に迎えられる。だが国王レオニスの隣には、幼馴染のセレスが“当然”のように立っていた。祝宴の夜、リーシャは国王が「つまらない妃だ」と語る声を聞いてしまい、心を閉ざす。
舞踏会で差し出された手を取らず、王弟アドリアンの助けで踊ったことで、噂は一気に燃え上がる――「王妃は王弟と」「国王の本命は幼馴染」と。
さらに宰相は儀礼と世論を操り、王妃を孤立させる策略を進める。監視の影、届かない贈り物、すり替えられた言葉、そして“白薔薇の香”が事件現場に残る冤罪の罠。
リーシャは微笑を鎧に「今日から、王の隣に立たない」と決めるが、距離を取るほど誤解は確定し、王宮は二人を引き裂いていく。
――つまらない妃とは、いったい誰が作ったのか。真実が露わになった時、失われた“隣”は戻るのか。

【完結】仰る通り、貴方の子ではありません
ユユ
恋愛
辛い悪阻と難産を経て産まれたのは
私に似た待望の男児だった。
なのに認められず、
不貞の濡れ衣を着せられ、
追い出されてしまった。
実家からも勘当され
息子と2人で生きていくことにした。
* 作り話です
* 暇つぶしにどうぞ
* 4万文字未満
* 完結保証付き
* 少し大人表現あり

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い
青の雀
恋愛
夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。
神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。
もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。
生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。
過去世と同じ轍を踏みたくない……
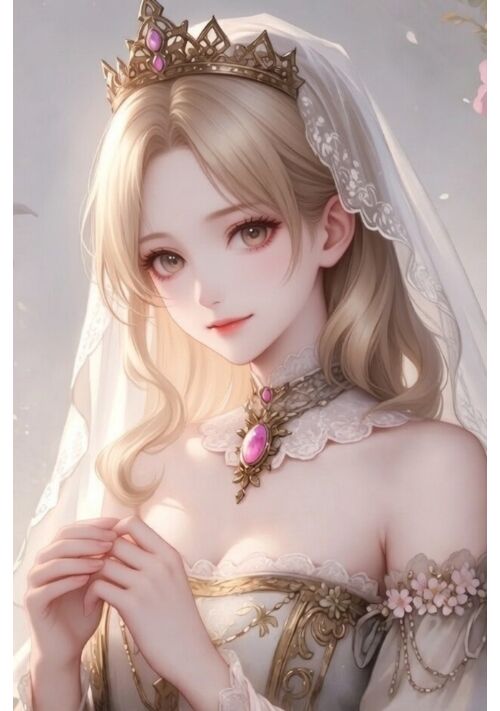
スキルなし王妃の逆転劇〜妹の策略で悪役令嬢にされ、婚約破棄された私が冷酷王の心を歌で揺らすまで〜
雪城 冴
恋愛
聖歌もファンファーレもない無音の結婚式。
「誓いの言葉は省略する」
冷酷王の宣言に、リリアナは言葉を失った。
スキル名を持たないという理由だけで“無能”と蔑まれてきたリリアナ。
妹の企みにより婚約破棄され、隣国の王・オスカーとの政略結婚が決まる。
義妹は悪魔のような笑みで言う。
「次は婚約破棄されないようにお気をつけて」
リリアナに残されたのは、自分を慰めるように歌うことだけ。
ところが、魔力が満ちるはずの王国には、舞踏会すら開かれない不気味な静寂が広がっていた。
――ここは〈音のない国〉
冷酷王が隠している“真実”とは?
そして、リリアナの本当のスキルとは――。
勇気と知性で運命を覆す、
痛快逆転ファンタジー。
※表紙絵はAI生成

前世で追放された王女は、腹黒幼馴染王子から逃げられない
ria_alphapolis
恋愛
前世、王宮を追放された王女エリシアは、
幼馴染である王太子ルシアンに見捨てられた――
そう思ったまま、静かに命を落とした。
そして目を覚ますと、なぜか追放される前の日。
人生、まさかの二周目である。
「今度こそ関わらない。目立たず、静かに生きる」
そう決意したはずなのに、前世では冷酷無比だった幼馴染王子の様子がおかしい。
距離、近い。
護衛、多い。
視線、重い。
挙げ句の果てに告げられたのは、彼との政略結婚。
しかもそれが――彼自身の手で仕組まれたものだと知ってしまう。
どうやらこの幼馴染王子、
前世で何かを盛大に後悔したらしく、
二度目の人生では王女を逃がす気が一切ない。
「愛されていなかった」と思い込む王女と、
「二度と手放さない」と決めた腹黒王子の、
少し物騒で、わりと甘い執着政略結婚ラブストーリー。

嘘をありがとう
七辻ゆゆ
恋愛
「まあ、なんて図々しいのでしょう」
おっとりとしていたはずの妻は、辛辣に言った。
「要するにあなた、貴族でいるために政略結婚はする。けれど女とは別れられない、ということですのね?」
妻は言う。女と別れなくてもいい、仕事と嘘をついて会いに行ってもいい。けれど。
「必ず私のところに帰ってきて、子どもをつくり、よい夫、よい父として振る舞いなさい。神に嘘をついたのだから、覚悟を決めて、その嘘を突き通しなさいませ」

新婚初夜に『白い結婚にしてほしい』と言われたので論理的に詰めたら夫が泣きました
ささい
恋愛
「愛人がいるから、白い結婚にしてほしい」
政略結婚の初夜にそう告げた夫ルーファス。
妻カレンの反応は——
「それ、契約不履行ですよね?」
「あなたの感情論、論理的に破綻してますよ?」
泣き落としは通じない。
そして初夜の翌朝、夫は泣いていた。
逃げ道は全部塞がれ、気づけば毎日論破されていた。
これは、論破され続けた夫がなぜか幸せになる話。

辺境伯夫人は領地を紡ぐ
やまだごんた
恋愛
王命によりヴァルデン辺境伯に嫁ぐことになった、前ベルンシュタイン公爵令嬢のマルグリット。
しかし、彼女を待っていたのは60年にも及ぶ戦争で荒廃し、冬を越す薪すら足りない現実だった。
物資も人手も足りない中、マルグリットは領地の立て直しに乗り出す。
戦しか知らなかったと自省する夫と向き合いながら、少しずつ築かれていく夫婦の距離。
これは、1人の女性が領地を紡ぎ、夫と共に未来を作る「内政×溺愛」の物語です。
全50話の予定です
※表紙はイメージです
※アルファポリス先行公開(なろうにも転載予定です)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















