4 / 20
4. 誘拐
しおりを挟む二週間後。
その日イグナーツは、接近戦のための剣術の訓練を受けていた。
ガギンという音とともに、イグナーツの持っていた剣が払われてどさりと地面に落ちる。
「勝負あり、ブルム二等兵の勝利!」
審判の声に、見ていた隊員たちがわあわあと騒ぐ。
「トット准尉よえー」
「2分ともたなかったぞ」
「やっぱ親が“ラミア”だからじゃねえの」
なんだそれ。イグナーツはむっと眉を寄せたが、何も言わずに剣を拾った。そして次の順番の隊員と入れ替わるようにして試合場から退散する。
イグナーツとて、自分が接近戦には向かないことをよくわかっていた。12歳で入隊してからずっと鍛えてきたつもりだが、中肉中背の彼は剣を持ったところで力の強い大男相手に打ち合いでは敵わない。
もちろんほんとうの戦闘中には銃が弾切れになったときに結局剣を使うときもある。そのために少しでも制御できるようにならなければならなかった。
「薪割り、毎日やった方がいいんじゃないですか」
後ろから声をかけられ、イグナーツは眉を寄せて振り向いた。去年入隊したばかりのヨアキム・ミュラーという若者だ。剣術ではイグナーツに勝るのでこんな口を聞くのだろう。
イグナーツはすぐに顔を背けると「余計なお世話だ」と言ったが、ヨアキムはにやにやしながら続けた。
「剣が弱くても准尉になれるんですね。トット准尉は軍部の人事にコネがなさそうですから実力なんですよね? きっと軍部の将校たちも大したことないんだろうなあ」
「舐めたこと抜かしやがる」
イグナーツとヨアキムの少し離れたところから突然低く唸るような声がした。聞き覚えのある声にイグナーツは心中で「ひえ」と悲鳴を上げた。どうやら今の話が聞こえてしまったらしい。
イグナーツは恐る恐るちらりと振り返ってみた。思った通り、本日の訓練の教官を務めるリッツ大佐が、怖い笑みを浮かべながら近づいてきてくる。そうだ、この人は恐ろしく地獄耳だった。イグナーツは逃げようと後ずさったが、リッツ大佐の熊のような大きな手で肩をがっと掴まれてしまった。もう動けない。
縦にも横にも大きいリッツ大佐は、イグナーツのすぐ横からヨアキムを見下ろすようにして言った。
「お前は、このトット准尉が先のドルイ戦で何人敵をやったか知らんだろう。レート戦のときゃ、信じられん距離から敵将の頭を撃ち抜いたんだぞ、ゲルト戦のときもだ。弱いなんて戯言は戦場で活躍してから言うんだな……舐めた口聞いてると、そのうちこいつにやられるかもしれんぞ。脳天を狙うことなんざ、こいつは造作もねえんだ。しかも遠距離からだからな、お前がぼうっとしてる間にズドン、だ」
やるわけないだろう、敵でもないのに。イグナーツは眉をしかめてリッツ大佐を見上げた。
一方でヨアキムの方は彼の言葉をすっかり本気にしてしまい、イグナーツの不満そうな顔を見ると「ひっ!」と悲鳴を漏らし、一瞬のうちにその場から居なくなってしまった。
リッツ大佐は「へっ、腰抜けが」と言って去っていく青年を見送ってから、変な顔をしてこちらを見ているイグナーツに視線を向けた。
「おい、トット准尉。あんな鼻垂れ小僧に言いたい放題言われて、いつも黙ってるってのか?」
「鼻垂れ小僧って、彼はそんな歳じゃありませんよ……俺ああいうのは慣れてるんです、もう言われ過ぎてますから。それよりも戦場であいつが銃で撃たれたとき俺のせいにされたらどうしてくれるんですか」
「戦場で誰のせいもあるか。全部敵のせいにしちまえばいいんだ」
めちゃくちゃ言うな、この人。ともあれ、がははと笑っているリッツ大佐がようやく手をイグナーツの肩から離してくれたので、距離をおこうとした。
「待て、トット准尉」
リッツ大佐はイグナーツの腕をガッと掴んで振り向かせた。
「さっきの試合に関してお前にアドバイスしてやる。剣を構えろーーおおい、お前らも注目しろいっ!」
大佐のドスの効いた声に、訓練場の隊員たちが皆二人の周りに集まってきた。
「いいか、お前が苦手な状況ーー自分よりも大柄で力のある相手が来ることを想定する。そういう時は不意をつくしか手はない。どんな手を使ってもいい。ほら、やってみろ」
「無理ですよ、俺は……うわっ」
問答無用で振り下ろしてきた上官の剣を慌てて避けると、仕方なく剣を構えた。
再びリッツ大佐が剣を振り上げたので、イグナーツは咄嗟に受けの体制を取った。しかしそれに対してリッツ大佐は「受けようとするな、重みには耐えられんぞ!」と怒鳴ってきたので再び避けた。イグナーツだってそんなことはわかっている。だからさっきの剣術試合で剣を落としたのだ。不意をつくしか手はないって言われても、結局どうすればいいんだ。
しかしそのとき、ふと大佐の仁王立ちした大股がイグナーツの目に入った。咄嗟にかかんでその間を素早くくぐり抜けると、大佐が振り向く前に背中に剣を当てることができた。
「おおー」という低い歓声があちこちから上がる。リッツ大佐は嬉しそうにわははと笑い声を上げた。
「なんだお前、できるじゃねえか! 今までめんどくさがって考えてなかっただけだろ?」
「え、いや、そういうわけじゃ……」
「これからは相手の不意をつくことを第一に動け。次にやる試合でまたさっきみたいに大剣を受け止めようとしたら、腕立て1000回だぞ」
つまり気を抜くなということだ。リッツ大佐はイグナーツの嫌そうな顔を見て満足そうに笑うと、周りにいた隊員たちに向かって言った。
「いいか、お前らも咄嗟の判断で相手の不意をつけるよう、常に頭を回転させながら剣を持て! 腕力以外でも剣術で勝てる方法はいくらでもある、わかったか!」
「「はいっ!」」
リッツ大佐の大声に、隊員たちの返事の声が響く。それからは試合場での剣の打ち合いが再開された。やっと自分から離れていく大佐の背中を見送りながら、イグナーツは頭をかいた。
すごい人だ。俺みたいな剣が不得意な人間に、あっという間に自信をつけさせて、周りの士気まであげてしまう。イグナーツは前に自分が小銃の撃ち方の教えを乞われたことを思い出し、教えるとはこういうことなのだなと思った。
事が起きたのはそれからしばらくしてからのことだった。
隊舎の門の方から誰かが馬に乗ってものすごい勢いでこちらに向かってきた。まず地響きで隊員たちはそれに気づいた。
そのただならぬ様子に、剣の打ち合いをしていた隊員たちは思わず手を止め、皆やってくる人物は何者かと様子を窺った。
イグナーツは目を細めた。あれはディーボルト中尉だ。精悍な顔を険しくさせている。何かあったのだ。
「リッツ大佐っ!」
ディーボルト中尉は、大佐の前まで馬を走らせてやってくると、はあはあと息を吐きながら馬を降り、敬礼しながら言った。
「侯爵の娘が誘拐されました!」
イグナーツは目を見開いた。侯爵の娘だって?
リッツ大佐は「なんだと?」と声を上げると、中尉が息を吸い込みながら言った。
「すぐに本部で緊急会議が行われます、この馬をお使いください! この場は私が引き受けます、後から追いかけますので」
ディーボルト中尉の額には汗が流れ、金髪は乱雑に振り乱されている。しかし息を切らせているにもかかわらず、中尉の言葉は澱みないものだった。
リッツ大佐は「悪いな」と言って中尉の肩を叩くと、すぐに馬に乗った。
「剣術の訓練はしまいだ、隊員たちには念のためにいつでも出動できるよう準備させておけ」
リッツ大佐は中尉に指示を出すと、瞬く間に馬を走らせて隊舎の門の向こうへと行ってしまった。隊員たちはそちらの方へと目をやっていたが、すぐにディーボルト中尉をわっと囲んだ。
「どういうことですか、ディーボルト中尉!」
「緊急会議って何事ですか!?」
「また国境で戦ですか?」
「侯爵って誰ですか!?」
口々に隊員たちが尋ねるのに、ディーボルト中尉は両手を広げて「まてまてまて!」と制した。
「まず、これは国内の誘拐事件だ。今の段階で他国との戦争は起こらない。リッツ大佐は出動の準備とおっしゃったが、実際のところ第三部隊は必要ない状況だ。犯人は少数、しかも村のごろつきだ」
「で、でも、それならなんでわざわざリッツ大佐が……」
ひとりの隊員が口を挟んだのに、ディーボルト中尉は「リッツ大佐が呼ばれたのは」と続けた。
「誘拐されたのが侯爵家のご令嬢だからだ。名家のお嬢さんが巻き込まれたのに軍が動かないとしめしがつかないだろう」
ディーボルト中尉が言ったのに隊員たちはああそうかと頷いたが、イグナーツはひとり、いや違うと思った。
中尉は家名を言わなかったが、あの慌てぶりはクラッセン侯爵家に違いない。軍部がとくに目をつけていた侯爵の娘が何者かに攫われたのだ、だから緊急会議となったのだろう。しかしあのビアンカ嬢が攫われただって? 誰の仕業だろう。目的はなんだ、まさか父親の自作自演だろうか。
イグナーツがぐるぐると考えているうちに、ディーボルト中尉が訓練中だった隊員全員に聞こえるように声を張って言った。
「本日の昼練はここまでとする。夜練の担当はフェーン大尉の指示に従うように。以上、解散!」
ディーボルト中尉の言葉に、隊員たちはざわざわしながらも隊舎の方へ戻り始めた。
イグナーツはディーボルト中尉が隊舎の方へ行くのを見て、追いかけようとした。中尉にきけばどんな状況か教えてくれるだろうか。いや、この件に関わっていない者には口外しないだろう。
イグナーツは迷いながら自室に戻った。しかしほとんど時を待たずしてバタンッと大きな音を立てて部屋の扉が開いた。「おい、イグナーツ!」と喚きながら入ってきたのはデニスである。
「やべえぞ、お前聞いたか!? クラッセン侯爵令嬢が、侯爵領の農夫たちに攫われたんだとよ!」
イグナーツは目を丸くさせた。
「デニス……! なんでそれを知ってるんだ」
「俺、今日はディーボルト中尉と一緒に市街の見回りしてたんだよ。そこに本部から緊急報告が来て急に見回りは中断になった。で、内容聞いちまったんだーー農夫たちは令嬢を捕まえて、アジトに立てこもってるんだとよ。今までの税金の不当な取り立てとかいろんな理由でクラッセン侯爵に金を要求してるらしい」
「アジト?」
「ああ。って言っても侯爵領の農家の倉庫らしいけどな。場所もはっきりしてる、ロアンド村って小さなとこだ。要求してるのも大した額じゃねえらしいけど、侯爵は全然動かねえって言ってたぜ。あの野郎、不当なことはしてないって、農夫たちの言い分を否定してんだ。このままだと令嬢が何されるか……だから軍に話が来たんだ」
彼女が何かされるだって? イグナーツは自分の心臓が早鐘を打つのを感じた。こんなことをしている場合じゃない……緊急会議なんかを待っていたら、彼女の身に危険が及ぶかもしれないのだ。
イグナーツは小銃を肩にかけ、双眼鏡を首に下げた。それから小さな鞄を持つと「デニス」と友人を呼んだ。
「お前、さっきまで見回りだったって言ってたな」
「え、うん」
「少なくともお前が乗ってた馬は厩舎にいるよな。お前がいつも使う馬はエリーだったか」
「おう、さっき厩に繋いで……おいイグナーツ、お前まさか!」
デニスは眉を寄せて友人の腕を掴もうとしたが遅かった。イグナーツは部屋を出ていったかと思うと、もう廊下にすらその姿はなかった。
「早すぎるだろ……おい!」
デニスが慌てて厩舎に駆けつけたときには、イグナーツはもうすでに馬のエリーにまたがっていた。
「ま、まてっ! これって規律違反……」
デニスがゆく手を阻む暇もなく、イグナーツは「悪いなデニス!」と言い捨てて、あっという間に駆け出していってしまった。
「行っちゃったよ……こりゃ薪割りどころじゃ済まねえぞ」
小さい黒い点になっていく友人を見ながらデニスがつぶやいたとき、突然後ろから「おい」と声がかけられ、彼は飛び上がりそうになった。
「ひっ、ディーボルト中尉……!」
中尉は青い目を瞬かせて言った。
「何をそんなに驚いてるんだ。今馬に乗っていったのは誰だ、誰の指示で動いてる?」
「そ、そ、その、ええと……」
デニスは後ずさりながら言い訳を考えようとしたが、いずれはわかってしまうことなので正直に話すしかなかった。
**********
令嬢の囚われているアジトが侯爵領のロアンド村という情報だけでは見当がつくか不安であったが、その周辺部にはすでに第一部隊が集結していたので、イグナーツにも場所がわかった。
アジトとされているのはどうやら三階建ての食糧庫のようで、隊員たちはその周りを取り囲んで上層部からの指示を待っているようだった。見上げると、どの階にも窓があるようだった。
地上の階であれば人質が逃げ出す可能性があるから、おそらくそれを用心して農夫たちは一番上の階に彼女を閉じ込めているはずだ。イグナーツは辺りを見回した。食糧庫から少し離れたところに林がある。
イグナーツは林のなかに入ると背の高い大きな木に登った。
食糧庫の三階と同じ高さまでたどり着くと、双眼鏡がなくても向かいの窓の中がよく見えた。
窓にはカーテンは取り付けられていないようだ。一階には銃や農具を持った男たちが三人、二階は空で、三階の部屋には黒い髭面の男が二人と銃を持った金髪の若い男が一人、そして件の令嬢ビアンカ・ロートバルト・フォン・クラッセンがいた。人質として木箱の上に座らされている。
銃を持った金髪の若い男は、頻繁に三階の部屋に出たり入ったりしながら喋っていた。ここからでは会話は聞こえないが、どうやら奥の階段を使って下階の仲間との連絡係を引き受けているらしい。
見たところ、三階で銃を持っているのは彼だけか。イグナーツはその若い男がずっと銃口を両手で握りしめているので、おそらく扱いには慣れていないと判断した。男たちは皆、身なりからして農夫たちのようだ。となるとデニスが言った通り、彼らは侯爵に虐げられ、重い税の取り立てで苦しめられたゆえに今回の騒動を起こしたということで間違いないのだろう。男たちの貧しい服装とやつれた顔からそれが見てとれた。
次にイグナーツは双眼鏡を目に押し当てて人質の顔を窺った。彼女の疲れた表情が目に入ると、無意識に手に力が入った。後ろ手に縛られているようだが、それ以外は自由に動けるようだ。自分の父親がまいた種だからと抵抗していないのかもしれない。なぜ彼女がこんな目にあわなきゃならないんだ……クラッセン侯爵は何をしている?
「報告!」
ふと食糧庫周りの隊員たちの方から声が聞こえた。一人の隊員が馬に乗ってやってきたらしい。報告ということは本部の緊急会議が終わったのだろうか。
それを一番前で出迎えているのは……げ、ランクル少佐じゃないか。イグナーツは無意識に息を潜めた。
「まもなく第二部隊もこちらに到着します! 戦闘は避け、農夫たちに我々軍隊の数を見せて自ら諦めさせる、戦意喪失させることを優先するとのことです!」
「妥当ですね」
ランクル少佐は頷いた。報告者の声は大きいのでここまで聴こえるが、少佐の声は小さいのでイグナーツは片手で双眼鏡を覗いて彼の唇を読んだ。
「それで、あれからクラッセン侯爵から連絡は? 本部には来たのですか」
少佐の問いに隊員の男は首を振った。
「いえ、侯爵に変わりはありません。ビアンカ嬢のことなど気にしていないようでした。侯爵は……金は払わない、彼らの好きにやらせておけばいいと……」
すぐそばでぽきりと響いた音に、イグナーツはびくっとした。どうやら双眼鏡でない方の手で持っていた枝を折ってしまったらしい。
後ろの林に響かないほどの音だったので、少佐たちにも聞こえなかったようだ。あぶないあぶない。
しかし今あの隊員はなんと言ったか。クラッセン侯爵は何もしていないのか? 娘が捕らえられているというのに?
そしてこの報告者の言葉は、食糧庫の一階にいる農夫たちの耳にも入ったようだった。
例の連絡係の金髪男が焦ったような表情で階段を上がってくるのが見えた。そうして何やらぺちゃくちゃと早口で喋ると、すぐにまた階下におりていった。
話を聞いた三階の二人の髭面の農夫たちは怒り狂ったように手当たり次第下に転がっている木箱を蹴とばし始めた。当然だ、ここまで苦労して篭城したというのに、何もかも無意味に終わろうとしているのである。
イグナーツはその様子に少し同情の念を抱いたが、その農夫たちがクラッセン侯爵令嬢の方を憎悪のこもった表情で振り向いたとき、ふと嫌な予感がした。
木箱の上に座らされているビアンカ嬢の顔が青くなっている。彼女は一生懸命何か喋りながら、首をふるふると振った。唇を読むと「いや、やめて」と言っているようだ。しかし男たちはそのままじりじりと彼女の方へ近づいていく。これはまずい状況なのかもしれない。
イグナーツは双眼鏡から目を離し、食糧庫の周りに包囲している第一部隊の方に目を向けた。少佐たちは三階で起こっている出来事にはもちろん気づいておらず、もうすぐ来ると言っていた第二部隊もまだ姿を見せていない。
イグナーツは再び双眼鏡で三階の窓の方を覗いた。そして部屋の様子を目にした瞬間、彼は反射的に肩にかけていた小銃を構え、ためらいもなく発砲した。
ダアンと銃声が鳴る。包囲していた隊員たちがなんだどうしたと騒ぎ出したが、イグナーツは目もくれなかった。
弾は狙い通り一番窓の近くにいた男の肩に命中した。撃たれた男は床に転がる。おかげで彼の向こうにいたもう一人がよく見えるようになったので、イグナーツはガチャンとボルトを立て直すとその男の腕を狙って、もう一度撃った。
再びダアンと銃声が響き、彼も倒れる。ひとまずこれでいい。
イグナーツは三階の様子を再び窺おうと双眼鏡を目に押し当てた。
ビアンカ嬢はやはり青ざめたまま驚いた様子できょろきょろと床を見ている。きっと転がっている男たちがうめいているのだろう。
とにかく彼女は無事だ。イグナーツはほっと胸を撫で下ろして銃を下ろした。
そのとき、ふと視線を感じたイグナーツは、食糧庫に包囲している隊員たちの方を見下ろしてから「うわ」と声を漏らした。
ランクル少佐がじっとこちらを見ていた。
二発も撃ってしまったのだから、少佐が場所を突き止めないわけがなかった。彼はイグナーツと目が合うと薄い笑みを浮かべた。これは怒っている顔だ。
ランクル少佐が怖い笑顔で手まねきするので、イグナーツはしぶしぶ木から下りると、上官のいる方へ足を向けた。
0
あなたにおすすめの小説

【完結】一番腹黒いのはだあれ?
やまぐちこはる
恋愛
■□■
貧しいコイント子爵家のソンドールは、貴族学院には進学せず、騎士学校に通って若くして正騎士となった有望株である。
三歳でコイント家に養子に来たソンドールの生家はパートルム公爵家。
しかし、関わりを持たずに生きてきたため、自分が公爵家生まれだったことなどすっかり忘れていた。
ある日、実の父がソンドールに会いに来て、自分の出自を改めて知り、勝手なことを言う実父に憤りながらも、生家の騒動に巻き込まれていく。

【完結】真実の愛はおいしいですか?
ゆうぎり
恋愛
とある国では初代王が妖精の女王と作り上げたのが国の成り立ちだと言い伝えられてきました。
稀に幼い貴族の娘は妖精を見ることができるといいます。
王族の婚約者には妖精たちが見えている者がなる決まりがありました。
お姉様は幼い頃妖精たちが見えていたので王子様の婚約者でした。
でも、今は大きくなったので見えません。
―――そんな国の妖精たちと貴族の女の子と家族の物語
※童話として書いています。
※「婚約破棄」の内容が入るとカテゴリーエラーになってしまう為童話→恋愛に変更しています。

さようならの定型文~身勝手なあなたへ
宵森みなと
恋愛
「好きな女がいる。君とは“白い結婚”を——」
――それは、夢にまで見た結婚式の初夜。
額に誓いのキスを受けた“その夜”、彼はそう言った。
涙すら出なかった。
なぜなら私は、その直前に“前世の記憶”を思い出したから。
……よりによって、元・男の人生を。
夫には白い結婚宣言、恋も砕け、初夜で絶望と救済で、目覚めたのは皮肉にも、“現実”と“前世”の自分だった。
「さようなら」
だって、もう誰かに振り回されるなんて嫌。
慰謝料もらって悠々自適なシングルライフ。
別居、自立して、左団扇の人生送ってみせますわ。
だけど元・夫も、従兄も、世間も――私を放ってはくれないみたい?
「……何それ、私の人生、まだ波乱あるの?」
はい、あります。盛りだくさんで。
元・男、今・女。
“白い結婚からの離縁”から始まる、人生劇場ここに開幕。
-----『白い結婚の行方』シリーズ -----
『白い結婚の行方』の物語が始まる、前のお話です。

【完結】ずっと、ずっとあなたを愛していました 〜後悔も、懺悔も今更いりません〜
高瀬船
恋愛
リスティアナ・メイブルムには二歳年上の婚約者が居る。
婚約者は、国の王太子で穏やかで優しく、婚約は王命ではあったが仲睦まじく関係を築けていた。
それなのに、突然ある日婚約者である王太子からは土下座をされ、婚約を解消して欲しいと願われる。
何故、そんな事に。
優しく微笑むその笑顔を向ける先は確かに自分に向けられていたのに。
婚約者として確かに大切にされていたのに何故こうなってしまったのか。
リスティアナの思いとは裏腹に、ある時期からリスティアナに悪い噂が立ち始める。
悪い噂が立つ事など何もしていないのにも関わらず、リスティアナは次第に学園で、夜会で、孤立していく。

伝える前に振られてしまった私の恋
喜楽直人
恋愛
第一部:アーリーンの恋
母に連れられて行った王妃様とのお茶会の席を、ひとり抜け出したアーリーンは、幼馴染みと友人たちが歓談する場に出くわす。
そこで、ひとりの令息が婚約をしたのだと話し出した。
第二部:ジュディスの恋
王女がふたりいるフリーゼグリーン王国へ、十年ほど前に友好国となったコベット国から見合いの申し入れがあった。
周囲は皆、美しく愛らしい妹姫リリアーヌへのものだと思ったが、しかしそれは賢しらにも女性だてらに議会へ提案を申し入れるような姉姫ジュディスへのものであった。
「何故、私なのでしょうか。リリアーヌなら貴方の求婚に喜んで頷くでしょう」
誰よりもジュディスが一番、この求婚を訝しんでいた。
第三章:王太子の想い
友好国の王子からの求婚を受け入れ、そのまま攫われるようにしてコベット国へ移り住んで一年。
ジュディスはその手を取った選択は正しかったのか、揺れていた。
すれ違う婚約者同士の心が重なる日は来るのか。
コベット国のふたりの王子たちの恋模様

【完結済】獅子姫と七人の騎士〜婚約破棄のうえ追放された公爵令嬢は戦場でも社交界でも無双するが恋愛には鈍感な件〜
鈴木 桜
恋愛
強く賢く、美しい。絵に描いたように完璧な公爵令嬢は、婚約者の王太子によって追放されてしまいます。
しかし……
「誰にも踏み躙られない。誰にも蔑ろにされない。私は、私として尊重されて生きたい」
追放されたが故に、彼女は最強の令嬢に成長していくのです。
さて。この最強の公爵令嬢には一つだけ欠点がありました。
それが『恋愛には鈍感である』ということ。
彼女に思いを寄せる男たちのアプローチを、ことごとくスルーして……。
一癖も二癖もある七人の騎士たちの、必死のアプローチの行方は……?
追放された『哀れな公爵令嬢』は、いかにして『帝国の英雄』にまで上り詰めるのか……?
どんなアプローチも全く効果なし!鈍感だけど最強の令嬢と騎士たちの英雄譚!
どうぞ、お楽しみください!

【完結】第一王子と侍従令嬢の将来の夢
かずえ
恋愛
第一王子は、常に毒を盛られ、すっかり生きることに疲れていた。子爵令嬢は目が悪く、日常生活にも支障が出るほどであったが、育児放棄され、とにかく日々を送ることに必死だった。
12歳で出会った二人は、大人になることを目標に、協力しあう契約を交わす。
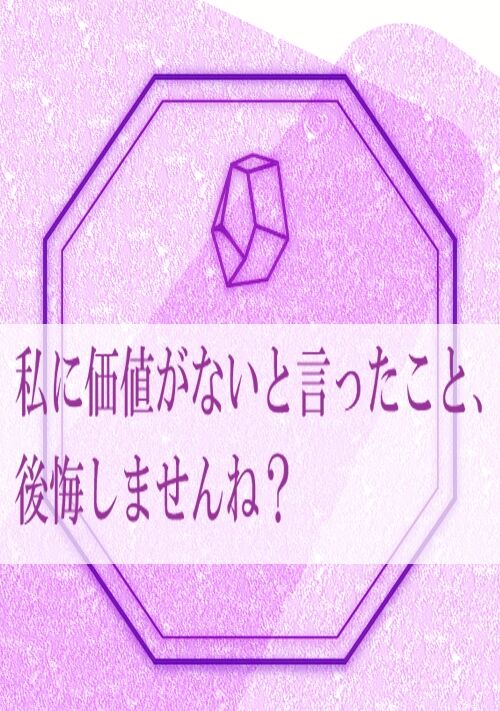
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















