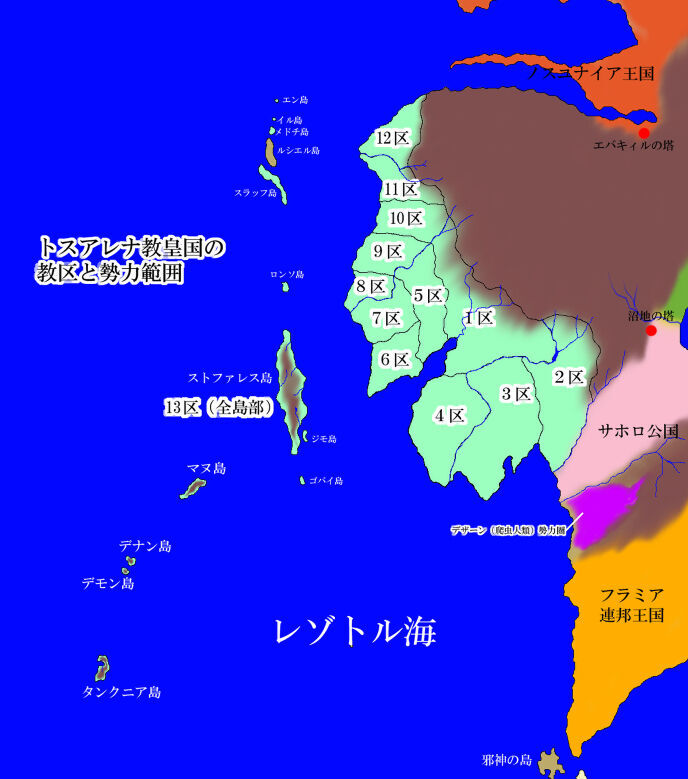25 / 49
第1章 第24話 叩かれた扉
しおりを挟む軌道サーリングの長い車列が駅に滑り込んできました。
駅にはすでに護衛部隊を編成したヴィッツ=ボーラ元帥の師団から選抜された兵隊たちが並んでいます。
午後のまだ早い時間。
ノスユナイア城下都市の門を遠くに眺めてシャアルも同じく安堵の表情を浮かべていました。
「ようやく到着したな」
その顔を見たカルがニヤッとします。
「なんだい?」
「いや。船上の君は快活そのものだったのに、陸地を行く間は憂鬱そうだったからな」
言ってくれるという表情のシャアル。「陸地の民にはわからない・・・と言ったら怒るかい?」
「いや、・・・だけどまあ気持ちは分かるつもりだよ。私だって」カルは近づきつつある城門を見て言いました。「弔問なんて辛気臭い仕事はさっさと終えて故国へ帰りたいと思ってる」
本当にそうなのかと言いたい気持ちを抑えてシャアルは言いました。
「僕は海ならどこでもいい。・・・ところでミニは?」
「え?」
どこだと探すカルたちの耳に沿道からのざわめきが聞こえてきました。気がつけば大勢のノスユナイア王国の民たちが沿道を埋め尽くしています。そしてその人々の視線が自分たちが乗っている客車の上に釘付けであることからカルは悟りました。
「あのバカ・・・」
「展望台か。ハハハ、彼女らしいな」
客車を引く軌道サーリングがくぐり抜けようとしています。
こういう外交にはミニみたいな人間に向いているのかもしれないとシャアルは苦笑いしました。展望台では寒いと言って騒いでいたミニが沿道の人々に笑顔を振りまいていたのです。
弔問とは言え、他国の王族が訪ねてくるという事が非常に珍しかったノスユナイアの住人たちは熱狂こそしませんでしたが、丸い帽子の羽飾り、首元にまかれた防寒の為だけでないきらめく布地、異国の香りあふれる華やかな装いのミニやその傍にいる近衛隊士たちの出で立ちに目を奪われていたのです。
「姫。・・・あまり軽はずみな行為カル様に叱られますよ」
「何を言うのサリ。不安や悲しみに沈んでいるであろうノスユナイア王国の民たちに、せめて私のかわいらしく美しい笑顔で元気づけてあげようという気持ちを少しは理解しなさいな」
やれやれと小さく息を吐いて姿勢を正すサリ。それにしても、と、沿道の人々のミニを見る表情が幾分暗いことを感じるにつけ、もしも自国であれば外国の貴賓が訪れれば国中から訪れた人々で熱狂の渦が生まれていても不思議ではない、今この国の状態は明らかに普通ではないのだと思わずにはいられませんでした。
「止めないのかい?」
「もう遅いよ」苦虫を噛み潰したような顔でカルは言いました。「今私が出て行ったら一緒に手を振る羽目になってしまう。妙なところで機転がきくんだあいつは。・・・変な格好をしていないだけいいが、・・・あとでたっぷりお灸を・・・」
「そう言うなよカル。近衛もついているし、別に恥を晒しているわけじゃない」
低く唸るカル。
「他国との国交なんて堅苦しいことばかりで成り立つものでもないだろう?」
「それはそうだが・・・」
カルの言葉を遮るように軌道サーリングが停止しました。
「さあ到着だ。行こうカル」
出口に向かうシャアルにカルは、「ちょっと待ってくれ」王族らしい振る舞いを体中に貼り付けることを忘れず身なりに不備はないか鏡に自分を映してからついて行きました。
客車の外ではノスユナイア王国の出迎えたちが待ち構えていました。その中のひとりが近づいてきて声をかけてきます。
「長旅ご苦労様です。私は国王陛下の後見人のローデン=エノレイルと申します」
「お出迎えいたみいります」
「はじめまして殿下」
「ありがとうエノレイル殿。カルです」
カルとローデンはがっちりと握手しました。
「お疲れでしょう。先ずは寛げるお部屋とお食事を用意しました。侍従長、ご案内をお願いします」
出迎えは後見人が、もてなしは専門家でもある侍従たちがとあらかじめ取り決めていた通りにローデンは振る舞います。
一通りの挨拶を済ませて一行は近衛隊の警護の中、城内に用意された来賓室へと導かれて往きました。
その道すがらシャアルがカルにこんなことを言っています。
「おいカル」
「ん?」
「見たか?ノスユナイア王国の近衛にすごい美人がいたぞ」
「ああ、見たよ」
「いやびっくりだな。あれほどの美女が近衛とは・・・」
カルは父王が側室のことを言っていたのを思い出していましたが、それと同時に母の剣幕も思い出していました。だからこう言ったのです。
「美人なんてどこの近衛にもいるよ」
「いやいや段違いだよ。・・・機会があれば話をしてみたいな」
「随分ご執心だなシャアル」
少し驚いたようにシャアルがカルを見ました。
「君はなんとも思わないのか?」
「趣味の違いだな」
「趣味だって?まってくれよカル。男なら誰でもあんな美人・・・」
「私に言わせればあの人は美女というより美青年に近いな。多分ハーフセノンだろう。エミリアの芸術家たちは喜びそうだけど、私の趣味とはちょっと違うな」
それは芸術にのめり込んでいるカルならではの言葉でした。芸術家たちに自分の彫像を彫らせるぐらいですから、彼はすこしばかり自己愛の傾向があるのかもしれません。それゆえか女性に対しては素っ気ないほど客観的発言というのはある意味ヤキモチなのかもしれません。
「ハーフか・・・なるほどね。でも僕はああいう感じの女(ひと)に惹かれるよ。名前はなんていうんだろう」
軽く鼻息を漏らし、カルは横目でシャアルが彼女の顔を思い出しているのを覗いながら言いました。
「君の女好きはなんというか・・・少し行き過ぎな感があるな」
「カルが淡白すぎるんだよ。海の男ってのは・・・」
「わかったわかった。海の男は情熱的なんだろ?・・・私はそんなことよりミニが阿呆を晒さないか心配でそんな気になれないよ。それに弔問なんだからそういうの、少し不謹慎じゃないか?」
シャアルは首を縮こませて「わかってるさ・・・」と反省の体で言いました。
彼らがそんなやり取りをしている頃、別の場所では。
「ッエクシュ!」
「や。少尉、風邪?」
ローデンはハンカチで鼻を覆うカレラを見て心配そうに言いました。
「まさか。ちょっとムズムズしただけで・・・。あ~、きっと」
「どこかのいい男が噂してた?とか」
「先生」
キッとした目でカレラはローデンをにらみます。
「あれ?違ってたかな?」
「そういう意地悪を言うとあとで仕返ししますよ?」
ローデンはうっと肩をすくめて笑顔を作ります。仕返し。彼女の場合冗談だとしてもちょっと気になる言葉です。
「気をつけて。これから数日は忙しいだろうし体は大事にしなさい」
「わかってます先生。わたし、年下には興味ないですから」
「年下?」
「え?あらなんで私こんなこと・・・。あ!もう行かなくちゃ。大佐に叱られちゃう」
勘のいいカレラのことなので、無意識にシャアルの視線に気がついていたのかもしれません。慌てて立ち去る彼女の後ろ姿を微笑みながら見送ると、ローデンは短く吐息して侍従長たちとの打ち合わせの場へと趣いてゆきました。
「明日は献花の儀式か・・・しばらく満足に眠れそうもないな」
弔問団の到着の報せを受けたアレスは憂鬱そうな顔をして、窓の外を見ていました。
「ねぇ、エデリカ」
「なに?」
アレスは窓の外を眺めながらエデリカに言います。
「1年ぐらい前の今頃って、確かユリアスがグナスに勝ったんだよね」
アレスの一歩後ろにいたエデリカは少し考えてから「そうだね」そう応えました。
「ユリアスは今頃どうしているかな」
「国境に帝国軍が増えたって言うから。きっと大変な思いをしてるんじゃないかな。・・・どうしたの?急に」
しばらくまた窓の外を眺め、アレスは。
「僕は国王より守り人になりたかったな」
エデリカは少し視線を落とします。「守り人って?」
「うん・・・」
迷っているのか、しばらく黙ってからアレスは言いました。
「僕は父上からあるものを守れって言われたんだ」
「あるものって?」
アレスは首を振ります。
「それは誰にも言ってはいけないんだ。けど、とにかくそれを守らないといけない。約束したんだ。エヴァキイルの塔で父上と」
「・・・どうやって守るの?」
「・・・黙ってること。それが唯一の方法なんだ」
エデリカはそれがとても大事なことだと直感しました。
「ねぇアレス」
「ん?」
「だったら私にそんな話をしたらダメだよ。約束したなら尚更誰にも言ってはダメだよ」
「わかってる・・・でも、なんだか怖いんだ」
「どうして?」
「だって。未来はどうなるかわからないから・・・」
エデリカはアレスに少し近づき、そして耳元に囁くようにして言いました。
「わたしは怖くないよ」
驚いたようにエデリカを振り返ると、そこには笑顔がありました。
「私は怖くない。だって今ここにアレスがいるもの。私のすぐ近くにアレスがいる」
エデリカを見つめ続けるアレスの顔は不思議そうでした。
「お父さんがね、言ってたの」
「・・・なんて?」
頷いてエデリカは微笑みます。「お父さんが死んだお母さんとのことを話してくれた時にね・・・」
”不思議に思うことが今でもたくさんある。どうして私たちは惹かれあったんだろう。どうして一緒に居ると心が安らぐのだろうってね。だけどそれはわからないでもいいんだ。暖かな気持ちになれる存在がすぐ近くに居る。お互いがお互いを求め合っていることがはっきりとわかる。それだけでいい。その理由を考えるという事にどれほどの価値があるのかなんて考える必要はなかった。目の前に彼女が居るだけで全て解決する。少なくとも私はそうだった”
かつて父が言っていた言葉をそのままアレスに伝え、そして。
「私も今は同じ気持ち」
何度か瞬きしたアレスはエデリカの手をそっと握りました。
「目の前にアレスがいる。それだけで全て解決するの。だから怖くなんてない」
アレスの目に小さな光が宿ったように潤みました。そして手を握ったままエデリカの肩に額をつけて言いました。
「そ、っか・・・」
「そうよ。未来は見えないから不安だけど、アレスとこうして居られる『今』は怖くない。・・・アレスにもそうであってほしい・・・」
「うん・・・」
アレスが静かに涙を流していたことに気がついたエデリカはそっとアレスの首筋あたりに手のひらを置き、二人はしばらくそのままじっとしていました。
エデリカから離れ、椅子に座ったアレスは涙を手で拭きながら泣き笑いの表情を見せると、エデリカは微笑んでからハンカチを手渡しました。それを受け取って目のあたりをこすりながらアレスは。「ほんとはね」
「ん?」
「ホントは献花式も謁見式も出たくなかった。弔問の人たちと会いたいなんて少しも思わなかった」
「え?・・・どうして?」
「だってさ。僕がいなくてもきっと大丈夫だと思ったから」
「アレス・・」
「うん。でももう平気だよ。エデリカが一緒にいてくれるなら」
「遠い国からせっかく来てくれたんだもの。お礼ぐらい言わなくちゃだよね?」
エデリカはにっこりとほほ笑みました。
「うん。そうだね」
エデリカはツェーデルや父親から言われた通りにアレスと接していました。
『国王として』とか『王である以上』といった、国王という立場を強調して奮い立たせようという意図的な言葉は極力避けるようにと言われたことを忠実に守ったのです。
エデリカもそれは納得できたことでした。
間違いなくアレスは国王という者が何であるかに疑問を感じて暗闇をさまよっているということを良く分かっていたのです。
■献花式
弔問団が到着したその翌日。
先ずは後見人のローデンが弔問者に対するお礼の言葉を述べあげ、その後は献花の儀式がしめやかに営まれる運びとなりました。
国王であるアレスの後ろにエデリカとモルド、そしてローデンが立ち、各院や元老院の代表者がその下手にズラリと並んでいる前をそれぞれの弔問国の代表が順番に供花するなか、アレスは不思議な思いを抱いていました。
まず服装の色形がノスユナイア国内では見られないもので、それが小さな国王の純粋な好奇心を呼び起こしました。
さらに国王のアレスに対して一礼し、そして墓碑に献花するのは誰もが一緒でしたが、その献花する際に捧げる祈りの方法が各国で異なっていたことに興味を抱いたのです。
最初にアレスに一礼したエフゾン大司教は連れていた司祭が献花したあと、右手の指先で左肩、右肩の順でチョンとついて胸のあたりで手を軽く握って、その拳を額のあたりまで挙げてそのまま目を閉じたまま10秒ほど祈りを捧げました。
次に献花したカル皇太子とミニ皇太女は胸に手のひらをつけてしばらく目を閉じて祈りを捧げます。
最後のシャアルは目を閉じ手のひらを貝のようにぎゅっと合わせて祈りを捧げました。
どれも右手を左手のひらで包んで祈りを捧げるノスユナイア王国のやり方と違っていたことにアレスは小さく驚き、その拍子に亡き父の言葉を思い出したのです。
文化の違い。
宗教の違い。
それらを否定してはいけないという父の言葉。
なによりも先ずは知っているという事が大切だと言った、大好きな父の言葉。
彼の胸の内に生まれた言霊の発する波動の振幅が、固く閉ざされたアレスの心の扉を叩いたのです。
■詩人
いよいよ訪問日程最後の日が明日となり、あてがわれた部屋でくつろいでいたカルとシャアル。
「どうしたんだカル。さっきからずっと黙りこくって」
「うん。・・・」
シャアルは彼が言った事を思い出しました。
そして彼の今の心のうちはアレスに対する哀れみや助けたいという支援の気持ちで溢れていることを推察したのです。
「カル。気持ちはわかるが、やめておけといったろ?深入りはよくないって」
「そうだな・・・」
「僕だってわかるよ。気の毒にも思う。悲嘆の極みだろうな・・・。まだ14歳だというのに・・・」
シャアルはそっと息を吐いて言いました。「それにしても驚きだよ」
「ん?」
「幼い国王擁立となれば、いくらか国内に不穏な動きがあってもおかしくないのにこの国にはその影すらない。あの後見人のエノレイルという人物にしてもとても奸智謀略に長けているようにはとても見えない好人物だ」
「見た目じゃ判断できないよ。けど・・・。まあそうだな。おそらく前国王がよほどの人物だったのだろう。自分が死したあともそうならないように普段から方々に手を尽くしていたんじゃないかな・・・つまり」
カルはひと息おいて言いました。
「傑出した王から息子への置き土産・・・というところかな」
シャアルはカルの言葉を少しの間かみしめてから言いました。
「国民性の違いもあるのかも」
そう言うシャアルを見てカルは問いかけます。
「というと?」
「うん。ノスユナイア王国は僕たちの国のように直接国境が見えない。つまり隣国が見えない。言ってみればノスユナイアという王国は陸の孤島と言える」
「ふむ」
言われてみればたしかにそうだとカルは頷きます。
「だからノスユナイア王国人にとって、ノスユナイア地方は世界なんだよ」
「世界?」
「あくまでも比喩だけど」
「わかってる」
シャアルは軽くうなずきます。
「僕たち船乗りはよく島に立ち寄る。で、島民というのは閉鎖的なところがあるうえに、広い海を生活の場、いや、糧としている割には意外と世界観が狭いんだ」
「それはなぜ?」
「彼らの気持ちは僕にはわからない。だからこれは推測だけど」
「うん」
「少ない人々で協力して生きていくには、島を訪れたすぐにいなくなってしまう外部の人間は脅威なんだ」
「君みたいな?」
シャアルは頷きながら話を続けます。
「そういう訪問者は身内を連れて出て行ってしまうかもしれない」
「君みたいに?」
シャアルは頷きかけて開いた口を閉じてカルを見ます。
「冗談だ。悪かった」
「そして同胞を連れて行った外部の人間は残った島民に何の恩恵も齎さない」
君はそんなことないよな。・・・カルはそう言いかけてやめました。が、シャアルはお見通しだった様でカルを見て苦笑いします。
「島民は自らを一個の生き物のように考えているんだろうな。引き裂かれた部位は死滅するだけ。生きていてこそ生命を維持できる」
「ノスユナイア王国はそれに似ている?」
頷くシャアル。
「ノスユナイア王国という陸地だけが自分たちの知っている世界の全てだと考えているのなら、ここを失うことは死を宣告されることに等しい」ひと呼吸おいて「島民というのは大陸の人間と違って些末なことでもひどく大切にしたり、よそ者を嫌ったり、普段の生活を乱すことや人を極度に嫌う。この国の人たちも無意識下にそういう思いがあるんじゃないのかな・・・」
何度か小さく頷いたカルは顎に手をやって応えます。
「面白い意見だな。・・・たしかに限られた生活圏でのいざこざは命取りになるだろうし、協力関係をよりよく保つために何らかの共通点を大切にする心の働きというのもあるんだろうな」
シャアルは指を立ててさらに続けました。
「僕らがここへ来た時、この国の民たちの僕たちへの反応が気になったんだけど、あれはきっと異文化への驚異的好奇心だったんだとすれば、そういう考えもあながち間違っていないと思う」
「悪言い方をすれば、井の中の蛙・・・か?」
「そうとも言える。でも、島民のような気持ちを持ち続ける限りこの国にある平穏は揺らぐことがない。しかしそれは神からの贈り物、とも言える」
「ふふ・・・」
「変かな?」
笑うカルにシャアルは少し自嘲的な笑みを浮かべました。
「いや」
「それじゃあ、その意味ありげな笑いは嘲笑か?」
「まさか。そうじゃない」ソファの肘掛にもたれかかり、手のひらを後頭部に当てて、カルは笑顔を絶やさず言いました。
「驚異的好奇心とか、神からの贈り物だとか・・・。私と違って君は・・・そうだな、まるで詩人だよ」
褒められたのか馬鹿にされたのか判別できないシャアルは黙ってカルを見続けます。
「私の言った”傑出した王から息子への置き土産”という言葉と君の詩的な表現は全く違うのに、表している意味は同じようにも聞こえる。ただ聴く者によって受け取り方は様々だろうけど」
それは同じものや出来事を見たり感じたりしてもリアリストとロマンチストでは全く違う気持ちを抱くのだということを言いたかったのです。
そしてカルは少しからかうように言い添えました。
「そうやって何人の女を口説いたんだ?詩人公爵」
眉間にしわを寄せて天井を見上げたシャアル。
「カル。僕がのべつ幕なしに女性を口説いていると思っているのか?」
「近衛の美人に入れ込んでたよな?」愉快そうに微笑むカル。
「口説いてない」
「なんだ。まだだったのか」大げさに驚いて見せ、情熱家が聞いて呆れるとカルは思わず笑ってしまいます。「私はとっくに声をかけて玉砕でもしたのかと期待していたのに」
「玉砕どころか近寄ることもできないね」
「おやおや」カルはハッとして思いついたことを言いました。「もしかしてあの近衛隊長のせいだな?」
図星だったようです。
「そうなんだ。あの人は殆どの場合あの近衛隊長のそばにいるから話しかけづらいというか・・・」
「モルド大佐・・・って言ったかな」
「そうそう。その男だ」
「ニックスが言っていたよ」
「なんて?」
「『教条主義とまではいかないが、モルド大佐は規律遵守に厳しく堅い男で威圧感がある。近衛隊長としてはこれ以上無く相応しい。だが近寄りがたい人物だ』・・・とね」
「へぇ。あの人でも怖れを抱く人がいるんだね。・・・ニックスさんは中佐だったかな?」
「そうだけど。どうして?」
それを聞いてシャアルは臍を噛みました。
「いや。せめてモルド大佐と同じ階級だったら・・・なんとか彼女と会えるようにとりなしてもらえるかなって・・・」
「なにを言って・・・」苦笑いをしてカルが目を伏せます。「自分のところの誰かに頼めばいいじゃないか」
「僕のところの衛兵は全て官僚付きでね」詰まり下っ端だけという意味です。「海王の船長は海軍大佐なんだけど」
「連れてくればよかったな」
「いや。同じ大佐でも畑が違うから・・・」
「畑?」
「近衛と海軍士官」
「同じ軍人じゃないか」
「心証が違うよ。同じ近衛だっていう方が段違いで親近感が違う。会話だって近衛同士の方が弾むに決まってる」
「そんなものかな?」
「僕だったらそう思う」そう言って胸に手を当てて天井を見上げるシャアル。「まいったなあ。明日かあ・・・。う~ん・・・」
詩人ならぬ悲劇の主人公にでもなったかの如きシャアルの表情にカルは呆れるやらおかしいやら、笑顔で首を左右に降るばかりでした。
「さて。私はちょっとミニの様子を見てくるよ」
その言葉を聞いてシャアルは椅子から跳ね起きました。
「え!」
「ん?」
「ちょ・・・カル・・・」
シャアルの様子に異変を感じ取ったカルの表情がみるみるうちに般若のごとく変貌してゆきます。顔にしまったという文字を貼り付けたシャアルを振り返りもせずドアを開けて勢いよく廊下に飛び出すと隣の部屋の前にいるニックス隊長に詰め寄りました。
「ニックス!」
その剣幕にニックスはさっと姿勢を正し内心では冷や汗を流し始めます。「ハ!」
「ミニはこの中か?」
部屋の中を指差すカルの顔は明らかに怒っています。
「い、いらっしゃるはずですが・・・」
「ええい!!どけ!」
ニックスを押し退けて部屋に入るとカルの視界に椅子の背もたれの向こうに誰かが座っているのが見えました。頭髪が見えていたのでカルは回り込んで誰かと確認するやその頭髪を掴んで床に叩きつけました。「小賢しい!」カツラです。
部屋は案の定、蛻の殻(もぬけのから)でした。
「ニックス!」
「ハ!」
「バカ!あれほどあれに好き勝手にさせるなと言ったのになんてことをしてくれた!」
「も・・・申し訳ございません!で、ですが・・・」
「言い訳などいい!ミニはどこだ!」
「それが・・・」ニックスは視線を合わせることができずカルの頭の上の方を見ながら口ごもりながらも言いました。「街へ・・・いらっしゃるとか」
「街だ、と?ひとりでか?!」
「グランダ中尉が同行しております・・・」
嘆息しながら首を振り「どいつもこいつもいいように乗せられおって・・・」大股で歩き始めるカル。
「で、殿下どちらへ!」
「騒ぎを起こす前に街だ!連れ戻す!決まってる!」
シャアルは言葉の順番がバラバラなのを聞いておかしくなりましたが、あたまにきてるというより相当慌てているらしいことを悟ってニックスと共にカルを追いかけました。
「待てよカル!」
目の前に回り込んだシャアルにカルは噛み付くように言いました。
「知ってたな?シャアル」
「悪かったよ。でもずっと部屋に閉じ込められたままじゃいくらなんでもかわいそうじゃないか・・・」
「それはそうしなければならなかったからだ!」
「わかったよ。怒鳴るなって。それより街に行くにしてもその格好で行くつもりか?」
カルは頭に血がのぼっていて自分が王族の正装でいることに気がつきませんでした。その装束で出かけようものなら街はきっと珍し物好きの民たちで大騒ぎが巻き起こるに違いありません。
「それに君が外出するならこの国の誰かに断りを入れなきゃ。黙っていなくなったら大騒ぎだぞ?」
するとそこへ折り良くノスユナイアの近衛兵がやって来ました。
「皇太子殿下?」
モルドです。
「どうされたのです?」
シャアルはモルドの後ろにカレラがいることを神に感謝しました。海の神がここまで僕についてきてくれていた。
しかし実はシャアルはこの事態こそを期待してミニが城外へ出ることを黙っていたのです。
「実は・・・その、彼の妹のミニが街へ出て行ってしまったらしく、我々で探しに行こうと思っていたのです」
「皇太女様が?!」
「大変。大佐、私探してきます!」カレラが狼狽してモルドに言いました。
「私も行こう。公爵閣下、皇太子殿下、我々が探してまいりますので、どうかお部屋でお待ちください。必ずお連れします」
「いやモルド大佐。わたしも行きます。妹の不始末を黙って人任せにすることはできません。どうか外出許可を」
カルは部屋で待つなどとんでもないと思いました。その目はメラメラと燃える炎が宿っているように、何を言われても探しに行くという目力で溢れていたのです。
モルドは少し考えてから言いました。
「承知しました。では殿下、そのお姿では目立ちますから着替えてから参りましょう。ニックス中佐、そちらの近衛隊の方々にもお手伝いいただきたい」
「ええ、もちろんです。おい、お前とお前は残ってあとは私について来い」
あっけないほど自分たちの外出にOKを出したモルドにシャアルはいささか面食らいましたが、許可を出したモルドの心の内よりも、しめたとばかりにカレラとペアを組めるようにする方法を考え始めた自分に半ば呆れながら嬉しい思いが顔に出ないようにするのに苦労したのです。
■ヴォルジ=オルレゲン元老院議員と二人の死者
そんな騒ぎが起こっていた頃。
「では聞かせてもらおうかゴネリア室長。オルレゲン元老院議員だったな?」
そう言って不機嫌そうに眉間にしわを寄せたボロギット=カフラー反国家審問委員長は執務室の自分の椅子に少し音を立てて座ります。
「現職の元老院議員。問題を起こすような危険人物でもなく、小さな所領の貴族で穏健派・・・未婚の独り者で両親は既に他界。こう言っては何だが彼が外国で死んだとしても気にするものは少ないだろうな」
手にしていた書類を目の前に立っているゴネリア室長の顔が隠れるように掲げるとそれが炎によって焼失し、ゴネリアの無表情な顔が現れました。
「ですが、元老院議員です委員長。さすがに国外で死なれると我が国の沽券にかかわります」
「勝手に出て行ったのだ。どうなろうと自業自得・・・と言いたいところだがね」
カフラーの意味ありげな言葉尻にゴネリアは視線を動かします。
「・・・と、仰いますと・・・」
カフラーは鼻息を吹き出しながらゴネリアをじろりと見ます。
「君の眼が節穴・・・とは思ってはいない、実際そうではないことはわかっているが私を失望させないでくれ室長」
フチなしの丸いメガネをかけた痩せている男、ゴネリアはやはり表情を変えずに答えました。
「私が確認したところでは、オルレゲン元老院議員はフスランにいる親戚に新年の挨拶に行くために国務院に出国届を出しています。過去の記録を見てもここ十数年の間は同じ時期に出国しています。・・・フスランへ」
「ふん・・・」
「フスランは帝国の息がかかっていますからそこへ現職の元老院議員が出向くことは危険とも言えますが・・・過去十数回、何も起きていないことを考えれば・・・まあこういうと語弊があるかもしれませんが、オルレゲン議員は帝国からも重要視されていないのでは・・・と、考えますが」
「・・・ではあの事とは無関係だと君は言うのだな?」
ゴネリアはカフラーに視線を合わせずに頷きます。
「確かにフスランに渡った邦人が立て続けに2名も死んだことは憂慮すべきことですが、フスランに潜っている諜報員の調査では、どちらも・・・」
「事故だという報告書は読んでいる」
ゴネリアは言葉を遮られたことを意に介さず少しだけうなずきました。
報告書に一人は酒に酔った末に橋から転落、もう一人はやはり酔った末に馬車に跳ね飛ばされたとありました。
「前国王陛下がお亡くなりになられてから、国情不安を危惧する一部の有力者や貴族が外国に資産を持ち出すことが増えているのは事実です。出国数の分母が増えたから、偶発的に発生した事故が目立ってしまった」
カフラーは不機嫌そうです。
「過去の事例に照らしても、国王陛下の世代交代が行われるたびに金持ち連中が財産を国外の親類縁者に託すのは珍しい事ではない。保険のつもりなのだろう」
ゴネリアは何も言わずカフラーの言葉に耳を傾けます。
「オルレゲン議員の持ち出した荷物の記録を見てもそれに類することであろう事が見て取れる。片道のみの護衛も雇っているようだしな」
「・・・」
「だが・・・」
「気になる点がありますか?」
カフラーはふっと息を吐いてから続けます。
「君は気にならないかね?」
ゴネリアはそう問われて暫し思案し言いました。
「確かに国外へ渡った邦人で死んだのはその二人だけで、渡航先は2人ともフスラン王国。渡航理由はフスランの縁者に会いに行くため、年始ですからその理由に怪しいところはないと思いますが・・・、二人ともが貴族ではないものの富裕層であり土地の有力者。兄弟はありますが独り身。・・・数名の従者を従えていたのは護衛のためでしょうね、おそらく財産の一部を運び出していた。・・・していることは先ほど委員長が仰っていた財産の持ち出しという点で一致しています」
ゴネリアはさらに続けます。
「私が唯一気になったのは、二人ともフスランへの渡航が初めてだった点です」
「そうだ、初めての渡航だった・・・が、交流は皆無ではなかった」
「はい。死んだ二人ともが商取引によってフスラン在住の親類縁者とつながりがあり、年に数回ではありますが手紙のやり取りがありました。しかし実際に会うことはほとんどなかったようですね。まあ遠隔地との商取引では珍しくもないですが」
「そこだよ」
「やはりそこですか」
「・・・」
「いえ。冗談を言っているわけではありません」
カフラーはやはり不機嫌そうな顔です。
詳細な個人の情報が報告に上がっている事は驚くに値しますが、カフラーもゴネリアも表情に変化がありませんでした。これがあたり前の世界に生きているからでしょう。
「ゴネリア室長」
「はい」
「どうして彼らはわざわざ敵国である帝国の息がかかったフスラン王国に一部とはいえ決して少なくない財産を持って出かけたのだろうね?」
ゴネリアは思いました。
デヴォール帝国のおひざ元よりもっと財産を移すのに適したところがあるではないか。カフラーはそう言いたいのだと。
しかし、その思いは頭に浮かんだ瞬間に消えました。
自分の上司の着目点はそこではないと思いなおしてすぐにいくつかの別の言葉が脳裏にひらめいたのです。
「強奪殺人をお考えですか?」
カフラー委員長はフスランの親類が商取引を種に呼び寄せて隠密裏に持ってきた財産を奪うために殺害したと考えている。
「報告書は読んだよ」
報告書にはフスラン在住の親類がお金に困っていることは全くなく、商売も順調でそれなりにの地位もある者たちであるとありました。事故を装っての殺人という人生を根底から瓦解させるような愚挙をするとは思えないというのはカフラーもゴネリアも見解は同じでした。
次にゴネリアはもう一つの考えを口にします。
「そうするしか他に選択肢がなかった・・・」
カフラーはふううっと眺めに息を吐きだします。
「全く君は期待に応える代わりに時折私を不愉快ににするな」
「恐縮です」
「褒めてはおらん」
「・・・」
「そうだ、彼らにはフスラン以外に選択肢がなかった・・・と私は考えている」
報告書には死んだ二人とも国外の親類縁者がフスランのみであることが明記されています。
「だが商取引がある親類がいるからという理由だけでは腑に落ちん。親類以外の商取引相手もいるはずだ」
「・・・商取引があるということは何らかの旨味もあったでしょうし、敵国の息がかかったフスラン王国とはいえ、現時点でフスラン王国と我が国の間は平穏を保っています」
平穏であることは商業活動が活発であることを意味します。
「まあ帝国の気まぐれや突然の増税などで財産を取り上げられる危険性が有ることは否めませんが、商人はそういう危機回避に優れたずる賢さも持っている者たちです。預けた財産の運用も任せられたでしょうし・・・」
カフラーが口元に笑みを浮かべていることにゴネリアは気が付きました。
「委員長?」
「ゴネリア情報室長。君の言うとおりだ。私が大きな財産を持っていて君の今の説明を聞かされたのなら、きっと私はたとえ敵国で商売をしている親類にでも財産を預けてしまいそうだ」
それが皮肉であることをゴネリアは知っていました。
「失礼しました。・・・つまり委員長は死んだ二人のフスランへの渡航理由が特別なもので、それが何かはわからないけれども、オルレゲン議員も同じ理由でフスランへ行っているのではないかとお考えなのですね?」
カフラーは腕を組んで背もたれに身を預けて自分が育てた配下を見ると、今度は面白くなさそうに視線を横に滑らせて言いました。
「全く不愉快だ」
そして心の中で”同族嫌悪”という言葉を思い出して、さらにモルド大佐のことまで思い出して苦い思いとともに眉間のしわを深くしたのです。
「君の今の説明、つまり裏付けともいえる推測が、誰かの思惑だと考えることもできるということだ」
ゴネリアは深くも浅くもない感じで頭を垂れました。
死んだ二人が財産を安全かつ儲けが発生するという話を誰かから持ち掛けられた。そしてフスランへ渡航する。罠であるとも知らずに。
「考えすぎだと思うかね?」
「そうは思いませんが・・・調査が必要かと」
「すまんが調査は既に進めている」
意外な言葉にゴネリアは初めて表情に変化を見せました。それを見てカフラーは少しだけ満足そうな顔をします。
「ここに死んだ二人の行動記録の調査結果が記されている。気になる点が一つだけあった。赤い線が引いてあるところだ」
カフラーは引き出しから取り出した2~3枚の超報告書をゴネリアに突き出します。
不愉快な顔ではありませんが、ゴネリアは悔しそうな風の目でカフラーから書類を受けとります。
書類の赤線に目を通したゴネリアは手のひらで口を押えるしぐさをしてちらりとカフラーを見て、書類をカフラーの執務机の上にそっと置きました。
「・・しかし、いったい何の・・・」
ゴネリアはハッとします。それでも疑念を払いきれませんでした。
「オルレゲン議員の渡航も、死んだ二人の渡航も、誰かに仕組まれたことだと?」
「これは勘から生まれた推測だよ。確証はない。だが死んだ二人とオルレゲン議員。その3人ともが一人になることを好み、週に2~3回は必ず個室付きの図書館に通っている」
何か言おうとするゴネリアを制してカフラーは続けます。
「そこで私は君に質問したい」
「・・・?」
「君はたった今3人の渡航が誰かに仕組まれたこと・・・・と言ったな?」
ゴネリアはうなずくことを拒否しきれない感じで頷きます。
「君のそういうところを私は評価しているんだ」
「・・・恐縮です」
「君が今、脳裏に浮かべている考えは私の考えと一致する事を確信している」
ゴネリアはカフラーの自分に対する評価を知っていました。だから後ろで手を組んで背筋を伸ばしたのです。
「ゴネリア情報室長。行動調査は誰でもできるが、ここからは君の領分だ」
カフラーはゴネリアが机に置いた書類を手に取ると、ゴネリアの目の前で炎で消し飛ばします。
つまりオルレゲンも死んだ二人と同様の運命をたどる危険性がある。
「死んだ二人に接点はない。しかしオルレゲン議員とはどうか・・・ということですね?」
「調べたまえ。私の考えすぎならそれでもいい。だが人死にが出ている以上は捨て置けない。現職の元老院議員が国外で死亡というのは、君と同様、私も避けたいと考えている。どんな小物でもな」
しかしゴネリアは。
「国外は情報部の管轄です。我々委員会は手が出せません」
カフラーは何度かうなずきながら言います。
「だがこの件については我々で処理したい。ヴォルジ=オルレゲン元老院議員の経歴を調べているうちに気になることが出てきたのでね」
「それは?」
「贈り物だよ」
「贈り物?」
「ん、前国王陛下、王妃殿下、そしてこの私や委員会あてばかりでなく元老院の派閥の中心人物や地元の高級士官などにもまめに贈り物をかなりの頻度でしている。郵便記録によればあの後見人にまでな」
本当にまめな人だとゴネリアはあきれたような顔をします。
「なんと・・・」
「こういう贈り物好きはたいていの場合人間関係を大切にするが、言い方を変えると庇護を受けたがる人間だ」
「庇護ですか・・・」
それが今回の二人の死亡の件が関わりがあるのか。
「そういう人間は臆病者といっていい。そんな臆病者が危険を顧みずに護衛まで仕立てて敵国に渡航する事が・・・私には不自然に思えてならんのだよ」
ゴネリアはまた無表情に戻ってカフラーを見ます。
「できることならオルレゲン議員に実際に会ってじっくりと訊きたいのだ。財産持ち出しとフスラン渡航の理由をな」
ゴネリアはカフラーの勘を信じたわけではありません。しかし上司として尊敬をしている人物の言うことを頭から否定することはできませんでした。何かしらの意味があるはずだと考えたのです。
「ハーリエンには通達済みだ。君はオルレゲンと死んだ二人の共通点から何かを導き出せ」
無茶を言う。そう思いながらもゴネリアは頭を下げ退室したのでした。
第25話へつづく
0
あなたにおすすめの小説

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話
登夢
恋愛
春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。



百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~
桂
ファンタジー
探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。
そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。
そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる