11 / 20
第二章 地下迷宮のオルクス
1
しおりを挟む
「瓶から酒がなくなるのは飲んだ人間がいるからだ、というね」
ギルドマスターは言った。
「それは」ミルコは一瞬迷った。「タウリスですか」
「今のはただのことわざだよ」
ギルドマスターは机の上で指を組んだ。
「ということを考えると、面白いことがわからないか」
「なんの話をされているのか、正直わかりません」ミルコは困惑して答えた。
「ああ…失礼」ギルドマスターは頭をかいた。「私は説明が下手で困るよ」
今日もまたギルドマスターに呼び出されている。何を期待されて呼ばれているのか全然わからないのだが、ギルドマスターはどうもミルコを自分の便利な手駒のように考えている節がある。節がある、というかそうに違いない、とミルコは思っている。
「最近迷宮の第一階層から第二階層を中心に、オルクスが目撃されているのは知っているかい」
「はい」その話を誰かから聞いた気がして、ミルコは頷いた。そうだ、あの隻眼の受付係だ。
「グルツさんから聞きました」
「うんうん」ギルドマスターは満足げに頷いた。
「おかしいとは思わないか」
「はい、少し思いました」
ミルコは言った。
「そもそもどこから?という話ですよね」
「そうだ」ギルドマスターは壁の図を指した。ギルドの建物から入獄門の周辺までが細かく図にされている。
「迷宮は国の資産でもあるからね」ギルドマスターは入獄門のあたりを指した。「この辺は高い塀で囲われているし、見張りもいるだろう?」
「つまり、入獄門以外の入り口がある、ということですよね」
「そう、それ」ギルドマスターはミルコを指さして、パチンと指を鳴らした。
「鋭いね。本当に話が早くて助かる」
「オルクスは山岳の洞窟などを住処にしています。そこから迷宮まで穴を掘って侵入してきている、ということですよね」
「そう、そうなんだが、入口を作ったとしてもすぐ塞がれてしまうだろう?」
「迷宮小人がいますからね」
その勤勉さと粘り強さ、仕事の速さと正確さは、先日ミルコ自身が目の当たりにしたのでよく理解している。
むしろその勤勉さを利用して難敵を倒したわけだけれども。
「我らが勤勉な隣人が迷宮を修復してしまうことを考えると、オルクスたちが侵入してくることはまず不可能なはずなんだが」
確かに、魔法を使って掘ったとしても一人か二人通ったあたりでレプラコーンに囲まれてしまうだろう。
「としたら」
「瓶から酒がなくなるのは」
「飲んでいる人間がいる」ミルコは引き継いで言った。「つまり」
「仕掛けがあるはずなんだ」
バッシュ・ザ・ギルドマスターはにこやかに言った。
「それを君に調べてほしい」
「で、どうするんだ」ハックが干し肉を齧りながら言った。
「まずはオルクスの目撃情報からですね。実際に被害を受けた人たちに確認を取りましょう」
「そもそも前提として」スラッシュは発酵酒の盃を舐めた。「オルクスたちは迷宮で何をしてるんだ」
「さあ」ミルコは豆をつまみながらエールを飲む。「ただ、はっきりしてるのは、これって結構大きな問題だということですよ」
「確かにオルクスは厄介な連中だが、追い剥ぎ程度の危険度しかねぇだろう。新兵が被害に遭わないよう気をつければなんとかなりそうなもんじゃねぇの」
ハックは発酵酒の瓶を倒した。もう飲み干してしまったらしい。
「入ってくるということは、出て行くこともあるということなんです」ミルコは言った。
「迷宮にしかいない魔法生物や危険な生き物が山に放たれたらどうなると思います」
「…なるほどな」スラッシュは静かに言った。
「私にとっては、これは大きな問題です」ミルコは言った。
「サンデルの山を汚すわけにはいかない。私はあそこで育ちましたから」
「まあ」ハックは気乗りしなさそうに言った。「リーダーはあんただ。手頃な依頼だとは思うよ。あのクソ眼鏡の言いなりってのがどうも気に入らないけどな」
「いったい何があったんですか」ミルコが苦笑した。「ギルドマスターと」
「さあな」スラッシュが肩をすくめる。
「そう言えば、お二人ってギルドマスターと面識があるんですか」
「俺は、ない」スラッシュは言った。「この間が初めてだ」
「ハックは」
ハックは突っ伏したまま答えない。
寝息が漏れる。
「寝たな」スラッシュが眉を顰めた。
「とりあえず明日の朝、もう一度ここに」ミルコは言った。
「まずは情報収集です。オルクスに会って生還したハンターに会いましょう」
「不意打ちでした。階段の陰にオルクスたちが隠れていたんです」
まだ少年と言ってもいい年齢のハンターは暗い表情で言った。
午前中のギルドホールに人はほとんどいない。休みの冒険者が遅い朝飯を食べるくらいのもので、テーブルに集まっているのはミルコたちだけだった。
ギルドマスターに頼んでおいた生還者として紹介されたのが目の前の新兵だ。
治癒魔法が効いて体は動くようになってきているようだが、まだ足を引きずっている。
「僕たちのパーティーはまだ二回しか潜ったことがなくて、暗鬼や兎鼠を狩るくらいでした。初めて二階に降りようとしたら」
「オルクスが襲ってきたのか」
「斧や剣を持ったオルクスたちが」新兵は顔を覆った。
「間違いなくオルクスだったのね」ミルコは確認するように言った。「厭鬼や戦鬼や大鬼ではなくて」
「豚のような鼻面をして、牙が生えてました。間違いなくオルクスでした」
僕は山育ちなので、奴らを見たことがあるんです、と少年兵は言った。
「奴らは戦い慣れていました。まるで僕らをからかうようにいたぶりながら追いつめて」
「どうやって逃げたの」
「僕は仲間を見捨てて走りました」泣き声になる。「みんな同じ故郷の友人たちだったんです。あんなに手強い敵がいるって知っていたら」
「オルクスは何人だったの」
「六人です。僕らと同じでした」
「六人」
ミルコたちは顔を見合わせる。
「ありがとう、辛い話をさせてごめんね」ミルコは少年兵の肩を叩いた。
「一人で生き残るのが辛いのは私もよく知ってる。ほら、私、疫病神なんて言われてるからさ」
ミルコは笑顔を少年兵に向けた。
「でも、必ずまた何かが始まるよ。それが迷宮でなくても」
少年兵は頷いた。
「さて」少年兵が宿舎に戻るのを見送りながらハックが言った。「どう思う」
ミルコは腕を組んだ。
「六人というのが、気になります」
「偶然だろう」
「オルクスに会ったことあります?」
「ああ」ハックは頷いた。「山で、奴らの縄張りにうっかり入ってしまって、逃げたことがある。その頃俺はまだガキだったけどな」
「オルクスは狩りをするとき、大体三人くらいですよね。部族間の衝突とかなら別ですけど」
「そう言われれば、そうだな」
「オルクスは六人ひと組で行動している。これってあれじゃないですかね」
ミルコは眼鏡を上げた。
「マカリスター・セオリー」
「迷宮で生き残るためには、六人が最適だってあれか」
「つまり、オルクスの目的は、迷宮内でハンターを襲うことなんじゃないかって話です」
ミルコは立ち上がった。
「迷宮でオルクスを探しましょう」
ギルドマスターは言った。
「それは」ミルコは一瞬迷った。「タウリスですか」
「今のはただのことわざだよ」
ギルドマスターは机の上で指を組んだ。
「ということを考えると、面白いことがわからないか」
「なんの話をされているのか、正直わかりません」ミルコは困惑して答えた。
「ああ…失礼」ギルドマスターは頭をかいた。「私は説明が下手で困るよ」
今日もまたギルドマスターに呼び出されている。何を期待されて呼ばれているのか全然わからないのだが、ギルドマスターはどうもミルコを自分の便利な手駒のように考えている節がある。節がある、というかそうに違いない、とミルコは思っている。
「最近迷宮の第一階層から第二階層を中心に、オルクスが目撃されているのは知っているかい」
「はい」その話を誰かから聞いた気がして、ミルコは頷いた。そうだ、あの隻眼の受付係だ。
「グルツさんから聞きました」
「うんうん」ギルドマスターは満足げに頷いた。
「おかしいとは思わないか」
「はい、少し思いました」
ミルコは言った。
「そもそもどこから?という話ですよね」
「そうだ」ギルドマスターは壁の図を指した。ギルドの建物から入獄門の周辺までが細かく図にされている。
「迷宮は国の資産でもあるからね」ギルドマスターは入獄門のあたりを指した。「この辺は高い塀で囲われているし、見張りもいるだろう?」
「つまり、入獄門以外の入り口がある、ということですよね」
「そう、それ」ギルドマスターはミルコを指さして、パチンと指を鳴らした。
「鋭いね。本当に話が早くて助かる」
「オルクスは山岳の洞窟などを住処にしています。そこから迷宮まで穴を掘って侵入してきている、ということですよね」
「そう、そうなんだが、入口を作ったとしてもすぐ塞がれてしまうだろう?」
「迷宮小人がいますからね」
その勤勉さと粘り強さ、仕事の速さと正確さは、先日ミルコ自身が目の当たりにしたのでよく理解している。
むしろその勤勉さを利用して難敵を倒したわけだけれども。
「我らが勤勉な隣人が迷宮を修復してしまうことを考えると、オルクスたちが侵入してくることはまず不可能なはずなんだが」
確かに、魔法を使って掘ったとしても一人か二人通ったあたりでレプラコーンに囲まれてしまうだろう。
「としたら」
「瓶から酒がなくなるのは」
「飲んでいる人間がいる」ミルコは引き継いで言った。「つまり」
「仕掛けがあるはずなんだ」
バッシュ・ザ・ギルドマスターはにこやかに言った。
「それを君に調べてほしい」
「で、どうするんだ」ハックが干し肉を齧りながら言った。
「まずはオルクスの目撃情報からですね。実際に被害を受けた人たちに確認を取りましょう」
「そもそも前提として」スラッシュは発酵酒の盃を舐めた。「オルクスたちは迷宮で何をしてるんだ」
「さあ」ミルコは豆をつまみながらエールを飲む。「ただ、はっきりしてるのは、これって結構大きな問題だということですよ」
「確かにオルクスは厄介な連中だが、追い剥ぎ程度の危険度しかねぇだろう。新兵が被害に遭わないよう気をつければなんとかなりそうなもんじゃねぇの」
ハックは発酵酒の瓶を倒した。もう飲み干してしまったらしい。
「入ってくるということは、出て行くこともあるということなんです」ミルコは言った。
「迷宮にしかいない魔法生物や危険な生き物が山に放たれたらどうなると思います」
「…なるほどな」スラッシュは静かに言った。
「私にとっては、これは大きな問題です」ミルコは言った。
「サンデルの山を汚すわけにはいかない。私はあそこで育ちましたから」
「まあ」ハックは気乗りしなさそうに言った。「リーダーはあんただ。手頃な依頼だとは思うよ。あのクソ眼鏡の言いなりってのがどうも気に入らないけどな」
「いったい何があったんですか」ミルコが苦笑した。「ギルドマスターと」
「さあな」スラッシュが肩をすくめる。
「そう言えば、お二人ってギルドマスターと面識があるんですか」
「俺は、ない」スラッシュは言った。「この間が初めてだ」
「ハックは」
ハックは突っ伏したまま答えない。
寝息が漏れる。
「寝たな」スラッシュが眉を顰めた。
「とりあえず明日の朝、もう一度ここに」ミルコは言った。
「まずは情報収集です。オルクスに会って生還したハンターに会いましょう」
「不意打ちでした。階段の陰にオルクスたちが隠れていたんです」
まだ少年と言ってもいい年齢のハンターは暗い表情で言った。
午前中のギルドホールに人はほとんどいない。休みの冒険者が遅い朝飯を食べるくらいのもので、テーブルに集まっているのはミルコたちだけだった。
ギルドマスターに頼んでおいた生還者として紹介されたのが目の前の新兵だ。
治癒魔法が効いて体は動くようになってきているようだが、まだ足を引きずっている。
「僕たちのパーティーはまだ二回しか潜ったことがなくて、暗鬼や兎鼠を狩るくらいでした。初めて二階に降りようとしたら」
「オルクスが襲ってきたのか」
「斧や剣を持ったオルクスたちが」新兵は顔を覆った。
「間違いなくオルクスだったのね」ミルコは確認するように言った。「厭鬼や戦鬼や大鬼ではなくて」
「豚のような鼻面をして、牙が生えてました。間違いなくオルクスでした」
僕は山育ちなので、奴らを見たことがあるんです、と少年兵は言った。
「奴らは戦い慣れていました。まるで僕らをからかうようにいたぶりながら追いつめて」
「どうやって逃げたの」
「僕は仲間を見捨てて走りました」泣き声になる。「みんな同じ故郷の友人たちだったんです。あんなに手強い敵がいるって知っていたら」
「オルクスは何人だったの」
「六人です。僕らと同じでした」
「六人」
ミルコたちは顔を見合わせる。
「ありがとう、辛い話をさせてごめんね」ミルコは少年兵の肩を叩いた。
「一人で生き残るのが辛いのは私もよく知ってる。ほら、私、疫病神なんて言われてるからさ」
ミルコは笑顔を少年兵に向けた。
「でも、必ずまた何かが始まるよ。それが迷宮でなくても」
少年兵は頷いた。
「さて」少年兵が宿舎に戻るのを見送りながらハックが言った。「どう思う」
ミルコは腕を組んだ。
「六人というのが、気になります」
「偶然だろう」
「オルクスに会ったことあります?」
「ああ」ハックは頷いた。「山で、奴らの縄張りにうっかり入ってしまって、逃げたことがある。その頃俺はまだガキだったけどな」
「オルクスは狩りをするとき、大体三人くらいですよね。部族間の衝突とかなら別ですけど」
「そう言われれば、そうだな」
「オルクスは六人ひと組で行動している。これってあれじゃないですかね」
ミルコは眼鏡を上げた。
「マカリスター・セオリー」
「迷宮で生き残るためには、六人が最適だってあれか」
「つまり、オルクスの目的は、迷宮内でハンターを襲うことなんじゃないかって話です」
ミルコは立ち上がった。
「迷宮でオルクスを探しましょう」
0
あなたにおすすめの小説

最愛の番に殺された獣王妃
望月 或
恋愛
目の前には、最愛の人の憎しみと怒りに満ちた黄金色の瞳。
彼のすぐ後ろには、私の姿をした聖女が怯えた表情で口元に両手を当てこちらを見ている。
手で隠しているけれど、その唇が堪え切れず嘲笑っている事を私は知っている。
聖女の姿となった私の左胸を貫いた彼の愛剣が、ゆっくりと引き抜かれる。
哀しみと失意と諦めの中、私の身体は床に崩れ落ちて――
突然彼から放たれた、狂気と絶望が入り混じった慟哭を聞きながら、私の思考は止まり、意識は閉ざされ永遠の眠りについた――はずだったのだけれど……?
「憐れなアンタに“選択”を与える。このままあの世に逝くか、別の“誰か”になって新たな人生を歩むか」
謎の人物の言葉に、私が選択したのは――

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜
AK
ファンタジー
ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。
そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。
さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。
しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。
それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。
だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。
そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。
※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

寵愛の花嫁は毒を愛でる~いじわる義母の陰謀を華麗にスルーして、最愛の公爵様と幸せになります~
紅葉山参
恋愛
アエナは貧しい子爵家から、国の英雄と名高いルーカス公爵の元へと嫁いだ。彼との政略結婚は、彼の底なしの優しさと、情熱的な寵愛によって、アエナにとってかけがえのない幸福となった。しかし、その幸福を妬み、毎日のように粘着質ないじめを繰り返す者が一人、それは夫の継母であるユーカ夫人である。
「たかが子爵の娘が、公爵家の奥様面など」 ユーカ様はそう言って、私に次から次へと理不尽な嫌がらせを仕掛けてくる。大切な食器を隠したり、ルーカス様に嘘の告げ口をしたり、社交界で恥をかかせようとしたり。
だが、私は決して挫けない。愛する公爵様との穏やかな日々を守るため、そして何より、彼が大切な家族と信じているユーカ様を悲しませないためにも、私はこの毒を静かに受け流すことに決めたのだ。
誰も気づかないほど巧妙に、いじめを優雅にスルーするアエナ。公爵であるあなたに心配をかけまいと、彼女は今日も微笑みを絶やさない。しかし、毒は徐々に、確実に、その濃度を増していく。ついに義母は、アエナの命に関わるような、取り返しのつかない大罪に手を染めてしまう。
愛と策略、そして運命の結末。この溺愛系ヒロインが、華麗なるスルー術で、最愛の公爵様との未来を掴み取る、痛快でロマンティックな物語の幕開けです。
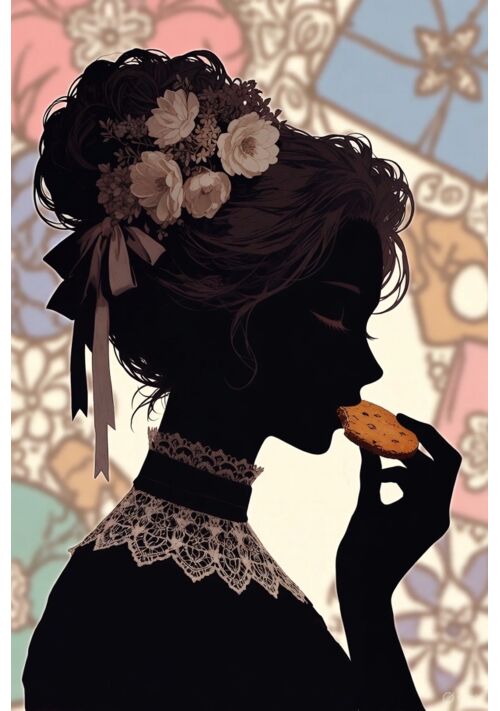
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。
猫屋敷 むぎ
恋愛
没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――
私の願いは一瞬にして踏みにじられました。
母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、
婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。
「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」
まさか――あの優しい彼が?
そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。
子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。
でも、私には、味方など誰もいませんでした。
ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。
白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。
「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」
やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。
それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、
冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。
没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。
これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。
※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ
※わんこが繋ぐ恋物語です
※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?
アノマロカリス
ファンタジー
マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。
泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。
16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。
マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。
あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…
もう…我慢しなくても良いですよね?
この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。
前作の登場人物達も多数登場する予定です。
マーテルリアのイラストを変更致しました。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

『白い結婚だったので、勝手に離婚しました。何か問題あります?』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
「――離婚届、受理されました。お疲れさまでした」
教会の事務官がそう言ったとき、私は心の底からこう思った。
ああ、これでようやく三年分の無視に終止符を打てるわ。
王命による“形式結婚”。
夫の顔も知らず、手紙もなし、戦地から帰ってきたという噂すらない。
だから、はい、離婚。勝手に。
白い結婚だったので、勝手に離婚しました。
何か問題あります?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















