13 / 33
夜狩りに出よう
しおりを挟む
「お前に折り入って頼みがある」
そう話を切り出されたのは、馴染みの酒場でのことだ。
「なんだよ。いきなりかしこまって」
ウーファと呼ばれる、紫水晶色の果実酒を口にしていたルイトが視線をあげる。
……こうやって二人で酒を飲むのが当たり前になったのは、あれから程なくしてから。
顔見知り程度だった二人は今やもう、親しい友人といってもいいくらいの関係だろう。なんせ、3日に一回はこうやって杯を酌み交わす間柄なのだから。
最初、この酒場に誘ったのは意外にもルイトだった。
『この前の酒と助けてくれたお礼』
と理由をつけたが、次からはもう特に理由もつくらず互いに誘い合うようになった。
飲んでいる間、とりとめのない雑談ばかり。仕事のことや、子育てのこと。失敗や成功も含めて、リュウガは彼の話を静かに聞いてくれる。
あまり口数の多い男ではないが、それでも真摯な聞きっぷりと諸外国を旅したことから珍しい話題に事欠かない。
なんならふと訪れる沈黙でさえ、居心地のよいものであった。
その上、少しでもルイトの体調が思わしくなければさり気なく気遣う様も好感をもてる。
そんな彼が、泡のついたジョッキをテーブルにおいて冒頭の一言。
いつになく真剣な表情に、こちらもついつい顔が曇る。
「そりゃあ、僕で出来ることがあればなんでもするけど――」
「おいおいおい、ルイト。そんなこと言っていいのかよ!」
横から口を出したのは、店の主人セト。
ルイトがここに彼を連れてくることをよく思っておらず、始終苦虫を噛み潰したような表情だったのだ。
手はテキパキと仕事をしつつも、射るような視線をよこしてくる。
「おいアンタ。おれの目は誤魔化せないぞ。彼の体目当てなら、ゆるさねぇからな」
「はぁ? 君は何をいってんだよ!」
突然、意味不明に怒り出す彼に思わず立ち上がる。
ここのところ少しおかしい。
根掘り葉掘りリュウガのことを聞き出す所から始まって。やたらと難しい顔をしてだまりこんでいると思ったら、酒を黙々と飲ませようとしてくる。
しかもそれがやたら度数の高いものだもんで、店の女の子たちが飛んでくる始末。
『店長ぉぉっ! それは人としてダメですぅぅぅっ』
『店長だけはッ、紳士でいてぇぇ!!!』
と。
まったくもってワケが分からない。首を傾げるばかりのルイトを尻目に、セトは大真面目に言い放った。
「コイツの貞操は、おれが守るッ!」
「だからなんなんだよ……」
店の経営とはこれほど大変なのだろうか。
疲れきって、ワケのわからないことをわめくくらいに。
(少しマメにきてやったほうがいいかもな)
大変だった時に助けてくれた恩人だ。なんなら友人くらいに思っている男が、精神的に参っているならなんとかしてやりたい。
たとえそれが、自分の力が及ばないことであっても。
……なんてある意味見当違いのことを考えながら、再びリュウガに向き直る。
「で。どんなことだ? 僕でよければ、力になるよ」
「おぅ。さすが俺のダチだぜ」
「!!!」
ぴくり、と身体を震わせたのは喜びによるものだった。
ダチ――つまり友人としてリュウガは自分をみてくれている。
これは彼にとってめちゃくちゃ嬉しかった。
田舎から出てきてこの生活。金は多少手に入るし刺激は多いが、人間関係には恵まれにくい。
彼にはまだ、困った時に助けてくれる人達がいるが。それも難しいのが、都会の荒波。
同業者であればなおさら。足の引っ張り合いなんて日常茶飯事で。
(友達か)
いってしまえば、こういう友情に憧れていたという。
町に出る前から彼には、ダチとかツレとかとよぶようなモノはいなかった。決してコミュ障だとか付き合い悪い方ではなかったのだが、なぜか同性からは距離を置かれがちだったのだ。
もちろん邪険にされてきたのではない。
むしろその逆で、ちやほやされてきたフシもある。
言わば姫扱いというべきか。実の両親ですらその違和感はあり、ついに嫌になったルイトは村を飛び出してきたのだ。
言えば必ず引き止められるだろうから、夜中にこっそり家出同然で。そして今に至る。
「どうした」
「いや……なんでもない」
ダチ、という言葉の響きに感動していた。
「で、僕はなにをすればいい?」
「おいっ、ルイト! 自分を安売りすんな!!!」
「うるさいな。セトは黙ってろよ」
横から飛んでくる声に舌打ちする。
この男も、たいがい距離感がおかしい。村の男たちも、たいがいこうだったのだ。
親切は嬉しいが、もっとこう対等な関係が欲しい。
「こんなこと。お前にしか頼めなくてな、助かるぜ。実はな――」
小さく笑みを浮かべるリュウガが、そのあと口にした言葉にルイトは目を点にした。
※※※
森に入っていく足音が二人分。夜の森に響く。
「二人とも、こんな時間に悪いな」
「いいんだ。な? ルシア」
「うん! おしごとー!」
まだまだチビだが口は達者な娘、ルシアと冒険者が二人だ。
いわゆる夜の狩りを手伝って欲しい、とリュウガから持ちかけられた時。少し首をかしげてしまった。
なぜなら『ルシアも一緒に』という言葉付きである。
(何を考えているんだ、コイツは)
まさか彼もロリコンだったとか。そうならもう、立ち直れない。そんな不安を胸に、もしそうなら森の中で叩き切ってやるのも友情なんじゃあないかとか。思考を暴走させつつ、この場に来た。
「でも本当にいいのか」
「いいや、気にするな」
ルシアはちゃっかりと、リュウガのたくましい腕に抱かれている。
彼女がどうしてもと言ってきかなかったのだ。
はじめての出会いもあってか、この幼い娘は彼に夢中だ。ともすれば。
『ママよりリュウガの抱っこの方が、紳士的だわ』
だなんて言ってのけて、ルイトをしこたま凹ませる始末。
幼女といえどイケメンには弱いのか。と大人げなくヤキモチも妬きたくなる。
(ついこの前まで『ママ、ママ』って僕じゃなきゃダメだったのに)
おマセな娘の成長に切なくも、うれしいというべきだろうか。それでもそっとため息をつけば、リュウガは微笑んだ。
「じゃあ行くか」
「おーっ!」
ルンルンの娘と、どこかふくれっ面のルイト。そしてその頭を、わしゃわしゃと撫で回す大きな手。
「っ、りゅ、リュウガ!」
「可愛い顔をしてたからつい、な」
「かっ、かわい……っ!?」
顔がみるみるうちに熱くなる。まるで首から上に火がついたようだ。
なせだか、全然イヤじゃない。むしろ、恥ずかしくて仕方ないのに喜んですらいた。
(友達に可愛いっていわれて、うれしいなんて)
おかしいにきまってる。他の者になら腹をたてこそすれ、頬を染めることだってしないだろう。
なのに彼は別。まるで極上の美女からの賛美のように、いやそれ以上に恥じらう姿は本人に自覚はなけれどまるで――。
「どうした」
「いや、別に」
無言になったルイトを、心配そうに覗き込むエメラルドグリーンの瞳。
この深い色に吸い込まれてそう、なんて考えれば今度は視線を外せなくなる。
「熱でもあるんじゃないのか」
「大丈夫だってば」
さすがのリュウガもなにか様子がおかしいと思ったのか、また一歩踏み込んでくる距離に心臓が跳ねる。
おかしい。さっきから、すごくおかしい。
妙な魔法か薬でも仕込まれたのではなかろうか、なんていつもならする警戒心もこの男の前では思考の端にものぼらない。
「そうか」
「うん。ていうか、リュウガだって……」
「俺か?」
そう。ルイトほどではないが、うっすら赤らんでいる頬。
互いに酒を飲んでいるワケじゃないのに。
(なんでこんなに、ドキドキするんだ)
娘を抱いた男がえらく魅力的に見える。普通にしていても美形な男のはずだが、それにしても美しい。
少しクセのある赤い髪は出会った時よりのびた。今度切ってやろうか、と思った瞬間。
「はーやーくぅぅっ! ママっ!! リュウガ!!!」
「……っ」
「そ、そうだな。行くか」
二人の間に流れる妙な空気を完全にぶち壊すのは、無邪気な娘の声。
彼らは一瞬視線を合わせて、また弾かれたようにそらして。
(な、なんなんだ今の)
甘ったるい雰囲気が夜の森にただようこと自体が、ひどく場違いだ。でも、それ以上に娘に気取られないようにするのに必死だった。
「ルイト?」
「あ、ああ。じゃあルシア、何かおかしいことがあればちゃんと言うんだぞ」
「はーいっ!」
一度、突然いなくなったことがあるから念押ししておくのを忘れない。それに彼女はどうも、目に見えぬ存在に気に入られているらしい。
まだ赤子と呼ばれるうちから、なにやら部屋の隅でキャッキャしてると思えばそこには何もおらず。
少し大きくなってからも、やはり目に見えぬ者たちとお喋りしていると言い出すことも多々あった。
単なる子どもの想像力とするには、あまりにもリアリティのある言動にルイトは深く考えるのをやめたのだ。
その代わり、こうやって目を離さないようにはしているわけだが。
「俺がついてるから大丈夫だな」
「うん! リュウガいるから、だいじょーぶ♡」
「……」
優しいを超えた声色の男に目をキラキラさせる娘。
そしてなぜか少しムッツリと黙り込んだルイトは、木々がざわめく森を進み出した。
彼らを密かに尾ける影に気がつくことなく――。
そう話を切り出されたのは、馴染みの酒場でのことだ。
「なんだよ。いきなりかしこまって」
ウーファと呼ばれる、紫水晶色の果実酒を口にしていたルイトが視線をあげる。
……こうやって二人で酒を飲むのが当たり前になったのは、あれから程なくしてから。
顔見知り程度だった二人は今やもう、親しい友人といってもいいくらいの関係だろう。なんせ、3日に一回はこうやって杯を酌み交わす間柄なのだから。
最初、この酒場に誘ったのは意外にもルイトだった。
『この前の酒と助けてくれたお礼』
と理由をつけたが、次からはもう特に理由もつくらず互いに誘い合うようになった。
飲んでいる間、とりとめのない雑談ばかり。仕事のことや、子育てのこと。失敗や成功も含めて、リュウガは彼の話を静かに聞いてくれる。
あまり口数の多い男ではないが、それでも真摯な聞きっぷりと諸外国を旅したことから珍しい話題に事欠かない。
なんならふと訪れる沈黙でさえ、居心地のよいものであった。
その上、少しでもルイトの体調が思わしくなければさり気なく気遣う様も好感をもてる。
そんな彼が、泡のついたジョッキをテーブルにおいて冒頭の一言。
いつになく真剣な表情に、こちらもついつい顔が曇る。
「そりゃあ、僕で出来ることがあればなんでもするけど――」
「おいおいおい、ルイト。そんなこと言っていいのかよ!」
横から口を出したのは、店の主人セト。
ルイトがここに彼を連れてくることをよく思っておらず、始終苦虫を噛み潰したような表情だったのだ。
手はテキパキと仕事をしつつも、射るような視線をよこしてくる。
「おいアンタ。おれの目は誤魔化せないぞ。彼の体目当てなら、ゆるさねぇからな」
「はぁ? 君は何をいってんだよ!」
突然、意味不明に怒り出す彼に思わず立ち上がる。
ここのところ少しおかしい。
根掘り葉掘りリュウガのことを聞き出す所から始まって。やたらと難しい顔をしてだまりこんでいると思ったら、酒を黙々と飲ませようとしてくる。
しかもそれがやたら度数の高いものだもんで、店の女の子たちが飛んでくる始末。
『店長ぉぉっ! それは人としてダメですぅぅぅっ』
『店長だけはッ、紳士でいてぇぇ!!!』
と。
まったくもってワケが分からない。首を傾げるばかりのルイトを尻目に、セトは大真面目に言い放った。
「コイツの貞操は、おれが守るッ!」
「だからなんなんだよ……」
店の経営とはこれほど大変なのだろうか。
疲れきって、ワケのわからないことをわめくくらいに。
(少しマメにきてやったほうがいいかもな)
大変だった時に助けてくれた恩人だ。なんなら友人くらいに思っている男が、精神的に参っているならなんとかしてやりたい。
たとえそれが、自分の力が及ばないことであっても。
……なんてある意味見当違いのことを考えながら、再びリュウガに向き直る。
「で。どんなことだ? 僕でよければ、力になるよ」
「おぅ。さすが俺のダチだぜ」
「!!!」
ぴくり、と身体を震わせたのは喜びによるものだった。
ダチ――つまり友人としてリュウガは自分をみてくれている。
これは彼にとってめちゃくちゃ嬉しかった。
田舎から出てきてこの生活。金は多少手に入るし刺激は多いが、人間関係には恵まれにくい。
彼にはまだ、困った時に助けてくれる人達がいるが。それも難しいのが、都会の荒波。
同業者であればなおさら。足の引っ張り合いなんて日常茶飯事で。
(友達か)
いってしまえば、こういう友情に憧れていたという。
町に出る前から彼には、ダチとかツレとかとよぶようなモノはいなかった。決してコミュ障だとか付き合い悪い方ではなかったのだが、なぜか同性からは距離を置かれがちだったのだ。
もちろん邪険にされてきたのではない。
むしろその逆で、ちやほやされてきたフシもある。
言わば姫扱いというべきか。実の両親ですらその違和感はあり、ついに嫌になったルイトは村を飛び出してきたのだ。
言えば必ず引き止められるだろうから、夜中にこっそり家出同然で。そして今に至る。
「どうした」
「いや……なんでもない」
ダチ、という言葉の響きに感動していた。
「で、僕はなにをすればいい?」
「おいっ、ルイト! 自分を安売りすんな!!!」
「うるさいな。セトは黙ってろよ」
横から飛んでくる声に舌打ちする。
この男も、たいがい距離感がおかしい。村の男たちも、たいがいこうだったのだ。
親切は嬉しいが、もっとこう対等な関係が欲しい。
「こんなこと。お前にしか頼めなくてな、助かるぜ。実はな――」
小さく笑みを浮かべるリュウガが、そのあと口にした言葉にルイトは目を点にした。
※※※
森に入っていく足音が二人分。夜の森に響く。
「二人とも、こんな時間に悪いな」
「いいんだ。な? ルシア」
「うん! おしごとー!」
まだまだチビだが口は達者な娘、ルシアと冒険者が二人だ。
いわゆる夜の狩りを手伝って欲しい、とリュウガから持ちかけられた時。少し首をかしげてしまった。
なぜなら『ルシアも一緒に』という言葉付きである。
(何を考えているんだ、コイツは)
まさか彼もロリコンだったとか。そうならもう、立ち直れない。そんな不安を胸に、もしそうなら森の中で叩き切ってやるのも友情なんじゃあないかとか。思考を暴走させつつ、この場に来た。
「でも本当にいいのか」
「いいや、気にするな」
ルシアはちゃっかりと、リュウガのたくましい腕に抱かれている。
彼女がどうしてもと言ってきかなかったのだ。
はじめての出会いもあってか、この幼い娘は彼に夢中だ。ともすれば。
『ママよりリュウガの抱っこの方が、紳士的だわ』
だなんて言ってのけて、ルイトをしこたま凹ませる始末。
幼女といえどイケメンには弱いのか。と大人げなくヤキモチも妬きたくなる。
(ついこの前まで『ママ、ママ』って僕じゃなきゃダメだったのに)
おマセな娘の成長に切なくも、うれしいというべきだろうか。それでもそっとため息をつけば、リュウガは微笑んだ。
「じゃあ行くか」
「おーっ!」
ルンルンの娘と、どこかふくれっ面のルイト。そしてその頭を、わしゃわしゃと撫で回す大きな手。
「っ、りゅ、リュウガ!」
「可愛い顔をしてたからつい、な」
「かっ、かわい……っ!?」
顔がみるみるうちに熱くなる。まるで首から上に火がついたようだ。
なせだか、全然イヤじゃない。むしろ、恥ずかしくて仕方ないのに喜んですらいた。
(友達に可愛いっていわれて、うれしいなんて)
おかしいにきまってる。他の者になら腹をたてこそすれ、頬を染めることだってしないだろう。
なのに彼は別。まるで極上の美女からの賛美のように、いやそれ以上に恥じらう姿は本人に自覚はなけれどまるで――。
「どうした」
「いや、別に」
無言になったルイトを、心配そうに覗き込むエメラルドグリーンの瞳。
この深い色に吸い込まれてそう、なんて考えれば今度は視線を外せなくなる。
「熱でもあるんじゃないのか」
「大丈夫だってば」
さすがのリュウガもなにか様子がおかしいと思ったのか、また一歩踏み込んでくる距離に心臓が跳ねる。
おかしい。さっきから、すごくおかしい。
妙な魔法か薬でも仕込まれたのではなかろうか、なんていつもならする警戒心もこの男の前では思考の端にものぼらない。
「そうか」
「うん。ていうか、リュウガだって……」
「俺か?」
そう。ルイトほどではないが、うっすら赤らんでいる頬。
互いに酒を飲んでいるワケじゃないのに。
(なんでこんなに、ドキドキするんだ)
娘を抱いた男がえらく魅力的に見える。普通にしていても美形な男のはずだが、それにしても美しい。
少しクセのある赤い髪は出会った時よりのびた。今度切ってやろうか、と思った瞬間。
「はーやーくぅぅっ! ママっ!! リュウガ!!!」
「……っ」
「そ、そうだな。行くか」
二人の間に流れる妙な空気を完全にぶち壊すのは、無邪気な娘の声。
彼らは一瞬視線を合わせて、また弾かれたようにそらして。
(な、なんなんだ今の)
甘ったるい雰囲気が夜の森にただようこと自体が、ひどく場違いだ。でも、それ以上に娘に気取られないようにするのに必死だった。
「ルイト?」
「あ、ああ。じゃあルシア、何かおかしいことがあればちゃんと言うんだぞ」
「はーいっ!」
一度、突然いなくなったことがあるから念押ししておくのを忘れない。それに彼女はどうも、目に見えぬ存在に気に入られているらしい。
まだ赤子と呼ばれるうちから、なにやら部屋の隅でキャッキャしてると思えばそこには何もおらず。
少し大きくなってからも、やはり目に見えぬ者たちとお喋りしていると言い出すことも多々あった。
単なる子どもの想像力とするには、あまりにもリアリティのある言動にルイトは深く考えるのをやめたのだ。
その代わり、こうやって目を離さないようにはしているわけだが。
「俺がついてるから大丈夫だな」
「うん! リュウガいるから、だいじょーぶ♡」
「……」
優しいを超えた声色の男に目をキラキラさせる娘。
そしてなぜか少しムッツリと黙り込んだルイトは、木々がざわめく森を進み出した。
彼らを密かに尾ける影に気がつくことなく――。
10
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
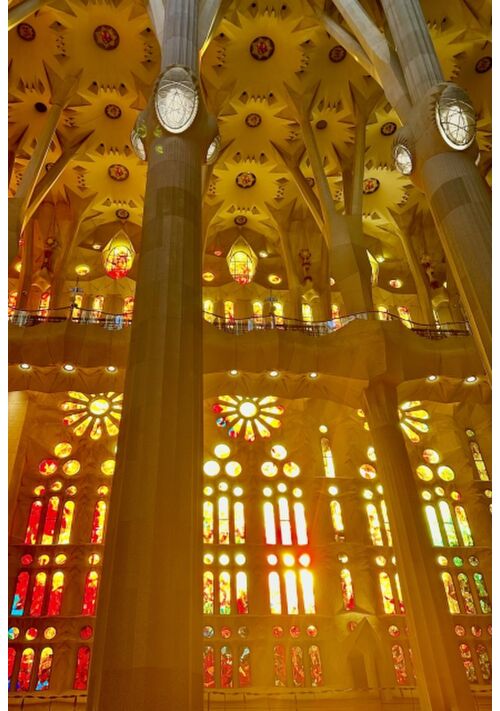
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















