14 / 33
夜狩に潜む黒い陰と悪魔の子1
しおりを挟む
闇に活気づくモンスターもいる。むしろ、彼らの多くは夜行性といってもいいだろう。
「お、これって……」
「ああ。魔性植物だ」
釣鐘型の可憐な花びらが特徴の、一般的な薬草とは違う。
同じ名をもつこれは、毒々しい真紅の花と黒い実を同時につける魔界原産の植物であった。
葉はもとより。根も実も、どこもかしこも煎じれば薬になる。昼性と違い、夜性はほとんどが毒や呪術に用いられる。
「珍しいな。つんで帰ろうか」
きっと薬屋に売れば高値になる、そう思って手を伸ばす。
「やめろ!」
「えっ」
存外、厳しい声がかえってきて思わず手をひっこめた。
そして恐る恐る、振り返る。
「すまない」
バツが悪そうに目を伏せながらも、彼はかすかに呻いているその植物を指さした。
「こいつは特に先祖返りが激しいみたいだ。見てみろ、茎に血管が通っている」
確かによく見れば、葉から土の下へ伸びてい茎にはふしのある管が数本。
しかも赤黒く、ドクドクと脈打っているのが分かる。
「マンドラゴラとは今や、人間界に群生しているがな。元はすべて魔界の生息動物、つまりモンスターの一種だったといわれている」
「そう、なのか……」
彼いわく。
進化や生育環境の変化。大敵の出現から、彼らは進化したと。動物かは植物への大胆な変換。それが過酷な環境からの脱出へとつながった。
「しかし元の習性が消えたわけじゃねぇ。ヤツらは、人を惑わして食う。気をつけな」
「わ、悪かったな」
悪魔の仕業といわれていることの多くは、この魔の植物によるものだと彼は言う。
呪いだったり毒薬がみせる幻覚だったり。はたまた、そのものが災いするのだと。
それがどんかものか検討もつかないが、ルイトはふと身を震わせた。
「ま、迷信も多いがな。とにかく、さわるるもんじゃねぇ」
「わか――っ!?」
わかった、と言おうと思ったのに。またその大きな手に頭をかるくなでられて目を見開く。
「……怒鳴っちまってわりぃ」
「こ、子どもあつかいしてんじゃない!」
見下ろしてくる眼差しが、ひたすらあたたかい。
なぜだろう。なぜかくすぐったいような、でもけっしてイヤじゃない。妙な気分。
「俺にとっては、ルシアと変わらないぜ」
「は、はぁぁぁ!?」
おマセであるがまだまだ幼い娘と、同じとはどういう事だ。さすがにそれはないだろうも詰め寄るも。
「どちらも大切な存在だっていうことだが」
「……」
(なんだよ、それ)
うれしいような。まだ少しモヤモヤするような。
でも。
(それじゃあ僕がなんか期待してるみたいじゃないか!)
ルシアもいるのに、とあわてて首をふって気持ちを切り変えようとする。
しかも相手は友達だ。はじめて出来たといってもいい。
今までのヤツらのように、変に距離をつめてきたり小娘にするような口説き文句で揶揄ってこない。
ちゃんと対等に、そして紳士に向き合ってくれる。
娘のことだって可愛がってくれて、彼女自身も彼を気に入っているのだ。
なんの邪念を抱くことがあろう。
「それにしても、くわしいんだな。植物系モンスターのこと」
改めて歩を進めながら、何ともなしに訊ねてみる。
すると、少し疲れたのかウトウトし始めたルシアを抱き直した彼は小さくうなずく。
「故郷では、動植物の研究をしていたからな」
「へぇ」
きけば幼いうちはそれなりの教育を受けてきたという。
もともと興味のあった分野ということもあり、学術研究を専門とする教育機関。つまり学校にいく機会にも恵まれた。
「すると君は、学者先生ってわけか」
「そんないいもんじゃねぇぜ」
照れ隠しなのか、片眉をあげて笑う。
「好きなことを好きなようにやってきたなけだ。今までも……そしてこれからも、な」
「!」
またこの目だ。
優しく降り注ぐ、日差しのような。それが友情であったり、慈愛であるのは分かっているつもりだが。それでもなぜか、身体の奥から湧き上がるなにかを感じていた。
「う……むにゃ……にくぅ……」
再び二人の視線が交わった瞬間。
幼子のなんとも無邪気な寝言が響く。
「ふふっ、ルシアはまた肉食う夢か」
「食いしん坊だからな」
食べ盛り育ち盛り。そして身体の変化がどんどん顕著になっていく。
「この子、頭につのが出てきたんだ」
「ふむ。生まれつきか」
そっと触れればわかる程度のものが、頭の左右に一対。まるでヤギの角のようだ、とルイトは言う
「あと尾てい骨? のあたりにも、しっぽらしきものが生えてきたんだ。こんなのまるで――」
「悪魔、だな」
「ああ」
天使と並び、架空の生物。魔界に住み、狡猾で人間の魂を食らうという。
一説によるとヤギの角や、半身をもったそれは同じく長いしっぽの先のトゲで人の心臓をえぐるのだとか。
荒唐無稽なおとぎ話であるとすればそれまでだが、子供から大人まで誰しもが知っている伝説だ。
「尖った耳から、多分魔族だとは思うんだけど……」
「思う? お前はこの子の実の親ではないのか」
「実の親さ。多分」
目の色から顔立ち。それらは確かに自分とそっくりだと言われる。しかし他があまりにも違いすぎる。
見事な赤髪も、普通なら持つはずのないツノもしっぽも。そして、尖った耳も。
「僕は、この子が大きくなるのが少し怖いんだ」
「……」
「成長はうれしいけど、やっぱり怖い。この子が何者なのか、それを知るのが」
母親を探そうと思ったのも、その恐怖を克服したいがためなのかもしれない。
少なくても。どう育つかわからない、先が見えない事に怯えなくてもいい。
それに。
「この仕事をしていたら、人間より魔物を見る方がずっと多いだろ」
そうすると己の娘のことなんて、まったく気にならなくなるのに気がついた。
一緒に連れて歩くのもそれが理由のひとつ。
「親として最低だけど」
スヤスヤと眠る彼女の髪をなでる。
「僕は、他人がルシアを抱いているのが少し恐ろしい」
可愛い可愛いと言われるし、もちろん可愛いのだけれど。ふとその者が向けた視線が気になってしまう。
『この子、なんか違う?』
といった表情に。
「魔族ってだけならまだ良かったんだ。この町には、人間以外にも多いから。でも、悪魔はダメだ」
以前、娘に触れた子どもが首をかしげて放った言葉。
『この子。悪魔の子みたい』
背筋が凍った。そんなのいるはずがない、って否定できず黙り込んでしまった自分に腹が立った。
「この子がどの種族とも違う、それが悲しい」
娘の将来を考えるだけで胸が潰れそうだ。
こんなに可愛いのに、こんなにお利口さんなのに。いつか彼女は、周りから忌まれ恐れられるのだろうか。
悪魔の子と、石を投げられたりしないだろうか。
唇を噛んだルイトに大柄な身体が、そっと寄り添う。
「じゃあ、守ってやりゃあいい」
「でも……っ」
「いつか、ルシアがテメェの身を守ることができるまでだ」
それが親ってもんだ、とリュウガは穏やかに言った。
「それが出来るのは、お前だろう」
「僕は――」
「お前には、たくさんの人間がいる。忘れたか?」
「……」
突然あらわれた赤子を前に、育てられないと泣き言いっても叱咤しつつ助けてくれたセト。
いつも娘だけでなく、親であるルイトのことも心配してくれたロロ。
他にも優しく見守ってくれている、町の人たちや酒場の女の子達もいるだろう。
彼らの顔を思い浮かべる。
「それに俺もいる」
「リュウガ」
「忘れんな。お前とお前の娘には、たくさんの味方がいるんだ。信じてやってくれ」
「……ありがとう」
目頭が熱くなって、慌ててまぶたをこすった。
「重たいだろ。そろそろ僕が抱っこするよ」
「大丈夫だぞ、これくらい」
「いいって。先はまだあるんだろ」
「しかし……」
大型ドラゴンの卵の方が重かった、なんてよく分からない例え話をする男の腕から笑いながら娘を受け取る。
「君も一緒に、この子の成長を見届けてくれないか」
少し寝ぐずりした娘の背中をさすりながら、ほとんど呟くように口にした言葉。
(え……いま、僕、何を……)
まるでプロポーズするような言い草に、自分で動揺した。
いや、そういう意味じゃなくて! なんて言い訳しようと顔をあげると。
「もちろん、そのつもりだ」
真摯な瞳に見つめられていた。
そしてついに、互いの視線が交差してゆっくりと差し出された腕に――。
「!」
「……下がってろ」
その瞬間。
近くの茂みから、甲高い雄叫びが夜の森を震わせた。
「お、これって……」
「ああ。魔性植物だ」
釣鐘型の可憐な花びらが特徴の、一般的な薬草とは違う。
同じ名をもつこれは、毒々しい真紅の花と黒い実を同時につける魔界原産の植物であった。
葉はもとより。根も実も、どこもかしこも煎じれば薬になる。昼性と違い、夜性はほとんどが毒や呪術に用いられる。
「珍しいな。つんで帰ろうか」
きっと薬屋に売れば高値になる、そう思って手を伸ばす。
「やめろ!」
「えっ」
存外、厳しい声がかえってきて思わず手をひっこめた。
そして恐る恐る、振り返る。
「すまない」
バツが悪そうに目を伏せながらも、彼はかすかに呻いているその植物を指さした。
「こいつは特に先祖返りが激しいみたいだ。見てみろ、茎に血管が通っている」
確かによく見れば、葉から土の下へ伸びてい茎にはふしのある管が数本。
しかも赤黒く、ドクドクと脈打っているのが分かる。
「マンドラゴラとは今や、人間界に群生しているがな。元はすべて魔界の生息動物、つまりモンスターの一種だったといわれている」
「そう、なのか……」
彼いわく。
進化や生育環境の変化。大敵の出現から、彼らは進化したと。動物かは植物への大胆な変換。それが過酷な環境からの脱出へとつながった。
「しかし元の習性が消えたわけじゃねぇ。ヤツらは、人を惑わして食う。気をつけな」
「わ、悪かったな」
悪魔の仕業といわれていることの多くは、この魔の植物によるものだと彼は言う。
呪いだったり毒薬がみせる幻覚だったり。はたまた、そのものが災いするのだと。
それがどんかものか検討もつかないが、ルイトはふと身を震わせた。
「ま、迷信も多いがな。とにかく、さわるるもんじゃねぇ」
「わか――っ!?」
わかった、と言おうと思ったのに。またその大きな手に頭をかるくなでられて目を見開く。
「……怒鳴っちまってわりぃ」
「こ、子どもあつかいしてんじゃない!」
見下ろしてくる眼差しが、ひたすらあたたかい。
なぜだろう。なぜかくすぐったいような、でもけっしてイヤじゃない。妙な気分。
「俺にとっては、ルシアと変わらないぜ」
「は、はぁぁぁ!?」
おマセであるがまだまだ幼い娘と、同じとはどういう事だ。さすがにそれはないだろうも詰め寄るも。
「どちらも大切な存在だっていうことだが」
「……」
(なんだよ、それ)
うれしいような。まだ少しモヤモヤするような。
でも。
(それじゃあ僕がなんか期待してるみたいじゃないか!)
ルシアもいるのに、とあわてて首をふって気持ちを切り変えようとする。
しかも相手は友達だ。はじめて出来たといってもいい。
今までのヤツらのように、変に距離をつめてきたり小娘にするような口説き文句で揶揄ってこない。
ちゃんと対等に、そして紳士に向き合ってくれる。
娘のことだって可愛がってくれて、彼女自身も彼を気に入っているのだ。
なんの邪念を抱くことがあろう。
「それにしても、くわしいんだな。植物系モンスターのこと」
改めて歩を進めながら、何ともなしに訊ねてみる。
すると、少し疲れたのかウトウトし始めたルシアを抱き直した彼は小さくうなずく。
「故郷では、動植物の研究をしていたからな」
「へぇ」
きけば幼いうちはそれなりの教育を受けてきたという。
もともと興味のあった分野ということもあり、学術研究を専門とする教育機関。つまり学校にいく機会にも恵まれた。
「すると君は、学者先生ってわけか」
「そんないいもんじゃねぇぜ」
照れ隠しなのか、片眉をあげて笑う。
「好きなことを好きなようにやってきたなけだ。今までも……そしてこれからも、な」
「!」
またこの目だ。
優しく降り注ぐ、日差しのような。それが友情であったり、慈愛であるのは分かっているつもりだが。それでもなぜか、身体の奥から湧き上がるなにかを感じていた。
「う……むにゃ……にくぅ……」
再び二人の視線が交わった瞬間。
幼子のなんとも無邪気な寝言が響く。
「ふふっ、ルシアはまた肉食う夢か」
「食いしん坊だからな」
食べ盛り育ち盛り。そして身体の変化がどんどん顕著になっていく。
「この子、頭につのが出てきたんだ」
「ふむ。生まれつきか」
そっと触れればわかる程度のものが、頭の左右に一対。まるでヤギの角のようだ、とルイトは言う
「あと尾てい骨? のあたりにも、しっぽらしきものが生えてきたんだ。こんなのまるで――」
「悪魔、だな」
「ああ」
天使と並び、架空の生物。魔界に住み、狡猾で人間の魂を食らうという。
一説によるとヤギの角や、半身をもったそれは同じく長いしっぽの先のトゲで人の心臓をえぐるのだとか。
荒唐無稽なおとぎ話であるとすればそれまでだが、子供から大人まで誰しもが知っている伝説だ。
「尖った耳から、多分魔族だとは思うんだけど……」
「思う? お前はこの子の実の親ではないのか」
「実の親さ。多分」
目の色から顔立ち。それらは確かに自分とそっくりだと言われる。しかし他があまりにも違いすぎる。
見事な赤髪も、普通なら持つはずのないツノもしっぽも。そして、尖った耳も。
「僕は、この子が大きくなるのが少し怖いんだ」
「……」
「成長はうれしいけど、やっぱり怖い。この子が何者なのか、それを知るのが」
母親を探そうと思ったのも、その恐怖を克服したいがためなのかもしれない。
少なくても。どう育つかわからない、先が見えない事に怯えなくてもいい。
それに。
「この仕事をしていたら、人間より魔物を見る方がずっと多いだろ」
そうすると己の娘のことなんて、まったく気にならなくなるのに気がついた。
一緒に連れて歩くのもそれが理由のひとつ。
「親として最低だけど」
スヤスヤと眠る彼女の髪をなでる。
「僕は、他人がルシアを抱いているのが少し恐ろしい」
可愛い可愛いと言われるし、もちろん可愛いのだけれど。ふとその者が向けた視線が気になってしまう。
『この子、なんか違う?』
といった表情に。
「魔族ってだけならまだ良かったんだ。この町には、人間以外にも多いから。でも、悪魔はダメだ」
以前、娘に触れた子どもが首をかしげて放った言葉。
『この子。悪魔の子みたい』
背筋が凍った。そんなのいるはずがない、って否定できず黙り込んでしまった自分に腹が立った。
「この子がどの種族とも違う、それが悲しい」
娘の将来を考えるだけで胸が潰れそうだ。
こんなに可愛いのに、こんなにお利口さんなのに。いつか彼女は、周りから忌まれ恐れられるのだろうか。
悪魔の子と、石を投げられたりしないだろうか。
唇を噛んだルイトに大柄な身体が、そっと寄り添う。
「じゃあ、守ってやりゃあいい」
「でも……っ」
「いつか、ルシアがテメェの身を守ることができるまでだ」
それが親ってもんだ、とリュウガは穏やかに言った。
「それが出来るのは、お前だろう」
「僕は――」
「お前には、たくさんの人間がいる。忘れたか?」
「……」
突然あらわれた赤子を前に、育てられないと泣き言いっても叱咤しつつ助けてくれたセト。
いつも娘だけでなく、親であるルイトのことも心配してくれたロロ。
他にも優しく見守ってくれている、町の人たちや酒場の女の子達もいるだろう。
彼らの顔を思い浮かべる。
「それに俺もいる」
「リュウガ」
「忘れんな。お前とお前の娘には、たくさんの味方がいるんだ。信じてやってくれ」
「……ありがとう」
目頭が熱くなって、慌ててまぶたをこすった。
「重たいだろ。そろそろ僕が抱っこするよ」
「大丈夫だぞ、これくらい」
「いいって。先はまだあるんだろ」
「しかし……」
大型ドラゴンの卵の方が重かった、なんてよく分からない例え話をする男の腕から笑いながら娘を受け取る。
「君も一緒に、この子の成長を見届けてくれないか」
少し寝ぐずりした娘の背中をさすりながら、ほとんど呟くように口にした言葉。
(え……いま、僕、何を……)
まるでプロポーズするような言い草に、自分で動揺した。
いや、そういう意味じゃなくて! なんて言い訳しようと顔をあげると。
「もちろん、そのつもりだ」
真摯な瞳に見つめられていた。
そしてついに、互いの視線が交差してゆっくりと差し出された腕に――。
「!」
「……下がってろ」
その瞬間。
近くの茂みから、甲高い雄叫びが夜の森を震わせた。
10
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
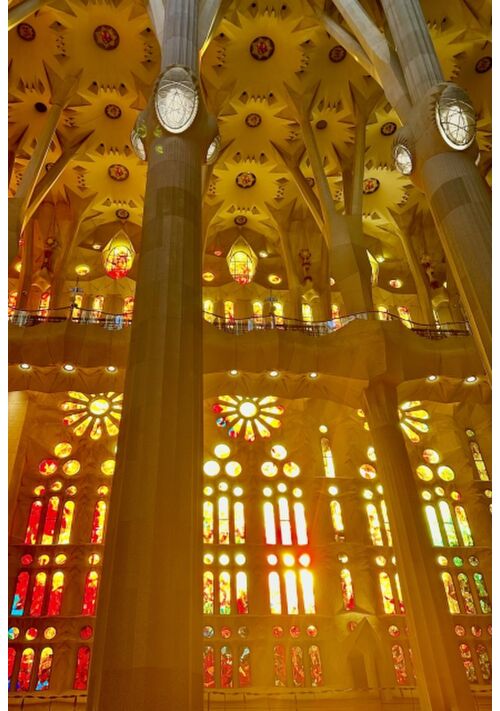
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















