30 / 33
瘴気の森の小屋4
しおりを挟む
ロロ・ココ。
この女性もまたリュウガと同じ、国に雇われた調査員だと彼女自身語った。
「まさか君が……兵士なのか」
「非正規雇用だけどネ」
驚きを隠せないといった彼に、ロロは豪快に笑ってみせる。
「全然知らなかったな」
「言ってなかったからヨ」
しかしとてもそうは見えない。無愛想だが気立ての良い中年女。確かに彼女の過去などよく聞いたことはないし、おそらくこの町の誰も知らないだろう。
ただ『気がついたらここに住み着いていた』のだと。
元々、人の出入りが激しい港町であり都会。それぞれが何がしかの過去を背負って生きているのだから、それを必要以上に詮索したりするのは野暮というものだ。
「それであの子は……」
どこかソワソワとした様子で、ルイトは辺りを見渡す。
やはり気になるのが、あの影だった。影のような全身真っ黒な兄妹。
まるでミュージカルのような軽やかさと、奇妙なフシのついた言葉回しの影人間達の姿が頭から離れない。
それもすべて夢だったのか。いや、夢であって欲しい。
それを実感するためにも、とにかく娘に会いたかった。
「ちょっト、待ってるヨ」
大きくうなずいた彼女は、身体を揺すりながら奥の部屋に消えていく。
そこもやはり悪夢のことが思い出され、落ち着かない。
すすめられた椅子に座るわけでもなく、視線をさ迷わせるルイトにリュウガがそっと触れた時。
「っ!」
身体が大きく震え、その手を叩いた。反射的な行動に、驚いたのは彼自身だったのだろう。
「あ……ぁ……」
とんでもないことをしでかした子供のような気分で、目頭が熱くなる。さすがに泣き出すことはないが、ようやく小さな声で。
「す、すまない」
とつぶやいた。
「いや。俺こそ驚かせて悪かったな」
そう彼が返し、そこから気まずい沈黙が部屋を支配する。
「ルイト、お姫様の登場ヨ」
そんな空気を一掃した明るい言葉と共に、部屋のドアが開いた。
「ママ!」
そこには、ロロの腕に抱かれた少女の姿が。
艶やかに揺れる赤毛は、少しのびたのだろう。きれいに梳かされ、整えられている。
背が少しのびて、シンプルながらレースのついた服を着た彼女はまるでどこぞの令嬢のようだった。
「る、ルシア?」
「そうよ。ママ、会いたかったわ」
舌たらずだったのが、いくぶんもしっかりした口調。
二人は固く抱き合った。
「ルシア……!」
「ママ。愛してる。やっと迎えに来てくれたのね」
潤んだ瞳を覗き込めば、光に反射してキラキラと煌めく紫水晶のごとく。
ああ、やはり本物の娘だと思うと同時に自らの目からも大粒の涙があふれた。
「ルシア……ごめん……ルシア……っ」
「ママ。泣かないで」
頬にキスをする愛娘。
どこも怪我などない、キレイな顔。勝気そうな目と薔薇色の頬は健康的だ。
「ありがとう。二人とも」
彼らが娘を救い出してくれたのだ。そうでなければ、こんなに元気な姿をみせるはずは無い。
ルイトは手の甲で目元をぬぐい、頭を下げる。
「俺らは任務を遂行しただけだ。なぁ、ロロ」
「そうヨ。大事なお姫様を救出する大役ネ」
かけられた言葉は、とても暖かい。
思わずまた涙が滲みそうになるが、グッとこらえた。そして、改めて腕の中の娘の重さに驚く。
「る、ルシア。なんか重くなってないか?」
「んまあ! ママってば、レディに失礼だわ」
頬を膨らませたが、やはりその身体はかなり成長している。とても数日間ぶりとは思えぬほどに。
(さすが魔族の子だな)
頭をなでた時、やはり手に感じたのは左右に生えたツノ。ヤギのそれのように、少しとがって髪の間から覗いている。
(だとしても)
ひときわ強く、抱きしめた。
「愛してるよ。ルシア」
魔族であったとて。いや、たとえ悪魔の子だと周囲に言われても、彼女は大切な愛娘だ。慈しみ、大切に育てたい。
共に生きたい、そう心から願うのは離れていたからこそだろう。
「本当に感謝するよ。ありがとう」
ルイトは顔をあげると、彼らを真っ直ぐに見据えた。
「この子はどこにいた」
あの森で彼と別れてすぐ、ランス・ロンドに襲われて。そこから気を失ってから、一体どこでどうしていたのだろう。助け出されるまでに、恐ろしい目にでも遭っていないだろうかと心配したのだ。
しかしなぜか、リュウガはすこし顔をしかめた。
「不思議なことがあってな……」
そして彼が話したことである。
――キメラ獣達を蹴散らしてから、彼は急いで二人を探し始めた。
魔物たちが暴れ回り踏み荒らした森を、かき分けるように歩き回る。捜索は、困難を極めた。
「もう二人とも駄目かもしれねぇって思った、その時だ」
リュウガは目を細め、ルシアの赤髪を指にからませる。
くすぐったそうな。鈴の音のような声が、少女の愛らしい唇からあがった。
「突然、強い光が空の向こうから飛んでくるのが見えた。真っ直ぐにこっちに」
大きな光の球体。
それがゆっくりと風に揺れる木の葉のようなスピードで、こちらに降りてくる。
辺りはまばゆいばかりの光に包まれ、目を開けていられないほどだった。
「だが俺にはなぜか確証があった」
あの光の球が、ルシアであると。
懸命に潰れそうな視力をこらえ、手を伸ばしてその光の球を抱きとる。
不思議と熱くもなく、むしろ少しひんやりと冷たかったという。
「そしたら一瞬で、それが弾けたんだ。シャボン玉が、弾けて消えちまうように。パチンとな」
すると腕の中には彼女がいた。
スヤスヤと安らかな微笑みを浮かべた寝顔で。
「まるで天使みてぇだったな」
感嘆とも思える声でしめくくり、やはり愛おしげに頬を撫でる。
ルシアもまた、嬉しそうにその大きく無骨な手に擦り寄った。
「初めてこの子に出会った時も、飛び込んできたんだぜ」
透明な存在に運ばれ、抱かれていた赤ん坊。まるで何か目に見ぬモノ達に護られるような、そんな娘は今も花のように笑っている。
「ルイト、ルシア」
赤髪の男は彼ら親子の前にひざまづく。
「俺にお前たちを守らせてくれないか」
その姿は忠誠を誓う騎士のようで。凛々しいが、どこか不安に揺れる瞳はこちらをジッとみつめていた。
「リュウガ、僕は――」
彼が言葉を発しようと、口を開いた時。
「!」
チラリと視界の端に、黒いなにかが踊った。
(見間違い、か)
しかし目をこすってまた視線をあげるも、再び踊る影。それは部屋にある暖炉の周りをくるりと回ると、テーブルの下へ。
「どうした、ルイト」
「い、いや……」
(そんなわけない。あれは夢だった)
影。人。踊る影の少女。
瞬く間に背中を嫌な汗が伝う。
「あっ!」
キャンディがひとつ、足元に転がってきた。
それを拾い上げることも出来ず、ルイトの身体は固まったように動けない。
(夢……じゃないのか)
それともこっちが夢か。目の前が真っ暗になる。
もしこれが、つかの間の幸せな夢であったら。もう戻りたくないし、戻されれば発狂してしまうだろう。
ああ、なんて脆くなってしまっただろう。これが百戦錬磨の敏腕冒険者だと、笑わせる。
今やただの臆病者。娘を、大事な者たちを失いたくないと泣きわめく弱虫ではないか。
それが嫌だと、変わりたいと飛び出して行ったのに――。
「ゔ……っ」
吐き気が込み上げる。しかし床に伏すことすらできない。
まるで見えない鎖でがんじがらめにされたかのように、ピクリと四肢が動かせないのだ。それどころか、声も出ない。
眼球だけを必死で動かして状況を把握しようにも、目の前に黒い霧が立ち込め始める。
ついに悪夢の幕開けか。
(くそ)
せめてこのまま、舌を噛みちぎってやろうかと思った瞬間。
「……しっかりしな。娘が見てるヨ」
異国訛りの声が、彼の頭上からかけられた。
同時に雷光のごとく閃く、一線。それはルイトの足元で、複雑な幾何学模様を描く。
「!」
ピンッ――と糸を貼って弾いたような、かすかな音。
そして刹那。
『ギョ゙ァア゙ァァ゙ァッ!!!』
不協和音とノイズの混じった絶叫が響く。
禍々しい瘴気が、部屋全体に一気に広がった。
この女性もまたリュウガと同じ、国に雇われた調査員だと彼女自身語った。
「まさか君が……兵士なのか」
「非正規雇用だけどネ」
驚きを隠せないといった彼に、ロロは豪快に笑ってみせる。
「全然知らなかったな」
「言ってなかったからヨ」
しかしとてもそうは見えない。無愛想だが気立ての良い中年女。確かに彼女の過去などよく聞いたことはないし、おそらくこの町の誰も知らないだろう。
ただ『気がついたらここに住み着いていた』のだと。
元々、人の出入りが激しい港町であり都会。それぞれが何がしかの過去を背負って生きているのだから、それを必要以上に詮索したりするのは野暮というものだ。
「それであの子は……」
どこかソワソワとした様子で、ルイトは辺りを見渡す。
やはり気になるのが、あの影だった。影のような全身真っ黒な兄妹。
まるでミュージカルのような軽やかさと、奇妙なフシのついた言葉回しの影人間達の姿が頭から離れない。
それもすべて夢だったのか。いや、夢であって欲しい。
それを実感するためにも、とにかく娘に会いたかった。
「ちょっト、待ってるヨ」
大きくうなずいた彼女は、身体を揺すりながら奥の部屋に消えていく。
そこもやはり悪夢のことが思い出され、落ち着かない。
すすめられた椅子に座るわけでもなく、視線をさ迷わせるルイトにリュウガがそっと触れた時。
「っ!」
身体が大きく震え、その手を叩いた。反射的な行動に、驚いたのは彼自身だったのだろう。
「あ……ぁ……」
とんでもないことをしでかした子供のような気分で、目頭が熱くなる。さすがに泣き出すことはないが、ようやく小さな声で。
「す、すまない」
とつぶやいた。
「いや。俺こそ驚かせて悪かったな」
そう彼が返し、そこから気まずい沈黙が部屋を支配する。
「ルイト、お姫様の登場ヨ」
そんな空気を一掃した明るい言葉と共に、部屋のドアが開いた。
「ママ!」
そこには、ロロの腕に抱かれた少女の姿が。
艶やかに揺れる赤毛は、少しのびたのだろう。きれいに梳かされ、整えられている。
背が少しのびて、シンプルながらレースのついた服を着た彼女はまるでどこぞの令嬢のようだった。
「る、ルシア?」
「そうよ。ママ、会いたかったわ」
舌たらずだったのが、いくぶんもしっかりした口調。
二人は固く抱き合った。
「ルシア……!」
「ママ。愛してる。やっと迎えに来てくれたのね」
潤んだ瞳を覗き込めば、光に反射してキラキラと煌めく紫水晶のごとく。
ああ、やはり本物の娘だと思うと同時に自らの目からも大粒の涙があふれた。
「ルシア……ごめん……ルシア……っ」
「ママ。泣かないで」
頬にキスをする愛娘。
どこも怪我などない、キレイな顔。勝気そうな目と薔薇色の頬は健康的だ。
「ありがとう。二人とも」
彼らが娘を救い出してくれたのだ。そうでなければ、こんなに元気な姿をみせるはずは無い。
ルイトは手の甲で目元をぬぐい、頭を下げる。
「俺らは任務を遂行しただけだ。なぁ、ロロ」
「そうヨ。大事なお姫様を救出する大役ネ」
かけられた言葉は、とても暖かい。
思わずまた涙が滲みそうになるが、グッとこらえた。そして、改めて腕の中の娘の重さに驚く。
「る、ルシア。なんか重くなってないか?」
「んまあ! ママってば、レディに失礼だわ」
頬を膨らませたが、やはりその身体はかなり成長している。とても数日間ぶりとは思えぬほどに。
(さすが魔族の子だな)
頭をなでた時、やはり手に感じたのは左右に生えたツノ。ヤギのそれのように、少しとがって髪の間から覗いている。
(だとしても)
ひときわ強く、抱きしめた。
「愛してるよ。ルシア」
魔族であったとて。いや、たとえ悪魔の子だと周囲に言われても、彼女は大切な愛娘だ。慈しみ、大切に育てたい。
共に生きたい、そう心から願うのは離れていたからこそだろう。
「本当に感謝するよ。ありがとう」
ルイトは顔をあげると、彼らを真っ直ぐに見据えた。
「この子はどこにいた」
あの森で彼と別れてすぐ、ランス・ロンドに襲われて。そこから気を失ってから、一体どこでどうしていたのだろう。助け出されるまでに、恐ろしい目にでも遭っていないだろうかと心配したのだ。
しかしなぜか、リュウガはすこし顔をしかめた。
「不思議なことがあってな……」
そして彼が話したことである。
――キメラ獣達を蹴散らしてから、彼は急いで二人を探し始めた。
魔物たちが暴れ回り踏み荒らした森を、かき分けるように歩き回る。捜索は、困難を極めた。
「もう二人とも駄目かもしれねぇって思った、その時だ」
リュウガは目を細め、ルシアの赤髪を指にからませる。
くすぐったそうな。鈴の音のような声が、少女の愛らしい唇からあがった。
「突然、強い光が空の向こうから飛んでくるのが見えた。真っ直ぐにこっちに」
大きな光の球体。
それがゆっくりと風に揺れる木の葉のようなスピードで、こちらに降りてくる。
辺りはまばゆいばかりの光に包まれ、目を開けていられないほどだった。
「だが俺にはなぜか確証があった」
あの光の球が、ルシアであると。
懸命に潰れそうな視力をこらえ、手を伸ばしてその光の球を抱きとる。
不思議と熱くもなく、むしろ少しひんやりと冷たかったという。
「そしたら一瞬で、それが弾けたんだ。シャボン玉が、弾けて消えちまうように。パチンとな」
すると腕の中には彼女がいた。
スヤスヤと安らかな微笑みを浮かべた寝顔で。
「まるで天使みてぇだったな」
感嘆とも思える声でしめくくり、やはり愛おしげに頬を撫でる。
ルシアもまた、嬉しそうにその大きく無骨な手に擦り寄った。
「初めてこの子に出会った時も、飛び込んできたんだぜ」
透明な存在に運ばれ、抱かれていた赤ん坊。まるで何か目に見ぬモノ達に護られるような、そんな娘は今も花のように笑っている。
「ルイト、ルシア」
赤髪の男は彼ら親子の前にひざまづく。
「俺にお前たちを守らせてくれないか」
その姿は忠誠を誓う騎士のようで。凛々しいが、どこか不安に揺れる瞳はこちらをジッとみつめていた。
「リュウガ、僕は――」
彼が言葉を発しようと、口を開いた時。
「!」
チラリと視界の端に、黒いなにかが踊った。
(見間違い、か)
しかし目をこすってまた視線をあげるも、再び踊る影。それは部屋にある暖炉の周りをくるりと回ると、テーブルの下へ。
「どうした、ルイト」
「い、いや……」
(そんなわけない。あれは夢だった)
影。人。踊る影の少女。
瞬く間に背中を嫌な汗が伝う。
「あっ!」
キャンディがひとつ、足元に転がってきた。
それを拾い上げることも出来ず、ルイトの身体は固まったように動けない。
(夢……じゃないのか)
それともこっちが夢か。目の前が真っ暗になる。
もしこれが、つかの間の幸せな夢であったら。もう戻りたくないし、戻されれば発狂してしまうだろう。
ああ、なんて脆くなってしまっただろう。これが百戦錬磨の敏腕冒険者だと、笑わせる。
今やただの臆病者。娘を、大事な者たちを失いたくないと泣きわめく弱虫ではないか。
それが嫌だと、変わりたいと飛び出して行ったのに――。
「ゔ……っ」
吐き気が込み上げる。しかし床に伏すことすらできない。
まるで見えない鎖でがんじがらめにされたかのように、ピクリと四肢が動かせないのだ。それどころか、声も出ない。
眼球だけを必死で動かして状況を把握しようにも、目の前に黒い霧が立ち込め始める。
ついに悪夢の幕開けか。
(くそ)
せめてこのまま、舌を噛みちぎってやろうかと思った瞬間。
「……しっかりしな。娘が見てるヨ」
異国訛りの声が、彼の頭上からかけられた。
同時に雷光のごとく閃く、一線。それはルイトの足元で、複雑な幾何学模様を描く。
「!」
ピンッ――と糸を貼って弾いたような、かすかな音。
そして刹那。
『ギョ゙ァア゙ァァ゙ァッ!!!』
不協和音とノイズの混じった絶叫が響く。
禍々しい瘴気が、部屋全体に一気に広がった。
0
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

【完結】この契約に愛なんてないはずだった
なの
BL
劣勢オメガの翔太は、入院中の母を支えるため、昼夜問わず働き詰めの生活を送っていた。
そんなある日、母親の入院費用が払えず、困っていた翔太を救ったのは、冷静沈着で感情を見せない、大企業副社長・鷹城怜司……優勢アルファだった。
数日後、怜司は翔太に「1年間、仮の番になってほしい」と持ちかける。
身体の関係はなし、報酬あり。感情も、未来もいらない。ただの契約。
生活のために翔太はその条件を受け入れるが、理性的で無表情なはずの怜司が、ふとした瞬間に見せる優しさに、次第に心が揺らいでいく。
これはただの契約のはずだった。
愛なんて、最初からあるわけがなかった。
けれど……二人の距離が近づくたびに、仮であるはずの関係は、静かに熱を帯びていく。
ツンデレなオメガと、理性を装うアルファ。
これは、仮のはずだった番契約から始まる、運命以上の恋の物語。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
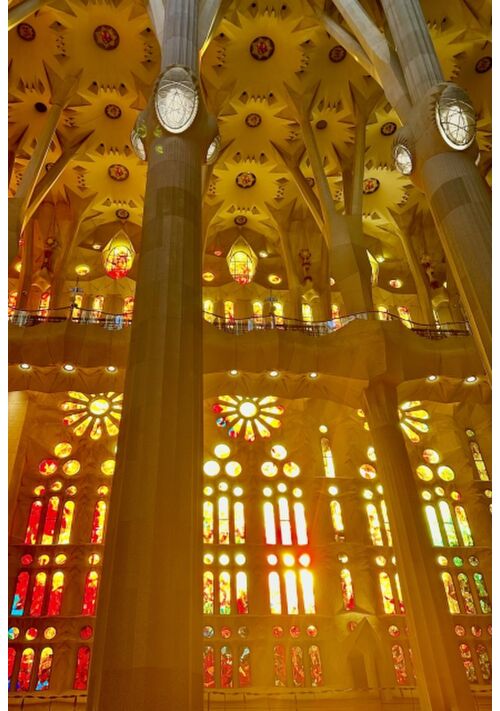
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















