31 / 33
影と幻想の悪夢
しおりを挟む
部屋はセピア色に染まった。
「動揺するな。これはお前を揺さぶるための演出にすぎない」
剣を構えるリュウガの声が、ルイトを救う。
「しっかりするヨ! ワタシたちがなぎ払っテやる」
同じく辺りをジッとにらみつけるロロの視線は、縦横無尽に張りめぐされた目に見えぬ糸を追っていた。
そうだ。彼女が何らかの魔法を使って、この突如現れた影たちを撃退しようとしている。それが、多少なりとも魔力を持っているルイトにもわかった。
「……っ」
微かな音、それはまるで鈴の音のような。
彼女の眉毛がはねあがった。
「【発動せよ】」
鋭い声と共に火花が散る。そして響いたのは、甲高く濁った叫び声。
部屋中に立ち込める異臭にルイトは顔をしかめた。まるで屍肉の焼けるような匂いといえばいいのだろうか。その酷さに、思わず顔をしかめる三人。
「ずっと付きまとっていたのは、こいつらだな」
リュウガが重々しくつぶやき剣をかまえる。
「悪夢の毒を撒き散らす影。やはりお前だったのか」
鋭い刃の先。クスクスという少女の軽やかな笑い声が聞こえた。
しかしそこにはなにも見えない。
「リュウガ、一体なにが……」
「こいつは宿主と決めた人間に悪夢をみせる。影のように付きまとい、対象が発狂するまで」
そしてその魂を根っこごと喰らい尽くすのだと、彼は冷たい視線を部屋のすみに走らせ言った。
「魂を?」
「魔族の一種とも言われているな。だがら契約を交わすことなく一方的に奪うことしか出来ない下等種だ」
いわくその名の通り、毒をまくかのように瘴気を立ち込めさせる。錯乱したターゲットの意識を今度は覚めることのない悪夢に引きずり込んで、その魂を食らいつくすのだ。
あとに残るのは空虚になった肉体だけ。そのまま衰弱し、死ぬのを待つだけという。
「そろそろ姿をあらわせ。忌々しい悪魔め」
その瞬間、キンッ――という金属質な音がした。
それは張り詰めた空気を震わせ、凍てつくような寒気が彼らを襲う。
『我らに 極上の 大罪を』
楽しげなソプラノ声が響く。異国の発音はなぜかひどく耳障りで、陰惨な色を想像させた。
「!」
部屋の真ん中に、それはいた。
「マルガレーテ……」
ルイトは半ば呆然とつぶやく。
影の少女、そのレースやフリルに彩られているであろうエプロンドレスの柄すら判別できない。
髪をふわりとなびかせ、彼女は蝶が舞うように一礼する。
あたかも今から、楽しくも美しい歌劇舞台が始まるかのように。
『うふふ、覚えていてくれたのね。光栄だわ、お姫様』
「なんで……あれは、夢のはず、なのに」
華麗に踊る白黒の影絵。そしてすぐに訪れる絶望の悪夢。
嫌というほど味あわされた凄惨な光景に、食いしばった歯がガチガチと鳴る。足は砕けたように力が入らない。
今にも崩れ落ちてしまいそうだった。
『そう――夢』
少女の声は軽やかに。
『儚くも美しく恐ろしい、つかの間の世界。そこへ迎え入れられる準備はできて?』
くるくると街の踊り子より優雅に艶やかな仕草で回ってみせた。そして膝を少し折った一礼。
『ああ悲しきお姫様。我が王の子を胎に宿すか、それとも卑しき悪魔の子を身ごもるか』
そのセリフとはうらはらに、残酷な無邪気さに満ちた口調。後ろには少年とおぼしき密やかな笑い声が聞こえる。
気がつけば、セピア色だった室内に鮮やかな色がついている。
目に眩しい、赤。
深紅の血痕が辺り一面に。
「!」
ルイトは慌てて辺りを見渡した。
誰もいない。ロロもリュウガも、そして。
「ルシ、ア……?」
血の海にたった一人、佇んでいたのだ。暖かな暖炉のある小屋でなく、荒れ果てた廃屋の中で。
(また悪夢をみせられているのか)
頭ではわかっている、カラクリさえ解かれれば。しかし心の中にヒタヒタと侵食してくる恐怖と不安からは逃げられない。
「あ、ぁ、ぁ」
喉が渇く、灼熱の炎に焼かれたように。手を差し出し、なんとか目の前の壊れかけたテーブルにすがりついた。
そうでもしなければ、埃まみれの床に倒れ込んでしまいそうだったから。
『あらあら、ずいぶんと頑丈なお姫様ねぇ』
嘲笑しながら影は近づいてくる。
『でもこれで終わり。アナタはアタシ達の一部になるの』
「く、くるなっ」
力の入らない身体を叱咤し、必死に腐った木の床を這いずり回った。視界に映した窓の外は、炎が轟々と音を立てて舞っている。
あとは呻き声。焼けただれ、腐り果てた亡者達の断末魔の悲鳴。
耳を削ぎ、目を潰してしまいたくなるほどの凄惨な光景が広がっているのだろう。影の少女は大きく揺れた。
『さぁ行きましょう、【楽園】へ』
優しい声だ。幼いはずなのに、どこか聖母を思わせる慈愛に満ちた。
しかし、騙されてはいけない。これこそがこの悪魔の甘言であり罠。
『ふふふ、快楽と共に送ってあげる』
そう言うと影が分裂した。正しく言うと、後ろから同じ体格の影が飛び出してきたのだ。
それがみるみるうちに大きく膨らみ変形する。
「!!」
『儚い愛と共に』
目の前にあらわれたのは一人の男。屈強で背の高い、しかし全てが黒く塗りつぶされて顔すら見えない。
それでもルイトは理解した、この人物を。
「リュウガ」
燃えるようか赤い髪も、深い色の瞳もない。しかし彼は手を伸ばした。歯を食いしばりながら。
「君、なのか?」
『ルイト』
名を呼ばれ歓喜に胸を震わせた。
低く優しい声に今すぐ抱かれたいとすら思う。全ての希望を剥ぎ取られたルイトにとって彼の存在を、小指の先ほどでも感じられるのならすがりつきたい。
目からはとめどなく涙があふれ、嗚咽のような言葉が口からこぼれ落ちる。
「どうして……どうして……」
微動だにしない男が恨めしい。早くこの手をとって欲しいのに。
逞しい胸の中に閉じ込めて、もう逃がさないでと訴えた。
『ルイト、行こう』
「リュウガ……僕は、僕は……」
そう泣きじゃくる姿は、あの名をとどろかせた冒険者の面影はない。恐怖と不安に心が壊れる寸前の、儚い乙女のようである。
――悪魔達が、笑った。
『ねぇお姫様。王子様には愛の言葉と誓いのキスが必要なのよ?』
いつの間にか回り込んでいたマルガレーテは顔を覗き込んでくる。相も変わらず、その表情おろか顔立ちすら真っ黒である。吸い込まれそうな闇とは、まさにこういう事をいう。
「愛の、言葉」
『偽りでなく、正統なる我らが魔王に服従の言葉を』
彼女の言葉とともに男が手を差し伸べた。その手を取り、接吻をせよということらしい。
床に膝をつきながら、ルイトはにじり寄る。
(リュウガ……魔王……王は、だれ……?)
答えにたどり着かぬ問いが不確定な単語と共にぐるぐる廻る。
魔王と人間たちの古の戦い。
再び起こるとされる歴史の闇と、あの美しく優しい男が関係あるというのだろうか。
混乱し、掻き乱される思考の中で懸命に目をこらす。
しっかりしなければ、これは悪夢だと己の中の理性が叫んだ。
『ほらほら。早く』
ねっとりと囁く声はひどく耳障りで。
「リュウガ……」
『いいえ。アナタが赦しと愛を乞うのは、あんな野蛮きわまりない男なんかじゃあないの』
そして吹き込まれたのは、やはり異国の言語。人の名前なのか、それとも何かの地位なのか。
その単語を口の中に転がしてみれば、不思議と馴染んだ。
敬虔な信者が、神の名を口にするような満足感というのだろうか。
『ルイト』
影の男がまた名を呼ぶ。
柔らかいがどこか無機質な声である。差し伸べられた手にすがり、ひざまずいて服従をと暗に示す。
「違う……君は、リュウガじゃ、ない」
酷い頭痛と吐き気をおぼえる。のたうち回り叫び出したいような苦痛。しかし何故か影たちから距離をとることすら出来なかった。
見えぬ手によって強引に押さえ込まれるかのように。
そんな彼に業を煮やしたのだろう。男がゆっくり近づいてきた。
『ルイト』
「やだっ、くるな! お前は違うッ!!」
やはり彼はニセモノだ――そう思った瞬間、先程までの歓喜は一転して恐怖に変わる。
なぜなら見えたのだ、背後に蠢く無数の触手達に。
それでもなお機械仕掛けめいたぎこちない動きで、彼はこちらへ歩み寄ってくる。
『さぁ王に、接吻を』
マルガレーテの声だけが嬉々として囁く。
まさに悪夢。ルイトは強く拳を握った。
「っ!」
自らの腕に噛み付いたのだ。むき出しになった白い肌に、思い切りよく歯が食い込む。焼け付くような痛みよりも先に、口の中に広がる血の香り。
「ゔぅ」
朦朧として定まらない意識を、自傷することで覚醒させようとしたのだ。
ルイトは冒険者だ。
幻覚や酩酊、眠気を誘う毒を吐く魔獣を相手にしたこともある。高価な薬草などを無駄にせぬよう、こうやって荒療治も心得ているのだ。
「この゙っ、ルイト・カントールをなめるな」
口に入った血を吐き捨て、ようやく少し明瞭となった頭を振る。
「もう悪夢に惑わされたりしない」
ふらつく足に懸命に力を入れ立ち上がる。腐っているはずの床は軋み一つ立てず。それは目の前の光景が、ただの幻覚であることを物語っていた。
『話に聞いていたけど、しぶといのねぇ。でも』
彼女の声が剣呑な色を帯びる。
『武器も持たず、夢魔とどう戦うのかしら』
みるみるうちに少女と男の影がぐにゃりと歪んで溶けた。
そして次の瞬間。
「なっ!?」
そびえ立つのは巨大な魔物。
青白い馬の頭。身体は毛むくじゃらの猿のようだった。
ブルルルッ、と鳴き歯を剥き出して笑う。
これが夢魔。
別名、悪夢の毒を撒き散らす影の正体である。
『……肉体ごと噛み砕いてやる』
しゃがれ声の夢魔が言った。
「動揺するな。これはお前を揺さぶるための演出にすぎない」
剣を構えるリュウガの声が、ルイトを救う。
「しっかりするヨ! ワタシたちがなぎ払っテやる」
同じく辺りをジッとにらみつけるロロの視線は、縦横無尽に張りめぐされた目に見えぬ糸を追っていた。
そうだ。彼女が何らかの魔法を使って、この突如現れた影たちを撃退しようとしている。それが、多少なりとも魔力を持っているルイトにもわかった。
「……っ」
微かな音、それはまるで鈴の音のような。
彼女の眉毛がはねあがった。
「【発動せよ】」
鋭い声と共に火花が散る。そして響いたのは、甲高く濁った叫び声。
部屋中に立ち込める異臭にルイトは顔をしかめた。まるで屍肉の焼けるような匂いといえばいいのだろうか。その酷さに、思わず顔をしかめる三人。
「ずっと付きまとっていたのは、こいつらだな」
リュウガが重々しくつぶやき剣をかまえる。
「悪夢の毒を撒き散らす影。やはりお前だったのか」
鋭い刃の先。クスクスという少女の軽やかな笑い声が聞こえた。
しかしそこにはなにも見えない。
「リュウガ、一体なにが……」
「こいつは宿主と決めた人間に悪夢をみせる。影のように付きまとい、対象が発狂するまで」
そしてその魂を根っこごと喰らい尽くすのだと、彼は冷たい視線を部屋のすみに走らせ言った。
「魂を?」
「魔族の一種とも言われているな。だがら契約を交わすことなく一方的に奪うことしか出来ない下等種だ」
いわくその名の通り、毒をまくかのように瘴気を立ち込めさせる。錯乱したターゲットの意識を今度は覚めることのない悪夢に引きずり込んで、その魂を食らいつくすのだ。
あとに残るのは空虚になった肉体だけ。そのまま衰弱し、死ぬのを待つだけという。
「そろそろ姿をあらわせ。忌々しい悪魔め」
その瞬間、キンッ――という金属質な音がした。
それは張り詰めた空気を震わせ、凍てつくような寒気が彼らを襲う。
『我らに 極上の 大罪を』
楽しげなソプラノ声が響く。異国の発音はなぜかひどく耳障りで、陰惨な色を想像させた。
「!」
部屋の真ん中に、それはいた。
「マルガレーテ……」
ルイトは半ば呆然とつぶやく。
影の少女、そのレースやフリルに彩られているであろうエプロンドレスの柄すら判別できない。
髪をふわりとなびかせ、彼女は蝶が舞うように一礼する。
あたかも今から、楽しくも美しい歌劇舞台が始まるかのように。
『うふふ、覚えていてくれたのね。光栄だわ、お姫様』
「なんで……あれは、夢のはず、なのに」
華麗に踊る白黒の影絵。そしてすぐに訪れる絶望の悪夢。
嫌というほど味あわされた凄惨な光景に、食いしばった歯がガチガチと鳴る。足は砕けたように力が入らない。
今にも崩れ落ちてしまいそうだった。
『そう――夢』
少女の声は軽やかに。
『儚くも美しく恐ろしい、つかの間の世界。そこへ迎え入れられる準備はできて?』
くるくると街の踊り子より優雅に艶やかな仕草で回ってみせた。そして膝を少し折った一礼。
『ああ悲しきお姫様。我が王の子を胎に宿すか、それとも卑しき悪魔の子を身ごもるか』
そのセリフとはうらはらに、残酷な無邪気さに満ちた口調。後ろには少年とおぼしき密やかな笑い声が聞こえる。
気がつけば、セピア色だった室内に鮮やかな色がついている。
目に眩しい、赤。
深紅の血痕が辺り一面に。
「!」
ルイトは慌てて辺りを見渡した。
誰もいない。ロロもリュウガも、そして。
「ルシ、ア……?」
血の海にたった一人、佇んでいたのだ。暖かな暖炉のある小屋でなく、荒れ果てた廃屋の中で。
(また悪夢をみせられているのか)
頭ではわかっている、カラクリさえ解かれれば。しかし心の中にヒタヒタと侵食してくる恐怖と不安からは逃げられない。
「あ、ぁ、ぁ」
喉が渇く、灼熱の炎に焼かれたように。手を差し出し、なんとか目の前の壊れかけたテーブルにすがりついた。
そうでもしなければ、埃まみれの床に倒れ込んでしまいそうだったから。
『あらあら、ずいぶんと頑丈なお姫様ねぇ』
嘲笑しながら影は近づいてくる。
『でもこれで終わり。アナタはアタシ達の一部になるの』
「く、くるなっ」
力の入らない身体を叱咤し、必死に腐った木の床を這いずり回った。視界に映した窓の外は、炎が轟々と音を立てて舞っている。
あとは呻き声。焼けただれ、腐り果てた亡者達の断末魔の悲鳴。
耳を削ぎ、目を潰してしまいたくなるほどの凄惨な光景が広がっているのだろう。影の少女は大きく揺れた。
『さぁ行きましょう、【楽園】へ』
優しい声だ。幼いはずなのに、どこか聖母を思わせる慈愛に満ちた。
しかし、騙されてはいけない。これこそがこの悪魔の甘言であり罠。
『ふふふ、快楽と共に送ってあげる』
そう言うと影が分裂した。正しく言うと、後ろから同じ体格の影が飛び出してきたのだ。
それがみるみるうちに大きく膨らみ変形する。
「!!」
『儚い愛と共に』
目の前にあらわれたのは一人の男。屈強で背の高い、しかし全てが黒く塗りつぶされて顔すら見えない。
それでもルイトは理解した、この人物を。
「リュウガ」
燃えるようか赤い髪も、深い色の瞳もない。しかし彼は手を伸ばした。歯を食いしばりながら。
「君、なのか?」
『ルイト』
名を呼ばれ歓喜に胸を震わせた。
低く優しい声に今すぐ抱かれたいとすら思う。全ての希望を剥ぎ取られたルイトにとって彼の存在を、小指の先ほどでも感じられるのならすがりつきたい。
目からはとめどなく涙があふれ、嗚咽のような言葉が口からこぼれ落ちる。
「どうして……どうして……」
微動だにしない男が恨めしい。早くこの手をとって欲しいのに。
逞しい胸の中に閉じ込めて、もう逃がさないでと訴えた。
『ルイト、行こう』
「リュウガ……僕は、僕は……」
そう泣きじゃくる姿は、あの名をとどろかせた冒険者の面影はない。恐怖と不安に心が壊れる寸前の、儚い乙女のようである。
――悪魔達が、笑った。
『ねぇお姫様。王子様には愛の言葉と誓いのキスが必要なのよ?』
いつの間にか回り込んでいたマルガレーテは顔を覗き込んでくる。相も変わらず、その表情おろか顔立ちすら真っ黒である。吸い込まれそうな闇とは、まさにこういう事をいう。
「愛の、言葉」
『偽りでなく、正統なる我らが魔王に服従の言葉を』
彼女の言葉とともに男が手を差し伸べた。その手を取り、接吻をせよということらしい。
床に膝をつきながら、ルイトはにじり寄る。
(リュウガ……魔王……王は、だれ……?)
答えにたどり着かぬ問いが不確定な単語と共にぐるぐる廻る。
魔王と人間たちの古の戦い。
再び起こるとされる歴史の闇と、あの美しく優しい男が関係あるというのだろうか。
混乱し、掻き乱される思考の中で懸命に目をこらす。
しっかりしなければ、これは悪夢だと己の中の理性が叫んだ。
『ほらほら。早く』
ねっとりと囁く声はひどく耳障りで。
「リュウガ……」
『いいえ。アナタが赦しと愛を乞うのは、あんな野蛮きわまりない男なんかじゃあないの』
そして吹き込まれたのは、やはり異国の言語。人の名前なのか、それとも何かの地位なのか。
その単語を口の中に転がしてみれば、不思議と馴染んだ。
敬虔な信者が、神の名を口にするような満足感というのだろうか。
『ルイト』
影の男がまた名を呼ぶ。
柔らかいがどこか無機質な声である。差し伸べられた手にすがり、ひざまずいて服従をと暗に示す。
「違う……君は、リュウガじゃ、ない」
酷い頭痛と吐き気をおぼえる。のたうち回り叫び出したいような苦痛。しかし何故か影たちから距離をとることすら出来なかった。
見えぬ手によって強引に押さえ込まれるかのように。
そんな彼に業を煮やしたのだろう。男がゆっくり近づいてきた。
『ルイト』
「やだっ、くるな! お前は違うッ!!」
やはり彼はニセモノだ――そう思った瞬間、先程までの歓喜は一転して恐怖に変わる。
なぜなら見えたのだ、背後に蠢く無数の触手達に。
それでもなお機械仕掛けめいたぎこちない動きで、彼はこちらへ歩み寄ってくる。
『さぁ王に、接吻を』
マルガレーテの声だけが嬉々として囁く。
まさに悪夢。ルイトは強く拳を握った。
「っ!」
自らの腕に噛み付いたのだ。むき出しになった白い肌に、思い切りよく歯が食い込む。焼け付くような痛みよりも先に、口の中に広がる血の香り。
「ゔぅ」
朦朧として定まらない意識を、自傷することで覚醒させようとしたのだ。
ルイトは冒険者だ。
幻覚や酩酊、眠気を誘う毒を吐く魔獣を相手にしたこともある。高価な薬草などを無駄にせぬよう、こうやって荒療治も心得ているのだ。
「この゙っ、ルイト・カントールをなめるな」
口に入った血を吐き捨て、ようやく少し明瞭となった頭を振る。
「もう悪夢に惑わされたりしない」
ふらつく足に懸命に力を入れ立ち上がる。腐っているはずの床は軋み一つ立てず。それは目の前の光景が、ただの幻覚であることを物語っていた。
『話に聞いていたけど、しぶといのねぇ。でも』
彼女の声が剣呑な色を帯びる。
『武器も持たず、夢魔とどう戦うのかしら』
みるみるうちに少女と男の影がぐにゃりと歪んで溶けた。
そして次の瞬間。
「なっ!?」
そびえ立つのは巨大な魔物。
青白い馬の頭。身体は毛むくじゃらの猿のようだった。
ブルルルッ、と鳴き歯を剥き出して笑う。
これが夢魔。
別名、悪夢の毒を撒き散らす影の正体である。
『……肉体ごと噛み砕いてやる』
しゃがれ声の夢魔が言った。
0
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
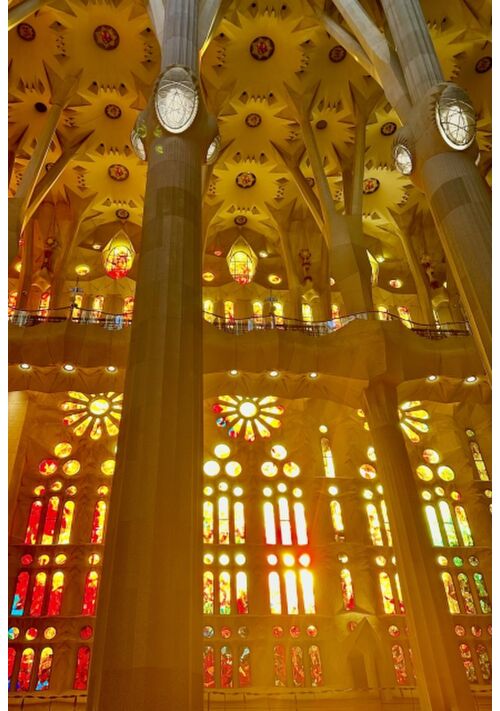
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















