1 / 4
第1話:出会いの香りは、極上に甘く、そして危険
しおりを挟む
蛍光灯がチカチカと不規則に瞬く。閉め切ったオフィスに満ちるのは、澱んだ空気と、鳴りやまない電話のコール音、そして微かな疲労の匂い。
私、佐藤美咲(さとうみさき)、26歳。広告代理店の営業事務。私の日常は、今まさに目の前で山となっている未処理の請求書のように、灰色の現実でできていた。
「佐藤さん、これ、急ぎで修正お願い。今日中ね」
「……はい、課長」
定時を二時間も過ぎた今になって「今日中」という魔法の言葉を繰り出す五十代の課長を、笑顔で見送る。心の中では舌打ちの嵐が吹き荒れているが、社会人として五年も経てば、無の表情を貼り付けることくらい朝飯前だ。
カタカタと無心でキーボードを叩き、気づけば時計の針は午後九時を回っていた。窓の外はとっぷりと暮れ、ビルの灯りが作り出す偽物の星が瞬いている。
(あー……お腹すいた。今日の晩ごはんは、コンビニの新作パスタにしようかな)
そんなささやかな楽しみを胸に、私は重たい身体を引きずって会社を後にした。満員電車に揺られ、誰かの香水の匂いや湿った息に耐えながら、ようやく最寄り駅にたどり着く。駅から徒歩十五分。築二十年の、オートロックもないけれど、日当たりだけは良い、私の城。
ぼんやりとアパートの階段を上っていた私は、ふと足を止めた。
長いこと『空室』の札が掛かっていたはずの、私の部屋の隣『102号室』。そのドアに、真新しい『九条』という陶器の表札が掛けられていたのだ。
(あ、お隣さん、入ったんだ。……どうしよう、挨拶、したほうがいいよね、一応)
社会人としての常識が、疲労困憊の身体に鞭を打つ。こういう時、気の利いた手土産の一つでもあればいいのに。生憎私のバッグには、スーパーで買った見切り品のカット野菜しか入っていない。
私は一度自室のドアを開け、部屋の奥から非常用に買い置きしていた、ちょっとだけ高級な洋菓子店のクッキーの箱を引っ張り出した。よし、これなら失礼にはならないだろう。
深呼吸を一つ。
ピンポーン。
静かな廊下に、少し間延びしたチャイムの音が響く。どんな人が出てくるんだろう。無口な人? それとも、騒がしい人? どうか、常識的な人でありますように。
そんなことを考えていると、カチャリ、と軽い音を立ててドアが開いた。
そこに立っていたのは―――現実感を喪失させるほど、美しい人だった。
「……はい」
穏やかなテノールの声。
艶のある、月の光を溶かし込んだような金の糸の髪。切りそろえられた前髪の下で、夕暮れの空をそのまま閉じ込めたような、紫と橙が混じった不思議な色の瞳が、静かに私を見つめている。シンプルな白いシャツ一枚なのに、それが世界で一番高価な衣装のように見えた。
少女漫画から抜け出してきた王子様、なんて陳yぷな表現では追いつかない。人という生き物の造形美を、遥かに超越している。
「あ……」
声が出ない。あまりの衝撃に固まっていると、彼が不思議そうに、そっと首を傾げた。その人間離れした美貌に、ふと人間らしい仕草が混じる。そのギャップに、私の心臓が「きゅっ」と小さな悲鳴を上げた。
「あ、あのっ! け、今日、101号室に越してきました、佐藤と申します! あ、違った、今日越してきたのは貴方で、私は前から住んでて……!」
「ふふ、大丈夫ですよ」
パニックで支離滅裂になる私を見て、彼が初めて小さく笑った。花が綻ぶ、という表現は、きっとこの人のためにあるのだろう。
私は顔が沸騰しそうなのを感じながら、必死でクッキーの箱を差し出した。
「こ、これ、つまらないものですが、どうぞ! これから、よろしくお願いします!」
「ご丁寧にどうも。……九条刹那(くじょうせつな)です。こちらこそ、よろしくお願いします」
刹那さん、と名乗った彼は、私の差し出した箱を、そっと受け取った。その時、彼の指先が僅かに私の手に触れる。ひんやりとしているのに、触れた部分から電気が走ったような衝撃があった。
彼の瞳が、私と、私の持つ箱をゆっくりと見比べる。そして、すぅ、と目を細めた。
「ですが」
―――その瞬間、空気が変わった。
それまでの柔らかな雰囲気が霧散し、ぞくりと背筋が粟立つような、濃密な何かが辺りに満ちる。
彼の夕暮れ色の瞳が、まるで獲物を見つけた飢えた獣のように、爛々と光を放った気がした。
「俺が本当に『食べたい』のは……」
―――え?
今、なんて……?
私の思考が、完全に停止する。彼の視線は、もうクッキーの箱にはない。まっすぐに、私の瞳を、私の喉を、私の心臓を射抜くように注がれている。その瞳は、甘く、飢えていて、そして、本能が警鐘を鳴らすほど、恐ろしかった。
「……そちらの箱よりも、貴女が作ってくれるという手料理だったりして。なんて」
刹那さんは、先程までの緊張感を微塵も感じさせない悪戯っぽい笑みを浮かべて、言葉を締めくくった。
「……っ!?」
私は自分の耳まで真っ赤になっているのを感じながら、ぶんぶんと勢いよく首を横に振る。
「い、いえ! そんな! とんでもない! あの、私、これで失礼します!」
何を言っているんだ、私は! 何をされているんだ、私は!
これ以上この空間にいたら、心臓が爆発するどころか、魂ごと吸い取られてしまいそうだ。私は脱兎のごとく踵を返し、自室のドアノブに手をかけた。
ドアが閉まる直前、彼の部屋から漂ってきた香りに、足がもつれそうになる。
高級な香水や、柔軟剤の匂いじゃない。もっと本能の奥深くに直接訴えかけてくるような、甘く熟した果実と、少しだけ獣めいたムスクが混じり合った、抗いがたい香り。
バタン、と自室のドアを乱暴に閉め、そのままズルズルと床にへたり込む。
(な、なんなの、あの人……!)
どくどくと暴れ続ける心臓を押さえる。ただ、とんでもないイケメンを前にして、緊張して、舞い上がっただけ。そうに決まってる。変なことを言われたのだって、きっと外国育ちの冗談か何かだ。
そう頭では理解しようとしているのに、身体の震えが止まらない。
あの瞳は、あの香りは、冗談なんかじゃなかった。
こうして、コンビニの新作パスタを食べるはずだった私の平凡な日常は、甘く、そして“喰われる”かもしれない危険な香りに満たされていくことになる。
まだ、私はその本当の意味を、知る由もなかった―――。
私、佐藤美咲(さとうみさき)、26歳。広告代理店の営業事務。私の日常は、今まさに目の前で山となっている未処理の請求書のように、灰色の現実でできていた。
「佐藤さん、これ、急ぎで修正お願い。今日中ね」
「……はい、課長」
定時を二時間も過ぎた今になって「今日中」という魔法の言葉を繰り出す五十代の課長を、笑顔で見送る。心の中では舌打ちの嵐が吹き荒れているが、社会人として五年も経てば、無の表情を貼り付けることくらい朝飯前だ。
カタカタと無心でキーボードを叩き、気づけば時計の針は午後九時を回っていた。窓の外はとっぷりと暮れ、ビルの灯りが作り出す偽物の星が瞬いている。
(あー……お腹すいた。今日の晩ごはんは、コンビニの新作パスタにしようかな)
そんなささやかな楽しみを胸に、私は重たい身体を引きずって会社を後にした。満員電車に揺られ、誰かの香水の匂いや湿った息に耐えながら、ようやく最寄り駅にたどり着く。駅から徒歩十五分。築二十年の、オートロックもないけれど、日当たりだけは良い、私の城。
ぼんやりとアパートの階段を上っていた私は、ふと足を止めた。
長いこと『空室』の札が掛かっていたはずの、私の部屋の隣『102号室』。そのドアに、真新しい『九条』という陶器の表札が掛けられていたのだ。
(あ、お隣さん、入ったんだ。……どうしよう、挨拶、したほうがいいよね、一応)
社会人としての常識が、疲労困憊の身体に鞭を打つ。こういう時、気の利いた手土産の一つでもあればいいのに。生憎私のバッグには、スーパーで買った見切り品のカット野菜しか入っていない。
私は一度自室のドアを開け、部屋の奥から非常用に買い置きしていた、ちょっとだけ高級な洋菓子店のクッキーの箱を引っ張り出した。よし、これなら失礼にはならないだろう。
深呼吸を一つ。
ピンポーン。
静かな廊下に、少し間延びしたチャイムの音が響く。どんな人が出てくるんだろう。無口な人? それとも、騒がしい人? どうか、常識的な人でありますように。
そんなことを考えていると、カチャリ、と軽い音を立ててドアが開いた。
そこに立っていたのは―――現実感を喪失させるほど、美しい人だった。
「……はい」
穏やかなテノールの声。
艶のある、月の光を溶かし込んだような金の糸の髪。切りそろえられた前髪の下で、夕暮れの空をそのまま閉じ込めたような、紫と橙が混じった不思議な色の瞳が、静かに私を見つめている。シンプルな白いシャツ一枚なのに、それが世界で一番高価な衣装のように見えた。
少女漫画から抜け出してきた王子様、なんて陳yぷな表現では追いつかない。人という生き物の造形美を、遥かに超越している。
「あ……」
声が出ない。あまりの衝撃に固まっていると、彼が不思議そうに、そっと首を傾げた。その人間離れした美貌に、ふと人間らしい仕草が混じる。そのギャップに、私の心臓が「きゅっ」と小さな悲鳴を上げた。
「あ、あのっ! け、今日、101号室に越してきました、佐藤と申します! あ、違った、今日越してきたのは貴方で、私は前から住んでて……!」
「ふふ、大丈夫ですよ」
パニックで支離滅裂になる私を見て、彼が初めて小さく笑った。花が綻ぶ、という表現は、きっとこの人のためにあるのだろう。
私は顔が沸騰しそうなのを感じながら、必死でクッキーの箱を差し出した。
「こ、これ、つまらないものですが、どうぞ! これから、よろしくお願いします!」
「ご丁寧にどうも。……九条刹那(くじょうせつな)です。こちらこそ、よろしくお願いします」
刹那さん、と名乗った彼は、私の差し出した箱を、そっと受け取った。その時、彼の指先が僅かに私の手に触れる。ひんやりとしているのに、触れた部分から電気が走ったような衝撃があった。
彼の瞳が、私と、私の持つ箱をゆっくりと見比べる。そして、すぅ、と目を細めた。
「ですが」
―――その瞬間、空気が変わった。
それまでの柔らかな雰囲気が霧散し、ぞくりと背筋が粟立つような、濃密な何かが辺りに満ちる。
彼の夕暮れ色の瞳が、まるで獲物を見つけた飢えた獣のように、爛々と光を放った気がした。
「俺が本当に『食べたい』のは……」
―――え?
今、なんて……?
私の思考が、完全に停止する。彼の視線は、もうクッキーの箱にはない。まっすぐに、私の瞳を、私の喉を、私の心臓を射抜くように注がれている。その瞳は、甘く、飢えていて、そして、本能が警鐘を鳴らすほど、恐ろしかった。
「……そちらの箱よりも、貴女が作ってくれるという手料理だったりして。なんて」
刹那さんは、先程までの緊張感を微塵も感じさせない悪戯っぽい笑みを浮かべて、言葉を締めくくった。
「……っ!?」
私は自分の耳まで真っ赤になっているのを感じながら、ぶんぶんと勢いよく首を横に振る。
「い、いえ! そんな! とんでもない! あの、私、これで失礼します!」
何を言っているんだ、私は! 何をされているんだ、私は!
これ以上この空間にいたら、心臓が爆発するどころか、魂ごと吸い取られてしまいそうだ。私は脱兎のごとく踵を返し、自室のドアノブに手をかけた。
ドアが閉まる直前、彼の部屋から漂ってきた香りに、足がもつれそうになる。
高級な香水や、柔軟剤の匂いじゃない。もっと本能の奥深くに直接訴えかけてくるような、甘く熟した果実と、少しだけ獣めいたムスクが混じり合った、抗いがたい香り。
バタン、と自室のドアを乱暴に閉め、そのままズルズルと床にへたり込む。
(な、なんなの、あの人……!)
どくどくと暴れ続ける心臓を押さえる。ただ、とんでもないイケメンを前にして、緊張して、舞い上がっただけ。そうに決まってる。変なことを言われたのだって、きっと外国育ちの冗談か何かだ。
そう頭では理解しようとしているのに、身体の震えが止まらない。
あの瞳は、あの香りは、冗談なんかじゃなかった。
こうして、コンビニの新作パスタを食べるはずだった私の平凡な日常は、甘く、そして“喰われる”かもしれない危険な香りに満たされていくことになる。
まだ、私はその本当の意味を、知る由もなかった―――。
0
あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~
Mio
ファンタジー
妻から手紙が来た。
妻が死んで18年目の今日。
息子の誕生日。
「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」
息子は…17年前に死んだ。
手紙はもう一通あった。
俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。
------------------------------


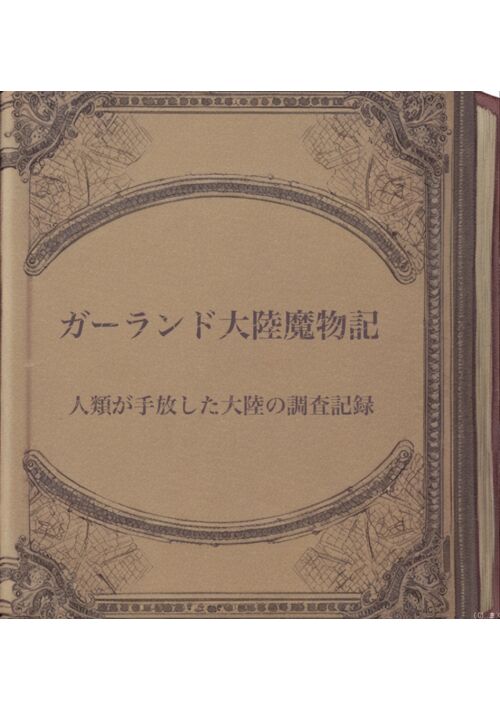
ガーランド大陸魔物記 人類が手放した大陸の調査記録
#Daki-Makura
ファンタジー
※タイトルを変更しました。
人類が植物に敗北した大陸〝ガーランド大陸〟
200年が経ち、再び大陸に入植するためにガーランド大陸の生態系。特に魔物の調査が行われることになった。
これは調査隊として派遣されたモウナイ王国ファートン子爵家三男 アンネスト•ファートンが記した魔物に関する記録である。
※昔に他サイトで掲載した物語に登場するものもあります。設定なども使用。
※設定はゆるゆるです。ゆるくお読みください。
※誤字脱字失礼します。
※一部AIを使用。(AI校正、誤字検索、添削等)
※その都度、修正させてもらっています。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。


冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

【完結】勇者の息子
つくも茄子
ファンタジー
勇者一行によって滅ぼされた魔王。
勇者は王女であり聖女である女性と結婚し、王様になった。
他の勇者パーティーのメンバー達もまた、勇者の治める国で要職につき、世界は平和な時代が訪れたのである。
そんな誰もが知る勇者の物語。
御伽噺にはじかれた一人の女性がいたことを知る者は、ほとんどいない。
月日は流れ、最年少で最高ランク(S級)の冒険者が誕生した。
彼の名前はグレイ。
グレイは幼い頃から実父の話を母親から子守唄代わりに聞かされてきた。
「秘密よ、秘密――――」
母が何度も語る秘密の話。
何故、父の話が秘密なのか。
それは長じるにつれ、グレイは理解していく。
自分の父親が誰なのかを。
秘密にする必要が何なのかを。
グレイは父親に似ていた。
それが全ての答えだった。
魔王は滅びても残党の魔獣達はいる。
主を失ったからか、それとも魔王という楔を失ったからか。
魔獣達は勢力を伸ばし始めた。
繁殖力もあり、倒しても倒しても次々に現れる。
各国は魔獣退治に頭を悩ませた。
魔王ほど強力でなくとも数が多すぎた。そのうえ、魔獣は賢い。群れを形成、奇襲をかけようとするほどになった。
皮肉にも魔王という存在がいたゆえに、魔獣は大人しくしていたともいえた。
世界は再び窮地に立たされていた。
勇者一行は魔王討伐以降、全盛期の力は失われていた。
しかも勇者は数年前から病床に臥している。
今や、魔獣退治の英雄は冒険者だった。
そんな時だ。
勇者の国が極秘でとある人物を探しているという。
噂では「勇者の子供(隠し子)」だという。
勇者の子供の存在は国家機密。だから極秘捜査というのは当然だった。
もともと勇者は平民出身。
魔王を退治する以前に恋人がいても不思議ではない。
何故、今頃になってそんな捜査が行われているのか。
それには理由があった。
魔獣は勇者の国を集中的に襲っているからだ。
勇者の子供に魔獣退治をさせようという魂胆だろう。
極秘捜査も不自然ではなかった。
もっともその極秘捜査はうまくいっていない。
本物が名乗り出ることはない。

ちゃんと忠告をしましたよ?
柚木ゆず
ファンタジー
ある日の、放課後のことでした。王立リザエンドワール学院に籍を置く私フィーナは、生徒会長を務められているジュリアルス侯爵令嬢アゼット様に呼び出されました。
「生徒会の仲間である貴方様に、婚約祝いをお渡したくてこうしておりますの」
アゼット様はそのように仰られていますが、そちらは嘘ですよね? 私は最愛の方に護っていただいているので、貴方様に悪意があると気付けるのですよ。
アゼット様。まだ間に合います。
今なら、引き返せますよ?
※現在体調の影響により、感想欄を一時的に閉じさせていただいております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















