52 / 68
第四章 セリアンスロップ共和国
13 ニャオ王子の冒険
しおりを挟む
言ってから、本人の前であることも思い出す。悔やむも後の祭り。マイアはキリルを見てにっこり笑った。キリルの緊張が解ける。
「そうね。最初は半信半疑だったけれど、抱き締められた時に、父だと確信した。なんだろう。匂いかしら」
「匂う?」
と、何故か自分の匂いを嗅ぐグリリ。
「いえ。それとわかるような匂いではない」
「フェロモンみたいなものか」
「ふぇろもん?」
「独り言。気にしないで」
この世界では分子の概念がない。
そこへ、召使いが現れた。
「お待たせしました。ご案内いたします」
部屋を出ると、ソゾンとネルルクに加えて、メリベルがいた。貴族令嬢ばりのドレス姿で、髪も短いなりに整えられている。首元まで布で覆うタイプの服ではあるが、上半身にぴったりした形なので、豊満な胸が一際目立った。服に合わせて態度までしおらしい。
こうして見ると、改めて彼女が美形であるとわかる。
食堂で席に着く。ソゾンの後方に、大きな肖像画が掲げられていた。明るい金髪の巻き毛に囲まれた美中年の胸像である。生き生きとした表情で、こちらを見つめている。瞳がきらりと光ったような気さえした。
「長老ですよ」
俺の視線に気づいたソゾンが教えてくれた。人は見た目じゃないが、これならマイアが嫁いでも良さそうだ、と思う。
「六十年前の姿じゃないか。わざわざ描き直したのに、モデルが古すぎる。この絵、新しいだろう?」
キリルが不機嫌をむき出しにして、指摘した。ソゾンは微笑で受け流した。
用意された飲み物を見て、初めてメリベルが蝙蝠人と知った。運ばれてくる料理も、俺たちとは異なっている。ネルルクも、自宅で俺たちと食事する時と違って、今日は蝙蝠人のメニューを食べていた。
食事中は、ほぼマイアの話題に終始した。レクルキスの魔法学院で教授として働いていると知ると、共和国側から感嘆と褒め言葉があめあられと降ってきた。とりわけキリルが喜んでいた。
「さすが我が娘だ。ここでもすぐ活躍できるぞ」
マイアを肴に、俺たちは食事を続けた。見た目も味も、ちゃんと人間用に美味しく出来ていた。
デザートになって、クレアが国交回復への協力をねじ込んだ。ソゾンは一応頷いていたものの、聞いていたかどうか心もとない。
竜人嫁取りの話は、微塵も俎上に載らなかった。そして、長老については紹介どころか、先ほどの肖像画以外、話題が持ち出されることもなく、今は、どんな見た目なのかを知ることもできなかった。
ネルルクの屋敷へ戻って着替えを終えると、クレアとマイアが俺たちの部屋を訪ねてきた。キリルは付いて来ていない。今度こそ、本当に仲間うちである。
「久しぶりだなあ」
エサムが言ったのも、同じ気持ちだろう。彼女たちにテーブルを囲む椅子に座ってもらい、会議室の出来上がり。テーブルも初めて本来の役に立った。
「何か新たな情報が?」
と聞いてみる。この貴重な時間も、いつまで続くか分からない。彼女たちは揃って頷いた。
「ネルルク議員が、昼食の前にソゾン代理とお話ししてくださったようで」
クレアが始める。
「国交については、長老派として反対する理由がない、とのことで、議決を採る際には賛成してもらえそうでs」
「クレアも頑張った甲斐があったな」
「いえ。ネルルク様のお陰」
エサムの労いに、却って落ち込むクレア。
「公使はきちんと仕事しているよ。続けて」
俺は方向を変えるべく、先を促した。
「はい。長老様は近頃気分のムラが激しく、今日も自室に篭っていたとか。マイアの噂は聞いていて、会いたがっていたと。ソゾン代理によると、寿命が尽きるまで引退する気はないそうでs」
「クセニヤ議員も候補ということは、今日代理に伝えたそうよ」
マイアが付け加えた。
「ソゾン代理は、次の長老になる気ありそう?」
グリリが訊く。
「本人は何とも。周囲はそのつもりで動いている、とネルルク議員が言っていたわ」
「ならば、マイアは今日得た情報も併せて、今後の進路を判断するんだな」
とエサムがまとめた。昼食会は、マイアとソゾンのお見合いみたいなものだろう。長老が三十年後も生き延びて無茶を言わなければ、の話であるが。
他にはないとのことだったので、解散した。二人が消えてから、グリリが手を上げる。
「あの~。ちょっといいかな」
「ん、何だ?」
とエサム。
「クセニヤ=ドラゴ議員が怒っていた宝物盗難事件、あれ、ニテオ王の冒険じゃないかな、と思って」
「ああ、それを言うなら思い出したぞ。俺が聞いたのは、ニャオ王子の冒険だった」
「あ、私も」
と俺も声を出した。それなら、読んだ覚えがある。
レクルキスの昔話だったか伝説だったかを扱った本で、王子がドラゴンを誤魔化して宝を手に入れ、持ち帰って王になりました、という話。ニャオ王子が長じてニテオ王になったのか。
「確かに竜が出てくる」
「何でさっき言わなかったんだ」
エサムは責める風ではない。俺にも答えはわかる気がする。
「王族が盗賊の謗りを受けるのは、内政的にも外交的にもまずいかな、と思って。公使に伝えたら、公式な記録に載る可能性がある」
「クレア真面目だしなあ」
頷くエサム。
「そうすると、奪われたお宝は王宮に保管されている訳か。どのみち国交が回復して交流が進めば、竜人側に知れるだろう。どうする?」
俺は思いついて指摘した。
「非公式なルートでやりとりできるよう、調整してもらうのがいいと思う。考えるのは、わたくしたちの役目ではない。ただ、帰国したら王宮側に事情を説明する必要は、ある」
「俺の記憶だと、宝は山分けにしたって話だった。全部戻すのは無理だろうな。それに王宮に渡った分も、そのまま残っているとは限らない」
「皆、亡くなっているからなあ」
ニテオ王は、現在のクラール王の祖父に当たる。
「確か仲間にエルフがいた。エサム、名前覚えているか」
グリリに問われたエサムは首を捻った。
「ああ、エルフはいた。でも、俺の覚えている話では、名前まで出てこなかった」
「それも、帰国後に調べてもらえばいい」
グリリが言った。
「明日は、市内観光をしましょうか」
夕食時に、ネルルクが切り出した。メリベルは、長老邸の帰路から従者に戻り、主の後ろに控えている。昼間眠らないところから、普通の蝙蝠人ではないことは確かだが、ネルルクに吸血されていないとすると、長老派の祖一族ということになる。
ソゾンの態度からしても、彼女が長老派と関わりがあるのは間違いない。ネルルクにとっては、身近に間諜というか、刺客を置いているようなものである。どういう因縁なのか、非常に気になる。
「ありがとうございます」
クレアがすかさず礼を言う。一日も早くバルヴィンの店に行きたいのだが、場所が分からない。直接聞く訳にもいかないから、まずは市街地の概要を把握しておく必要がある。
「議会など、主だった場所をご案内するつもりです。何かご希望がありましたら、仰ってください」
「お土産を買いたいです。パラメントゥムを訪れた記念になるような手頃な品物はありますか。あと、流行りの食堂でお勧め料理も食べてみたいです。それに、日持ちするお菓子があれば、買って帰りたいですね。あ、本屋とか、文房具屋があれば、そこでも買い物したいです。それから、国外持ち出し禁止の物があったら、教えてください」
考え始めたクレアを横に、グリリが勢い込んで言った。片方しかない目がきらきらしている。
どう見ても、公務ではなく私欲で語っている。
クセニヤ議員が相手だったら、切り捨て御免になりかねない。彼は公的には公使の護衛に過ぎない。しかも、一応人間ということになっている。
ネルルクの別邸からこの方、ずっとひと所に閉じ込められて、行動が制限されているという鬱屈が噴き出たようだった。
メリベルがグリリを険しい顔で見る。ネルルクの方は、微笑を崩さなかった。苦笑が混じっているようにも見える。
「持ち出しを禁じられている物は、市中の販売品にはないと思います。ただ、野生の動植物を生きたまま持ち出したい場合は、事前にご相談ください。それに、ご希望を全て叶えるためには、一日では足りませんね。考えておきます」
「ありがとうございます」
グリリは、見たことがないほどの満面の笑みで礼を言った。何らかの作戦だろうか。
「他の皆さんは如何ですか」
「私は、この街全体を上から眺めてみたいです」
マイアが言った。ネルルクが声を出して笑った。
「ふふっ。竜人らしい望みです。あいにく、ドラゴニア皇国の崩壊後、皇帝の居城が破壊されてしまって、今は一望できる場所がありません。市街地上空は竜の飛行禁止地域に指定されていますし‥‥でも、貴女の望みなら、そのうちキリルが叶えてくれるでしょう」
そのキリルは、ソゾン邸から戻った後、自宅へ帰っていた。彼にも仕事があるらしい。
「私は、ネルルク様が案内してくださる場所に興味があります。グリリが先ほど挙げた店なども、時間が許せば行ってみたく思います」
クレアが遠慮がちに言った。その後ネルルクは、エサムと俺にも希望を尋ねてくれた。よくできた人である。
エサムは軍隊の訓練を見たい、と大胆な発言をした。俺は何の考えもなく、咄嗟に学校が見たい、と答えた。
ここで初めて、ネルルクが残念そうな顔をした。
「軍の訓練については、機密に触れる部分もあるので、お約束しかねます。後でキリルに頼んでみます。共和国に、学校に当たるものは、ありません。今後の課題です。マイアさんのような経験者に、ご協力いただけるとありがたいですね」
「考えておきます」
マイアはネルルクを見て、にこりとした。メリベルの鋭い視線が彼女に移った。
背後から飛ばされる援護射撃に気付いているのかいないのか、ネルルクの方は穏やかな表情のままである。
その晩は、夕食後すぐに解放された。エサムは酒と肴がなくて不服そうだったが、俺たちの部屋にも一応酒瓶は常備してあった。
封を切って匂いを嗅ぐと、ブランデーのようである。早速飲み始めるエサム。勧められたが、俺は遠慮した。グリリはもとより飲まない。
「明日楽しみ。先に休む。おやすみなさい」
「おう、おやすみ」
「おやすみ」
グリリは猫になって端のエクストラベッドへ潜り込んだ。ここへ来てから、ほぼ鎧を着ていない。たちまち響き渡るいびき。
いつもバリアをかけていたので、本来どのくらいの音量なのか、失念していた。
エサムは平気な顔で飲んでいる。毎晩同じバリアの中で聞いているから平気なのか。眠気か轟音か、俺の頭がぼんやりしてきた。
「私も休む」
「む。結界張らなくていいのか?」
エサムも鎧を着ていない。脱ぎ着を手伝う必要もなく、動くたびにガチャガチャうるさくもないから、このいびきさえ無視できれば、安心して寝られる筈だ。
「夜中に起きたら張るよ。おやすみ」
「ああ。おやすみ」
「そうね。最初は半信半疑だったけれど、抱き締められた時に、父だと確信した。なんだろう。匂いかしら」
「匂う?」
と、何故か自分の匂いを嗅ぐグリリ。
「いえ。それとわかるような匂いではない」
「フェロモンみたいなものか」
「ふぇろもん?」
「独り言。気にしないで」
この世界では分子の概念がない。
そこへ、召使いが現れた。
「お待たせしました。ご案内いたします」
部屋を出ると、ソゾンとネルルクに加えて、メリベルがいた。貴族令嬢ばりのドレス姿で、髪も短いなりに整えられている。首元まで布で覆うタイプの服ではあるが、上半身にぴったりした形なので、豊満な胸が一際目立った。服に合わせて態度までしおらしい。
こうして見ると、改めて彼女が美形であるとわかる。
食堂で席に着く。ソゾンの後方に、大きな肖像画が掲げられていた。明るい金髪の巻き毛に囲まれた美中年の胸像である。生き生きとした表情で、こちらを見つめている。瞳がきらりと光ったような気さえした。
「長老ですよ」
俺の視線に気づいたソゾンが教えてくれた。人は見た目じゃないが、これならマイアが嫁いでも良さそうだ、と思う。
「六十年前の姿じゃないか。わざわざ描き直したのに、モデルが古すぎる。この絵、新しいだろう?」
キリルが不機嫌をむき出しにして、指摘した。ソゾンは微笑で受け流した。
用意された飲み物を見て、初めてメリベルが蝙蝠人と知った。運ばれてくる料理も、俺たちとは異なっている。ネルルクも、自宅で俺たちと食事する時と違って、今日は蝙蝠人のメニューを食べていた。
食事中は、ほぼマイアの話題に終始した。レクルキスの魔法学院で教授として働いていると知ると、共和国側から感嘆と褒め言葉があめあられと降ってきた。とりわけキリルが喜んでいた。
「さすが我が娘だ。ここでもすぐ活躍できるぞ」
マイアを肴に、俺たちは食事を続けた。見た目も味も、ちゃんと人間用に美味しく出来ていた。
デザートになって、クレアが国交回復への協力をねじ込んだ。ソゾンは一応頷いていたものの、聞いていたかどうか心もとない。
竜人嫁取りの話は、微塵も俎上に載らなかった。そして、長老については紹介どころか、先ほどの肖像画以外、話題が持ち出されることもなく、今は、どんな見た目なのかを知ることもできなかった。
ネルルクの屋敷へ戻って着替えを終えると、クレアとマイアが俺たちの部屋を訪ねてきた。キリルは付いて来ていない。今度こそ、本当に仲間うちである。
「久しぶりだなあ」
エサムが言ったのも、同じ気持ちだろう。彼女たちにテーブルを囲む椅子に座ってもらい、会議室の出来上がり。テーブルも初めて本来の役に立った。
「何か新たな情報が?」
と聞いてみる。この貴重な時間も、いつまで続くか分からない。彼女たちは揃って頷いた。
「ネルルク議員が、昼食の前にソゾン代理とお話ししてくださったようで」
クレアが始める。
「国交については、長老派として反対する理由がない、とのことで、議決を採る際には賛成してもらえそうでs」
「クレアも頑張った甲斐があったな」
「いえ。ネルルク様のお陰」
エサムの労いに、却って落ち込むクレア。
「公使はきちんと仕事しているよ。続けて」
俺は方向を変えるべく、先を促した。
「はい。長老様は近頃気分のムラが激しく、今日も自室に篭っていたとか。マイアの噂は聞いていて、会いたがっていたと。ソゾン代理によると、寿命が尽きるまで引退する気はないそうでs」
「クセニヤ議員も候補ということは、今日代理に伝えたそうよ」
マイアが付け加えた。
「ソゾン代理は、次の長老になる気ありそう?」
グリリが訊く。
「本人は何とも。周囲はそのつもりで動いている、とネルルク議員が言っていたわ」
「ならば、マイアは今日得た情報も併せて、今後の進路を判断するんだな」
とエサムがまとめた。昼食会は、マイアとソゾンのお見合いみたいなものだろう。長老が三十年後も生き延びて無茶を言わなければ、の話であるが。
他にはないとのことだったので、解散した。二人が消えてから、グリリが手を上げる。
「あの~。ちょっといいかな」
「ん、何だ?」
とエサム。
「クセニヤ=ドラゴ議員が怒っていた宝物盗難事件、あれ、ニテオ王の冒険じゃないかな、と思って」
「ああ、それを言うなら思い出したぞ。俺が聞いたのは、ニャオ王子の冒険だった」
「あ、私も」
と俺も声を出した。それなら、読んだ覚えがある。
レクルキスの昔話だったか伝説だったかを扱った本で、王子がドラゴンを誤魔化して宝を手に入れ、持ち帰って王になりました、という話。ニャオ王子が長じてニテオ王になったのか。
「確かに竜が出てくる」
「何でさっき言わなかったんだ」
エサムは責める風ではない。俺にも答えはわかる気がする。
「王族が盗賊の謗りを受けるのは、内政的にも外交的にもまずいかな、と思って。公使に伝えたら、公式な記録に載る可能性がある」
「クレア真面目だしなあ」
頷くエサム。
「そうすると、奪われたお宝は王宮に保管されている訳か。どのみち国交が回復して交流が進めば、竜人側に知れるだろう。どうする?」
俺は思いついて指摘した。
「非公式なルートでやりとりできるよう、調整してもらうのがいいと思う。考えるのは、わたくしたちの役目ではない。ただ、帰国したら王宮側に事情を説明する必要は、ある」
「俺の記憶だと、宝は山分けにしたって話だった。全部戻すのは無理だろうな。それに王宮に渡った分も、そのまま残っているとは限らない」
「皆、亡くなっているからなあ」
ニテオ王は、現在のクラール王の祖父に当たる。
「確か仲間にエルフがいた。エサム、名前覚えているか」
グリリに問われたエサムは首を捻った。
「ああ、エルフはいた。でも、俺の覚えている話では、名前まで出てこなかった」
「それも、帰国後に調べてもらえばいい」
グリリが言った。
「明日は、市内観光をしましょうか」
夕食時に、ネルルクが切り出した。メリベルは、長老邸の帰路から従者に戻り、主の後ろに控えている。昼間眠らないところから、普通の蝙蝠人ではないことは確かだが、ネルルクに吸血されていないとすると、長老派の祖一族ということになる。
ソゾンの態度からしても、彼女が長老派と関わりがあるのは間違いない。ネルルクにとっては、身近に間諜というか、刺客を置いているようなものである。どういう因縁なのか、非常に気になる。
「ありがとうございます」
クレアがすかさず礼を言う。一日も早くバルヴィンの店に行きたいのだが、場所が分からない。直接聞く訳にもいかないから、まずは市街地の概要を把握しておく必要がある。
「議会など、主だった場所をご案内するつもりです。何かご希望がありましたら、仰ってください」
「お土産を買いたいです。パラメントゥムを訪れた記念になるような手頃な品物はありますか。あと、流行りの食堂でお勧め料理も食べてみたいです。それに、日持ちするお菓子があれば、買って帰りたいですね。あ、本屋とか、文房具屋があれば、そこでも買い物したいです。それから、国外持ち出し禁止の物があったら、教えてください」
考え始めたクレアを横に、グリリが勢い込んで言った。片方しかない目がきらきらしている。
どう見ても、公務ではなく私欲で語っている。
クセニヤ議員が相手だったら、切り捨て御免になりかねない。彼は公的には公使の護衛に過ぎない。しかも、一応人間ということになっている。
ネルルクの別邸からこの方、ずっとひと所に閉じ込められて、行動が制限されているという鬱屈が噴き出たようだった。
メリベルがグリリを険しい顔で見る。ネルルクの方は、微笑を崩さなかった。苦笑が混じっているようにも見える。
「持ち出しを禁じられている物は、市中の販売品にはないと思います。ただ、野生の動植物を生きたまま持ち出したい場合は、事前にご相談ください。それに、ご希望を全て叶えるためには、一日では足りませんね。考えておきます」
「ありがとうございます」
グリリは、見たことがないほどの満面の笑みで礼を言った。何らかの作戦だろうか。
「他の皆さんは如何ですか」
「私は、この街全体を上から眺めてみたいです」
マイアが言った。ネルルクが声を出して笑った。
「ふふっ。竜人らしい望みです。あいにく、ドラゴニア皇国の崩壊後、皇帝の居城が破壊されてしまって、今は一望できる場所がありません。市街地上空は竜の飛行禁止地域に指定されていますし‥‥でも、貴女の望みなら、そのうちキリルが叶えてくれるでしょう」
そのキリルは、ソゾン邸から戻った後、自宅へ帰っていた。彼にも仕事があるらしい。
「私は、ネルルク様が案内してくださる場所に興味があります。グリリが先ほど挙げた店なども、時間が許せば行ってみたく思います」
クレアが遠慮がちに言った。その後ネルルクは、エサムと俺にも希望を尋ねてくれた。よくできた人である。
エサムは軍隊の訓練を見たい、と大胆な発言をした。俺は何の考えもなく、咄嗟に学校が見たい、と答えた。
ここで初めて、ネルルクが残念そうな顔をした。
「軍の訓練については、機密に触れる部分もあるので、お約束しかねます。後でキリルに頼んでみます。共和国に、学校に当たるものは、ありません。今後の課題です。マイアさんのような経験者に、ご協力いただけるとありがたいですね」
「考えておきます」
マイアはネルルクを見て、にこりとした。メリベルの鋭い視線が彼女に移った。
背後から飛ばされる援護射撃に気付いているのかいないのか、ネルルクの方は穏やかな表情のままである。
その晩は、夕食後すぐに解放された。エサムは酒と肴がなくて不服そうだったが、俺たちの部屋にも一応酒瓶は常備してあった。
封を切って匂いを嗅ぐと、ブランデーのようである。早速飲み始めるエサム。勧められたが、俺は遠慮した。グリリはもとより飲まない。
「明日楽しみ。先に休む。おやすみなさい」
「おう、おやすみ」
「おやすみ」
グリリは猫になって端のエクストラベッドへ潜り込んだ。ここへ来てから、ほぼ鎧を着ていない。たちまち響き渡るいびき。
いつもバリアをかけていたので、本来どのくらいの音量なのか、失念していた。
エサムは平気な顔で飲んでいる。毎晩同じバリアの中で聞いているから平気なのか。眠気か轟音か、俺の頭がぼんやりしてきた。
「私も休む」
「む。結界張らなくていいのか?」
エサムも鎧を着ていない。脱ぎ着を手伝う必要もなく、動くたびにガチャガチャうるさくもないから、このいびきさえ無視できれば、安心して寝られる筈だ。
「夜中に起きたら張るよ。おやすみ」
「ああ。おやすみ」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
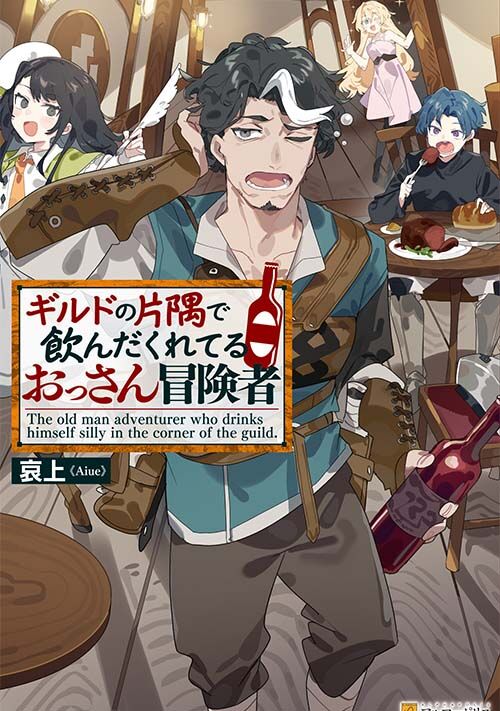
ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者
哀上
ファンタジー
チートを貰い転生した。
何も成し遂げることなく35年……
ついに前世の年齢を超えた。
※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。
※この小説は他サイトにも投稿しています。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します
namisan
ファンタジー
バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。
マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。
その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。
「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。
しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。
「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」
公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。
前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。
これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

SSSレア・スライムに転生した魚屋さん ~戦うつもりはないけど、どんどん強くなる~
草笛あたる(乱暴)
ファンタジー
転生したらスライムの突然変異だった。
レアらしくて、成長が異常に早いよ。
せっかくだから、自分の特技を活かして、日本の魚屋技術を異世界に広めたいな。
出刃包丁がない世界だったので、スライムの体内で作ったら、名刀に仕上がっちゃった。

50代無職、エルフに転生で異世界ざわつく
かわさきはっく
ファンタジー
就職氷河期を生き抜き、数々の職を転々とした末に無職となった50代の俺。
ある日、病で倒れ、気づけば異世界のエルフの賢者に転生していた!?
俺が転生したのは、高位エルフの秘術の失敗によって魂が取り込まれた賢者の肉体。
第二の人生をやり直そうと思ったのも束の間、俺の周囲は大騒ぎだ。
「導き手の復活か!?」「賢者を語る偽物か!?」
信仰派と保守派が入り乱れ、エルフの社会はざわつき始める。
賢者の力を示すため、次々と課される困難な試練。
様々な事件に巻き込まれながらも、俺は異世界で無双する!
異世界ざわつき転生譚、ここに開幕!
※話数は多いですが、一話ごとのボリュームは少なめです。
※「小説家になろう」「カクヨム」「Caita」にも掲載しています。

『冒険者をやめて田舎で隠居します 〜気づいたら最強の村になってました〜』
チャチャ
ファンタジー
> 世界には4つの大陸がある。東に魔神族、西に人族、北に獣人とドワーフ、南にエルフと妖精族——種族ごとの国が、それぞれの文化と価値観で生きていた。
その世界で唯一のSSランク冒険者・ジーク。英雄と呼ばれ続けることに疲れた彼は、突如冒険者を引退し、田舎へと姿を消した。
「もう戦いたくない、静かに暮らしたいんだ」
そう願ったはずなのに、彼の周りにはドラゴンやフェンリル、魔神族にエルフ、ドワーフ……あらゆる種族が集まり、最強の村が出来上がっていく!?
のんびりしたいだけの元英雄の周囲が、どんどんカオスになっていく異世界ほのぼの(?)ファンタジー。

【完結】帝国から追放された最強のチーム、リミッター外して無双する
エース皇命
ファンタジー
【HOTランキング2位獲得作品】
スペイゴール大陸最強の帝国、ユハ帝国。
帝国に仕え、最強の戦力を誇っていたチーム、『デイブレイク』は、突然議会から追放を言い渡される。
しかし帝国は気づいていなかった。彼らの力が帝国を拡大し、恐るべき戦力を誇示していたことに。
自由になった『デイブレイク』のメンバー、エルフのクリス、バランス型のアキラ、強大な魔力を宿すジャック、杖さばきの達人ランラン、絶世の美女シエナは、今まで抑えていた実力を完全開放し、ゼロからユハ帝国を超える国を建国していく。
※この世界では、杖と魔法を使って戦闘を行います。しかし、あの稲妻型の傷を持つメガネの少年のように戦うわけではありません。どうやって戦うのかは、本文を読んでのお楽しみです。杖で戦う戦士のことを、本文では杖士(ブレイカー)と描写しています。
※舞台の雰囲気は中世ヨーロッパ〜近世ヨーロッパに近いです。
〜『デイブレイク』のメンバー紹介〜
・クリス(男・エルフ・570歳)
チームのリーダー。もともとはエルフの貴族の家系だったため、上品で高潔。白く透明感のある肌に、整った顔立ちである。エルフ特有のとがった耳も特徴的。メンバーからも信頼されているが……
・アキラ(男・人間・29歳)
杖術、身体能力、頭脳、魔力など、あらゆる面のバランスが取れたチームの主力。独特なユーモアのセンスがあり、ムードメーカーでもある。唯一の弱点が……
・ジャック(男・人間・34歳)
怪物級の魔力を持つ杖士。その魔力が強大すぎるがゆえに、普段はその魔力を抑え込んでいるため、感情をあまり出さない。チームで唯一の黒人で、ドレッドヘアが特徴的。戦闘で右腕を失って以来義手を装着しているが……
・ランラン(女・人間・25歳)
優れた杖の腕前を持ち、チームを支える杖士。陽気でチャレンジャーな一面もあり、可愛さも武器である。性格の共通点から、アキラと親しく、親友である。しかし実は……
・シエナ(女・人間・28歳)
絶世の美女。とはいっても杖士としての実力も高く、アキラと同じくバランス型である。誰もが羨む美貌をもっているが、本人はあまり自信がないらしく、相手の反応を確認しながら静かに話す。あるメンバーのことが……

【第2章完結】最強な精霊王に転生しました。のんびりライフを送りたかったのに、問題にばかり巻き込まれるのはなんで?
山咲莉亜
ファンタジー
ある日、高校二年生だった桜井渚は魔法を扱うことができ、世界最強とされる精霊王に転生した。家族で海に遊びに行ったが遊んでいる最中に溺れた幼い弟を助け、代わりに自分が死んでしまったのだ。
だけど正直、俺は精霊王の立場に興味はない。精霊らしく、のんびり気楽に生きてみせるよ。
趣味の寝ることと読書だけをしてマイペースに生きるつもりだったナギサだが、優しく仲間思いな性格が災いして次々とトラブルに巻き込まれていく。果たしてナギサはそれらを乗り越えていくことができるのか。そして彼の行動原理とは……?
ロマンス、コメディ、シリアス───これは物語が進むにつれて露わになるナギサの闇やトラブルを共に乗り越えていく仲間達の物語。
※HOT男性ランキング最高6位でした。ありがとうございました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















