65 / 68
第五章 マドゥヤ帝国
10 絶景で尋問
しおりを挟む
綺麗に直立した岩の塔が、見渡す限り生えている。自然に出来たものだ。
てっぺんに木が茂り、針葉樹の濃い緑に彩られている。遠くへ行くほど色が霞み、青みがかっていく。
霧がかかって、下の方も見えない。場合が場合でなければ、見惚れる景観である。
俺達が乗ってきた箱は、そのうちの一つに安置されていた。うまい具合に木が生えておらず、岩肌が平らに剥き出している。
レンヤは、岩の周囲を囲むように長い胴体を巻きつけ、頭をこちらへ向けていた。そういう状況であるからして、箱の外側には大して余裕がない。
「航路を外れているじゃないか」
マドゥヤの兵士が怒気を含んだ声で、誰にともなく吐き捨てる。
直接レンヤを責めないのは、龍の協力なしに、ここから脱出するのが不可能だからだろう。俺でも分かる。
「姫の安全を守るために、確認せねばならぬことがある」
ようやく、ロン・レンヤが口を開いた。
俺達レクルキスの護衛組は、はっとして身構えた。
オピテルとイレナは、もとより王妃の側を固めている。俺も側にいる。差し当たり、他の人間が王妃に危害を加えることは、できない筈だ。
「どういうことです?」
自然、俺達と対峙する形になった、フィオナが戸惑う。
「まず、マドゥヤの役人は外へ出てもらおうか。箱の中に隠れていては、話もできぬ」
「何で」
マドゥヤの兵士は、三人いた。それぞれが文句を言いかけたのを、フィオナが押さえて共に外へ出た。
壁沿いに、顔を外に向けて立ち並ぶ。すれ違える程度の幅はあるし、その外側にレンヤがとぐろを巻いている。
すぐ落ちる心配はないものの、緊張を強いられる立ち位置である。
「次に、武装した者達」
「えっ、私達も?」
通詞役の言葉を聞いて、近衛隊長達は心外だという顔つきで王妃に助けを求めたが、結局近侍である俺以外の護衛が外へ出た。
侍女のチャルビと、ルキウス王太子は残る。箱の外側に、九人横並びである。
「何故トリスだけ?」
最後まで出るのを渋ったメッサラは、尚も抵抗を試みた。イレナがすかさず訳す。
「わしとリャンヤが判断した。それに彼は、近侍だろう?」
俺は心の裡で、世話係のウー・リャンヤに感謝した。
誰も、それ以上文句を言わなかった。崖の上に留まる時間が、長引くだけ、と理解したのだ。
「さて、始めよう」
ロン・レンヤが、ほぼ一列に並んだ人間達を一瞥した。どちらが偉いのか、危ぶまれる。
「山中から砲撃を受けた。魔法を使っている。獣人が関わっていたかもしれん」
「シャンツイチュンは? 撃ち落とされた? まさか敵に‥‥」
フィオナが言葉を呑み込む。そういえば、レンヤの他にも、龍がもう一体いた。入国時の経験から推測するに、荷物を運ぶ担当だった、と思う。
「シャンも砲撃を受けた。吊り箱から中身が落ちた。だが、シャンはそのまま飛び去った。敵はわしが焼いた。撃たれる心配はない」
レンヤは少し頭を引いて、口の横から小さな火の玉を吐き出した。十分距離をおいているのに、温度が上がったように感じられた。この龍は、ゴジラみたいに火を吐けるらしい。あるいは、竜人のように、と例えるべきか。
「え、全員焼き殺したということ?」
フィオナの言葉に身がすくむ。揺れる箱の外で、そんな惨事が起きていたとは。しかし、レンヤが応戦しなければ、俺達は砲撃で墜落していただろう。すなわち、死んでいたのは、俺達の方だった。
「問題は、攻撃を受けたシャンが、そのまま飛び去ったことだ」
レンヤが、また箱の外を一瞥する。敵を殲滅したことに、後ろめたさは微塵も感じていなさそうである。
如何にも彼は、戦闘用の龍だった。シャンツイチュンとかいう龍が、今ここにいないのは確かである。レンヤが同族を殺すとも思えない。
仮に龍が殺されるとしても、鳴き声で俺達に知れるのではなかろうか。
従って、レンヤは真実を述べている。彼が問題視する、事実の示す意味とは何か。
「龍が、突発時に従前の行動を継続するのは、予め指示があった時である」
答えを出したのは、コーシャ王妃だった。
「シャンツイチュンは、箱が砲撃されることを知っていた。更に、その地点で箱の中身が投下されることは予め決まっていた。箱は内部を仕切ることができる。底板の色を変えるなどして印をつければ、魔法を使える者達が、必要な部分にのみ、穴を開けることは容易い。レンヤは誰と代わったの?」
「シアツイチュン。シャンと双子の弟だ」
レンヤが答えた。
何となく、フィオナを含めたマドゥヤの護衛達の様子が、不穏に感じられる。
いつの間にか、王妃は王太子を抱き寄せていた。レンヤは味方でも、敵の全てを一度に排除する技は持っていなさそうだ。ここは、逃げ道のない場所である。不安に駆られたのは、俺も一緒だ。
「黄金の龍が持つ箱を、宝物と思って砲撃したのね。予定外の交代で、連絡が間に合わなかった。でも、レンヤなら、敵から逃げ切れたでしょう。敵を倒し、航路を外れる必要はない」
「姫。わしはな、人間どもが互いの決め事を破ろうが、私利を貪ろうが、いちいち目くじらを立てん。だが、姫に危険が及ぶなら、原因を徹底的に排除する。たとえ手違いだろうが、姫が二度とこの地を踏むことがなかろうが、関係ない」
ロン・レンヤは長々と話して疲れたのか、むふーっと鼻から盛大に息を噴き出した。ちょうど目の前にいたフィオナがよろけ、マドゥヤの護衛に支えられた。
何が起こったのか、最初は理解できなかった。
マドゥヤの護衛がグリリに斬りかかり、紙一重で避けられると、更に踏み込んでイレナを薙ぎ払った。
彼女は、王妃と龍の対話を通訳しており、護衛に半ば背を向けていた。不意打ちの形となり、悲鳴も上げずに下界へ落ちていった。
反対側では、リヌスの悲鳴が聞こえた。見ると、これも落下していくところだった。残ったメッサラが、マドゥヤの護衛二人に応戦する。頼もしいことに、二人相手にも負けていない。
「王妃を!」
イレナを落としたマドゥヤの護衛と、剣を交えるオピテルが叫ぶ。俺は、王妃と王太子を庇いつつ、箱の出入り口に立ち塞がった。チャルビが二人を奥へ導く。
「だめ。せめて、フィオナは殺さないで」
王妃の声が耳に届いた。そのフィオナは、グリリと掴み合いになっている。言われずとも、殺すつもりはないようだ。俺と同じ日本から来た人間だ。人殺しには、抵抗があるだろう。
俺は、まず自分の後ろにバリアを張った。オピテルが、マドゥヤの護衛を切り伏せる。
敵は、自ら落ちていった。すぐさまメッサラの援護に向かう。しかし、場所が狭くて、互いに二人並んで戦うのは難しい。
フィオナが急に、ぐったりとした。グリリが闇魔法を使ったに違いない。
俺は、メッサラに対峙する一人に、戦意喪失の魔法をかけた。途端にメッサラが打撃を与えたので、その護衛は落下した。
残る一人が焦って剣を振り回すのを、メッサラは難なく打ち据えた。
その間に、グリリがフィオナの服を利用し、彼女に目隠しをして縛り上げた。グリリの眼帯がずれ、閉じた片目が見えている。側で見るより大変だったようだ。
「この下、どうなっているかね?」
オピテルが身振りと共に、レンヤに尋ねる。レクルキス語である。龍は首を振った。何となく通じたのだろう。
「イレナとリヌスは、諦めるしかないのか。二人共、優秀な若者だった」
両隊長は、下界に向かって祈りを捧げた。俺も自己流で冥福を祈る。
見知った人が、二人も殺された割には、感情が動かない。死体が見えないせいもある。
マドゥヤの護衛の体から、血がピョロピョロ吹き出しているのを見ても、痛そうだなあ、と膜がかかったぼんやりした感想を抱いただけだった。
緊迫した状況で、頭が麻痺しているのかもしれない。
メッサラがその死体を引きずって箱へ入れた。俺の張ったバリアは、既に解けている。四隅の一角へ押し込めた。まさに重石である。
「その女を生かすのは、災いの元だ」
レンヤが言った。
彼は俺達がごちゃごちゃと戦っている間、元の場所でじっと見守っていた。火を吐いて援護してくれても良さそうなものだが、コーシャ王妃を巻き込みたくなかった、と考えれば納得がいく。
この狭さだ。確実に箱も焼ける。
「これは外交問題になる。フィオナは現皇帝の従姉妹よ。襲われたとはいえ、役人を殺すのとは訳が違う。それに、物資の横流しがあったとすれば、宮中にも関係者は残っている。全て洗い出さなければ、レンヤの言う徹底的に排除したことにはならないわ。そのためにも、フィオナを生かしておく必要がある」
「何と仰った?」
メッサラが小声で聞く。チャルビは王妃がコーシャ姫の頃から付き従っているし、ルキウス王太子は王族の教養としてお茶会で困らない程度に、マドゥヤ語を身につけている。
両隊長以外は、マドゥヤ語を理解できるのだ。通詞役が二人共殺されたせいで、二人共、話が見えていない。
「フィオナさんは皇帝の親戚で、殺したらまずいそうです」
そのフィオナを、オピテルと二人がかりで運び込もうとしていたグリリが言った。
既に眼帯は、元の位置に戻してあった。内容は正しいが、もの凄い端折り方である。通訳として如何なものか。
「そうか。言われてみれば、王妃様にも似てらっしゃる」
オピテルの動きが、やや慎重になった。いや、似てないと思うが。
彼は迷った挙句、人手不足の折もあり、死体の対角にフィオナを下ろした。備え付けの椅子に、縛めの上からベルトで固定する。
「レンヤ。私達をティエンジ港まで連れて行くのです」
「一旦戻れ。ティエンジには、今頃シャンが着いて騒ぎになっている。わしがいないとわかれば、リャンヤがここまで探しにくる」
王妃とレンヤの話は続いている。王太子はチャルビに促されて座席に腰掛けていたのだが、命の危険が去って安心したのか、眠りに落ちていた。寝顔は、あどけない子供だ。
「殺フィてよ」
後ろから、不明瞭な声が発せられた。フィオナが意識を取り戻したのだ。喋れる程度に猿轡の締めを甘くしたのか、単に噛ませ方が下手だったのか。縛ったのは、グリリである。
グリリがまた魔法をかけようとして、止めた。王妃がフィオナの方へ近寄って来たからだ。
レンヤも後を追って、顔を入り口へ寄せる。無論、大きすぎて入らない。髭だけが、別の生き物のように空中を漂う。
「殺さない。あなたは宮廷へ戻り、取り調べを受けて罪を償うの」
「偉フォウに。フォウ国の妃が、アドゥヤの皇フォくに指図しないで」
段々猿轡が緩んできた。メッサラもオピテルも、もどかしげに俺やグリリをちらちら見るが、雰囲気で内容は察しているようなので、俺は無視した。
グリリが猿轡を締め直そうとするのを、王妃が制する。彼は緩んだ猿轡をそのままに、引き下がった。
てっぺんに木が茂り、針葉樹の濃い緑に彩られている。遠くへ行くほど色が霞み、青みがかっていく。
霧がかかって、下の方も見えない。場合が場合でなければ、見惚れる景観である。
俺達が乗ってきた箱は、そのうちの一つに安置されていた。うまい具合に木が生えておらず、岩肌が平らに剥き出している。
レンヤは、岩の周囲を囲むように長い胴体を巻きつけ、頭をこちらへ向けていた。そういう状況であるからして、箱の外側には大して余裕がない。
「航路を外れているじゃないか」
マドゥヤの兵士が怒気を含んだ声で、誰にともなく吐き捨てる。
直接レンヤを責めないのは、龍の協力なしに、ここから脱出するのが不可能だからだろう。俺でも分かる。
「姫の安全を守るために、確認せねばならぬことがある」
ようやく、ロン・レンヤが口を開いた。
俺達レクルキスの護衛組は、はっとして身構えた。
オピテルとイレナは、もとより王妃の側を固めている。俺も側にいる。差し当たり、他の人間が王妃に危害を加えることは、できない筈だ。
「どういうことです?」
自然、俺達と対峙する形になった、フィオナが戸惑う。
「まず、マドゥヤの役人は外へ出てもらおうか。箱の中に隠れていては、話もできぬ」
「何で」
マドゥヤの兵士は、三人いた。それぞれが文句を言いかけたのを、フィオナが押さえて共に外へ出た。
壁沿いに、顔を外に向けて立ち並ぶ。すれ違える程度の幅はあるし、その外側にレンヤがとぐろを巻いている。
すぐ落ちる心配はないものの、緊張を強いられる立ち位置である。
「次に、武装した者達」
「えっ、私達も?」
通詞役の言葉を聞いて、近衛隊長達は心外だという顔つきで王妃に助けを求めたが、結局近侍である俺以外の護衛が外へ出た。
侍女のチャルビと、ルキウス王太子は残る。箱の外側に、九人横並びである。
「何故トリスだけ?」
最後まで出るのを渋ったメッサラは、尚も抵抗を試みた。イレナがすかさず訳す。
「わしとリャンヤが判断した。それに彼は、近侍だろう?」
俺は心の裡で、世話係のウー・リャンヤに感謝した。
誰も、それ以上文句を言わなかった。崖の上に留まる時間が、長引くだけ、と理解したのだ。
「さて、始めよう」
ロン・レンヤが、ほぼ一列に並んだ人間達を一瞥した。どちらが偉いのか、危ぶまれる。
「山中から砲撃を受けた。魔法を使っている。獣人が関わっていたかもしれん」
「シャンツイチュンは? 撃ち落とされた? まさか敵に‥‥」
フィオナが言葉を呑み込む。そういえば、レンヤの他にも、龍がもう一体いた。入国時の経験から推測するに、荷物を運ぶ担当だった、と思う。
「シャンも砲撃を受けた。吊り箱から中身が落ちた。だが、シャンはそのまま飛び去った。敵はわしが焼いた。撃たれる心配はない」
レンヤは少し頭を引いて、口の横から小さな火の玉を吐き出した。十分距離をおいているのに、温度が上がったように感じられた。この龍は、ゴジラみたいに火を吐けるらしい。あるいは、竜人のように、と例えるべきか。
「え、全員焼き殺したということ?」
フィオナの言葉に身がすくむ。揺れる箱の外で、そんな惨事が起きていたとは。しかし、レンヤが応戦しなければ、俺達は砲撃で墜落していただろう。すなわち、死んでいたのは、俺達の方だった。
「問題は、攻撃を受けたシャンが、そのまま飛び去ったことだ」
レンヤが、また箱の外を一瞥する。敵を殲滅したことに、後ろめたさは微塵も感じていなさそうである。
如何にも彼は、戦闘用の龍だった。シャンツイチュンとかいう龍が、今ここにいないのは確かである。レンヤが同族を殺すとも思えない。
仮に龍が殺されるとしても、鳴き声で俺達に知れるのではなかろうか。
従って、レンヤは真実を述べている。彼が問題視する、事実の示す意味とは何か。
「龍が、突発時に従前の行動を継続するのは、予め指示があった時である」
答えを出したのは、コーシャ王妃だった。
「シャンツイチュンは、箱が砲撃されることを知っていた。更に、その地点で箱の中身が投下されることは予め決まっていた。箱は内部を仕切ることができる。底板の色を変えるなどして印をつければ、魔法を使える者達が、必要な部分にのみ、穴を開けることは容易い。レンヤは誰と代わったの?」
「シアツイチュン。シャンと双子の弟だ」
レンヤが答えた。
何となく、フィオナを含めたマドゥヤの護衛達の様子が、不穏に感じられる。
いつの間にか、王妃は王太子を抱き寄せていた。レンヤは味方でも、敵の全てを一度に排除する技は持っていなさそうだ。ここは、逃げ道のない場所である。不安に駆られたのは、俺も一緒だ。
「黄金の龍が持つ箱を、宝物と思って砲撃したのね。予定外の交代で、連絡が間に合わなかった。でも、レンヤなら、敵から逃げ切れたでしょう。敵を倒し、航路を外れる必要はない」
「姫。わしはな、人間どもが互いの決め事を破ろうが、私利を貪ろうが、いちいち目くじらを立てん。だが、姫に危険が及ぶなら、原因を徹底的に排除する。たとえ手違いだろうが、姫が二度とこの地を踏むことがなかろうが、関係ない」
ロン・レンヤは長々と話して疲れたのか、むふーっと鼻から盛大に息を噴き出した。ちょうど目の前にいたフィオナがよろけ、マドゥヤの護衛に支えられた。
何が起こったのか、最初は理解できなかった。
マドゥヤの護衛がグリリに斬りかかり、紙一重で避けられると、更に踏み込んでイレナを薙ぎ払った。
彼女は、王妃と龍の対話を通訳しており、護衛に半ば背を向けていた。不意打ちの形となり、悲鳴も上げずに下界へ落ちていった。
反対側では、リヌスの悲鳴が聞こえた。見ると、これも落下していくところだった。残ったメッサラが、マドゥヤの護衛二人に応戦する。頼もしいことに、二人相手にも負けていない。
「王妃を!」
イレナを落としたマドゥヤの護衛と、剣を交えるオピテルが叫ぶ。俺は、王妃と王太子を庇いつつ、箱の出入り口に立ち塞がった。チャルビが二人を奥へ導く。
「だめ。せめて、フィオナは殺さないで」
王妃の声が耳に届いた。そのフィオナは、グリリと掴み合いになっている。言われずとも、殺すつもりはないようだ。俺と同じ日本から来た人間だ。人殺しには、抵抗があるだろう。
俺は、まず自分の後ろにバリアを張った。オピテルが、マドゥヤの護衛を切り伏せる。
敵は、自ら落ちていった。すぐさまメッサラの援護に向かう。しかし、場所が狭くて、互いに二人並んで戦うのは難しい。
フィオナが急に、ぐったりとした。グリリが闇魔法を使ったに違いない。
俺は、メッサラに対峙する一人に、戦意喪失の魔法をかけた。途端にメッサラが打撃を与えたので、その護衛は落下した。
残る一人が焦って剣を振り回すのを、メッサラは難なく打ち据えた。
その間に、グリリがフィオナの服を利用し、彼女に目隠しをして縛り上げた。グリリの眼帯がずれ、閉じた片目が見えている。側で見るより大変だったようだ。
「この下、どうなっているかね?」
オピテルが身振りと共に、レンヤに尋ねる。レクルキス語である。龍は首を振った。何となく通じたのだろう。
「イレナとリヌスは、諦めるしかないのか。二人共、優秀な若者だった」
両隊長は、下界に向かって祈りを捧げた。俺も自己流で冥福を祈る。
見知った人が、二人も殺された割には、感情が動かない。死体が見えないせいもある。
マドゥヤの護衛の体から、血がピョロピョロ吹き出しているのを見ても、痛そうだなあ、と膜がかかったぼんやりした感想を抱いただけだった。
緊迫した状況で、頭が麻痺しているのかもしれない。
メッサラがその死体を引きずって箱へ入れた。俺の張ったバリアは、既に解けている。四隅の一角へ押し込めた。まさに重石である。
「その女を生かすのは、災いの元だ」
レンヤが言った。
彼は俺達がごちゃごちゃと戦っている間、元の場所でじっと見守っていた。火を吐いて援護してくれても良さそうなものだが、コーシャ王妃を巻き込みたくなかった、と考えれば納得がいく。
この狭さだ。確実に箱も焼ける。
「これは外交問題になる。フィオナは現皇帝の従姉妹よ。襲われたとはいえ、役人を殺すのとは訳が違う。それに、物資の横流しがあったとすれば、宮中にも関係者は残っている。全て洗い出さなければ、レンヤの言う徹底的に排除したことにはならないわ。そのためにも、フィオナを生かしておく必要がある」
「何と仰った?」
メッサラが小声で聞く。チャルビは王妃がコーシャ姫の頃から付き従っているし、ルキウス王太子は王族の教養としてお茶会で困らない程度に、マドゥヤ語を身につけている。
両隊長以外は、マドゥヤ語を理解できるのだ。通詞役が二人共殺されたせいで、二人共、話が見えていない。
「フィオナさんは皇帝の親戚で、殺したらまずいそうです」
そのフィオナを、オピテルと二人がかりで運び込もうとしていたグリリが言った。
既に眼帯は、元の位置に戻してあった。内容は正しいが、もの凄い端折り方である。通訳として如何なものか。
「そうか。言われてみれば、王妃様にも似てらっしゃる」
オピテルの動きが、やや慎重になった。いや、似てないと思うが。
彼は迷った挙句、人手不足の折もあり、死体の対角にフィオナを下ろした。備え付けの椅子に、縛めの上からベルトで固定する。
「レンヤ。私達をティエンジ港まで連れて行くのです」
「一旦戻れ。ティエンジには、今頃シャンが着いて騒ぎになっている。わしがいないとわかれば、リャンヤがここまで探しにくる」
王妃とレンヤの話は続いている。王太子はチャルビに促されて座席に腰掛けていたのだが、命の危険が去って安心したのか、眠りに落ちていた。寝顔は、あどけない子供だ。
「殺フィてよ」
後ろから、不明瞭な声が発せられた。フィオナが意識を取り戻したのだ。喋れる程度に猿轡の締めを甘くしたのか、単に噛ませ方が下手だったのか。縛ったのは、グリリである。
グリリがまた魔法をかけようとして、止めた。王妃がフィオナの方へ近寄って来たからだ。
レンヤも後を追って、顔を入り口へ寄せる。無論、大きすぎて入らない。髭だけが、別の生き物のように空中を漂う。
「殺さない。あなたは宮廷へ戻り、取り調べを受けて罪を償うの」
「偉フォウに。フォウ国の妃が、アドゥヤの皇フォくに指図しないで」
段々猿轡が緩んできた。メッサラもオピテルも、もどかしげに俺やグリリをちらちら見るが、雰囲気で内容は察しているようなので、俺は無視した。
グリリが猿轡を締め直そうとするのを、王妃が制する。彼は緩んだ猿轡をそのままに、引き下がった。
0
あなたにおすすめの小説
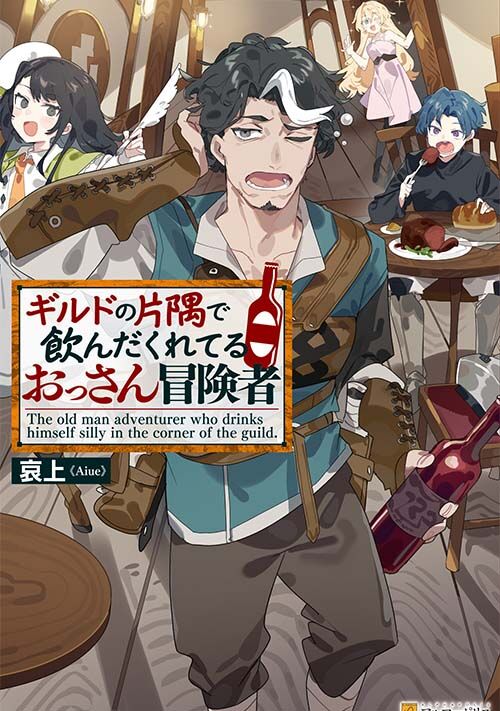
ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者
哀上
ファンタジー
チートを貰い転生した。
何も成し遂げることなく35年……
ついに前世の年齢を超えた。
※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。
※この小説は他サイトにも投稿しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します
namisan
ファンタジー
バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。
マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。
その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。
「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。
しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。
「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」
公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。
前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。
これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

『冒険者をやめて田舎で隠居します 〜気づいたら最強の村になってました〜』
チャチャ
ファンタジー
> 世界には4つの大陸がある。東に魔神族、西に人族、北に獣人とドワーフ、南にエルフと妖精族——種族ごとの国が、それぞれの文化と価値観で生きていた。
その世界で唯一のSSランク冒険者・ジーク。英雄と呼ばれ続けることに疲れた彼は、突如冒険者を引退し、田舎へと姿を消した。
「もう戦いたくない、静かに暮らしたいんだ」
そう願ったはずなのに、彼の周りにはドラゴンやフェンリル、魔神族にエルフ、ドワーフ……あらゆる種族が集まり、最強の村が出来上がっていく!?
のんびりしたいだけの元英雄の周囲が、どんどんカオスになっていく異世界ほのぼの(?)ファンタジー。

50代無職、エルフに転生で異世界ざわつく
かわさきはっく
ファンタジー
就職氷河期を生き抜き、数々の職を転々とした末に無職となった50代の俺。
ある日、病で倒れ、気づけば異世界のエルフの賢者に転生していた!?
俺が転生したのは、高位エルフの秘術の失敗によって魂が取り込まれた賢者の肉体。
第二の人生をやり直そうと思ったのも束の間、俺の周囲は大騒ぎだ。
「導き手の復活か!?」「賢者を語る偽物か!?」
信仰派と保守派が入り乱れ、エルフの社会はざわつき始める。
賢者の力を示すため、次々と課される困難な試練。
様々な事件に巻き込まれながらも、俺は異世界で無双する!
異世界ざわつき転生譚、ここに開幕!
※話数は多いですが、一話ごとのボリュームは少なめです。
※「小説家になろう」「カクヨム」「Caita」にも掲載しています。

【第2章完結】最強な精霊王に転生しました。のんびりライフを送りたかったのに、問題にばかり巻き込まれるのはなんで?
山咲莉亜
ファンタジー
ある日、高校二年生だった桜井渚は魔法を扱うことができ、世界最強とされる精霊王に転生した。家族で海に遊びに行ったが遊んでいる最中に溺れた幼い弟を助け、代わりに自分が死んでしまったのだ。
だけど正直、俺は精霊王の立場に興味はない。精霊らしく、のんびり気楽に生きてみせるよ。
趣味の寝ることと読書だけをしてマイペースに生きるつもりだったナギサだが、優しく仲間思いな性格が災いして次々とトラブルに巻き込まれていく。果たしてナギサはそれらを乗り越えていくことができるのか。そして彼の行動原理とは……?
ロマンス、コメディ、シリアス───これは物語が進むにつれて露わになるナギサの闇やトラブルを共に乗り越えていく仲間達の物語。
※HOT男性ランキング最高6位でした。ありがとうございました!

家族転生 ~父、勇者 母、大魔導師 兄、宰相 姉、公爵夫人 弟、S級暗殺者 妹、宮廷薬師 ……俺、門番~
北条新九郎
ファンタジー
三好家は一家揃って全滅し、そして一家揃って異世界転生を果たしていた。
父は勇者として、母は大魔導師として異世界で名声を博し、現地人の期待に応えて魔王討伐に旅立つ。またその子供たちも兄は宰相、姉は公爵夫人、弟はS級暗殺者、妹は宮廷薬師として異世界を謳歌していた。
ただ、三好家第三子の神太郎だけは異世界において冴えない立場だった。
彼の職業は………………ただの門番である。
そして、そんな彼の目的はスローライフを送りつつ、異世界ハーレムを作ることだった。
二月から週二回更新になります。お気に入り・感想、宜しくお願いします。

異世界転生おじさんは最強とハーレムを極める
自ら
ファンタジー
定年を半年後に控えた凡庸なサラリーマン、佐藤健一(50歳)は、不慮の交通事故で人生を終える。目覚めた先で出会ったのは、自分の魂をトラックの前に落としたというミスをした女神リナリア。
その「お詫び」として、健一は剣と魔法の異世界へと30代後半の肉体で転生することになる。チート能力の選択を迫られ、彼はあらゆる経験から無限に成長できる**【無限成長(アンリミテッド・グロース)】**を選び取る。
異世界で早速遭遇したゴブリンを一撃で倒し、チート能力を実感した健一は、くたびれた人生を捨て、最強のセカンドライフを謳歌することを決意する。
定年間際のおじさんが、女神の気まぐれチートで異世界最強への道を歩み始める、転生ファンタジーの開幕。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















