1 / 20
第一章 転入生と地味な僕
01 やってきた転入生
しおりを挟む
どうして気づかなかったのだろう。
なぜ忘れてしまっていたのだろう。
──思い出した?
歌うように、朗らかに彼は笑う。
やっと出逢えた観測者は、あのときと変わらない笑みで顔を傾けた。
あれだけ満開だった桜は葉桜へと変わり、夏を匂わせるもなりきれていない季節となった。過ごしやすいし、けっこう好きな季節だ。
毎年同じ季節をルーティンで過ごす中、今年はちょっとしたニュースが舞い込んできた。
軋む引き戸が引かれ、いつものように担任が入ってきた。心なしか、顔に緊張が宿っている。後ろから入ってきたのは、初めて見る顔の生徒。同じ制服を着ていて、赤みがかった髪とすらりとした上背に甘ったるい薄い笑みは、女子生徒に悲鳴を上げさせるのに充分すぎるほどだった。
呆然と見ていると、担任の先生と目が合った。すみません、見惚れていたのはあなたじゃないんですと申し訳なさそうな顔をすると、担任は苦笑いを浮かべてしまった。ごめんなさい。
男性は一点集中して視線を浴びても、少しも動じることなくこちらを見ている。俺を。そう、俺だ。他の誰でもない、至って目立たない地味な俺を。
「転入生の水瀬葵さんだ。海外からやってきて、英語が得意なんだそうだ。仲良くしてやってくれ。席は……」
「そこ、空いています」
声も良いときたか。水瀬は俺の後ろを指差した。確かに空いている。担任の指示を待たず、転入生は迷わず俺の席の斜め後ろに腰を下ろした。
「よろしくね」
「う、うん……よろしくね」
俺の席は一番前で、窓際からふたつ離れた席だ。そして目の前にはガラス張りの棚がある。本や英語の教材が隙間なく並んでいる。
声をかけられた女子生徒は上擦った声を交わす。
ガラス越しに、転入生と目が合った。黄色い声を無駄に浴びた担任を見ると、小テストを行うなど何か話している。喝采は一気にブーイングと化した。生徒の親指が下を向いている。
もう一度ガラスに目を向けると、偶然ではなかった。転入生は、口元で何かを作り、笑みを浮かべる。分からず首を傾げると、もっとゆっくり唇の形を変えた。
読唇術の才がなくとも読めた。たった四文字の言葉だ。よろしく。
気恥ずかしかったが、目を逸らしながら同じ言葉を作ると、後ろから含み笑いが聞こえた。
放課後、職員室に課題の提出をしてクラスに戻ると、転入生はすでにいなかった。
「ねえ、水瀬君知らない?」
「さあ? 見てないけど」
「いなくなっちゃったのよねえ。一緒に帰りたかったのに」
この分だと、逃げたのかもしれない。甘いマスクというか、女子受けしそうな顔だ。わたあめみたいなやつ。ほとんど話していないが、中身のギャップはあるのかないのか、どういう人だろう。
いつもの空き教室に向かうと、曲がり角で靴の底が悲鳴を上げた。音に反応して彼は俺に向くと、今朝の自己紹介のときのような笑顔で片手を上げる。
「やあ。ホームルームぶりだね」
「……帰ったんじゃないの?」
「ここは何部?」
質問には質問で返す。俺の問いに答える気はないようだ。
なんだか腑に落ちないので、俺も答えず返事の代わりに引き戸を引いた。
遮光カーテンにより閉ざされた空間に明かりを点すと、埃がスポットライトを浴びたように浮かび上がる。いずれ掃除しようと思っていても、それから半年が過ぎてしまった。
窓を開けて空気の入れ換えをすると、いくらかましになってくる。
テーブルにあるポスターを見て、水瀬は手に取った。
「探偵?」
「……一応、探偵の活動をしてる」
「好きなの?」
「まあ……それなりに」
それなりなんて嘘だ。家の本棚に並ぶのは、ミステリー小説ばかり。恋愛や自伝なんて、一割にも満たない。
「活動内容は?」
「……………………」
沈黙で、悟ってくれたようだ。
俺は半年前、勇気を出して探偵クラブという名前の通りのクラブを設立した。部員は俺ひとりなので、正確に言うと設立できなかったわけだが、一応、仮という形でこの空き教室を借りている。資料が並ぶ物置部屋なので、いきなり生徒に悲鳴を上げられるなんてたまにある。
「とりあえず、君のことから知りたいかな」
「俺のこと?」
「名前も知らない人に、依頼なんて頼めない」
ガタ、と椅子が揺れた。ついでに机の脚も蹴ってしまった。
「い、依頼してくれるのか……?」
「名前」
自己紹介ほど恥ずかしく、緊張するものはない。けれど将来に繋がる第一歩だと言い聞かせ、口を開いた。
「さ、佐藤鈴弥。……えーと、探偵、してます。したいです」
「声が小さい。誕生日は?」
「夏休み。八月」
「血液型は?」
「A型」
「趣味は?」
「読書」
「リンはさ、」
「リン?」
「あ、一番声が大きい」
捉えどころのない笑みは、今朝見た笑顔と変わらない。リンってどういうことだ。
「名前は、さ・と・う、す・ず・や」
「うん、リンでしょ?」
「……その呼び名、言われたことないんだけど……」
「……本当に?」
「ないよ。親にすら言われたことない」
「クラスの友達は君のことをなんて呼ぶの?」
「……佐藤」
佐藤ですら呼ばれたのはいつ頃か。だいたい「ねえ」や「おい」が多い。クラスメイトは、きっと俺の名前を知らないし、覚える気もない。
「リンの好きな食べ物は?」
「……だから俺は…………」
「肉派? 魚派? それともご飯? パン?」
「……全部好き」
「オッケー。じゃあ帰ろうか」
「は?」
人の話を聞かないのか。
書きかけのポスターを机に置き、水瀬は俺の手首を掴んだ。
「ちょっと、どこ行くの」
「ご飯もパンもあって、肉があるところ。食べ盛りだし、いける」
今日も探偵の活動をしないまま、終えてしまった。虚しい日々は毎回味わっているが、今日は少し特別な日だ。
ひとりであれば廊下を歩いていても注目を浴びることなんて一切ないのに、今は視線のシャワーを浴びる。しかも勢いが強い。
連れて来られた場所は、駅前にあるよく見るチェーン店のハンバーガーショップだった。離された手首に血が通い、じんわりと熱くなる。
「ま、待って……」
「嫌い?」
「あんまり、得意じゃない……!」
「味が苦手ってこと? 今日のお弁当にはミニハンバーグが入ってなかったっけ?」
「なんで知ってるのさ……味は好きだけど……雰囲気が……」
「俺も一緒だから大丈夫」
この人は、人の殻を簡単に破ってくる人だ。彼に限らず、そういう人は苦手な分類に入る。でもなぜか、また繋がれた手首は振り解けなかった。それは多分、彼の雰囲気がそうさせているのだと思う。
俺はクラスによくいるようなムードメーカータイプの人が苦手だ。明るすぎる人は回りを照らすのではなく、底なし沼へ落とす力も持っている。今日一日しか過ごしていないが、転入生は人付き合いをのらりくらり交わしていた。波長を合わせるタイプでもない。
「……中学のときの話だけど、五、六人がクラスに残ってて、とある男子がハンバーガーショップに行こうって誘っていたんだ。一緒に行こうと誘ってくれたんだけど、微妙な顔というか、嫌々というか。たまたまいたから誘うしかなかったってのが見え見えで。それで……苦手になった。昔を思い出すし」
何を語っているのか。初対面の男に。しかも店の前で。店員も、入るのか入らないのかどっちなんだという顔だ。あのときのクラスメイトを思い出す。
「そっか。入ろう」
「俺の話聞いてた? しかもご飯ないじゃん」
「ライスバーガーがあるよ。頼んでみたら? でもお昼はふりかけご飯だったよね。ならパンの方がいいかな」
「どこまで人の弁当事情に詳しいのさっ」
店の中に入ると、営業スマイルで対応された。無理な笑顔より、俺は真顔で対応の方が有り難い。気を使われるのは、俺も疲れるから。
セットを平らげ、夕食も食べる自信はなかった。チーズバーガーをひとつと、飲み物はコーラを注文した。端末をかざし、彼は俺の分も払ってくれた。
席を探していると、同じ制服を着た女子がこちらを見ている。正確に言うと俺の前を歩く人物に、だ。本人はどこ吹く風で、彼女たちから遠い席の窓際に座った。春だと窓際が気持ちいい。
「ポテト食べる?」
一本差し出して僕の口元へ持ってきた。横にいる女性が口を開けている。
「なに考えてるんだ……食べないよ」
「そっか」
行き場を失ったポテトは、水瀬の口に吸い込まれていく。機嫌が悪いのか寂しいのか、ポテトは折れ曲がっていた。
「チーズが好きなの?」
「滅多に来ないけど、だいたいこれしか食べない」
「どうして?」
「……ピクルス」
「好きなんだ? あれ美味しいよね」
水瀬が食べているのは、ライスバーガーだ。人にすすめておいて、結局自分が食べている。
「あのさ……いろいろ、聞きたいんだけど」
「なに?」
返事が優しい。これでは女子が落ちるのも頷ける。
「なんで、俺なの?」
「どういう意味かな?」
「なんで……俺と……初対面だし……」
「初対面の人間とハンバーガーを食べちゃいけない決まりでもあるの?」
「……ないけど」
「君は中学のとき、数年一緒にいたクラスメイトとハンバーガーショップに行ったことはあるの?」
話を蒸し返されてしまった。
「人間関係は独自のルールで縛るものではないんだよ。過去も切り離して考えないとね」
これは、もしかして。
食べ終わった紙をたたみ、ジュースを飲む仕草まで色男だ。なんだか悔しくて、お礼を言うことすらできなかった。あまりに自分がちっぽけな人間に見えた。
話の流れで連絡先を交換することになり、学生時代の記念すべき初のID交換は、転入生とすることになった。
家に帰ると、夕食はハンバーグで軽く絶望した。フィッシュバーガーにすればよかった。
またいこうねとメッセージが届いていたので、ハンバーグの写真を撮り送りつけてやった。
なぜ忘れてしまっていたのだろう。
──思い出した?
歌うように、朗らかに彼は笑う。
やっと出逢えた観測者は、あのときと変わらない笑みで顔を傾けた。
あれだけ満開だった桜は葉桜へと変わり、夏を匂わせるもなりきれていない季節となった。過ごしやすいし、けっこう好きな季節だ。
毎年同じ季節をルーティンで過ごす中、今年はちょっとしたニュースが舞い込んできた。
軋む引き戸が引かれ、いつものように担任が入ってきた。心なしか、顔に緊張が宿っている。後ろから入ってきたのは、初めて見る顔の生徒。同じ制服を着ていて、赤みがかった髪とすらりとした上背に甘ったるい薄い笑みは、女子生徒に悲鳴を上げさせるのに充分すぎるほどだった。
呆然と見ていると、担任の先生と目が合った。すみません、見惚れていたのはあなたじゃないんですと申し訳なさそうな顔をすると、担任は苦笑いを浮かべてしまった。ごめんなさい。
男性は一点集中して視線を浴びても、少しも動じることなくこちらを見ている。俺を。そう、俺だ。他の誰でもない、至って目立たない地味な俺を。
「転入生の水瀬葵さんだ。海外からやってきて、英語が得意なんだそうだ。仲良くしてやってくれ。席は……」
「そこ、空いています」
声も良いときたか。水瀬は俺の後ろを指差した。確かに空いている。担任の指示を待たず、転入生は迷わず俺の席の斜め後ろに腰を下ろした。
「よろしくね」
「う、うん……よろしくね」
俺の席は一番前で、窓際からふたつ離れた席だ。そして目の前にはガラス張りの棚がある。本や英語の教材が隙間なく並んでいる。
声をかけられた女子生徒は上擦った声を交わす。
ガラス越しに、転入生と目が合った。黄色い声を無駄に浴びた担任を見ると、小テストを行うなど何か話している。喝采は一気にブーイングと化した。生徒の親指が下を向いている。
もう一度ガラスに目を向けると、偶然ではなかった。転入生は、口元で何かを作り、笑みを浮かべる。分からず首を傾げると、もっとゆっくり唇の形を変えた。
読唇術の才がなくとも読めた。たった四文字の言葉だ。よろしく。
気恥ずかしかったが、目を逸らしながら同じ言葉を作ると、後ろから含み笑いが聞こえた。
放課後、職員室に課題の提出をしてクラスに戻ると、転入生はすでにいなかった。
「ねえ、水瀬君知らない?」
「さあ? 見てないけど」
「いなくなっちゃったのよねえ。一緒に帰りたかったのに」
この分だと、逃げたのかもしれない。甘いマスクというか、女子受けしそうな顔だ。わたあめみたいなやつ。ほとんど話していないが、中身のギャップはあるのかないのか、どういう人だろう。
いつもの空き教室に向かうと、曲がり角で靴の底が悲鳴を上げた。音に反応して彼は俺に向くと、今朝の自己紹介のときのような笑顔で片手を上げる。
「やあ。ホームルームぶりだね」
「……帰ったんじゃないの?」
「ここは何部?」
質問には質問で返す。俺の問いに答える気はないようだ。
なんだか腑に落ちないので、俺も答えず返事の代わりに引き戸を引いた。
遮光カーテンにより閉ざされた空間に明かりを点すと、埃がスポットライトを浴びたように浮かび上がる。いずれ掃除しようと思っていても、それから半年が過ぎてしまった。
窓を開けて空気の入れ換えをすると、いくらかましになってくる。
テーブルにあるポスターを見て、水瀬は手に取った。
「探偵?」
「……一応、探偵の活動をしてる」
「好きなの?」
「まあ……それなりに」
それなりなんて嘘だ。家の本棚に並ぶのは、ミステリー小説ばかり。恋愛や自伝なんて、一割にも満たない。
「活動内容は?」
「……………………」
沈黙で、悟ってくれたようだ。
俺は半年前、勇気を出して探偵クラブという名前の通りのクラブを設立した。部員は俺ひとりなので、正確に言うと設立できなかったわけだが、一応、仮という形でこの空き教室を借りている。資料が並ぶ物置部屋なので、いきなり生徒に悲鳴を上げられるなんてたまにある。
「とりあえず、君のことから知りたいかな」
「俺のこと?」
「名前も知らない人に、依頼なんて頼めない」
ガタ、と椅子が揺れた。ついでに机の脚も蹴ってしまった。
「い、依頼してくれるのか……?」
「名前」
自己紹介ほど恥ずかしく、緊張するものはない。けれど将来に繋がる第一歩だと言い聞かせ、口を開いた。
「さ、佐藤鈴弥。……えーと、探偵、してます。したいです」
「声が小さい。誕生日は?」
「夏休み。八月」
「血液型は?」
「A型」
「趣味は?」
「読書」
「リンはさ、」
「リン?」
「あ、一番声が大きい」
捉えどころのない笑みは、今朝見た笑顔と変わらない。リンってどういうことだ。
「名前は、さ・と・う、す・ず・や」
「うん、リンでしょ?」
「……その呼び名、言われたことないんだけど……」
「……本当に?」
「ないよ。親にすら言われたことない」
「クラスの友達は君のことをなんて呼ぶの?」
「……佐藤」
佐藤ですら呼ばれたのはいつ頃か。だいたい「ねえ」や「おい」が多い。クラスメイトは、きっと俺の名前を知らないし、覚える気もない。
「リンの好きな食べ物は?」
「……だから俺は…………」
「肉派? 魚派? それともご飯? パン?」
「……全部好き」
「オッケー。じゃあ帰ろうか」
「は?」
人の話を聞かないのか。
書きかけのポスターを机に置き、水瀬は俺の手首を掴んだ。
「ちょっと、どこ行くの」
「ご飯もパンもあって、肉があるところ。食べ盛りだし、いける」
今日も探偵の活動をしないまま、終えてしまった。虚しい日々は毎回味わっているが、今日は少し特別な日だ。
ひとりであれば廊下を歩いていても注目を浴びることなんて一切ないのに、今は視線のシャワーを浴びる。しかも勢いが強い。
連れて来られた場所は、駅前にあるよく見るチェーン店のハンバーガーショップだった。離された手首に血が通い、じんわりと熱くなる。
「ま、待って……」
「嫌い?」
「あんまり、得意じゃない……!」
「味が苦手ってこと? 今日のお弁当にはミニハンバーグが入ってなかったっけ?」
「なんで知ってるのさ……味は好きだけど……雰囲気が……」
「俺も一緒だから大丈夫」
この人は、人の殻を簡単に破ってくる人だ。彼に限らず、そういう人は苦手な分類に入る。でもなぜか、また繋がれた手首は振り解けなかった。それは多分、彼の雰囲気がそうさせているのだと思う。
俺はクラスによくいるようなムードメーカータイプの人が苦手だ。明るすぎる人は回りを照らすのではなく、底なし沼へ落とす力も持っている。今日一日しか過ごしていないが、転入生は人付き合いをのらりくらり交わしていた。波長を合わせるタイプでもない。
「……中学のときの話だけど、五、六人がクラスに残ってて、とある男子がハンバーガーショップに行こうって誘っていたんだ。一緒に行こうと誘ってくれたんだけど、微妙な顔というか、嫌々というか。たまたまいたから誘うしかなかったってのが見え見えで。それで……苦手になった。昔を思い出すし」
何を語っているのか。初対面の男に。しかも店の前で。店員も、入るのか入らないのかどっちなんだという顔だ。あのときのクラスメイトを思い出す。
「そっか。入ろう」
「俺の話聞いてた? しかもご飯ないじゃん」
「ライスバーガーがあるよ。頼んでみたら? でもお昼はふりかけご飯だったよね。ならパンの方がいいかな」
「どこまで人の弁当事情に詳しいのさっ」
店の中に入ると、営業スマイルで対応された。無理な笑顔より、俺は真顔で対応の方が有り難い。気を使われるのは、俺も疲れるから。
セットを平らげ、夕食も食べる自信はなかった。チーズバーガーをひとつと、飲み物はコーラを注文した。端末をかざし、彼は俺の分も払ってくれた。
席を探していると、同じ制服を着た女子がこちらを見ている。正確に言うと俺の前を歩く人物に、だ。本人はどこ吹く風で、彼女たちから遠い席の窓際に座った。春だと窓際が気持ちいい。
「ポテト食べる?」
一本差し出して僕の口元へ持ってきた。横にいる女性が口を開けている。
「なに考えてるんだ……食べないよ」
「そっか」
行き場を失ったポテトは、水瀬の口に吸い込まれていく。機嫌が悪いのか寂しいのか、ポテトは折れ曲がっていた。
「チーズが好きなの?」
「滅多に来ないけど、だいたいこれしか食べない」
「どうして?」
「……ピクルス」
「好きなんだ? あれ美味しいよね」
水瀬が食べているのは、ライスバーガーだ。人にすすめておいて、結局自分が食べている。
「あのさ……いろいろ、聞きたいんだけど」
「なに?」
返事が優しい。これでは女子が落ちるのも頷ける。
「なんで、俺なの?」
「どういう意味かな?」
「なんで……俺と……初対面だし……」
「初対面の人間とハンバーガーを食べちゃいけない決まりでもあるの?」
「……ないけど」
「君は中学のとき、数年一緒にいたクラスメイトとハンバーガーショップに行ったことはあるの?」
話を蒸し返されてしまった。
「人間関係は独自のルールで縛るものではないんだよ。過去も切り離して考えないとね」
これは、もしかして。
食べ終わった紙をたたみ、ジュースを飲む仕草まで色男だ。なんだか悔しくて、お礼を言うことすらできなかった。あまりに自分がちっぽけな人間に見えた。
話の流れで連絡先を交換することになり、学生時代の記念すべき初のID交換は、転入生とすることになった。
家に帰ると、夕食はハンバーグで軽く絶望した。フィッシュバーガーにすればよかった。
またいこうねとメッセージが届いていたので、ハンバーグの写真を撮り送りつけてやった。
0
あなたにおすすめの小説

宵にまぎれて兎は回る
宇土為名
BL
高校3年の春、同級生の名取に告白した冬だったが名取にはあっさりと冗談だったことにされてしまう。それを否定することもなく卒業し手以来、冬は親友だった名取とは距離を置こうと一度も連絡を取らなかった。そして8年後、勤めている会社の取引先で転勤してきた名取と8年ぶりに再会を果たす。再会してすぐ名取は自身の結婚式に出席してくれと冬に頼んできた。はじめは断るつもりだった冬だが、名取の願いには弱く結局引き受けてしまう。そして式当日、幸せに溢れた雰囲気に疲れてしまった冬は式場の中庭で避難するように休憩した。いまだに思いを断ち切れていない自分の情けなさを反省していると、そこで別の式に出席している男と出会い…

【全10作】BLショートショート・短編集
雨樋雫
BL
文字数が少なめのちょこっとしたストーリーはこちらにまとめることにしました。
1話完結のショートショートです。
あからさまなものはありませんが、若干の性的な関係を示唆する表現も含まれます。予めご理解お願いします。

仮面の王子と優雅な従者
emanon
BL
国土は小さいながらも豊かな国、ライデン王国。
平和なこの国の第一王子は、人前に出る時は必ず仮面を付けている。
おまけに病弱で無能、醜男と専らの噂だ。
しかしそれは世を忍ぶ仮の姿だった──。
これは仮面の王子とその従者が暗躍する物語。
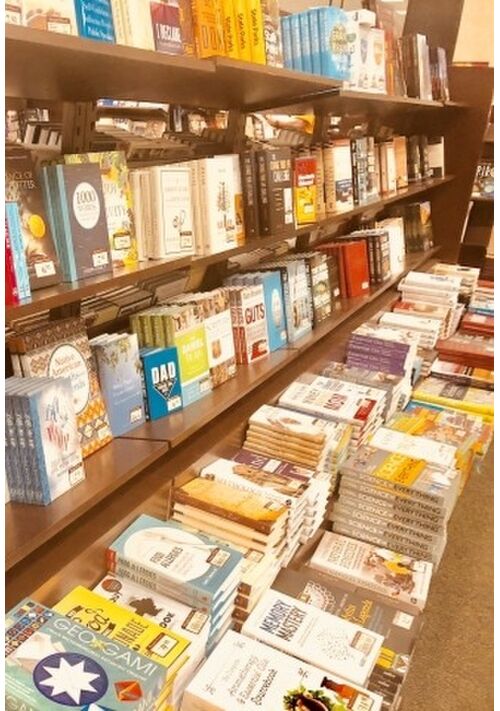
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)


秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

人気作家は売り専男子を抱き枕として独占したい
白妙スイ@1/9新刊発売
BL
八架 深都は好奇心から売り専のバイトをしている大学生。
ある日、不眠症の小説家・秋木 晴士から指名が入る。
秋木の家で深都はもこもこの部屋着を着せられて、抱きもせず添い寝させられる。
戸惑った深都だったが、秋木は気に入ったと何度も指名してくるようになって……。
●八架 深都(はちか みと)
20歳、大学2年生
好奇心旺盛な性格
●秋木 晴士(あきぎ せいじ)
26歳、小説家
重度の不眠症らしいが……?
※性的描写が含まれます
完結いたしました!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















