13 / 20
第一章 転入生と地味な僕
013 白昼夢と現実の狭間で
しおりを挟む
また、現実か夢かも曖昧な夢を見た。悲しい夢ではなく、幸せだった記憶が夢として現れたような、同じ世界を二度体験したかのような出来事で、起床するといつも目から涙が流れていた。
最後だからとわざわざ今日のために制服をクリーニングに出してくれ、新品のような制服がかけられている。
「おはよう、鈴弥。しっかり食べていってね」
「気合い入りすぎじゃない?」
卵焼きにあんがかかっている。とろとろで美味しそうだが、朝から食べるものではない。ちょっとした豪華な食事でしか見たことがなかった。テストで良い点を取ったときだったり、文化祭お疲れ様の夕食でも食べた。
「高校最後の日よ? これくらいの気合いは入っちゃうわ」
「食べ過ぎて卒業出られなくなったらどうするのさ」
味は最高すぎるから文句なんてすぐに引っ込んでいった。お吸い物まである。
「卒業式の後はどうするの? 聖子ちゃんと出かける?」
「う、ん……分かんないけど」
そういえば、約束なんてしていたっけ? 付き合っているからといって、必ず一緒にいなければならないものでもない。友達同士でカラオケやボーリングをしたり、すぐに家に帰ってきたっておかしくない。
未だに俺は北野さんと呼び続けている。聖子さんとは一度も呼べない。何度も喉まで出かかっては、口が閉じてしまう。暗示にかかったみたいに、自分の意思とは違う何かに邪魔をされてしまう。
新品みたいになった制服に袖を通すと、縮んだ気がした。実際は俺の身長が伸びたからだ。目標だった百七十センチも超えたし、体重も増えた。でも身長はあと少しほしい。
校舎まで行くと、俺は記念に一枚写真を撮った。真新しく感じていた建物も、三年間の想い出とともに古美に心に刻まれていくだろう。
教室ではすでに泣いている女子、いつも通り騒ぎ続ける男子、我関せずと読書で違う世界を放浪する人と様々だ。
泣きそうになっている担任からは長々と有り難い話を聞かされ、式では校長からもさらに長い話を聞かされ、無事に卒業式を終えた。
目の奥がつんともしない。卒業式より大事なことが頭の片隅にあって、友人の呼び止めにも立ち止まらずに階段を駆け上がった。
「……ひどい」
ぼろぼろになったポスターは、落書きもされて探偵の文字には画鋲で押さえつけられている。一生懸命作った……ポスター。
「……誰だっけ?」
俺は作った記憶がない。そもそも俺の字じゃない。誰かが作って、貼ったポスターだ。
探偵クラブは、俺の代で終わる。俺が作って俺が終わらせた。入ってくれる後輩もいなかった。誰も興味なんて持ってくれない。
「ここにいると思った」
「北野さん……」
胸元には大きな花が飾られている。後輩からもらったのだろう。
「初めてここで鈴弥君と出会ったのよね。覚えてる? 親身になって悩みを聞いてくれて、私、あのときから……」
「ねえ、何の悩み相談だっけ?」
「相談? うーん……なんだったかな……小さい悩みだったのかも」
「このポスターって、誰が書いたか分かる?」
「鈴弥君しかいないんじゃないの? だって部員ひとりでしょう? あっちょっと、大丈夫?」
心臓が大きく揺れ、耳鳴りのような音が届く。壁に手をつき、何度か深呼吸を繰り返した。
「俺……脳がおかしいのかもしれない。なんかへんだ。違う自分がもうひとりいるみたいで、おかしな夢もみるし」
「もしかして体調悪いの? 来週の旅行は取りやめようか?」
そうだった。旅行のことをすっかり忘れていた。
俺はいきたい孤島があると話したら、彼女はついてきてくれると言った。本当は北海道が良かったはずなのに、北野さんは俺に合わせてくれたのだ。
「うん、ごめん」
「旅行はいつでも行けるしね」
台詞と顔が一致していない。毎日メールでやりとりするほど、彼女は楽しみにしていたのに。
申し訳なさすぎて、俺は何度も頭を下げた。彼女はそこまでしないでといい、俺の隣に腰を下ろす。違う、そうじゃないんだ。旅行をキャンセルしたことを謝っているわけではなく、旅行に行けなくなってどこかほっとしている俺がいて。彼女が思う謝罪と一致していない。北野さんとは、いつも歯車が合わない。がりがり音を立てて俺の心が削れていく。まるで違う世界線を生きているみたいだ。
「世界線……?」
どこかで、誰かが言っていた。多分、夢だ。夢の中で、俺の選ぶ選択は生と死の真っ二つで、それが高校生のときに訪れると。内容だけだと恐ろしい夢なのに、ずっと夢の中でふわふわしていたかった。現実に不満があるわけではないのに、おかしい。
北野さんとは校門で別れ、俺は母と家に帰った。別れる直前も母に、俺が具合が悪いと伝えたものだから、しっかりした人だ。ふらついただけでもうどこも悪くないのに、罪悪感で大丈夫だと言えなかった。
小さくなった最後の制服を脱ぎ捨て、ベットに横になりながらSNSやメールを返していく。ふと、俺に一度返信をしてくれた人のアカウントを覗いた。俺にお守りのある孤島を教えてくれてから、誰にも返信していないしフォローも俺だけだ。
リビングに顔を出すと、母が誰かと電話していた。お寿司を取るつもりらしい。
「寝てなくていい? お寿司取ったんだけど、やめようか?」
「まさか。寿司がいい。ねえ……俺ってお母さんの子供だよね?」
突拍子もない質問に母は驚くが、すぐに笑って野菜を切り始める。
「これだけ顔が似ていて、まさか川から拾ってきたと思っているの? お母さんとお父さんの子供に決まっているでしょう?」
「だよね。ただの気の迷いの質問だから」
「大きな怪我も病気もしないで育ってくれただけで嬉しいわ」
「本当に? 怪我したことはない? 瓦礫に挟まったり、誰かに刺されたり」
「どうしたのよ。事故も事件もないわよ」
冗談と受け取ったのか、母は笑うだけで相手にしてくれなくなった。
部屋に戻ってもう一度ベッドに伏せた。北野さんからメールが届いている。
──具合は大丈夫?
──寝てる。大丈夫だよ、ありがとう。
罪悪感が積み重なっていく。彼女からのメールより、卒業式に持っていったお守りの方が気になっているものだから、なおさら心が痛い。手のひらに収めると、こんなに小さいのにずっしりと重みを感じる。
スマホが震えている。誰からの電話だろう。出なければならないのに、急に身体が重くなって触れることさえできなかった。
直感的に、またあの夢を見るのだと思った。現実味があって夢のままでは終わらなそうな夢。俺は、恐ろしくとも夢に幸せを感じている。
電車、徒歩、フェリーと移動ばかりの一日だが、ようやく席に座ることができた。まだ十代なのに、いろんなものが確実に腰にきている。痛い。隣に座るおばあさんと目が合い、同じものを抱えているのねと憐れみの目で見られてしまった。
半分夢の世界で過ごしていると、もうすぐ予定通りに着港すると船内放送が流れる。うんと伸びをして横を見るも、おばあさんがいない。気づかないほど眠っていたらしい。
先に降りた観光客が歓声を上げている。島に上陸すると、電流が全身を流れて感覚の無くなった足は雄叫びを上げた。尻餅をついた俺を見て、女性たちは悲鳴に似た声を出す。
「大丈夫ですか? 宿泊する民宿はここから近いですか?」
「そんなに遠くないはずです。さっきまで寝ていたんで、急に立ちくらみが起こっただけです」
おかしなことに、左胸が熱くなった。ポケットにはお守りが入っていて、何か訴えているような気がした。
民宿に到着すると、着物を着た女性が出迎えてくれた。予約したのにひとりになってしまい謝罪をすると、お連れの方とまたいらっしゃいと優しいお言葉だ。
「すみません、ここで開かれているお祭りについて聞きたいんです。あと。これは知っていますか?」
お守りは冷たいままだ。けれど熱を帯びたのは幻と思えない。
「人からもらったものなんです」
「では、こちらを手に入れた方は祭りの関係者ですね」
「どういうことですか?」
「祭りの日しか手に入らないものですよ。しかも極少数。観光客の方では、持っている方はほとんどいらっしゃらないかと。販売しているのは似たお守りで、そちらは近親者にしか配られていないものです」
「近親者……?」
「見た目は分かりにくいですが、この島の人間ならばすぐに分かります」
女将さんは祭りについて詳しく教えてくれた。大昔、この辺り一帯で農作物も採れなくなり、濁った水で餓えを凌ぐほど大飢饉に襲われた。人間たちの前に姿を現したのは、人語を話す狐だった。
──肥えた土を取り戻したければ、一番裕福な家の子供を差し出せ。
狐はそう言い残すと、森の中へ消えた。
稚児をひとり差し出すと、みるみるうちに土地が蘇り、大ぶりの肥えた作物が実るようになったという。
「村の人に聞いても、いろんな説があって面白いですよ。稚児ではなく若い女を差し出しただの、狐ではなく狸だっただの」
「でも野菜が大きいのはびっくりしました」
「水がいいんですよ。祭りの行われる神社や山でも飲めますから、ぜひ召し上がって下さいね」
夕食まで時間がある。民宿に荷物を置かせてもらい、外に出た。島は瑞々しい香りで満たされている。都会では絶対に嗅ぐことのできない自然の匂いだ。
狐が物陰からじっと見ている。人に慣れているようで、逃げる様子もない。食べ物も持っていないのにすり寄ってきては、ポケットから出ていたお守りのひもを咥えた。
「あっちょっと!」
口に入れるでもなく、お守りを口に挟んだまま狐は歩き出してしまった。慌てて後を追う。小走りでないとついていけない。
道のない森の中、木々の間をすり抜けていく狐は、息を切らす俺と一定の距離を離れない。時折後ろを振り向いては、いるかどうか確認をしている。
都会にあるような飾られた家とも違う、山小屋に似た建物だ。畑には数種類の野菜が植えられている。根を張った木々の隙間からしか太陽の光を射さず、夜であれば不気味な雰囲気になりそうだ。
狐は止まり、畑の横で座ってしまった。お守りを返してもらおうと手を伸ばすが、元々返すつもりだったのか取りやすいように口を開ける。
「ここに案内してくれたのか?」
頭を撫でようとすると、耳を飛行機みたいに横に広げ、思わず笑ってしまった。
家から物音がし、女性が出てきた。俺を見ては笑い、こんにちはと笑顔を見せる。目尻の皺が優しい。
「こ、こんにちは」
「観光でいらしたの?」
「そうです……」
「若い子が珍しいねえ。何にもないところなのに」
「えと……ここの祭りに興味があって」
笑っていたおばあさんは歓迎の目をしていたのに、どこか違う世界に迷い込んだようだった。
最後だからとわざわざ今日のために制服をクリーニングに出してくれ、新品のような制服がかけられている。
「おはよう、鈴弥。しっかり食べていってね」
「気合い入りすぎじゃない?」
卵焼きにあんがかかっている。とろとろで美味しそうだが、朝から食べるものではない。ちょっとした豪華な食事でしか見たことがなかった。テストで良い点を取ったときだったり、文化祭お疲れ様の夕食でも食べた。
「高校最後の日よ? これくらいの気合いは入っちゃうわ」
「食べ過ぎて卒業出られなくなったらどうするのさ」
味は最高すぎるから文句なんてすぐに引っ込んでいった。お吸い物まである。
「卒業式の後はどうするの? 聖子ちゃんと出かける?」
「う、ん……分かんないけど」
そういえば、約束なんてしていたっけ? 付き合っているからといって、必ず一緒にいなければならないものでもない。友達同士でカラオケやボーリングをしたり、すぐに家に帰ってきたっておかしくない。
未だに俺は北野さんと呼び続けている。聖子さんとは一度も呼べない。何度も喉まで出かかっては、口が閉じてしまう。暗示にかかったみたいに、自分の意思とは違う何かに邪魔をされてしまう。
新品みたいになった制服に袖を通すと、縮んだ気がした。実際は俺の身長が伸びたからだ。目標だった百七十センチも超えたし、体重も増えた。でも身長はあと少しほしい。
校舎まで行くと、俺は記念に一枚写真を撮った。真新しく感じていた建物も、三年間の想い出とともに古美に心に刻まれていくだろう。
教室ではすでに泣いている女子、いつも通り騒ぎ続ける男子、我関せずと読書で違う世界を放浪する人と様々だ。
泣きそうになっている担任からは長々と有り難い話を聞かされ、式では校長からもさらに長い話を聞かされ、無事に卒業式を終えた。
目の奥がつんともしない。卒業式より大事なことが頭の片隅にあって、友人の呼び止めにも立ち止まらずに階段を駆け上がった。
「……ひどい」
ぼろぼろになったポスターは、落書きもされて探偵の文字には画鋲で押さえつけられている。一生懸命作った……ポスター。
「……誰だっけ?」
俺は作った記憶がない。そもそも俺の字じゃない。誰かが作って、貼ったポスターだ。
探偵クラブは、俺の代で終わる。俺が作って俺が終わらせた。入ってくれる後輩もいなかった。誰も興味なんて持ってくれない。
「ここにいると思った」
「北野さん……」
胸元には大きな花が飾られている。後輩からもらったのだろう。
「初めてここで鈴弥君と出会ったのよね。覚えてる? 親身になって悩みを聞いてくれて、私、あのときから……」
「ねえ、何の悩み相談だっけ?」
「相談? うーん……なんだったかな……小さい悩みだったのかも」
「このポスターって、誰が書いたか分かる?」
「鈴弥君しかいないんじゃないの? だって部員ひとりでしょう? あっちょっと、大丈夫?」
心臓が大きく揺れ、耳鳴りのような音が届く。壁に手をつき、何度か深呼吸を繰り返した。
「俺……脳がおかしいのかもしれない。なんかへんだ。違う自分がもうひとりいるみたいで、おかしな夢もみるし」
「もしかして体調悪いの? 来週の旅行は取りやめようか?」
そうだった。旅行のことをすっかり忘れていた。
俺はいきたい孤島があると話したら、彼女はついてきてくれると言った。本当は北海道が良かったはずなのに、北野さんは俺に合わせてくれたのだ。
「うん、ごめん」
「旅行はいつでも行けるしね」
台詞と顔が一致していない。毎日メールでやりとりするほど、彼女は楽しみにしていたのに。
申し訳なさすぎて、俺は何度も頭を下げた。彼女はそこまでしないでといい、俺の隣に腰を下ろす。違う、そうじゃないんだ。旅行をキャンセルしたことを謝っているわけではなく、旅行に行けなくなってどこかほっとしている俺がいて。彼女が思う謝罪と一致していない。北野さんとは、いつも歯車が合わない。がりがり音を立てて俺の心が削れていく。まるで違う世界線を生きているみたいだ。
「世界線……?」
どこかで、誰かが言っていた。多分、夢だ。夢の中で、俺の選ぶ選択は生と死の真っ二つで、それが高校生のときに訪れると。内容だけだと恐ろしい夢なのに、ずっと夢の中でふわふわしていたかった。現実に不満があるわけではないのに、おかしい。
北野さんとは校門で別れ、俺は母と家に帰った。別れる直前も母に、俺が具合が悪いと伝えたものだから、しっかりした人だ。ふらついただけでもうどこも悪くないのに、罪悪感で大丈夫だと言えなかった。
小さくなった最後の制服を脱ぎ捨て、ベットに横になりながらSNSやメールを返していく。ふと、俺に一度返信をしてくれた人のアカウントを覗いた。俺にお守りのある孤島を教えてくれてから、誰にも返信していないしフォローも俺だけだ。
リビングに顔を出すと、母が誰かと電話していた。お寿司を取るつもりらしい。
「寝てなくていい? お寿司取ったんだけど、やめようか?」
「まさか。寿司がいい。ねえ……俺ってお母さんの子供だよね?」
突拍子もない質問に母は驚くが、すぐに笑って野菜を切り始める。
「これだけ顔が似ていて、まさか川から拾ってきたと思っているの? お母さんとお父さんの子供に決まっているでしょう?」
「だよね。ただの気の迷いの質問だから」
「大きな怪我も病気もしないで育ってくれただけで嬉しいわ」
「本当に? 怪我したことはない? 瓦礫に挟まったり、誰かに刺されたり」
「どうしたのよ。事故も事件もないわよ」
冗談と受け取ったのか、母は笑うだけで相手にしてくれなくなった。
部屋に戻ってもう一度ベッドに伏せた。北野さんからメールが届いている。
──具合は大丈夫?
──寝てる。大丈夫だよ、ありがとう。
罪悪感が積み重なっていく。彼女からのメールより、卒業式に持っていったお守りの方が気になっているものだから、なおさら心が痛い。手のひらに収めると、こんなに小さいのにずっしりと重みを感じる。
スマホが震えている。誰からの電話だろう。出なければならないのに、急に身体が重くなって触れることさえできなかった。
直感的に、またあの夢を見るのだと思った。現実味があって夢のままでは終わらなそうな夢。俺は、恐ろしくとも夢に幸せを感じている。
電車、徒歩、フェリーと移動ばかりの一日だが、ようやく席に座ることができた。まだ十代なのに、いろんなものが確実に腰にきている。痛い。隣に座るおばあさんと目が合い、同じものを抱えているのねと憐れみの目で見られてしまった。
半分夢の世界で過ごしていると、もうすぐ予定通りに着港すると船内放送が流れる。うんと伸びをして横を見るも、おばあさんがいない。気づかないほど眠っていたらしい。
先に降りた観光客が歓声を上げている。島に上陸すると、電流が全身を流れて感覚の無くなった足は雄叫びを上げた。尻餅をついた俺を見て、女性たちは悲鳴に似た声を出す。
「大丈夫ですか? 宿泊する民宿はここから近いですか?」
「そんなに遠くないはずです。さっきまで寝ていたんで、急に立ちくらみが起こっただけです」
おかしなことに、左胸が熱くなった。ポケットにはお守りが入っていて、何か訴えているような気がした。
民宿に到着すると、着物を着た女性が出迎えてくれた。予約したのにひとりになってしまい謝罪をすると、お連れの方とまたいらっしゃいと優しいお言葉だ。
「すみません、ここで開かれているお祭りについて聞きたいんです。あと。これは知っていますか?」
お守りは冷たいままだ。けれど熱を帯びたのは幻と思えない。
「人からもらったものなんです」
「では、こちらを手に入れた方は祭りの関係者ですね」
「どういうことですか?」
「祭りの日しか手に入らないものですよ。しかも極少数。観光客の方では、持っている方はほとんどいらっしゃらないかと。販売しているのは似たお守りで、そちらは近親者にしか配られていないものです」
「近親者……?」
「見た目は分かりにくいですが、この島の人間ならばすぐに分かります」
女将さんは祭りについて詳しく教えてくれた。大昔、この辺り一帯で農作物も採れなくなり、濁った水で餓えを凌ぐほど大飢饉に襲われた。人間たちの前に姿を現したのは、人語を話す狐だった。
──肥えた土を取り戻したければ、一番裕福な家の子供を差し出せ。
狐はそう言い残すと、森の中へ消えた。
稚児をひとり差し出すと、みるみるうちに土地が蘇り、大ぶりの肥えた作物が実るようになったという。
「村の人に聞いても、いろんな説があって面白いですよ。稚児ではなく若い女を差し出しただの、狐ではなく狸だっただの」
「でも野菜が大きいのはびっくりしました」
「水がいいんですよ。祭りの行われる神社や山でも飲めますから、ぜひ召し上がって下さいね」
夕食まで時間がある。民宿に荷物を置かせてもらい、外に出た。島は瑞々しい香りで満たされている。都会では絶対に嗅ぐことのできない自然の匂いだ。
狐が物陰からじっと見ている。人に慣れているようで、逃げる様子もない。食べ物も持っていないのにすり寄ってきては、ポケットから出ていたお守りのひもを咥えた。
「あっちょっと!」
口に入れるでもなく、お守りを口に挟んだまま狐は歩き出してしまった。慌てて後を追う。小走りでないとついていけない。
道のない森の中、木々の間をすり抜けていく狐は、息を切らす俺と一定の距離を離れない。時折後ろを振り向いては、いるかどうか確認をしている。
都会にあるような飾られた家とも違う、山小屋に似た建物だ。畑には数種類の野菜が植えられている。根を張った木々の隙間からしか太陽の光を射さず、夜であれば不気味な雰囲気になりそうだ。
狐は止まり、畑の横で座ってしまった。お守りを返してもらおうと手を伸ばすが、元々返すつもりだったのか取りやすいように口を開ける。
「ここに案内してくれたのか?」
頭を撫でようとすると、耳を飛行機みたいに横に広げ、思わず笑ってしまった。
家から物音がし、女性が出てきた。俺を見ては笑い、こんにちはと笑顔を見せる。目尻の皺が優しい。
「こ、こんにちは」
「観光でいらしたの?」
「そうです……」
「若い子が珍しいねえ。何にもないところなのに」
「えと……ここの祭りに興味があって」
笑っていたおばあさんは歓迎の目をしていたのに、どこか違う世界に迷い込んだようだった。
0
あなたにおすすめの小説

宵にまぎれて兎は回る
宇土為名
BL
高校3年の春、同級生の名取に告白した冬だったが名取にはあっさりと冗談だったことにされてしまう。それを否定することもなく卒業し手以来、冬は親友だった名取とは距離を置こうと一度も連絡を取らなかった。そして8年後、勤めている会社の取引先で転勤してきた名取と8年ぶりに再会を果たす。再会してすぐ名取は自身の結婚式に出席してくれと冬に頼んできた。はじめは断るつもりだった冬だが、名取の願いには弱く結局引き受けてしまう。そして式当日、幸せに溢れた雰囲気に疲れてしまった冬は式場の中庭で避難するように休憩した。いまだに思いを断ち切れていない自分の情けなさを反省していると、そこで別の式に出席している男と出会い…

【全10作】BLショートショート・短編集
雨樋雫
BL
文字数が少なめのちょこっとしたストーリーはこちらにまとめることにしました。
1話完結のショートショートです。
あからさまなものはありませんが、若干の性的な関係を示唆する表現も含まれます。予めご理解お願いします。

仮面の王子と優雅な従者
emanon
BL
国土は小さいながらも豊かな国、ライデン王国。
平和なこの国の第一王子は、人前に出る時は必ず仮面を付けている。
おまけに病弱で無能、醜男と専らの噂だ。
しかしそれは世を忍ぶ仮の姿だった──。
これは仮面の王子とその従者が暗躍する物語。
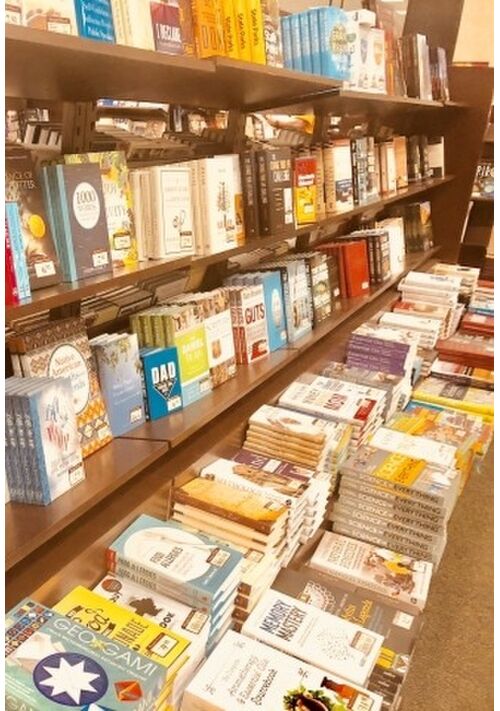
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)


秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

人気作家は売り専男子を抱き枕として独占したい
白妙スイ@1/9新刊発売
BL
八架 深都は好奇心から売り専のバイトをしている大学生。
ある日、不眠症の小説家・秋木 晴士から指名が入る。
秋木の家で深都はもこもこの部屋着を着せられて、抱きもせず添い寝させられる。
戸惑った深都だったが、秋木は気に入ったと何度も指名してくるようになって……。
●八架 深都(はちか みと)
20歳、大学2年生
好奇心旺盛な性格
●秋木 晴士(あきぎ せいじ)
26歳、小説家
重度の不眠症らしいが……?
※性的描写が含まれます
完結いたしました!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















