20 / 20
エピローグ
エピローグ─愛の巣─
しおりを挟む
「本当に本当に、お世話になりました」
こちらが申し訳ないくらいに頭を下げ、女性は大事そうにカゴを抱きかかえた。
女性の名前は綾川さん。前にストーカーに追われた過去があり、心も身体も疲労が溜まってしばらく入退院を繰り返していた。これではいけないと新しい人生に挑戦した結果、今は薬を飲まなくても外を歩けるようになったという。大きな一歩だ。解決に導いた俺も、鼻が高い。
「この子も元気に帰ってきました。何度、佐藤さんにお世話になったか……」
この子と言われた猫はつまらなそうに小さく鳴いた。大冒険が見知らぬ男に捕まえられて、終わりを迎えてしまったのだ。猫の立場からすれば、たまったものじゃないだろう。
綾川さんの挑戦というのは、猫を飼うことだ。昔から好きで、けれど家族に猫アレルギーの人がいたために、なかなか機会に恵まれなかったのだそう。念願の一人暮らしを始めて、ストーカー事件も一応解決を迎え、引っ越しを機に猫を飼い始めた。仕事帰りに玄関を開けると、隙をついて逃げてしまったと、探偵事務所に相談があったのだ。
三日間で見つけられたのは運がいい。かつお節が好物だというのでペットショップで購入し、猫のたまり場をうろうろしていると、すぐに食いついた白黒の猫がいた。抱き上げてもそれよりかつお節を寄越せという姿勢を崩さなかった猫は、紛れもなく綾川さんの飼い猫だと確信を持った。
「よければ、こちらをどうぞ。お礼です。ようかんなので、冷やして食べて下さい」
「嬉しいです。甘いものはすごく好きなんですよ」
一番好きなのは相方だとは言わず、有り難く受け取った。事前まで冷蔵庫に入れていたのか、紙袋もひんやりしている。
事務所を施錠し、ビルの二階に位置するため、エレベーターを使わずに階段を降りる。ちょっとでも体力が向上すればいいと祈りを込めて。
車に乗ると、メールを送った。
──今日は卵安売りの日だから買っていくけど、家になかったよね?
──はい。
うんではなく、はい、だ。なんだか嫌な予感がする。
駅前のスーパーでお一人様ひとパックまでの卵と、豚肉。今日は生姜焼きが食べたい。キャベツはある。溶き卵入りのみそ汁も作りたい。
適当に安い野菜を買えば、野菜炒めでもなんでも作れる。うちでは肉の消費量が多いので、意識して野菜を買うようにしている。
買い物を終えてマンションに向かうと、ずっと家にいたのか隣の車に走らせた跡がない。ビニール袋と紙袋を抱えて家に鍵を差し込むと、隙間から冷たい風が身体を冷やす。
廊下の電気は消えている。風呂場の電気はついていて、シャワーの音が聞こえた。ただいまと挨拶してもよかったが、引きずり込まれるのがオチなので見なかったことにしよう。蛇のように身体に巻きつく腕は、絶対に離そうとしない。今は八月。熱風と太陽を浴びた身体は、欲より冷たいサイダーを欲している。
冷蔵庫に材料をしまおうと扉を開けると、変な声が出てしまった。
「もう! なんだよこれ」
「あ、おかえりー」
やらかした張本人はへらりと笑い、俺の頬と唇にキスを落とす。
「俺メール送ったよね? 卵あるかどうかって。なんで冷蔵庫に二パックも入ってんのさっ」
「あー、うん。あれね。ごめん、寝起きなんだ。昼寝してた」
確かに寝起きの声だ。でもそういう問題じゃない。
「明日の朝はオムレツ確定。今日の夕食は豚の生姜焼きにしようと思ったけど、」
「やった」
「止める」
「ええ……」
「エセ親子丼にする」
「おいしそー」
「風呂入ってくるから、葵が材料切ってて。豚肉を細くして、玉ねぎも切る。鶏肉の代わりに豚肉を使うから」
「はーい」
探偵事務所は今日は俺ひとりで、明日はふたり一緒に休みだ。今日葵を休みにしたのは、引っ越しの荷解きのためだ。今まで狭いアパートでふたりで暮らしていたため、そろそろ広い場所を選ぼうと、事務所に近いマンションを選んだ。引っ越しをしたのはいいが、今までの葵を考えていなかった。
高校生のときも、探偵事務所で先輩後輩として出会ったときも、葵は生活力が皆無だった。何にもない部屋にほとんど使われていないキッチン。新居の個室に布団を敷いてはい終了なものだから、頭を抱えた。
引っ越し祝いにベッドをプレゼントしたいと言うと、葵は真剣に悩んでくれた。条件としては、ふたりで寝られる大きさ、下に響かない、音を吸収してくれる。それを店員に真剣に伝え詰め寄るので、俺はできるだけ距離を離れて他人のふりをしていた。
シャワーを終えると、待ちかまえていた葵は部屋にきてきてと子供の笑みで腕を引っ張る。
部屋についていくと、布団の敷いてあった場所に大きなベッドがある。うまく組み立てられたようだ。一日がかりだったろうし、疲れて昼寝もしたくなるだろう。
えらいえらいと頭を撫でると、もっとしてと押しつけてくる。ああ、かわいい。こんな可愛い人が僕より年上で、甘えたがりで、自慢の恋人なんだ。
キッチンには、材料を切っていてくれるだけでよかったのに、すでにどんぶりが出来上がっている。それとインスタントのお吸い物。松茸の良い香りがする。
俺の飲みたかったサイダーも用意してくれ、一緒に乾杯した。
「綾川さんの猫見つかったよ」
「よかったね。俺が近寄ると全猫が逃げるんだよねえ……なんでだろ?」
「得体の知れない生き物に見えたんじゃない? 過去遡ったりしてたし」
「あはは、言えてる」
「これからは俺が動物担当かなあ」
「そうだね。俺が餌買ってきたりネットで野良猫がたむろしている場所を調べる。猫を見つけたらだっこはリンの役目」
動物に嫌われるわけではない。あの孤島に行ったとき、少なくとも狐には嫌われていなかった。狐だけに好かれるのか、猫だけに嫌われるのかまだはっきりしない。
片づけは葵が担当して、俺は寝具を整えた。今日は誰かさんのせいで寝坊してしまい、布団を蹴ったまま出社したのだ。溢れ出たゴミ箱のティッシュを押し込み、空になりそうな箱の隣に新しくティッシュ箱を出した。
「用意がいいね」
「今日はしないよ」
「明日休みなのに?」
「……明日はふたりで散歩するって約束じゃん」
こっそり手を繋いで散歩したいと、俺のちょっとしたわがまま。
葵の可愛いところは、時折幼児返りをするところだ。おっぱい吸いたいと言い出し、パジャマのボタンを外しにかかる。こうなれば何を言っても通じないので、いつも好きにさせている。
「おっぱいだけだからね」
「今のいい……もう一回言って?」
「……おっぱい吸っていいよ?」
「ごめん、止まらない」
結局こうなるのだ。
分かっていて乗ってしまう俺も俺だから、似た者同士かもしれない。
朝はオムレツとソーセージ、キャベツの千切りサラダとパンを食べ、まったりとした午前を過ごした。
最近は立て続けに依頼が入り、忙しい日々を送っていた。こうしてソファーに座ってお茶を飲む時間が与えられると、身近な幸せを感じられて甘えたくなる。
「珍しい。ベッドの上でしか甘えないのに」
「うるさーい」
「キスで塞いじゃえ」
「へへー」
顔のいいキスが降ってくる。黙って受け止めた。
葵の膝枕は、やさしい。頭に置かれた手は、世界一大事だと優しく撫でる。
しばらくいちゃついた後は、午後はどうしても行きたかった手を繋いでの散歩時間。暑いし、かき氷はどうしても食べたい。駅前のかき氷屋はこう暑いとさすがに長蛇の列を作っていた。
「どうする? 並ぶ?」
「並ぶ。絶対」
「タピオカが乗ったかき氷もあるってさ。食べる?」
「嫌だよ……カエルの卵じゃん……」
列に並ぶ女性が振り返った。手に持つものはお品書きで、ちょうどタピオカのページを開いていた。なんか、ごめんなさい。悪気はないんです。
「ティラミスとイチゴで迷ってるんだけど、どっちがいいと思う?」
「半分こする?」
「いいね、それ」
かき氷を食べたかったのは俺なのに、店に来ると葵の方が子供に戻っている。これで三十歳を超えているのだから、可愛いしか出てこない。ほんとに可愛い。
店内は気温の差が激しく、寒いくらいだった。壁にかけられている温度計は、二十一度を伝えている。
「家でもかき氷作りたいなあ。食感が優しい感じの」
「ガリガリじゃなくね。分かるよ。でも冬はどうせ食べなくなるし、店に来て食べた方が早いよ」
「ん」
スプーンには粉まみれのティラミス味のかき氷。差し出されたスプーンをいつものことだと特に気にせず口にすると、先ほどの女性と目が合った。俺を凝視している。
「ちょっと葵……」
「イチゴちょうだい」
口を開けたまま早くしてと、目が訴えている。こういうときの葵は強固の意思を崩さない。俺が折れるしかないのだ。
「幸せ……次来たときはチーズケーキ味でも頼もうかな」
「タピオカは? 俺にはすすめておいて」
「えー、だってカエルの卵みたいじゃん」
葵は俺のまねをして、半笑いで首を傾げた。隣にいる女性はスプーンを持ったまま固まっている。何度もごめんなさい。悪気はないんです。食べているかき氷が雲に浮かぶ爬虫類の卵に見えて、俺は無言で目を逸らした。
結局食べ足りなかった俺たちはほうじ茶味のかき氷も食べ、ふたりでつついた。
普段は車で通る道も、徒歩だと違う風景が広がっている。小指が絡んだ素肌から熱が伝わり、かき氷で冷えた身体も熱を帯びていく。
「あれ?」
葵が急に止まったものだから、絡まった指が離れた。
「あそこに女の子がいる」
洋風の屋敷の庭に白いワンピースの女の子がじっとしている。こんなに暑いのに微動だにせず、様子がおかしかった。庭で屋敷の二階を眺めているが、カーテンが閉まり人の気配が一切感じられない建物だった。
「入ってみる?」
「人の家の敷地だろ? ダメだって」
「じゃあ呼ぼうか? こんにちはー」
聞こえていないのか、少女は動かない。立ったまま亡くなっているように見えて、背中に悪寒が走った。
「ってかこんなところに建物なんてあったっけ?」
「……………………」
「えー、その顔やめてよっ」
「ほら、普段車で走るからさ、気づかなかったんだよ」
俺と同じフィーリングだ。なんて頼りない。
「全然気づかないよ」
「ちょっと葵……」
失礼します、と葵は柵を押すと、鍵がかかっておらず簡単に開いた。
後を追いかけてしまうのは、探偵の性だ。
近くまで寄ると、少女はようやく俺たちを見上げた。
可愛い、とは言い難い。可愛いのだけれど、喉まで込み上げてきたものを呑み込んだ。
瞳孔や角膜、結膜のへだたりが分からないほど、目が真っ黒だった。
葵は右足を一歩後ろに下げた。俺と同じ気持ちだろう。
少女は屋敷の二階を指差したまま、動かなくなった。
「ここはキミの家?」
「ううん、ちがうよ。しらない」
「知らない人の家なんだ?」
「うん」
「どうしてここにいるの?」
少女は小首を傾け、空を見上げる。
「ともだちがね、なかにいるの」
復唱して聞いていくと、子供は会話しやすい。子供キラーな葵は、将来結婚したいと宣言されたこともある。
「もしかして、勝手に入っちゃったのかなあ」
「……………………」
「表札がないよ。インターホン押してみる?」
「うん」
音は聞こえた。けれど応答がない。二度三度押しても、誰も出なかった。
「あ」
「なに?」
「カーテンが揺れた」
離れたところにいる葵の隣に立ち、俺も二階に目を向ける。
微かだが、揺れているようにも見える。エアコンの風で揺れている程度のものだ。気のせいだと言われれば、そう見えてしまう。
「え……なんだよ……あれ」
「…………行こう」
低めの「行こう」は、感情を抑えているときに出る声だ。
カーテンに赤い染みが滲み、じわじわと広がっていく。勘違いと思いたいが、白に赤であれば見間違いは有り得ない。
それでも、勘違いであってほしいと祈りながらドアを開け、土足で足を踏み入れた。
長い廊下が続く中、すぐ目の前に階段がある。急な階段は子供が上るには大変そうだ。
二階は狭い通路と扉が五部屋。上がってすぐに左奥の部屋に行き、葵は勢いのままに開けた。
閉まっていたはずの窓は開き、カーテンが外で泳いでいる。窓のすぐ側で、女の子が泣いていた。
「大丈夫? 怪我はない?」
淡いピンクのワンピースを着た少女だ。泣きすぎたのか、顔が真っ赤に腫れている。血も出ていないし、痛みで泣いているわけではないようだ。
少女は身体を大きくびくつかせていたが、葵がしゃがんで頭を撫でると、徐々に落ち着きを取り戻していった。
「お兄さんたちね、迷子の子がいるって聞いたから来たんだ。ここの家の子?」
「……ちがう。家、わかんない」
「一度外に出ない? 分かる人呼んであげるから」
「……………………」
少女は頑なにその場を離れようとしなかった。
下手に連れ回さない方がいいと判断し、俺は警察に通報した。少女が知らない人の家に紛れ込んで泣いている、迷子かもしれないと、曖昧に伝え、余計なことは口走らないようにした。
通報からおよそ二十分後、その場を離れられないと窓から手を振って警察を呼び、少女を彼らに引き渡そうとしたのだが。
「………………いや」
少女は葵の袖を掴み、首を横に振るばかりだ。
「……………………」
「ちょっと、そんな目で見る?」
「……子供キラーなのは相変わらずだな」
「俺が結婚したいと思ってるのは一人だけだって」
「わざわざ通報ありがとうございます。それで、あなた方の連絡先を知りたいのですが……」
葵は懐から名刺を出し、警察官に渡した。おや、と眉を曲げ、俺と葵を交互に見る。
「探偵事務所の方だったんですか」
「お困りの際は、うちの事務所にぜひご相談を。一応、手帳に住所と名前も書きましょうか」
「お願いします」
「それで、こちらのお家の方は……?」
「んー…………」
警察官はペンの動きをじっと見ては、質問に質問を被せてきた。
どこから来たの、この子との関係は、ふたりで探偵しているの、など。疑われても仕方ない。隠すことはないので、一つ一つ丁寧に答えていった。
「ははあ、白いワンピースの子が?」
「ここに友達が入っていってしまったと言っていたので、それで、」
「私たちが代わりに捜しに入ったんです。探偵の性分といいますか、いても立ってもいられなくて。勝手に土足で入ったことは謝罪したいのですが、家主の方もいらっしゃらないようで、どうしたらいいのか」
葵は俺の声に被せて語り出した。余計なことは言うな、と言われている気がして、黙って連絡先と名前を書いていく。
「家主の方は捜索しているから」
「捜索?」
「ご家族の方から捜索願が出されているんだよ。それより、どうやって入ったの? 窓は開いているし」
「ドアなら鍵はかかっていませんでしたよ。そもそもこの子が先に入ったんだし」
この子と呼ばれた少女はつんと横を向き、けれどしっかり葵の手は離さない。
「お嬢ちゃんはどこから来たの?」
「このお兄ちゃん、うそついてる」
「え?」
変な汗が背中を濡らす。後ろで待機している警察官の目が光った。
「嘘? どういうことだい?」
「ともだち、いないもん。ここきたばっかりだし」
「もしかして、引っ越しして来たばかりなのかな?」
少女は小さく頷いた。
「うみからきた」
「海……? 北海道とかかな?」
背負っている小さなリュックサックには、マリモのキーホルダーがついている。
「本当に、白いワンピースの子はいたの?」
ああ……結局こうなるのか。
土足で上がる前に頭の中で想定していた最悪の状況と一致した。それより悪いのかもしれない。
せめて素性が謎な男をかばわなければと、強く誓った。
テーブルに紙袋を置き、冷蔵庫からはコーラを出して氷を入れたグラスをテーブルに並べる。
ほぼ同時にハンバーガーにかぶりついた。いつからか、疲れて帰ってきた日の夕食は、チェーン店のハンバーガーが暗黙の了解となっていた。
「……美味しい」
「だね」
「疲れたときは肉と炭水化物だよね」
「うん、分かる。最強。もっとコーラ飲む?」
「飲む」
葵は二杯目のコーラを二つのグラスに注ぐ。爽やかな笑顔で本心を隠すのが上手いが、今日は疲労の色が拭えない。
警察官に事情聴取を受けてかれこれ数時間。お互いに何度も同じ質問をされ、いい加減飽き飽きしていても終わりが見えず、ようやく解放されたときにはすでに日は沈んでいた。
「結局、血のついたカーテンはなんだったんだろ」
俺も葵も確かに見た。真ん中から四方八方に広がり、赤黒く染まるカーテンを見て、土足で家主のいない家に上がり込んだのだ。なのに、カーテンは染み一つついていない。おまけに誰かが開けた窓かも分からない。高さがあるため、少女が開けるには難しい。そもそも開ける意味がない。
「家の人は行方不明らしいしね。世の中不思議だらけだね」
のほほんとポテトに手を伸ばしているが、不思議人代表は間違いなく葵だろう。
俺の前から消えた後、数年後に「すべてが解決した」と晴れ晴れしく現れた葵は、これ以上話したくないと寂しげに訴えた。俺もつつき回すようなことはせず、同棲生活をスタートさせた。今のところは葵に危害をくわえるような人もいないし、ごく一般的な生活を送っている。
遠回りした幸せだけれど、毎日増えていく幸せを大事にしたい。
こちらが申し訳ないくらいに頭を下げ、女性は大事そうにカゴを抱きかかえた。
女性の名前は綾川さん。前にストーカーに追われた過去があり、心も身体も疲労が溜まってしばらく入退院を繰り返していた。これではいけないと新しい人生に挑戦した結果、今は薬を飲まなくても外を歩けるようになったという。大きな一歩だ。解決に導いた俺も、鼻が高い。
「この子も元気に帰ってきました。何度、佐藤さんにお世話になったか……」
この子と言われた猫はつまらなそうに小さく鳴いた。大冒険が見知らぬ男に捕まえられて、終わりを迎えてしまったのだ。猫の立場からすれば、たまったものじゃないだろう。
綾川さんの挑戦というのは、猫を飼うことだ。昔から好きで、けれど家族に猫アレルギーの人がいたために、なかなか機会に恵まれなかったのだそう。念願の一人暮らしを始めて、ストーカー事件も一応解決を迎え、引っ越しを機に猫を飼い始めた。仕事帰りに玄関を開けると、隙をついて逃げてしまったと、探偵事務所に相談があったのだ。
三日間で見つけられたのは運がいい。かつお節が好物だというのでペットショップで購入し、猫のたまり場をうろうろしていると、すぐに食いついた白黒の猫がいた。抱き上げてもそれよりかつお節を寄越せという姿勢を崩さなかった猫は、紛れもなく綾川さんの飼い猫だと確信を持った。
「よければ、こちらをどうぞ。お礼です。ようかんなので、冷やして食べて下さい」
「嬉しいです。甘いものはすごく好きなんですよ」
一番好きなのは相方だとは言わず、有り難く受け取った。事前まで冷蔵庫に入れていたのか、紙袋もひんやりしている。
事務所を施錠し、ビルの二階に位置するため、エレベーターを使わずに階段を降りる。ちょっとでも体力が向上すればいいと祈りを込めて。
車に乗ると、メールを送った。
──今日は卵安売りの日だから買っていくけど、家になかったよね?
──はい。
うんではなく、はい、だ。なんだか嫌な予感がする。
駅前のスーパーでお一人様ひとパックまでの卵と、豚肉。今日は生姜焼きが食べたい。キャベツはある。溶き卵入りのみそ汁も作りたい。
適当に安い野菜を買えば、野菜炒めでもなんでも作れる。うちでは肉の消費量が多いので、意識して野菜を買うようにしている。
買い物を終えてマンションに向かうと、ずっと家にいたのか隣の車に走らせた跡がない。ビニール袋と紙袋を抱えて家に鍵を差し込むと、隙間から冷たい風が身体を冷やす。
廊下の電気は消えている。風呂場の電気はついていて、シャワーの音が聞こえた。ただいまと挨拶してもよかったが、引きずり込まれるのがオチなので見なかったことにしよう。蛇のように身体に巻きつく腕は、絶対に離そうとしない。今は八月。熱風と太陽を浴びた身体は、欲より冷たいサイダーを欲している。
冷蔵庫に材料をしまおうと扉を開けると、変な声が出てしまった。
「もう! なんだよこれ」
「あ、おかえりー」
やらかした張本人はへらりと笑い、俺の頬と唇にキスを落とす。
「俺メール送ったよね? 卵あるかどうかって。なんで冷蔵庫に二パックも入ってんのさっ」
「あー、うん。あれね。ごめん、寝起きなんだ。昼寝してた」
確かに寝起きの声だ。でもそういう問題じゃない。
「明日の朝はオムレツ確定。今日の夕食は豚の生姜焼きにしようと思ったけど、」
「やった」
「止める」
「ええ……」
「エセ親子丼にする」
「おいしそー」
「風呂入ってくるから、葵が材料切ってて。豚肉を細くして、玉ねぎも切る。鶏肉の代わりに豚肉を使うから」
「はーい」
探偵事務所は今日は俺ひとりで、明日はふたり一緒に休みだ。今日葵を休みにしたのは、引っ越しの荷解きのためだ。今まで狭いアパートでふたりで暮らしていたため、そろそろ広い場所を選ぼうと、事務所に近いマンションを選んだ。引っ越しをしたのはいいが、今までの葵を考えていなかった。
高校生のときも、探偵事務所で先輩後輩として出会ったときも、葵は生活力が皆無だった。何にもない部屋にほとんど使われていないキッチン。新居の個室に布団を敷いてはい終了なものだから、頭を抱えた。
引っ越し祝いにベッドをプレゼントしたいと言うと、葵は真剣に悩んでくれた。条件としては、ふたりで寝られる大きさ、下に響かない、音を吸収してくれる。それを店員に真剣に伝え詰め寄るので、俺はできるだけ距離を離れて他人のふりをしていた。
シャワーを終えると、待ちかまえていた葵は部屋にきてきてと子供の笑みで腕を引っ張る。
部屋についていくと、布団の敷いてあった場所に大きなベッドがある。うまく組み立てられたようだ。一日がかりだったろうし、疲れて昼寝もしたくなるだろう。
えらいえらいと頭を撫でると、もっとしてと押しつけてくる。ああ、かわいい。こんな可愛い人が僕より年上で、甘えたがりで、自慢の恋人なんだ。
キッチンには、材料を切っていてくれるだけでよかったのに、すでにどんぶりが出来上がっている。それとインスタントのお吸い物。松茸の良い香りがする。
俺の飲みたかったサイダーも用意してくれ、一緒に乾杯した。
「綾川さんの猫見つかったよ」
「よかったね。俺が近寄ると全猫が逃げるんだよねえ……なんでだろ?」
「得体の知れない生き物に見えたんじゃない? 過去遡ったりしてたし」
「あはは、言えてる」
「これからは俺が動物担当かなあ」
「そうだね。俺が餌買ってきたりネットで野良猫がたむろしている場所を調べる。猫を見つけたらだっこはリンの役目」
動物に嫌われるわけではない。あの孤島に行ったとき、少なくとも狐には嫌われていなかった。狐だけに好かれるのか、猫だけに嫌われるのかまだはっきりしない。
片づけは葵が担当して、俺は寝具を整えた。今日は誰かさんのせいで寝坊してしまい、布団を蹴ったまま出社したのだ。溢れ出たゴミ箱のティッシュを押し込み、空になりそうな箱の隣に新しくティッシュ箱を出した。
「用意がいいね」
「今日はしないよ」
「明日休みなのに?」
「……明日はふたりで散歩するって約束じゃん」
こっそり手を繋いで散歩したいと、俺のちょっとしたわがまま。
葵の可愛いところは、時折幼児返りをするところだ。おっぱい吸いたいと言い出し、パジャマのボタンを外しにかかる。こうなれば何を言っても通じないので、いつも好きにさせている。
「おっぱいだけだからね」
「今のいい……もう一回言って?」
「……おっぱい吸っていいよ?」
「ごめん、止まらない」
結局こうなるのだ。
分かっていて乗ってしまう俺も俺だから、似た者同士かもしれない。
朝はオムレツとソーセージ、キャベツの千切りサラダとパンを食べ、まったりとした午前を過ごした。
最近は立て続けに依頼が入り、忙しい日々を送っていた。こうしてソファーに座ってお茶を飲む時間が与えられると、身近な幸せを感じられて甘えたくなる。
「珍しい。ベッドの上でしか甘えないのに」
「うるさーい」
「キスで塞いじゃえ」
「へへー」
顔のいいキスが降ってくる。黙って受け止めた。
葵の膝枕は、やさしい。頭に置かれた手は、世界一大事だと優しく撫でる。
しばらくいちゃついた後は、午後はどうしても行きたかった手を繋いでの散歩時間。暑いし、かき氷はどうしても食べたい。駅前のかき氷屋はこう暑いとさすがに長蛇の列を作っていた。
「どうする? 並ぶ?」
「並ぶ。絶対」
「タピオカが乗ったかき氷もあるってさ。食べる?」
「嫌だよ……カエルの卵じゃん……」
列に並ぶ女性が振り返った。手に持つものはお品書きで、ちょうどタピオカのページを開いていた。なんか、ごめんなさい。悪気はないんです。
「ティラミスとイチゴで迷ってるんだけど、どっちがいいと思う?」
「半分こする?」
「いいね、それ」
かき氷を食べたかったのは俺なのに、店に来ると葵の方が子供に戻っている。これで三十歳を超えているのだから、可愛いしか出てこない。ほんとに可愛い。
店内は気温の差が激しく、寒いくらいだった。壁にかけられている温度計は、二十一度を伝えている。
「家でもかき氷作りたいなあ。食感が優しい感じの」
「ガリガリじゃなくね。分かるよ。でも冬はどうせ食べなくなるし、店に来て食べた方が早いよ」
「ん」
スプーンには粉まみれのティラミス味のかき氷。差し出されたスプーンをいつものことだと特に気にせず口にすると、先ほどの女性と目が合った。俺を凝視している。
「ちょっと葵……」
「イチゴちょうだい」
口を開けたまま早くしてと、目が訴えている。こういうときの葵は強固の意思を崩さない。俺が折れるしかないのだ。
「幸せ……次来たときはチーズケーキ味でも頼もうかな」
「タピオカは? 俺にはすすめておいて」
「えー、だってカエルの卵みたいじゃん」
葵は俺のまねをして、半笑いで首を傾げた。隣にいる女性はスプーンを持ったまま固まっている。何度もごめんなさい。悪気はないんです。食べているかき氷が雲に浮かぶ爬虫類の卵に見えて、俺は無言で目を逸らした。
結局食べ足りなかった俺たちはほうじ茶味のかき氷も食べ、ふたりでつついた。
普段は車で通る道も、徒歩だと違う風景が広がっている。小指が絡んだ素肌から熱が伝わり、かき氷で冷えた身体も熱を帯びていく。
「あれ?」
葵が急に止まったものだから、絡まった指が離れた。
「あそこに女の子がいる」
洋風の屋敷の庭に白いワンピースの女の子がじっとしている。こんなに暑いのに微動だにせず、様子がおかしかった。庭で屋敷の二階を眺めているが、カーテンが閉まり人の気配が一切感じられない建物だった。
「入ってみる?」
「人の家の敷地だろ? ダメだって」
「じゃあ呼ぼうか? こんにちはー」
聞こえていないのか、少女は動かない。立ったまま亡くなっているように見えて、背中に悪寒が走った。
「ってかこんなところに建物なんてあったっけ?」
「……………………」
「えー、その顔やめてよっ」
「ほら、普段車で走るからさ、気づかなかったんだよ」
俺と同じフィーリングだ。なんて頼りない。
「全然気づかないよ」
「ちょっと葵……」
失礼します、と葵は柵を押すと、鍵がかかっておらず簡単に開いた。
後を追いかけてしまうのは、探偵の性だ。
近くまで寄ると、少女はようやく俺たちを見上げた。
可愛い、とは言い難い。可愛いのだけれど、喉まで込み上げてきたものを呑み込んだ。
瞳孔や角膜、結膜のへだたりが分からないほど、目が真っ黒だった。
葵は右足を一歩後ろに下げた。俺と同じ気持ちだろう。
少女は屋敷の二階を指差したまま、動かなくなった。
「ここはキミの家?」
「ううん、ちがうよ。しらない」
「知らない人の家なんだ?」
「うん」
「どうしてここにいるの?」
少女は小首を傾け、空を見上げる。
「ともだちがね、なかにいるの」
復唱して聞いていくと、子供は会話しやすい。子供キラーな葵は、将来結婚したいと宣言されたこともある。
「もしかして、勝手に入っちゃったのかなあ」
「……………………」
「表札がないよ。インターホン押してみる?」
「うん」
音は聞こえた。けれど応答がない。二度三度押しても、誰も出なかった。
「あ」
「なに?」
「カーテンが揺れた」
離れたところにいる葵の隣に立ち、俺も二階に目を向ける。
微かだが、揺れているようにも見える。エアコンの風で揺れている程度のものだ。気のせいだと言われれば、そう見えてしまう。
「え……なんだよ……あれ」
「…………行こう」
低めの「行こう」は、感情を抑えているときに出る声だ。
カーテンに赤い染みが滲み、じわじわと広がっていく。勘違いと思いたいが、白に赤であれば見間違いは有り得ない。
それでも、勘違いであってほしいと祈りながらドアを開け、土足で足を踏み入れた。
長い廊下が続く中、すぐ目の前に階段がある。急な階段は子供が上るには大変そうだ。
二階は狭い通路と扉が五部屋。上がってすぐに左奥の部屋に行き、葵は勢いのままに開けた。
閉まっていたはずの窓は開き、カーテンが外で泳いでいる。窓のすぐ側で、女の子が泣いていた。
「大丈夫? 怪我はない?」
淡いピンクのワンピースを着た少女だ。泣きすぎたのか、顔が真っ赤に腫れている。血も出ていないし、痛みで泣いているわけではないようだ。
少女は身体を大きくびくつかせていたが、葵がしゃがんで頭を撫でると、徐々に落ち着きを取り戻していった。
「お兄さんたちね、迷子の子がいるって聞いたから来たんだ。ここの家の子?」
「……ちがう。家、わかんない」
「一度外に出ない? 分かる人呼んであげるから」
「……………………」
少女は頑なにその場を離れようとしなかった。
下手に連れ回さない方がいいと判断し、俺は警察に通報した。少女が知らない人の家に紛れ込んで泣いている、迷子かもしれないと、曖昧に伝え、余計なことは口走らないようにした。
通報からおよそ二十分後、その場を離れられないと窓から手を振って警察を呼び、少女を彼らに引き渡そうとしたのだが。
「………………いや」
少女は葵の袖を掴み、首を横に振るばかりだ。
「……………………」
「ちょっと、そんな目で見る?」
「……子供キラーなのは相変わらずだな」
「俺が結婚したいと思ってるのは一人だけだって」
「わざわざ通報ありがとうございます。それで、あなた方の連絡先を知りたいのですが……」
葵は懐から名刺を出し、警察官に渡した。おや、と眉を曲げ、俺と葵を交互に見る。
「探偵事務所の方だったんですか」
「お困りの際は、うちの事務所にぜひご相談を。一応、手帳に住所と名前も書きましょうか」
「お願いします」
「それで、こちらのお家の方は……?」
「んー…………」
警察官はペンの動きをじっと見ては、質問に質問を被せてきた。
どこから来たの、この子との関係は、ふたりで探偵しているの、など。疑われても仕方ない。隠すことはないので、一つ一つ丁寧に答えていった。
「ははあ、白いワンピースの子が?」
「ここに友達が入っていってしまったと言っていたので、それで、」
「私たちが代わりに捜しに入ったんです。探偵の性分といいますか、いても立ってもいられなくて。勝手に土足で入ったことは謝罪したいのですが、家主の方もいらっしゃらないようで、どうしたらいいのか」
葵は俺の声に被せて語り出した。余計なことは言うな、と言われている気がして、黙って連絡先と名前を書いていく。
「家主の方は捜索しているから」
「捜索?」
「ご家族の方から捜索願が出されているんだよ。それより、どうやって入ったの? 窓は開いているし」
「ドアなら鍵はかかっていませんでしたよ。そもそもこの子が先に入ったんだし」
この子と呼ばれた少女はつんと横を向き、けれどしっかり葵の手は離さない。
「お嬢ちゃんはどこから来たの?」
「このお兄ちゃん、うそついてる」
「え?」
変な汗が背中を濡らす。後ろで待機している警察官の目が光った。
「嘘? どういうことだい?」
「ともだち、いないもん。ここきたばっかりだし」
「もしかして、引っ越しして来たばかりなのかな?」
少女は小さく頷いた。
「うみからきた」
「海……? 北海道とかかな?」
背負っている小さなリュックサックには、マリモのキーホルダーがついている。
「本当に、白いワンピースの子はいたの?」
ああ……結局こうなるのか。
土足で上がる前に頭の中で想定していた最悪の状況と一致した。それより悪いのかもしれない。
せめて素性が謎な男をかばわなければと、強く誓った。
テーブルに紙袋を置き、冷蔵庫からはコーラを出して氷を入れたグラスをテーブルに並べる。
ほぼ同時にハンバーガーにかぶりついた。いつからか、疲れて帰ってきた日の夕食は、チェーン店のハンバーガーが暗黙の了解となっていた。
「……美味しい」
「だね」
「疲れたときは肉と炭水化物だよね」
「うん、分かる。最強。もっとコーラ飲む?」
「飲む」
葵は二杯目のコーラを二つのグラスに注ぐ。爽やかな笑顔で本心を隠すのが上手いが、今日は疲労の色が拭えない。
警察官に事情聴取を受けてかれこれ数時間。お互いに何度も同じ質問をされ、いい加減飽き飽きしていても終わりが見えず、ようやく解放されたときにはすでに日は沈んでいた。
「結局、血のついたカーテンはなんだったんだろ」
俺も葵も確かに見た。真ん中から四方八方に広がり、赤黒く染まるカーテンを見て、土足で家主のいない家に上がり込んだのだ。なのに、カーテンは染み一つついていない。おまけに誰かが開けた窓かも分からない。高さがあるため、少女が開けるには難しい。そもそも開ける意味がない。
「家の人は行方不明らしいしね。世の中不思議だらけだね」
のほほんとポテトに手を伸ばしているが、不思議人代表は間違いなく葵だろう。
俺の前から消えた後、数年後に「すべてが解決した」と晴れ晴れしく現れた葵は、これ以上話したくないと寂しげに訴えた。俺もつつき回すようなことはせず、同棲生活をスタートさせた。今のところは葵に危害をくわえるような人もいないし、ごく一般的な生活を送っている。
遠回りした幸せだけれど、毎日増えていく幸せを大事にしたい。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

宵にまぎれて兎は回る
宇土為名
BL
高校3年の春、同級生の名取に告白した冬だったが名取にはあっさりと冗談だったことにされてしまう。それを否定することもなく卒業し手以来、冬は親友だった名取とは距離を置こうと一度も連絡を取らなかった。そして8年後、勤めている会社の取引先で転勤してきた名取と8年ぶりに再会を果たす。再会してすぐ名取は自身の結婚式に出席してくれと冬に頼んできた。はじめは断るつもりだった冬だが、名取の願いには弱く結局引き受けてしまう。そして式当日、幸せに溢れた雰囲気に疲れてしまった冬は式場の中庭で避難するように休憩した。いまだに思いを断ち切れていない自分の情けなさを反省していると、そこで別の式に出席している男と出会い…

【全10作】BLショートショート・短編集
雨樋雫
BL
文字数が少なめのちょこっとしたストーリーはこちらにまとめることにしました。
1話完結のショートショートです。
あからさまなものはありませんが、若干の性的な関係を示唆する表現も含まれます。予めご理解お願いします。

仮面の王子と優雅な従者
emanon
BL
国土は小さいながらも豊かな国、ライデン王国。
平和なこの国の第一王子は、人前に出る時は必ず仮面を付けている。
おまけに病弱で無能、醜男と専らの噂だ。
しかしそれは世を忍ぶ仮の姿だった──。
これは仮面の王子とその従者が暗躍する物語。
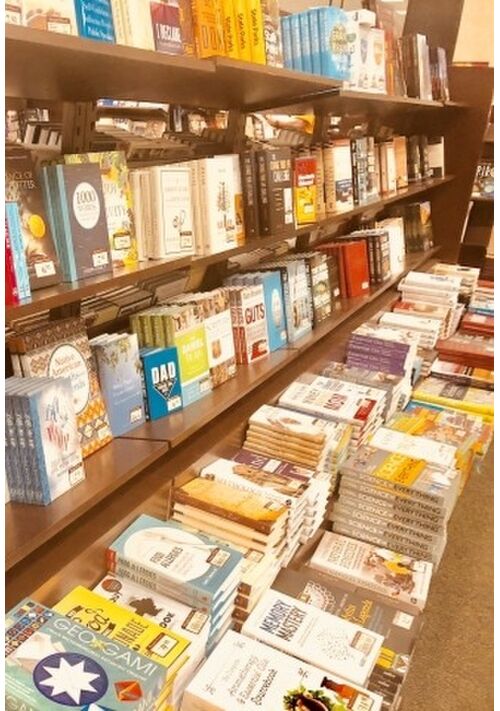
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)


秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

人気作家は売り専男子を抱き枕として独占したい
白妙スイ@1/9新刊発売
BL
八架 深都は好奇心から売り専のバイトをしている大学生。
ある日、不眠症の小説家・秋木 晴士から指名が入る。
秋木の家で深都はもこもこの部屋着を着せられて、抱きもせず添い寝させられる。
戸惑った深都だったが、秋木は気に入ったと何度も指名してくるようになって……。
●八架 深都(はちか みと)
20歳、大学2年生
好奇心旺盛な性格
●秋木 晴士(あきぎ せいじ)
26歳、小説家
重度の不眠症らしいが……?
※性的描写が含まれます
完結いたしました!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















