2 / 77
第一章:当主と花嫁の出会い
2:本当の花嫁
しおりを挟む
顔をあげることができずにいると、不穏なざわめきとともに足音が近づいてくる。
「なぜおまえが招待客にまぎれている?」
頭上から響く声に、葛葉は身をこわばらせた。
気配がちかい。
初対面の可畏に声をかけられるとは思ってもいなかった。
まったく状況が飲みこめないが、ひたすら目をあわせないようにうつむいたまま、何とかこの場をやりすごそうと試みる。
「わたしは特務科にかよう、倉橋葛葉と申します。本日は紅葉様とあなたの婚約を祝福するために参りました」
「婚約を祝福? おまえが?」
凛とひびく低い声が、わずかに苛立ちを含んでいる。
葛葉はなにかとてつもない粗相をしてしまったのかと身をすくめた。
「……どういうことだ」
「え?」
冷たい声を聞いたと同時に、可畏が強引に葛葉の左腕をつかんだ。祖母に譲ってもらった数珠をみて、嘲るようにわらう。
「これはなんだ?」
「は、はなしてください!」
可畏は葛葉の腕をつかんだまま、紅葉の前まで歩いていく。引きずられるように、葛葉も二人の前にひきだされてしまう。
「倉橋侯爵の御令嬢。これはどういうことなのか説明していただけるのか?」
可畏の有無を言わせない詰問に、紅葉は答えない。ただ青ざめた顔で立ち尽くしているだけだった。
けれど、その紅葉の狼狽える様子が、可畏にとっては答えになったようである。
「どうやらご令嬢殿は自分が偽物であることをわかっていらっしゃるようだ」
可畏は冷然と微笑する。紅葉の隣に立つ父親も顔色を失っていた。
「倉橋侯爵。これは御門家への宣戦布告か?」
「まさか! これには理由が!」
可畏は紅葉と葛葉を見くらべると、吐き捨てるようにわらった。
「……とんだ茶番だな」
腹に据えかねるといいたげな、低いささやき。葛葉は突然の成りゆきに、ただ震えるだけだった。
何が起きているのかわからないが、何かが可畏の逆鱗に触れたことはまちがいがない。
(どうしよう)
葛葉の在籍する特務科は、軍の特務部とつながっている。特務部を率いる可畏を怒らせて、お咎めなしということはありえないはずだ。
特務科の席を抹消され、退学に追いこまれたら、葛葉は路頭にまよってしまう。
(もし寄宿舎を追いだされるようなことになったら、どうしよう)
最悪の状況を思い描いてしまい、血の気のひく思いで可畏を仰ぐと、ふたたび目があった。葛葉はすぐに目をそらしたが、赤い瞳に一瞬労るような光がみえた。
可畏は葛葉の手をとると、壮麗な洋館に集った者へ向けて声高らかに宣言する。
「すこし手違いがあったようだが、私の花嫁は彼女だ」
洋館にひびく喧騒が、ひときわ大きなうねりとなって葛葉をつつんだ。
可畏の声がざわめきを切り裂くように、凛とひびく。
「どうか皆様も誤解なきように」
葛葉の気持ちをおき去りに、彼はためらいもなく続ける。
「では、改めて私の婚約者を紹介したい。倉橋葛葉です」
名を語られて、葛葉は反射的に首をふった。
「待ってください! 違います! 何かのまちがいです!」
葛葉は声のかぎりに訴える。
「わたしは紅葉様と御門家のご当主様の婚約を祝福にきた、特務科の一生徒にすぎません!」
「それが間違いだったと説明している」
「でも……」
葛葉はぎゅっと左腕の数珠に右手をそえる。
「わ、わたしはとんでもない不幸体質なんです! だから、わたしに関わると、あなたも不幸になるかもしれない!」
「何を言い出すかと思えば……」
可畏は険しい視線で、葛葉の腕の数珠をにらんだ。
「今すぐ、その石を外せ」
「駄目です! これはお守りです!」
「そんなものは守りでも何でもない。おまえが拒むなら、私が外してやる」
再び可畏に左腕をつかまれると、突然ぼうっと炎があがった。見たこともない、海洋のような青い炎。腕が数珠ごと碧くうねる炎に包まれてしまう。
葛葉は悲鳴をあげて逃れようとしたが、体が動かない。
「やめてください! 離して!」
目の前であがった火柱は、異能の炎。
燃え盛る碧い炎に包まれているが、腕が焼け落ちる気配はなかった。熱さもなくただ温かい。
やがて炎が光となって、葛葉にも正視できないきらめきが広がった。
「やめてっ……、数珠が――」
光の向こうがわで、数珠がはずれる気配がする。
パチンと、何かがはじける音がした。
「あ……」
途端に、葛葉の身をおそった暗い衝撃。
ごうごうと、一面が赤い炎につつまれる錯覚。
すべてを焼き尽くした炎。
「ああ!」
突如、脳裏に蘇った絶望で何もみえなくなる。
「っ……!」
ひきつるような細い悲鳴が、喉をついてでた。葛葉はなりふりかまわず、声の限りにさけぶ。
(おばあちゃん!)
焼け落ちていく古い家屋の向こうがわに消えた人影。脳裏を蹂躙する赤い記憶。
「しっかりしろ!」
誰かが自分を引きもどそうとして、腕をつかんでいる。
振り向こうとすると、ぐらりと目の前の光景がぶれた。記憶の炎がうしなわれ、洋館の広間が戻ってくる。天井で輝く多灯式照明の光がまぶしい。
昔の記憶をなぞっていたのだと理解した瞬間、葛葉の目元にじわりと熱がこもっていく。
(かならず、……かならず見つけだすから)
涙がこぼれ落ちると、すうっと視野が狭窄していく。
視界に影がながれこみ、きざみこまれた火災の記憶が遮断された。すべての残像が、闇にのまれて暗転する。
深淵に引きこまれるように、葛葉は意識をうしなった。
「なぜおまえが招待客にまぎれている?」
頭上から響く声に、葛葉は身をこわばらせた。
気配がちかい。
初対面の可畏に声をかけられるとは思ってもいなかった。
まったく状況が飲みこめないが、ひたすら目をあわせないようにうつむいたまま、何とかこの場をやりすごそうと試みる。
「わたしは特務科にかよう、倉橋葛葉と申します。本日は紅葉様とあなたの婚約を祝福するために参りました」
「婚約を祝福? おまえが?」
凛とひびく低い声が、わずかに苛立ちを含んでいる。
葛葉はなにかとてつもない粗相をしてしまったのかと身をすくめた。
「……どういうことだ」
「え?」
冷たい声を聞いたと同時に、可畏が強引に葛葉の左腕をつかんだ。祖母に譲ってもらった数珠をみて、嘲るようにわらう。
「これはなんだ?」
「は、はなしてください!」
可畏は葛葉の腕をつかんだまま、紅葉の前まで歩いていく。引きずられるように、葛葉も二人の前にひきだされてしまう。
「倉橋侯爵の御令嬢。これはどういうことなのか説明していただけるのか?」
可畏の有無を言わせない詰問に、紅葉は答えない。ただ青ざめた顔で立ち尽くしているだけだった。
けれど、その紅葉の狼狽える様子が、可畏にとっては答えになったようである。
「どうやらご令嬢殿は自分が偽物であることをわかっていらっしゃるようだ」
可畏は冷然と微笑する。紅葉の隣に立つ父親も顔色を失っていた。
「倉橋侯爵。これは御門家への宣戦布告か?」
「まさか! これには理由が!」
可畏は紅葉と葛葉を見くらべると、吐き捨てるようにわらった。
「……とんだ茶番だな」
腹に据えかねるといいたげな、低いささやき。葛葉は突然の成りゆきに、ただ震えるだけだった。
何が起きているのかわからないが、何かが可畏の逆鱗に触れたことはまちがいがない。
(どうしよう)
葛葉の在籍する特務科は、軍の特務部とつながっている。特務部を率いる可畏を怒らせて、お咎めなしということはありえないはずだ。
特務科の席を抹消され、退学に追いこまれたら、葛葉は路頭にまよってしまう。
(もし寄宿舎を追いだされるようなことになったら、どうしよう)
最悪の状況を思い描いてしまい、血の気のひく思いで可畏を仰ぐと、ふたたび目があった。葛葉はすぐに目をそらしたが、赤い瞳に一瞬労るような光がみえた。
可畏は葛葉の手をとると、壮麗な洋館に集った者へ向けて声高らかに宣言する。
「すこし手違いがあったようだが、私の花嫁は彼女だ」
洋館にひびく喧騒が、ひときわ大きなうねりとなって葛葉をつつんだ。
可畏の声がざわめきを切り裂くように、凛とひびく。
「どうか皆様も誤解なきように」
葛葉の気持ちをおき去りに、彼はためらいもなく続ける。
「では、改めて私の婚約者を紹介したい。倉橋葛葉です」
名を語られて、葛葉は反射的に首をふった。
「待ってください! 違います! 何かのまちがいです!」
葛葉は声のかぎりに訴える。
「わたしは紅葉様と御門家のご当主様の婚約を祝福にきた、特務科の一生徒にすぎません!」
「それが間違いだったと説明している」
「でも……」
葛葉はぎゅっと左腕の数珠に右手をそえる。
「わ、わたしはとんでもない不幸体質なんです! だから、わたしに関わると、あなたも不幸になるかもしれない!」
「何を言い出すかと思えば……」
可畏は険しい視線で、葛葉の腕の数珠をにらんだ。
「今すぐ、その石を外せ」
「駄目です! これはお守りです!」
「そんなものは守りでも何でもない。おまえが拒むなら、私が外してやる」
再び可畏に左腕をつかまれると、突然ぼうっと炎があがった。見たこともない、海洋のような青い炎。腕が数珠ごと碧くうねる炎に包まれてしまう。
葛葉は悲鳴をあげて逃れようとしたが、体が動かない。
「やめてください! 離して!」
目の前であがった火柱は、異能の炎。
燃え盛る碧い炎に包まれているが、腕が焼け落ちる気配はなかった。熱さもなくただ温かい。
やがて炎が光となって、葛葉にも正視できないきらめきが広がった。
「やめてっ……、数珠が――」
光の向こうがわで、数珠がはずれる気配がする。
パチンと、何かがはじける音がした。
「あ……」
途端に、葛葉の身をおそった暗い衝撃。
ごうごうと、一面が赤い炎につつまれる錯覚。
すべてを焼き尽くした炎。
「ああ!」
突如、脳裏に蘇った絶望で何もみえなくなる。
「っ……!」
ひきつるような細い悲鳴が、喉をついてでた。葛葉はなりふりかまわず、声の限りにさけぶ。
(おばあちゃん!)
焼け落ちていく古い家屋の向こうがわに消えた人影。脳裏を蹂躙する赤い記憶。
「しっかりしろ!」
誰かが自分を引きもどそうとして、腕をつかんでいる。
振り向こうとすると、ぐらりと目の前の光景がぶれた。記憶の炎がうしなわれ、洋館の広間が戻ってくる。天井で輝く多灯式照明の光がまぶしい。
昔の記憶をなぞっていたのだと理解した瞬間、葛葉の目元にじわりと熱がこもっていく。
(かならず、……かならず見つけだすから)
涙がこぼれ落ちると、すうっと視野が狭窄していく。
視界に影がながれこみ、きざみこまれた火災の記憶が遮断された。すべての残像が、闇にのまれて暗転する。
深淵に引きこまれるように、葛葉は意識をうしなった。
1
あなたにおすすめの小説

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

後宮の偽花妃 国を追われた巫女見習いは宦官になる
gari@七柚カリン
キャラ文芸
旧題:国を追われた巫女見習いは、隣国の後宮で二重に花開く
☆4月上旬に書籍発売です。たくさんの応援をありがとうございました!☆ 植物を慈しむ巫女見習いの凛月には、二つの秘密がある。それは、『植物の心がわかること』『見目が変化すること』。
そんな凛月は、次期巫女を侮辱した罪を着せられ国外追放されてしまう。
心機一転、紹介状を手に向かったのは隣国の都。そこで偶然知り合ったのは、高官の峰風だった。
峰風の取次ぎで紹介先の人物との対面を果たすが、提案されたのは後宮内での二つの仕事。ある時は引きこもり後宮妃(欣怡)として巫女の務めを果たし、またある時は、少年宦官(子墨)として庭園管理の仕事をする、忙しくも楽しい二重生活が始まった。
仕事中に秘密の能力を活かし活躍したことで、子墨は女嫌いの峰風の助手に抜擢される。女であること・巫女であることを隠しつつ助手の仕事に邁進するが、これがきっかけとなり、宮廷内の様々な騒動に巻き込まれていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。
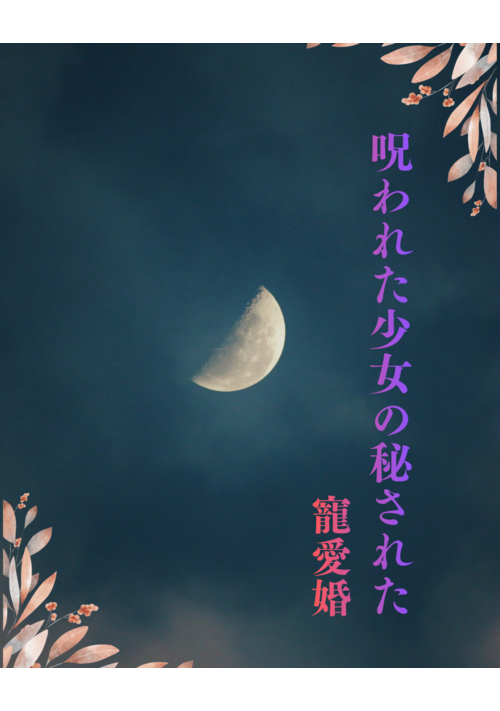
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















