あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m
✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。
【あらすじ】
神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!
そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!
事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!
カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!
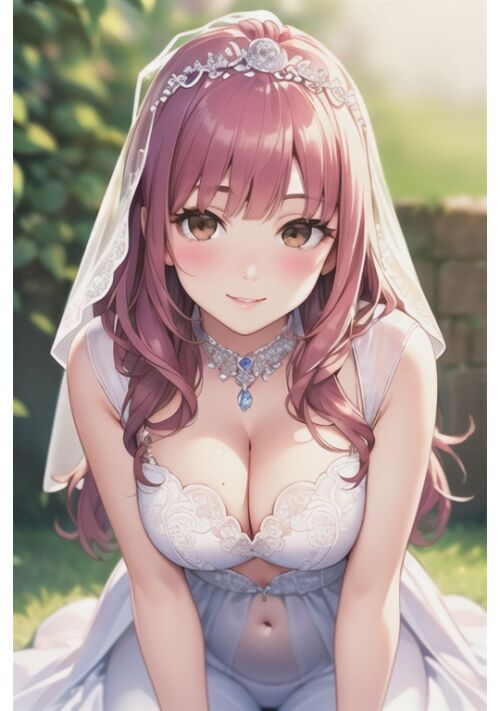
兄貴のお嫁さんは異世界のセクシー・エルフ! 巨乳の兄嫁にひと目惚れ!!
オズ研究所《横須賀ストーリー紅白へ》
ファンタジー
夏休み前、友朗は祖父の屋敷の留守を預かっていた。
その屋敷に兄貴と共に兄嫁が現れた。シェリーと言う名の巨乳の美少女エルフだった。
友朗はシェリーにひと目惚れしたが、もちろん兄嫁だ。好きだと告白する事は出来ない。
兄貴とシェリーが仲良くしているのを見ると友朗は嫉妬心が芽生えた。
そして兄貴が事故に遭い、両足を骨折し入院してしまった。
当分の間、友朗はセクシー・エルフのシェリーとふたりっきりで暮らすことになった。

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。

妻に不倫され間男にクビ宣告された俺、宝くじ10億円当たって防音タワマンでバ美肉VTuberデビューしたら人生爆逆転
小林一咲
ライト文芸
不倫妻に捨てられ、会社もクビ。
人生の底に落ちたアラフォー社畜・恩塚聖士は、偶然買った宝くじで“非課税10億円”を当ててしまう。
防音タワマン、最強機材、そしてバ美肉VTuber「姫宮みこと」として新たな人生が始まる。
どん底からの逆転劇は、やがて裏切った者たちの運命も巻き込んでいく――。

旧校舎の地下室
守 秀斗
恋愛
高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















