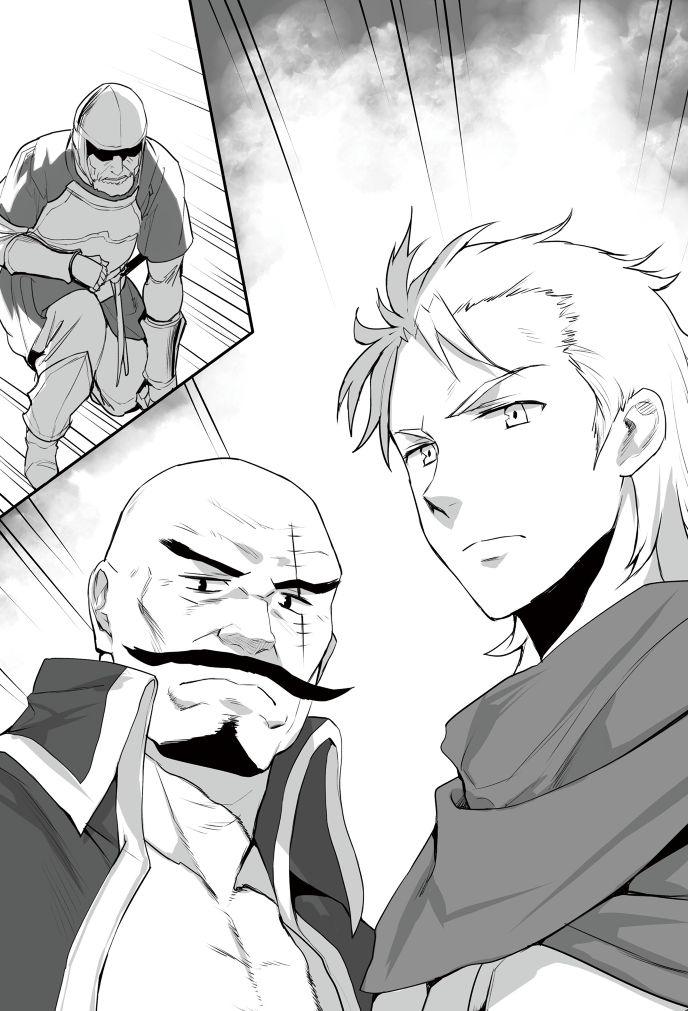99 / 128
7巻
7-3
しおりを挟む
ハンスの目の前に展開される近代的な設備は、キョウジが考案し、ダンジョンマスターのイツカが組み上げたものだった。浮遊島との一件以来、イツカの能力はさらに強化されていたのである。
従来あったトラップの機能向上に加え、新しいトラップによる設備の追加。さらには、今まではイツカを助ける外部能力装置「ジャビコ」しか使えなかったモニター類も、トラップとして自由に設置できるようになっていた。
これを機に、ロックハンマー侯爵は自身の執務室に、便利そうなものを片っ端から導入させたのである。
「今もイツカ殿にちょくちょく来てもらって、調整している最中なのだがね。いや、これがなかなか便利でね。あちこちにゴーレムを設置して監視カメラとして使ったり、通話道具として使ったり」
「監視カメラ、ですか。確か、カメラというのは映像を映すための装置、でしたか」
「そうそう。キョウジ殿達が説明していた言葉だね。これらのおかげで、仕事が恐ろしく捗ってね。特に文字などを入力すると、ゴーレムが出力してくれるワープロ、というものが素晴らしい。私が先ほど使っていたものなのだが」
そう言いながら、ロックハンマー侯爵は部屋の一角を指さした。そこには四角い箱に似た物体が置いてある。その内部からは軽い駆動音が響いており、時折紙が吐き出されていた。
「あれは、先ほどのモニターと対応していてね。内部にペンを仕込んだゴーレムが入っている。紙を補充して指示を出せば、モニターで入力した文字と寸分違わぬものを描き出してくれる仕組みだ」
使用方法は、幾らでも思い浮かぶ。純粋な武官であるハンスでもそう思うのだから、頭のいい人間が見たら、どんな事態を招くだろう。
それ以前に、ハンスはロックハンマー侯爵が順応していることも恐ろしかった。すでに当たり前のように使いこなしている。
「プリンター、という名前だそうでね。彼らの世界にあるものを真似て作ったらしい。筆跡が一定になってしまうので、私が直接書かなければならない手紙類では使えないのだが。書類などはこれで代用できるから、素晴らしく時間が短縮できるのだよ。便利なものに慣れると戻れなくなるというのは、まさにこれのことだと思うのだがね」
まあ、それはともかく、と、ロックハンマー侯爵は本題を切り出した。机の上に置いてある箱に手を伸ばして蓋を取る。中に入っているのは、一通の手紙だ。
ロックハンマー侯爵から手渡されたそれを、ハンスはためつすがめつ確認する。
宛名は、地方騎士ハンス・スエラーとなっていた。
「差出人」代わりの封蝋は、王城の執政官室のものだった。それは、王の仕事を助ける執政官を補佐し、実務的な活動をする組織のことである。ハンスの国の中ではかなり重要な組織であり、強い権限と力を持っていた。
にわかにハンスの眼光が鋭くなる。どこかの国と開戦し、「騎士」としてのハンスの力が必要になったのではないか。ハンスが真っ先に思い浮かべたのは、戦争の二文字だ。
ハンスの内心を察したのか、ロックハンマー侯爵は首を横に振った。
「実は私の方にも執政官室から手紙が来ていてね。君宛の手紙の内容に関する記述もあったのだがね」
「お聞きしても?」
「うむ。先日君の街の近くで起きた天変地異について報告をして欲しい、とのことなのだがね」
その単語を耳にして、ハンスは首を傾げた。確かに成層圏から人が落下してきたり、デカイ島が飛んできたりはしたが、これらは人為的なものである。ここ最近、自然災害の類が起きた記憶はない。
怪訝な顔をするハンスに、ロックハンマー侯爵は言葉を続けた。
「どうやら、教会の方から何かを言ってきたようでね。お告げで災害の暗示があったとか」
「教会、ですか」
教会と言えば、「太陽教会」という宗教団体のことを指す。数多くの国で信仰されている宗教で、ハンス達の国もそのご多分に漏れない。大抵の街には、その支部である教会が建設されているのだが、ハンスが住む街には看板をかけただけの無人の建物しかなかった。クソ田舎だからである。
初めて街を訪れたとき、教会すらないことを知ったハンスは、「ここは一体、どこの地の果てなんだ?」と思ったものだ。
それはまあ、いいとして――。
「教会には、神託を受けられる者がいてね。そこにお告げがあったそうなのだよ。君の街の近くに、大規模な天変地異が起こった、と。ただ内容までは詳しく分からないらしくてね。まさか、とは思うのだが……」
「浮遊島の件なのではないか、と?」
「うむ。正直なところ、神託というのに関しては眉唾だとは思うのだがね?」
国教とはいえ、すべての人間が敬虔な信者というわけではない。行事に参加したり、寄付などは行ったりするものの、聖職者が祈祷で起こす奇跡を心から信じている者は意外と多くはなかった。特に、軍部には信者がほとんどおらず、神の力ではなく魔法の効果だとする考えが一般的である。
魔法という力を個人で持ち得ることが当たり前の世界であるが故に、そういう迷信じみた力は、かえって一部の人間の間では真に受けにくくなっているのかもしれない。
どうやら、ロックハンマー侯爵もその一人だったようだ。ハンスもほぼ同じ考えである。
「しかし、時期が悪かったね。今年何があるか、覚えているかね?」
「確か大分先に、第一王子の立太子の式典があるはずでしたが」
それは王位継承権第一位の王子を、公式に次の国王として布告するための行事である。その重要度から、国のすべての貴族に参加が義務づけられていた。とはいっても、爵位を持つ家長に限られる。ハンスのような者は、逆に会場に近づくことも許されないだろう。
「そう、それだよ。知ってのとおり、あの式典は太陽教会から司祭を呼ぶのだがね。どうもそれに関係しているようなのだよ。立太子式典の直前に天変地異が起きたのは、不吉な兆候やもしれない。詳細に調べるべき、だとかね」
国で行う大きな行事には、国教である太陽教会を招く場合がほとんどだ。王は神からその権限を与えられたことになっているので、建前上、絶対に必要なのである。
その太陽教会から、王太子擁立のタイミングで物言いがついたとなれば一大事だ。よしんばこの話が民衆にでも流れれば、王太子は神に祝福されていないのではないかという悪い噂のもとにもなりかねない。
「すぐに千里眼の使い手が集められ、君の街の周辺を調べたそうだよ。ところが、街から少し離れたある地点だけさっぱり見通せない……となったのだそうだ」
千里眼は、大きな魔力の乱れがあると無効化されてしまうことがある。その場所は、十中八九、浮遊島が落下した地点だろう。
「そこで、これは一大事かもしれない、と事情を知る者達の間で騒ぎになったらしいのだよ。手紙には至急現場を調査し、直接王城へ報告せよ、と書いてあるのだがね」
「直接、というと……。まさか侯爵閣下もですか」
「ああ。おおよその経過は、王城と遠話魔法を繋げている者が居るから、彼らを通じて報告できるのだがね。流石に事が事だから、形式に則した命を下したと、いうところだと思うのだがね」
確かに、報告だけならば遠話魔法で事足りるはずだ。だが重要な案件だけに、口頭での報告が直接必要になったらしい。王太子の立場を磐石にするためにも慎重さが求められているのだろう。
「最終的な報告会は、式典の直前に行うそうだよ。私はそのまま王都に留まり、式典へ出るわけだね」
「なるほど」
ハンスは少し考え込むように顔を伏せた。それから手にした手紙を凝視して言った。
「一応、私も中身を確認してみます」
ロックハンマー侯爵が頷くのを確認して、ハンスは封蝋を開けた。手紙の内容は、おおよそロックハンマー侯爵が話したとおりであった。
ハンスは手紙をロックハンマー侯爵に渡した。
「読んでもいいのか?」という問いに、ハンスは首を縦に振る。ロックハンマー侯爵は素早く文面に目を通した。
「やはり、同じような内容だね。私に届いたものに比べれば、随分と情報が削ぎ落とされているが」
「地方騎士へ届けられるものですから、当然です」
「まあ、それはそうかもしれないと思うのだがね。とにかく、どう説明したものか」
侯爵の言葉のとおりである。バカ正直に、何があったか説明するのは大いに煩わしい。
――ああ、その件なら空飛ぶ島が、めっちゃ魔獣とか積んできてぇー! 戦争みたいな騒ぎになったんですよぉー!
――なんて、どうして説明できようか。
そんな下手を打てば、これまでの事件をすべて報告するはめになる。ロックハンマー侯爵の立場の失墜を招く恐れがあるばかりか、日本人達の立場も危うくなるだろう。
牢獄には現在、ファヌルスという爆弾まで抱えているのだ。国の中央に報告するにしても時期尚早だ。
「まあ、ごまかすしかないとは思いますが。こちらのことを向こうがどの程度掴んでいるのかが気になりますね」
執政官室が、指示だけ出して何もしないとも考えにくい。独自に調査官などを派遣してくる可能性もある。
もっとも、表向きには、そういう者達は来ないだろう。
ロックハンマー侯爵領内で起こった問題に関する裁量は、統治者である侯爵に任されるのが当たり前だからだ。まして「人里ではない場所で起こったかもしれない天変地異」である。
そもそも捨て置かれてもおかしくない案件だ。今回のような時期でもない限り、調べられもしないだろう。危険な魔獣だとか、不思議な魔法だとかいったものが普通に存在する世界の話である。何の被害もなければ、天変地異などどうでもいいことなのだ。
――だからこそと言うべきか。
表からの調査がなければ、当然裏から密偵の類が放たれ、独自に潜入捜査などをされる恐れがあるわけだ。
とはいえ、ロックハンマー侯爵のもとには同種の任務を専門とするコールスト子爵家がある。彼らの目を盗んで、そういった者達が領内を自由に暗躍するのは至難の業と言っていい。
これに加えて、コウシロウの千里眼と、ケンイチの配下である魔獣達もいるのだ。
余程の腕利きでもない限り、ハンスやロックハンマー侯爵の身を危うくする致命的な情報が漏れる心配はないだろう。
ただし、状況的には非常時に近いため、万全を期しておいて損はない。
「私もそれが気になってね。念のため、セヴェリジェとセルジュ殿を王都に派遣する予定だよ」
「はぁ、なるほど。……って、はぁ⁉」
セヴェリジェとは、件のコールスト子爵家の次男である。強力な魔法が扱え、隠密活動なども得意としていた。
問題なのはもう一人の、セルジュの方だ。元々隣国の兵士であった彼は、裏仕事をするために生まれてきたような男である。
得意分野は、諜報、隠密活動に、破壊工作。
今はいろいろあって、ロックハンマー侯爵お抱えの傭兵として活動しているものの、そんな危険な素性の男を、王都に潜り込ませてよいものか。ハンスが驚くのも無理はなかった。
「セルジュ殿には、私の館があるこの辺りの街の、商会の主人の立場を与えてある。きちんと実体のある店だよ」
商人は小回りの利く立場だ。品物の買いつけと言い張れば、どこに居ても怪しまれる心配はあまりない。金回りがよくても不自然ではなく、諜報を行う者には適職である。
「しかし、危険ではありませんか? いろいろと」
「そのためにセヴェリジェを同行させたからね。問題はないとも」
侯爵に力強く胸を張られ、ハンスはぐっと言葉を詰まらせた。
セルジュは小器用な男だ。上手くやりそうな気はする。が、元々彼は敵国の兵士であり、〝雷光〟という二つ名で恐れられた存在だ。ハンス達の国の軍隊を散々引っ掻き回し、大きな痛手を与えた記憶は今も生々しい。
「ああ、安心したまえ。変装はするそうだからね。私も実際に見たが、あれはなかなかに化けていると思うのだがね」
「いえ、そういうことを言っているのではないのですが……」
どうしたものかと悩むハンスだったが、まあ、ロックハンマー侯爵がよいというのだから、異論を唱えようとは思わない。無理やり納得して、話を先に進めることにする。
「ごまかすにしても、どうするおつもりですか?」
「状況によるが、とりあえず地すべりが起きた影響で、魔石を含む地層が出てきたことにすれば、いろいろと都合がいいと思うのだがね」
――天変地異は、地すべり。
確かにそれならば説明がつく。千里眼が効かなくなったのは、地層に含まれた魔石の魔力のせいにできる。
「ですがそれだと、魔石採掘の話が持ち上がりませんか?」
魔石は貴重な鉱物資源だ。魔法道具の材料になるので、採掘場所には多くの人員が投入されると予想される。
「確認できたのは、クズ石だけ、ということにしようと思っているのだがね」
鉱山などは、それがある領内の貴族が管理者とされている。そこから得られる資源は、必然的にその貴族の収入となるのだ。従って、そこには当然のごとく税がかかる。
ならば鉱山の存在を隠蔽すれば納税の義務から逃れられるかというと、そうとも言えない。国の監察官の目は厳しく、出し抜くのは相当困難だからだ。
また、魔石は扱いが難しいため、買い手も限られてくる。ごまかしたところで換金方法も少なく、国の監察官に発見されれば、最悪の場合、爵位を返上する懲罰の対象となる。そうなると、そこまでのリスクを負う貴族は皆無と言ってよいだろう。
しかも素直に国に報告すれば、鉱山の開発費用の一部を援助してくれるのである。
「魔石と言っても、大粒のものでなければ加工の手段がないからね。砂粒大の魔石ばかりが出る地層も多い。それが出土したと言えば、不審に思う者はまずいないと思うのだがね」
こういった地層は「ハズレ」と言われることがほとんどだ。砂粒大の魔石が出てきたところで、魔法道具の材料にならないのである。大きな粒に加工する方法も研究されているが、未だに見つかってはいない。
大きな魔石を削った屑は、地球で言う火薬のようにも扱えるが、もとが小さな魔石では、その手の使用も難しかった。爆発はするものの、威力は大きな魔石の削り屑の五十分の一以下。土や砂粒と仕分けるのもすこぶる大変で、費用対効果も合わない。
はっきり言って、何の役にも立たない代物だった。
そのため、ハンスから見ても、ロックハンマー侯爵の話の持っていき方は上手い手だと思えた。
「流石、ロックハンマー侯爵閣下ですね。それならば皆も納得するでしょう」
「そうだね。何か余程の事情でもない限り、これでどうにでもなると思うのだがね」
確かに普通であれば、その報告で無事終了となるだろう。
「場所柄、人的被害もなかったとなれば、まさにただの地すべり。立太子の式典にケチがつくこともない」
物や人に被害がなければ、天変地異など起こっていないのと同じだ。だが問題はある。式典に関することではなく、タイミングの話だ。
「本当にただの神託なのでしょうか? こちらの事情を掴んでいるのでは?」
「私もそれを考えていたのだがね。何しろ言い出したのは、太陽教会だからね」
太陽教会は、ハンス達の国だけではなく、様々な国に影響力を持つ巨大宗教組織だ。隣国の事情を知っていたとしても、おかしくはない。
つまり、浮遊島の一件が把握されている恐れがあるわけだ。とはいえ、あくまで宗教団体でしかない彼らに何ができるというのか。知らぬ存ぜぬでしらを切り通せば、強引な介入も不可能だ。
「だが、実際にこちらが『それがどうしたのか?』と言えば、それ以上首も突っ込んでこないだろう。確かに様々な場所に影響力を持ってはいるが、それまでだ。彼らの懐に入る金の量が増えるわけでもないし、彼らにとって、その件を取り上げるメリットは特にないと思うのだが」
ロックハンマー侯爵は言葉を続け、暫く悩む素振りを見せた後、首を横に振った。
「まあ、とにかく彼らの目的が分からないことには、調べてみないとなんとも言えない、と思うのだがね」
情報がなければ、何も判断できないため、具体的な方策も立てられない。今のところ、これ以上できることはないだろう。
「調査結果のでっち上げは適当にしておくよ。口裏合わせのために、また何度か、こちらに足を運んでもらうことになると思うのだがね」
「分かりました。よろしくお願いします」
「よろしく頼む。ひとまず、そんなところかな」
今後の方針が決まったところで、ハンスは席を立とうと腰を浮かした。ロックハンマー侯爵は忙しい身の上でもある。長居は無用だ。
そのとき、部屋の扉がノックされた。ロックハンマー侯爵が口を開く前に扉が開いた。入って来たのは、兵士の一人であった。
「お話しのところ、失礼します! 緊急にご報告せねばならないことが! ハンス殿にも、お聞きいただいた方がよい内容です!」
二人はすぐに、表情を引き締めた。
ロックハンマー侯爵の目配せに、ハンスは小さく頷いてみせる。
「聞こう」
「ファヌルス・リアブリュックの尋問に当たっていた、スドウ・キョウジ殿より連絡です。ファヌルスが、自分の背後にいたものについて供述しました」
余程大きな、あるいは厄介なものの名前が明かされたのだろう。兵士は一度深呼吸して、気持ちを静めてから、はっきりとよく通る声で言った。
「背後にいたのは、太陽教会。あらかじめファヌルスの能力を知った上で、協力を申し出てきたそうです」
ロックハンマー侯爵は、鋭く目を細めた。
ハンスは目を見開き、表情を険しくしている。
王都からの手紙。
ファヌルス。
そのどちらにも関係する、太陽教会。
これだけインパクトのあるカードを並べられては、きな臭いものを感じるな、というだけではすまないだろう。
「騎士ハンス。これは少々、厄介な事態になりそうだと思うのだがね」
「そのようですね」
ハンスはソファーにどっかりと腰を下ろすと、悟られないように小さく溜め息を吐くのであった。
3 説明する女と聞く男
ファヌルスが七、八歳くらいの頃、突然、一通の手紙が届いた。
その手紙を受け取ったファヌルスは、大変困惑したという。驚くのも無理はない。「差出人」は、太陽教会の総本山である中央大教会となっていたのだ。
一体どういうことなのか。恐る恐る中身を確認してみると、ファヌルスはさらに驚愕した。
手紙の書き出しが、次のようなものだったからである。
「はじめまして。私は現在、教会で聖職者をしている、元日本人だ」
そう、その手紙の送り主は、ファヌルスと同じ元日本人、転生者だというのである。
喜び、驚き、様々な感情が湧き上がる中、ファヌルスは震える手で内容を読み進めた。書き出しの後には、突然手紙を送ったことを詫びる文章が続いていく。
「急にこんな手紙を送られて、さぞ驚いただろう。君のことは、遠くから見させてもらった。すぐに声をかけようかとも思ったのだが、君の能力を考えて、まずは手紙を出すことにする」
要約すれば、そのようなことが書いてあった。
ファヌルスの能力とは、「ニコポ・ナデポ」のことにほかならない。それなら確かに、傍へ近づくのは躊躇われるだろう。
しかし何故、手紙の「差出人」は、ファヌルスの能力を知っているのか。
その答えは、手紙の続きに綴られていた。
「自分には『鑑定』という能力がある。目にしたものがどんなものか、正確に推し量り、解析できる能力だ。たとえば人間なら、名前、年齢、出身、特技、現在の能力、潜在能力、生い立ちなど、私が望む情報を、ほとんど知ることができる。その能力を使って、君のことを見抜いたのだ。もちろん、君がその能力を大いに嫌っていることも、分かっている」
ファヌルスは、後頭部を思い切り殴りつけられたような衝撃を覚えた。
内容が嘘なのではないか。
だがそれを書く理由がないし、嘘なら書かれている中身の説明がつかない。ファヌルスは自分の能力について、生まれてから誰にも打ち明けていなかったからだ。
それを知る方法として、「差出人」の能力が本当なら納得がいく。
では一体、その目的は何なのか。
続く内容は、次のようなものであった。
「たとえば、『君が不安がる必要はない。すべて能力のせいだから』とか、『きっと皆、君のことを赦してくれるし、そもそも愛してくれている』とか。そういった聞こえのいいことを言ったところで、君は受け入れてくれないだろう」
手紙は、じわじわとファヌルスの内面に入り込んでくる。
「君は偽善的な言葉は信じず、もっと穿ったものの見方をする。能力のおかげで、君の性格を知ることができた。その上で、君が何を企んでいるのかも」
それから核心を突くような文章が続いた。
「誰かを助け感謝してもらうことで、好いてもらう。猪口才で、しゃらくさくて、小ざかしい。でも、間違ってはいない、よい手段だ。そんな君に、提案がある」
なるほど、手紙の主の能力は本物らしい。端から慰めたり肯定したりするのではなく、一度貶してから認める。この話の持っていき方は、ファヌルスの性格を捉えていた。この「差出人」は得体が知れないが、信用できそうだ。
何より、生まれ変わってからずっと、周囲の人々に甘やかされて育ってきたファヌルスにとって、こういった皮肉の利いた辛口の評価は、甘美な刺激として受け取れたのである。
それにしても、提案とは何なのか。
従来あったトラップの機能向上に加え、新しいトラップによる設備の追加。さらには、今まではイツカを助ける外部能力装置「ジャビコ」しか使えなかったモニター類も、トラップとして自由に設置できるようになっていた。
これを機に、ロックハンマー侯爵は自身の執務室に、便利そうなものを片っ端から導入させたのである。
「今もイツカ殿にちょくちょく来てもらって、調整している最中なのだがね。いや、これがなかなか便利でね。あちこちにゴーレムを設置して監視カメラとして使ったり、通話道具として使ったり」
「監視カメラ、ですか。確か、カメラというのは映像を映すための装置、でしたか」
「そうそう。キョウジ殿達が説明していた言葉だね。これらのおかげで、仕事が恐ろしく捗ってね。特に文字などを入力すると、ゴーレムが出力してくれるワープロ、というものが素晴らしい。私が先ほど使っていたものなのだが」
そう言いながら、ロックハンマー侯爵は部屋の一角を指さした。そこには四角い箱に似た物体が置いてある。その内部からは軽い駆動音が響いており、時折紙が吐き出されていた。
「あれは、先ほどのモニターと対応していてね。内部にペンを仕込んだゴーレムが入っている。紙を補充して指示を出せば、モニターで入力した文字と寸分違わぬものを描き出してくれる仕組みだ」
使用方法は、幾らでも思い浮かぶ。純粋な武官であるハンスでもそう思うのだから、頭のいい人間が見たら、どんな事態を招くだろう。
それ以前に、ハンスはロックハンマー侯爵が順応していることも恐ろしかった。すでに当たり前のように使いこなしている。
「プリンター、という名前だそうでね。彼らの世界にあるものを真似て作ったらしい。筆跡が一定になってしまうので、私が直接書かなければならない手紙類では使えないのだが。書類などはこれで代用できるから、素晴らしく時間が短縮できるのだよ。便利なものに慣れると戻れなくなるというのは、まさにこれのことだと思うのだがね」
まあ、それはともかく、と、ロックハンマー侯爵は本題を切り出した。机の上に置いてある箱に手を伸ばして蓋を取る。中に入っているのは、一通の手紙だ。
ロックハンマー侯爵から手渡されたそれを、ハンスはためつすがめつ確認する。
宛名は、地方騎士ハンス・スエラーとなっていた。
「差出人」代わりの封蝋は、王城の執政官室のものだった。それは、王の仕事を助ける執政官を補佐し、実務的な活動をする組織のことである。ハンスの国の中ではかなり重要な組織であり、強い権限と力を持っていた。
にわかにハンスの眼光が鋭くなる。どこかの国と開戦し、「騎士」としてのハンスの力が必要になったのではないか。ハンスが真っ先に思い浮かべたのは、戦争の二文字だ。
ハンスの内心を察したのか、ロックハンマー侯爵は首を横に振った。
「実は私の方にも執政官室から手紙が来ていてね。君宛の手紙の内容に関する記述もあったのだがね」
「お聞きしても?」
「うむ。先日君の街の近くで起きた天変地異について報告をして欲しい、とのことなのだがね」
その単語を耳にして、ハンスは首を傾げた。確かに成層圏から人が落下してきたり、デカイ島が飛んできたりはしたが、これらは人為的なものである。ここ最近、自然災害の類が起きた記憶はない。
怪訝な顔をするハンスに、ロックハンマー侯爵は言葉を続けた。
「どうやら、教会の方から何かを言ってきたようでね。お告げで災害の暗示があったとか」
「教会、ですか」
教会と言えば、「太陽教会」という宗教団体のことを指す。数多くの国で信仰されている宗教で、ハンス達の国もそのご多分に漏れない。大抵の街には、その支部である教会が建設されているのだが、ハンスが住む街には看板をかけただけの無人の建物しかなかった。クソ田舎だからである。
初めて街を訪れたとき、教会すらないことを知ったハンスは、「ここは一体、どこの地の果てなんだ?」と思ったものだ。
それはまあ、いいとして――。
「教会には、神託を受けられる者がいてね。そこにお告げがあったそうなのだよ。君の街の近くに、大規模な天変地異が起こった、と。ただ内容までは詳しく分からないらしくてね。まさか、とは思うのだが……」
「浮遊島の件なのではないか、と?」
「うむ。正直なところ、神託というのに関しては眉唾だとは思うのだがね?」
国教とはいえ、すべての人間が敬虔な信者というわけではない。行事に参加したり、寄付などは行ったりするものの、聖職者が祈祷で起こす奇跡を心から信じている者は意外と多くはなかった。特に、軍部には信者がほとんどおらず、神の力ではなく魔法の効果だとする考えが一般的である。
魔法という力を個人で持ち得ることが当たり前の世界であるが故に、そういう迷信じみた力は、かえって一部の人間の間では真に受けにくくなっているのかもしれない。
どうやら、ロックハンマー侯爵もその一人だったようだ。ハンスもほぼ同じ考えである。
「しかし、時期が悪かったね。今年何があるか、覚えているかね?」
「確か大分先に、第一王子の立太子の式典があるはずでしたが」
それは王位継承権第一位の王子を、公式に次の国王として布告するための行事である。その重要度から、国のすべての貴族に参加が義務づけられていた。とはいっても、爵位を持つ家長に限られる。ハンスのような者は、逆に会場に近づくことも許されないだろう。
「そう、それだよ。知ってのとおり、あの式典は太陽教会から司祭を呼ぶのだがね。どうもそれに関係しているようなのだよ。立太子式典の直前に天変地異が起きたのは、不吉な兆候やもしれない。詳細に調べるべき、だとかね」
国で行う大きな行事には、国教である太陽教会を招く場合がほとんどだ。王は神からその権限を与えられたことになっているので、建前上、絶対に必要なのである。
その太陽教会から、王太子擁立のタイミングで物言いがついたとなれば一大事だ。よしんばこの話が民衆にでも流れれば、王太子は神に祝福されていないのではないかという悪い噂のもとにもなりかねない。
「すぐに千里眼の使い手が集められ、君の街の周辺を調べたそうだよ。ところが、街から少し離れたある地点だけさっぱり見通せない……となったのだそうだ」
千里眼は、大きな魔力の乱れがあると無効化されてしまうことがある。その場所は、十中八九、浮遊島が落下した地点だろう。
「そこで、これは一大事かもしれない、と事情を知る者達の間で騒ぎになったらしいのだよ。手紙には至急現場を調査し、直接王城へ報告せよ、と書いてあるのだがね」
「直接、というと……。まさか侯爵閣下もですか」
「ああ。おおよその経過は、王城と遠話魔法を繋げている者が居るから、彼らを通じて報告できるのだがね。流石に事が事だから、形式に則した命を下したと、いうところだと思うのだがね」
確かに、報告だけならば遠話魔法で事足りるはずだ。だが重要な案件だけに、口頭での報告が直接必要になったらしい。王太子の立場を磐石にするためにも慎重さが求められているのだろう。
「最終的な報告会は、式典の直前に行うそうだよ。私はそのまま王都に留まり、式典へ出るわけだね」
「なるほど」
ハンスは少し考え込むように顔を伏せた。それから手にした手紙を凝視して言った。
「一応、私も中身を確認してみます」
ロックハンマー侯爵が頷くのを確認して、ハンスは封蝋を開けた。手紙の内容は、おおよそロックハンマー侯爵が話したとおりであった。
ハンスは手紙をロックハンマー侯爵に渡した。
「読んでもいいのか?」という問いに、ハンスは首を縦に振る。ロックハンマー侯爵は素早く文面に目を通した。
「やはり、同じような内容だね。私に届いたものに比べれば、随分と情報が削ぎ落とされているが」
「地方騎士へ届けられるものですから、当然です」
「まあ、それはそうかもしれないと思うのだがね。とにかく、どう説明したものか」
侯爵の言葉のとおりである。バカ正直に、何があったか説明するのは大いに煩わしい。
――ああ、その件なら空飛ぶ島が、めっちゃ魔獣とか積んできてぇー! 戦争みたいな騒ぎになったんですよぉー!
――なんて、どうして説明できようか。
そんな下手を打てば、これまでの事件をすべて報告するはめになる。ロックハンマー侯爵の立場の失墜を招く恐れがあるばかりか、日本人達の立場も危うくなるだろう。
牢獄には現在、ファヌルスという爆弾まで抱えているのだ。国の中央に報告するにしても時期尚早だ。
「まあ、ごまかすしかないとは思いますが。こちらのことを向こうがどの程度掴んでいるのかが気になりますね」
執政官室が、指示だけ出して何もしないとも考えにくい。独自に調査官などを派遣してくる可能性もある。
もっとも、表向きには、そういう者達は来ないだろう。
ロックハンマー侯爵領内で起こった問題に関する裁量は、統治者である侯爵に任されるのが当たり前だからだ。まして「人里ではない場所で起こったかもしれない天変地異」である。
そもそも捨て置かれてもおかしくない案件だ。今回のような時期でもない限り、調べられもしないだろう。危険な魔獣だとか、不思議な魔法だとかいったものが普通に存在する世界の話である。何の被害もなければ、天変地異などどうでもいいことなのだ。
――だからこそと言うべきか。
表からの調査がなければ、当然裏から密偵の類が放たれ、独自に潜入捜査などをされる恐れがあるわけだ。
とはいえ、ロックハンマー侯爵のもとには同種の任務を専門とするコールスト子爵家がある。彼らの目を盗んで、そういった者達が領内を自由に暗躍するのは至難の業と言っていい。
これに加えて、コウシロウの千里眼と、ケンイチの配下である魔獣達もいるのだ。
余程の腕利きでもない限り、ハンスやロックハンマー侯爵の身を危うくする致命的な情報が漏れる心配はないだろう。
ただし、状況的には非常時に近いため、万全を期しておいて損はない。
「私もそれが気になってね。念のため、セヴェリジェとセルジュ殿を王都に派遣する予定だよ」
「はぁ、なるほど。……って、はぁ⁉」
セヴェリジェとは、件のコールスト子爵家の次男である。強力な魔法が扱え、隠密活動なども得意としていた。
問題なのはもう一人の、セルジュの方だ。元々隣国の兵士であった彼は、裏仕事をするために生まれてきたような男である。
得意分野は、諜報、隠密活動に、破壊工作。
今はいろいろあって、ロックハンマー侯爵お抱えの傭兵として活動しているものの、そんな危険な素性の男を、王都に潜り込ませてよいものか。ハンスが驚くのも無理はなかった。
「セルジュ殿には、私の館があるこの辺りの街の、商会の主人の立場を与えてある。きちんと実体のある店だよ」
商人は小回りの利く立場だ。品物の買いつけと言い張れば、どこに居ても怪しまれる心配はあまりない。金回りがよくても不自然ではなく、諜報を行う者には適職である。
「しかし、危険ではありませんか? いろいろと」
「そのためにセヴェリジェを同行させたからね。問題はないとも」
侯爵に力強く胸を張られ、ハンスはぐっと言葉を詰まらせた。
セルジュは小器用な男だ。上手くやりそうな気はする。が、元々彼は敵国の兵士であり、〝雷光〟という二つ名で恐れられた存在だ。ハンス達の国の軍隊を散々引っ掻き回し、大きな痛手を与えた記憶は今も生々しい。
「ああ、安心したまえ。変装はするそうだからね。私も実際に見たが、あれはなかなかに化けていると思うのだがね」
「いえ、そういうことを言っているのではないのですが……」
どうしたものかと悩むハンスだったが、まあ、ロックハンマー侯爵がよいというのだから、異論を唱えようとは思わない。無理やり納得して、話を先に進めることにする。
「ごまかすにしても、どうするおつもりですか?」
「状況によるが、とりあえず地すべりが起きた影響で、魔石を含む地層が出てきたことにすれば、いろいろと都合がいいと思うのだがね」
――天変地異は、地すべり。
確かにそれならば説明がつく。千里眼が効かなくなったのは、地層に含まれた魔石の魔力のせいにできる。
「ですがそれだと、魔石採掘の話が持ち上がりませんか?」
魔石は貴重な鉱物資源だ。魔法道具の材料になるので、採掘場所には多くの人員が投入されると予想される。
「確認できたのは、クズ石だけ、ということにしようと思っているのだがね」
鉱山などは、それがある領内の貴族が管理者とされている。そこから得られる資源は、必然的にその貴族の収入となるのだ。従って、そこには当然のごとく税がかかる。
ならば鉱山の存在を隠蔽すれば納税の義務から逃れられるかというと、そうとも言えない。国の監察官の目は厳しく、出し抜くのは相当困難だからだ。
また、魔石は扱いが難しいため、買い手も限られてくる。ごまかしたところで換金方法も少なく、国の監察官に発見されれば、最悪の場合、爵位を返上する懲罰の対象となる。そうなると、そこまでのリスクを負う貴族は皆無と言ってよいだろう。
しかも素直に国に報告すれば、鉱山の開発費用の一部を援助してくれるのである。
「魔石と言っても、大粒のものでなければ加工の手段がないからね。砂粒大の魔石ばかりが出る地層も多い。それが出土したと言えば、不審に思う者はまずいないと思うのだがね」
こういった地層は「ハズレ」と言われることがほとんどだ。砂粒大の魔石が出てきたところで、魔法道具の材料にならないのである。大きな粒に加工する方法も研究されているが、未だに見つかってはいない。
大きな魔石を削った屑は、地球で言う火薬のようにも扱えるが、もとが小さな魔石では、その手の使用も難しかった。爆発はするものの、威力は大きな魔石の削り屑の五十分の一以下。土や砂粒と仕分けるのもすこぶる大変で、費用対効果も合わない。
はっきり言って、何の役にも立たない代物だった。
そのため、ハンスから見ても、ロックハンマー侯爵の話の持っていき方は上手い手だと思えた。
「流石、ロックハンマー侯爵閣下ですね。それならば皆も納得するでしょう」
「そうだね。何か余程の事情でもない限り、これでどうにでもなると思うのだがね」
確かに普通であれば、その報告で無事終了となるだろう。
「場所柄、人的被害もなかったとなれば、まさにただの地すべり。立太子の式典にケチがつくこともない」
物や人に被害がなければ、天変地異など起こっていないのと同じだ。だが問題はある。式典に関することではなく、タイミングの話だ。
「本当にただの神託なのでしょうか? こちらの事情を掴んでいるのでは?」
「私もそれを考えていたのだがね。何しろ言い出したのは、太陽教会だからね」
太陽教会は、ハンス達の国だけではなく、様々な国に影響力を持つ巨大宗教組織だ。隣国の事情を知っていたとしても、おかしくはない。
つまり、浮遊島の一件が把握されている恐れがあるわけだ。とはいえ、あくまで宗教団体でしかない彼らに何ができるというのか。知らぬ存ぜぬでしらを切り通せば、強引な介入も不可能だ。
「だが、実際にこちらが『それがどうしたのか?』と言えば、それ以上首も突っ込んでこないだろう。確かに様々な場所に影響力を持ってはいるが、それまでだ。彼らの懐に入る金の量が増えるわけでもないし、彼らにとって、その件を取り上げるメリットは特にないと思うのだが」
ロックハンマー侯爵は言葉を続け、暫く悩む素振りを見せた後、首を横に振った。
「まあ、とにかく彼らの目的が分からないことには、調べてみないとなんとも言えない、と思うのだがね」
情報がなければ、何も判断できないため、具体的な方策も立てられない。今のところ、これ以上できることはないだろう。
「調査結果のでっち上げは適当にしておくよ。口裏合わせのために、また何度か、こちらに足を運んでもらうことになると思うのだがね」
「分かりました。よろしくお願いします」
「よろしく頼む。ひとまず、そんなところかな」
今後の方針が決まったところで、ハンスは席を立とうと腰を浮かした。ロックハンマー侯爵は忙しい身の上でもある。長居は無用だ。
そのとき、部屋の扉がノックされた。ロックハンマー侯爵が口を開く前に扉が開いた。入って来たのは、兵士の一人であった。
「お話しのところ、失礼します! 緊急にご報告せねばならないことが! ハンス殿にも、お聞きいただいた方がよい内容です!」
二人はすぐに、表情を引き締めた。
ロックハンマー侯爵の目配せに、ハンスは小さく頷いてみせる。
「聞こう」
「ファヌルス・リアブリュックの尋問に当たっていた、スドウ・キョウジ殿より連絡です。ファヌルスが、自分の背後にいたものについて供述しました」
余程大きな、あるいは厄介なものの名前が明かされたのだろう。兵士は一度深呼吸して、気持ちを静めてから、はっきりとよく通る声で言った。
「背後にいたのは、太陽教会。あらかじめファヌルスの能力を知った上で、協力を申し出てきたそうです」
ロックハンマー侯爵は、鋭く目を細めた。
ハンスは目を見開き、表情を険しくしている。
王都からの手紙。
ファヌルス。
そのどちらにも関係する、太陽教会。
これだけインパクトのあるカードを並べられては、きな臭いものを感じるな、というだけではすまないだろう。
「騎士ハンス。これは少々、厄介な事態になりそうだと思うのだがね」
「そのようですね」
ハンスはソファーにどっかりと腰を下ろすと、悟られないように小さく溜め息を吐くのであった。
3 説明する女と聞く男
ファヌルスが七、八歳くらいの頃、突然、一通の手紙が届いた。
その手紙を受け取ったファヌルスは、大変困惑したという。驚くのも無理はない。「差出人」は、太陽教会の総本山である中央大教会となっていたのだ。
一体どういうことなのか。恐る恐る中身を確認してみると、ファヌルスはさらに驚愕した。
手紙の書き出しが、次のようなものだったからである。
「はじめまして。私は現在、教会で聖職者をしている、元日本人だ」
そう、その手紙の送り主は、ファヌルスと同じ元日本人、転生者だというのである。
喜び、驚き、様々な感情が湧き上がる中、ファヌルスは震える手で内容を読み進めた。書き出しの後には、突然手紙を送ったことを詫びる文章が続いていく。
「急にこんな手紙を送られて、さぞ驚いただろう。君のことは、遠くから見させてもらった。すぐに声をかけようかとも思ったのだが、君の能力を考えて、まずは手紙を出すことにする」
要約すれば、そのようなことが書いてあった。
ファヌルスの能力とは、「ニコポ・ナデポ」のことにほかならない。それなら確かに、傍へ近づくのは躊躇われるだろう。
しかし何故、手紙の「差出人」は、ファヌルスの能力を知っているのか。
その答えは、手紙の続きに綴られていた。
「自分には『鑑定』という能力がある。目にしたものがどんなものか、正確に推し量り、解析できる能力だ。たとえば人間なら、名前、年齢、出身、特技、現在の能力、潜在能力、生い立ちなど、私が望む情報を、ほとんど知ることができる。その能力を使って、君のことを見抜いたのだ。もちろん、君がその能力を大いに嫌っていることも、分かっている」
ファヌルスは、後頭部を思い切り殴りつけられたような衝撃を覚えた。
内容が嘘なのではないか。
だがそれを書く理由がないし、嘘なら書かれている中身の説明がつかない。ファヌルスは自分の能力について、生まれてから誰にも打ち明けていなかったからだ。
それを知る方法として、「差出人」の能力が本当なら納得がいく。
では一体、その目的は何なのか。
続く内容は、次のようなものであった。
「たとえば、『君が不安がる必要はない。すべて能力のせいだから』とか、『きっと皆、君のことを赦してくれるし、そもそも愛してくれている』とか。そういった聞こえのいいことを言ったところで、君は受け入れてくれないだろう」
手紙は、じわじわとファヌルスの内面に入り込んでくる。
「君は偽善的な言葉は信じず、もっと穿ったものの見方をする。能力のおかげで、君の性格を知ることができた。その上で、君が何を企んでいるのかも」
それから核心を突くような文章が続いた。
「誰かを助け感謝してもらうことで、好いてもらう。猪口才で、しゃらくさくて、小ざかしい。でも、間違ってはいない、よい手段だ。そんな君に、提案がある」
なるほど、手紙の主の能力は本物らしい。端から慰めたり肯定したりするのではなく、一度貶してから認める。この話の持っていき方は、ファヌルスの性格を捉えていた。この「差出人」は得体が知れないが、信用できそうだ。
何より、生まれ変わってからずっと、周囲の人々に甘やかされて育ってきたファヌルスにとって、こういった皮肉の利いた辛口の評価は、甘美な刺激として受け取れたのである。
それにしても、提案とは何なのか。
10
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

私が死んで満足ですか?
マチバリ
恋愛
王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。
ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。
全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。
書籍化にともない本編を引き下げいたしました

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。