この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

妹のために愛の無い結婚をすることになりました
バンブー竹田
恋愛
「エミリー、君との婚約は破棄することに決まった」
愛するラルフからの唐突な通告に私は言葉を失ってしまった。
婚約が破棄されたことはもちろんショックだけど、それだけじゃない。
私とラルフの結婚は妹のシエルの命がかかったものでもあったから・・・。
落ちこむ私のもとに『アレン』という大金持ちの平民からの縁談が舞い込んできた。
思い悩んだ末、私は会ったこともない殿方と結婚することに決めた。

婚約破棄? 私、この国の守護神ですが。
國樹田 樹
恋愛
王宮の舞踏会場にて婚約破棄を宣言された公爵令嬢・メリザンド=デラクロワ。
声高に断罪を叫ぶ王太子を前に、彼女は余裕の笑みを湛えていた。
愚かな男―――否、愚かな人間に、女神は鉄槌を下す。
古の盟約に縛られた一人の『女性』を巡る、悲恋と未来のお話。
よくある感じのざまぁ物語です。
ふんわり設定。ゆるーくお読みください。
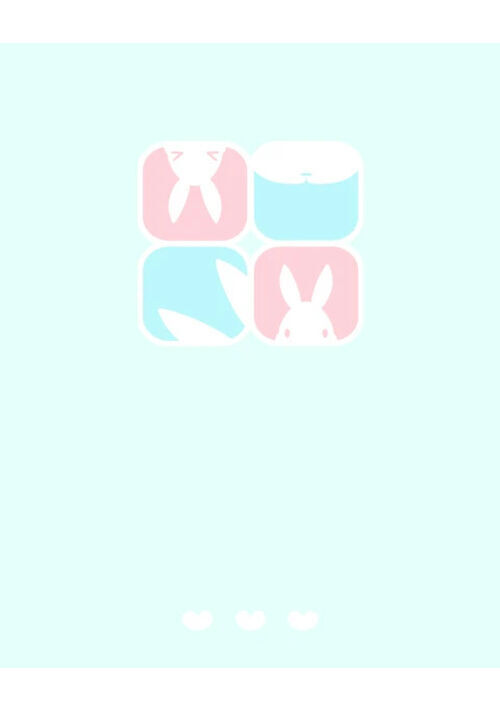
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。

幼馴染み同士で婚約した私達は、何があっても結婚すると思っていた。
喜楽直人
恋愛
領地が隣の田舎貴族同士で爵位も釣り合うからと親が決めた婚約者レオン。
学園を卒業したら幼馴染みでもある彼と結婚するのだとローラは素直に受け入れていた。
しかし、ふたりで王都の学園に通うようになったある日、『王都に居られるのは学生の間だけだ。その間だけでも、お互い自由に、世界を広げておくべきだと思う』と距離を置かれてしまう。
挙句、学園内のパーティの席で、彼の隣にはローラではない令嬢が立ち、エスコートをする始末。
パーティの度に次々とエスコートする令嬢を替え、浮名を流すようになっていく婚約者に、ローラはひとり胸を痛める。
そうしてついに恐れていた事態が起きた。
レオンは、いつも同じ令嬢を連れて歩くようになったのだ。

大魔法使いは、人生をやり直す~婚約破棄されなかった未来は最悪だったので、今度は婚約破棄を受け入れて生きてみます~
キョウキョウ
恋愛
歴史に名を残す偉業を数多く成し遂げた、大魔法使いのナディーン王妃。
彼女の活躍のおかげで、アレクグル王国は他国より抜きん出て発展することが出来たと言っても過言ではない。
そんなナディーンは、結婚したリカード王に愛してもらうために魔法の新技術を研究して、アレクグル王国を発展させてきた。役に立って、彼に褒めてほしかった。けれど、リカード王がナディーンを愛することは無かった。
王子だったリカードに言い寄ってくる女達を退け、王になったリカードの愛人になろうと近寄ってくる女達を追い払って、彼に愛してもらおうと必死に頑張ってきた。しかし、ナディーンの努力が実ることはなかったのだ。
彼は、私を愛してくれない。ナディーンは、その事実に気づくまでに随分と時間を無駄にしてしまった。
年老いて死期を悟ったナディーンは、準備に取り掛かった。時間戻しの究極魔法で、一か八か人生をやり直すために。
今度はリカードという男に人生を無駄に捧げない、自由な生き方で生涯を楽しむために。
逆行して、彼と結婚する前の時代に戻ってきたナディーン。前と違ってリカードの恋路を何も邪魔しなかった彼女は、とあるパーティーで婚約破棄を告げられる。
それから紆余曲折あって、他国へ嫁ぐことになったナディーン。
自分が積極的に関わらなくなったことによって変わっていく彼と、アレクグル王国の変化を遠くで眺めて楽しみながら、魔法の研究に夢中になる。良い人と出会って、愛してもらいながら幸せな人生をやり直す。そんな物語です。
※カクヨムにも掲載中の作品です。

婚約破棄されたけど、どうして王子が泣きながら戻ってくるんですか?
ほーみ
恋愛
「――よって、リリアーヌ・アルフェン嬢との婚約は、ここに破棄とする!」
華やかな夜会の真っ最中。
王子の口から堂々と告げられたその言葉に、場は静まり返った。
「……あ、そうなんですね」
私はにこやかにワイングラスを口元に運ぶ。周囲の貴族たちがどよめく中、口をぽかんと開けたままの王子に、私は笑顔でさらに一言添えた。
「で? 次のご予定は?」
「……は?」

ゲームのシナリオライターは悪役令嬢になりましたので、シナリオを書き換えようと思います
暖夢 由
恋愛
『婚約式、本編では語られないけどここから第1王子と公爵令嬢の話しが始まるのよね』
頭の中にそんな声が響いた。
そして、色とりどりの絵が頭の中を駆け巡っていった。
次に気が付いたのはベットの上だった。
私は日本でゲームのシナリオライターをしていた。
気付いたここは自分で書いたゲームの中で私は悪役令嬢!??
それならシナリオを書き換えさせていただきます

婚約破棄されましたが、私はもう必要ありませんので
ふわふわ
恋愛
「婚約破棄?
……そうですか。では、私の役目は終わりですね」
王太子ロイド・ヴァルシュタインの婚約者として、
国と王宮を“滞りなく回す存在”であり続けてきた令嬢
マルグリット・フォン・ルーヴェン。
感情を表に出さず、
功績を誇らず、
ただ淡々と、最善だけを積み重ねてきた彼女に突きつけられたのは――
偽りの奇跡を振りかざす“聖女”による、突然の婚約破棄だった。
だが、マルグリットは嘆かない。
怒りもしない。
復讐すら、望まない。
彼女が選んだのは、
すべてを「仕組み」と「基準」に引き渡し、静かに前線から降りること。
彼女がいなくなっても、領地は回る。
判断は滞らず、人々は困らない。
それこそが、彼女が築いた“完成形”だった。
一方で、
彼女を切り捨てた王太子と偽聖女は、
「彼女がいない世界」で初めて、自分たちの無力さと向き合うことになる。
――必要とされない価値。
――前に出ない強さ。
――名前を呼ばれない完成。
これは、
騒がず、縋らず、静かに去った令嬢が、
最後にすべてを置き去りにして手に入れる“自由”の物語。
ざまぁは静かに、
恋は後半に、
そして物語は、凛と終わる。
アルファポリス女子読者向け
「大人の婚約破棄ざまぁ恋愛」、ここに完結。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















