49 / 93
第2章 旅立ち
別れの時④
しおりを挟む
そこに、マリウスはうずくまっていた。
サイロの煉瓦壁のそば、膝を抱えて顔を伏せている背中が見える。
顔をあたりにめぐらせると、アーラは少し離れた草原で、野に咲く花をプチプチ摘んでは、ぼんやりと眺めていた。
ふたたびマリウスの方を見つめたが、その背中はピクリとも動かない。
マリウスの姿は、すべてを拒絶していた。
だからニゲルは立ち尽くして、いったいどのように声を掛けたらよいものか、そんな風におろおろと考える事しかできなかった。
どうしようか。
そう考えても、マリウスのうずくまる姿を目にすると、なんにも思い浮かばない。
ただ、やはり、離れがたかった。
離れたくないと心が叫んでいて、それをやり過ごすことにニゲルも精一杯になる。
きょうだいの姿を見たら、胸が苦しくなって、息が苦しくなって、はあはあと荒い息が口から出ていくばかりで、目も潤んできて、別れの言葉なんて、口にできそうもない。
本当は、本当は、一緒にいたい。
仕方ない。手紙にしよう。
手紙だったら、ちゃんとお別れの言葉を言える。きっと、兄らしい態度で締めくくれる。
そうおもって、高ぶってくる気持ちを冷ますように熱い息を吐き出すと、そっとその場を離れた。
「君、待ってたの…」
ニゲルが牛舎を後にしたとき、あの黒い犬がどこからともなく現れて、傍らを歩いてくる。
いまは恥ずかしくて涙がでる顔を誰にも見られたくはなかった。
うつむいて、一人になれるだろう、放牧場へと歩いていた。
「ごめんね…言えなかったよ。せっかく、教えてくれたのに」
なかば独り言のようではあったけれど、ニゲルは犬に謝罪と感謝を告げる。
情けなくなって、いつまでも強くなれない自分が嫌になった。
でも、サフィラスとここを出て、いずれ一人になると思うと、怖い。怖くて仕方ない。この不安な気持ちをどうにも変えられないのだ。
「はあ…」
適当に歩いて木のそばに座り込むと、ニゲルもひざを抱えてうつむく。
どうしようと無駄なことを考えてしまうが、行くしかない。
それしか、皆が助かる道はないのだ。
「…お母さんに会いたいよ」
目の前で黙って座り込む黒い毛並みを、なんとなく触りながらひとりつぶやく。
「お母さんはなんにも言わなかったけど、もしかしたら僕みたいに力があって、最後は居なくならなきゃいけなかったのかもしれないな…」
けどいつかお母さんに会えるなら会いたい。サフィラスと旅をしながら探しても良いだろうか。きっとどこかに居るんじゃないか、そんな気がするのだ。アーラとマリウスの代わりに自分が探しに行けば、そうすれば、いつかまた4人で暮らせるようになるかもしれない。
それに、お母さんを探しに行くといえば、マリウスだって、ニゲルがいなくなる事を少しは許してくれるかもしれない。
空を見上げると、朝焼けに染まる山々の峰から、黄金の光が漏れ広がり、白い雲を浮かび上がらせるような印影をつけながら、赤く色付けていた。
ニゲルは犬の背をなでながら、その幻想的な空をただただ、何も考えずにしばらく眺めていた。
サイロの煉瓦壁のそば、膝を抱えて顔を伏せている背中が見える。
顔をあたりにめぐらせると、アーラは少し離れた草原で、野に咲く花をプチプチ摘んでは、ぼんやりと眺めていた。
ふたたびマリウスの方を見つめたが、その背中はピクリとも動かない。
マリウスの姿は、すべてを拒絶していた。
だからニゲルは立ち尽くして、いったいどのように声を掛けたらよいものか、そんな風におろおろと考える事しかできなかった。
どうしようか。
そう考えても、マリウスのうずくまる姿を目にすると、なんにも思い浮かばない。
ただ、やはり、離れがたかった。
離れたくないと心が叫んでいて、それをやり過ごすことにニゲルも精一杯になる。
きょうだいの姿を見たら、胸が苦しくなって、息が苦しくなって、はあはあと荒い息が口から出ていくばかりで、目も潤んできて、別れの言葉なんて、口にできそうもない。
本当は、本当は、一緒にいたい。
仕方ない。手紙にしよう。
手紙だったら、ちゃんとお別れの言葉を言える。きっと、兄らしい態度で締めくくれる。
そうおもって、高ぶってくる気持ちを冷ますように熱い息を吐き出すと、そっとその場を離れた。
「君、待ってたの…」
ニゲルが牛舎を後にしたとき、あの黒い犬がどこからともなく現れて、傍らを歩いてくる。
いまは恥ずかしくて涙がでる顔を誰にも見られたくはなかった。
うつむいて、一人になれるだろう、放牧場へと歩いていた。
「ごめんね…言えなかったよ。せっかく、教えてくれたのに」
なかば独り言のようではあったけれど、ニゲルは犬に謝罪と感謝を告げる。
情けなくなって、いつまでも強くなれない自分が嫌になった。
でも、サフィラスとここを出て、いずれ一人になると思うと、怖い。怖くて仕方ない。この不安な気持ちをどうにも変えられないのだ。
「はあ…」
適当に歩いて木のそばに座り込むと、ニゲルもひざを抱えてうつむく。
どうしようと無駄なことを考えてしまうが、行くしかない。
それしか、皆が助かる道はないのだ。
「…お母さんに会いたいよ」
目の前で黙って座り込む黒い毛並みを、なんとなく触りながらひとりつぶやく。
「お母さんはなんにも言わなかったけど、もしかしたら僕みたいに力があって、最後は居なくならなきゃいけなかったのかもしれないな…」
けどいつかお母さんに会えるなら会いたい。サフィラスと旅をしながら探しても良いだろうか。きっとどこかに居るんじゃないか、そんな気がするのだ。アーラとマリウスの代わりに自分が探しに行けば、そうすれば、いつかまた4人で暮らせるようになるかもしれない。
それに、お母さんを探しに行くといえば、マリウスだって、ニゲルがいなくなる事を少しは許してくれるかもしれない。
空を見上げると、朝焼けに染まる山々の峰から、黄金の光が漏れ広がり、白い雲を浮かび上がらせるような印影をつけながら、赤く色付けていた。
ニゲルは犬の背をなでながら、その幻想的な空をただただ、何も考えずにしばらく眺めていた。
0
あなたにおすすめの小説

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

#アタシってば魔王の娘なんだけどぶっちゃけ勇者と仲良くなりたいから城を抜け出して仲間になってみようと思う
釈 余白(しやく)
児童書・童話
ハアーイハロハロー。アタシの名前はヴーゲンクリャナ・オオカマって言ぅの。てゆうか長すぎでみんなからはヴーケって呼ばれてる『普通』の女の子だょ。
最近の悩みはパパが自分の跡継ぎにするって言って修行とか勉強とかを押し付けて厳しいことカナ。てゆうかマジウザすぎてぶっちゃけやってらンない。
てゆうかそんな毎日に飽きてるンだけどタイミングよく勇者のハルトウって子に会ったのょ。思わずアタシってば囚われの身なのってウソついたら信じちゃったわけ。とりまそんなン秒でついてくよね。
てゆうか勇者一行の旅ってばビックリばっか。外の世界ってスッゴク華やかでなんでもあるしアタシってば大興奮のウキウキ気分で舞い上がっちゃった。ぶっちゃけハルトウもかわいくて優しぃし初めての旅が人生の終着点へ向かってるカモ? てゆうかアタシってばなに言っちゃってンだろね。
デモ絶対に知られちゃいけないヒミツがあるの。てゆうかアタシのパパって魔王ってヤツだし人間とは戦争バッカしてるし? てゆうか当然アタシも魔人だからバレたら秒でヤラレちゃうかもしンないみたいな?
てゆうか騙してンのは悪いと思ってるょ? でも簡単にバラすわけにもいかなくて新たな悩みが増えちゃった。これってぶっちゃけ葛藤? てゆうかどしたらいンだろね☆ミ

生まれたばかりですが、早速赤ちゃんセラピー?始めます!
mabu
児童書・童話
超ラッキーな環境での転生と思っていたのにママさんの体調が危ないんじゃぁないの?
ママさんが大好きそうなパパさんを闇落ちさせない様に赤ちゃんセラピーで頑張ります。
力を使って魔力を増やして大きくなったらチートになる!
ちょっと赤ちゃん系に挑戦してみたくてチャレンジしてみました。
読みにくいかもしれませんが宜しくお願いします。
誤字や意味がわからない時は皆様の感性で受け捉えてもらえると助かります。
流れでどうなるかは未定なので一応R15にしております。
現在投稿中の作品と共に地道にマイペースで進めていきますので宜しくお願いします🙇
此方でも感想やご指摘等への返答は致しませんので宜しくお願いします。

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394

星降る夜に落ちた子
千東風子
児童書・童話
あたしは、いらなかった?
ねえ、お父さん、お母さん。
ずっと心で泣いている女の子がいました。
名前は世羅。
いつもいつも弟ばかり。
何か買うのも出かけるのも、弟の言うことを聞いて。
ハイキングなんて、来たくなかった!
世羅が怒りながら歩いていると、急に体が浮きました。足を滑らせたのです。その先は、とても急な坂。
世羅は滑るように落ち、気を失いました。
そして、目が覚めたらそこは。
住んでいた所とはまるで違う、見知らぬ世界だったのです。
気が強いけれど寂しがり屋の女の子と、ワケ有りでいつも諦めることに慣れてしまった綺麗な男の子。
二人がお互いの心に寄り添い、成長するお話です。
全年齢ですが、けがをしたり、命を狙われたりする描写と「死」の表現があります。
苦手な方は回れ右をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私が子どもの頃から温めてきたお話のひとつで、小説家になろうの冬の童話際2022に参加した作品です。
石河 翠さまが開催されている個人アワード『石河翠プレゼンツ勝手に冬童話大賞2022』で大賞をいただきまして、イラストはその副賞に相内 充希さまよりいただいたファンアートです。ありがとうございます(^-^)!
こちらは他サイトにも掲載しています。
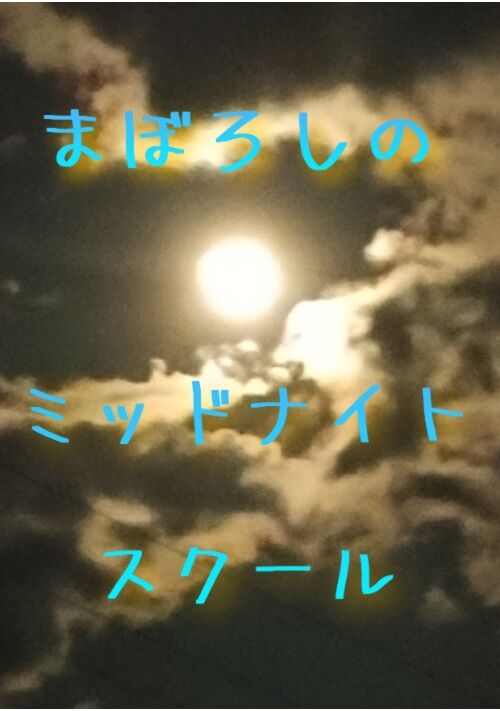
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

左左左右右左左 ~いらないモノ、売ります~
菱沼あゆ
児童書・童話
菜乃たちの通う中学校にはあるウワサがあった。
『しとしとと雨が降る十三日の金曜日。
旧校舎の地下にヒミツの購買部があらわれる』
大富豪で負けた菜乃は、ひとりで旧校舎の地下に下りるはめになるが――。

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















