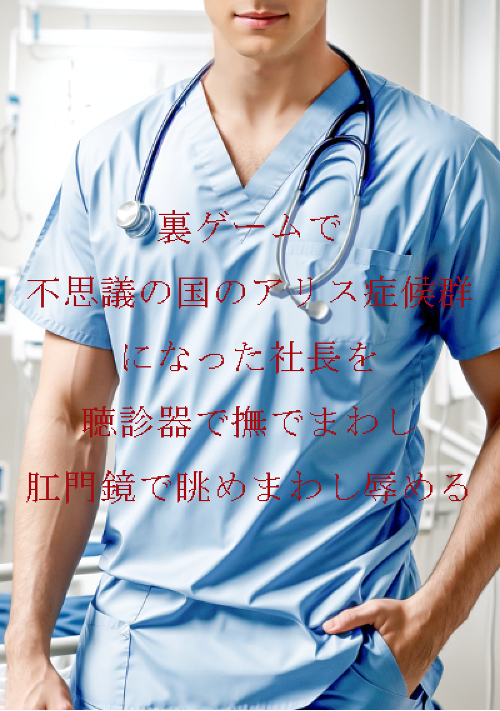13 / 24
魔人ダンダーラの略奪愛
①
しおりを挟む劇団の公演が終わってから一週間休みとなった。
公演まで徹夜つづきで缶詰になっていたとなれば、休みに入ってわざわざ稽古場に顔を出す物好きな団員はいない。
俺以外は、だ。
休みに入ったその日から俺は稽古場に赴き、基礎練習やストレッチ、かるい一人芝居なんかをやっていた。
団員に見られたら、あだ名の一つ「鍛錬魔」と囃されそうだけど、そう言われるほど鍛錬に没頭しているようで、実は上の空だったりする。
今回の公演で、俺は台詞のない役を演じた。
普段から舞台上では存在感が薄く、台詞がないとなれば、さらに他の演者、ライオンこと羅伊緒などの影に隠れてしまって、今回はいつにも増して俺は観客や演劇関係者の目に留まることがなかった。
が、団員は、俺が声がでなくなって役を降りてからの羅伊緒の荒れっぷりを知っている分、見る目が違った。
俺がまた舞台に戻ってきたことで、まるで使い物にならなかった羅伊緒が目覚しい復活を遂げ、公演が大成功をおさめたとなれば、そりゃあ、俺の存在をありがたく貴重なものと思うだろう。
そう再評価してくれた劇団は、次の公演は羅伊緒と俺をダブル主演にすると、公演が終わった直後に発表をしたのだ。
単独でないとはいえ、主役を張るのははじめてだ。
「華がない」「上手いけど地味」と言われつづけて、正直、主役に向かないのかもと諦めかけていただけに、発表を聞いたときはすぐに信じられなかった。
今もまだ地に足がついていないようで、稽古をしていないことには、現実感を失いそうになる。
主役に抜擢されたのが羅伊緒のおかげと言えなくもないから、余計だ。
邪念を払うように木刀を振り回して、一息ついたところで、着信音が鳴った。
隅に置いてある鞄の元へいき、タオルで顔を拭いてから、取りだしたスマホの画面を見る。
「イベント会社社長」と表示されているのに、幾度か瞬きをしてから「どうも久しぶりです」と電話に出た。
「久しぶりー、元気してた?」と応えてくれたのは、前にピンクレンジャーの代役として出演した、そのショーを仕切っていた会社の社長だ。
ピンクレンジャーの代役は、会社に知られないようマスクを隠れ蓑に入れ替わる方法でしていたのだけど、今や社長は俺の携帯番号を知っているし、こうして親しげに接してもいる。
実はあのとき、社長はマスクの下で、本来のピンクレンジャーの彼女から俺に入れ替わっていることに気づいていたという。
というか、彼女が前から同じように、別人と入れ替わっているのも知っていたらしい。
他のスタッフや演出、監督などは騙されていたようだけど、体を痛めるまでスタントとして名を馳せていた社長の目は誤魔化せなかったようだ。
それでいて、どうして、見逃していたのかといえば「面白かったから」とのこと。
ショー向きでアクションに長けた彼女を手放すのが惜しかったのもありつつ、彼女が代役に選ぶ人物にハズレがなかったのにも感心したのだとか。
アクションに長けた彼女に化けるのだから、代役は同等か近いスキルを持っているのは当たり前。
その上で細かい違いが見られるのに個性が光り「次はどんな、面白い子を連れてくるのだろう」と社長は、それぞれの代役の魅力を見つけるのを、ひそかに楽しみにしていたらしい。
俺も元名スタントの社長のお眼鏡にかなった一人なわけで、代役を終えたその日に「うちの会社入らないか?」と誘われた。
社長が言うには、これまで見てきた代役の中で、スカウトをしたのは初めてとのことだった。
まあ、それは多分おべっかにしても、劇団の稼ぎをはるかに上回る給与と「彼女が連れてきた代役の中でも、あれだけ客を沸かせたのは君だけだ。君なら会社の目玉になって、スーツアクターのスターになれると思うよ」との誘い文句に心が揺れないでもなかった。
そのときは、劇団でスターなど夢もまた夢。
主役もやれていない状態で、行き詰まり感を覚えていたせいもあるけど、その原因の一端である羅伊緒の顔が浮かんで、気がついたら「有難いお話ですけど」と言っていた。
「そうか、残念だけどしかたない。
でも、たまに暇なときに代役を頼んでもいいかな」
そうして連絡先を交換した社長からの連絡。
案の定「ピンクレンジャーの代役、頼めないかな?」と言われた。
「ピンクレンジャーの子が、オーディションに受かったからって、急に一ヶ月休みを欲しいって言ってきたんだよ。
自分で代役を見つけようともしないでさ。
そう思うと、やっぱり前のピンクレンジャーの子は良かったよ。
会社に隠し事をしていたとは言っても、ちゃんと役に穴を開けないように代役を連れてきて、スケジュール管理もしっかりしていたんだから」
俺に代役を頼んだ彼女は、すでにピンクレンジャーを卒業していた。
俺に代役を頼んだきっかけ、オーディションに受かって射止めた大舞台の役を華麗にこなしてみせて、名と顔が売れ演劇の賞ももらい、一躍、売れっ子の舞台女優となったからだ。
レンジャーを卒業するときはマスクを取って顔を晒し、これまで密かに代役を立てていたことも明かして詫びたらしい。
「こっちは惜しいだけだったから、代役のことなんか、彼女が辞めやすい口実になったって感じだったね」と社長はぼやいていたもので。
「ああ、話が逸れたね。
で、そうそう、代役を頼めないかなって話。
できたら、今日の午後から、五日ぐらいつづけて代役をしてもらえたら、助かるのだけど」
「いいですよ。
ちょうど前の公演が終わって、休みに入ったところですから。
今日の午後から行けます。
休みまでは後、五日あるんで、その間は朝から晩までステージにあがれますし。
その後は一週間くらい、午前は劇団の打ち合わせがありますが、午後は丸まる空いているんで」
「ほんと?そんなに出てくれるの?助かるなあ!」と電話越しからは社長のはしゃぐ声が聞こえてきたものの、一人で稽古場にいても、気が詰まりそうだったから、俺のほうこそ助かった思いだ。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
15
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる