4 / 44
山芒編
4山芒
しおりを挟む
オオオォ……と洞穴を風が吹き抜けていく音のような声がし始める。妖魔の群れが目を覚まし始めた声だ。
騎馬が機動力を活かして部隊全体の戦闘を補いつつ、歩兵は列が千切れないよう荷車を庇いながら懸命に前進を続ける。
現在、部隊は橋を渡るその真っ只中にあった。間に合わなかったのだ。日没までに橋を渡り切る事が出来なかった。
ここに至っていくつか想定外の事態が起きていた。
ひとつはまだ日没を迎えていないのに妖魔たちが湧き始めた事だ。
二つ目は雨が完全に上がった事。霧は残っているが夜を前に篝火を焚けるのは心強い。
そして最後に、川周辺の妖魔が想定の数段上をいく強さだった事。
「こ、れはっ……! 下がっていて下さいお二方!!」
ぶすりともぐさりともつかない鈍い音を立てて妖魔を斬って吼える辛新の背に庇われながら、舌打ちしたい衝動を堪える。隣では梅が剣を構えていた。梅が剣を抜く姿は初めて見る。
部隊はこれまでにないほど殺伐とし、橋で一列に伸びた前後から戦う兵士たちの声が響く。その中に時折悲鳴じみたものが混じるのを聞いては、玲馨はぐっと歯を食いしばった。
この期に及んでも玲馨の頭の中は戊陽の事でいっぱいだった。いや寧ろ、強力な妖魔に囲まれていくほどに、玲馨の不安は大きくなる。
妖魔祓いの力を、恐らく戊陽は使うつもりでいる。
日没を待たずに妖魔が出現したのは想定外ではあったものの、橋を渡り切らずに夜を迎えてしまう可能性は、林で立ち往生した時に考えていたはずだ。それでもなお引き返さずに行軍を再開させたのは、部隊全体を妖魔から守りきる算段が戊陽にあるからだ。その力を、戊陽だけが持っているからだ。
水の中から次々と飛び出してきては圧倒的な数で押し寄せてくる妖魔にどうにか対応しながらも、玲馨の視線は戊陽を探してさまよい続けている。
「はああっ!」
辛新が気合いの一閃を浴びせると、僅かに妖魔が途切れて橋の先を見通す隙間が出来た。東西に伸びた橋のほぼ中央、戊陽は李将軍と武官に守られながら、自身は剣を構えていないのを見つける。
「おい玲馨!!」
梅の焦ったような声のすぐ後に「オ゛ァ゛ッ」と気味の悪い呻き声が玲馨のすぐ真後ろで上がる。
「ぼさっとすんなって!」
「お前、剣が使えたのか」
「はあ?」
梅は玲馨に苛立つように答えながらも無駄の少ない動きで妖魔を次々と斬っていく。その立ち回りは禁軍の兵士たちにも引けを取らない。
そうか、と漸く腑に落ちた。戊陽が梅を選んだ理由だ。性格的な面で戊陽と梅の相性が良さそうだと玲馨が感じたように、逆もまた然りだったはず。梅と玲馨は性格的に相性が悪い。しかしそれでも梅を選んだのは、彼が武芸に覚えのある宦官だったからだ。辛新では心許ないと感じたのか、それとも──それとも他に何か理由があるのか。
今、ひとつ確かな事は、こうして戊陽に守られておきながら、玲馨には戊陽を守る術がないという事だ。
「梅、橋の中央に行きたい」
「この状況で何言ってんだよセンパイ。何か考えがあるのか?」
「いや無い。だが、陛下の近くに居た方が、安全になるかも知れないな」
「言ってる意味が、あ、おい! 待てって!」
ついてくるにせよ残るにせよ勝手にしろと思ったが、梅は結局玲馨についてきた。そればかりか玲馨に襲い掛かってくる妖魔を斬って露払いのような事までしてくれる。恩を売りたいのか、それとも戊陽からの密命でも帯びているのか。何にせよ戊陽の近くまで行くのに梅は大いに役立った。
橋の中央に近づくと、馬から降りていた戊陽がそれまで鞘に納めていた剣を引き抜くのが見えた。
「皇帝さんは何してんだ、あれ」
戊陽の周囲を固める将軍と武官たちは皇帝に指一本触れさせまいと必死の様相で剣を振るっている。その中心に立つ戊陽はまるで目の前で起きている戦闘が見えていないかのように、極めて集中していた。
ふと、戊陽の顔が上がる。
目が合ったような気がした。
次の瞬間、風か何か、目に見えないものが戊陽を発生源として円状に駆け抜けていった。
「……はえ?」
梅の間抜けな声が間近で上がる。兵士たちの戦いの音も止まっている。
橋の上全体が刹那の間静寂に包まれて、ザアアと川が流れる音が現実へと引き戻した。
「全軍、全速、前進──!!」
李将軍の角笛にも劣らぬほどの大号令が響き渡り、鍛えられた禁軍兵たちは一瞬の間に体勢を立て直して橋を渡り始める。
「ちょ、待て待て、何が起きた? 何が起きた!!」
釣られて走り出しながら梅が混乱の声を上げる。
玲馨はまだ戊陽を見ていた。
戊陽は橋に突き立てた剣を支えにしてどうにか倒れずにいるといった感じだ。すぐに李将軍が戊陽に手を貸し自分の駆る馬に戊陽を引き上げる。
玲馨と梅が橋の中央に着く頃には戊陽たちはとっくにその場を離れており、戊陽に声を掛ける事はかなわなかった。
そうこうしているうちに部隊の全員が橋を渡り切る。しかしそれも束の間、一度全滅していた妖魔があちこちで息を吹き返し、ゆらりとその影を夕日に照らし出した。
皮肉な事に、夜はこれから始まるのだ。
その後部隊は岳川から全速で離れながら東進し続け、街道が緩い傾斜を描き始める頃になると妖魔の力が弱まっていった。
後は東のまだまだ遠くに見える青々とした高い山を目指すだけだ。そこがこの旅の目的地、山芒である。
一難を乗り越えて、いつの間にか追いついてきた辛新と合流し、三人は野犬も出ない静かなあわいで溜息を漏らす。この辺りは妖魔避けの薬が効くようで、野営の準備が始まると妖魔はすっかり姿を消していた。
「大変でした……。初めて山芒を出た日はあの橋を迂回する道を行ったので、あんなにも岳側の妖魔が手強いとは」
少人数での移動なら森を切り開いた隘路を行く道が別にあるのだが、五十を越える一軍となるとそちらは使えない。
「それにしてもお二方は一体どこへおられたんですか? いつの間にか見失って心配していました」
「すいません、私の独断で持ち場を離れてしまったので」
「いえ、ご無事だったので良かったです」
控えめに笑ってみせた辛新は疲れは見えるが傷などはないようだった。
この旅はまさに命がけなのだ。
一説によると妖魔という存在は地脈の自浄作用のものだという。枯れた大地の手足となって、妖魔は生き物から生気を吸うのだ。
あわいや地脈について独自に調べ上げたらしいその手記はまだ玲馨が少年だった頃に読んだ物だ。その頃の知識が今になって思い起こされたが、しかしあの手記の内容の正誤について証明するものはなかった。
だが、と、玲馨はとぼとぼと天幕を立てている兵士たちを眺めて考える。
激しい戦闘があったとはいえ、初日の様子とまるで違い兵士たちはすっかり疲弊しきっている。かくいう玲馨も、今再び妖魔が襲ってきたら今度こそ逃げられない気がする。もしかすると、妖魔たちは傍に立つだけでも人間や馬など生き物から気を吸い取っているのかもしれない。
とにもかくにも、
「今夜は休みましょう」
異論などあるはずもなく、三人はそれぞれの天幕へ向かう。しかし、玲馨だけはそのまま自分の天幕へは行かず、戊陽が使っている天幕へと足を向けた。
戊陽の天幕の入り口で見張りをしている兵士は初日に見たのと同じ顔だった。恐らく玲馨の事を覚えていてくれるだろうが、既に休んでいるかも知れない事を考えるとここまで来て声を掛けるのを躊躇った。
せめてあの後戊陽がどうしていたかを訊こうと考えて足を進めようとすると、天幕の入り口を覆っていた布が中から持ち上がり、戊陽が外へと出て来た。
「玲馨?」
「あ……」と息のような声のような掠れた音が出るだけで、その先が続かない。顔を見ただけでほっとしてしまったらしい。
「おかしな顔をしてどうした?」
「ご無事で良かったと、思って……」
それは最も素直な感想だったのだが、今度は戊陽がおかしな顔をする番だった。拍子抜けしたのか眉尻も目尻も下がった顔は少し情けない。
「てっきり怒り出すかと思ったんだが」
「怒る? 私が陛下を怒鳴りつけるなど、首と別れる覚悟はまだしたくありません」
揺れる篝火の炎に合わせるように、ふ、と笑った戊陽の体も揺れる。
戊陽が笑った事で並々ならぬ雰囲気が漏れてしまったのだろう。見張りの兵士がそわそわしながら戊陽と玲馨をこっそり見比べている。
「中に入るか?」
玲馨は首を横に振った。
「休まれてください」
訊きたい事はあったが、兵士の視線が気になった。このまま天幕に入っても聞き耳を立てられていたらと思うとそう多くの事は訊けまい。
「分かった」
「では……失礼致します」
最後、戊陽は玲馨を安心させるように笑みを深めた。玲馨が心配して訪ねてきたのだと、戊陽には筒抜けだったようだ。
後ろ髪引かれる思いで戊陽のもとを立ち去り、自分の天幕へ戻っていく。
戊陽は無事だった。今はそれでいい。
*
残り二日となった行軍は存外呆気なく終わっていく。橋という最大の山場を戊陽の力で乗り越えたおかげで、本来の旅程内におさまる形で目的地へと到着する事になった。
「あ、見えてきましたよ!」
辛新が馬上から指差した先を視線で追うと、そこには山の麓となる位置に「芒守門」という扁額が掛かった牌楼──屋根のついた門──が見えた。
そこは嘗ての山芒の入り口であった場所だ。現在はあわいに含まれるため未登記の土地という事になる。門を管理する必要がなくなったため、扁額は錆びて屋根も朽ちて瓦が剥げてしまっていた。門から更に一時辰ほどなだらかな山道を進んだところが現在の山芒だ。
芒守門は古ぼけてしまっているが、周辺には橋から南西にあったあの枯れ林よりはずっと緑が残っていた。まだ地脈が僅かに大地を通っているからだろう。大木ほど嵐に耐えきれず折れているが、若木は枯れ葉を枝につけながらも懸命に根を生やし立っている。腐葉土のような匂いもほんの微かに地面から昇っていた。
紫沈から北玄海への道のりは多くが平野且つ荒野であった。途中川沿いを進む事にはなるが禿げた土地と黒く濁った川水よりも、枯れかけた今まさに命尽きようとしている森林地帯はよほど視覚的に悲惨さを伝えてくるようだ。
若い兵士たちの中には紫沈から出たことがなかった者も多いようで、彼らは辺りを痛ましいような物珍しいような目で見ていた。
日が中天にかかる頃、一行は長い六日の旅を終えて山芒最西端の街藍心に辿り着いた。
一行の先頭を李将軍と並び馬で進んでいた戊陽は、地方官吏らしき男に出迎えられて何かを話している様子が後方からもうかがえる。しかし残念ながら、いよいよここから玲馨たち三人は救助活動に向かう禁軍とはお別れだ。
「なーまずは宿探そうぜ宿。もうあっちこっち体バキバキよ」
「恐らく我々にも一時的に禁軍に貸し出される宿舎が割り当てられるはずだ」
「あ、はい! そのように仰せつかっております!」
「ほう? そりゃどこだ? 今すぐ案内せよ辛新!」
「はいー!」
玲馨の護衛にと遣わされたらしい不埒者と現役武官が相手では、体力面で玲馨に勝ち目は全くない。元気に駆けていった二人を見失わない程度に遅れてついていく事にする。
去り際、玲馨はちらと戊陽を見遣った。顔色はあまり優れないが今すぐ倒れるという事もなさそうだ。こちらはこちらで城に戻ってから訊き出さねばならない事が増えた。
あれもこれもと成すべき事ばかりが増えて、どれも一つと解決していない現状は非常に悩ましかった。
皇帝及び禁軍兵およそ五十名余り。あの橋の難戦では終ぞ一人も命を落とさなかった。妖魔に触れた者もあったが軽傷で済んでいる。
疲労が最高潮に達していた一行にあてがわれたのは嘗ては宿であった高楼で、まるまる一軒貸し切りだという。しかし実際には五十人全てが藍心に滞在する訳ではない。
支援物資を向家に届けた後は現地の状況を見て必要のない人員は紫沈にとんぼ返りである。五十人が各地に分散するならいざ知らず、全員がひとところに長く留まるとなると主に食料が足らなくなる。それでは本末転倒なので、禁軍のうち概ね半数ほどは数日のうちに帰還する事になるだろう。
更に言えば戊陽と李将軍も同じ高楼に泊まる訳ではないらしい。
さて、それらの事情を一応は把握している玲馨だが、玲馨たちとは既に関係のない事だ。高楼の一室に入った三人は年季の入った卓を囲んで腰を落ち着ける。
「それで、具体的にはどう調査をなさるんです? 詳細は玲馨さんに訊けとの事でしたので」
「川だ」
「と、言いますと?」
玲馨は高楼へと案内してくれた女性から借りてきた山芒のたいへん大雑把な──子供の落書きのような──地図を入った卓に広げると、山芒の山頂付近から続く大きな川を示す。
「岳川ですね」
「ここへ向かう」
「待て……待て待て待て! また川か!?」
お腹が空いたでしょうから、と案内の女性から貰ってしまった饅頭を一人で全部食べて転寝していた梅が、血相を変えて飛び起きる。
「もうあんな目に遭うのはこりごりだ!」
「調査は日中に行う。それに川と言っても今度は領内の川だ。夜に行ったところで妖魔が出る事はまずない」
「お、お~そうか、そうだったな」
焦ってしまったのが恥ずかしかったのか、梅は下手くそな口笛を吹いて誤魔化すが誤魔化せていない。
「あの、玲馨さん。岳川は恐らく支流も派流も多いと思いますが」
「この地図だと……本流しか書かれていないようです」
筆で豪快に書かれた一本の線は、果たして本流と呼んで良いかも甚だ怪しい。
「まずは岳川を詳しく書き込んだ地図を探す所からですね」
「ええ~、面倒くさ。俺寝てて」
「辛新殿はこの町には詳しいですか? 恐らく町の郷長なら農地と川の──」
「いえ玲馨さん、山芒はとても集権的なんです。領内の権力差という意味でならそれこそ中央以上に」
本流の一本だけが太い線で引かれた簡素な地図を見下ろして、玲馨は顎に手を当てる。
「まさか、川を記した地図一枚借りるのに、木王とお会いしなくてはならない……なんて言いませんね?」
「いいえいいえ。そのまさか、です」
ご明察とでも言わんばかりの口ぶりに、胃の腑がずっしりと重たくなる。
木王とは四王のうち東の領地を治める王の称号であり、現在は向家の領主がそれを務める。今頃戊陽が堅苦しい話をしているだろう相手だ。
いかに中央から派遣されてきたとはいえ所詮は宦官二人と下級武官一人だ。戊陽の部隊に同道していたが残念ながら皇帝の使いという立場ではなく、あくまで私的に山芒を訪れた唯の人でしかなかった。その裏には今回の調査は大っぴらにしたくはないという事情があるからなのだが。
つまり仮に玲馨が木王に個人的に拝謁出来る高級官吏だったとしても会う訳にはいかないのだ。
しかし、である。事は地図の話。山芒の詳細な地図をまさか木王だけが所持しているという事はないだろう。いかに集権的と言えど農地を直接管理しているのはその町や村の長なのだから彼らにとって地図は不可欠だ。
要は郷長から秘密裏に地図を拝借すれば良い。
それにしても、敵国の間諜でもあるまいに地図一つ手に入れるためだけに危険を犯さねばならないとは想像もしなかった。
「辛新、あんた確か山芒のどっかのお坊っちゃんて話だったよな?」
「はい! 藍心より更に北に家族が暮らしております」
「名家だってんなら地図くらい持ってるべ?」
見苦しく尻を掻きながら放った梅の盲点をつく一言に、玲馨と辛新は顔を見合わせて声を上げた。その手があったかと。
*
四合院という建築様式で造られた向家の屋敷は、日の字型に院子を二つ構えた造りになっている。後宮でも妃たちの宮は全て四合院になっているが、平地の紫沈とは違い東に向かって傾斜のある山芒に建てたこの屋敷は庭と庭の間の垂花門の前後に短い階がある。それは紫沈では見かけない珍しい造りだった。表門から見て正面が母屋で右手が客堂になっているらしい。
また通りから中を隠すために作られる影壁には龍が彫られた塑壁があった。あわいによって国が分断されてからというもの四王の土地は随分縁遠くなったが、戊陽の記憶によればこれは青龍と呼ばれる四神の一柱で山芒を守護する神の似姿である。青龍の力を借りたつまるところ魔除けの類だ。仮にあわいがここまで広がってきた所で、妖魔はこの門を易々とは突破出来ないだろう。
紫沈から連れてきた禁軍の兵士たちはひとまず藍心の高楼に留まらせ、戊陽は李将軍と二人でこの山芒の領主が住まう向家の屋敷へと来ていた。
垂花門を潜り客堂に入ると知らずと息が漏れていく。戊陽の額はうっすらと汗で湿っていた。
あの日、岳川の橋で戊陽は初めて妖魔祓いを行った。天幕を訪ねてきた玲馨に対して少々見栄を張った自覚があるだけに、つい休まずここまで来てしまった。しかし、見栄を張っただけでこれだけ動けているという事は、妖魔祓いの力は思った以上に体に対して負担があるものではないのかも知れない。もしも癒やしの力で妖魔と同じ数だけの傷病人に治癒を施していたら、数日は昏倒していただろう。
「陛下、今日一日休まれてからでもよろしかったのでは?」
武芸一辺倒で叩き上げの李将軍は無骨でやや愚直なところのある武人だ。鍛え上げた大きな肉体は見た目にも物理的にも威圧感があった。
一見すると恐ろしい男なのだが、全く気遣いが出来ない訳でもない。宮女たちが「お髭の将軍さん」と親しみを込めて影で呼んでいる事を戊陽は知っている。
──お髭の将軍さん……。
「陛下?」
「問題ない。これが済んだら休む」
この男は決してそんな可愛らしい名で呼んで良い男ではない。宮女たちも武器を構えた李将軍と一対一で対峙し、あの圧倒的な存在感を目の当たりにすれば恐ろしくて声も出せなくなるはずだ。
暫く待っていると侍女らしき女が複数入ってきて、菓子と茶が卓に並べられていく。所作が美しく、見目も良い。木王の趣味かと思っていると一人の侍女が李将軍と目があった。侍女は愛らしく微笑んでから一礼すると他の侍女たちと共に去っていく。
隣をちらりと横目に見ると李将軍は耳を真っ赤にしていた。わざとらしく咳払いをすると将軍はピンと背筋を伸ばしながらも気まずそうに視線を逸らす。
──お髭の将軍さん……。
李将軍からは剣術を学んだ事もある。あの当時の李将軍に戊陽が「お髭の将軍さん」だなどと言えばたちまち鋭い一撃を打ち込まれた事だろう。
──国最高の武人の弱点は、女の笑顔だったか。
いかめしい最高位の武官と愛らしい侍女との遣り取りに和んだのはつかの間の事だった。
「木王、向青倫、此度の陛下の御厚誼に感謝申し上げる」
文官風の男に付き添われてやってきた五十過ぎの男は緩慢に拱手すると、些か過ぎるくらいに恭しく言った。
向青倫──。この屋敷の、引いては山芒全てを取り仕切る領主の登場によってその場の空気は一瞬で張り詰めた。
「良い。面を上げよ。私はまだ何も成しておらぬ」
「はっ」
所作の一つ一つにゆとりがあり、そして重い。人間として培ってきた厚みが如実に表れている。仮に戊陽が今も皇弟の立場だったとしてもこの男よりもずっと貴い生まれだ。だけど格が違うと思わされる。
ふと、隣で身動ぐ気配を感じた。李将軍だ。この将軍さんは無骨だが、気遣いの出来る男であった事を思い出す。向青倫が現れてから急激に冷え始めていた指先に、少しずつ熱が戻ってくるのを感じた。
「向青倫」
自分自身を仕切り直し、改めて向青倫を正面から見据える。
この男は狸だ。
戊陽が即位して二年余り。直接会って言葉を交わしたのは即位式のただの一度きり。以来、宮廷で執り行われる祭儀にも自分は隠居のようなものと宣い、代わりに息子を遣わしたという経緯がある。
この男を憎いとは思わないが、おいそれと向青倫の取ってきた態度を許すことは戊陽の座る椅子が許さない。
「単刀直入に訊く。此度、私をここまで呼びつけたのはそなたの企てか?」
正面の椅子に腰掛けた向青倫の黒鳶色の瞳が戊陽を見つめる。頭は白髪混じりでも目はひとつも濁っていない。何が隠居かと胸の内で揶揄する。
「企てとは滅相もない。此度の事は地下水の放出による事故で御座います。兵は消耗し、東の練族の略奪行為が今起きれば対応は厳しい。妖魔はあわいより外へは出ませんが、万に一つという事もありましょう。領地を預かる四王が一人として、恥を忍んでお助け願った所存に御座います」
事前に準備していた台詞かもしれないが、それにしたってよく回る舌だ。
向青倫の口から出た練族とは東の遊牧民族の事だ。山芒の東に位置する山を越えた先には高原が広がっており、そこには古くから遊牧の民が暮らしている。彼らの事を沈では練族と呼んだ。
嘗ては峠を境にして互いに不干渉を貫いていたが、七十年ほど前から練族からの一方的な侵略及び略奪行為が繰り返されるようになった。原因は東の高原にもあわいが広がっているからではないかと言われている。
侵攻はそう頻繁ではない。早くて一年、平均すると数年に一度で侵攻してくると先々代皇帝の時代の報告にはあった。これは年々減少傾向にあり、高原より先は絶海という地形から練族の人口が減少しているのではないかと推測されている。
戊陽は救援部隊が編成されるまでの三日の間、公務の合間に山芒や向家について可能な限り調べていた。それを頭の中で思い返しながら向青倫と相対する。
「今の山芒には何が不足している?」
人か、物か、兵力か。
「有事への備えはある。答えよ、向青倫」
この男は何故山芒から出てこない?
本当に戊陽を見下しているからか。それとも、何かを恐れているのか、或いは何かを画策しているのか。
「……禁軍の兵力を、この向青倫に預けて頂けますかな」
向青倫は殊更下手に出るという事はしなかった。口振りとしては断っても構わないと言っているようにも聞こえる。
試しているのか。あろうことか自身が仕える君主を。
だとしたら戊陽の答えは決まっている。
「千だ」
向青倫の憂いを取り払うのに必要な兵の数を、戊陽は千と見立てた。
「どうだ。足りるか、向青倫」
山芒軍四千に対して千を動員するとくれば十分に兵力の補強となるだろう。
千の兵士をただ派兵するのではない。戦線を維持するのに必要な軍需もある程度支援するのだ。
そのためにかかる経費はどれほどか。食糧は勿論、あわいを往復するのに必要な馬に人員、千の兵を駐屯させるのに簡易の宿舎を建てる必要も出てくるだろう。それらを支援すると、戊陽は言っている。
傍に控えた李将軍の脳裏には胃をキリキリさせる宰相の顔が浮かぶが戊陽には見えていない。国とはそうあるべきなのだ。何より長らく皇帝らしく振る舞う事が出来なかった戊陽としては、これが宮廷内の改革のきっかけにならないかとさえ考えていた。
向青倫にこれといって驚いた様子はなかった。かと言ってまんまと皇帝を騙してやったという風でもなく、暫くの間黙考しているようだった。
「戊陽皇帝陛下。まずは岳川付近に起きた事故についてお話し致しましょう。陛下がお連れ下さった兵にも働いてもらわねばなりませぬ故」
*
戊陽が向青倫と対峙していたその頃、玲馨たちは辛新が実家から借りてきた地図を片手に岳川の支流のうちの一つを目指していた。
山芒は一つの大きな山岳地帯を内包する土地で、山間に村落を築き生活している。おかげで人里を離れるとどこもかしこも木々や崖に行く手を阻まれた。峠を越すと高原だと聞くが、それが嘘のように山肌は森林に覆われている。
また、岳川の支流も多かった。その中で藍心から近く比較的大きな支流へ向かっているのだが、山の斜面である事に加えて人の手があまり入っていない林の中と、とにかく隘路が続いて玲馨はすっかり息が上がってしまっていた。
「はー……。何も着いた当日に行かなくてもよぉ」
文句を垂れている梅だが、見るからに彼が最も余力を残している。一方、汀彩城を歩き回る以外に体を鍛える機会の無い玲馨は全身汗だくだった。
「まぁまぁ梅さん。少しでも早く調査を進めようとなさる玲馨さんの姿勢はご立派ですよ」
辛新は馬を降りたが山芒が地元とあって山歩きに長けている。梅ほどではないにせよ彼も十分に余裕が見えた。もはや喋るのも億劫になっていた玲馨は二人には取り合わず黙々と歩いていく。
辛新が藍心出身ではなかったのと地図だけでは心許ないと考えて、藍心から山に入る前に地元の人間に道を訊ねていた。
農夫の話では支流まではずっと一本の道が続くという事だったが、果たしてこれは道と言えるだろうか。途中渡った吊橋付近から目に見えて悪路となり、辛うじて獣道という体裁のそれをもう半時辰ほど歩いている。藍心を出たのが正午をとっくに過ぎていた事を思えば、そろそろ引き返す事も視野に入れなくてはならない。山芒は紫沈よりも日没が早いと聞く。
「あ、思い出しました。こういう道を地元じゃ豚の畦道っていうんです」
「豚? 猪じゃなくてか?」
「はい。山芒に伝わる昔話に、飼っていた豚が飼い主を嫌って脱走して豚の国を築くという話があるんですが、体の大きい豚が群れを成して山を練り歩いたために出来た道が登場するんです」
「はーん。で、飼い主は豚だろうと大事にしましょうねーって落ちだな」
「よそではそうなんですか? 山芒だと、豚に国を築くなど到底無理な話だと悟った豚は反省して飼い主の所に帰ってきますね」
「何だそりゃ。ますます飼い主が調子に乗るだけじゃねぇか」
集権的な山芒らしいといえばそうだろう。似たようなお伽話は紫沈にもあるが、要は身の丈に合わない事をやるべきではないといった教訓を子供に分かりやすく伝えるためのものだ。
身の丈に合わない事──。
宦官が秘密裏に皇帝の勅命を受けて四王の土地を探るというのは果たしてどうなのだろう。身の丈という言葉には、宦官を当てるのか、それとも玲馨を当てるのか。
地図一つ得るのに間諜のような事をと困惑したが、玲馨のこれは間諜そのものでなくて何だろうか。北玄海の際は文官がきちんと任命を受けている上、北玄海の刺史と地方官吏が対応し、最終的には皇帝へと報告をしているので今回とは事情が異なる。
あれ? と玲馨は首を傾げる。
──今回私は、ここで何を探るのが正解なのか。
玲馨は思索にふけっていく。
ともすれば山芒の王である向青倫の痛い腹を探らなくてはならないかも知れない、という事まではおおよそ覚悟していたが、それだけではないのだろうか。
北玄海の岳川の「治水」と岳川上流である山芒。この間にどんな繋がりがあるのかを探るだけのはずだが、仮にそれだけではないとしたら?
玲馨の手足になる者として戊陽は梅をつけた。そういえば結局梅と別行動をする事は叶わなかったが今にしてそれで良かったという気がしている。梅は腕の立つ宦官だった。「羅清」という梅の旧名の名乗りを聞いて戊陽に驚いた様子はなかったのだから、宦官になる以前の経験を知っていて玲馨の「護衛」につけたのだ。
護衛──戦闘が起こる事を戊陽は予測している。そして戊陽は山芒までの旅で梅と行動するかを判断しろと言ったが、あれは梅の剣の腕前を玲馨にその目で確かめさせたかったからと考えて良いだろう。実際に梅の戦い方を見て玲馨は何と思ったのだったか。
『その立ち回りは禁軍の兵士たちにも引けを取らない』
『辛新では心許ないと感じたのか、それとも──それとも他に何か理由があるのか』
「ん? 川の音がしますね。心無しか空気も涼んできたような」
玲馨を思索から引き戻したのは辛新の屈託のない声だった。
「少し見てきますね。お二方は待っていて下さい!」
先頭を進んでいた辛新が歩調を早め、一足先に道向こうを確かめに行く。すぐに戻ってきた辛新は晴れやかな顔で「ありましたよ!」と報告した。
「豚の畦道」の終点から苔むした下り坂が続いており、少し下ると目的の川岸に出た。
川は小規模だが上流が連瀑帯になっており、水深は極めて浅く、少し下流に行った所に本流との合流地点があった。川の音がしたのは小さな滝壺に水が落ちる音だったようだ。
滝壺を囲うようにして谷間になっており、対岸に向かって水深が深くなっているように見える。
「梅、対岸から石を拾ってこい」
「は? 何で俺が」
玲馨は視線をまず自分の足元に向け、次いで辛新を経由し最後に梅を見る。
「あー? ……ったくよぉ。足が濡れたくないのは俺だって一緒だぜ?」
ぶつぶつ言いながらも梅は浅い川をざぶざぶいわせながら対岸に渡っていく。
三人とも袍に袴を身に着けていたが、梅だけが革の長靴を履いていた。梅を行かせた理由はそれだけだ。
「梅さんは面白い人です。それに頼りになります」
対岸に着いた梅は崖から剥き出しになった岩に片手をついていくつか水底に沈んでいた石を拾っている。
「……そうですね。役に立つ者です」
橋の上での事を思い出した。梅が居なければ、今回の行軍は死者一名になっていた事だろう。自分の背中を狙っていた妖魔に玲馨は気付いていなかった。それを斬ったのは梅だ。
玲馨と辛新が水に濡れない安全地帯から眺めているのを水の中から見た梅は「こういうのでいーんだな?」と叫びながら石を投げてくる。石を投げるなどぞっとしないが、投げられた石は二人の手前で落ちてばしゃりと水を跳ねさせた。
「……前言撤回だ」
水底に沈むのだから投げた石がどれかなんて分かるはずがない。
濡れた顔を手で拭いながら梅をじっとりと睨みつけた。
「よく川がおかしいって気付いたな」
梅が川辺にあった大きな岩のような石に寄りかかりながら気怠げに話す。
「対岸で土砂崩れでもあったんでしょうか?」
梅はさほど興味がなさそうなのに対して、辛新は玲馨の調査に少し興味が湧いてきたのか梅が拾ってきた石と足元にあった石をしげしげと見比べながら訊ねた。
上流から見て左手にある川岸の水底にあった石は角が鋭利で全体的に四角いのに対し、玲馨たちが立っている右岸の石はどれもつるりと丸い。これは嘗ては玲馨たちの場所まで水の流れがあった事を意味するが、では左岸は?
「土砂崩れがあったかどうかは農夫に聞けば恐らく分かるでしょう」
左岸は剥き出しになった岩を覆うように木の根が伸びている。それは岩肌に張り付くのではなく、紐暖簾のように垂れ下がっている。岩の天井からは地面がせり出しており、本来ならその先にまだ地面が続いていたかのように見えた。木は崖上で辛うじて倒れずにいるようだが、大雨などで地盤が緩めばどうなるか分からない。土砂崩れというより崖崩れがあったと言った方が正しいだろう。
仮にここで崖崩れが起こったと仮定すると、川の形が変わった事になる。その変化が本流へどれだけ影響があったか分からないが、岳川はいくつも支流と合流しながらあわいと北玄海を経由し、北方に広がる海まで流れ出る。
そして北玄海では最近、治水と称して領地を広げている。つまり岳川に向かって川岸を舗装し、舗装したからには領地であるという主張だ。更に舗装された川の近くにはもともと浮民が住んでいた。舗装した川までを領地とするなら浮民も領民になるのだと、これが北玄海で記録の上で人口が増大している理由だ。何もよそから人を攫って増やしているのではなく、元からそこにいた浮浪者たちに戸籍登録をさせているのだ。
やはり繋がるのか、岳川上流の動きと、北玄海の領地拡大が。
「おい玲馨、ぼーっとしてねぇで、気が済んだならそろそろ戻るぞ」
言うが早いか梅は先に「豚の畦道」の方へ向かい出す。
玲馨は梅が拾ってきた石を川に放り投げる。パシンッと音を立てて水面を揺らし、角張った小石が丸い石の中に混じって底に沈んでいった。もう玲馨の目からはどれが角張った石か分からないが、そこには確かに他の石とは違う左岸の石が沈んでいる。
「お前は礼儀と作法を身に着けろ梅。素首を落とされていいなら構わないが」
「素っ首ねぇ。あんたも性格に似合わない言葉遣いはやめといたらどうだ?」
梅が言っているのはどっちだろうか。梅に対する言葉遣いと辛新に対する言葉遣い。どちらが玲馨に似合いだと言っているのだろうか。
騎馬が機動力を活かして部隊全体の戦闘を補いつつ、歩兵は列が千切れないよう荷車を庇いながら懸命に前進を続ける。
現在、部隊は橋を渡るその真っ只中にあった。間に合わなかったのだ。日没までに橋を渡り切る事が出来なかった。
ここに至っていくつか想定外の事態が起きていた。
ひとつはまだ日没を迎えていないのに妖魔たちが湧き始めた事だ。
二つ目は雨が完全に上がった事。霧は残っているが夜を前に篝火を焚けるのは心強い。
そして最後に、川周辺の妖魔が想定の数段上をいく強さだった事。
「こ、れはっ……! 下がっていて下さいお二方!!」
ぶすりともぐさりともつかない鈍い音を立てて妖魔を斬って吼える辛新の背に庇われながら、舌打ちしたい衝動を堪える。隣では梅が剣を構えていた。梅が剣を抜く姿は初めて見る。
部隊はこれまでにないほど殺伐とし、橋で一列に伸びた前後から戦う兵士たちの声が響く。その中に時折悲鳴じみたものが混じるのを聞いては、玲馨はぐっと歯を食いしばった。
この期に及んでも玲馨の頭の中は戊陽の事でいっぱいだった。いや寧ろ、強力な妖魔に囲まれていくほどに、玲馨の不安は大きくなる。
妖魔祓いの力を、恐らく戊陽は使うつもりでいる。
日没を待たずに妖魔が出現したのは想定外ではあったものの、橋を渡り切らずに夜を迎えてしまう可能性は、林で立ち往生した時に考えていたはずだ。それでもなお引き返さずに行軍を再開させたのは、部隊全体を妖魔から守りきる算段が戊陽にあるからだ。その力を、戊陽だけが持っているからだ。
水の中から次々と飛び出してきては圧倒的な数で押し寄せてくる妖魔にどうにか対応しながらも、玲馨の視線は戊陽を探してさまよい続けている。
「はああっ!」
辛新が気合いの一閃を浴びせると、僅かに妖魔が途切れて橋の先を見通す隙間が出来た。東西に伸びた橋のほぼ中央、戊陽は李将軍と武官に守られながら、自身は剣を構えていないのを見つける。
「おい玲馨!!」
梅の焦ったような声のすぐ後に「オ゛ァ゛ッ」と気味の悪い呻き声が玲馨のすぐ真後ろで上がる。
「ぼさっとすんなって!」
「お前、剣が使えたのか」
「はあ?」
梅は玲馨に苛立つように答えながらも無駄の少ない動きで妖魔を次々と斬っていく。その立ち回りは禁軍の兵士たちにも引けを取らない。
そうか、と漸く腑に落ちた。戊陽が梅を選んだ理由だ。性格的な面で戊陽と梅の相性が良さそうだと玲馨が感じたように、逆もまた然りだったはず。梅と玲馨は性格的に相性が悪い。しかしそれでも梅を選んだのは、彼が武芸に覚えのある宦官だったからだ。辛新では心許ないと感じたのか、それとも──それとも他に何か理由があるのか。
今、ひとつ確かな事は、こうして戊陽に守られておきながら、玲馨には戊陽を守る術がないという事だ。
「梅、橋の中央に行きたい」
「この状況で何言ってんだよセンパイ。何か考えがあるのか?」
「いや無い。だが、陛下の近くに居た方が、安全になるかも知れないな」
「言ってる意味が、あ、おい! 待てって!」
ついてくるにせよ残るにせよ勝手にしろと思ったが、梅は結局玲馨についてきた。そればかりか玲馨に襲い掛かってくる妖魔を斬って露払いのような事までしてくれる。恩を売りたいのか、それとも戊陽からの密命でも帯びているのか。何にせよ戊陽の近くまで行くのに梅は大いに役立った。
橋の中央に近づくと、馬から降りていた戊陽がそれまで鞘に納めていた剣を引き抜くのが見えた。
「皇帝さんは何してんだ、あれ」
戊陽の周囲を固める将軍と武官たちは皇帝に指一本触れさせまいと必死の様相で剣を振るっている。その中心に立つ戊陽はまるで目の前で起きている戦闘が見えていないかのように、極めて集中していた。
ふと、戊陽の顔が上がる。
目が合ったような気がした。
次の瞬間、風か何か、目に見えないものが戊陽を発生源として円状に駆け抜けていった。
「……はえ?」
梅の間抜けな声が間近で上がる。兵士たちの戦いの音も止まっている。
橋の上全体が刹那の間静寂に包まれて、ザアアと川が流れる音が現実へと引き戻した。
「全軍、全速、前進──!!」
李将軍の角笛にも劣らぬほどの大号令が響き渡り、鍛えられた禁軍兵たちは一瞬の間に体勢を立て直して橋を渡り始める。
「ちょ、待て待て、何が起きた? 何が起きた!!」
釣られて走り出しながら梅が混乱の声を上げる。
玲馨はまだ戊陽を見ていた。
戊陽は橋に突き立てた剣を支えにしてどうにか倒れずにいるといった感じだ。すぐに李将軍が戊陽に手を貸し自分の駆る馬に戊陽を引き上げる。
玲馨と梅が橋の中央に着く頃には戊陽たちはとっくにその場を離れており、戊陽に声を掛ける事はかなわなかった。
そうこうしているうちに部隊の全員が橋を渡り切る。しかしそれも束の間、一度全滅していた妖魔があちこちで息を吹き返し、ゆらりとその影を夕日に照らし出した。
皮肉な事に、夜はこれから始まるのだ。
その後部隊は岳川から全速で離れながら東進し続け、街道が緩い傾斜を描き始める頃になると妖魔の力が弱まっていった。
後は東のまだまだ遠くに見える青々とした高い山を目指すだけだ。そこがこの旅の目的地、山芒である。
一難を乗り越えて、いつの間にか追いついてきた辛新と合流し、三人は野犬も出ない静かなあわいで溜息を漏らす。この辺りは妖魔避けの薬が効くようで、野営の準備が始まると妖魔はすっかり姿を消していた。
「大変でした……。初めて山芒を出た日はあの橋を迂回する道を行ったので、あんなにも岳側の妖魔が手強いとは」
少人数での移動なら森を切り開いた隘路を行く道が別にあるのだが、五十を越える一軍となるとそちらは使えない。
「それにしてもお二方は一体どこへおられたんですか? いつの間にか見失って心配していました」
「すいません、私の独断で持ち場を離れてしまったので」
「いえ、ご無事だったので良かったです」
控えめに笑ってみせた辛新は疲れは見えるが傷などはないようだった。
この旅はまさに命がけなのだ。
一説によると妖魔という存在は地脈の自浄作用のものだという。枯れた大地の手足となって、妖魔は生き物から生気を吸うのだ。
あわいや地脈について独自に調べ上げたらしいその手記はまだ玲馨が少年だった頃に読んだ物だ。その頃の知識が今になって思い起こされたが、しかしあの手記の内容の正誤について証明するものはなかった。
だが、と、玲馨はとぼとぼと天幕を立てている兵士たちを眺めて考える。
激しい戦闘があったとはいえ、初日の様子とまるで違い兵士たちはすっかり疲弊しきっている。かくいう玲馨も、今再び妖魔が襲ってきたら今度こそ逃げられない気がする。もしかすると、妖魔たちは傍に立つだけでも人間や馬など生き物から気を吸い取っているのかもしれない。
とにもかくにも、
「今夜は休みましょう」
異論などあるはずもなく、三人はそれぞれの天幕へ向かう。しかし、玲馨だけはそのまま自分の天幕へは行かず、戊陽が使っている天幕へと足を向けた。
戊陽の天幕の入り口で見張りをしている兵士は初日に見たのと同じ顔だった。恐らく玲馨の事を覚えていてくれるだろうが、既に休んでいるかも知れない事を考えるとここまで来て声を掛けるのを躊躇った。
せめてあの後戊陽がどうしていたかを訊こうと考えて足を進めようとすると、天幕の入り口を覆っていた布が中から持ち上がり、戊陽が外へと出て来た。
「玲馨?」
「あ……」と息のような声のような掠れた音が出るだけで、その先が続かない。顔を見ただけでほっとしてしまったらしい。
「おかしな顔をしてどうした?」
「ご無事で良かったと、思って……」
それは最も素直な感想だったのだが、今度は戊陽がおかしな顔をする番だった。拍子抜けしたのか眉尻も目尻も下がった顔は少し情けない。
「てっきり怒り出すかと思ったんだが」
「怒る? 私が陛下を怒鳴りつけるなど、首と別れる覚悟はまだしたくありません」
揺れる篝火の炎に合わせるように、ふ、と笑った戊陽の体も揺れる。
戊陽が笑った事で並々ならぬ雰囲気が漏れてしまったのだろう。見張りの兵士がそわそわしながら戊陽と玲馨をこっそり見比べている。
「中に入るか?」
玲馨は首を横に振った。
「休まれてください」
訊きたい事はあったが、兵士の視線が気になった。このまま天幕に入っても聞き耳を立てられていたらと思うとそう多くの事は訊けまい。
「分かった」
「では……失礼致します」
最後、戊陽は玲馨を安心させるように笑みを深めた。玲馨が心配して訪ねてきたのだと、戊陽には筒抜けだったようだ。
後ろ髪引かれる思いで戊陽のもとを立ち去り、自分の天幕へ戻っていく。
戊陽は無事だった。今はそれでいい。
*
残り二日となった行軍は存外呆気なく終わっていく。橋という最大の山場を戊陽の力で乗り越えたおかげで、本来の旅程内におさまる形で目的地へと到着する事になった。
「あ、見えてきましたよ!」
辛新が馬上から指差した先を視線で追うと、そこには山の麓となる位置に「芒守門」という扁額が掛かった牌楼──屋根のついた門──が見えた。
そこは嘗ての山芒の入り口であった場所だ。現在はあわいに含まれるため未登記の土地という事になる。門を管理する必要がなくなったため、扁額は錆びて屋根も朽ちて瓦が剥げてしまっていた。門から更に一時辰ほどなだらかな山道を進んだところが現在の山芒だ。
芒守門は古ぼけてしまっているが、周辺には橋から南西にあったあの枯れ林よりはずっと緑が残っていた。まだ地脈が僅かに大地を通っているからだろう。大木ほど嵐に耐えきれず折れているが、若木は枯れ葉を枝につけながらも懸命に根を生やし立っている。腐葉土のような匂いもほんの微かに地面から昇っていた。
紫沈から北玄海への道のりは多くが平野且つ荒野であった。途中川沿いを進む事にはなるが禿げた土地と黒く濁った川水よりも、枯れかけた今まさに命尽きようとしている森林地帯はよほど視覚的に悲惨さを伝えてくるようだ。
若い兵士たちの中には紫沈から出たことがなかった者も多いようで、彼らは辺りを痛ましいような物珍しいような目で見ていた。
日が中天にかかる頃、一行は長い六日の旅を終えて山芒最西端の街藍心に辿り着いた。
一行の先頭を李将軍と並び馬で進んでいた戊陽は、地方官吏らしき男に出迎えられて何かを話している様子が後方からもうかがえる。しかし残念ながら、いよいよここから玲馨たち三人は救助活動に向かう禁軍とはお別れだ。
「なーまずは宿探そうぜ宿。もうあっちこっち体バキバキよ」
「恐らく我々にも一時的に禁軍に貸し出される宿舎が割り当てられるはずだ」
「あ、はい! そのように仰せつかっております!」
「ほう? そりゃどこだ? 今すぐ案内せよ辛新!」
「はいー!」
玲馨の護衛にと遣わされたらしい不埒者と現役武官が相手では、体力面で玲馨に勝ち目は全くない。元気に駆けていった二人を見失わない程度に遅れてついていく事にする。
去り際、玲馨はちらと戊陽を見遣った。顔色はあまり優れないが今すぐ倒れるという事もなさそうだ。こちらはこちらで城に戻ってから訊き出さねばならない事が増えた。
あれもこれもと成すべき事ばかりが増えて、どれも一つと解決していない現状は非常に悩ましかった。
皇帝及び禁軍兵およそ五十名余り。あの橋の難戦では終ぞ一人も命を落とさなかった。妖魔に触れた者もあったが軽傷で済んでいる。
疲労が最高潮に達していた一行にあてがわれたのは嘗ては宿であった高楼で、まるまる一軒貸し切りだという。しかし実際には五十人全てが藍心に滞在する訳ではない。
支援物資を向家に届けた後は現地の状況を見て必要のない人員は紫沈にとんぼ返りである。五十人が各地に分散するならいざ知らず、全員がひとところに長く留まるとなると主に食料が足らなくなる。それでは本末転倒なので、禁軍のうち概ね半数ほどは数日のうちに帰還する事になるだろう。
更に言えば戊陽と李将軍も同じ高楼に泊まる訳ではないらしい。
さて、それらの事情を一応は把握している玲馨だが、玲馨たちとは既に関係のない事だ。高楼の一室に入った三人は年季の入った卓を囲んで腰を落ち着ける。
「それで、具体的にはどう調査をなさるんです? 詳細は玲馨さんに訊けとの事でしたので」
「川だ」
「と、言いますと?」
玲馨は高楼へと案内してくれた女性から借りてきた山芒のたいへん大雑把な──子供の落書きのような──地図を入った卓に広げると、山芒の山頂付近から続く大きな川を示す。
「岳川ですね」
「ここへ向かう」
「待て……待て待て待て! また川か!?」
お腹が空いたでしょうから、と案内の女性から貰ってしまった饅頭を一人で全部食べて転寝していた梅が、血相を変えて飛び起きる。
「もうあんな目に遭うのはこりごりだ!」
「調査は日中に行う。それに川と言っても今度は領内の川だ。夜に行ったところで妖魔が出る事はまずない」
「お、お~そうか、そうだったな」
焦ってしまったのが恥ずかしかったのか、梅は下手くそな口笛を吹いて誤魔化すが誤魔化せていない。
「あの、玲馨さん。岳川は恐らく支流も派流も多いと思いますが」
「この地図だと……本流しか書かれていないようです」
筆で豪快に書かれた一本の線は、果たして本流と呼んで良いかも甚だ怪しい。
「まずは岳川を詳しく書き込んだ地図を探す所からですね」
「ええ~、面倒くさ。俺寝てて」
「辛新殿はこの町には詳しいですか? 恐らく町の郷長なら農地と川の──」
「いえ玲馨さん、山芒はとても集権的なんです。領内の権力差という意味でならそれこそ中央以上に」
本流の一本だけが太い線で引かれた簡素な地図を見下ろして、玲馨は顎に手を当てる。
「まさか、川を記した地図一枚借りるのに、木王とお会いしなくてはならない……なんて言いませんね?」
「いいえいいえ。そのまさか、です」
ご明察とでも言わんばかりの口ぶりに、胃の腑がずっしりと重たくなる。
木王とは四王のうち東の領地を治める王の称号であり、現在は向家の領主がそれを務める。今頃戊陽が堅苦しい話をしているだろう相手だ。
いかに中央から派遣されてきたとはいえ所詮は宦官二人と下級武官一人だ。戊陽の部隊に同道していたが残念ながら皇帝の使いという立場ではなく、あくまで私的に山芒を訪れた唯の人でしかなかった。その裏には今回の調査は大っぴらにしたくはないという事情があるからなのだが。
つまり仮に玲馨が木王に個人的に拝謁出来る高級官吏だったとしても会う訳にはいかないのだ。
しかし、である。事は地図の話。山芒の詳細な地図をまさか木王だけが所持しているという事はないだろう。いかに集権的と言えど農地を直接管理しているのはその町や村の長なのだから彼らにとって地図は不可欠だ。
要は郷長から秘密裏に地図を拝借すれば良い。
それにしても、敵国の間諜でもあるまいに地図一つ手に入れるためだけに危険を犯さねばならないとは想像もしなかった。
「辛新、あんた確か山芒のどっかのお坊っちゃんて話だったよな?」
「はい! 藍心より更に北に家族が暮らしております」
「名家だってんなら地図くらい持ってるべ?」
見苦しく尻を掻きながら放った梅の盲点をつく一言に、玲馨と辛新は顔を見合わせて声を上げた。その手があったかと。
*
四合院という建築様式で造られた向家の屋敷は、日の字型に院子を二つ構えた造りになっている。後宮でも妃たちの宮は全て四合院になっているが、平地の紫沈とは違い東に向かって傾斜のある山芒に建てたこの屋敷は庭と庭の間の垂花門の前後に短い階がある。それは紫沈では見かけない珍しい造りだった。表門から見て正面が母屋で右手が客堂になっているらしい。
また通りから中を隠すために作られる影壁には龍が彫られた塑壁があった。あわいによって国が分断されてからというもの四王の土地は随分縁遠くなったが、戊陽の記憶によればこれは青龍と呼ばれる四神の一柱で山芒を守護する神の似姿である。青龍の力を借りたつまるところ魔除けの類だ。仮にあわいがここまで広がってきた所で、妖魔はこの門を易々とは突破出来ないだろう。
紫沈から連れてきた禁軍の兵士たちはひとまず藍心の高楼に留まらせ、戊陽は李将軍と二人でこの山芒の領主が住まう向家の屋敷へと来ていた。
垂花門を潜り客堂に入ると知らずと息が漏れていく。戊陽の額はうっすらと汗で湿っていた。
あの日、岳川の橋で戊陽は初めて妖魔祓いを行った。天幕を訪ねてきた玲馨に対して少々見栄を張った自覚があるだけに、つい休まずここまで来てしまった。しかし、見栄を張っただけでこれだけ動けているという事は、妖魔祓いの力は思った以上に体に対して負担があるものではないのかも知れない。もしも癒やしの力で妖魔と同じ数だけの傷病人に治癒を施していたら、数日は昏倒していただろう。
「陛下、今日一日休まれてからでもよろしかったのでは?」
武芸一辺倒で叩き上げの李将軍は無骨でやや愚直なところのある武人だ。鍛え上げた大きな肉体は見た目にも物理的にも威圧感があった。
一見すると恐ろしい男なのだが、全く気遣いが出来ない訳でもない。宮女たちが「お髭の将軍さん」と親しみを込めて影で呼んでいる事を戊陽は知っている。
──お髭の将軍さん……。
「陛下?」
「問題ない。これが済んだら休む」
この男は決してそんな可愛らしい名で呼んで良い男ではない。宮女たちも武器を構えた李将軍と一対一で対峙し、あの圧倒的な存在感を目の当たりにすれば恐ろしくて声も出せなくなるはずだ。
暫く待っていると侍女らしき女が複数入ってきて、菓子と茶が卓に並べられていく。所作が美しく、見目も良い。木王の趣味かと思っていると一人の侍女が李将軍と目があった。侍女は愛らしく微笑んでから一礼すると他の侍女たちと共に去っていく。
隣をちらりと横目に見ると李将軍は耳を真っ赤にしていた。わざとらしく咳払いをすると将軍はピンと背筋を伸ばしながらも気まずそうに視線を逸らす。
──お髭の将軍さん……。
李将軍からは剣術を学んだ事もある。あの当時の李将軍に戊陽が「お髭の将軍さん」だなどと言えばたちまち鋭い一撃を打ち込まれた事だろう。
──国最高の武人の弱点は、女の笑顔だったか。
いかめしい最高位の武官と愛らしい侍女との遣り取りに和んだのはつかの間の事だった。
「木王、向青倫、此度の陛下の御厚誼に感謝申し上げる」
文官風の男に付き添われてやってきた五十過ぎの男は緩慢に拱手すると、些か過ぎるくらいに恭しく言った。
向青倫──。この屋敷の、引いては山芒全てを取り仕切る領主の登場によってその場の空気は一瞬で張り詰めた。
「良い。面を上げよ。私はまだ何も成しておらぬ」
「はっ」
所作の一つ一つにゆとりがあり、そして重い。人間として培ってきた厚みが如実に表れている。仮に戊陽が今も皇弟の立場だったとしてもこの男よりもずっと貴い生まれだ。だけど格が違うと思わされる。
ふと、隣で身動ぐ気配を感じた。李将軍だ。この将軍さんは無骨だが、気遣いの出来る男であった事を思い出す。向青倫が現れてから急激に冷え始めていた指先に、少しずつ熱が戻ってくるのを感じた。
「向青倫」
自分自身を仕切り直し、改めて向青倫を正面から見据える。
この男は狸だ。
戊陽が即位して二年余り。直接会って言葉を交わしたのは即位式のただの一度きり。以来、宮廷で執り行われる祭儀にも自分は隠居のようなものと宣い、代わりに息子を遣わしたという経緯がある。
この男を憎いとは思わないが、おいそれと向青倫の取ってきた態度を許すことは戊陽の座る椅子が許さない。
「単刀直入に訊く。此度、私をここまで呼びつけたのはそなたの企てか?」
正面の椅子に腰掛けた向青倫の黒鳶色の瞳が戊陽を見つめる。頭は白髪混じりでも目はひとつも濁っていない。何が隠居かと胸の内で揶揄する。
「企てとは滅相もない。此度の事は地下水の放出による事故で御座います。兵は消耗し、東の練族の略奪行為が今起きれば対応は厳しい。妖魔はあわいより外へは出ませんが、万に一つという事もありましょう。領地を預かる四王が一人として、恥を忍んでお助け願った所存に御座います」
事前に準備していた台詞かもしれないが、それにしたってよく回る舌だ。
向青倫の口から出た練族とは東の遊牧民族の事だ。山芒の東に位置する山を越えた先には高原が広がっており、そこには古くから遊牧の民が暮らしている。彼らの事を沈では練族と呼んだ。
嘗ては峠を境にして互いに不干渉を貫いていたが、七十年ほど前から練族からの一方的な侵略及び略奪行為が繰り返されるようになった。原因は東の高原にもあわいが広がっているからではないかと言われている。
侵攻はそう頻繁ではない。早くて一年、平均すると数年に一度で侵攻してくると先々代皇帝の時代の報告にはあった。これは年々減少傾向にあり、高原より先は絶海という地形から練族の人口が減少しているのではないかと推測されている。
戊陽は救援部隊が編成されるまでの三日の間、公務の合間に山芒や向家について可能な限り調べていた。それを頭の中で思い返しながら向青倫と相対する。
「今の山芒には何が不足している?」
人か、物か、兵力か。
「有事への備えはある。答えよ、向青倫」
この男は何故山芒から出てこない?
本当に戊陽を見下しているからか。それとも、何かを恐れているのか、或いは何かを画策しているのか。
「……禁軍の兵力を、この向青倫に預けて頂けますかな」
向青倫は殊更下手に出るという事はしなかった。口振りとしては断っても構わないと言っているようにも聞こえる。
試しているのか。あろうことか自身が仕える君主を。
だとしたら戊陽の答えは決まっている。
「千だ」
向青倫の憂いを取り払うのに必要な兵の数を、戊陽は千と見立てた。
「どうだ。足りるか、向青倫」
山芒軍四千に対して千を動員するとくれば十分に兵力の補強となるだろう。
千の兵士をただ派兵するのではない。戦線を維持するのに必要な軍需もある程度支援するのだ。
そのためにかかる経費はどれほどか。食糧は勿論、あわいを往復するのに必要な馬に人員、千の兵を駐屯させるのに簡易の宿舎を建てる必要も出てくるだろう。それらを支援すると、戊陽は言っている。
傍に控えた李将軍の脳裏には胃をキリキリさせる宰相の顔が浮かぶが戊陽には見えていない。国とはそうあるべきなのだ。何より長らく皇帝らしく振る舞う事が出来なかった戊陽としては、これが宮廷内の改革のきっかけにならないかとさえ考えていた。
向青倫にこれといって驚いた様子はなかった。かと言ってまんまと皇帝を騙してやったという風でもなく、暫くの間黙考しているようだった。
「戊陽皇帝陛下。まずは岳川付近に起きた事故についてお話し致しましょう。陛下がお連れ下さった兵にも働いてもらわねばなりませぬ故」
*
戊陽が向青倫と対峙していたその頃、玲馨たちは辛新が実家から借りてきた地図を片手に岳川の支流のうちの一つを目指していた。
山芒は一つの大きな山岳地帯を内包する土地で、山間に村落を築き生活している。おかげで人里を離れるとどこもかしこも木々や崖に行く手を阻まれた。峠を越すと高原だと聞くが、それが嘘のように山肌は森林に覆われている。
また、岳川の支流も多かった。その中で藍心から近く比較的大きな支流へ向かっているのだが、山の斜面である事に加えて人の手があまり入っていない林の中と、とにかく隘路が続いて玲馨はすっかり息が上がってしまっていた。
「はー……。何も着いた当日に行かなくてもよぉ」
文句を垂れている梅だが、見るからに彼が最も余力を残している。一方、汀彩城を歩き回る以外に体を鍛える機会の無い玲馨は全身汗だくだった。
「まぁまぁ梅さん。少しでも早く調査を進めようとなさる玲馨さんの姿勢はご立派ですよ」
辛新は馬を降りたが山芒が地元とあって山歩きに長けている。梅ほどではないにせよ彼も十分に余裕が見えた。もはや喋るのも億劫になっていた玲馨は二人には取り合わず黙々と歩いていく。
辛新が藍心出身ではなかったのと地図だけでは心許ないと考えて、藍心から山に入る前に地元の人間に道を訊ねていた。
農夫の話では支流まではずっと一本の道が続くという事だったが、果たしてこれは道と言えるだろうか。途中渡った吊橋付近から目に見えて悪路となり、辛うじて獣道という体裁のそれをもう半時辰ほど歩いている。藍心を出たのが正午をとっくに過ぎていた事を思えば、そろそろ引き返す事も視野に入れなくてはならない。山芒は紫沈よりも日没が早いと聞く。
「あ、思い出しました。こういう道を地元じゃ豚の畦道っていうんです」
「豚? 猪じゃなくてか?」
「はい。山芒に伝わる昔話に、飼っていた豚が飼い主を嫌って脱走して豚の国を築くという話があるんですが、体の大きい豚が群れを成して山を練り歩いたために出来た道が登場するんです」
「はーん。で、飼い主は豚だろうと大事にしましょうねーって落ちだな」
「よそではそうなんですか? 山芒だと、豚に国を築くなど到底無理な話だと悟った豚は反省して飼い主の所に帰ってきますね」
「何だそりゃ。ますます飼い主が調子に乗るだけじゃねぇか」
集権的な山芒らしいといえばそうだろう。似たようなお伽話は紫沈にもあるが、要は身の丈に合わない事をやるべきではないといった教訓を子供に分かりやすく伝えるためのものだ。
身の丈に合わない事──。
宦官が秘密裏に皇帝の勅命を受けて四王の土地を探るというのは果たしてどうなのだろう。身の丈という言葉には、宦官を当てるのか、それとも玲馨を当てるのか。
地図一つ得るのに間諜のような事をと困惑したが、玲馨のこれは間諜そのものでなくて何だろうか。北玄海の際は文官がきちんと任命を受けている上、北玄海の刺史と地方官吏が対応し、最終的には皇帝へと報告をしているので今回とは事情が異なる。
あれ? と玲馨は首を傾げる。
──今回私は、ここで何を探るのが正解なのか。
玲馨は思索にふけっていく。
ともすれば山芒の王である向青倫の痛い腹を探らなくてはならないかも知れない、という事まではおおよそ覚悟していたが、それだけではないのだろうか。
北玄海の岳川の「治水」と岳川上流である山芒。この間にどんな繋がりがあるのかを探るだけのはずだが、仮にそれだけではないとしたら?
玲馨の手足になる者として戊陽は梅をつけた。そういえば結局梅と別行動をする事は叶わなかったが今にしてそれで良かったという気がしている。梅は腕の立つ宦官だった。「羅清」という梅の旧名の名乗りを聞いて戊陽に驚いた様子はなかったのだから、宦官になる以前の経験を知っていて玲馨の「護衛」につけたのだ。
護衛──戦闘が起こる事を戊陽は予測している。そして戊陽は山芒までの旅で梅と行動するかを判断しろと言ったが、あれは梅の剣の腕前を玲馨にその目で確かめさせたかったからと考えて良いだろう。実際に梅の戦い方を見て玲馨は何と思ったのだったか。
『その立ち回りは禁軍の兵士たちにも引けを取らない』
『辛新では心許ないと感じたのか、それとも──それとも他に何か理由があるのか』
「ん? 川の音がしますね。心無しか空気も涼んできたような」
玲馨を思索から引き戻したのは辛新の屈託のない声だった。
「少し見てきますね。お二方は待っていて下さい!」
先頭を進んでいた辛新が歩調を早め、一足先に道向こうを確かめに行く。すぐに戻ってきた辛新は晴れやかな顔で「ありましたよ!」と報告した。
「豚の畦道」の終点から苔むした下り坂が続いており、少し下ると目的の川岸に出た。
川は小規模だが上流が連瀑帯になっており、水深は極めて浅く、少し下流に行った所に本流との合流地点があった。川の音がしたのは小さな滝壺に水が落ちる音だったようだ。
滝壺を囲うようにして谷間になっており、対岸に向かって水深が深くなっているように見える。
「梅、対岸から石を拾ってこい」
「は? 何で俺が」
玲馨は視線をまず自分の足元に向け、次いで辛新を経由し最後に梅を見る。
「あー? ……ったくよぉ。足が濡れたくないのは俺だって一緒だぜ?」
ぶつぶつ言いながらも梅は浅い川をざぶざぶいわせながら対岸に渡っていく。
三人とも袍に袴を身に着けていたが、梅だけが革の長靴を履いていた。梅を行かせた理由はそれだけだ。
「梅さんは面白い人です。それに頼りになります」
対岸に着いた梅は崖から剥き出しになった岩に片手をついていくつか水底に沈んでいた石を拾っている。
「……そうですね。役に立つ者です」
橋の上での事を思い出した。梅が居なければ、今回の行軍は死者一名になっていた事だろう。自分の背中を狙っていた妖魔に玲馨は気付いていなかった。それを斬ったのは梅だ。
玲馨と辛新が水に濡れない安全地帯から眺めているのを水の中から見た梅は「こういうのでいーんだな?」と叫びながら石を投げてくる。石を投げるなどぞっとしないが、投げられた石は二人の手前で落ちてばしゃりと水を跳ねさせた。
「……前言撤回だ」
水底に沈むのだから投げた石がどれかなんて分かるはずがない。
濡れた顔を手で拭いながら梅をじっとりと睨みつけた。
「よく川がおかしいって気付いたな」
梅が川辺にあった大きな岩のような石に寄りかかりながら気怠げに話す。
「対岸で土砂崩れでもあったんでしょうか?」
梅はさほど興味がなさそうなのに対して、辛新は玲馨の調査に少し興味が湧いてきたのか梅が拾ってきた石と足元にあった石をしげしげと見比べながら訊ねた。
上流から見て左手にある川岸の水底にあった石は角が鋭利で全体的に四角いのに対し、玲馨たちが立っている右岸の石はどれもつるりと丸い。これは嘗ては玲馨たちの場所まで水の流れがあった事を意味するが、では左岸は?
「土砂崩れがあったかどうかは農夫に聞けば恐らく分かるでしょう」
左岸は剥き出しになった岩を覆うように木の根が伸びている。それは岩肌に張り付くのではなく、紐暖簾のように垂れ下がっている。岩の天井からは地面がせり出しており、本来ならその先にまだ地面が続いていたかのように見えた。木は崖上で辛うじて倒れずにいるようだが、大雨などで地盤が緩めばどうなるか分からない。土砂崩れというより崖崩れがあったと言った方が正しいだろう。
仮にここで崖崩れが起こったと仮定すると、川の形が変わった事になる。その変化が本流へどれだけ影響があったか分からないが、岳川はいくつも支流と合流しながらあわいと北玄海を経由し、北方に広がる海まで流れ出る。
そして北玄海では最近、治水と称して領地を広げている。つまり岳川に向かって川岸を舗装し、舗装したからには領地であるという主張だ。更に舗装された川の近くにはもともと浮民が住んでいた。舗装した川までを領地とするなら浮民も領民になるのだと、これが北玄海で記録の上で人口が増大している理由だ。何もよそから人を攫って増やしているのではなく、元からそこにいた浮浪者たちに戸籍登録をさせているのだ。
やはり繋がるのか、岳川上流の動きと、北玄海の領地拡大が。
「おい玲馨、ぼーっとしてねぇで、気が済んだならそろそろ戻るぞ」
言うが早いか梅は先に「豚の畦道」の方へ向かい出す。
玲馨は梅が拾ってきた石を川に放り投げる。パシンッと音を立てて水面を揺らし、角張った小石が丸い石の中に混じって底に沈んでいった。もう玲馨の目からはどれが角張った石か分からないが、そこには確かに他の石とは違う左岸の石が沈んでいる。
「お前は礼儀と作法を身に着けろ梅。素首を落とされていいなら構わないが」
「素っ首ねぇ。あんたも性格に似合わない言葉遣いはやめといたらどうだ?」
梅が言っているのはどっちだろうか。梅に対する言葉遣いと辛新に対する言葉遣い。どちらが玲馨に似合いだと言っているのだろうか。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
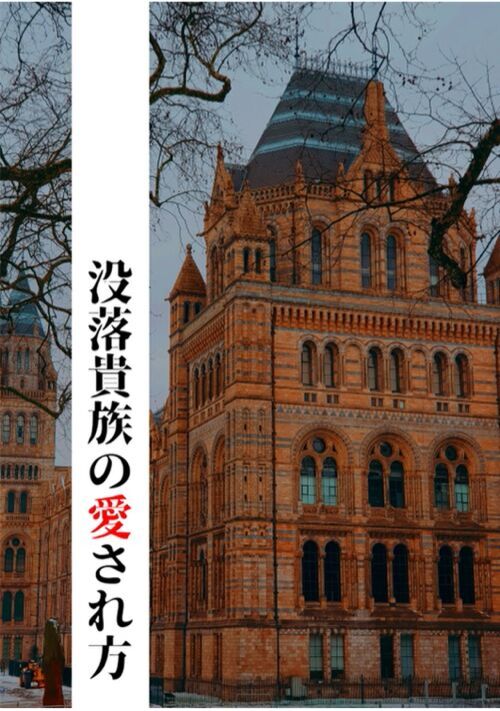
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















