8 / 44
山芒編
8友
しおりを挟む
三つ並んだうち三番目の房に入れと言われ、一番奥の鉄扉を開ける。途端むわっと鼻を衝いた匂いが何の物かは考えないようにした。
「名は玲馨、十二歳で間違いないな」
「はい」
ここは浄身するための処置室だ。執刀医らしき男が一人、他に大人が二人。腰を曲げなくても良いような高さの広い台があって、玲馨はそこに寝かされるらしい。
目につく道具のほとんどが何に使われる物なのかが分からない。無愛想な大人たちの態度も恐怖心を煽ってくる。
大丈夫、大丈夫。自分に言い聞かせるように心の中で唱える。
これを終えたら猿猿との約束がある。戊陽が後宮で待っている。
玲馨には怖いものがたくさんある。玲馨は怖がりだ。だけど自分にはやるべき事、やりたい事があると思うと少しだけ、本当に少しだけ怖さが紛れていくようだった。
淡々と準備を進めていく執刀医がふと手を止めて「泣かないのか。偉いな」と言った。
*
処置が終わり、最初の二日ほどは痛みで意識が朦朧としていた。三日目になると医師がやってきてまた痛みを伴う処置を施してから「成功だよ」と端的に告げた。
成功の言葉に喜べるような余裕は一切なく、尚も続く苦痛に昼も夜もなく悶え苦しんだ。
そんな日が一週間ほど続いた頃、玲馨の検診をしていた医師の表情が芳しくない事に気付く。
「……私は、何かおかしいですか?」
意識があると思われていなかったようで医師の表情は驚きに変わる。
「体が熱いだろう」
「はい……」
「このまま熱が下がらないと、危ないかもしれない」
──危ない? 何が?
何が危ないというのか。はっきりと言葉にしてほしくて医師の袖を掴んで引っ張った。
「お前が悪いのではない。こういうのは天運によるものだ」
「てん、うん……?」
話が噛み合っていない。玲馨は自分で自分を責めてなどいないし、欲しかった答えとは違っている。
しかし医師は最後まで詳しく説明する事なく、気休めのようにいつもより薬を多く置いていった。苦くて飲むたび喉奥でえずいてしまう嫌いな薬だ。飲むと眠くなるけど、起きた時の夢から醒めきらないような怠さが厄介な薬。
いつもは嫌いでも患部の痛みに耐えきれず薬を飲まずにはいられなかったのに、今日は飲みたくないと思った。飲んだらもう次は目が覚めないような気がして、ゾッと背筋を恐怖と悪寒が駆け上がっていった。
全身に冷たい嫌な汗が浮かんでいるのに、全身はじりじりと火で炙られているように熱感が消えない。
死ぬのかと思った時、浄身でも泣かなかった玲馨の目に涙が滲んだ。
怖かった事、辛かった事、玲馨はこれまでたくさん耐えてたくさん乗り越えてきた。
知らない事は怖い事だと思った。けれど死は無理だ。死は越えられない。この先死ぬのだと知っても、ちっとも恐怖は和らがない。
「──から、……くれ」
玲馨が寝ている部屋の外から声が聞こえた。水の中にいるような朦朧とした意識の中でも戊陽の声だとすぐに分かった。
血相を変えて部屋に入ってきた戊陽は、ついてきていたいつもの宦官を中には入れずに扉を閉めた。一瞬入り込んだ日差しがす……と途切れて暗くなり、そういえばこの部屋には窓のような物がない事に今更気付く。
「……うーやん、殿下」
部屋に二人きりだけになると一度驚きで止まっていた涙がまた溢れ出し、戊陽の名前を呼びながら必死に手を伸ばした。
「玲馨……。遅くなった。すまない」
「殿下、私は」
「ん?」
「約束をしました。一緒に、勉強をすると、約束を……」
「大丈夫だ。俺が必ず会わせてやるから」
「猿猿と、共に後宮へ仕えようと」
「……」
玲馨の手を力強く握っていた戊陽の手が一瞬、硬く強張った。
「死んだら、会えません」
何も言わない戊陽の手は冷たかった。玲馨の手が熱過ぎるのだ。
「私、は……お、男に股を開かされ、母に捨てられて、男の象徴を失っても、私は生きていました。だけど、これから死ぬのだと知って、私は、怖いと……怖いんです、戊陽っ、死にたくない……っ!」
玲馨、と静かに名を呼んで戊陽はそれ以上何も言わなかった。ただ、いつかそうしたように、玲馨の手を握り祈るようにして目を閉じている。玲馨の手を額に当てて、そこからじんわりと熱のようなものが伝わって。
そこで玲馨は眠りに落ちていった。眠る瞬間も戊陽が居てくれると思うと恐ろしさはそこにはなく、浄身してから薬を使わずに眠れたのは初めての事だった。
次に目が覚めると体を怠くさせていた熱感も、患部の痛みもすっかり消えていた。
恐る恐る自分の股に手をやってみる。痛くはない。ついでにあるべきものもない。それは奇妙な感覚で落ち着かない感じがあるが、何よりあの苦痛がさっぱりなくなってしまった事の方が大きかった。
──殿下は?
室内には玲馨一人だ。窓がないので時間が分からないし、どれくらい眠っていたかも分からない。
玲馨は体をずらして寝台の端に腰掛けると、そっと足を地面についてみる。長くまともに食事を取っていないのでフラつく感じはあるものの、立ち上がり、歩く事が出来た。
もっと小さかった頃は転ぶのが怖くて床を這いつくばっていた事を思い出しながら、壁に手を付き歩を進める。今では転ぶ事はもうそんなに怖くはなくなっていた。
角を曲がるとすぐに灯りが見えた。大人の話し声のようなものが聞こえると思ったが、どうも誰かが怒鳴る声のようだ。
「いいからここに呼べ」
「さきほどから何度も言っておりますが、令状などを確認出来なくては私どもも仕事ですので」
「黙れ! 皇子を害した子供を、貴様らは庇い立てしているんだぞ!」
壁か扉を殴ったような激しい音がして、男の厳しい声が壁越しにいる玲馨の所まではっきり聞こえてくる。
玲馨は音を立てないようゆっくり廊下を進み、声のする所まで行く。どうやら怒鳴られている方は通せんぼをするように扉の前に立っているらしい。その正面に怒鳴り続けている男が居る。
「子供の連続死の件、お前に類が及ぶかも知れんがそれでいいんだなぁ?」
「……卑怯な」
足音がする。それは扉から去っていく。
まずいと思った時には既に遅く、目の前の扉が勢いよくこちら側に向かって開かれて、玲馨の体は軽々と吹っ飛んだ。
「何だ? 誰だお前は。名を名乗れ」
「あ……」
怖い。怖い。
筋骨隆々とした大きな体は、玲馨の恐怖の象徴だ。伸ばしっぱなしの顎髭に、彫りの深い顔。声が大きく気に入らないとすぐに怒鳴る。
そういう男はたくさん居た。よく相手をさせられた。あの男たちは金払いが良かったのだ。
声も出せず震えている玲馨の片腕を掴み男が引っ張り上げる。すっかり足から力が抜けており、肩が悲鳴を上げた。
「い゛っ、ぅっ」
「名を名乗れと言ったのが聞こえなかったのか」
名乗ってはいけないという予感がある。だが今ここで偽名を使ったとてすぐに嘘だと見抜かれるだろうし、そうなった後が恐ろしかった。
「り──」
「玲馨です。その少年の名は玲馨」
玲馨の代わりに答えたのは、扉を通せんぼしていた男だった。恐らく執刀医だ。
どうしてか裏切られたような気分になって、がたいの良い男越しに執刀医を見ると目を逸らされた。
「ふむ。お前が玲馨か。来い。貴様は皇子を害した罪に問われる」
「罪……?」
身に覚えなんてあるはずがない。正確な日数は分からないが自分は十日ばかりここで生死の境を彷徨っていたのだ。それに何より皇子は戊陽の事しか知らなければ、彼に対して害意なんてとんでもない事だった。
「あ、あの、私は知らな」
「知らない? では何故、貴様は生きている? 貴様は本来死ぬはずだった。違うか?」
その言葉で分かった。害された皇子とは戊陽の事だ。だが何故、その罪を玲馨に問うのか。
言い返せずにいると男は玲馨の腕を引いて部屋から出ていこうとする。玲馨は抵抗しかけるも体が言う事を聞いてくれず、震えながら男に従って外へ出た。
「おや、玲馨。浄身を済ませたのか」
玲馨は、耳を疑った。視線を上げて、声の主を確かめて、どんな顔をしていいか分からなくなる。
病棟から出たところで待っていたのは永参だった。永参に声を掛けられたのは彼に部屋を追い出されたあの日以来だ。
「これを猿猿が僕に預けていったんだ。猿猿が戻らなかったらお前に渡してくれとね」
「小猿が……?」
永参は何かを投げて寄越した。平べったいそれは宙を斜めに横切るようにして玲馨の足元へ落ちる。男が腕を放してくれたので拾い上げるとそれは折りたたまれた紙だった。書き損じを使ったものではない、綺麗な紙だ。
「あれは僕とお前の事を勘違いしている可哀想な子供だったな。だが悪い子ではなかったよ。その手紙を預かるくらいの事はしてやっても良いと思える子供だった」
媚びを売る猿のような下品さは気に入らなかったけどね──。
耳を塞ぎたくなるような捨て台詞を吐いて永参は去っていく。その背中に石を投げてやりたくなった。
玲馨は猿猿からの手紙を読もうとしたのだが、男がまた玲馨の腕を掴むので慌てて懐にしまい込む。
「お前は性悪の永参と同室だったんだってなぁ?」
男は玲馨の腕を自分の方へ向かって強く引くと、玲馨の顎を片手で捉えてねぶるような視線で玲馨の顔を見回した。嫌悪感で背筋が粟立つも、玲馨は嫌だと突っぱねる事は出来ない。
「いっちょまえに綺麗な顔してやがるじゃねぇか」
玲馨はこれから何をされるのかすぐに察した。
案の定男は歩幅の違いも気にせず足早に歩いて倉庫のような建物の影に玲馨を連れて行く。
逃げたい。戊陽に何があったのか確かめなくてはいけない。それに猿猿からの手紙もある。
だけど抵抗すれば男は容赦なく玲馨を殴るだろう。無理矢理組敷かれて強引に暴かれて、大人しく従うよりもずっと苦しい目に遭うのが分かりきっている。
そうこうしているうちに男は玲馨に膝をつかせると、袴を寛げてまだ兆していないだらしなく垂れ下がった陰茎を取り出し持ち上げた。ぐ、と頭を掴まれて鼻が触れそうな位置に陰茎がぶら下がる。
「咥えろ」
言われずとも分かっていた。分かっていたが、玲馨は大人しく言うことを聞いてしまいそうになる自分をどうにか押さえ込んでいた。
「……ああそうか。永参に後ろは仕込まれても、あいつにはこれがついてないからなぁ!」
嫌な笑い声を立てて男は陰茎でぺちぺちと玲馨の頬を叩いた。
「仕方ねぇ、俺が教えてやるよ。じっくりとな」
そんな事されずとも、玲馨はよっぽどそれの咥え方を知っている。舌の動き、喉の使い方、暇な手で竿と玉を刺激してやればよく褒められた。
「ほら、口開けろ。歯は立てるなよ」
顎の関節に指を差し込まれると痛みで勝手に口が開いてしまう。抵抗しようとしても痛みがそれを許さない。
母に言われて男に抱かれていた時の方がまだ良かった。あれには金という対価が支払われていた。永参はどうしようもない人間だが手荒くされたのは最後の一度きりで、やはり勉学という対価をくれた。
ではこの男は? この男は玲馨に何をくれるだろうか。
無理やり開かされた口の中に悪臭を放つそれがねじ込まれる。ふにゃりとしたそれはあっという間に口の中で強張りはじめ、芯が出来てくる。
「子供ってのは舌も小せぇのか?」
文句を言う割には硬さはもう十分なくらい膨れており、玲馨の口では全体を含めないほど勃起していた。
「あー……上手ぇなおい……はっ、永参は玩具でも舐めさせてたか?」
舌に苦いような渋いようなえぐみのある味が広がった。
もうこんな事は永参で最後だと思ったのに。どうしてこんな目に遭わなくてはならないのか。
男の先走りはどんどん溢れて涎と混じって玲馨の顎を汚していく。男はもうすっかり夢中になっており、玲馨の頭から手が離れていた。
抵抗するなら今しかない──そう思った時、玲馨は男のそれを思い切り噛んだ。
「いぎあああっ!!!」
それは酷い悲鳴を上げて男は玲馨の顔を咄嗟に殴り突き飛ばす。男は目に涙を浮かべて股を押さえもんどり打った。
「く、そが、ふざけんなよ、クソガキがぁ……っ」
玲馨は噛まれるより痛い思いをして浄身したのだと思うと、泣いて吠えるばかりの男は酷く情けなく見えた。
体はもうフラフラで走っているつもりが歩いてしまっているが、懸命に男の傍から離れた。
まずは戊陽の様子を確かめるために後宮に行かなくてはいけない。だがどうやって中へと入ろうか。
逃げながら考えて、玲馨はある事を思いついて病棟の方へと引き返す。あそこには玲馨が受け取りそこねた宝があるはずだ。
宦官はその身が浄身済みである証明に、切り落とした一物を宝と呼んで大切に持っていなくてはいけない。それがあれば、玲馨も後宮に入れてもらえるだろうと考えた。
宦官を作るためだけに建てられた棟はこじんまりとしていて屋根や壁も粗末だ。
出てきた時と同じ木戸を開けて中へ飛び込むと、玲馨の名を勝手に教えたあの執刀医がそこに居た。
「何だ。騒がしくするな」
「あの、私の宝を」
「ああ……」
執刀医はすぐに小さな箱を取り出して玲馨に渡してくれる。木箱はとても軽くて、あの想像を絶する痛みによって切り離したものはこんなにも軽いものだったのかと驚く。
「本当なら忘れてったら金を取るんだがな、俺はお前に対して仕事をやり遂げられなかった借りがある」
宦官はその存在を蔑ろにされる事も多いが、だからといって徒に傷付けたり命を奪ったりして良いものではない。執刀医たちには当然宦官たちを預かる責任があるし、玲馨があのまま男に殺されたりして行方が知れなくなれば、責任は執刀医に問われる事になっただろう。
彼はその事について謝罪をする気はないらしい。だがもう玲馨はどうでも良かった。体が万全ではないので考えるのが億劫になっていた。
箱を懐に仕舞うと、その指先に何かが触れた。猿猿からの手紙だ。読みたいと思う気持ちを堪えてとにかく後宮へと急いだ。
「はぁ……はぁ……」
後宮まで後僅かに迫る頃、西の空で日が傾き始めていた。今ちょうど申の刻くらいだ。
後宮へ続く門は二箇所あり、一つは黄麟宮と呼ばれる皇帝の寝所からの直通だ。もちろんそこは通れないので、宦官の宿舎側にある門を通らなくてはならない。
しかし後少し行けばもう門が見えてくるというのに足が立たなくなり始めていた。
少しだけ休憩しようと考えて、木の根本に座り込む。屈んだ拍子に腹の辺りで何か触る感触があった。猿猿の手紙だ。
取り出してみると少し端が折れてしまっていた。これ以上折れたりしないよう丁寧に開いていき、手本のような形の字が並ぶそれを読み始めた。
『玲馨がこれを読んでるって事は、きっと僕は死んじゃったんだね』
「えっ……?」
思わず声が出ていた。冒頭からなんて事を書くのだと思ったが、頭の中に何か引っ掛かるものがあった。
『永参先輩に頼んでおいたの。僕が戻らなかったらこの手紙を玲馨に渡して下さいって。永参先輩、僕の事あんまり好きじゃないみたいだけど、お願い聞いてくれるといいなぁ』
『これを猿猿が僕に預けていったんだ。猿猿が戻らなかったらお前に渡してくれとね』
書いてある事と全く同じことを永参は言っていなかっただろうか。
『あのね、僕玲馨の事優しくないって言ったけど、玲馨は本当は誰よりも優しいのかもなぁって思ってる。うーんでもやっぱり違うかも? 誠実って言うのかなぁ? 嘘つけない所が僕は好き』
ところどころ字を間違えているが、書体は綺麗で読みやすく、紙に墨跳ねも無い。筆の使い方が丁寧で器用なのだ。
『だから僕も本当の事話す。本当はね、玲馨が皇子様にお仕えするのが決まってるって知った時すごくすごく羨ましかった。腹が立った。何で僕じゃなかったんだろうって思った。ううん、本当はもっと前、皇子様と知り合ってた事からもうすっごい嫉妬してたの。玲馨みたいに綺麗なのが好きなら、僕みたいに可愛いのでもいいじゃん! って』
玲馨を好きだと言ってくれたが文面はあまりにあけすけでいっそ嫌悪感すら見えるようだ。ひょっとすると最初は玲馨の事を嫌っていたのかも知れない。
『だけど玲馨と話すようになってから、僕きっと玲馨に憧れてたの。あーこれ書くのすっごく恥ずかしい! 玲馨は自分の事どう思う? 玲馨はね頑固なんだよ。芯があるの。譲らない事は絶対に譲らない。僕はきっと譲っちゃうんだ。大切なものだって、僕はいざって時に手放しちゃう。もしかしたら大切だって気付かないのかも。お母さんと一緒にいる事を選ばなかったみたいに。お母さんもきっと同じで、僕と一緒に居て死ぬ事より、お互い別れて生きる事を選んじゃった。おかげで僕たちはもう二度と会えない。二度と会えないのと、一緒に死んじゃうの、どっちが幸せだったんだろうね』
もしこれを面と向かって猿猿に訊ねられてもやっぱり玲馨は答えられなかっただろう。だけどこの本音は彼の口から聞きたかったと思ってしまう。時間がかかってもいつか答えを見つけたいと思う。
本当にもう猿猿は居ないのだろうか。もう答えを届ける相手は居なくなったのだろうか。
『どうせ玲馨は答えてくれないんだよね。意地悪なんじゃなくて、きっと上手く答えられないんだって思ってたけど、本当はどうだった? 僕の事、どう思ってた? ねぇ玲馨』
猿猿が戻って来ていないのは、永参の勘違いだと思いたい。だけど永参はもはや玲馨への興味をなくしている。いっそ恨みすらしている。そんな玲馨が晴れて本当に「少年」ではなくなって、生死を彷徨い心身がボロボロになっていたあの瞬間に、この手紙を届ける事で玲馨がどんなに辛い思いをするか、永参はよく分かっていただろう。玲馨は生きて、猿猿は死んでいる。それを知らしめられるから永参はわざわざ手紙を運んだのだ。
だからこの手紙が玲馨に届けられたのは勘違いなどではないと確信出来た。
『この手紙、玲馨に届かないといいなぁ。そしたらいつか、ちゃんと自分で玲馨に全部話せるもんね』
手紙はそれで終わりだった。別れの言葉も何もない、素っ気ない終わり方。紙にはまだ少し余白があったが、最後の一文は掠れていた。墨が足りなくなったのかもしれない。もしくは、もっと別の理由で書けなかったのか。
実感の無い喪失感は、玲馨の頭の中を空っぽに浚っていって、しばらくの間玲馨はその場から動けなかった。
手紙を風で飛ばされたり汚したりしないよう折り目に沿って畳んで懐に仕舞いこむ。
再び戊陽の元へ行かなくてはと腰を上げたのは、西の空が真っ赤に燃え始める頃だった。
後宮へ続く門には門番の兵士が二人立っており、拱手する玲馨の姿を見た彼らは槍を構えて通れなくする。
兵士たちは玲馨を襲ったあの体格の良い男と同じ格好をしていた。あの男は兵士だったようだ。
「お前は、宦官の少年か……?」
「あの、これを」
玲馨は懐から宝の入った木箱を取り出し両手に乗せて恭しく掲げた。
「中身は私の宝です。浄身を終えた身ですのでここを通して頂けませんか」
頭を下げた向こうで兵士二人が困惑したように囁きあっている。「何か聞いてるか?」「いや何も」「どの宮の宦官だ?」「待て。俺はこいつの顔を初めて見るぞ」
怪しい、という意見で一致した兵士たちは槍を構えたままじりじりと玲馨へ躙り寄ってくる。
玲馨は戊陽の様子を確かめたいだけで悪さをしようというのではない。どうすればそれを分かってもらえるか懸命に知恵を絞る。
「どうしたのです、何かの騒ぎですか?」
「あなたは……」
「と、東妃様!」
槍を下げた兵士はさっと抱拳礼をして、門の奥から宮女を引き連れ現れた妃に頭を垂れた。
玲馨は木箱を掲げた姿勢のまま、自分の腕の隙間から覗く東妃の髪色に驚く。玲馨の見てきた物の中でその美しい色を喩えられそうなものが思い浮かばない。強いて言うなら今まさに東妃が纏っている裙を締める赤い帯に施された金糸に近いだろうか。
「その子は?」
「はっ。宦官だそうです。ここを通せと申しているのですが」
どうするのが正解か分からないが、ひとまず木箱の中身を思うとそれを妃に向かって掲げているのはまずいような気がしてさっと戻す。それから再び拱手の姿勢を取って沙汰を待った。
「名は何と?」
「玲馨と申します」
「玲馨……」
東妃の顔は見えないが若い声だ。
歳は二十前後。三年ほど前に漸く男児に恵まれた事で後宮内での地位を得られた一番最後の妃だと玲馨たちは教わっている。
例え雑事だろうとやがて後宮に出向く事になるため玲馨たちは後宮の事については特にみっちりと教えられている。五人の皇子たちから妃の出身地、妃同士の仲の良し悪しに、果ては妃の食の好みまで。
東妃は五番目の最も年若い妃で同時に最も位が低く、後宮内では浮いた存在。それには彼女の特徴的な外見も原因の一つだそうだ。
「顔を上げなさい、玲馨」
「はい」
腕を下げ、腰を伸ばして東妃と正対する。
東妃はその金の御髪に似合いの美しい顔立ちだった。肌は透き通るように白く、孔雀の羽のような鮮やかな碧は沈人には無い色合いだ。この容姿なら確かに目立つだろう。
それから位が一番低かろうと、やはり貴人は貴人なのだと思い知る。恐らく本人も意識しない圧倒的な気配はただ歳が上であるというだけで出せるものではない。
「あなたの事は聞いていますよ。戊陽殿下がよく話して聞かせてくれます。あなたはとても賢いのだと」
「畏れ多い事です」
「戊陽殿下に仕える事が決まったのですか?」
正式にはまだ、という事になるのだろう。ここで嘘をついてしまうと戊陽に迷惑がかかるような気がして正直に「いいえ」と答える。
「ではここへはどうして?」
「殿下に、戊陽殿下に話をうかがいに」
玲馨を取り巻く大人たちの空気が変わるのが肌で分かった。
「私は先ほど武官に暴力を振るわれました。理由は戊陽殿下に対し何か無礼があったという事でした」
門衛の兵士たちが顔を見合わせ、片方が肩を竦める。
「ですが私には身に覚えがありません。私はこの十日ほど少年が宦官となるために努める事情によって臥せっておりましたので、私が殿下に対し無礼を働いたのだとしたら何かの勘違いだと思ったのです。ですが私の勘違いではなかった場合誠心誠意謝りたく、傷が回復したその足でここへ参りました」
嘘は一つも言っていない。ただとにかくここを通してほしい一心で、丁寧に誠実に自分の事情を話した。
東妃は少しの間考えるようにして黙った後、踵を返しながら言う。
「入りなさい。まずは私の宮に」
「は……はい!」
東妃の答えを待つ間、無意識のうちに息を止めてしまっていたらしい。返事をするのと同時に呼吸が戻り頭がくらりとした。それくらい、緊張感は極限に達していた。
宦官とはいえまだ子供で、浄身済みの証となる宝も持参していた。その上東妃も許したとあっては、兵士たちは槍を下ろすしかなかった。
馬車ごと乗り入れる事が出来るように広めに作られた後宮への門が今、玲馨へとその口を広げる。
後宮の中と外でどこが違うだろうと考えた時、玲馨の目に一番に留まったのは植物の種類だった。花をつけているものから葉を繁茂させているものまで種類が多い。四合院の院子は、回廊を囲うように手入れされた花木と低木で彩られており、名前が分かるものはほんの一部で自分の不勉強さが悔しい。
東妃の殿舎が見えてくると今度はその絢爛さに驚いた。細かな透かし彫りがされた大きく重たそうな扉があり、宮女が左右に別れて扉を開けると中には子供の体ならすっぽり収まってしまいそうな大きな鼎炉が置いてある。今は香を炊いていないようだが、屋内には沈香の香りが染み付いていた。
絹張りの宮灯にはすでに火が入れてあり、採光用の窓も多く誂えてあるおかげで中は隅まで明るく見渡せる。窓枠ひとつとっても飾りがしてあったり、複雑な柄──恐らく花の──があしらわれた氈が敷いてあったりと、あちこちを飾り付ける事に余念がない。宦官の宿舎がいかに粗末であったかを思い知る。
「あなたはここへ何をしに来たのです」
東妃は宮女を傍に控えさせ自らは寝台に腰掛ける。
門の外で訊かれた事と同じ事を、言葉を変えてまた訊ねられる。ここが東妃にとって私的な場所だからか、飾り気のなくなった言葉には鋭さが宿っている。
玲馨は床に膝をつき拱手した。
「戊陽殿下のご様子を確かめに参りました」
門外で答えた事に嘘はない。しかし相手が率直である以上、玲馨もまた言葉を飾らず短く答えた。
「そう」
熱の伴わない端的な返事にまるで打ち据えられたかのように玲馨の体が震えた。病み上がりの体が緊張に耐えきれず、持ち上げた腕が錘をつけたかのように重たい。後宮に来るまで必死だったものが、後宮の雰囲気や東妃の醸す気配に中てられすっかり萎れてしまっていた。けれどここまで来て戊陽の容態を聞かずには帰れない。
祈るような思いで待っていると東妃は「誰か戊陽殿下の宦官を呼んでおいで」と宮女に告げた。
「私にはその判断を下す権利がない。出来る事は殿下の宦官に取り次ぐくらいの事です」
「あ、ありがとうございます」
「それより──」
不意に目の前の人物の雰囲気ががらりと変わった。何事かを聞く暇もなく宮女が玲馨の両腕を取って立ち上がらせる。
「水を」
「すぐに」
「誰かこの子に衣をやれぬか? この際女物でも良いでしょう」
「でしたら宦官の袍があったはずですよ。訊いて参ります」
何だ何だと思っていると桶に水が運ばれてきて、玲馨の体には少し大きめの袍や袴が用意され、あれよあれよと脱がされ全身を手際よく拭き清められていく。
「わ、あっ、あのっ」
いくら何でもこの待遇は羞恥の限界を感じる。しかし止めるに止められず、最後の方は両手で顔を覆ってされるがままになっていた。
「戊陽殿下は体調を崩されておいでと私のもとにも届いています。そんな所へ汚れた格好で行かせる訳には行きませんでしょう?」
東妃はにこりともせずそう言った。
東妃は間違いなく佳人だが、ツンとしていて他者に否やを言わせない雰囲気がある。しかし彼女の言っている事は正論で、玲馨は萎縮して身を縮めた。
言われてみて改めて自分の軽率さに頭が上がらなくなりそうだが、東妃は建前ではなくちゃんと玲馨を戊陽と会わせようとしてくれているらしい。
初めて会ったはずなのに何故ここまでしてくれるのだろうと考えたが、戊陽のおかげだとしか思えなかった。
戊陽からは普段後宮でどんな暮らしをしているかを聞く事があった。彼はとにかく落ち着きがなく、後宮の中なら喧しく咎められる事も少ないからと兄弟の暮らす宮へよく訪ねたという。戊陽はまだ子供であるしあの人柄なので、きっと妃たちからも警戒される事なく兄弟の仲を深める事が出来たに違いない。
これは東妃が戊陽に対し払った敬意であって、決して玲馨への親切ではないと自分に言い聞かせた。
再度丁寧にお礼を告げると、少ししてからやってきたあの無口な宦官に伴われて、玲馨は東妃の宮を去った。殿舎から去る直前、部屋の奥から小さな子供の泣く声がすると東妃は少し焦ったようにして奥へと消えていくのが見えていた。
無口な宦官に先に戊陽の事を確認するべきかを迷っているうちに賢妃の宮へと着いてしまっていた。建物全体は東妃宮と似たような形だが扉の色と彫りが違っている。扉に続く階を照らす灯籠も数が少ない。特徴的なのは花木が一種類しかない事だろう。恐らく全て桃の木だ。
「賢妃様、戻りました」
宦官が扉の向こうに呼びかけるとやはりこちらでも宮女が今度は中から扉を開けてくれる。内装は東妃の宮に比べると質素で落ち着いている。全体的に使っている色が少ないのだ。
「その子は何です?」
宮女が訊くと宦官は「玲馨です」と答える。無口な宦官とはお互い顔を知りながらも一言も話したことが無いという間柄だったが、玲馨の名は知っていたらしい。戊陽が玲馨の事を話すのだろう。
玲馨の名を伝えただけで通じるのかという驚きはもう無かった。東妃宮で既に存在を知られているのなら、戊陽の生母である賢妃が知らないはずがない。
宦官に続いて中へ入ると賢妃は舶来品らしい猫脚の椅子に腰かけていた。
「戊陽ならまだ眠っているわ」
玲馨が何をしにきたのか既に察していたらしい。その声音は固いものの、東妃のように突っぱねるような冷たさはない。歳が十ばかり違うのでそのせいもあるだろうが、もともと賢妃はとても穏やかな人だという。
「玲馨、あなたの体はどうなのかしら?」
「はい。私は熱が出て意識が朦朧としておりましたので、はっきりと申し上げる事は出来ませんが、戊陽殿下が私の病室に来て下さったのは覚えております」
「それで?」
「……全て良くなりました」
患部も熱もどちらも治っている。体に残った気怠さは十日ほど寝たきりで食事もろくに取れていない事が原因だろう。
全て、戊陽のおかげだ。そしてこれは推測だが、戊陽は玲馨を救ったために床に臥してしまったのではないか。そう考えると玲馨へ無体を働いたあの武官の言動も合点がいく。
玲馨を問い詰める雰囲気は消えていき、賢妃は静かに宦官へと告げる。「玲馨を戊陽のもとへ」
戊陽は先月に十二歳を迎えて半元服の儀を済ませているので、東妃とは殿舎を分けている。門から見て正面が東妃の、右手が戊陽の休む殿舎だ。
再び宦官の後ろをついて回廊を渡り、やはり質素な扉の前まで連れてこられる。今度は宦官は自ら扉を開けて先に中へと入っていってしまう。
中はしんと静まり返っていた。人の気配がなく、灯りも小さな吊り灯籠にひとつ火が灯っているだけだ。宮女も控えておらず、あまりの静けさに何故か不安になった。
戊陽が休んでいるらしい寝台には紗が掛けられている。足音を立てないようゆっくりと近づき寝台の傍に立つが、やはり気配も音もしない。
猿猿の事が頭を過った。だが戊陽は違う。後宮には侍医が詰めていて、何かあればすぐに診てもらえる。看病をしてくれる人だってたくさんいる。
紗を避けて顔を見たいと思っても、それはさすがに憚られた。
宦官は扉から入ってすぐのところに控えており、玲馨はこれ以上どうしていいか分からなくなってそちらへ戻ろうとした。
「……四郎?」
戊陽の声だ。紗が小さく揺れて、隙間から腕が覗く。紗を開けようとしているらしいと気付いて捲ってやると、戊陽は驚いた顔で玲馨を見上げた。
「りん、しん……」
声が掠れてしまっている。水差しを探して視線を巡らせると、左手を握られほんの僅かに引き寄せられた。ツン、とつま先が寝台の脚に当たってつんのめる。
「治ったんだな。良かった」
「よく……あ、ありがとうございます」
そのせいで戊陽が臥せっているのだと思うと咄嗟に良くないですと言い掛けたがどうにか誤魔化した。戊陽が居なければ玲馨は死んでいた。また、猿猿が頭に浮かぶ。
「戊陽殿下のお体の具合が悪いと聞いて、どうしても様子を確かめたくて」
「俺の力のせいだから、玲馨のせいではない」
「はい……あの、殿下は」
「戊陽」
こういう押しが強い所だけ猿猿と似ていると思った。
「戊陽は、体は大丈夫なの? 寝てれば治る?」
うん、と言いたかったのだろうが掠れて音にならず、代わりに戊陽は首肯した。
左手はまだ戊陽に握られていて、その手があまり暖かくないのが気にかかった。ずれた上掛けを片手で引っ張り上げて首の辺りまで覆ってやる。しかしまだ、手は離れていかない。
「俺は、玲馨に嘘を言った。ごめん。出来ない事を出来ると言ってしまった」
弱弱しい声で、その響きはどこか玲馨に向けているというより、戊陽の中に向かっているような気がした。
「猿猿とお前は約束をしていると言っていた。俺は相手が猿猿だと知らず、会わせてやると言ってしまったが──」
永参が現れ、手紙を読んでもまだ実感を伴わなかったものが、戊陽の酷く参っているような声で告げられると急速に現実みを帯びていく。
猿猿が死んだ。それは本当に起こった事なのだと理屈ではなく、分かってしまった。
「玲馨……」
嘘みたいに涙がボロボロと溢れてくる。あっという間に息が苦しくなって胸元を押さえて必死に喘いだ。
「玲馨、玲馨」
掴まれていた手に力がこもり痛いくらい握られる。
戊陽は玲馨の名を呼びながらもう片方の腕を横に広げてみせた。
それを見たら体が勝手に動いて玲馨は戊陽に覆いかぶさるようにして戊陽に抱きついた。
はっ、はっ、と震えながら浅い呼吸を繰り返す玲馨を、戊陽は力はあまり入っていなかったがそれでもしっかり抱きしめてくれる。
東妃に着替えさせられて良かったと、どこか頭の隅に置き去りにされた冷静な思考が場違いな事を思う。
「ここにっ、来たとき、戊陽も死んっ」
死んだかと思ったと言おうとして理性が止める。そんな事を口にすれば不敬だ。
「死なない。俺には天帝が力を恵んで下さったから、俺は死なないんだ。力を持って生まれた皇族は、みんな長生きなんだ」
嘘か本当かも分からないがそれを聞いて玲馨は確かに安堵を覚えている。ああこういう事かと、猿猿が玲馨に求めていたものは、きっとこういう言葉だったのだと今になって思い至る。
だからこそ猿猿と戊陽が出会えていたらと考えて、ますます涙が止まらなくなった。きっと戊陽なら猿猿の欲しい言葉を与えてやれたに違いない。
それからひとしきり存分に泣いた後で戊陽に平謝りし、無口な宦官と共に涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった戊陽の衣を着替えさせた。
再び横臥すると戊陽はすぐに寝付いて小さく寝息を立て始めた。
玲馨は宦官に礼を言い、東妃と賢妃にはどう礼をすればいいか訊ねると、また日を改めて来いと言われた。早晩お前は第二皇子付きの宦官になるのだから、と。
「名は玲馨、十二歳で間違いないな」
「はい」
ここは浄身するための処置室だ。執刀医らしき男が一人、他に大人が二人。腰を曲げなくても良いような高さの広い台があって、玲馨はそこに寝かされるらしい。
目につく道具のほとんどが何に使われる物なのかが分からない。無愛想な大人たちの態度も恐怖心を煽ってくる。
大丈夫、大丈夫。自分に言い聞かせるように心の中で唱える。
これを終えたら猿猿との約束がある。戊陽が後宮で待っている。
玲馨には怖いものがたくさんある。玲馨は怖がりだ。だけど自分にはやるべき事、やりたい事があると思うと少しだけ、本当に少しだけ怖さが紛れていくようだった。
淡々と準備を進めていく執刀医がふと手を止めて「泣かないのか。偉いな」と言った。
*
処置が終わり、最初の二日ほどは痛みで意識が朦朧としていた。三日目になると医師がやってきてまた痛みを伴う処置を施してから「成功だよ」と端的に告げた。
成功の言葉に喜べるような余裕は一切なく、尚も続く苦痛に昼も夜もなく悶え苦しんだ。
そんな日が一週間ほど続いた頃、玲馨の検診をしていた医師の表情が芳しくない事に気付く。
「……私は、何かおかしいですか?」
意識があると思われていなかったようで医師の表情は驚きに変わる。
「体が熱いだろう」
「はい……」
「このまま熱が下がらないと、危ないかもしれない」
──危ない? 何が?
何が危ないというのか。はっきりと言葉にしてほしくて医師の袖を掴んで引っ張った。
「お前が悪いのではない。こういうのは天運によるものだ」
「てん、うん……?」
話が噛み合っていない。玲馨は自分で自分を責めてなどいないし、欲しかった答えとは違っている。
しかし医師は最後まで詳しく説明する事なく、気休めのようにいつもより薬を多く置いていった。苦くて飲むたび喉奥でえずいてしまう嫌いな薬だ。飲むと眠くなるけど、起きた時の夢から醒めきらないような怠さが厄介な薬。
いつもは嫌いでも患部の痛みに耐えきれず薬を飲まずにはいられなかったのに、今日は飲みたくないと思った。飲んだらもう次は目が覚めないような気がして、ゾッと背筋を恐怖と悪寒が駆け上がっていった。
全身に冷たい嫌な汗が浮かんでいるのに、全身はじりじりと火で炙られているように熱感が消えない。
死ぬのかと思った時、浄身でも泣かなかった玲馨の目に涙が滲んだ。
怖かった事、辛かった事、玲馨はこれまでたくさん耐えてたくさん乗り越えてきた。
知らない事は怖い事だと思った。けれど死は無理だ。死は越えられない。この先死ぬのだと知っても、ちっとも恐怖は和らがない。
「──から、……くれ」
玲馨が寝ている部屋の外から声が聞こえた。水の中にいるような朦朧とした意識の中でも戊陽の声だとすぐに分かった。
血相を変えて部屋に入ってきた戊陽は、ついてきていたいつもの宦官を中には入れずに扉を閉めた。一瞬入り込んだ日差しがす……と途切れて暗くなり、そういえばこの部屋には窓のような物がない事に今更気付く。
「……うーやん、殿下」
部屋に二人きりだけになると一度驚きで止まっていた涙がまた溢れ出し、戊陽の名前を呼びながら必死に手を伸ばした。
「玲馨……。遅くなった。すまない」
「殿下、私は」
「ん?」
「約束をしました。一緒に、勉強をすると、約束を……」
「大丈夫だ。俺が必ず会わせてやるから」
「猿猿と、共に後宮へ仕えようと」
「……」
玲馨の手を力強く握っていた戊陽の手が一瞬、硬く強張った。
「死んだら、会えません」
何も言わない戊陽の手は冷たかった。玲馨の手が熱過ぎるのだ。
「私、は……お、男に股を開かされ、母に捨てられて、男の象徴を失っても、私は生きていました。だけど、これから死ぬのだと知って、私は、怖いと……怖いんです、戊陽っ、死にたくない……っ!」
玲馨、と静かに名を呼んで戊陽はそれ以上何も言わなかった。ただ、いつかそうしたように、玲馨の手を握り祈るようにして目を閉じている。玲馨の手を額に当てて、そこからじんわりと熱のようなものが伝わって。
そこで玲馨は眠りに落ちていった。眠る瞬間も戊陽が居てくれると思うと恐ろしさはそこにはなく、浄身してから薬を使わずに眠れたのは初めての事だった。
次に目が覚めると体を怠くさせていた熱感も、患部の痛みもすっかり消えていた。
恐る恐る自分の股に手をやってみる。痛くはない。ついでにあるべきものもない。それは奇妙な感覚で落ち着かない感じがあるが、何よりあの苦痛がさっぱりなくなってしまった事の方が大きかった。
──殿下は?
室内には玲馨一人だ。窓がないので時間が分からないし、どれくらい眠っていたかも分からない。
玲馨は体をずらして寝台の端に腰掛けると、そっと足を地面についてみる。長くまともに食事を取っていないのでフラつく感じはあるものの、立ち上がり、歩く事が出来た。
もっと小さかった頃は転ぶのが怖くて床を這いつくばっていた事を思い出しながら、壁に手を付き歩を進める。今では転ぶ事はもうそんなに怖くはなくなっていた。
角を曲がるとすぐに灯りが見えた。大人の話し声のようなものが聞こえると思ったが、どうも誰かが怒鳴る声のようだ。
「いいからここに呼べ」
「さきほどから何度も言っておりますが、令状などを確認出来なくては私どもも仕事ですので」
「黙れ! 皇子を害した子供を、貴様らは庇い立てしているんだぞ!」
壁か扉を殴ったような激しい音がして、男の厳しい声が壁越しにいる玲馨の所まではっきり聞こえてくる。
玲馨は音を立てないようゆっくり廊下を進み、声のする所まで行く。どうやら怒鳴られている方は通せんぼをするように扉の前に立っているらしい。その正面に怒鳴り続けている男が居る。
「子供の連続死の件、お前に類が及ぶかも知れんがそれでいいんだなぁ?」
「……卑怯な」
足音がする。それは扉から去っていく。
まずいと思った時には既に遅く、目の前の扉が勢いよくこちら側に向かって開かれて、玲馨の体は軽々と吹っ飛んだ。
「何だ? 誰だお前は。名を名乗れ」
「あ……」
怖い。怖い。
筋骨隆々とした大きな体は、玲馨の恐怖の象徴だ。伸ばしっぱなしの顎髭に、彫りの深い顔。声が大きく気に入らないとすぐに怒鳴る。
そういう男はたくさん居た。よく相手をさせられた。あの男たちは金払いが良かったのだ。
声も出せず震えている玲馨の片腕を掴み男が引っ張り上げる。すっかり足から力が抜けており、肩が悲鳴を上げた。
「い゛っ、ぅっ」
「名を名乗れと言ったのが聞こえなかったのか」
名乗ってはいけないという予感がある。だが今ここで偽名を使ったとてすぐに嘘だと見抜かれるだろうし、そうなった後が恐ろしかった。
「り──」
「玲馨です。その少年の名は玲馨」
玲馨の代わりに答えたのは、扉を通せんぼしていた男だった。恐らく執刀医だ。
どうしてか裏切られたような気分になって、がたいの良い男越しに執刀医を見ると目を逸らされた。
「ふむ。お前が玲馨か。来い。貴様は皇子を害した罪に問われる」
「罪……?」
身に覚えなんてあるはずがない。正確な日数は分からないが自分は十日ばかりここで生死の境を彷徨っていたのだ。それに何より皇子は戊陽の事しか知らなければ、彼に対して害意なんてとんでもない事だった。
「あ、あの、私は知らな」
「知らない? では何故、貴様は生きている? 貴様は本来死ぬはずだった。違うか?」
その言葉で分かった。害された皇子とは戊陽の事だ。だが何故、その罪を玲馨に問うのか。
言い返せずにいると男は玲馨の腕を引いて部屋から出ていこうとする。玲馨は抵抗しかけるも体が言う事を聞いてくれず、震えながら男に従って外へ出た。
「おや、玲馨。浄身を済ませたのか」
玲馨は、耳を疑った。視線を上げて、声の主を確かめて、どんな顔をしていいか分からなくなる。
病棟から出たところで待っていたのは永参だった。永参に声を掛けられたのは彼に部屋を追い出されたあの日以来だ。
「これを猿猿が僕に預けていったんだ。猿猿が戻らなかったらお前に渡してくれとね」
「小猿が……?」
永参は何かを投げて寄越した。平べったいそれは宙を斜めに横切るようにして玲馨の足元へ落ちる。男が腕を放してくれたので拾い上げるとそれは折りたたまれた紙だった。書き損じを使ったものではない、綺麗な紙だ。
「あれは僕とお前の事を勘違いしている可哀想な子供だったな。だが悪い子ではなかったよ。その手紙を預かるくらいの事はしてやっても良いと思える子供だった」
媚びを売る猿のような下品さは気に入らなかったけどね──。
耳を塞ぎたくなるような捨て台詞を吐いて永参は去っていく。その背中に石を投げてやりたくなった。
玲馨は猿猿からの手紙を読もうとしたのだが、男がまた玲馨の腕を掴むので慌てて懐にしまい込む。
「お前は性悪の永参と同室だったんだってなぁ?」
男は玲馨の腕を自分の方へ向かって強く引くと、玲馨の顎を片手で捉えてねぶるような視線で玲馨の顔を見回した。嫌悪感で背筋が粟立つも、玲馨は嫌だと突っぱねる事は出来ない。
「いっちょまえに綺麗な顔してやがるじゃねぇか」
玲馨はこれから何をされるのかすぐに察した。
案の定男は歩幅の違いも気にせず足早に歩いて倉庫のような建物の影に玲馨を連れて行く。
逃げたい。戊陽に何があったのか確かめなくてはいけない。それに猿猿からの手紙もある。
だけど抵抗すれば男は容赦なく玲馨を殴るだろう。無理矢理組敷かれて強引に暴かれて、大人しく従うよりもずっと苦しい目に遭うのが分かりきっている。
そうこうしているうちに男は玲馨に膝をつかせると、袴を寛げてまだ兆していないだらしなく垂れ下がった陰茎を取り出し持ち上げた。ぐ、と頭を掴まれて鼻が触れそうな位置に陰茎がぶら下がる。
「咥えろ」
言われずとも分かっていた。分かっていたが、玲馨は大人しく言うことを聞いてしまいそうになる自分をどうにか押さえ込んでいた。
「……ああそうか。永参に後ろは仕込まれても、あいつにはこれがついてないからなぁ!」
嫌な笑い声を立てて男は陰茎でぺちぺちと玲馨の頬を叩いた。
「仕方ねぇ、俺が教えてやるよ。じっくりとな」
そんな事されずとも、玲馨はよっぽどそれの咥え方を知っている。舌の動き、喉の使い方、暇な手で竿と玉を刺激してやればよく褒められた。
「ほら、口開けろ。歯は立てるなよ」
顎の関節に指を差し込まれると痛みで勝手に口が開いてしまう。抵抗しようとしても痛みがそれを許さない。
母に言われて男に抱かれていた時の方がまだ良かった。あれには金という対価が支払われていた。永参はどうしようもない人間だが手荒くされたのは最後の一度きりで、やはり勉学という対価をくれた。
ではこの男は? この男は玲馨に何をくれるだろうか。
無理やり開かされた口の中に悪臭を放つそれがねじ込まれる。ふにゃりとしたそれはあっという間に口の中で強張りはじめ、芯が出来てくる。
「子供ってのは舌も小せぇのか?」
文句を言う割には硬さはもう十分なくらい膨れており、玲馨の口では全体を含めないほど勃起していた。
「あー……上手ぇなおい……はっ、永参は玩具でも舐めさせてたか?」
舌に苦いような渋いようなえぐみのある味が広がった。
もうこんな事は永参で最後だと思ったのに。どうしてこんな目に遭わなくてはならないのか。
男の先走りはどんどん溢れて涎と混じって玲馨の顎を汚していく。男はもうすっかり夢中になっており、玲馨の頭から手が離れていた。
抵抗するなら今しかない──そう思った時、玲馨は男のそれを思い切り噛んだ。
「いぎあああっ!!!」
それは酷い悲鳴を上げて男は玲馨の顔を咄嗟に殴り突き飛ばす。男は目に涙を浮かべて股を押さえもんどり打った。
「く、そが、ふざけんなよ、クソガキがぁ……っ」
玲馨は噛まれるより痛い思いをして浄身したのだと思うと、泣いて吠えるばかりの男は酷く情けなく見えた。
体はもうフラフラで走っているつもりが歩いてしまっているが、懸命に男の傍から離れた。
まずは戊陽の様子を確かめるために後宮に行かなくてはいけない。だがどうやって中へと入ろうか。
逃げながら考えて、玲馨はある事を思いついて病棟の方へと引き返す。あそこには玲馨が受け取りそこねた宝があるはずだ。
宦官はその身が浄身済みである証明に、切り落とした一物を宝と呼んで大切に持っていなくてはいけない。それがあれば、玲馨も後宮に入れてもらえるだろうと考えた。
宦官を作るためだけに建てられた棟はこじんまりとしていて屋根や壁も粗末だ。
出てきた時と同じ木戸を開けて中へ飛び込むと、玲馨の名を勝手に教えたあの執刀医がそこに居た。
「何だ。騒がしくするな」
「あの、私の宝を」
「ああ……」
執刀医はすぐに小さな箱を取り出して玲馨に渡してくれる。木箱はとても軽くて、あの想像を絶する痛みによって切り離したものはこんなにも軽いものだったのかと驚く。
「本当なら忘れてったら金を取るんだがな、俺はお前に対して仕事をやり遂げられなかった借りがある」
宦官はその存在を蔑ろにされる事も多いが、だからといって徒に傷付けたり命を奪ったりして良いものではない。執刀医たちには当然宦官たちを預かる責任があるし、玲馨があのまま男に殺されたりして行方が知れなくなれば、責任は執刀医に問われる事になっただろう。
彼はその事について謝罪をする気はないらしい。だがもう玲馨はどうでも良かった。体が万全ではないので考えるのが億劫になっていた。
箱を懐に仕舞うと、その指先に何かが触れた。猿猿からの手紙だ。読みたいと思う気持ちを堪えてとにかく後宮へと急いだ。
「はぁ……はぁ……」
後宮まで後僅かに迫る頃、西の空で日が傾き始めていた。今ちょうど申の刻くらいだ。
後宮へ続く門は二箇所あり、一つは黄麟宮と呼ばれる皇帝の寝所からの直通だ。もちろんそこは通れないので、宦官の宿舎側にある門を通らなくてはならない。
しかし後少し行けばもう門が見えてくるというのに足が立たなくなり始めていた。
少しだけ休憩しようと考えて、木の根本に座り込む。屈んだ拍子に腹の辺りで何か触る感触があった。猿猿の手紙だ。
取り出してみると少し端が折れてしまっていた。これ以上折れたりしないよう丁寧に開いていき、手本のような形の字が並ぶそれを読み始めた。
『玲馨がこれを読んでるって事は、きっと僕は死んじゃったんだね』
「えっ……?」
思わず声が出ていた。冒頭からなんて事を書くのだと思ったが、頭の中に何か引っ掛かるものがあった。
『永参先輩に頼んでおいたの。僕が戻らなかったらこの手紙を玲馨に渡して下さいって。永参先輩、僕の事あんまり好きじゃないみたいだけど、お願い聞いてくれるといいなぁ』
『これを猿猿が僕に預けていったんだ。猿猿が戻らなかったらお前に渡してくれとね』
書いてある事と全く同じことを永参は言っていなかっただろうか。
『あのね、僕玲馨の事優しくないって言ったけど、玲馨は本当は誰よりも優しいのかもなぁって思ってる。うーんでもやっぱり違うかも? 誠実って言うのかなぁ? 嘘つけない所が僕は好き』
ところどころ字を間違えているが、書体は綺麗で読みやすく、紙に墨跳ねも無い。筆の使い方が丁寧で器用なのだ。
『だから僕も本当の事話す。本当はね、玲馨が皇子様にお仕えするのが決まってるって知った時すごくすごく羨ましかった。腹が立った。何で僕じゃなかったんだろうって思った。ううん、本当はもっと前、皇子様と知り合ってた事からもうすっごい嫉妬してたの。玲馨みたいに綺麗なのが好きなら、僕みたいに可愛いのでもいいじゃん! って』
玲馨を好きだと言ってくれたが文面はあまりにあけすけでいっそ嫌悪感すら見えるようだ。ひょっとすると最初は玲馨の事を嫌っていたのかも知れない。
『だけど玲馨と話すようになってから、僕きっと玲馨に憧れてたの。あーこれ書くのすっごく恥ずかしい! 玲馨は自分の事どう思う? 玲馨はね頑固なんだよ。芯があるの。譲らない事は絶対に譲らない。僕はきっと譲っちゃうんだ。大切なものだって、僕はいざって時に手放しちゃう。もしかしたら大切だって気付かないのかも。お母さんと一緒にいる事を選ばなかったみたいに。お母さんもきっと同じで、僕と一緒に居て死ぬ事より、お互い別れて生きる事を選んじゃった。おかげで僕たちはもう二度と会えない。二度と会えないのと、一緒に死んじゃうの、どっちが幸せだったんだろうね』
もしこれを面と向かって猿猿に訊ねられてもやっぱり玲馨は答えられなかっただろう。だけどこの本音は彼の口から聞きたかったと思ってしまう。時間がかかってもいつか答えを見つけたいと思う。
本当にもう猿猿は居ないのだろうか。もう答えを届ける相手は居なくなったのだろうか。
『どうせ玲馨は答えてくれないんだよね。意地悪なんじゃなくて、きっと上手く答えられないんだって思ってたけど、本当はどうだった? 僕の事、どう思ってた? ねぇ玲馨』
猿猿が戻って来ていないのは、永参の勘違いだと思いたい。だけど永参はもはや玲馨への興味をなくしている。いっそ恨みすらしている。そんな玲馨が晴れて本当に「少年」ではなくなって、生死を彷徨い心身がボロボロになっていたあの瞬間に、この手紙を届ける事で玲馨がどんなに辛い思いをするか、永参はよく分かっていただろう。玲馨は生きて、猿猿は死んでいる。それを知らしめられるから永参はわざわざ手紙を運んだのだ。
だからこの手紙が玲馨に届けられたのは勘違いなどではないと確信出来た。
『この手紙、玲馨に届かないといいなぁ。そしたらいつか、ちゃんと自分で玲馨に全部話せるもんね』
手紙はそれで終わりだった。別れの言葉も何もない、素っ気ない終わり方。紙にはまだ少し余白があったが、最後の一文は掠れていた。墨が足りなくなったのかもしれない。もしくは、もっと別の理由で書けなかったのか。
実感の無い喪失感は、玲馨の頭の中を空っぽに浚っていって、しばらくの間玲馨はその場から動けなかった。
手紙を風で飛ばされたり汚したりしないよう折り目に沿って畳んで懐に仕舞いこむ。
再び戊陽の元へ行かなくてはと腰を上げたのは、西の空が真っ赤に燃え始める頃だった。
後宮へ続く門には門番の兵士が二人立っており、拱手する玲馨の姿を見た彼らは槍を構えて通れなくする。
兵士たちは玲馨を襲ったあの体格の良い男と同じ格好をしていた。あの男は兵士だったようだ。
「お前は、宦官の少年か……?」
「あの、これを」
玲馨は懐から宝の入った木箱を取り出し両手に乗せて恭しく掲げた。
「中身は私の宝です。浄身を終えた身ですのでここを通して頂けませんか」
頭を下げた向こうで兵士二人が困惑したように囁きあっている。「何か聞いてるか?」「いや何も」「どの宮の宦官だ?」「待て。俺はこいつの顔を初めて見るぞ」
怪しい、という意見で一致した兵士たちは槍を構えたままじりじりと玲馨へ躙り寄ってくる。
玲馨は戊陽の様子を確かめたいだけで悪さをしようというのではない。どうすればそれを分かってもらえるか懸命に知恵を絞る。
「どうしたのです、何かの騒ぎですか?」
「あなたは……」
「と、東妃様!」
槍を下げた兵士はさっと抱拳礼をして、門の奥から宮女を引き連れ現れた妃に頭を垂れた。
玲馨は木箱を掲げた姿勢のまま、自分の腕の隙間から覗く東妃の髪色に驚く。玲馨の見てきた物の中でその美しい色を喩えられそうなものが思い浮かばない。強いて言うなら今まさに東妃が纏っている裙を締める赤い帯に施された金糸に近いだろうか。
「その子は?」
「はっ。宦官だそうです。ここを通せと申しているのですが」
どうするのが正解か分からないが、ひとまず木箱の中身を思うとそれを妃に向かって掲げているのはまずいような気がしてさっと戻す。それから再び拱手の姿勢を取って沙汰を待った。
「名は何と?」
「玲馨と申します」
「玲馨……」
東妃の顔は見えないが若い声だ。
歳は二十前後。三年ほど前に漸く男児に恵まれた事で後宮内での地位を得られた一番最後の妃だと玲馨たちは教わっている。
例え雑事だろうとやがて後宮に出向く事になるため玲馨たちは後宮の事については特にみっちりと教えられている。五人の皇子たちから妃の出身地、妃同士の仲の良し悪しに、果ては妃の食の好みまで。
東妃は五番目の最も年若い妃で同時に最も位が低く、後宮内では浮いた存在。それには彼女の特徴的な外見も原因の一つだそうだ。
「顔を上げなさい、玲馨」
「はい」
腕を下げ、腰を伸ばして東妃と正対する。
東妃はその金の御髪に似合いの美しい顔立ちだった。肌は透き通るように白く、孔雀の羽のような鮮やかな碧は沈人には無い色合いだ。この容姿なら確かに目立つだろう。
それから位が一番低かろうと、やはり貴人は貴人なのだと思い知る。恐らく本人も意識しない圧倒的な気配はただ歳が上であるというだけで出せるものではない。
「あなたの事は聞いていますよ。戊陽殿下がよく話して聞かせてくれます。あなたはとても賢いのだと」
「畏れ多い事です」
「戊陽殿下に仕える事が決まったのですか?」
正式にはまだ、という事になるのだろう。ここで嘘をついてしまうと戊陽に迷惑がかかるような気がして正直に「いいえ」と答える。
「ではここへはどうして?」
「殿下に、戊陽殿下に話をうかがいに」
玲馨を取り巻く大人たちの空気が変わるのが肌で分かった。
「私は先ほど武官に暴力を振るわれました。理由は戊陽殿下に対し何か無礼があったという事でした」
門衛の兵士たちが顔を見合わせ、片方が肩を竦める。
「ですが私には身に覚えがありません。私はこの十日ほど少年が宦官となるために努める事情によって臥せっておりましたので、私が殿下に対し無礼を働いたのだとしたら何かの勘違いだと思ったのです。ですが私の勘違いではなかった場合誠心誠意謝りたく、傷が回復したその足でここへ参りました」
嘘は一つも言っていない。ただとにかくここを通してほしい一心で、丁寧に誠実に自分の事情を話した。
東妃は少しの間考えるようにして黙った後、踵を返しながら言う。
「入りなさい。まずは私の宮に」
「は……はい!」
東妃の答えを待つ間、無意識のうちに息を止めてしまっていたらしい。返事をするのと同時に呼吸が戻り頭がくらりとした。それくらい、緊張感は極限に達していた。
宦官とはいえまだ子供で、浄身済みの証となる宝も持参していた。その上東妃も許したとあっては、兵士たちは槍を下ろすしかなかった。
馬車ごと乗り入れる事が出来るように広めに作られた後宮への門が今、玲馨へとその口を広げる。
後宮の中と外でどこが違うだろうと考えた時、玲馨の目に一番に留まったのは植物の種類だった。花をつけているものから葉を繁茂させているものまで種類が多い。四合院の院子は、回廊を囲うように手入れされた花木と低木で彩られており、名前が分かるものはほんの一部で自分の不勉強さが悔しい。
東妃の殿舎が見えてくると今度はその絢爛さに驚いた。細かな透かし彫りがされた大きく重たそうな扉があり、宮女が左右に別れて扉を開けると中には子供の体ならすっぽり収まってしまいそうな大きな鼎炉が置いてある。今は香を炊いていないようだが、屋内には沈香の香りが染み付いていた。
絹張りの宮灯にはすでに火が入れてあり、採光用の窓も多く誂えてあるおかげで中は隅まで明るく見渡せる。窓枠ひとつとっても飾りがしてあったり、複雑な柄──恐らく花の──があしらわれた氈が敷いてあったりと、あちこちを飾り付ける事に余念がない。宦官の宿舎がいかに粗末であったかを思い知る。
「あなたはここへ何をしに来たのです」
東妃は宮女を傍に控えさせ自らは寝台に腰掛ける。
門の外で訊かれた事と同じ事を、言葉を変えてまた訊ねられる。ここが東妃にとって私的な場所だからか、飾り気のなくなった言葉には鋭さが宿っている。
玲馨は床に膝をつき拱手した。
「戊陽殿下のご様子を確かめに参りました」
門外で答えた事に嘘はない。しかし相手が率直である以上、玲馨もまた言葉を飾らず短く答えた。
「そう」
熱の伴わない端的な返事にまるで打ち据えられたかのように玲馨の体が震えた。病み上がりの体が緊張に耐えきれず、持ち上げた腕が錘をつけたかのように重たい。後宮に来るまで必死だったものが、後宮の雰囲気や東妃の醸す気配に中てられすっかり萎れてしまっていた。けれどここまで来て戊陽の容態を聞かずには帰れない。
祈るような思いで待っていると東妃は「誰か戊陽殿下の宦官を呼んでおいで」と宮女に告げた。
「私にはその判断を下す権利がない。出来る事は殿下の宦官に取り次ぐくらいの事です」
「あ、ありがとうございます」
「それより──」
不意に目の前の人物の雰囲気ががらりと変わった。何事かを聞く暇もなく宮女が玲馨の両腕を取って立ち上がらせる。
「水を」
「すぐに」
「誰かこの子に衣をやれぬか? この際女物でも良いでしょう」
「でしたら宦官の袍があったはずですよ。訊いて参ります」
何だ何だと思っていると桶に水が運ばれてきて、玲馨の体には少し大きめの袍や袴が用意され、あれよあれよと脱がされ全身を手際よく拭き清められていく。
「わ、あっ、あのっ」
いくら何でもこの待遇は羞恥の限界を感じる。しかし止めるに止められず、最後の方は両手で顔を覆ってされるがままになっていた。
「戊陽殿下は体調を崩されておいでと私のもとにも届いています。そんな所へ汚れた格好で行かせる訳には行きませんでしょう?」
東妃はにこりともせずそう言った。
東妃は間違いなく佳人だが、ツンとしていて他者に否やを言わせない雰囲気がある。しかし彼女の言っている事は正論で、玲馨は萎縮して身を縮めた。
言われてみて改めて自分の軽率さに頭が上がらなくなりそうだが、東妃は建前ではなくちゃんと玲馨を戊陽と会わせようとしてくれているらしい。
初めて会ったはずなのに何故ここまでしてくれるのだろうと考えたが、戊陽のおかげだとしか思えなかった。
戊陽からは普段後宮でどんな暮らしをしているかを聞く事があった。彼はとにかく落ち着きがなく、後宮の中なら喧しく咎められる事も少ないからと兄弟の暮らす宮へよく訪ねたという。戊陽はまだ子供であるしあの人柄なので、きっと妃たちからも警戒される事なく兄弟の仲を深める事が出来たに違いない。
これは東妃が戊陽に対し払った敬意であって、決して玲馨への親切ではないと自分に言い聞かせた。
再度丁寧にお礼を告げると、少ししてからやってきたあの無口な宦官に伴われて、玲馨は東妃の宮を去った。殿舎から去る直前、部屋の奥から小さな子供の泣く声がすると東妃は少し焦ったようにして奥へと消えていくのが見えていた。
無口な宦官に先に戊陽の事を確認するべきかを迷っているうちに賢妃の宮へと着いてしまっていた。建物全体は東妃宮と似たような形だが扉の色と彫りが違っている。扉に続く階を照らす灯籠も数が少ない。特徴的なのは花木が一種類しかない事だろう。恐らく全て桃の木だ。
「賢妃様、戻りました」
宦官が扉の向こうに呼びかけるとやはりこちらでも宮女が今度は中から扉を開けてくれる。内装は東妃の宮に比べると質素で落ち着いている。全体的に使っている色が少ないのだ。
「その子は何です?」
宮女が訊くと宦官は「玲馨です」と答える。無口な宦官とはお互い顔を知りながらも一言も話したことが無いという間柄だったが、玲馨の名は知っていたらしい。戊陽が玲馨の事を話すのだろう。
玲馨の名を伝えただけで通じるのかという驚きはもう無かった。東妃宮で既に存在を知られているのなら、戊陽の生母である賢妃が知らないはずがない。
宦官に続いて中へ入ると賢妃は舶来品らしい猫脚の椅子に腰かけていた。
「戊陽ならまだ眠っているわ」
玲馨が何をしにきたのか既に察していたらしい。その声音は固いものの、東妃のように突っぱねるような冷たさはない。歳が十ばかり違うのでそのせいもあるだろうが、もともと賢妃はとても穏やかな人だという。
「玲馨、あなたの体はどうなのかしら?」
「はい。私は熱が出て意識が朦朧としておりましたので、はっきりと申し上げる事は出来ませんが、戊陽殿下が私の病室に来て下さったのは覚えております」
「それで?」
「……全て良くなりました」
患部も熱もどちらも治っている。体に残った気怠さは十日ほど寝たきりで食事もろくに取れていない事が原因だろう。
全て、戊陽のおかげだ。そしてこれは推測だが、戊陽は玲馨を救ったために床に臥してしまったのではないか。そう考えると玲馨へ無体を働いたあの武官の言動も合点がいく。
玲馨を問い詰める雰囲気は消えていき、賢妃は静かに宦官へと告げる。「玲馨を戊陽のもとへ」
戊陽は先月に十二歳を迎えて半元服の儀を済ませているので、東妃とは殿舎を分けている。門から見て正面が東妃の、右手が戊陽の休む殿舎だ。
再び宦官の後ろをついて回廊を渡り、やはり質素な扉の前まで連れてこられる。今度は宦官は自ら扉を開けて先に中へと入っていってしまう。
中はしんと静まり返っていた。人の気配がなく、灯りも小さな吊り灯籠にひとつ火が灯っているだけだ。宮女も控えておらず、あまりの静けさに何故か不安になった。
戊陽が休んでいるらしい寝台には紗が掛けられている。足音を立てないようゆっくりと近づき寝台の傍に立つが、やはり気配も音もしない。
猿猿の事が頭を過った。だが戊陽は違う。後宮には侍医が詰めていて、何かあればすぐに診てもらえる。看病をしてくれる人だってたくさんいる。
紗を避けて顔を見たいと思っても、それはさすがに憚られた。
宦官は扉から入ってすぐのところに控えており、玲馨はこれ以上どうしていいか分からなくなってそちらへ戻ろうとした。
「……四郎?」
戊陽の声だ。紗が小さく揺れて、隙間から腕が覗く。紗を開けようとしているらしいと気付いて捲ってやると、戊陽は驚いた顔で玲馨を見上げた。
「りん、しん……」
声が掠れてしまっている。水差しを探して視線を巡らせると、左手を握られほんの僅かに引き寄せられた。ツン、とつま先が寝台の脚に当たってつんのめる。
「治ったんだな。良かった」
「よく……あ、ありがとうございます」
そのせいで戊陽が臥せっているのだと思うと咄嗟に良くないですと言い掛けたがどうにか誤魔化した。戊陽が居なければ玲馨は死んでいた。また、猿猿が頭に浮かぶ。
「戊陽殿下のお体の具合が悪いと聞いて、どうしても様子を確かめたくて」
「俺の力のせいだから、玲馨のせいではない」
「はい……あの、殿下は」
「戊陽」
こういう押しが強い所だけ猿猿と似ていると思った。
「戊陽は、体は大丈夫なの? 寝てれば治る?」
うん、と言いたかったのだろうが掠れて音にならず、代わりに戊陽は首肯した。
左手はまだ戊陽に握られていて、その手があまり暖かくないのが気にかかった。ずれた上掛けを片手で引っ張り上げて首の辺りまで覆ってやる。しかしまだ、手は離れていかない。
「俺は、玲馨に嘘を言った。ごめん。出来ない事を出来ると言ってしまった」
弱弱しい声で、その響きはどこか玲馨に向けているというより、戊陽の中に向かっているような気がした。
「猿猿とお前は約束をしていると言っていた。俺は相手が猿猿だと知らず、会わせてやると言ってしまったが──」
永参が現れ、手紙を読んでもまだ実感を伴わなかったものが、戊陽の酷く参っているような声で告げられると急速に現実みを帯びていく。
猿猿が死んだ。それは本当に起こった事なのだと理屈ではなく、分かってしまった。
「玲馨……」
嘘みたいに涙がボロボロと溢れてくる。あっという間に息が苦しくなって胸元を押さえて必死に喘いだ。
「玲馨、玲馨」
掴まれていた手に力がこもり痛いくらい握られる。
戊陽は玲馨の名を呼びながらもう片方の腕を横に広げてみせた。
それを見たら体が勝手に動いて玲馨は戊陽に覆いかぶさるようにして戊陽に抱きついた。
はっ、はっ、と震えながら浅い呼吸を繰り返す玲馨を、戊陽は力はあまり入っていなかったがそれでもしっかり抱きしめてくれる。
東妃に着替えさせられて良かったと、どこか頭の隅に置き去りにされた冷静な思考が場違いな事を思う。
「ここにっ、来たとき、戊陽も死んっ」
死んだかと思ったと言おうとして理性が止める。そんな事を口にすれば不敬だ。
「死なない。俺には天帝が力を恵んで下さったから、俺は死なないんだ。力を持って生まれた皇族は、みんな長生きなんだ」
嘘か本当かも分からないがそれを聞いて玲馨は確かに安堵を覚えている。ああこういう事かと、猿猿が玲馨に求めていたものは、きっとこういう言葉だったのだと今になって思い至る。
だからこそ猿猿と戊陽が出会えていたらと考えて、ますます涙が止まらなくなった。きっと戊陽なら猿猿の欲しい言葉を与えてやれたに違いない。
それからひとしきり存分に泣いた後で戊陽に平謝りし、無口な宦官と共に涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった戊陽の衣を着替えさせた。
再び横臥すると戊陽はすぐに寝付いて小さく寝息を立て始めた。
玲馨は宦官に礼を言い、東妃と賢妃にはどう礼をすればいいか訊ねると、また日を改めて来いと言われた。早晩お前は第二皇子付きの宦官になるのだから、と。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
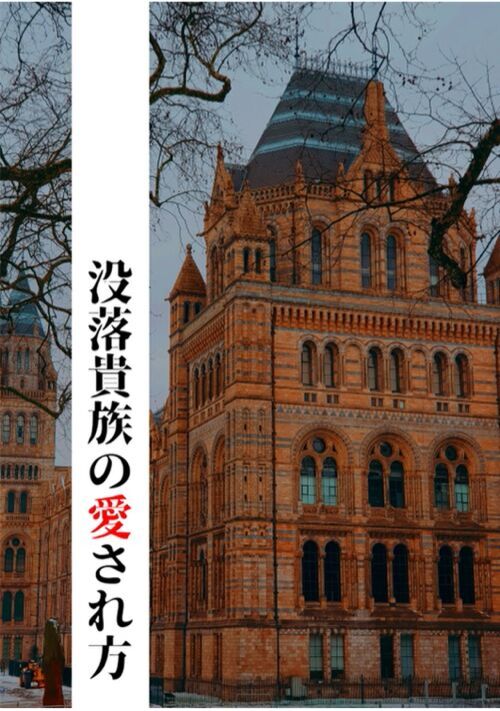
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















