9 / 44
山芒編
9再会
しおりを挟む
時は現在、場所は東の山芒である。
「譫言であなたの名をしきりに呼んでいます」と言われた時には玲馨は自分の目と耳を疑った。
戊陽が生まれた頃から仕えている無口な宦官の名を四郎というので、四男の生まれだったのだろうかと密かに考えているが本人に直接訊いた事はない。
四郎は無口などという生易しい表現では足りないほど寡黙だった。まず口を開くという事をほとんどしない。二十年来の付き合いで知らない事はないくらいの戊陽をして「奴との交流は諦めた」と言わしめるほど徹底した滅私ぶりである。
玲馨とも十年ほどの付き合いになるのでもうすっかり鉄面皮にも慣れたものだが、幼少期はにこりともしない表情の死んだ顔が不気味だった。
四郎は戊陽の影だ。いついかなる時も戊陽の傍に侍るが口を開かない。言い付けられた事を素早くこなすが余計な事は絶対にしない。
そんな四郎が玲馨を早朝一番に戊陽のもとを離れてまで呼びに来たという事実は、戊陽の身に何かよっぽどの緊急事態が発生したのかと焦らせ、玲馨は朝もまだ暗いうちから領都の株景まで走らされた。
結果、爆睡する戊陽の寝顔を拝む事になった。穏やかな寝息を立てる戊陽の様子は癒やしの力を使いすぎた反動で、これまで何度か玲馨も見てきた姿と変わらない。拍子抜けである。とは言えもちろん安堵する気持ちは大きい。
戊陽が彼だけに使える力を行使する様を何度か見てきた。怪我も病気もたちまち治してしまうがその代償に戊陽は自身の体力を削られる。どうやらそれは傷病の重篤さに比例するのと、単純に多くの患者を治せばそれだけ疲弊するものらしい。
それから所謂「死病」を取り除く事は出来ない。彼の父である黄雷は胸を患い、戊陽の献身も報われずに早逝した。怪我も同じだ。治せる「程度」というものがある事は力を宿した代々の皇族たちの研究によって判明している。
株景に着く頃には朝日も上り、町が活動を始めていた。玲馨が来るまでに落ち着いたのか、戊陽は深く寝入っており譫言を呟く様子はない。
玲馨は深く眠る戊陽の無事を確認して部屋を出て行こうとしたが、戊陽が身動ぐ微かな音に引き留められた。
「り……しん」
戊陽の穏やかな寝顔が段々と険しくなり始め眉間に深い皺が刻まれる。どこか痛むのか堪えるように歯を食いしばり、胸が大きく上下し呼吸が荒くなっていく。
「りんしん、玲馨……っ」
人の名を呼びながら悪夢を見ているとは。複雑な胸中にさせられつつも見ていられなくて戊陽の肩を掴んで揺り起こした。
「陛下、戊陽陛下。もっと幸せそうな夢をご覧に──」
続く言葉は突然大きく開いた戊陽の目に遮られる。音がするほど近い距離で目と目が合っている。しかしそうして見つめ合っていたのは、そんなに長い時間ではなかった。
戊陽はすぐに自分の目の前にある顔が玲馨だと分かると、小さく玲馨の名を呟いた。
「随分な夢見だったようですね」
目尻に微かに滲んだ涙は見なかった事にしてやろうと離れようとするも、「りんしん」と余りにも切なげに名前を呼ばれるので思わず躊躇する。
「玲馨……頼む、抱きしめてくれ」
「……」
まるで子供みたいだとか、ふざけないでくれだとか、揶揄う言葉や拒否する言葉が頭の中でわっと溢れ出す。しかしその全てを戊陽の弱った視線がまとめて砕いていった。
気後れしながらも横になった戊陽に覆いかぶさるようにして抱きしめる。頭の下に手を入れ自分の首元に収めるようにすると、ひやりと冷たい戊陽の肌に触れてゾッとした。
「陛下、体の温まるものを胃に入れて下さい」
「……うん」
こういう時に玲馨が畏まる事を戊陽は嫌うのだが、今日はごねる気力さえも無いらしい。
暫く抱き締めていたが玲馨の方が体の熱を奪われていくようでちっとも体温が上がらない。前に寝込んだ時もこうだった。玲馨を死の淵から救ったあの時も。
戊陽は玲馨を救い、戊陽は床に臥した。それから、感謝されこそすれ謝る事など何一つなかったというのに、猿猿の事を玲馨にどうやって詫びたらよいかをずっと悩んでいたのだと打ち明けた。
そういう人だと身に沁みて分かっているからこそ、今回の派兵に戊陽が同行すると知って気が気ではなかったのだ。案の定、こうして横臥する戊陽を見る羽目になってしまった。
「……俺がこれだけ弱っても、まだお前はどこか及び腰になってしまうんだな」
俄に驚き体を離す。こんな時に言う台詞ではない。
「寧ろ、病人を相手に積極的になれましょうか」
「ふ……。いつもお前にはやり込められてばかりだ。玲馨には一生勝てそうにない」
笑ったつもりなのだろう、目を微かに細め、戊陽は手を玲馨の頬に差し伸べた。その冷たい手を取って両手で包み込むと、玲馨は祈るように目を閉じる。
玲馨に癒やしの力はないが、祈る事くらい許されるだろう。
玲馨が祈るのは、この先の戊陽が自分を棄てるような日が来ないようにだ。
「……また、兄上の夢だった」
戊陽が悪夢を見る時は決まって彼の兄、黄昌の最期だ。黄昌は非業の死を遂げている。
そして戊陽は、第二皇子に生まれ本来即くはずのない帝位に即き、後ろ盾がないまま二年。即位して暫くは貴族間の勢力図も乱れ、政治は混乱し、皇太后の座であわや血が流れるのではと思うほど宮廷は逼迫した。それらをどうにか抑え込み、無理矢理にでもまとめられたのは戊陽の叔父の助言があったからだった。だが紛れもなく戊陽の采配で宮廷はひとまず纏りはしたという事に嘘はない。
戊陽が皇帝に相応しいか見極めの時期は疾うに過ぎたろう。第三、第四皇弟を神輿に権力を得たい貴族たちも、間もなく見切りをつけて戊陽の信頼を獲得しに動き出すはずだ。玲馨の耳に届いていないだけで、水面下では既に何かしら動いているかも知れない。
いよいよこの天下は戊陽の物になるのだ。そうしたら──もう、逃げられない。戊陽は真に皇帝になってしまう。
「次、があれば……」
「……ん?」
「次は、逃げないと約束します」
玲馨の言った意味を理解した瞬間、戊陽の頬がぽっと赤く染まった。こんな事で熱を取り戻しては威厳に愛想をつかされそうだ。
釣られて自分まで赤くなりそうだったのでさっさと戊陽の手を放し立ち上がる。
「白湯を持つよう伝えておきます」
「もう帰るのか」
見上げてくる目は男というよりさながら幼い子供のそれだ。もしこれが児戯のような視線でなければ、玲馨は留まったかもしれない。ほっとしたような、少し物足りないような気持ちを抱えて踵を返す。
「陛下は、時々私が皇帝付きの宦官だという事を忘れているような気がします」
「それは……どういう……」
戊陽が意味を理解するのと玲馨が扉を閉めるのはほとんど同時だった。扉の向こうからうーんという呻き声が聞こえてくるが体調不良が原因ではない事くらい分かる。
皇帝付きの宦官は皇帝のためのもの。皇帝の傍に控えて身の回りの世話をするものだ。望むなら昼も、夜も。
せいぜい悶々として過ごせばいい。
火照った頬に戊陽のおかげで冷えていた手の甲を当てながらその場を立ち去った。
向青倫の屋敷はそれは立派な構えだった。山芒郡は山を開拓していった土地で、全ての山村そして領都が山間に位置している。当然平地は少なく山や森林と隣合い共存するように家も畑も作っていった。そのため都市の一つに数えられながらも大きな建築物というのは数が限られており、その中で敷地面積で言えば軍事施設に次いで向青倫の屋敷は広いのだそうだ。
屋敷のうち一つの房を客間として使っており、戊陽と李将軍はそこに泊まっている。目に入る物全てが玲馨たちが寄宿する高楼より上等な物ばかりの中を歩き、表門を出てすぐだった。
「止まって下さい」
聞き覚えのある声に言われて体はすんなり止まれを出来たが、視線は目の前に突きつけられた怪しく光る金属を追いかけた。反りのない細長い剣身の先、柄を握りしめたその人物に、玲馨は落胆する。
「……辛新殿。どうしました?」
玲馨の喉が裂ける距離まで一寸。左右を振り返る動作でさえ皮膚を傷つけそうで根源的な怖じ気が血の気を引かせていく。
「玲馨さん、あなたは……」
──あなたは、皇帝の情夫ですか?
反射的に体を引くとすぐ真後ろにあった辛新の胸と背中がぶつかった。玲馨の体が当たったくらいではよろめかない武人の体は硬く、気の良さそうな辛新の姿が想像出来なくなる。武芸を齧った程度の玲馨にも力の差がよく分かった。
「私に、向家の公主ほどの価値があると思われましたか?」
「っ……!」
背後の体に緊張が走ったのが分かった。首筋を剣の刃が掠めて血が滲む。
「正直に話しましょう。私という人間を盾に取られた戊陽陛下がどんな行動に出るのかは私にも分かりません。いっそ見てみたいくらいです」
「恐ろしい事を言うんですね……」
「どうします? 殺しますか? 出来れば、いえ絶対に勘弁してほしいのですが、もし私に本当に人質としての価値があるなら試してみても良いかも知れません」
戊陽の枷になるくらいなら死んでしまった方が良い? いいやそんな事は露も思っていない。これは玲馨の性格がそう勝手に言葉を吐かせているだけだ。
恐怖に負けてしまうのは子供の時にやめると誓った。抗わなくては弱者である玲馨は何もかもを奪われてしまうのだから。
震えていた剣が下げられると、知らず知らず詰めていた息を吐き出した。恐ろしいものはやはり恐ろしいので、今になって指先が震え出す。咄嗟に拳を握った。
後ろを振り返れば、青い顔で視線を落とす辛新が佇んでいた。そうして体を丸めていると、兵士にしては小柄な体格がより浮彫になる気がする。
「なーんだよ俺の出番は無しかー?」
間延びした声の闖入者はぺしぺしと短剣の腹で手の平をうちながら、塀の影から姿を現した。それに驚いたのは辛新だけで、玲馨は平時と態度が変わらない。いや寧ろ少し怒っている。
「遅い。辛新殿が思いとどまらなければ私は首と泣き別れだった」
「これだから素人は。あの角度で人間の首を落とすなんざ出来た日にゃそいつは化け物よ」
「な、何なんですか、何て物騒な話ですか!」
「いやあんたに言われてもな、辛新」
梅 にしては珍しく剣呑な目つきで睨みつけられると辛新は言葉に詰まって押し黙った。さしもの辛新でも今の梅の言葉を笑って流せる能天気ぶりは発揮出来ないらしい。
梅が無言で手の平を上にして辛新に向かって差し出すと、何を求められているのか察して辛新は剣を渡した。ごくありふれた軍の単剣だ。梅は剣を鞘から少しだけ抜いて刃を眺めて「へぇ」と感心している。
「それで? こいつの事は誰に報告するのが正解? 皇帝、木王、将軍、と選り取り見取りだなぁ」
辛新の所属を考えれば将軍だが、梅の軽口に付き合っていると時間だけが過ぎてしまう。ひとまず彼の存在は無視して、無手となった辛新へと向き直った。
「少し、場所を移しましょうか。木王の傍ではあなたも口が重くなりそうですから」
腹が減ったと梅が言うので株景の屋台で麺の入った汁物を三人分購入し、小川の近くの欄干に座って麺をすする。子供でも食べ切れる程度の量だったので梅はほとんど飲むようにしてあっという間に平らげてしまった。一方辛新は食が進まないようで匙さえ手にせず椀に視線を落としている。
「概ね辛新殿の事情は調べたつもりです」
丸二日だ。辛新が朝には戻ると言って玲馨たちと別れてから二日以上が経っても戻って来ないので、さすがに疑っておいた方が良いかと彼の素性についてあちこち聞き込みをした。
「私を使って陛下を脅したところで向家の公主の入宮を取り消すというのはほとんど不可能ですよ。あなたと私で共倒れして、公主は大切な人を失って。悲劇にしかならない」
ついでに戊陽とて悲しむだろう。ああそうだ戊陽は絶対に悲しむのだからわざわざ死を覚悟して辛新を煽ったわけではない。
「そんな事をするくらいなら、まだ駆け落ちの方が可能性があるかもしれませんね」
他人の色恋にはよっぽど興味が湧かないのか梅は鼻などほじりながら、小川で元気よく跳ねる魚を鑑賞している。小川に屋台の店主が野菜の端切れか出汁を取った後の貝でも捨てているのかも知れない。梅が小石を投げると魚はぱくぱく口を開いて虚空を食んでいる。
「でもあなたも公主も駆け落ちを選ばなかった。選べなかった、と推察されますが」
反論があればさぁどうぞと言葉を切り、玲馨も最後の一口を食べ終えた。使っている醤が紫沈とは違うようで甘辛い汁は山間部という過酷な環境で働く農夫たちに好まれそうである。
「……やはりどなたから私の噂を聞かれたのですね」
「あんた、有名人じゃねぇか。名前出したら出るわ出るわ女の噂話!」
辛新を責めるとなる梅は途端に身を乗り出し玲馨たちの会話へと混ざってくる。かと思えば、梅は一口も手つかずなのをいいことに辛新から椀を奪って麺を食べ始める。梅には配慮というものが欠けている、というよりまるで無い。
「向家の公主さんに懸想してんのがバレて左遷なんだってなぁ」
皇帝直属の禁軍へ入る事を左遷と梅が表現したのは、玲馨と梅に夜這いを仕掛けた毛花鈴の口振りをそのまま受け取っただけだ。花鈴によれば辛新は左遷と似たような扱いを受けたようだった。
とはいえ、後宮に入れようとしている一人娘と下級貴族が恋仲になどなってしまって、その命を取られなかっただけ感謝しなくてはならない。しかし、辛新は諦め悪くどうにか公主を自分の女にせんと画策した訳である。
その結果、辿り着いたのが玲馨を使っての脅し、交換条件といったところか。「お前の愛妾を返してほしくば向の公主をこちらへよこせ」
これが成功したなら戊陽は皇族きっての恥さらしとして歴史に名を残すに違いない。それはそれで面白いし、いっそこんな皇帝には国を任せられないと退位でもさせられれば玲馨もこんなに楽な事は無いと思うが。現実はそう簡単にはいかない。
「こちらでは向公主の顔は広く知られているのですか?」
あわい発生以後七十年、切り離された地方は地域色が強まっているというが、やれ嫁入り前の娘だと大事にしすぎるあまり日の光さえ浴びさせてもらえないという事がないとも言い切れない。しかし「人気の公主様です。慰問に出向けば民に囲まれるような」という辛新の言葉で否定される。駆け落ちという強引な手段に出られない訳である。
「八方塞がりという訳ですね」
最早会話に加わってくる気をなくしたか、辛新の分も食べ終えた梅は欄干に座ったまま船を漕ぎ出した。落ちろ、落ちろと念じていると辛新が控えめに声を掛けてくる。
「私の気のせいでしょうか。先程から玲馨さんはまるで私たちを応援して下さっているように聞こえるのですが……」
応援とはこれまた大それた事を言う。しかし今のところそう思わせておく方が都合が良いかも知れないと考え応援については触れず、玲馨はこう答えた。
「お二人が添い遂げるためには、どうやら最たる障害を消すしかないようですね」
つい、と玲馨が視線を向けたのは向家の屋敷だ。そこには今誰が居るのか。向青倫夫妻とその娘。それから──。
「え……えええっ!?」
辛新の大声でびっくりして目が覚めた梅は、勢い余って本当に川へと落ちたのだった。
尻から川に落ちた梅を辛新が助ける横で一切手を貸さずに玲馨はひとりごちる。
「ところで、辛新殿は何故私を陛下の情夫などと思われたのです?」
建国数百年ともなれば沈国の皇帝には宦官を情夫にし男色を好んだ者も少なくないが、実情はさておき戊陽が「そう」という噂は耳にした事がない。結婚が遅いという意味なら先帝の黄昌《ホアンチャン》も皇后や妃を選ぶ事なく世を去ったが黄昌にも男色の噂はなかったはずだ。
と、二対の視線が瞬きも忘れて玲馨を見つめている事に気付く。その視線にはどうしてか距離を感じた。
「……私は陛下ご本人も暗に認めているんだと思っていました。だから後宮を持たないんだとばかり」
「まぁこんだけあっちこっち作りが良いとなぁ……。女からの嫉妬も凄そうだぜ」
梅は辛新を快く思っていないはずだが何故か同調して同じ所から玲馨を見ている。梅の視線にはあの値踏みする気持ち悪さが加算されているが。
玲馨の外見についてだが、二十年以上生きてくれば自分の顔形の良し悪しにはさすがに自覚せざるを得なかった。人間の姿の美醜にはあまり頓着しないが、玲馨のそれは上から順に佳麗美で格付けするなら佳人と呼ばれるような造形だと認めている。
宦官である事を差し引いても男らしさとはあまり縁が無く、細身で肌も白い。だがそのほっそりとした体付きがこの中性的な見た目によく似合い、鼻の下を伸ばす男も見惚れる女も、そして嫉妬や羨望を向けてくる者も相応に多かった。
だが、まず戊陽と玲馨との間には明確な身分という隔たりがある上に、たった一人の宦官のために皇后も妃も選ばず、世継ぎを作るという天子の使命を放棄するなど有り得ない。と、玲馨は思うが、存外人とは本のようなお伽噺を現実に見たりするものなのかも知れない。
頭の中で猿猿が笑ったような気がした。
「とりあえず事情は分かりました」
「否定はしないんですね玲馨さん」
「……」
「……え?」
「違いますよ」
「ええっ!?」
「勝手に納得しないでください。まぁ、どう解釈されようがさほど困るものでもありませんが」
皇帝が宦官に熱を上げていようがやがて入宮する者は決められて戊陽の後宮が築かれるのだから、ここで取り繕う事にさほどの意味はない。
「玲馨さんは肝が据わってるんですね……?」
「それを言うなら辛新殿の方ですよ。私は自分の恋路のために皇帝を脅すなんて実行に移せませんから」
「ああもうその件は本当にすみませんでした!! あの晩実は──」
おおかたそうだろうと予測をつけてはいたのだが、玲馨と梅が花鈴に夜這いを仕掛けられていた頃、辛新は実家に帰ると嘘をついて向家の公主と逢引きをしていたそうだ。そこで我慢していたものが爆発しいてもたってもいられず大した計画があるでもなく玲馨に剣を向けたのだと告白し深く謝罪した。
思い合う人と添い遂げたい。それは時として酷く難しい。親子でさえ共に暮らしていく事が出来ない世の中で、我欲を通す事で生まれる不都合の多さといったらない。
辛新と公主がもし駆け落ちをしたら今度は公主の姉妹やそれに近い立場の従姉妹などが後宮に召される。向の公主には姉妹はいないそうだから、今回に至っては親戚筋から若い娘が選ばれるだろう。
辛新たちが自分の幸せを選べば誰かが不幸になる。逆に辛新と公主が我欲を飲み込めば誰かが不幸にはならない。
だから選ばなくてはいけないのだ。自分の幸福か他人のせめて不幸ではない人生か。歩いは、新たな道を模索するか。
「天を脅かす、という方法もありますね」
「……? 何の話ですか?」
「公主を後宮から遠ざける方法です。宮廷が火に包まれれば入宮どころではなくなると思いませんか」
「火ってまさか……」
「もちろん喩えですが」
辛新の円らな瞳がだんだんと怯えの色に染まっていく。
一体辛新は何を想像しただろうか。燃え上がる城か、それとも火矢を番えた大量の弓兵に包囲される場面か。
「玲馨さんは恐ろしい人です。私はあなたを使って陛下に交渉しようと考えた時、自分で自分の発想を恐ろしいと思いましたが、私はあなたの足元にも及ばない」
光栄です、と答えれば良かっただろうか。玲馨はただ、無言で応えた。
岳川の調査について現在分かっている事は、どうやら河川の幅を広げようとしている事と、川周辺の水脈を掘り当てようとしているという二点だ。あちこちを掘り返しているのでまず山芒の水不足を考えたがそんな様子はない。だとすると、川そのものを拡大させようとしている、という推測だけが玲馨の中に残った。
川幅を広げたところで流れる水の量は据え置きである。そのため地下水脈を掘り当て川を増水させようとしているのではないか。上流で川が増水すれば下流のどこかで氾濫が起きるかも知れない。岳川の下流には北玄海がある。
川というのは流れるものだ。川にも地脈が影響を及ぼすが、上流で豊富な地脈の力を蓄えた水が何故あわいを通ると濁るのか。それはあわいを通るうちに川の地脈が吸い取られるからだと考えられている。
では上流から流れる地脈を多く含んだ川の水が増えればどうなるか。ややもすると海に流れ出るまでに僅かに地脈の力が残るのではないか。
もしも、下流で氾濫するのは地脈の力を残した川の水だとすると──。
「何が起きるんですか玲馨さん」
すっかり元の調子を取り戻した辛新は、改めて朝食を食べながら玲馨の仮説に耳を傾ける。
梅は濡れた袍の裾を帯に挟み袴を膝までたくしあげた格好で通りがかった女に悲鳴を上げられているが、本人は一切気にしておらずすれ違ってゆく女たちに手などを振っている。
「きっとあわいが縮むんです」
「ほう……というと?」
「これが上手くいけば沈からあわいが消える事になりますね」
「なんと! それはとんでもない発見ではないですか!」
玲馨は自分で言っておきながら実際には難しいだろうと思っている。
というのも、山芒で行われている事は地脈を薄く伸ばしているだけに過ぎないからだ。
しかし地脈は沈の建国以前からこの土地と深く結びついたものでありながら、未だに分からない事が多い。薄く伸ばしたのだとしてもそこから地脈が回復するとも知れないし、薄くても十分に人が暮らしていけるなら問題はない。
が、しかし、である。たった一ヶ月程度の工事でそんな事が可能ならこの七十年の間に川によって流れた地脈で海のある北玄海はもっと地脈が回復していても良いはずなのだ。
「しかし、地脈とは不思議なものです。まるで生き物のような」
生き物。
何故かその表現が、玲馨の中で引っ掛かった。
「地脈について知るには、切り口が少なすぎますね」
嘗ては卜師と呼ばれる人たちが彼ら独自の技術を用いて地脈を読み国に繁栄を齎したとされるが、あわいが発生した頃に卜師たちは凱寧皇帝の怒りを買って罷免されている。公的な記録には残っていないが、その後卜師たちは一人残らず処刑されているだろう事が個人の手記によって考察出来た。
卜師たちの持つ技術や知恵が現代に残っていれば、もう少し状況も違っただろうに。
ふと、騒がしかった、というより騒がれていた男が静かになっている事に気付く。梅を探して辺りを見回すと、屋台の影に隠れてどこかを注視している。格好はそのままだわ屋台の店主には迷惑そうな顔をされているわで目立っているが、本人はやはり気にしていない。
「何をしているんだ」
「あいつ、物盗りっぽいなって」
通りに沿って堀があり、堀に沿って民家が並んでいるが、そのうちの一つに男が立っている。格好は短褐穿結──粗末な服装──であるが村人だと思えば普通の範囲に収まるか。しかし髪は肩の下で緩く結わえておりそれがみすぼらしさを加速させ、戸口の中を覗く様子がどうもおかしい。
「逆に怪しすぎると思うが」
「んー……」
何かの勘が働くのか梅の関心は男から逸れていかない。ここでこうして見張るのは玲馨たちの領分ではないので山芒の役人にでも報告するのが筋だが。
玲馨の頭の中で、閃くものがあった。
「……おい梅、身なりを整えろ。それからあの怪しい男を捕まえるんだ」
「何で?」
「恐らく私はあの男を知っている」
荒事になるとやはり梅は手際がよく、怪しい男に音もなく近づくと男の腰に左手で持った短剣の柄を当てて声を掛けた。
「おっと。大声は上げてくれるなよ。ちょっとだけ話を聞かせてくれねぇか」
「……誰だ貴様は」
「ご無沙汰しております周刺史」
後ろからついてきていた玲馨が梅の隣に並んで声を掛けると、剣呑だった男の顔つきががらっと変わる。
「あなたは……!」
物盗りに見えた男の正体は地方を監察するために任命される刺史だ。歳は五十近く、名を周子佑といい、玲馨が北玄海で調査に当たった時に現地で対応したのは彼だった。つまりどういう訳か北の地の刺史が管轄外の山芒に来ている事になる。
「もしやお休みのところ里帰りなさっていたのでしょうか?」
「へ? あーあはは、ええそうでそうです。元は山芒の出身でして」
山芒出身の官吏が中央の采配で北玄海の刺史に。無い事ではないが。
「少し暇を頂きまして実家に……あの、その物騒な物を退けていただけませんかねぇ」
至って胡散臭そうに周刺史を見下ろしていた梅だったが、肩を竦めて剣を戻した。
周刺史は息を吐いて縮めていた体を伸ばすと些か威厳を取り戻した声で言った。
「私的な事ですので、どうか今日ばかりはご勘弁を」
その「今日」を逃したらこの男はきっと山芒からも北玄海からも行方を眩ますのだろう。そんな雰囲気がある。
「そうしたいのはやまやまですが、私も明日には山芒を発つ予定でして」
玲馨よりも後ろで「え?」と声を上げたのは辛新だ。すかさず彼を隠すように体の角度を変える。
「陛下にもあなたの事を報告した所、周刺史の辣腕ぶりに感心しておられました。良ければまた北玄海の時のように、今度は地元の山芒の話を周刺史からお聞きしてみたい」
ふ、と微かに玲馨が微笑むと、周刺史はぐぅと唸りたそうな顔で黙り、やがて小さく「分かりました」と答え渋々中へ三人を案内した。
「譫言であなたの名をしきりに呼んでいます」と言われた時には玲馨は自分の目と耳を疑った。
戊陽が生まれた頃から仕えている無口な宦官の名を四郎というので、四男の生まれだったのだろうかと密かに考えているが本人に直接訊いた事はない。
四郎は無口などという生易しい表現では足りないほど寡黙だった。まず口を開くという事をほとんどしない。二十年来の付き合いで知らない事はないくらいの戊陽をして「奴との交流は諦めた」と言わしめるほど徹底した滅私ぶりである。
玲馨とも十年ほどの付き合いになるのでもうすっかり鉄面皮にも慣れたものだが、幼少期はにこりともしない表情の死んだ顔が不気味だった。
四郎は戊陽の影だ。いついかなる時も戊陽の傍に侍るが口を開かない。言い付けられた事を素早くこなすが余計な事は絶対にしない。
そんな四郎が玲馨を早朝一番に戊陽のもとを離れてまで呼びに来たという事実は、戊陽の身に何かよっぽどの緊急事態が発生したのかと焦らせ、玲馨は朝もまだ暗いうちから領都の株景まで走らされた。
結果、爆睡する戊陽の寝顔を拝む事になった。穏やかな寝息を立てる戊陽の様子は癒やしの力を使いすぎた反動で、これまで何度か玲馨も見てきた姿と変わらない。拍子抜けである。とは言えもちろん安堵する気持ちは大きい。
戊陽が彼だけに使える力を行使する様を何度か見てきた。怪我も病気もたちまち治してしまうがその代償に戊陽は自身の体力を削られる。どうやらそれは傷病の重篤さに比例するのと、単純に多くの患者を治せばそれだけ疲弊するものらしい。
それから所謂「死病」を取り除く事は出来ない。彼の父である黄雷は胸を患い、戊陽の献身も報われずに早逝した。怪我も同じだ。治せる「程度」というものがある事は力を宿した代々の皇族たちの研究によって判明している。
株景に着く頃には朝日も上り、町が活動を始めていた。玲馨が来るまでに落ち着いたのか、戊陽は深く寝入っており譫言を呟く様子はない。
玲馨は深く眠る戊陽の無事を確認して部屋を出て行こうとしたが、戊陽が身動ぐ微かな音に引き留められた。
「り……しん」
戊陽の穏やかな寝顔が段々と険しくなり始め眉間に深い皺が刻まれる。どこか痛むのか堪えるように歯を食いしばり、胸が大きく上下し呼吸が荒くなっていく。
「りんしん、玲馨……っ」
人の名を呼びながら悪夢を見ているとは。複雑な胸中にさせられつつも見ていられなくて戊陽の肩を掴んで揺り起こした。
「陛下、戊陽陛下。もっと幸せそうな夢をご覧に──」
続く言葉は突然大きく開いた戊陽の目に遮られる。音がするほど近い距離で目と目が合っている。しかしそうして見つめ合っていたのは、そんなに長い時間ではなかった。
戊陽はすぐに自分の目の前にある顔が玲馨だと分かると、小さく玲馨の名を呟いた。
「随分な夢見だったようですね」
目尻に微かに滲んだ涙は見なかった事にしてやろうと離れようとするも、「りんしん」と余りにも切なげに名前を呼ばれるので思わず躊躇する。
「玲馨……頼む、抱きしめてくれ」
「……」
まるで子供みたいだとか、ふざけないでくれだとか、揶揄う言葉や拒否する言葉が頭の中でわっと溢れ出す。しかしその全てを戊陽の弱った視線がまとめて砕いていった。
気後れしながらも横になった戊陽に覆いかぶさるようにして抱きしめる。頭の下に手を入れ自分の首元に収めるようにすると、ひやりと冷たい戊陽の肌に触れてゾッとした。
「陛下、体の温まるものを胃に入れて下さい」
「……うん」
こういう時に玲馨が畏まる事を戊陽は嫌うのだが、今日はごねる気力さえも無いらしい。
暫く抱き締めていたが玲馨の方が体の熱を奪われていくようでちっとも体温が上がらない。前に寝込んだ時もこうだった。玲馨を死の淵から救ったあの時も。
戊陽は玲馨を救い、戊陽は床に臥した。それから、感謝されこそすれ謝る事など何一つなかったというのに、猿猿の事を玲馨にどうやって詫びたらよいかをずっと悩んでいたのだと打ち明けた。
そういう人だと身に沁みて分かっているからこそ、今回の派兵に戊陽が同行すると知って気が気ではなかったのだ。案の定、こうして横臥する戊陽を見る羽目になってしまった。
「……俺がこれだけ弱っても、まだお前はどこか及び腰になってしまうんだな」
俄に驚き体を離す。こんな時に言う台詞ではない。
「寧ろ、病人を相手に積極的になれましょうか」
「ふ……。いつもお前にはやり込められてばかりだ。玲馨には一生勝てそうにない」
笑ったつもりなのだろう、目を微かに細め、戊陽は手を玲馨の頬に差し伸べた。その冷たい手を取って両手で包み込むと、玲馨は祈るように目を閉じる。
玲馨に癒やしの力はないが、祈る事くらい許されるだろう。
玲馨が祈るのは、この先の戊陽が自分を棄てるような日が来ないようにだ。
「……また、兄上の夢だった」
戊陽が悪夢を見る時は決まって彼の兄、黄昌の最期だ。黄昌は非業の死を遂げている。
そして戊陽は、第二皇子に生まれ本来即くはずのない帝位に即き、後ろ盾がないまま二年。即位して暫くは貴族間の勢力図も乱れ、政治は混乱し、皇太后の座であわや血が流れるのではと思うほど宮廷は逼迫した。それらをどうにか抑え込み、無理矢理にでもまとめられたのは戊陽の叔父の助言があったからだった。だが紛れもなく戊陽の采配で宮廷はひとまず纏りはしたという事に嘘はない。
戊陽が皇帝に相応しいか見極めの時期は疾うに過ぎたろう。第三、第四皇弟を神輿に権力を得たい貴族たちも、間もなく見切りをつけて戊陽の信頼を獲得しに動き出すはずだ。玲馨の耳に届いていないだけで、水面下では既に何かしら動いているかも知れない。
いよいよこの天下は戊陽の物になるのだ。そうしたら──もう、逃げられない。戊陽は真に皇帝になってしまう。
「次、があれば……」
「……ん?」
「次は、逃げないと約束します」
玲馨の言った意味を理解した瞬間、戊陽の頬がぽっと赤く染まった。こんな事で熱を取り戻しては威厳に愛想をつかされそうだ。
釣られて自分まで赤くなりそうだったのでさっさと戊陽の手を放し立ち上がる。
「白湯を持つよう伝えておきます」
「もう帰るのか」
見上げてくる目は男というよりさながら幼い子供のそれだ。もしこれが児戯のような視線でなければ、玲馨は留まったかもしれない。ほっとしたような、少し物足りないような気持ちを抱えて踵を返す。
「陛下は、時々私が皇帝付きの宦官だという事を忘れているような気がします」
「それは……どういう……」
戊陽が意味を理解するのと玲馨が扉を閉めるのはほとんど同時だった。扉の向こうからうーんという呻き声が聞こえてくるが体調不良が原因ではない事くらい分かる。
皇帝付きの宦官は皇帝のためのもの。皇帝の傍に控えて身の回りの世話をするものだ。望むなら昼も、夜も。
せいぜい悶々として過ごせばいい。
火照った頬に戊陽のおかげで冷えていた手の甲を当てながらその場を立ち去った。
向青倫の屋敷はそれは立派な構えだった。山芒郡は山を開拓していった土地で、全ての山村そして領都が山間に位置している。当然平地は少なく山や森林と隣合い共存するように家も畑も作っていった。そのため都市の一つに数えられながらも大きな建築物というのは数が限られており、その中で敷地面積で言えば軍事施設に次いで向青倫の屋敷は広いのだそうだ。
屋敷のうち一つの房を客間として使っており、戊陽と李将軍はそこに泊まっている。目に入る物全てが玲馨たちが寄宿する高楼より上等な物ばかりの中を歩き、表門を出てすぐだった。
「止まって下さい」
聞き覚えのある声に言われて体はすんなり止まれを出来たが、視線は目の前に突きつけられた怪しく光る金属を追いかけた。反りのない細長い剣身の先、柄を握りしめたその人物に、玲馨は落胆する。
「……辛新殿。どうしました?」
玲馨の喉が裂ける距離まで一寸。左右を振り返る動作でさえ皮膚を傷つけそうで根源的な怖じ気が血の気を引かせていく。
「玲馨さん、あなたは……」
──あなたは、皇帝の情夫ですか?
反射的に体を引くとすぐ真後ろにあった辛新の胸と背中がぶつかった。玲馨の体が当たったくらいではよろめかない武人の体は硬く、気の良さそうな辛新の姿が想像出来なくなる。武芸を齧った程度の玲馨にも力の差がよく分かった。
「私に、向家の公主ほどの価値があると思われましたか?」
「っ……!」
背後の体に緊張が走ったのが分かった。首筋を剣の刃が掠めて血が滲む。
「正直に話しましょう。私という人間を盾に取られた戊陽陛下がどんな行動に出るのかは私にも分かりません。いっそ見てみたいくらいです」
「恐ろしい事を言うんですね……」
「どうします? 殺しますか? 出来れば、いえ絶対に勘弁してほしいのですが、もし私に本当に人質としての価値があるなら試してみても良いかも知れません」
戊陽の枷になるくらいなら死んでしまった方が良い? いいやそんな事は露も思っていない。これは玲馨の性格がそう勝手に言葉を吐かせているだけだ。
恐怖に負けてしまうのは子供の時にやめると誓った。抗わなくては弱者である玲馨は何もかもを奪われてしまうのだから。
震えていた剣が下げられると、知らず知らず詰めていた息を吐き出した。恐ろしいものはやはり恐ろしいので、今になって指先が震え出す。咄嗟に拳を握った。
後ろを振り返れば、青い顔で視線を落とす辛新が佇んでいた。そうして体を丸めていると、兵士にしては小柄な体格がより浮彫になる気がする。
「なーんだよ俺の出番は無しかー?」
間延びした声の闖入者はぺしぺしと短剣の腹で手の平をうちながら、塀の影から姿を現した。それに驚いたのは辛新だけで、玲馨は平時と態度が変わらない。いや寧ろ少し怒っている。
「遅い。辛新殿が思いとどまらなければ私は首と泣き別れだった」
「これだから素人は。あの角度で人間の首を落とすなんざ出来た日にゃそいつは化け物よ」
「な、何なんですか、何て物騒な話ですか!」
「いやあんたに言われてもな、辛新」
梅 にしては珍しく剣呑な目つきで睨みつけられると辛新は言葉に詰まって押し黙った。さしもの辛新でも今の梅の言葉を笑って流せる能天気ぶりは発揮出来ないらしい。
梅が無言で手の平を上にして辛新に向かって差し出すと、何を求められているのか察して辛新は剣を渡した。ごくありふれた軍の単剣だ。梅は剣を鞘から少しだけ抜いて刃を眺めて「へぇ」と感心している。
「それで? こいつの事は誰に報告するのが正解? 皇帝、木王、将軍、と選り取り見取りだなぁ」
辛新の所属を考えれば将軍だが、梅の軽口に付き合っていると時間だけが過ぎてしまう。ひとまず彼の存在は無視して、無手となった辛新へと向き直った。
「少し、場所を移しましょうか。木王の傍ではあなたも口が重くなりそうですから」
腹が減ったと梅が言うので株景の屋台で麺の入った汁物を三人分購入し、小川の近くの欄干に座って麺をすする。子供でも食べ切れる程度の量だったので梅はほとんど飲むようにしてあっという間に平らげてしまった。一方辛新は食が進まないようで匙さえ手にせず椀に視線を落としている。
「概ね辛新殿の事情は調べたつもりです」
丸二日だ。辛新が朝には戻ると言って玲馨たちと別れてから二日以上が経っても戻って来ないので、さすがに疑っておいた方が良いかと彼の素性についてあちこち聞き込みをした。
「私を使って陛下を脅したところで向家の公主の入宮を取り消すというのはほとんど不可能ですよ。あなたと私で共倒れして、公主は大切な人を失って。悲劇にしかならない」
ついでに戊陽とて悲しむだろう。ああそうだ戊陽は絶対に悲しむのだからわざわざ死を覚悟して辛新を煽ったわけではない。
「そんな事をするくらいなら、まだ駆け落ちの方が可能性があるかもしれませんね」
他人の色恋にはよっぽど興味が湧かないのか梅は鼻などほじりながら、小川で元気よく跳ねる魚を鑑賞している。小川に屋台の店主が野菜の端切れか出汁を取った後の貝でも捨てているのかも知れない。梅が小石を投げると魚はぱくぱく口を開いて虚空を食んでいる。
「でもあなたも公主も駆け落ちを選ばなかった。選べなかった、と推察されますが」
反論があればさぁどうぞと言葉を切り、玲馨も最後の一口を食べ終えた。使っている醤が紫沈とは違うようで甘辛い汁は山間部という過酷な環境で働く農夫たちに好まれそうである。
「……やはりどなたから私の噂を聞かれたのですね」
「あんた、有名人じゃねぇか。名前出したら出るわ出るわ女の噂話!」
辛新を責めるとなる梅は途端に身を乗り出し玲馨たちの会話へと混ざってくる。かと思えば、梅は一口も手つかずなのをいいことに辛新から椀を奪って麺を食べ始める。梅には配慮というものが欠けている、というよりまるで無い。
「向家の公主さんに懸想してんのがバレて左遷なんだってなぁ」
皇帝直属の禁軍へ入る事を左遷と梅が表現したのは、玲馨と梅に夜這いを仕掛けた毛花鈴の口振りをそのまま受け取っただけだ。花鈴によれば辛新は左遷と似たような扱いを受けたようだった。
とはいえ、後宮に入れようとしている一人娘と下級貴族が恋仲になどなってしまって、その命を取られなかっただけ感謝しなくてはならない。しかし、辛新は諦め悪くどうにか公主を自分の女にせんと画策した訳である。
その結果、辿り着いたのが玲馨を使っての脅し、交換条件といったところか。「お前の愛妾を返してほしくば向の公主をこちらへよこせ」
これが成功したなら戊陽は皇族きっての恥さらしとして歴史に名を残すに違いない。それはそれで面白いし、いっそこんな皇帝には国を任せられないと退位でもさせられれば玲馨もこんなに楽な事は無いと思うが。現実はそう簡単にはいかない。
「こちらでは向公主の顔は広く知られているのですか?」
あわい発生以後七十年、切り離された地方は地域色が強まっているというが、やれ嫁入り前の娘だと大事にしすぎるあまり日の光さえ浴びさせてもらえないという事がないとも言い切れない。しかし「人気の公主様です。慰問に出向けば民に囲まれるような」という辛新の言葉で否定される。駆け落ちという強引な手段に出られない訳である。
「八方塞がりという訳ですね」
最早会話に加わってくる気をなくしたか、辛新の分も食べ終えた梅は欄干に座ったまま船を漕ぎ出した。落ちろ、落ちろと念じていると辛新が控えめに声を掛けてくる。
「私の気のせいでしょうか。先程から玲馨さんはまるで私たちを応援して下さっているように聞こえるのですが……」
応援とはこれまた大それた事を言う。しかし今のところそう思わせておく方が都合が良いかも知れないと考え応援については触れず、玲馨はこう答えた。
「お二人が添い遂げるためには、どうやら最たる障害を消すしかないようですね」
つい、と玲馨が視線を向けたのは向家の屋敷だ。そこには今誰が居るのか。向青倫夫妻とその娘。それから──。
「え……えええっ!?」
辛新の大声でびっくりして目が覚めた梅は、勢い余って本当に川へと落ちたのだった。
尻から川に落ちた梅を辛新が助ける横で一切手を貸さずに玲馨はひとりごちる。
「ところで、辛新殿は何故私を陛下の情夫などと思われたのです?」
建国数百年ともなれば沈国の皇帝には宦官を情夫にし男色を好んだ者も少なくないが、実情はさておき戊陽が「そう」という噂は耳にした事がない。結婚が遅いという意味なら先帝の黄昌《ホアンチャン》も皇后や妃を選ぶ事なく世を去ったが黄昌にも男色の噂はなかったはずだ。
と、二対の視線が瞬きも忘れて玲馨を見つめている事に気付く。その視線にはどうしてか距離を感じた。
「……私は陛下ご本人も暗に認めているんだと思っていました。だから後宮を持たないんだとばかり」
「まぁこんだけあっちこっち作りが良いとなぁ……。女からの嫉妬も凄そうだぜ」
梅は辛新を快く思っていないはずだが何故か同調して同じ所から玲馨を見ている。梅の視線にはあの値踏みする気持ち悪さが加算されているが。
玲馨の外見についてだが、二十年以上生きてくれば自分の顔形の良し悪しにはさすがに自覚せざるを得なかった。人間の姿の美醜にはあまり頓着しないが、玲馨のそれは上から順に佳麗美で格付けするなら佳人と呼ばれるような造形だと認めている。
宦官である事を差し引いても男らしさとはあまり縁が無く、細身で肌も白い。だがそのほっそりとした体付きがこの中性的な見た目によく似合い、鼻の下を伸ばす男も見惚れる女も、そして嫉妬や羨望を向けてくる者も相応に多かった。
だが、まず戊陽と玲馨との間には明確な身分という隔たりがある上に、たった一人の宦官のために皇后も妃も選ばず、世継ぎを作るという天子の使命を放棄するなど有り得ない。と、玲馨は思うが、存外人とは本のようなお伽噺を現実に見たりするものなのかも知れない。
頭の中で猿猿が笑ったような気がした。
「とりあえず事情は分かりました」
「否定はしないんですね玲馨さん」
「……」
「……え?」
「違いますよ」
「ええっ!?」
「勝手に納得しないでください。まぁ、どう解釈されようがさほど困るものでもありませんが」
皇帝が宦官に熱を上げていようがやがて入宮する者は決められて戊陽の後宮が築かれるのだから、ここで取り繕う事にさほどの意味はない。
「玲馨さんは肝が据わってるんですね……?」
「それを言うなら辛新殿の方ですよ。私は自分の恋路のために皇帝を脅すなんて実行に移せませんから」
「ああもうその件は本当にすみませんでした!! あの晩実は──」
おおかたそうだろうと予測をつけてはいたのだが、玲馨と梅が花鈴に夜這いを仕掛けられていた頃、辛新は実家に帰ると嘘をついて向家の公主と逢引きをしていたそうだ。そこで我慢していたものが爆発しいてもたってもいられず大した計画があるでもなく玲馨に剣を向けたのだと告白し深く謝罪した。
思い合う人と添い遂げたい。それは時として酷く難しい。親子でさえ共に暮らしていく事が出来ない世の中で、我欲を通す事で生まれる不都合の多さといったらない。
辛新と公主がもし駆け落ちをしたら今度は公主の姉妹やそれに近い立場の従姉妹などが後宮に召される。向の公主には姉妹はいないそうだから、今回に至っては親戚筋から若い娘が選ばれるだろう。
辛新たちが自分の幸せを選べば誰かが不幸になる。逆に辛新と公主が我欲を飲み込めば誰かが不幸にはならない。
だから選ばなくてはいけないのだ。自分の幸福か他人のせめて不幸ではない人生か。歩いは、新たな道を模索するか。
「天を脅かす、という方法もありますね」
「……? 何の話ですか?」
「公主を後宮から遠ざける方法です。宮廷が火に包まれれば入宮どころではなくなると思いませんか」
「火ってまさか……」
「もちろん喩えですが」
辛新の円らな瞳がだんだんと怯えの色に染まっていく。
一体辛新は何を想像しただろうか。燃え上がる城か、それとも火矢を番えた大量の弓兵に包囲される場面か。
「玲馨さんは恐ろしい人です。私はあなたを使って陛下に交渉しようと考えた時、自分で自分の発想を恐ろしいと思いましたが、私はあなたの足元にも及ばない」
光栄です、と答えれば良かっただろうか。玲馨はただ、無言で応えた。
岳川の調査について現在分かっている事は、どうやら河川の幅を広げようとしている事と、川周辺の水脈を掘り当てようとしているという二点だ。あちこちを掘り返しているのでまず山芒の水不足を考えたがそんな様子はない。だとすると、川そのものを拡大させようとしている、という推測だけが玲馨の中に残った。
川幅を広げたところで流れる水の量は据え置きである。そのため地下水脈を掘り当て川を増水させようとしているのではないか。上流で川が増水すれば下流のどこかで氾濫が起きるかも知れない。岳川の下流には北玄海がある。
川というのは流れるものだ。川にも地脈が影響を及ぼすが、上流で豊富な地脈の力を蓄えた水が何故あわいを通ると濁るのか。それはあわいを通るうちに川の地脈が吸い取られるからだと考えられている。
では上流から流れる地脈を多く含んだ川の水が増えればどうなるか。ややもすると海に流れ出るまでに僅かに地脈の力が残るのではないか。
もしも、下流で氾濫するのは地脈の力を残した川の水だとすると──。
「何が起きるんですか玲馨さん」
すっかり元の調子を取り戻した辛新は、改めて朝食を食べながら玲馨の仮説に耳を傾ける。
梅は濡れた袍の裾を帯に挟み袴を膝までたくしあげた格好で通りがかった女に悲鳴を上げられているが、本人は一切気にしておらずすれ違ってゆく女たちに手などを振っている。
「きっとあわいが縮むんです」
「ほう……というと?」
「これが上手くいけば沈からあわいが消える事になりますね」
「なんと! それはとんでもない発見ではないですか!」
玲馨は自分で言っておきながら実際には難しいだろうと思っている。
というのも、山芒で行われている事は地脈を薄く伸ばしているだけに過ぎないからだ。
しかし地脈は沈の建国以前からこの土地と深く結びついたものでありながら、未だに分からない事が多い。薄く伸ばしたのだとしてもそこから地脈が回復するとも知れないし、薄くても十分に人が暮らしていけるなら問題はない。
が、しかし、である。たった一ヶ月程度の工事でそんな事が可能ならこの七十年の間に川によって流れた地脈で海のある北玄海はもっと地脈が回復していても良いはずなのだ。
「しかし、地脈とは不思議なものです。まるで生き物のような」
生き物。
何故かその表現が、玲馨の中で引っ掛かった。
「地脈について知るには、切り口が少なすぎますね」
嘗ては卜師と呼ばれる人たちが彼ら独自の技術を用いて地脈を読み国に繁栄を齎したとされるが、あわいが発生した頃に卜師たちは凱寧皇帝の怒りを買って罷免されている。公的な記録には残っていないが、その後卜師たちは一人残らず処刑されているだろう事が個人の手記によって考察出来た。
卜師たちの持つ技術や知恵が現代に残っていれば、もう少し状況も違っただろうに。
ふと、騒がしかった、というより騒がれていた男が静かになっている事に気付く。梅を探して辺りを見回すと、屋台の影に隠れてどこかを注視している。格好はそのままだわ屋台の店主には迷惑そうな顔をされているわで目立っているが、本人はやはり気にしていない。
「何をしているんだ」
「あいつ、物盗りっぽいなって」
通りに沿って堀があり、堀に沿って民家が並んでいるが、そのうちの一つに男が立っている。格好は短褐穿結──粗末な服装──であるが村人だと思えば普通の範囲に収まるか。しかし髪は肩の下で緩く結わえておりそれがみすぼらしさを加速させ、戸口の中を覗く様子がどうもおかしい。
「逆に怪しすぎると思うが」
「んー……」
何かの勘が働くのか梅の関心は男から逸れていかない。ここでこうして見張るのは玲馨たちの領分ではないので山芒の役人にでも報告するのが筋だが。
玲馨の頭の中で、閃くものがあった。
「……おい梅、身なりを整えろ。それからあの怪しい男を捕まえるんだ」
「何で?」
「恐らく私はあの男を知っている」
荒事になるとやはり梅は手際がよく、怪しい男に音もなく近づくと男の腰に左手で持った短剣の柄を当てて声を掛けた。
「おっと。大声は上げてくれるなよ。ちょっとだけ話を聞かせてくれねぇか」
「……誰だ貴様は」
「ご無沙汰しております周刺史」
後ろからついてきていた玲馨が梅の隣に並んで声を掛けると、剣呑だった男の顔つきががらっと変わる。
「あなたは……!」
物盗りに見えた男の正体は地方を監察するために任命される刺史だ。歳は五十近く、名を周子佑といい、玲馨が北玄海で調査に当たった時に現地で対応したのは彼だった。つまりどういう訳か北の地の刺史が管轄外の山芒に来ている事になる。
「もしやお休みのところ里帰りなさっていたのでしょうか?」
「へ? あーあはは、ええそうでそうです。元は山芒の出身でして」
山芒出身の官吏が中央の采配で北玄海の刺史に。無い事ではないが。
「少し暇を頂きまして実家に……あの、その物騒な物を退けていただけませんかねぇ」
至って胡散臭そうに周刺史を見下ろしていた梅だったが、肩を竦めて剣を戻した。
周刺史は息を吐いて縮めていた体を伸ばすと些か威厳を取り戻した声で言った。
「私的な事ですので、どうか今日ばかりはご勘弁を」
その「今日」を逃したらこの男はきっと山芒からも北玄海からも行方を眩ますのだろう。そんな雰囲気がある。
「そうしたいのはやまやまですが、私も明日には山芒を発つ予定でして」
玲馨よりも後ろで「え?」と声を上げたのは辛新だ。すかさず彼を隠すように体の角度を変える。
「陛下にもあなたの事を報告した所、周刺史の辣腕ぶりに感心しておられました。良ければまた北玄海の時のように、今度は地元の山芒の話を周刺史からお聞きしてみたい」
ふ、と微かに玲馨が微笑むと、周刺史はぐぅと唸りたそうな顔で黙り、やがて小さく「分かりました」と答え渋々中へ三人を案内した。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
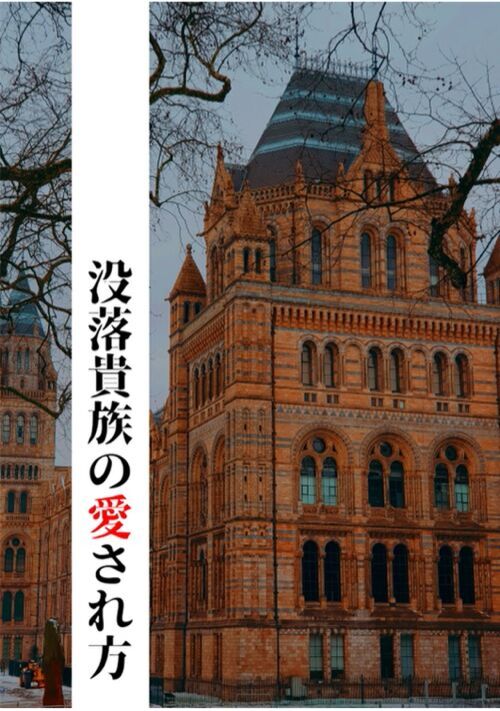
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















