15 / 44
宮廷編
15宮廷の毒
しおりを挟む
沈では官職の最高位の事を宰相と呼んでいる。時に皇帝に変わって政を取り仕切り、或いは皇帝に知恵を授ける相談役のような立場であるが、現在の宰相職に就いている者は「鳩」である。
二年前、前皇帝が急逝した際に、皇位が空白の期間が存在した。その短い空白期間に官吏の人事を司る部署が中心となって配置換えが行われた。既に当時から国政は皇帝の手から離れつつあった事の証明でもある。
そうして連れてこられた宰相はそれはもう小胆な男で政にも一切詳しくない、見かけも性格もまさに小男だった。
背後に居る誰かの言葉を皇帝に伝え、皇帝の意思を同様に誰かに伝える。故に「鳩」だ。あの宰相はそれ以上の役割を果たす事を許されておらず、残念な事に本人もそれを良しとしてしまっていた。
そんな宰相に、玲馨は北玄海へ行くよう言い渡された。それが二ヶ月ほど前の事だ。断る事は出来たが、「北玄海で浮民の受け入れが行われている」という情報は戊陽も玲馨も単純に気になった。恐らくは玲馨の邪魔をしたい勢力からの妨害だろうと思いながらも、北玄海行きを決めたのだった。
調査の結果はご存じの通りである。宰相の差配は邪魔どころか寧ろ戊陽への密告と言って良いだろう。それを「邪魔」だと早合点してしまったのはこれまでの宰相の立ち回りももちろんだが、北玄海へ行く前の玲馨の行動に理由があった。
玲馨は北玄海へと赴く前に、とある事を調べていた。先帝黄昌を毒殺したその下手人の出身についてだ。
戊陽の兄は二年前、毒を飲まされ殺された。
玲馨とそして戊陽は、服毒し血を吐き横たわった黄昌の遺体をその目で見ている。二人が、最初に死んだ黄昌を見つけ、事が明るみになったのだ。その時に黄昌へ毒を盛ったと思われる男も共に死んで見付かっている。
「玲馨? どうした話を続けてくれ」
「あ……はい。ええと」
じ、と間近で戊陽に見つめられてたじろぐ。息がかかりそうなほど顔を近づけられていたのに全く気付かなった。
すぐに一人で考え込むのは玲馨の悪い癖だ。戊陽もよく知っているので狼狽える玲馨を見て小さく笑っている。それを横目に睨むと、戊陽はますます楽しそうに笑みを深めた。
ここは紅桃宮の戊陽の寝所だ。寝所に居る理由はただ一つ。密談するのに向いているから。宦官も宮女も全て完全に人払いがされている。
まさか戊陽と玲馨が寝所で皇帝暗殺について話しているなどとは誰も考えないだろう。証拠に気を利かせた宮女は湯を張った桶や手巾を用意し、玲馨には潤滑剤に使う香油の補充は必要無いかなどと聞いてきた。何と答えたものか悩んで玲馨が黙っていると、聞き耳を立てていた戊陽が「先日私が補充したので問題無い」と代わりに答えてしまった。
否定してしまうより勘違いを利用した方が都合が良い事は分かっていても、玲馨の胸中は複雑だ。ただでさえこのところ、朝議では後宮に入れる妃の事で持ち切りだと言うのに、戊陽が宦官に入れあげているという噂が立つのは外聞が良くない。
それに、実のところ香油は戊陽が後宮を出てから一度も使われた事はない。玲馨が宦官の宿舎に戻ってしまうと途端に機会がなくなった。何より当時は宦官も科挙を受けられるように奏上をすべく、案を練っている所で互いにそうした事柄へ意識が向かなかったという事もある。
だから、戊陽と玲馨は宮女たちが噂するような関係ではないのだ。
ひっそりと内心で溜め息を落とすものの、玲馨は一体何について嘆息したい気分になったのか、その自覚はない。戊陽との関係が噂される事にか、それともその噂に真実が伴わない事に、か。
「少し情報をさらいます。まず先帝を弑した下手人の名は呂憲。禁軍の兵士で、呂家へ養子に入って紫沈所縁の貴族身分を獲得しています。元の名や出身は不明」
うん、と戊陽は首を小さく振る。続けろという意味だ。
「下手人の元の名や身分については徹底的に身元を隠されているようで緒が見付からず……。なので呂家の方を調査する事にしました」
「そうしたら呂家、つまり呂氏は既に没落し、身分を放棄した貴族だった事が分かった」
「そうです」
呂という姓の貴族はおよそ六十年も昔に貴族ではなくなっていた。跡継ぎに恵まれなかったのか、資金繰りに困窮し屋敷や家財など売り払って矜持を保てず身分を手放したのか、詳しい理由は分からない。とにかく呂氏という貴族は既に沈には居ないという事だ。
それが何故か養子を迎えてあろうことかその養子は皇帝直轄の護衛軍である禁軍の兵士になっていた。
黄昌が呂憲の事を知っていたかどうかは今となっては分からない。呂という家の怪しさから呂憲は宮廷へ送り込まれた刺客だった事は確実だろう。
それから呂氏に関して更に詳しく調べていくと、呂氏は元々商家だった事が判明する。元は呂という姓ではなかったのだ。
最後は身分を放棄してしまう事になるが当時は豪商として名を馳せており、呂氏から身分を買って呂という貴族になった元商人の家系だった。
では呂氏とは一体どこの貴族なのか。
沈の貴族にはいくつか種類があるが大きく分けて三つ。
一つ目は臣籍降下──または降嫁──や、賜姓降下によって皇族の親戚となった貴族。
二つ目は四方の領地を治める王の親類縁者。
三つ目は勲功を称えて皇帝によって新たに貴族として認められた氏族。
このうちのどれに属するかで、概ね勢力が分かれる。
しかし呂氏が身分を放棄したのが既に六十年前と古く、身分が売買された時期も不鮮明で、呂氏の過去を辿る線は難航していた。
……と、ここまでが北玄海へと発つ前に玲馨が調べていた事で、呂氏調査に行き詰まったところで件の宰相から北玄海行きの話が出たのである。
そのせいで呂氏について調べられては困る者から横槍が入ったのだとばかり思っていたが、呂氏の調査については北玄海で思わぬ進展を見せる事になる。
「呂氏は北玄海の貴族の可能性が高いようです。浮民受け入れによる人口増加の記録の中に呂姓を名乗らされている元浮民が五十名ほど居ました。恐らく土着の姓を宛てがう事で新住民を誤魔化したつもりだったのでしょう」
「では呂氏とは水王の縁者だったと?」
玲馨は首肯する。
「確証はありませんが」
沈の貴族の興りはとても古く紫沈で全ての貴族を管理するようになったのは七十年ほど前の事だ。呂氏の身分放棄は紫沈で管理されるようになって間もない頃の記録に残っていたが、呂氏の出自についての記録は無かった。
では古くは貴族の戸籍はどう管理していたかというと、出身地によって個別に管理していた。
紫沈では皇家縁戚の貴族と勲功貴族を管理し、四王縁戚の貴族は四方の地で管理していたという事だ。
呂氏の名が紫沈に記録として残っていない以上、四方貴族である事はほぼ確実。更に平民にも姓が与えられるようになってからは、その土地を四王から命じられて管理していた貴族の姓を名乗る事がほとんどだ。
浮民たちに付けられた「呂」という姓が誰かの思い付きでなければ、呂氏は古くは北玄海で暮らしていたと考えてまず間違いないだろう。
「それと、首謀者として獄死した文官ですが、同じく北の出身です。こちらは生家もはっきりしており、戴氏という貴族です。戴の人間に話を聞く事は出来ませんでしたが、噂が流れており何でも近頃戴家の者が数名罷免されたとか」
「兄上諸共、戴の者は謀られたか」
戊陽は低く呟いて、苦しいものを外に出すようにゆっくりと息を吐き出した。
「なまじ一月も紫沈を離れていなかったな、玲馨」
「ええ、本来の目的が完遂出来ないならと思って粘った甲斐が……」
嘆息と共に集中力も吐き出してしまったのか、戊陽の手が膝の上に置かれていた玲馨の手に重なる。一つしか無い机に椅子を二つ近くに並べていたせいで、肩を抱くにも腰を抱くにも絶妙な距離感に互いの体がある。
「陛下」
宮女に余計な気を遣わせてしまったせいで、そういう空気にならないよう敢えて二人きりでも態度を崩さなかったのに、そんな予防線は戊陽には通用しない。
何をするつもりなのかと身構えていると、戊陽はくったりと玲馨の肩に凭れかかった。
「罠の可能性も疑っていた」
戊陽の言葉にハッと息を呑む。ずっと意識しないようにしていた事だった。仮に罠だとしても動けるうちに動いておくべきだと思ったのだ。結果、事は思いの外玲馨たちにとって良い方向へ動いた。
「……心配をお掛けしました」
「本当にな。だから私を慰めてくれ玲馨」
「はい、はい?」
「お前の方から口吸いをしてほしい」
「は……」
今度こそ逃げられないように腰に手が回されて、戊陽は玲馨の方に首を傾けて目を閉じた。
腰を抱かれると、視界に映るのは、漏窓から斑に注ぐ日の光に照らされた戊陽だけでいっぱいになる。この時刻、日光は彼だけを明るく照らしていた。
玲馨と違って日に照らされると戊陽の髪はほんの少し赤く見えた。長い睫毛の下には金の虹彩が輝く瞳があるが今は瞼の下だ。鼻筋は高く通っていて唇は薄い端正な顔立ちをしており、改めて顔を見つめて男らしく育ったなと感慨に耽る。
このまま胸を押しやって突っぱねても拗ねはするが怒りはしないだろう。
なかなか玲馨が動こうとしないのでそのうち戊陽の眉根がむっと顰められる。思わずふ、と息を漏らして笑い、待ち侘びているその頬に唇を落とした。
「……………口吸いではない」
「私は口を吸いました」
「俺は吸ってない……」
「陛下、今日は久しぶりに李将軍と手合わせをするのでしょう? でしたら早く今回のことをまとめてしまわないといけません」
「……そうだな。分かってはいるんだ、分かっては」
ぶつぶつと文句を言いながらも改めて玲馨が調べ上げた調書に目を通し始める。
こんな風にまたふざけ合えるようになって良かったと思う。先帝が亡くなってからの戊陽は気が塞ぎ、それでも皇帝として即位すれば日々多忙に身をやつし、やがて酷い頭痛を起こすようになっていった。
今では頭痛の頻度は月に片手で数える程度にまで落ち着いている。痛みも随分軽くなったようで薬を飲むほどでも無い事がほとんどだ。
「それにしても戴氏の罷免は最近の事だと言ったな? 戴が先帝暗殺の首謀者として突き出されてから一年以上が経つが、遅すぎないか?」
「戴氏は北玄海の王である菫氏と並ぶ古い氏族だそうです。罷免されたと言っても刑死した者と兄弟関係だった者のみで、他には水王の菫武修であっても手が及ばなかったのでしょう」
「北は一枚岩ではないという事だな。そして尚書令は菫氏に協力していると」
いつ頃からそうなったのか分からないが、菫氏と並んで戴氏が力を持つ事は北玄海で暮らす者にとっては常識のようだった。しかしそれは明るみなれば常に周囲を蹴落とさんと鵜の目鷹の目の三方に付け入る隙を与える事になる。事実、今回の事で菫氏と尚書令が協力し戴氏は勢力を削がれる事となった。
その結果が果たして山芒と北玄海の協力関係に繋がるのかどうかまでは分からないが、戴氏の弱体は菫氏を身軽にしたに違いない。
「お前が紫沈を離れている間にな、俺は俺で調べていたんだが……」
「陛下が自ら? 何て危険な事を」
「いい加減にあの尚書令の対処をしなくては、沈の政は難渋を極めていくばかりだろ」
「そうは言っても」
「ふ、俺の心配する気持ちが多少は理解出来たか?」
「……私とあなたでは立場が違──」
思わず出た言葉だったが戊陽にじっとりと睨まれたので言葉を引っ込め小さく謝罪する。
「そも、凱寧帝の時代には強大だった皇帝の力が七十年の後にここまで衰退したのは何故だと思う?」
玲馨は教練房で教わった沈の歴史を思い出す。
「あわいによる地方との分断、後宮の縮小、官吏の減少……紫沈から『人』が減ったから、ですよね」
皇帝の権勢が衰えた原因は複合的なものでこれと明確に一つのものを挙げられない。
玲馨が指折り数えるのに合わせてうん、うん、と頷いていた戊陽は「だが」と顔を上げる。
「今と昔を比較した時、官吏は七十年前と遜色ないほど数を戻しているぞ」
「そう、なのですか?」
「見たからな、登用名簿を過去百年分ほど遡って」
一体彼のどこにそんな時間があったのか疑問に思ったが、常日頃玲馨が相手をしている時間を一ヶ月分調査の時間に割り当てたのだと気付いて突っ込むのをやめた。
「転機は凱寧帝が崩御した二十一年前、俺の生まれた年だ。そこを境に中央での官吏登用数がぐんと増えている」
凱寧は自身が皇帝の座に即いてから没するまでの数十年間、沈を掌握していた独裁者──暴君として今に伝わっている。その独裁が崩れた途端に旗色が変わったというのは概ね納得がいく。
「だが、それまで凱寧帝は徹底して自分に都合の良くなるよう周囲を固めていたはずだ。四王勢力を軒並み敬遠し、地方と紫沈を切り離して凱寧帝だけのための京師を築き上げた。だというのに死んだ途端に多くの四王所縁の貴族が宮廷に入ってくるのはおかしいと思わないか?」
戊陽はつまり誰がそれだけの官吏を登用したのか問うている。
普通に考えたら凱寧の次の皇帝か、当時の吏部の長官が主導する事になる。だが凱寧の実子である当時の皇帝はもちろん、吏部についても凱寧が抱き込んでいたはずだ。
玲馨は戊陽が即位する前の、皇帝が空位だった時期の事を思い出す。あの時、皇帝の指示なく勝手な官吏の配置換えが行われた。その中心となったのは吏部を含む実務機関を下に置く尚書省──現在の尚書令だ。
二十年前と言えば当時からの官吏も現在に多く残っており、凱寧崩御の頃と戊陽即位後の宮廷内勢力は実のところさほど大きくは変わっていないという事なのかも知れない。
「気付いたか? 老獪たちの一部は二十年前には既に凱寧帝の目を盗んで宮廷に入り込んでいたんだ。年齢から考えると最も長い者で五十年ほど前には四王勢力が皇帝から権力を奪おうと紫沈で画策していた事になる」
貴族身分であれば科挙を受ける必要がない都合上、二十歳になれば官吏として宮廷に入る権利を得る事になる。ただし当然誰かがその者の身分を保証しなくてはならない。現在の官吏たちのうち概ね四十路以上の者たちの中にはその「誰か」を見繕ってさも中央の貴族然として官吏となった訳だ。
その「誰か」を手っ取り早く見つける方法が一つだけある。
「……養子、ですか」
戊陽がゆっくりと深く頷く。
「先祖を悪し様には言いたくないが、こればっかりは凱寧帝に感謝だな。紫沈で全ての貴族を管理させたおかげで、当時戸籍まで偽るのはなかなかに難しかったらしい」
そう言って戊陽は一度椅子から立ち上がると、櫃から巻子を持って戻ってくる。とある貴族の戸籍の写しのようだ。
まだ真新しい紙の匂いのするそれを広げると、そこにはいくつかの人名が記されてあった。とある人物の前後三世代分の男子の名があり、それは二家に跨っている。この人物は養子縁組によって東江から紫沈の貴族になった事が明記されていた。
「これは、尚書令の……!」
尚書令は現在の宮廷において最も権威のある官吏の事だ。その名を林隆宸という。
戊陽と玲馨は、黄昌暗殺の真の首謀者は、林隆宸だと考えていた。
写しを見る限り、隆宸が林氏に養子に入る前の姓は楊といって東江の貴族である事が分かる。
「この楊というのは?」
戊陽は緩く首を左右に振る。
「東江の貴族という事しか分からなかった。だが、林氏というのは元を辿るとやはり東江の貴族らしい。それが長い間紫沈に暮らしたためいつ頃からか紫沈の貴族を自称するようになったのだろうな。この辺りはややこしくて面倒だ」
玲馨はこれまでに分かった事を頭の中で整理していく。
仮に林隆宸が黄昌暗殺の首謀者だとすると、正体不明の下手人を北玄海の貴族である呂氏に養子に迎えさせて呂憲と名乗らせた、という事になる。更に林隆宸が東江の出身ならば、北玄海は山芒のみならず東江とも協力関係を築いている事になるだろう。
玲馨は少し前まで四方が二つに分かれて相争う可能性を考えていた。しかし三方が協力しているとなると国を二つに分ける争いは起こらないと考えても良いのだろうか。
──いや……そんなに単純な話か? これは。
今回の山芒遠征を経て木王向青倫と皇帝が密に接したという事が外向きにも伝わってしまっている。一見すると三方が手を組む輪に皇帝勢力が加わったようにも見えるかも知れない──が、北玄海と東江には働きかけていない以上、見方を変えれば四方が互いに監視し合う輪から山芒だけが一つ抜けたという風にも見える。
これが四方の関係にどう影響するかは分からない。玲馨の頭で思い付く事はやはり、一刻も早く後宮に妃を入れようと山芒以外の勢力が躍起になるだろうという事くらいだ。
兎にも角にも万一の事態に備えるべく内憂は早々に解決したいところだが、数十年に渡って宮廷で勢力を育ててきた林尚書令が相手ではどうしても取っ掛かりが見つけられない。まさに八方塞がりだ。
「……陛下、周刺史いえ、周元刺史と話をする事は出来ますか?」
「周子佑か。数日中に紫沈まで護送されるはずだ。俺が刑部に話を通しておこう」
「よろしくお願いします。今なら、以前よりも有益な事をお話しして下さるかも知れません」
周子佑なら玲馨には探れなかった北玄海の深い事情まで知っているはずだ。問題は話させるために玲馨から提示出来るものが今のところ思いつかない事。北玄海について情報を渡せば刑を軽くしてやるとでも言えれば良かったが、如何せん玲馨はおろか戊陽にもその権限はない。
「北と東の刺史の二人は、一体どんな刑罰になるのでしょう?」
「んー……。禁固刑数年だろうな、普通なら。そも刺史とは令外官だ。刑を執行するにしても俺の頭を簡単に越える事は出来ない……──いや、そうか!」
林尚書令の記録の写しをくるくると巻いていた戊陽はその手を止めて何かを確信したような顔つきで玲馨の方へと顔を向ける。
「俺も行こう。お前の悩みを一つ解消してやれるぞ」
周子佑と同じく元刺史である卓浩の二人はおよそ七日の後に無事紫沈へと護送されてきた。偶然とはいえ禁軍が居合わせたおかげで、「不慮の事故」などに遭って死んでしまうという事はなかった。
戊陽は約束通り刑部に話を通し、玲馨を伴う形で二人は牢へと足を運ぶ。紫沈の地下にある牢屋へ訪れるのはこれが二度目だ。
初めてここへ来たのは一年前、黄昌暗殺の首謀者として身代わりに連れてこられた戴が獄死した時だ。病だったと言われているが当然殺されたのだ。戊陽が戴に刑罰を与えなかったせいで、やがて戴の口から真実が漏れる事を恐れて始末されたのだろう。
環境はあの頃からさほど変わっていない。天井の高いところに頑丈な格子が嵌め込まれた明かり取りの窓があるが、それ以外に光源の無い地下牢は日中でさえも薄暗い。こんな所に数日も居れば気が触れそうだ。
湿気った空気には独特の臭気があった。囚人たちの怨念に、死の気配、鬱屈した感情とが綯交ぜになった暗澹そのもののような活気の無さは、更生の余地がある者の心さえも暗い所へ落としてしまうような雰囲気がある。
「酷いな……」
そう呟く戊陽は、きっとどうにか出来ないかと思案しているのだろう。およそ一年前にここへ来た時にはそんな事へ気を配る余裕も無かった。あの頃と比べると随分と状況が落ち着いたのだと改めて実感する。
ここに居るのは皆囚人で、檻に入れられるだけの罪を犯した者たちだ。だが、果たして周子佑や卓浩のような者にこのような劣悪な環境が相応しいかと問われると、玲馨は答えに窮するだろう。
「ここだ──周子佑だな?」
戊陽が鉄格子の奥で丸まっている男へ向けて声を掛ける。闇の中、もぞりと蠢いた男が緩慢に顔を持ち上げると、確かに周子佑だった。しかしせいぜい十日ほど前に見た頃とはあまりにも様子が違ってしまっている。
「……はい」
戊陽と再会してから今日までよっぽど食事を取らなかったのか頬が痩け、表情には全く覇気が無い。辛うじて返事のために喉を動かしたという具合だ。
「周さん、私です。玲馨です」
少し間が空いてから「ああ」と納得するような声が漏れた。それからやはり緩慢に玲馨の前に立つ戊陽を見てから僅かに思案の表情を浮かべる。
「……まさか」
「こちらは戊陽陛下であらせられます」
憔悴しきった様子でも目の前の人物に多少の畏敬はあったようで、慌てて手を組み頭を下げた。とは言えその動きは酷く鈍かったが。
密かに支援してきた婚外子の実子諸共囚えられてしまった事は周子佑にとってよほど彼の心身を苛んだらしい。気の毒だとは思うが玲馨は自分の行動に後悔は無い。周子佑の北玄海での振る舞いは皇帝への反逆と言っても差し支えはないのだ。
「こ、この様な所へ、一体何の御用で御座いましょう」
「そう怯えるな。ただ話をしたいだけだ」
「は、はい」
「お前は『呂氏』を知っているか?」
再び間が空く。すかさず戊陽が「知っている顔だな」と詰め寄ると、周子佑は力無く「はい」と存外正直に認める。
「呂氏について知っている事を話せ」
「……呂氏は、元々は北玄海の土着の貴族でしたが商人に身分を買われ、後にその商人が名乗った姓だと記憶しております。少なからず官吏も排出しておりますが、やがて没落し今では子孫が残っていないかと」
「没落は数十年も昔だ。周子佑、何故お前は呂氏を知っている?」
「は、はい……北玄海の塩商と言えば複数の氏族が関わっておりますが、その中に呂氏の名がありました。記録が残っていて、私はそこで……」
二人の会話を聞きながら玲馨は納得する。どうりで呂氏はその身分を売り渡した訳である。
塩は利益の大きい商売だ。沈での豪商といえばそのほとんどが塩商と鉱山経営と養蚕業のどれかを営んでいる。
その中でも特に利益が安定しているのが塩商だ。表向きには国内でしか塩を売買していない事になっているが、北玄海は海を挟んだ先の国と塩を取り引きしているような気配があった。
しかしいかに豪商と言えども落ちぶれる事が全くないという事ではないようだ。元は商人だったのなら貴族身分が肌に合わなかったか、或いはやはり子孫に恵まれなかったか。
とにかくこれで呂氏が北玄海の貴族であった事は確定した。
「……ふむ。もう少し何か欲しいな」
周子佑の肩がびくりと跳ねる。北玄海で相対した時には口の上手い男だと思ったが、こうして化けの皮が剥がれてしまうと案外彼の反応は分かりやすい。
戊陽がちらと玲馨を振り返る。玲馨が話す番のようだ。
一歩格子側に進み出ると周子佑は怯えと警戒の混じった目で玲馨を見上げる。山芒の時は焦燥しやがて諦念へと変わっていったが、あれから時が経ち冷静になった今、周子佑は皇帝を前に怯えている。皇帝が怖いのではない。皇帝に北玄海の内情を話すことで、北玄海側からの報復を恐れているのだ。
彼のそんな恐怖を拭い去ってやる事は、残念ながら玲馨には不可能だ。それでも周子佑からは聞き出さなくてはならない事があった。
「刺史として紫沈に戻ってくる事もあったと思いますが、年にどれくらいでしょう?」
「……一年に一度ほどです」
思った以上に少ない。
「それでは紫沈との連絡には別の方が遣わされていたのでしょうか?」
「は……いえ……。どう、ですかね」
歯切れの悪い返事だ。何かを隠そうとしているのだろう。
いずれは尋問に掛けられる事になるのだから今吐こうが後で吐こうが同じことではないか──とはいかないのが今の宮廷の情勢だ。尋問する人間次第ではまだ周子佑は助かる道がある。彼を刺史に任命したであろう北玄海側の尋問では重要なほとんどの事が伏せられたまま終わり、罪も軽くなる。
しかし北玄海の息のかかった者が周子佑に近付くのは、同時に危険も伴うはずだ。水王が周子佑を不要と思えばあっさり切られる事だろう。その時、周子佑に待つのは死だ。
どうすれば彼に口を割らせる事が出来るのか。黙って思案していると、再び戊陽が口を開く。
「山芒から紫沈までの旅はどうだった?」
質問の意図が分からないのだろう、周子佑は困惑ぎみに顔を上げる。玲馨にも戊陽が何を知ろうとしているのか分からない。
「よもや縄を荷台に括りつけ引きずられて来たのではあるまい」
つまり護送されてきた時の状況を聞いているらしい。
「は……私は自分の足では歩いておりません。荷台に乗せられ頭から布を被せられ、気付けばこの牢屋の中で御座いました」
息子の卓浩とは荷台を分けられたのだろうか名前が出てこない。だとしたら随分と慎重に護送をしたものだ。その分人手も馬も余分に必要になる。
「そうだろうな」
会話は途切れ、やはり戊陽の真意が分からず周子佑は目を伏せ考え込み始める。
一方玲馨は戊陽の言いたい事に概ね察しがついていた。
周子佑を厳重且つ安全に護送してきたのが一体誰だったのか、それを思い出してみろと言っている。わざと遠回しな言い方をさせる事で彼に自ら考え気付かせたいらしい。そうして自らの頭で辿り着いた答えの方が納得しやすいからだ。
戊陽のやり方はどこか懐かしさを感じる。燕太傅を思い出すのだ。彼の人は答えをいきなり与えるのではなくよくこうして問答をして、戊陽や玲馨に「考える」という事をさせた。仮に答えが間違っても頭ごなしに否定したりはしない。或いは別の考え方として答えを教え、そうして己の世界が広がっていく、知識が深まっていくのがただ純粋に楽しかった。
蛍火のように淡く浮かんだ懐古は、周子佑が「まさか」と呟く声に掻き消されていった。
「我が身をお助け頂けるのですか……? い、いえ、それなら、それなら私などではなく」
「勘違いしてはならぬぞ。沈を興した初代皇帝の教旨は信賞必罰。贖罪は必ず果たすのだ。だが、『正しく』お前の罪を裁かせると約束しよう」
周子佑を護送してきた禁軍という力が、皇帝にはあるのだから──。
要は北玄海の勢力から守ると言っているのに等しい。しかしそれでも周子佑の顔が晴れないのを見て、戊陽はトドメと言わんばかりに言葉を付け足した。
「無論、卓浩の事もだ」
息子を引き合いに出せば効果覿面である事は山芒の一件から心得ていた事だ。もちろん戊陽にも事の一部始終を報告してあった。
結果、周子佑からは意外な話が聞ける事になる。
「北と中央を繋ぐ事に関してなら、卓浩の方が詳しいはずです」
何故北玄海と紫沈の事に山芒の刺史だった卓浩の名が出てくるのか。俄には分からず二人は周子佑の言葉に従い、別の独房へと向かう。
二年前、前皇帝が急逝した際に、皇位が空白の期間が存在した。その短い空白期間に官吏の人事を司る部署が中心となって配置換えが行われた。既に当時から国政は皇帝の手から離れつつあった事の証明でもある。
そうして連れてこられた宰相はそれはもう小胆な男で政にも一切詳しくない、見かけも性格もまさに小男だった。
背後に居る誰かの言葉を皇帝に伝え、皇帝の意思を同様に誰かに伝える。故に「鳩」だ。あの宰相はそれ以上の役割を果たす事を許されておらず、残念な事に本人もそれを良しとしてしまっていた。
そんな宰相に、玲馨は北玄海へ行くよう言い渡された。それが二ヶ月ほど前の事だ。断る事は出来たが、「北玄海で浮民の受け入れが行われている」という情報は戊陽も玲馨も単純に気になった。恐らくは玲馨の邪魔をしたい勢力からの妨害だろうと思いながらも、北玄海行きを決めたのだった。
調査の結果はご存じの通りである。宰相の差配は邪魔どころか寧ろ戊陽への密告と言って良いだろう。それを「邪魔」だと早合点してしまったのはこれまでの宰相の立ち回りももちろんだが、北玄海へ行く前の玲馨の行動に理由があった。
玲馨は北玄海へと赴く前に、とある事を調べていた。先帝黄昌を毒殺したその下手人の出身についてだ。
戊陽の兄は二年前、毒を飲まされ殺された。
玲馨とそして戊陽は、服毒し血を吐き横たわった黄昌の遺体をその目で見ている。二人が、最初に死んだ黄昌を見つけ、事が明るみになったのだ。その時に黄昌へ毒を盛ったと思われる男も共に死んで見付かっている。
「玲馨? どうした話を続けてくれ」
「あ……はい。ええと」
じ、と間近で戊陽に見つめられてたじろぐ。息がかかりそうなほど顔を近づけられていたのに全く気付かなった。
すぐに一人で考え込むのは玲馨の悪い癖だ。戊陽もよく知っているので狼狽える玲馨を見て小さく笑っている。それを横目に睨むと、戊陽はますます楽しそうに笑みを深めた。
ここは紅桃宮の戊陽の寝所だ。寝所に居る理由はただ一つ。密談するのに向いているから。宦官も宮女も全て完全に人払いがされている。
まさか戊陽と玲馨が寝所で皇帝暗殺について話しているなどとは誰も考えないだろう。証拠に気を利かせた宮女は湯を張った桶や手巾を用意し、玲馨には潤滑剤に使う香油の補充は必要無いかなどと聞いてきた。何と答えたものか悩んで玲馨が黙っていると、聞き耳を立てていた戊陽が「先日私が補充したので問題無い」と代わりに答えてしまった。
否定してしまうより勘違いを利用した方が都合が良い事は分かっていても、玲馨の胸中は複雑だ。ただでさえこのところ、朝議では後宮に入れる妃の事で持ち切りだと言うのに、戊陽が宦官に入れあげているという噂が立つのは外聞が良くない。
それに、実のところ香油は戊陽が後宮を出てから一度も使われた事はない。玲馨が宦官の宿舎に戻ってしまうと途端に機会がなくなった。何より当時は宦官も科挙を受けられるように奏上をすべく、案を練っている所で互いにそうした事柄へ意識が向かなかったという事もある。
だから、戊陽と玲馨は宮女たちが噂するような関係ではないのだ。
ひっそりと内心で溜め息を落とすものの、玲馨は一体何について嘆息したい気分になったのか、その自覚はない。戊陽との関係が噂される事にか、それともその噂に真実が伴わない事に、か。
「少し情報をさらいます。まず先帝を弑した下手人の名は呂憲。禁軍の兵士で、呂家へ養子に入って紫沈所縁の貴族身分を獲得しています。元の名や出身は不明」
うん、と戊陽は首を小さく振る。続けろという意味だ。
「下手人の元の名や身分については徹底的に身元を隠されているようで緒が見付からず……。なので呂家の方を調査する事にしました」
「そうしたら呂家、つまり呂氏は既に没落し、身分を放棄した貴族だった事が分かった」
「そうです」
呂という姓の貴族はおよそ六十年も昔に貴族ではなくなっていた。跡継ぎに恵まれなかったのか、資金繰りに困窮し屋敷や家財など売り払って矜持を保てず身分を手放したのか、詳しい理由は分からない。とにかく呂氏という貴族は既に沈には居ないという事だ。
それが何故か養子を迎えてあろうことかその養子は皇帝直轄の護衛軍である禁軍の兵士になっていた。
黄昌が呂憲の事を知っていたかどうかは今となっては分からない。呂という家の怪しさから呂憲は宮廷へ送り込まれた刺客だった事は確実だろう。
それから呂氏に関して更に詳しく調べていくと、呂氏は元々商家だった事が判明する。元は呂という姓ではなかったのだ。
最後は身分を放棄してしまう事になるが当時は豪商として名を馳せており、呂氏から身分を買って呂という貴族になった元商人の家系だった。
では呂氏とは一体どこの貴族なのか。
沈の貴族にはいくつか種類があるが大きく分けて三つ。
一つ目は臣籍降下──または降嫁──や、賜姓降下によって皇族の親戚となった貴族。
二つ目は四方の領地を治める王の親類縁者。
三つ目は勲功を称えて皇帝によって新たに貴族として認められた氏族。
このうちのどれに属するかで、概ね勢力が分かれる。
しかし呂氏が身分を放棄したのが既に六十年前と古く、身分が売買された時期も不鮮明で、呂氏の過去を辿る線は難航していた。
……と、ここまでが北玄海へと発つ前に玲馨が調べていた事で、呂氏調査に行き詰まったところで件の宰相から北玄海行きの話が出たのである。
そのせいで呂氏について調べられては困る者から横槍が入ったのだとばかり思っていたが、呂氏の調査については北玄海で思わぬ進展を見せる事になる。
「呂氏は北玄海の貴族の可能性が高いようです。浮民受け入れによる人口増加の記録の中に呂姓を名乗らされている元浮民が五十名ほど居ました。恐らく土着の姓を宛てがう事で新住民を誤魔化したつもりだったのでしょう」
「では呂氏とは水王の縁者だったと?」
玲馨は首肯する。
「確証はありませんが」
沈の貴族の興りはとても古く紫沈で全ての貴族を管理するようになったのは七十年ほど前の事だ。呂氏の身分放棄は紫沈で管理されるようになって間もない頃の記録に残っていたが、呂氏の出自についての記録は無かった。
では古くは貴族の戸籍はどう管理していたかというと、出身地によって個別に管理していた。
紫沈では皇家縁戚の貴族と勲功貴族を管理し、四王縁戚の貴族は四方の地で管理していたという事だ。
呂氏の名が紫沈に記録として残っていない以上、四方貴族である事はほぼ確実。更に平民にも姓が与えられるようになってからは、その土地を四王から命じられて管理していた貴族の姓を名乗る事がほとんどだ。
浮民たちに付けられた「呂」という姓が誰かの思い付きでなければ、呂氏は古くは北玄海で暮らしていたと考えてまず間違いないだろう。
「それと、首謀者として獄死した文官ですが、同じく北の出身です。こちらは生家もはっきりしており、戴氏という貴族です。戴の人間に話を聞く事は出来ませんでしたが、噂が流れており何でも近頃戴家の者が数名罷免されたとか」
「兄上諸共、戴の者は謀られたか」
戊陽は低く呟いて、苦しいものを外に出すようにゆっくりと息を吐き出した。
「なまじ一月も紫沈を離れていなかったな、玲馨」
「ええ、本来の目的が完遂出来ないならと思って粘った甲斐が……」
嘆息と共に集中力も吐き出してしまったのか、戊陽の手が膝の上に置かれていた玲馨の手に重なる。一つしか無い机に椅子を二つ近くに並べていたせいで、肩を抱くにも腰を抱くにも絶妙な距離感に互いの体がある。
「陛下」
宮女に余計な気を遣わせてしまったせいで、そういう空気にならないよう敢えて二人きりでも態度を崩さなかったのに、そんな予防線は戊陽には通用しない。
何をするつもりなのかと身構えていると、戊陽はくったりと玲馨の肩に凭れかかった。
「罠の可能性も疑っていた」
戊陽の言葉にハッと息を呑む。ずっと意識しないようにしていた事だった。仮に罠だとしても動けるうちに動いておくべきだと思ったのだ。結果、事は思いの外玲馨たちにとって良い方向へ動いた。
「……心配をお掛けしました」
「本当にな。だから私を慰めてくれ玲馨」
「はい、はい?」
「お前の方から口吸いをしてほしい」
「は……」
今度こそ逃げられないように腰に手が回されて、戊陽は玲馨の方に首を傾けて目を閉じた。
腰を抱かれると、視界に映るのは、漏窓から斑に注ぐ日の光に照らされた戊陽だけでいっぱいになる。この時刻、日光は彼だけを明るく照らしていた。
玲馨と違って日に照らされると戊陽の髪はほんの少し赤く見えた。長い睫毛の下には金の虹彩が輝く瞳があるが今は瞼の下だ。鼻筋は高く通っていて唇は薄い端正な顔立ちをしており、改めて顔を見つめて男らしく育ったなと感慨に耽る。
このまま胸を押しやって突っぱねても拗ねはするが怒りはしないだろう。
なかなか玲馨が動こうとしないのでそのうち戊陽の眉根がむっと顰められる。思わずふ、と息を漏らして笑い、待ち侘びているその頬に唇を落とした。
「……………口吸いではない」
「私は口を吸いました」
「俺は吸ってない……」
「陛下、今日は久しぶりに李将軍と手合わせをするのでしょう? でしたら早く今回のことをまとめてしまわないといけません」
「……そうだな。分かってはいるんだ、分かっては」
ぶつぶつと文句を言いながらも改めて玲馨が調べ上げた調書に目を通し始める。
こんな風にまたふざけ合えるようになって良かったと思う。先帝が亡くなってからの戊陽は気が塞ぎ、それでも皇帝として即位すれば日々多忙に身をやつし、やがて酷い頭痛を起こすようになっていった。
今では頭痛の頻度は月に片手で数える程度にまで落ち着いている。痛みも随分軽くなったようで薬を飲むほどでも無い事がほとんどだ。
「それにしても戴氏の罷免は最近の事だと言ったな? 戴が先帝暗殺の首謀者として突き出されてから一年以上が経つが、遅すぎないか?」
「戴氏は北玄海の王である菫氏と並ぶ古い氏族だそうです。罷免されたと言っても刑死した者と兄弟関係だった者のみで、他には水王の菫武修であっても手が及ばなかったのでしょう」
「北は一枚岩ではないという事だな。そして尚書令は菫氏に協力していると」
いつ頃からそうなったのか分からないが、菫氏と並んで戴氏が力を持つ事は北玄海で暮らす者にとっては常識のようだった。しかしそれは明るみなれば常に周囲を蹴落とさんと鵜の目鷹の目の三方に付け入る隙を与える事になる。事実、今回の事で菫氏と尚書令が協力し戴氏は勢力を削がれる事となった。
その結果が果たして山芒と北玄海の協力関係に繋がるのかどうかまでは分からないが、戴氏の弱体は菫氏を身軽にしたに違いない。
「お前が紫沈を離れている間にな、俺は俺で調べていたんだが……」
「陛下が自ら? 何て危険な事を」
「いい加減にあの尚書令の対処をしなくては、沈の政は難渋を極めていくばかりだろ」
「そうは言っても」
「ふ、俺の心配する気持ちが多少は理解出来たか?」
「……私とあなたでは立場が違──」
思わず出た言葉だったが戊陽にじっとりと睨まれたので言葉を引っ込め小さく謝罪する。
「そも、凱寧帝の時代には強大だった皇帝の力が七十年の後にここまで衰退したのは何故だと思う?」
玲馨は教練房で教わった沈の歴史を思い出す。
「あわいによる地方との分断、後宮の縮小、官吏の減少……紫沈から『人』が減ったから、ですよね」
皇帝の権勢が衰えた原因は複合的なものでこれと明確に一つのものを挙げられない。
玲馨が指折り数えるのに合わせてうん、うん、と頷いていた戊陽は「だが」と顔を上げる。
「今と昔を比較した時、官吏は七十年前と遜色ないほど数を戻しているぞ」
「そう、なのですか?」
「見たからな、登用名簿を過去百年分ほど遡って」
一体彼のどこにそんな時間があったのか疑問に思ったが、常日頃玲馨が相手をしている時間を一ヶ月分調査の時間に割り当てたのだと気付いて突っ込むのをやめた。
「転機は凱寧帝が崩御した二十一年前、俺の生まれた年だ。そこを境に中央での官吏登用数がぐんと増えている」
凱寧は自身が皇帝の座に即いてから没するまでの数十年間、沈を掌握していた独裁者──暴君として今に伝わっている。その独裁が崩れた途端に旗色が変わったというのは概ね納得がいく。
「だが、それまで凱寧帝は徹底して自分に都合の良くなるよう周囲を固めていたはずだ。四王勢力を軒並み敬遠し、地方と紫沈を切り離して凱寧帝だけのための京師を築き上げた。だというのに死んだ途端に多くの四王所縁の貴族が宮廷に入ってくるのはおかしいと思わないか?」
戊陽はつまり誰がそれだけの官吏を登用したのか問うている。
普通に考えたら凱寧の次の皇帝か、当時の吏部の長官が主導する事になる。だが凱寧の実子である当時の皇帝はもちろん、吏部についても凱寧が抱き込んでいたはずだ。
玲馨は戊陽が即位する前の、皇帝が空位だった時期の事を思い出す。あの時、皇帝の指示なく勝手な官吏の配置換えが行われた。その中心となったのは吏部を含む実務機関を下に置く尚書省──現在の尚書令だ。
二十年前と言えば当時からの官吏も現在に多く残っており、凱寧崩御の頃と戊陽即位後の宮廷内勢力は実のところさほど大きくは変わっていないという事なのかも知れない。
「気付いたか? 老獪たちの一部は二十年前には既に凱寧帝の目を盗んで宮廷に入り込んでいたんだ。年齢から考えると最も長い者で五十年ほど前には四王勢力が皇帝から権力を奪おうと紫沈で画策していた事になる」
貴族身分であれば科挙を受ける必要がない都合上、二十歳になれば官吏として宮廷に入る権利を得る事になる。ただし当然誰かがその者の身分を保証しなくてはならない。現在の官吏たちのうち概ね四十路以上の者たちの中にはその「誰か」を見繕ってさも中央の貴族然として官吏となった訳だ。
その「誰か」を手っ取り早く見つける方法が一つだけある。
「……養子、ですか」
戊陽がゆっくりと深く頷く。
「先祖を悪し様には言いたくないが、こればっかりは凱寧帝に感謝だな。紫沈で全ての貴族を管理させたおかげで、当時戸籍まで偽るのはなかなかに難しかったらしい」
そう言って戊陽は一度椅子から立ち上がると、櫃から巻子を持って戻ってくる。とある貴族の戸籍の写しのようだ。
まだ真新しい紙の匂いのするそれを広げると、そこにはいくつかの人名が記されてあった。とある人物の前後三世代分の男子の名があり、それは二家に跨っている。この人物は養子縁組によって東江から紫沈の貴族になった事が明記されていた。
「これは、尚書令の……!」
尚書令は現在の宮廷において最も権威のある官吏の事だ。その名を林隆宸という。
戊陽と玲馨は、黄昌暗殺の真の首謀者は、林隆宸だと考えていた。
写しを見る限り、隆宸が林氏に養子に入る前の姓は楊といって東江の貴族である事が分かる。
「この楊というのは?」
戊陽は緩く首を左右に振る。
「東江の貴族という事しか分からなかった。だが、林氏というのは元を辿るとやはり東江の貴族らしい。それが長い間紫沈に暮らしたためいつ頃からか紫沈の貴族を自称するようになったのだろうな。この辺りはややこしくて面倒だ」
玲馨はこれまでに分かった事を頭の中で整理していく。
仮に林隆宸が黄昌暗殺の首謀者だとすると、正体不明の下手人を北玄海の貴族である呂氏に養子に迎えさせて呂憲と名乗らせた、という事になる。更に林隆宸が東江の出身ならば、北玄海は山芒のみならず東江とも協力関係を築いている事になるだろう。
玲馨は少し前まで四方が二つに分かれて相争う可能性を考えていた。しかし三方が協力しているとなると国を二つに分ける争いは起こらないと考えても良いのだろうか。
──いや……そんなに単純な話か? これは。
今回の山芒遠征を経て木王向青倫と皇帝が密に接したという事が外向きにも伝わってしまっている。一見すると三方が手を組む輪に皇帝勢力が加わったようにも見えるかも知れない──が、北玄海と東江には働きかけていない以上、見方を変えれば四方が互いに監視し合う輪から山芒だけが一つ抜けたという風にも見える。
これが四方の関係にどう影響するかは分からない。玲馨の頭で思い付く事はやはり、一刻も早く後宮に妃を入れようと山芒以外の勢力が躍起になるだろうという事くらいだ。
兎にも角にも万一の事態に備えるべく内憂は早々に解決したいところだが、数十年に渡って宮廷で勢力を育ててきた林尚書令が相手ではどうしても取っ掛かりが見つけられない。まさに八方塞がりだ。
「……陛下、周刺史いえ、周元刺史と話をする事は出来ますか?」
「周子佑か。数日中に紫沈まで護送されるはずだ。俺が刑部に話を通しておこう」
「よろしくお願いします。今なら、以前よりも有益な事をお話しして下さるかも知れません」
周子佑なら玲馨には探れなかった北玄海の深い事情まで知っているはずだ。問題は話させるために玲馨から提示出来るものが今のところ思いつかない事。北玄海について情報を渡せば刑を軽くしてやるとでも言えれば良かったが、如何せん玲馨はおろか戊陽にもその権限はない。
「北と東の刺史の二人は、一体どんな刑罰になるのでしょう?」
「んー……。禁固刑数年だろうな、普通なら。そも刺史とは令外官だ。刑を執行するにしても俺の頭を簡単に越える事は出来ない……──いや、そうか!」
林尚書令の記録の写しをくるくると巻いていた戊陽はその手を止めて何かを確信したような顔つきで玲馨の方へと顔を向ける。
「俺も行こう。お前の悩みを一つ解消してやれるぞ」
周子佑と同じく元刺史である卓浩の二人はおよそ七日の後に無事紫沈へと護送されてきた。偶然とはいえ禁軍が居合わせたおかげで、「不慮の事故」などに遭って死んでしまうという事はなかった。
戊陽は約束通り刑部に話を通し、玲馨を伴う形で二人は牢へと足を運ぶ。紫沈の地下にある牢屋へ訪れるのはこれが二度目だ。
初めてここへ来たのは一年前、黄昌暗殺の首謀者として身代わりに連れてこられた戴が獄死した時だ。病だったと言われているが当然殺されたのだ。戊陽が戴に刑罰を与えなかったせいで、やがて戴の口から真実が漏れる事を恐れて始末されたのだろう。
環境はあの頃からさほど変わっていない。天井の高いところに頑丈な格子が嵌め込まれた明かり取りの窓があるが、それ以外に光源の無い地下牢は日中でさえも薄暗い。こんな所に数日も居れば気が触れそうだ。
湿気った空気には独特の臭気があった。囚人たちの怨念に、死の気配、鬱屈した感情とが綯交ぜになった暗澹そのもののような活気の無さは、更生の余地がある者の心さえも暗い所へ落としてしまうような雰囲気がある。
「酷いな……」
そう呟く戊陽は、きっとどうにか出来ないかと思案しているのだろう。およそ一年前にここへ来た時にはそんな事へ気を配る余裕も無かった。あの頃と比べると随分と状況が落ち着いたのだと改めて実感する。
ここに居るのは皆囚人で、檻に入れられるだけの罪を犯した者たちだ。だが、果たして周子佑や卓浩のような者にこのような劣悪な環境が相応しいかと問われると、玲馨は答えに窮するだろう。
「ここだ──周子佑だな?」
戊陽が鉄格子の奥で丸まっている男へ向けて声を掛ける。闇の中、もぞりと蠢いた男が緩慢に顔を持ち上げると、確かに周子佑だった。しかしせいぜい十日ほど前に見た頃とはあまりにも様子が違ってしまっている。
「……はい」
戊陽と再会してから今日までよっぽど食事を取らなかったのか頬が痩け、表情には全く覇気が無い。辛うじて返事のために喉を動かしたという具合だ。
「周さん、私です。玲馨です」
少し間が空いてから「ああ」と納得するような声が漏れた。それからやはり緩慢に玲馨の前に立つ戊陽を見てから僅かに思案の表情を浮かべる。
「……まさか」
「こちらは戊陽陛下であらせられます」
憔悴しきった様子でも目の前の人物に多少の畏敬はあったようで、慌てて手を組み頭を下げた。とは言えその動きは酷く鈍かったが。
密かに支援してきた婚外子の実子諸共囚えられてしまった事は周子佑にとってよほど彼の心身を苛んだらしい。気の毒だとは思うが玲馨は自分の行動に後悔は無い。周子佑の北玄海での振る舞いは皇帝への反逆と言っても差し支えはないのだ。
「こ、この様な所へ、一体何の御用で御座いましょう」
「そう怯えるな。ただ話をしたいだけだ」
「は、はい」
「お前は『呂氏』を知っているか?」
再び間が空く。すかさず戊陽が「知っている顔だな」と詰め寄ると、周子佑は力無く「はい」と存外正直に認める。
「呂氏について知っている事を話せ」
「……呂氏は、元々は北玄海の土着の貴族でしたが商人に身分を買われ、後にその商人が名乗った姓だと記憶しております。少なからず官吏も排出しておりますが、やがて没落し今では子孫が残っていないかと」
「没落は数十年も昔だ。周子佑、何故お前は呂氏を知っている?」
「は、はい……北玄海の塩商と言えば複数の氏族が関わっておりますが、その中に呂氏の名がありました。記録が残っていて、私はそこで……」
二人の会話を聞きながら玲馨は納得する。どうりで呂氏はその身分を売り渡した訳である。
塩は利益の大きい商売だ。沈での豪商といえばそのほとんどが塩商と鉱山経営と養蚕業のどれかを営んでいる。
その中でも特に利益が安定しているのが塩商だ。表向きには国内でしか塩を売買していない事になっているが、北玄海は海を挟んだ先の国と塩を取り引きしているような気配があった。
しかしいかに豪商と言えども落ちぶれる事が全くないという事ではないようだ。元は商人だったのなら貴族身分が肌に合わなかったか、或いはやはり子孫に恵まれなかったか。
とにかくこれで呂氏が北玄海の貴族であった事は確定した。
「……ふむ。もう少し何か欲しいな」
周子佑の肩がびくりと跳ねる。北玄海で相対した時には口の上手い男だと思ったが、こうして化けの皮が剥がれてしまうと案外彼の反応は分かりやすい。
戊陽がちらと玲馨を振り返る。玲馨が話す番のようだ。
一歩格子側に進み出ると周子佑は怯えと警戒の混じった目で玲馨を見上げる。山芒の時は焦燥しやがて諦念へと変わっていったが、あれから時が経ち冷静になった今、周子佑は皇帝を前に怯えている。皇帝が怖いのではない。皇帝に北玄海の内情を話すことで、北玄海側からの報復を恐れているのだ。
彼のそんな恐怖を拭い去ってやる事は、残念ながら玲馨には不可能だ。それでも周子佑からは聞き出さなくてはならない事があった。
「刺史として紫沈に戻ってくる事もあったと思いますが、年にどれくらいでしょう?」
「……一年に一度ほどです」
思った以上に少ない。
「それでは紫沈との連絡には別の方が遣わされていたのでしょうか?」
「は……いえ……。どう、ですかね」
歯切れの悪い返事だ。何かを隠そうとしているのだろう。
いずれは尋問に掛けられる事になるのだから今吐こうが後で吐こうが同じことではないか──とはいかないのが今の宮廷の情勢だ。尋問する人間次第ではまだ周子佑は助かる道がある。彼を刺史に任命したであろう北玄海側の尋問では重要なほとんどの事が伏せられたまま終わり、罪も軽くなる。
しかし北玄海の息のかかった者が周子佑に近付くのは、同時に危険も伴うはずだ。水王が周子佑を不要と思えばあっさり切られる事だろう。その時、周子佑に待つのは死だ。
どうすれば彼に口を割らせる事が出来るのか。黙って思案していると、再び戊陽が口を開く。
「山芒から紫沈までの旅はどうだった?」
質問の意図が分からないのだろう、周子佑は困惑ぎみに顔を上げる。玲馨にも戊陽が何を知ろうとしているのか分からない。
「よもや縄を荷台に括りつけ引きずられて来たのではあるまい」
つまり護送されてきた時の状況を聞いているらしい。
「は……私は自分の足では歩いておりません。荷台に乗せられ頭から布を被せられ、気付けばこの牢屋の中で御座いました」
息子の卓浩とは荷台を分けられたのだろうか名前が出てこない。だとしたら随分と慎重に護送をしたものだ。その分人手も馬も余分に必要になる。
「そうだろうな」
会話は途切れ、やはり戊陽の真意が分からず周子佑は目を伏せ考え込み始める。
一方玲馨は戊陽の言いたい事に概ね察しがついていた。
周子佑を厳重且つ安全に護送してきたのが一体誰だったのか、それを思い出してみろと言っている。わざと遠回しな言い方をさせる事で彼に自ら考え気付かせたいらしい。そうして自らの頭で辿り着いた答えの方が納得しやすいからだ。
戊陽のやり方はどこか懐かしさを感じる。燕太傅を思い出すのだ。彼の人は答えをいきなり与えるのではなくよくこうして問答をして、戊陽や玲馨に「考える」という事をさせた。仮に答えが間違っても頭ごなしに否定したりはしない。或いは別の考え方として答えを教え、そうして己の世界が広がっていく、知識が深まっていくのがただ純粋に楽しかった。
蛍火のように淡く浮かんだ懐古は、周子佑が「まさか」と呟く声に掻き消されていった。
「我が身をお助け頂けるのですか……? い、いえ、それなら、それなら私などではなく」
「勘違いしてはならぬぞ。沈を興した初代皇帝の教旨は信賞必罰。贖罪は必ず果たすのだ。だが、『正しく』お前の罪を裁かせると約束しよう」
周子佑を護送してきた禁軍という力が、皇帝にはあるのだから──。
要は北玄海の勢力から守ると言っているのに等しい。しかしそれでも周子佑の顔が晴れないのを見て、戊陽はトドメと言わんばかりに言葉を付け足した。
「無論、卓浩の事もだ」
息子を引き合いに出せば効果覿面である事は山芒の一件から心得ていた事だ。もちろん戊陽にも事の一部始終を報告してあった。
結果、周子佑からは意外な話が聞ける事になる。
「北と中央を繋ぐ事に関してなら、卓浩の方が詳しいはずです」
何故北玄海と紫沈の事に山芒の刺史だった卓浩の名が出てくるのか。俄には分からず二人は周子佑の言葉に従い、別の独房へと向かう。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
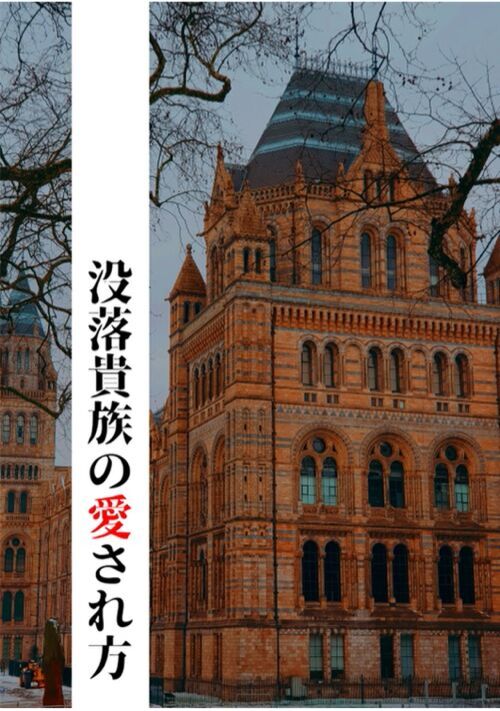
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















