17 / 44
宮廷編
17時を待つ
しおりを挟む
酒は量を守って飲む分には気分をほどよく開放的にさせてくれる良い物だと玲馨は思う。口にする機会はもちろん少ないが、特別弱くも強くもないので気持ちよく酔って後に残らない飲み方が出来る。
しかし。
「いやぁー、こんな所にへい、っといけない。洋様がいらっしゃるだなんて。早く仰ってくれたら私が良い妓女を紹介しましたものを」
ぐわん、と大きく体が後ろに傾いだかと思うと腹筋の力で元に戻ってきた桂昭はへらりとだらしなく笑って空になった杯を持ち上げる。しかし先ほど戊陽が全ての妓女を下がらせてしまった事を遅れて思い出し、手酌して一口呷って満足気に息を吐いた。中身を水にすり替えてもらっているのだが、桂昭は全く気付いていない。
先程まで酒に酔って娘に絡もうとする桂昭を梅に止めさせていたので図らずも卓浩の云っていたように衣も髪も乱れてだらしない無精髭のお役人姿が出来上がっている。朝議で見かけた時には髭はなかったような気がするので、体毛が濃い体質なのだろう。
ただでさえ酩酊していたのに飲ませ続けているのは水なので危険はないというのはもちろん、酒入れば舌出づと言うのでこの際彼には好きにお喋りをしてもらおうという魂胆だ。
「籠に飼われた鳥でもあるまいに、自分の好きなものは自分で見つける」
「はっはっは! いやーさすがさすが、ご立派でいらっしゃる! 遠くからお声を聞いているだけでは分からない事があるものですなぁ」
相手は酔っ払いと分かっていても戊陽を軽んじるような発言に玲馨の表情が微かに歪む。言われた本人は言葉の内容よりも呂律も怪しいへべれけぶりに呆れている様子だ。
少し酔いが覚めるのを待つべきかと思っていたが、突然、割れてしまうのではないという勢いで杯を置くやいなや桂昭は据わった目で戊陽をゆらゆらと見据えた。
「ところで、へい、いや洋様は、うちの娘に何か御用で?」
娘とは先の妓女、桂茜の事だ。歳は十八、念願の一人娘として生まれて、芸事から文字に算術まで様々な事を学ばせ大事に育てたと好きに喋ってくれた。目に入れても痛くないほど猫可愛がりしており、どうやらこの部屋に乱入してきたのは娘の貞操守るためであったようだ。
だったらどうして妓楼などという男を相手に仕事をするような所で働かせているのか。興味はあるが本題とは関係ない。
「桂昭。お前は『柳』が好きなのだそうだな」
「んん……?」
何のことだかピンと来ていないようで、いかにも文官らしい細く肉刺の無い手で顎を擦る。
「柳……ええまあ嫌いって事はありませんがね……」
当てが外れたという落胆が押し寄せる。数奇な事に目的の男と早くも接触が叶ったが、現実は上手くいかないものだと。
落胆が諦めに変わろうとした時、桂昭の眉が跳ねた。本人にその自覚があったかは分からない。だがその一瞬の仕草が思い出したような閃いたような表情を作ってはすぐに消えていった。
──今のは何だ?
「ああ~ははっ、柳はね、洋様。隠語というか、暗号というか、宮廷内のほら、そうそう『合言葉』なんですよ」
「合言葉?」
「ええそう合言葉。己の派閥を明かすための符号ですよ」
明かすため、という言い方が気になった。
柳の事を否定しないとなると、卓浩の言った「桂」は桂昭の事で間違いなかったようだ。よくよく見れば着ている衣はさほど上等な物ではない。市井に紛れるためなのか、それとも官吏然として見られる事を嫌うのか、いずれにせよ仮にこの格好で向青倫の前に現れたのだとしたらだらしなく思われた事だろう。
「秘密の話をするにも相手の派閥は大事でしょう? 後宮だってそういう事があったと思いますがねぇ。──ああでも、前皇后様は貴妃様でありながら御子も立太子なさったのでした。いやいや陛下……じゃなかった、洋様の時代は後宮史でも稀に見る穏しき時代だったのかも知れませんなぁ」
ぺらぺらとよく回る舌はおべっかを並べる周子佑にも負けていない。違いは話の内容がおべっかでは無い点だ。寧ろ侮られている。平和ボケした皇帝陛下、と。しかしこの程度で気を悪くする戊陽ではなく、眉一つ動かさずに桂昭の言葉に答えた。
「平和は良いな。民が精力的になり文化は発展し、反乱はなく、政は安定する。そのために皇帝というものは存在するのだ」
想像とは違う答えだったのか、桂昭の表情からニヤついた笑みが消える。消えた後の顔は思いの外真面目な表情で、酒の気配を残しながらも理性的に見えた。
更に戊陽は続ける。
「宮廷内の合言葉と言ったな? だとしたら私はその言葉を知る由もなかったはずだ。何しろ柳の話を聞いたのは城の外だった」
言外に山芒で聞いたと明かしたようなものだ。桂昭が卓浩に自らその話題を振った事を覚えていて、尚且つ彼が北玄海側の人間なら卓浩の命が脅かされる事になる。
さて、どう出てくるか。
甘いような辛いよう麝香の香りが充満した妓楼の一室が、そうとは思えないほど張り詰めた緊迫感に包まれる。
パシンッ──と突然乾いた音がしたのは、桂昭が自身の膝を力強く叩いた音だった。胡座をかいた両膝に両手を乗せて桂昭は話す。
「柳はね、春を告げる花を咲かせるんです。吉祥木なんても言いますなぁ。城の水路でも枝垂れて風情のある景観を作るのに一役買ってる。けど、柳も増え過ぎたら堀の視界は悪く、秋には大量に葉を散らして塵のように水面を埋めて腐って臭う。何だって過ぎれば毒だと思いませんか? ねぇ洋様」
外連味を効かせた言い回しは回りくどくて面倒臭いついでに胡散臭い。「柳」とは何かを直接言わずに仄めかしているのはよく分かるが、身振り手振りを交えて話すおかげで気が散った。結局何が言いたいんだと詰め寄りたくなる。
しかし戊陽は冷静だった。
「増えすぎた柳を、お前ならどうする?」
戊陽に訊ねられた桂昭の目がぎらりと光る。
「──間引く」
「方法は?」
間髪入れずに訊き返されて瞠目したのは一瞬だった。
「奴らは自分で作った毒を抱え込んでるもんです。それを暴いて飲ませてやれば、勝手に減ってゆくでしょう」
そうか、と一言頷いて、戊陽は梅の名を呼んだ。すると梅は徐に立ち上がって背後にあった扉を開ける。
「わぁっ、あ、ああっ──」
突然扉を開けられた事で体勢を崩した桂茜が正面から倒れ込み転ぶ──と思うより早くに梅が彼女の肩を支えて事なきを得る。扉の向こうには娘の桂茜が張り付いていた。
「あの、あの、ごめんなさい私」
「酒を」
「は、はい……?」
「この男に酒を持ってきてくれ。私たちはそろそろ帰るから、その代わりに」
「は、はい!」
戊陽に笑いかけられてぽっと頬を染めながら桂茜は慌ただしく部屋を出ていった。「男なら誰でも良いのかよ」と一人相手にされず不満げに呟く梅の声は聞こえなかった事にした。
帰り際、持参していた玉を店の者に握らせれば、妓女を追い出したばかりかろくに酒も飲んでいかなかった戊陽たちだが責められるという事はなかった。寧ろ笑顔を固まらせてひどく畏まった様子で見送られてしまった。
「少々やり過ぎだったのでは?」
皇帝だと思われはしないだろうが、それでも怪しまれる種を与えてしまったような気がする。
「大丈夫だろう。若い貴族は見栄を張りたがるものだしな」
そうならいいが、桂昭と鉢合わせた以上はあの男が戊陽の正体をうっかり漏らさないとも限らない。
桂昭と言えばおかしな男だった。酔いのせいで気が大きくなっていたのだろうが、それにしては弁が立つ。呂律の怪しいところを無視すれば途中から彼は半分以上正気だった。
きっかけは、何だ。彼がまともに話そうとしたきっかけは。
『平和は良いな。民が精力的になり文化は発展し──』
平和ボケと馬鹿にされて怒るどころか逆手に取った戊陽の言葉、或いは態度を見て、桂昭は「柳」について「合言葉」以上の何かを仄めかした。
きっと合言葉だというのも嘘ではないだろう。柳が妓楼の隠語だと分かっていれば言い訳はどうとでも出来る。女にだらしないような印象を与えるかも知れない難点さえ除けば。
「柳は、結局何を示していたのでしょう……」
考えるあまりつい言葉にしてしまっていた。沈黙が返ってきた事ではっとして、周囲に視線を巡らせる。前を歩く梅が持つ灯りに照らされる範囲に人影はない。
「人だろうな、特定の」
「特定の?」
まさか気付かなかったのか? そう問われているような視線が隣から向けられる。玲馨は考える。
桂昭は言っていた。何事も過ぎれば毒となると。柳が増えすぎて害が出る事に喩えてそう言った。
ならば一人ではなく集団だと考えるところだが、戊陽の見解は違っていた。
「柳は貴族の姓だろう?」
姓と言われて漸く玲馨にも閃くものがあった。
「楊の事ですね」
「そうだ。楊は東江の姓だ。つまり──」
戊陽はその先を言わなかった。ここが外である事を懸念してだ。梅に話を聞かせ過ぎるのもあまり良くない。彼の身の安全を気にしてやる必要は無いと玲馨は思うが。
だからそこからは玲馨も黙って考えた。
戊陽は柳とは楊氏を指すと考えている。そして楊とは尚書令の林隆宸の旧姓だと既に判明していた。
養子だらけの宮廷で合言葉を使って互いの裏の顔を探り合うというのは確かに便利だろう。しかし、誰がどの四王の勢力に属しているかは注意深く監察していれば自ずと見えてくるもの。合言葉を使うというのは些か大袈裟なような気がする。
では具体的に何を確かめるための合言葉だったかを考えた時、桂昭の言った「己の派閥を明かすため」という言葉を思い出した。
派閥ではなく所属や組織のようなものだとしたら──。
林隆宸は自身の手駒となるような者を自身の名のもとに組織しているのではないか。
戊陽が、つまり「皇帝」が柳という合言葉を用いて桂昭に話題を振った時、桂昭は咄嗟に何の事か分からないととぼけてみせた。今にして思えばそれはおかしな反応だ。
柳が単に派閥の問いかけなのだとしたら、皇帝が合言葉を使っても不思議ではない。表向きは対立しているように見せかけて、その実柳の派閥を味方につけようとしている、と考えられなくもない。
だが桂昭はそうは考えなかった。何故なら皇帝が柳に属しているのはおかしいと知っているから。
柳が林隆宸を指すのだとしたら、皇帝に反目し続けてきた林隆宸のその組織する集団に皇帝が下るなんてことは有り得ないのだ。
そう考えると「明かす」という言い回しにもしっくりくる。林隆宸の組織に属する者が互いの所属を明かすのに合言葉を使うという事だ。
ほとんどが想像の域を出ないが、恐らくそう間違ってはいないだろう。増えすぎた柳を間引くという表現にもピンと来るものがある。
林隆宸は現在宮廷内で事実上最高権力を持っていると言って過言ではない。彼の権勢は皇帝を遥かに凌ぐ。それは他方からすれば邪魔者で、同胞からすれば目の上の瘤だ。そして皇帝──戊陽にとってもまた、宮廷から去ってほしい人である。林隆宸の強引で急進的なやり方は常に犠牲の上に成り立つと戊陽はそして玲馨もよく知っている。獄死した、いやさせられた戴氏の件が一つの例だ。
戊陽の「平和」に対する考え方から桂昭が何を読み取ったのかまでは分からない。彼を味方につけられると安易に考えない方が賢明だろう。桂昭が思惑の一端を明かした理由は、林隆宸を排斥するためにいっときの共闘関係を築きたいという遠回しな提案で、その後も戊陽の味方で居続ける保証はどこにもない。
しかしそれは裏を返せば、戊陽に皇帝としての力を得てほしくない玲馨にとっては好都合だった。
林隆宸。あの男を生かしたままでは、いずれ奴の毒牙は戊陽にも及ぶだろう。宮廷の悪い腫瘤を切り離すには、今この時を逃す手は無いように思われた。
「梅、灯りはお前が持っていっていいぞ。宿舎側は灯りが少ないからな」
戊陽の声に思索から返ってきた玲馨は人知れずぎょっとする。いつの間にか城まで戻ってきており、既に後宮まで続く門の前に来ていた。よっぽど考え事に夢中だったらしい。
ここから先は警備のための篝火が焚かれているので戊陽の言う通り下級宦官の宿舎へ向かうのに比べると足元はずっと明るい。
「いやさすがに陛下から手燭を奪ってくわけにはいきませんて」
「問題ない。それは貸し出すのだからな」
「陛下の事なら私が黄麟宮まできちんとお送りする。帰っていいぞ梅」
「あーはいはい! ったく二人して俺を邪魔者扱いしやがって! 馬に蹴られるのは御免なんで言われた通りにしますよ!」
後宮と下級宦官の宿舎は離れており、夜も深い時間に往復するとなるとろくに眠る事無く朝を迎えるだろう。
これは戊陽の気遣いだ。それに梅も気付いている。だから空気が固くならないように冗談を飛ばして踵を返す。
梅の事は嫌いだが、悪い奴ではない事はもう理解していた。それに察しの良さもある。
「玲馨も帰っていいぞ」
梅の姿が角の先に消えると戊陽がさも当然のように言ってくるので玲馨は声を固くする。
「ご冗談を」
「だったら俺の部屋で休むか?」
すかさず同じ言葉で切り返そうとしたが思いの外真剣な眼差しとぶつかって声は喉元で霧散した。
別に、断る理由は無い。望まれるなら、望まれるままに皇帝の寝所に入るのは、実のところ玲馨とて吝かではない。だけど。
視線を逸らしたのは戊陽からだった。それから抑えた声で「俺が自分で決めた事だしな」と呟いたのだが、玲馨にはほとんど聞き取れなかった。
「必ず俺のところに戻ってくるんだろう」
何があろうとも──。
彼の台詞には言葉にならない続きが聞こえるようだった。
「はい」
翌日の朝議ではうっかりすると襲ってくる睡魔に抗うために敢えて考え事に没頭していた。
気になる事は山の如しであるが、目下の懸念は桂昭との連絡手段だ。柳云々が合言葉だというのなら、それはつまり柳の意味を知る者同士で監視し合う事にもなるだろう。そうでなくとも宮廷での一挙手一投足は誰に見られているか分かったものではない。怪しまれず個人的に「皇帝」と接触する事の難しさは、科挙に及第するより上かも知れない。
果たして昨日よりは早くにお開きとなった朝議の後で、また今日も後宮について話題に上らなかったと不思議に感じたのはほんの短い間だった。外廷から内廷へと足を踏み入れた所で梅が待っていたのだ。
「書簡をお持ちしました」
昨日の今日だ、誰からなんて聞くまでもない。だがここには四郎が居る。珍しくちゃんと宦官らしく振る舞う梅に驚く余裕さえなく、玲馨は努めて反応しないようにした。
折りたたまれた書簡の最初だけを確認した戊陽は梅に短く命じる。「下がって良いぞ」それから「玲馨」と名前を呼んだ。「はい」返事をする。来いという意味だ。あわいの宦官は正午を境に皇弟の元を訪ねるので時間はまだある。
本当に、珍しく正しい姿勢で頭を下げてから、梅は静かに去っていった。いくらなんでも不気味だったが、ここには四郎だけに留まらず少し戻れば外廷から内廷へと続く道を警備する兵士がいるのである。梅の畏まった態度は大いに正解だった。不気味だったが。
朝議の後は決まって黄麟宮に戻るのだが、今日は紅桃宮へと引き上げた。無論、受け取った書簡の確認をするためである。連日四郎を遠ざけているのでそろそろ文句なり言ってくるかと思ったが、滅私の鉄人はこの程度では折れないらしい。
紅桃宮にある宦官の部屋へと戻った四郎は、以降は呼ばれなければ寝所にまで来る事はない。
何も四郎にだけ知られないようにしている訳ではなかった。こうした事は知る人数は少なければ少ないほどあらゆる面で安全というだけだ。
「何が書かれてありました?」
「まぁそう急くな。気持ちは分かるが。一緒に読むといい」
いつもの場所──漏窓からの光がよく当たる部屋の中央──にある椅子に座り、卓の上に書簡を広げる。その瞬間、さきほども感じたとある香りがむわっと広がった。
濃くて甘い、秘め事にうってつけな麝香の香り。妓楼に漂っていた淫靡なそれは書簡の向こうに見える男の影を消すためだろうか。それにしたって妓女から艶書──恋文とも言う──が皇帝に送られてくるというのは戊陽の品位を落としはしないか不安になる。
戊陽の隣に立って書簡を覗き込むようにすると無言で空いた椅子を叩かれたので、仕方なく腰を下ろして改めて書簡を読み始める。
当たり前のように送り主の名は書いていない。代筆でも頼んだか文字の雰囲気はいかにも女が筆を取ったかのようなしなやかさがあって、送り主の正体を知っていると先の梅に負けず劣らず不気味に思えた。
肝心の内容は「才女」を演出するためか詩文など古典からの引用が多分に含まれてとにかく読み難い。
ちらと戊陽の顔を窺う。思った通り、目が遠くて字を読めない老人のような顔をして書簡を睨みつけている。
それにしてもこれは、と苦い声が玲馨の心の中にも吐き出される。好き嫌いは置いておいて、教養という意味でなら戊陽の方が遥かに豊富な知識を持っている。勉学に触れて来た時間がまるで違うから当然だ。当時国で一番の賢者を物心つく頃から師につけていた戊陽をして渋面を作るほどとなると、玲馨にはところどころ意味を掴みあぐねる箇所が散見された。
どうにか読み終えると、戊陽は鼻梁の根本を指で揉みほぐす。
「とりあえず先日の非礼を侘びている辺り、酒で気が大きくなり過ぎるきらいがあるのだろうな」
相手が戊陽で命拾いしたという事だ。ちょうど玲馨には意味が分からなかった文を拾って戊陽が説明する。
「それから、何かあるなら妓楼の桂茜へ連絡をつけろと言っている。先日使った『洋』という名が通るようにしたそうだ」
ぱち、と瞬いて、玲馨は隣にある顔を見た。
「詳しくは書かれていないが、いくつか不正や悪事の情報を……どうした玲馨?」
「いえ……陛下は、私の事をよくご存じなのだなと……私が分からない所ばかり教えて下さる、ので……」
言ってしまってからとんだ思い上がりの発言だったと気付いて、カッと耳の付け根の辺りから熱が上るのを感じた。案の定、ふ、ふ、と隣で戊陽の体が楽し気に揺れる。単なる偶然を自分の都合の良いように解釈してしまうなど恥ずかしくてたまらない。
「お前は頭が良いからすぐに忘れてしまうが、共に学んだのはせいぜい三年くらいの事だったのだな」
「……はい。私には過分な、有難い事でした」
「ふと、時々思う。あの頃のように、時も幸福も際限無いものだと信じていた自分に戻れたらと。自分に与えられた力にもやはり限りはないのだと思い込んでいた」
戊陽の言うあの頃は黄雷の生きていた時代だ。およそ十年前、懐かしんで帰りたいと思うには幼い。だがそれよりも後年には彼にとってつらい経験が待ち構えている。「あの頃は良かった」などという言葉は彼の年頃には全く相応しくない。もちろん玲馨にとってもだ。
「もし、もしも、戻れると言われたら?」
「ん?」
「望むままに、力を活かす道を探る日々に戻れるとしたら」
戊陽は何を選択するのか──。
答えが返ってくるまでにさほどの時はかからなかった。
「沈に時を戻す異能の力があれば良かったんだがな」
緩く笑む横顔には未練や哀愁のようなものは無かった。代わりに浮かんでいたのは諦念と、地に足のついた覚悟。
すぐに、玲馨は自分が酷い質問を投げかけたのだと察して強く動揺した。とにかく謝罪の言葉しか頭に浮かんでこず椅子から降りようとしたが、先んじて止めらる。
「なぁ玲馨。俺はお前が居れば良い。この先、母上ともいずれは別れる日が訪れる。そうなった時、俺にはお前が居てくれるんだと思うだけでその日を逃げずに受け止められるんだ」
まるで女を口説くような甘言だ。この世の誰が言ったとしても玲馨はその言葉を信じなかっただろう。けれど戊陽ならば、玲馨に対して対等にそして真っすぐに向き合い続けた戊陽の言う事だから、上滑りせず確かな重さを持って玲馨の胸を打つ。
何と返せば良いのか分からず、暫くの間読む訳でもなく無言で書簡に視線を落としていた。それはひょっとすると鼻の奥が沁みるような痛みを堪えている時間だったのかも知れない。
「……戊陽」
結局、長い時をかけて口を衝いたのはそれだけで、滅多に玲馨からは聞かない名を耳にして驚き振り返った戊陽は、玲馨の表情を見て更に驚き言葉をなくす。
或いは泣いた後だと言われた方が信じるくらいの感極まった玲馨の表情は、目の縁や鼻の頭がほんのり赤く染まっていた。そんな顔で名を呼ばれて放っておけるほど戊陽は自制のきく歳ではなかったし、また玲馨もそれを止められるいつもの余裕は消えていた。
どちらともなく顔を近づけて、互いの呼吸を感じる距離にくると自然に瞼をおろす。柔らかな肉の感触が唇に触れると一度離れて見つめ合い、互いの目に消えない熾火のような熱を見つけるとまた重ね合わせる。
夢中になって唇を貪った。いつ以来だろう。分からない。だけど戊陽の味は忘れていなかった。
舌が入ってきて、ほんの少しまごつきながらも受け止めて、絡めて。幼い日、初めてこうした時はもっとたどたどしくて探るようだった戊陽の舌使いも数年のうちに玲馨を翻弄するまでになった。
麝香の香りに中てられたかのように頭の奥がぼうっとし始めて、自然とすぐ傍にある寝台を意識した。
その瞬間だった。
ゴオォォンという鐘の音が汀彩城で働く者たちへ正午を告げる。あわいの宦官があわいたる所以を務める午後の訪れである。
「はあ……」
生温くて名残惜しさを隠しもしない吐息を漏らしたのはどちらだったのか。互いに理性を取り戻して苦笑する。
「昼から盛るところだった」
「結局今後の事を決められませんでした」
「俺が考えておく。小杰の所へ行っておいで」
「私も、何か出来ないか考えておきます」
「ああ。また明日だ」
「はい」
戊陽の寝所を出てからもまだ顔が赤くなっているような気がして、片手で顔を仰ぎながら後宮へと向かった。
北玄海で一ヶ月、その後山芒で約半月。顔を出せなかった時期が長かったせいで、東妃宮へ通う足取りはさしもの玲馨であっても軽いとは言えなかった。紫沈に戻ってきて数日経つがやっと小杰が口をきいてくれるようになったところだ。
東妃宮は春の盛りになると、大きく華やかな牡丹の花が見頃を迎えて庭を美しく彩る。派手好みな東妃は様々な花を庭に植えさせており、季節ごとに違った顔を見せるのが他の宮にはない特徴だ。それがまた他の妃から反感を買っていたのだが、そうと知りながらも決して自分の趣味を変えるような事はしなかった。その逸話は東妃という人を端的によく表していると玲馨は思う。
花の王とも呼ばれる大輪の牡丹に見られながら、玲馨は心なしか庭をそろりと歩む。
「東妃様、小杰殿下。玲馨が参りました」
朱に塗られた透かし彫りが美しい扉が内側から開けられると、玲馨は目を瞠った。
「小杰殿下!」
玲馨は慌てて拱手する。
宮女の代わりに自ら扉を開けた小杰が、合言葉を言わなければ通さないとでもいうように腕組みをして扉の向こうに立っていた。
「待っておったのだ。首を長く長ーくして玲馨を待っておったのだ」
つい先日まで意地を張って口を閉ざしていたというのに、一度気を許した途端にこうである。よくよく懐かれたものだと、小杰の拗ねた声を聞きながら玲馨の眉が下がる。
「申し訳御座いません殿下」
「良い。お主に謝らせたいのではないからな」
皇子への教育は妃ごとに方針が異なる。戊陽の母賢妃は比較的放任主義だった。戊陽のさせたいようにさせた結果が脱走癖だったので上手くいったとは言えないが、それがなければ今の玲馨はなかったので偶然への感謝はある。
一方小杰の母東妃は、小杰の耳や目に入れるもの、口にするもの袖を通すものと全ての事柄に細かく口を出す人だ。更に皇子としての振る舞いや気品を求める人なので、東妃宮に仕える侍女や宦官は自然と幼い小杰へも畏敬を持って接する事になる。同腹の兄弟姉妹は他になく良く言えば大事にされているが、悪く言えば過干渉で過保護にされてきた。そうしてわがままで尊大に育った十二の子供に罪はない。
わがままと言っても度が過ぎるという事はなかった。せいぜい歳よりも子供っぽく見える程度、可愛いものだ。尊大な態度は皇子である事を思えば当然のもので、五男だろうと卑屈にならないのは彼の今後にとって大事な事なのかも知れない。
そんな小杰が数日もの間玲馨と口を聞きたがらなかったのはとても珍しい事だった。それほど怒っていた、というより心から寂しかったのだろう。
小杰にとって玲馨は他の宦官とは違い、師という側面もある。完全にこの宮に仕えているわけでもないのでどこか客分のような立場でもあった。毎日通ってきては他の宦官のようにあくせく世話をするでもなく、自分に物事を教えてくれる年上の存在というのは、やはり慕いたくなるものなのだろう。
だがそんな日々も間もなく終わりが近い。玲馨は数ある教育係の一人としてこの東妃宮に仕えている。小杰が後宮を出ればそのお役目も終わりになるのだ。
いざその日が来たら小杰は癇癪を起こして泣いてしまうのではないだろうか。年季が明けた宮女が里帰りするといっては毎度ぐずるような子なので、先行きは不安である。
そのためにも于雨という年下の存在は小杰に必要だと思うのだが、今はまだその時ではない。長らくの不在は戊陽側の都合で起こった事なのだから、それを忘れて玲馨の希望を口にするというのは憚られた。
「今日は庭に出ます。牡丹が良い見頃を迎えていますから」
宮殿の主である東妃の一声で、宮女や宦官たちがいそいそと支度を始める。
後宮の各妃たちの居所には庭があるが、四阿が建てられるほど広くはない。そのため庭で花が見たい茶が飲みたいと妃が言い出せば、毎度卓と椅子を外に運び出す事になる。丈の伸び始めた下生えの上に下ろしても傾かないような重い調度品を使うので、力仕事をこなす宦官たちには花見の評判はいまひとつだ。それは恐らくどの宮でも大差ないだろう。
玲馨ももちろん手伝うのであるが、ふと気付くと玲馨の仕事はなくなっている。玲馨を皇帝付きの宦官と見做して気遣っているのではなく、寧ろその逆だ。若くして皇帝と皇弟を股にかけているのが気に入らない宦官は決して少なくなく、表立って嫌がらせはされない代わりにさり気なく輪から外される。宮女たちからの態度も似たようなものだ。
別に彼らに気に入られたいとか仲良くしたという気はない。そこはお互い様だろう。だが、今後何かのきっかけがあって今以上に東妃宮で長い時間を過ごさなくてはならなくなるような事があれば想像だけでも気が滅入る事は確かだ。
ふと卓の上に並んだ菓子の中に月餅を見つけて懐かしいような気持ちになる。子供の頃よく賢妃宮でも食べさせてもらったものだ。
月餅は秋頃によく食べる菓子だが秋にしか食べてはいけないという事はない。形や中の餡には地域性があり、東江では専ら真ん丸で白い生地に豆の餡を包むのが一般的だ。紫沈の物は皮はきつね色に焼いて型を押し、餡は大抵いくつかの種類を混ぜた物で作るので歯触りがしっかりとしている。
東妃宮に仕えるのは面倒な事も多いが遠く西方の昆の影響も受けているので、その文化の違いに触れられるのは楽しい。それにやはり同郷だからか賢妃宮と食事や衣類や装飾品に共通のものを見つけるのも何となく心を落ち着かせてくれた。
「何だか今日の玲馨は上の空のようだ」
出来上がった花見の席で白い月餅を一口含んで小杰が言う。
「申し訳御座いません小杰殿下」
「ここに居ても、ここではない所に居るような」
「私には一切そのようなつもりはないので御座いますが、何分私はあまり器用な性質ではないもので、少し忙しくなるとその事で精一杯になるのです」
「それは私には手伝えない事か?」
予想外の言葉に虚を突かれる。玲馨の事を慕ってはいても手伝いたいなどという意思表示は初めての事だ。これまで彼の目標は皇帝の、つまり戊陽の助けになる事のみだった。
「いえ、滅相も御座いません。殿下のお手を煩わせるような事はお仕えする身として相応しくありません」
少し突き放すような言い方になってしまっただろうか。頭の隅に林隆宸や桂昭の事を思い浮かべたせいだ。しかし小杰は気を悪くするような事はなく、やや肩を落としながら「そうか」と素直に納得した。
「私がもう少し大人になって戊陽兄上を助けられるようになれば、玲馨も楽が出来るか?」
「それは、もちろんで御座います。私などよりも、陛下がさぞお喜びになられましょう」
何もお世辞で言っているのではない。母同士はさておき、兄弟仲は非常に良いのが当代の皇帝とその弟たちだ。さしもの戊陽も黄昌が存命の頃は皇太子である兄に遠慮というものを持ち合わせていたが、殊弟たちに至っては積極的に交流を持ちたがった。お陰で玲馨もよく他の妃の宮に連れ回されてはおろおろしていた。
間もなく三男、四男も宮廷に上がる事がかなう歳になる。そうなれば宮廷で孤立した戊陽にも多少の追い風にはなるだろう。小杰がその輪に加わる頃には、皇族の権威もいくらか回復しているかも知れない。
戊陽は玲馨の事を「待つ」と言ってくれた。玲馨の抱える問題が片付くのを待ってくれている。
では、玲馨はどれだけ「待つ」を出来るだろうか。
三年? 五年? 十年は待てない。待ちたくない。自分にこの世の全てを動かすような強大な力があったなら、今すぐにだって行動を起こしたいというのに。
世が完全な安寧となるのを待っているうちに終ぞ玲馨の願いは叶わぬまま戊陽は賢帝とでも呼ばれて帝のまま世を去るとも限らない。玲馨とていつまでも生きていられるわけではないのだ。
焦りが募る。小杰の歳が幼い事にすら焦れる。
こんなにも欲深な自分を大人になるまで知らなかった。玲馨を性の捌け口として使ってきた男たちを何と醜い事かと、玲馨が稼いだ金で自分ばかり楽をする母を何と憐れかとずっと思ってきた。
けれども玲馨も同じだった。玲馨という皮の下にはあの大人たちと同じ傲慢で身勝手な化け物が棲んでいる。
怖がりだった「明杰」は、陽の光を浴びるその背中に濃い影を作り出した。影は、太陽なくして生まれない。
──戊陽。あなたの光の暖かさは、魔性のものだ。
小杰に指摘されたばかりだというのに、次第に強くなる焦りは玲馨の心を浮き足立たせてゆく。
しかし。
「いやぁー、こんな所にへい、っといけない。洋様がいらっしゃるだなんて。早く仰ってくれたら私が良い妓女を紹介しましたものを」
ぐわん、と大きく体が後ろに傾いだかと思うと腹筋の力で元に戻ってきた桂昭はへらりとだらしなく笑って空になった杯を持ち上げる。しかし先ほど戊陽が全ての妓女を下がらせてしまった事を遅れて思い出し、手酌して一口呷って満足気に息を吐いた。中身を水にすり替えてもらっているのだが、桂昭は全く気付いていない。
先程まで酒に酔って娘に絡もうとする桂昭を梅に止めさせていたので図らずも卓浩の云っていたように衣も髪も乱れてだらしない無精髭のお役人姿が出来上がっている。朝議で見かけた時には髭はなかったような気がするので、体毛が濃い体質なのだろう。
ただでさえ酩酊していたのに飲ませ続けているのは水なので危険はないというのはもちろん、酒入れば舌出づと言うのでこの際彼には好きにお喋りをしてもらおうという魂胆だ。
「籠に飼われた鳥でもあるまいに、自分の好きなものは自分で見つける」
「はっはっは! いやーさすがさすが、ご立派でいらっしゃる! 遠くからお声を聞いているだけでは分からない事があるものですなぁ」
相手は酔っ払いと分かっていても戊陽を軽んじるような発言に玲馨の表情が微かに歪む。言われた本人は言葉の内容よりも呂律も怪しいへべれけぶりに呆れている様子だ。
少し酔いが覚めるのを待つべきかと思っていたが、突然、割れてしまうのではないという勢いで杯を置くやいなや桂昭は据わった目で戊陽をゆらゆらと見据えた。
「ところで、へい、いや洋様は、うちの娘に何か御用で?」
娘とは先の妓女、桂茜の事だ。歳は十八、念願の一人娘として生まれて、芸事から文字に算術まで様々な事を学ばせ大事に育てたと好きに喋ってくれた。目に入れても痛くないほど猫可愛がりしており、どうやらこの部屋に乱入してきたのは娘の貞操守るためであったようだ。
だったらどうして妓楼などという男を相手に仕事をするような所で働かせているのか。興味はあるが本題とは関係ない。
「桂昭。お前は『柳』が好きなのだそうだな」
「んん……?」
何のことだかピンと来ていないようで、いかにも文官らしい細く肉刺の無い手で顎を擦る。
「柳……ええまあ嫌いって事はありませんがね……」
当てが外れたという落胆が押し寄せる。数奇な事に目的の男と早くも接触が叶ったが、現実は上手くいかないものだと。
落胆が諦めに変わろうとした時、桂昭の眉が跳ねた。本人にその自覚があったかは分からない。だがその一瞬の仕草が思い出したような閃いたような表情を作ってはすぐに消えていった。
──今のは何だ?
「ああ~ははっ、柳はね、洋様。隠語というか、暗号というか、宮廷内のほら、そうそう『合言葉』なんですよ」
「合言葉?」
「ええそう合言葉。己の派閥を明かすための符号ですよ」
明かすため、という言い方が気になった。
柳の事を否定しないとなると、卓浩の言った「桂」は桂昭の事で間違いなかったようだ。よくよく見れば着ている衣はさほど上等な物ではない。市井に紛れるためなのか、それとも官吏然として見られる事を嫌うのか、いずれにせよ仮にこの格好で向青倫の前に現れたのだとしたらだらしなく思われた事だろう。
「秘密の話をするにも相手の派閥は大事でしょう? 後宮だってそういう事があったと思いますがねぇ。──ああでも、前皇后様は貴妃様でありながら御子も立太子なさったのでした。いやいや陛下……じゃなかった、洋様の時代は後宮史でも稀に見る穏しき時代だったのかも知れませんなぁ」
ぺらぺらとよく回る舌はおべっかを並べる周子佑にも負けていない。違いは話の内容がおべっかでは無い点だ。寧ろ侮られている。平和ボケした皇帝陛下、と。しかしこの程度で気を悪くする戊陽ではなく、眉一つ動かさずに桂昭の言葉に答えた。
「平和は良いな。民が精力的になり文化は発展し、反乱はなく、政は安定する。そのために皇帝というものは存在するのだ」
想像とは違う答えだったのか、桂昭の表情からニヤついた笑みが消える。消えた後の顔は思いの外真面目な表情で、酒の気配を残しながらも理性的に見えた。
更に戊陽は続ける。
「宮廷内の合言葉と言ったな? だとしたら私はその言葉を知る由もなかったはずだ。何しろ柳の話を聞いたのは城の外だった」
言外に山芒で聞いたと明かしたようなものだ。桂昭が卓浩に自らその話題を振った事を覚えていて、尚且つ彼が北玄海側の人間なら卓浩の命が脅かされる事になる。
さて、どう出てくるか。
甘いような辛いよう麝香の香りが充満した妓楼の一室が、そうとは思えないほど張り詰めた緊迫感に包まれる。
パシンッ──と突然乾いた音がしたのは、桂昭が自身の膝を力強く叩いた音だった。胡座をかいた両膝に両手を乗せて桂昭は話す。
「柳はね、春を告げる花を咲かせるんです。吉祥木なんても言いますなぁ。城の水路でも枝垂れて風情のある景観を作るのに一役買ってる。けど、柳も増え過ぎたら堀の視界は悪く、秋には大量に葉を散らして塵のように水面を埋めて腐って臭う。何だって過ぎれば毒だと思いませんか? ねぇ洋様」
外連味を効かせた言い回しは回りくどくて面倒臭いついでに胡散臭い。「柳」とは何かを直接言わずに仄めかしているのはよく分かるが、身振り手振りを交えて話すおかげで気が散った。結局何が言いたいんだと詰め寄りたくなる。
しかし戊陽は冷静だった。
「増えすぎた柳を、お前ならどうする?」
戊陽に訊ねられた桂昭の目がぎらりと光る。
「──間引く」
「方法は?」
間髪入れずに訊き返されて瞠目したのは一瞬だった。
「奴らは自分で作った毒を抱え込んでるもんです。それを暴いて飲ませてやれば、勝手に減ってゆくでしょう」
そうか、と一言頷いて、戊陽は梅の名を呼んだ。すると梅は徐に立ち上がって背後にあった扉を開ける。
「わぁっ、あ、ああっ──」
突然扉を開けられた事で体勢を崩した桂茜が正面から倒れ込み転ぶ──と思うより早くに梅が彼女の肩を支えて事なきを得る。扉の向こうには娘の桂茜が張り付いていた。
「あの、あの、ごめんなさい私」
「酒を」
「は、はい……?」
「この男に酒を持ってきてくれ。私たちはそろそろ帰るから、その代わりに」
「は、はい!」
戊陽に笑いかけられてぽっと頬を染めながら桂茜は慌ただしく部屋を出ていった。「男なら誰でも良いのかよ」と一人相手にされず不満げに呟く梅の声は聞こえなかった事にした。
帰り際、持参していた玉を店の者に握らせれば、妓女を追い出したばかりかろくに酒も飲んでいかなかった戊陽たちだが責められるという事はなかった。寧ろ笑顔を固まらせてひどく畏まった様子で見送られてしまった。
「少々やり過ぎだったのでは?」
皇帝だと思われはしないだろうが、それでも怪しまれる種を与えてしまったような気がする。
「大丈夫だろう。若い貴族は見栄を張りたがるものだしな」
そうならいいが、桂昭と鉢合わせた以上はあの男が戊陽の正体をうっかり漏らさないとも限らない。
桂昭と言えばおかしな男だった。酔いのせいで気が大きくなっていたのだろうが、それにしては弁が立つ。呂律の怪しいところを無視すれば途中から彼は半分以上正気だった。
きっかけは、何だ。彼がまともに話そうとしたきっかけは。
『平和は良いな。民が精力的になり文化は発展し──』
平和ボケと馬鹿にされて怒るどころか逆手に取った戊陽の言葉、或いは態度を見て、桂昭は「柳」について「合言葉」以上の何かを仄めかした。
きっと合言葉だというのも嘘ではないだろう。柳が妓楼の隠語だと分かっていれば言い訳はどうとでも出来る。女にだらしないような印象を与えるかも知れない難点さえ除けば。
「柳は、結局何を示していたのでしょう……」
考えるあまりつい言葉にしてしまっていた。沈黙が返ってきた事ではっとして、周囲に視線を巡らせる。前を歩く梅が持つ灯りに照らされる範囲に人影はない。
「人だろうな、特定の」
「特定の?」
まさか気付かなかったのか? そう問われているような視線が隣から向けられる。玲馨は考える。
桂昭は言っていた。何事も過ぎれば毒となると。柳が増えすぎて害が出る事に喩えてそう言った。
ならば一人ではなく集団だと考えるところだが、戊陽の見解は違っていた。
「柳は貴族の姓だろう?」
姓と言われて漸く玲馨にも閃くものがあった。
「楊の事ですね」
「そうだ。楊は東江の姓だ。つまり──」
戊陽はその先を言わなかった。ここが外である事を懸念してだ。梅に話を聞かせ過ぎるのもあまり良くない。彼の身の安全を気にしてやる必要は無いと玲馨は思うが。
だからそこからは玲馨も黙って考えた。
戊陽は柳とは楊氏を指すと考えている。そして楊とは尚書令の林隆宸の旧姓だと既に判明していた。
養子だらけの宮廷で合言葉を使って互いの裏の顔を探り合うというのは確かに便利だろう。しかし、誰がどの四王の勢力に属しているかは注意深く監察していれば自ずと見えてくるもの。合言葉を使うというのは些か大袈裟なような気がする。
では具体的に何を確かめるための合言葉だったかを考えた時、桂昭の言った「己の派閥を明かすため」という言葉を思い出した。
派閥ではなく所属や組織のようなものだとしたら──。
林隆宸は自身の手駒となるような者を自身の名のもとに組織しているのではないか。
戊陽が、つまり「皇帝」が柳という合言葉を用いて桂昭に話題を振った時、桂昭は咄嗟に何の事か分からないととぼけてみせた。今にして思えばそれはおかしな反応だ。
柳が単に派閥の問いかけなのだとしたら、皇帝が合言葉を使っても不思議ではない。表向きは対立しているように見せかけて、その実柳の派閥を味方につけようとしている、と考えられなくもない。
だが桂昭はそうは考えなかった。何故なら皇帝が柳に属しているのはおかしいと知っているから。
柳が林隆宸を指すのだとしたら、皇帝に反目し続けてきた林隆宸のその組織する集団に皇帝が下るなんてことは有り得ないのだ。
そう考えると「明かす」という言い回しにもしっくりくる。林隆宸の組織に属する者が互いの所属を明かすのに合言葉を使うという事だ。
ほとんどが想像の域を出ないが、恐らくそう間違ってはいないだろう。増えすぎた柳を間引くという表現にもピンと来るものがある。
林隆宸は現在宮廷内で事実上最高権力を持っていると言って過言ではない。彼の権勢は皇帝を遥かに凌ぐ。それは他方からすれば邪魔者で、同胞からすれば目の上の瘤だ。そして皇帝──戊陽にとってもまた、宮廷から去ってほしい人である。林隆宸の強引で急進的なやり方は常に犠牲の上に成り立つと戊陽はそして玲馨もよく知っている。獄死した、いやさせられた戴氏の件が一つの例だ。
戊陽の「平和」に対する考え方から桂昭が何を読み取ったのかまでは分からない。彼を味方につけられると安易に考えない方が賢明だろう。桂昭が思惑の一端を明かした理由は、林隆宸を排斥するためにいっときの共闘関係を築きたいという遠回しな提案で、その後も戊陽の味方で居続ける保証はどこにもない。
しかしそれは裏を返せば、戊陽に皇帝としての力を得てほしくない玲馨にとっては好都合だった。
林隆宸。あの男を生かしたままでは、いずれ奴の毒牙は戊陽にも及ぶだろう。宮廷の悪い腫瘤を切り離すには、今この時を逃す手は無いように思われた。
「梅、灯りはお前が持っていっていいぞ。宿舎側は灯りが少ないからな」
戊陽の声に思索から返ってきた玲馨は人知れずぎょっとする。いつの間にか城まで戻ってきており、既に後宮まで続く門の前に来ていた。よっぽど考え事に夢中だったらしい。
ここから先は警備のための篝火が焚かれているので戊陽の言う通り下級宦官の宿舎へ向かうのに比べると足元はずっと明るい。
「いやさすがに陛下から手燭を奪ってくわけにはいきませんて」
「問題ない。それは貸し出すのだからな」
「陛下の事なら私が黄麟宮まできちんとお送りする。帰っていいぞ梅」
「あーはいはい! ったく二人して俺を邪魔者扱いしやがって! 馬に蹴られるのは御免なんで言われた通りにしますよ!」
後宮と下級宦官の宿舎は離れており、夜も深い時間に往復するとなるとろくに眠る事無く朝を迎えるだろう。
これは戊陽の気遣いだ。それに梅も気付いている。だから空気が固くならないように冗談を飛ばして踵を返す。
梅の事は嫌いだが、悪い奴ではない事はもう理解していた。それに察しの良さもある。
「玲馨も帰っていいぞ」
梅の姿が角の先に消えると戊陽がさも当然のように言ってくるので玲馨は声を固くする。
「ご冗談を」
「だったら俺の部屋で休むか?」
すかさず同じ言葉で切り返そうとしたが思いの外真剣な眼差しとぶつかって声は喉元で霧散した。
別に、断る理由は無い。望まれるなら、望まれるままに皇帝の寝所に入るのは、実のところ玲馨とて吝かではない。だけど。
視線を逸らしたのは戊陽からだった。それから抑えた声で「俺が自分で決めた事だしな」と呟いたのだが、玲馨にはほとんど聞き取れなかった。
「必ず俺のところに戻ってくるんだろう」
何があろうとも──。
彼の台詞には言葉にならない続きが聞こえるようだった。
「はい」
翌日の朝議ではうっかりすると襲ってくる睡魔に抗うために敢えて考え事に没頭していた。
気になる事は山の如しであるが、目下の懸念は桂昭との連絡手段だ。柳云々が合言葉だというのなら、それはつまり柳の意味を知る者同士で監視し合う事にもなるだろう。そうでなくとも宮廷での一挙手一投足は誰に見られているか分かったものではない。怪しまれず個人的に「皇帝」と接触する事の難しさは、科挙に及第するより上かも知れない。
果たして昨日よりは早くにお開きとなった朝議の後で、また今日も後宮について話題に上らなかったと不思議に感じたのはほんの短い間だった。外廷から内廷へと足を踏み入れた所で梅が待っていたのだ。
「書簡をお持ちしました」
昨日の今日だ、誰からなんて聞くまでもない。だがここには四郎が居る。珍しくちゃんと宦官らしく振る舞う梅に驚く余裕さえなく、玲馨は努めて反応しないようにした。
折りたたまれた書簡の最初だけを確認した戊陽は梅に短く命じる。「下がって良いぞ」それから「玲馨」と名前を呼んだ。「はい」返事をする。来いという意味だ。あわいの宦官は正午を境に皇弟の元を訪ねるので時間はまだある。
本当に、珍しく正しい姿勢で頭を下げてから、梅は静かに去っていった。いくらなんでも不気味だったが、ここには四郎だけに留まらず少し戻れば外廷から内廷へと続く道を警備する兵士がいるのである。梅の畏まった態度は大いに正解だった。不気味だったが。
朝議の後は決まって黄麟宮に戻るのだが、今日は紅桃宮へと引き上げた。無論、受け取った書簡の確認をするためである。連日四郎を遠ざけているのでそろそろ文句なり言ってくるかと思ったが、滅私の鉄人はこの程度では折れないらしい。
紅桃宮にある宦官の部屋へと戻った四郎は、以降は呼ばれなければ寝所にまで来る事はない。
何も四郎にだけ知られないようにしている訳ではなかった。こうした事は知る人数は少なければ少ないほどあらゆる面で安全というだけだ。
「何が書かれてありました?」
「まぁそう急くな。気持ちは分かるが。一緒に読むといい」
いつもの場所──漏窓からの光がよく当たる部屋の中央──にある椅子に座り、卓の上に書簡を広げる。その瞬間、さきほども感じたとある香りがむわっと広がった。
濃くて甘い、秘め事にうってつけな麝香の香り。妓楼に漂っていた淫靡なそれは書簡の向こうに見える男の影を消すためだろうか。それにしたって妓女から艶書──恋文とも言う──が皇帝に送られてくるというのは戊陽の品位を落としはしないか不安になる。
戊陽の隣に立って書簡を覗き込むようにすると無言で空いた椅子を叩かれたので、仕方なく腰を下ろして改めて書簡を読み始める。
当たり前のように送り主の名は書いていない。代筆でも頼んだか文字の雰囲気はいかにも女が筆を取ったかのようなしなやかさがあって、送り主の正体を知っていると先の梅に負けず劣らず不気味に思えた。
肝心の内容は「才女」を演出するためか詩文など古典からの引用が多分に含まれてとにかく読み難い。
ちらと戊陽の顔を窺う。思った通り、目が遠くて字を読めない老人のような顔をして書簡を睨みつけている。
それにしてもこれは、と苦い声が玲馨の心の中にも吐き出される。好き嫌いは置いておいて、教養という意味でなら戊陽の方が遥かに豊富な知識を持っている。勉学に触れて来た時間がまるで違うから当然だ。当時国で一番の賢者を物心つく頃から師につけていた戊陽をして渋面を作るほどとなると、玲馨にはところどころ意味を掴みあぐねる箇所が散見された。
どうにか読み終えると、戊陽は鼻梁の根本を指で揉みほぐす。
「とりあえず先日の非礼を侘びている辺り、酒で気が大きくなり過ぎるきらいがあるのだろうな」
相手が戊陽で命拾いしたという事だ。ちょうど玲馨には意味が分からなかった文を拾って戊陽が説明する。
「それから、何かあるなら妓楼の桂茜へ連絡をつけろと言っている。先日使った『洋』という名が通るようにしたそうだ」
ぱち、と瞬いて、玲馨は隣にある顔を見た。
「詳しくは書かれていないが、いくつか不正や悪事の情報を……どうした玲馨?」
「いえ……陛下は、私の事をよくご存じなのだなと……私が分からない所ばかり教えて下さる、ので……」
言ってしまってからとんだ思い上がりの発言だったと気付いて、カッと耳の付け根の辺りから熱が上るのを感じた。案の定、ふ、ふ、と隣で戊陽の体が楽し気に揺れる。単なる偶然を自分の都合の良いように解釈してしまうなど恥ずかしくてたまらない。
「お前は頭が良いからすぐに忘れてしまうが、共に学んだのはせいぜい三年くらいの事だったのだな」
「……はい。私には過分な、有難い事でした」
「ふと、時々思う。あの頃のように、時も幸福も際限無いものだと信じていた自分に戻れたらと。自分に与えられた力にもやはり限りはないのだと思い込んでいた」
戊陽の言うあの頃は黄雷の生きていた時代だ。およそ十年前、懐かしんで帰りたいと思うには幼い。だがそれよりも後年には彼にとってつらい経験が待ち構えている。「あの頃は良かった」などという言葉は彼の年頃には全く相応しくない。もちろん玲馨にとってもだ。
「もし、もしも、戻れると言われたら?」
「ん?」
「望むままに、力を活かす道を探る日々に戻れるとしたら」
戊陽は何を選択するのか──。
答えが返ってくるまでにさほどの時はかからなかった。
「沈に時を戻す異能の力があれば良かったんだがな」
緩く笑む横顔には未練や哀愁のようなものは無かった。代わりに浮かんでいたのは諦念と、地に足のついた覚悟。
すぐに、玲馨は自分が酷い質問を投げかけたのだと察して強く動揺した。とにかく謝罪の言葉しか頭に浮かんでこず椅子から降りようとしたが、先んじて止めらる。
「なぁ玲馨。俺はお前が居れば良い。この先、母上ともいずれは別れる日が訪れる。そうなった時、俺にはお前が居てくれるんだと思うだけでその日を逃げずに受け止められるんだ」
まるで女を口説くような甘言だ。この世の誰が言ったとしても玲馨はその言葉を信じなかっただろう。けれど戊陽ならば、玲馨に対して対等にそして真っすぐに向き合い続けた戊陽の言う事だから、上滑りせず確かな重さを持って玲馨の胸を打つ。
何と返せば良いのか分からず、暫くの間読む訳でもなく無言で書簡に視線を落としていた。それはひょっとすると鼻の奥が沁みるような痛みを堪えている時間だったのかも知れない。
「……戊陽」
結局、長い時をかけて口を衝いたのはそれだけで、滅多に玲馨からは聞かない名を耳にして驚き振り返った戊陽は、玲馨の表情を見て更に驚き言葉をなくす。
或いは泣いた後だと言われた方が信じるくらいの感極まった玲馨の表情は、目の縁や鼻の頭がほんのり赤く染まっていた。そんな顔で名を呼ばれて放っておけるほど戊陽は自制のきく歳ではなかったし、また玲馨もそれを止められるいつもの余裕は消えていた。
どちらともなく顔を近づけて、互いの呼吸を感じる距離にくると自然に瞼をおろす。柔らかな肉の感触が唇に触れると一度離れて見つめ合い、互いの目に消えない熾火のような熱を見つけるとまた重ね合わせる。
夢中になって唇を貪った。いつ以来だろう。分からない。だけど戊陽の味は忘れていなかった。
舌が入ってきて、ほんの少しまごつきながらも受け止めて、絡めて。幼い日、初めてこうした時はもっとたどたどしくて探るようだった戊陽の舌使いも数年のうちに玲馨を翻弄するまでになった。
麝香の香りに中てられたかのように頭の奥がぼうっとし始めて、自然とすぐ傍にある寝台を意識した。
その瞬間だった。
ゴオォォンという鐘の音が汀彩城で働く者たちへ正午を告げる。あわいの宦官があわいたる所以を務める午後の訪れである。
「はあ……」
生温くて名残惜しさを隠しもしない吐息を漏らしたのはどちらだったのか。互いに理性を取り戻して苦笑する。
「昼から盛るところだった」
「結局今後の事を決められませんでした」
「俺が考えておく。小杰の所へ行っておいで」
「私も、何か出来ないか考えておきます」
「ああ。また明日だ」
「はい」
戊陽の寝所を出てからもまだ顔が赤くなっているような気がして、片手で顔を仰ぎながら後宮へと向かった。
北玄海で一ヶ月、その後山芒で約半月。顔を出せなかった時期が長かったせいで、東妃宮へ通う足取りはさしもの玲馨であっても軽いとは言えなかった。紫沈に戻ってきて数日経つがやっと小杰が口をきいてくれるようになったところだ。
東妃宮は春の盛りになると、大きく華やかな牡丹の花が見頃を迎えて庭を美しく彩る。派手好みな東妃は様々な花を庭に植えさせており、季節ごとに違った顔を見せるのが他の宮にはない特徴だ。それがまた他の妃から反感を買っていたのだが、そうと知りながらも決して自分の趣味を変えるような事はしなかった。その逸話は東妃という人を端的によく表していると玲馨は思う。
花の王とも呼ばれる大輪の牡丹に見られながら、玲馨は心なしか庭をそろりと歩む。
「東妃様、小杰殿下。玲馨が参りました」
朱に塗られた透かし彫りが美しい扉が内側から開けられると、玲馨は目を瞠った。
「小杰殿下!」
玲馨は慌てて拱手する。
宮女の代わりに自ら扉を開けた小杰が、合言葉を言わなければ通さないとでもいうように腕組みをして扉の向こうに立っていた。
「待っておったのだ。首を長く長ーくして玲馨を待っておったのだ」
つい先日まで意地を張って口を閉ざしていたというのに、一度気を許した途端にこうである。よくよく懐かれたものだと、小杰の拗ねた声を聞きながら玲馨の眉が下がる。
「申し訳御座いません殿下」
「良い。お主に謝らせたいのではないからな」
皇子への教育は妃ごとに方針が異なる。戊陽の母賢妃は比較的放任主義だった。戊陽のさせたいようにさせた結果が脱走癖だったので上手くいったとは言えないが、それがなければ今の玲馨はなかったので偶然への感謝はある。
一方小杰の母東妃は、小杰の耳や目に入れるもの、口にするもの袖を通すものと全ての事柄に細かく口を出す人だ。更に皇子としての振る舞いや気品を求める人なので、東妃宮に仕える侍女や宦官は自然と幼い小杰へも畏敬を持って接する事になる。同腹の兄弟姉妹は他になく良く言えば大事にされているが、悪く言えば過干渉で過保護にされてきた。そうしてわがままで尊大に育った十二の子供に罪はない。
わがままと言っても度が過ぎるという事はなかった。せいぜい歳よりも子供っぽく見える程度、可愛いものだ。尊大な態度は皇子である事を思えば当然のもので、五男だろうと卑屈にならないのは彼の今後にとって大事な事なのかも知れない。
そんな小杰が数日もの間玲馨と口を聞きたがらなかったのはとても珍しい事だった。それほど怒っていた、というより心から寂しかったのだろう。
小杰にとって玲馨は他の宦官とは違い、師という側面もある。完全にこの宮に仕えているわけでもないのでどこか客分のような立場でもあった。毎日通ってきては他の宦官のようにあくせく世話をするでもなく、自分に物事を教えてくれる年上の存在というのは、やはり慕いたくなるものなのだろう。
だがそんな日々も間もなく終わりが近い。玲馨は数ある教育係の一人としてこの東妃宮に仕えている。小杰が後宮を出ればそのお役目も終わりになるのだ。
いざその日が来たら小杰は癇癪を起こして泣いてしまうのではないだろうか。年季が明けた宮女が里帰りするといっては毎度ぐずるような子なので、先行きは不安である。
そのためにも于雨という年下の存在は小杰に必要だと思うのだが、今はまだその時ではない。長らくの不在は戊陽側の都合で起こった事なのだから、それを忘れて玲馨の希望を口にするというのは憚られた。
「今日は庭に出ます。牡丹が良い見頃を迎えていますから」
宮殿の主である東妃の一声で、宮女や宦官たちがいそいそと支度を始める。
後宮の各妃たちの居所には庭があるが、四阿が建てられるほど広くはない。そのため庭で花が見たい茶が飲みたいと妃が言い出せば、毎度卓と椅子を外に運び出す事になる。丈の伸び始めた下生えの上に下ろしても傾かないような重い調度品を使うので、力仕事をこなす宦官たちには花見の評判はいまひとつだ。それは恐らくどの宮でも大差ないだろう。
玲馨ももちろん手伝うのであるが、ふと気付くと玲馨の仕事はなくなっている。玲馨を皇帝付きの宦官と見做して気遣っているのではなく、寧ろその逆だ。若くして皇帝と皇弟を股にかけているのが気に入らない宦官は決して少なくなく、表立って嫌がらせはされない代わりにさり気なく輪から外される。宮女たちからの態度も似たようなものだ。
別に彼らに気に入られたいとか仲良くしたという気はない。そこはお互い様だろう。だが、今後何かのきっかけがあって今以上に東妃宮で長い時間を過ごさなくてはならなくなるような事があれば想像だけでも気が滅入る事は確かだ。
ふと卓の上に並んだ菓子の中に月餅を見つけて懐かしいような気持ちになる。子供の頃よく賢妃宮でも食べさせてもらったものだ。
月餅は秋頃によく食べる菓子だが秋にしか食べてはいけないという事はない。形や中の餡には地域性があり、東江では専ら真ん丸で白い生地に豆の餡を包むのが一般的だ。紫沈の物は皮はきつね色に焼いて型を押し、餡は大抵いくつかの種類を混ぜた物で作るので歯触りがしっかりとしている。
東妃宮に仕えるのは面倒な事も多いが遠く西方の昆の影響も受けているので、その文化の違いに触れられるのは楽しい。それにやはり同郷だからか賢妃宮と食事や衣類や装飾品に共通のものを見つけるのも何となく心を落ち着かせてくれた。
「何だか今日の玲馨は上の空のようだ」
出来上がった花見の席で白い月餅を一口含んで小杰が言う。
「申し訳御座いません小杰殿下」
「ここに居ても、ここではない所に居るような」
「私には一切そのようなつもりはないので御座いますが、何分私はあまり器用な性質ではないもので、少し忙しくなるとその事で精一杯になるのです」
「それは私には手伝えない事か?」
予想外の言葉に虚を突かれる。玲馨の事を慕ってはいても手伝いたいなどという意思表示は初めての事だ。これまで彼の目標は皇帝の、つまり戊陽の助けになる事のみだった。
「いえ、滅相も御座いません。殿下のお手を煩わせるような事はお仕えする身として相応しくありません」
少し突き放すような言い方になってしまっただろうか。頭の隅に林隆宸や桂昭の事を思い浮かべたせいだ。しかし小杰は気を悪くするような事はなく、やや肩を落としながら「そうか」と素直に納得した。
「私がもう少し大人になって戊陽兄上を助けられるようになれば、玲馨も楽が出来るか?」
「それは、もちろんで御座います。私などよりも、陛下がさぞお喜びになられましょう」
何もお世辞で言っているのではない。母同士はさておき、兄弟仲は非常に良いのが当代の皇帝とその弟たちだ。さしもの戊陽も黄昌が存命の頃は皇太子である兄に遠慮というものを持ち合わせていたが、殊弟たちに至っては積極的に交流を持ちたがった。お陰で玲馨もよく他の妃の宮に連れ回されてはおろおろしていた。
間もなく三男、四男も宮廷に上がる事がかなう歳になる。そうなれば宮廷で孤立した戊陽にも多少の追い風にはなるだろう。小杰がその輪に加わる頃には、皇族の権威もいくらか回復しているかも知れない。
戊陽は玲馨の事を「待つ」と言ってくれた。玲馨の抱える問題が片付くのを待ってくれている。
では、玲馨はどれだけ「待つ」を出来るだろうか。
三年? 五年? 十年は待てない。待ちたくない。自分にこの世の全てを動かすような強大な力があったなら、今すぐにだって行動を起こしたいというのに。
世が完全な安寧となるのを待っているうちに終ぞ玲馨の願いは叶わぬまま戊陽は賢帝とでも呼ばれて帝のまま世を去るとも限らない。玲馨とていつまでも生きていられるわけではないのだ。
焦りが募る。小杰の歳が幼い事にすら焦れる。
こんなにも欲深な自分を大人になるまで知らなかった。玲馨を性の捌け口として使ってきた男たちを何と醜い事かと、玲馨が稼いだ金で自分ばかり楽をする母を何と憐れかとずっと思ってきた。
けれども玲馨も同じだった。玲馨という皮の下にはあの大人たちと同じ傲慢で身勝手な化け物が棲んでいる。
怖がりだった「明杰」は、陽の光を浴びるその背中に濃い影を作り出した。影は、太陽なくして生まれない。
──戊陽。あなたの光の暖かさは、魔性のものだ。
小杰に指摘されたばかりだというのに、次第に強くなる焦りは玲馨の心を浮き足立たせてゆく。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
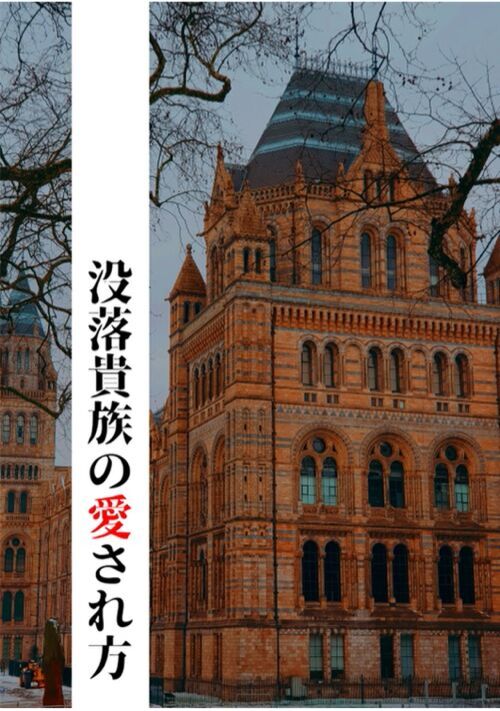
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















