43 / 44
完結編
43蜜月
しおりを挟む
初夏のやんわりとした熱を孕む風が頬を撫でていく。ほんのついさっきまで風はおろか日差しも差し込まない暗い地底のような場所にいたからだろう。汗ばむような外の暑さにさえも気持ちはそわそわし、視界いっぱいに広がる景色に感極まりそうになる。
もはや二度と見る事は叶わないと思っていた。優に十年は過ごしたはずの慣れ親しんだ汀彩城の風景を見渡して、今度こそ最後の別れを胸の裡で告げる。それから後宮の最奥へと歩を進める。
黄麟宮──。それは沈の皇帝が住まう宮殿。紫沈を守護する黄金の龍から名をとったその場所は、この国の持てる最高の技で造り上げた格別の居所である。宮女も宦官もここに仕える事は至高であり、生え抜きの者だけが皇帝を世話する役目を仰せつかる事が叶う。
しかし現在、この宮殿はもぬけの殻である。同様に後宮からも全ての人が去っていた。
先日ここ紫沈は、戦禍に見舞われた。建物は壊され民にも死者が出て、お膳立てなどなくとも皇帝の信頼は地に落ちていった。
およそ十日に及んだ戦乱は、皇帝の死を以て決着となる。そうして主のいなくなった黄麟宮からは、宮女も宦官も全てが追い出されて無人となったのだった。
無人となった後、東江の大男、関虎が一人で黄麟宮へと続く門を守るようになった。それが蘇智望の命である事も、その目的も訊ねずとも理解出来た。
門を通る時、互いに短く礼をするだけで言葉は交わさない。今日、ここ黄麟宮へ人が来る事は、彼の耳にも伝わっていたようだ。
庭の景色に荒んだ様子はなかった。無人になっても人の手は入っているようで、池の水面は透き通り、短く刈られた下草は歩行の邪魔にはならない。
扉を開ける時にわざわざ中へ声を掛ける必要も最早ない。重い扉を無言で開けば、人が消えた寂しげな広間が出迎える。皇帝は仕事をする時ここを執務室として使い、奥の間は寝所とした。
黄麟宮にはさほど振り返りたい思い出はない。それどころか辛く苦しい過去ばかりが蘇る。
黄昌の死から始まった過酷な日々は、日常にあった大切な何かを一息に壊していった。壊れたものを拾い集めて繋ぎ合わせ、どうにか体裁だけでも取り戻したように見えて、どこまでも昔とは違ってしまった。後宮を無邪気に駆け回っていたあの頃の姿は、もうきっと取り返せはしなかったのだ。
梅と風蘭の二人は門の外に残してきた。先程まで姦しかった彼らの声から離れると、静寂に耳が痛むようだ。
執務用の机の脇には使い込んだ香炉がそのままになっていた。近くを通るとほんの僅かに香の残り香が嗅覚を刺激する。
桃の淡い匂い──。それを知覚した瞬間に、ふっ、と息が漏れていった。
コツ、コツ、と自分の足音だけが響く違和感に慣れ始めた頃、寝所が視界に入る。二年の間に何度となく通った部屋の窓際に、人影があった。皇帝が死に、侍従たちが追い出された黄麟宮は、隠すのにはうってつけだったとそういう事だ。世話する者のない宮殿でひっそりと隠され過ごしてきた姿に、最早皇帝らしい威光はない。長い髪は無造作に下ろされ、衣は着るのが楽な簡素なもの。それから、記憶より少し痩せていた。
「戊陽」
思いの外掠れた声が出て、初めて喉がからからに乾いている事に気付く。
窓の外を眺めていた人影──戊陽は、振り返るなりあんぐりと口を開けてまるで幽霊でも見ているような顔をした。
「……玲馨」
戊陽は何もないところで躓きそうになりながらふらふらと近付いてくる。漸く互いが手を伸ばせば届く所までくると、玲馨はその距離を詰めさせないために右手に抱えていた物を突き出した。
「それは……何のつもりだ、玲馨」
右手に持った物。それは剣だ。
玲馨は剣を持ち替えて両手で戊陽に柄の方を向けて差し出す。その場に跪き、首を見せるようにして頭を垂れた。
「りんし──」
「私はあなたの思いを踏みにじった」
牢の中で枯れるほど泣いたはずなのに、じわりと熱くなった眦からぼとぼとと涙が溢れてくる。
「私は、私のためだけにあなたを裏切った」
抑えようとしても声は震え、喉が熱くてたまらなくなる。同情を買うようで嫌だと思うのに、思えば思うほどに視界は滲んでいった。
「どうか、あなたの手で殺してください」
それ以上言葉は必要ないだろう。
玲馨が握っていた剣が、戊陽によって引き抜かれる。鞘から抜けていく擦れる音を聞きながらぎゅっと目を瞑り、静かにその時を待った。
カラン、カラン……、と余韻を残しながら何か硬い物が床を滑って遠ざかっていく。視界の端に音の正体を捉えて玲馨はたまらず顔を上げた。
「なぜっ」
「歯を食い縛れ」
言うが早いかバチンという音が左から鳴って視界が大きく左右に揺さぶられた。遅れて頬を張られたのだと気付く。
死を覚悟したこんな時にでさえ大人の男に強い力で暴力を振るわれるという状況に、言葉にならない恐怖が襲いくる。しかし、戊陽の顔に涙の筋を見つけると、嘘のように恐怖は消えていった。
戊陽はただ無言で玲馨の体を抱き締めた。玲馨の肩に顔を埋めて、戊陽は泣き声を噛み殺している。それでも漏れてくる乱れた呼吸には誤魔化しきれない涙の気配があって、再び玲馨の頬にも同じものが零れていった。
しばらくの間、互いの熱を感じ呼吸を聞くだけの時間が続いた。やがて落ち着くと、戊陽がそっと肩を掴んで体を離す。
「ふっ……ははっ、酷い顔だ」
玲馨は戊陽のようには笑えなかった。
「俺は、死ぬんだと思っていた」
「私は」
玲馨が言い掛けると、戊陽が首を左右に振って言葉を遮る。
「俺は俺の事を言っている。俺はお前が死ぬと分かったら、俺も死ぬんだと思ったんだ」
大袈裟に言っているのではないのだと、戊陽の顔を見れば分かった。
「何もかもが全部どうでもよくなった。腹も減らなくなったんだ。それでも死ねなかったのは、最初のうちは刃物が全部ここから取り上げられたからだ。でもそのうち、運ばれてくる食事の皿を割ってでも凶器は作り出せると気付いた」
戊陽は訥々と語る。
「今日は居ないがいつもは知らぬ女が俺の給仕をしていた。毎日一切手をつけないのに女は必ず食事を運んでくる。それを断るのも億劫で暫く放っておいたが、その日は俺から食事を部屋に運んでほしいと頼んだ。それで気付かれたんだろうな。驚くほど勘の良い女だったよ。死ぬのに失敗して、後はもう餓死するのを待つくらいしか出来ないと思った時、蘇智望が黄麟宮に現れた」
玲馨の肩に置かれていた手に力が入るのが分かった。きっと無意識なのだろう。
「生きろと言ってきたんだ。信じられるか? 激昂して、俺は蘇智望を殺そうと掴みかかったが、食事を取っていない体はまるで言うことを聞いてくれなくて、簡単にあしらわれた。玲馨を死に追いやった男を殺す事さえ俺は出来ないんだ。この手は救いたい人を救えず、殺したい奴を殺せない」
玲馨から手を放し体を起こすと、戊陽は窓際に戻っていく。話しながらその時の感情がぶり返したのだろう、固い壁を拳で殴る。強い力ではなかった。溢れてくるものをどうにかいなすような、苦し気な拳が壁をもう一度鳴らす。
「情けなく床に倒れていた俺に、蘇智望はまず無理矢理水を飲ませた。咳き込むのも構わずに粥を流し込まれて、俺はそこで料理の味がしない事に気付くんだ。またか、と思った。お前にも話さなかったが、実は兄上が亡くなられた時も少しの間味が分からなくなっていた事がある。とうとう体まで生きる事を諦めたんだと思ったら、蘇智望はまた言うんだ『生きろ』と」
蘇智望が戊陽を生かそうとした理由を、玲馨は知っている。蘇智望は戊陽のために生きろと言ったのではない。ましてや玲馨のためなどあろうはずもない。蘇智望の想い人のためだ。
「あの男の俺を見る目には憎しみが込められていた。俺の顔を見たくないと心底から思っているくせに、時々ここへ現れては生きろの繰り返し。最初ほどではないにせよ、食事も無理矢理口に入れられた。そうして命を長らえて、刑が執行された当日だ。玲馨は生きていると教えられた。玲馨を身代わりにさせた元凶で、自分を恨んでいる男の言葉の何を信用出来るかと思ったのに、俺はその日情けないくらい泣いたんだ。食事も自ら食べた」
窓から差し込む陽光を背に振り返った戊陽の瞳は揺れていた。微かにきらめく黄金の虹彩が、玲馨を呼ぶ。
「俺の言いたい事が分かるか?」
分かってくれと切なる眼差しを向けられるほどに、彼の言葉を己に都合よく解釈しそうになる。どんなに必要とされようとも従者として主を裏切ったその報いは必ず受けなくてはならない、その覚悟を決めて蘇智望についていったのだ。
だから、だから──。
「玲馨」
呼ばれていた。視線で、声で、ここへ来いと呼ばれていた。
紐で引かれるように右、左と動き出した玲馨の足は戊陽に向かって進み、目の前に来たところで迎えるように両手を広げられる。結局、自分からその腕の中に飛び込む事は出来なくて、察した戊陽が困ったように笑って互いの間の距離を消した。
「お前と居たい」
背中に回された腕が、息が苦しくなるほどきつく締められる。
「頼む。玲馨に望んでほしいんだ。俺と同じように、共にありたいと」
ああ戊陽だ、という至極当たり前の事が過る。皇子とは結局どこまでも人の上に立つ者としての傲慢さを隠し切れないのだ。お前の嫌がる事はしないと言いながら、彼はいつだって彼自身の欲望を溢れさせていた。何でどうしてと戸惑う気持ちさえ掻き消されてしまうほど分かりやすく求められ続け、彼の気持ちを疑う隙などどこにも無かった。
今だって戊陽を疑うから迷うのではない。
「私も……私だって、ずっと」
立場、身分、性別。色々なものが戊陽との間には横たわっていた。どれだけ彼の事を愛しても決して自分だけのものにはならないと分かっていたから、自分は分を弁えられる理性的な人間だと言い聞かせ続けてきたのだ。
「玲馨」
「あなたに、どれだけ惹かれていた事か……」
玲馨が言い終わる前に性急に唇を重ねられ、歯と歯が小さくぶつかった。痛みはないが、戊陽にやめる気配はない。
互いに泣き過ぎて腫れぼったくなった唇は驚くほど熱くて、口付けの合間に漏れていく吐息も熱病に罹ったかのようだ。
「ん、ふぁ……っ」
小さく開いた唇の隙間から舌が入り込んでくると、己の舌を夢中で絡めた。
「……はぁ、駄目だ。ここでは、駄目だ。用意がない。刃物だけじゃなくて、何もかも取り上げられてしまったからな」
どちらともなく唇を離して開口一番、戊陽は心底残念そうに言うので、思わず玲馨が力なく笑う。と、戊陽は一度まじまじと玲馨の顔を見つめてから、ほっとしたように笑顔になるのだった。
*
「ちゃんと仲直り出来た?」
黄麟宮を出て門に戻るとくありと大きな欠伸をしながら風蘭が訊ねてくる。仲直りという表現をされると何とも言えない据わりの悪さを覚える。玲馨たちにとっては生きるか死ぬかが懸かっていたというのに、他人から見ればせいぜい子供の喧嘩くらいの事だったのだ。「まぁ」と視線が定まらぬまま玲馨が答えると、風蘭は「良かったじゃん」と言ってくれるのに対して梅はにやりと口角を吊り上げた。
「俺ぁもう少し出てくるのが遅くなるかと思ってたんすけどねぇ?」
「それならもう少し長く居たら良かったな。せっかく気を遣って早く出てきてやったというに。なぁ、玲馨」
「私に振らないで下さい」
現在、黄麟宮にはもう守衛は必要なくなるので門番をしていた関虎が一行を先導し、北門に向かって移動しているところだ。世間的には生きていてはいけない人間が混ざっている割にはやんやと喧しく会話を弾ませながら、ふと戊陽が「それでな」と切り出した。
「梅と玲馨は、その言葉遣いを改めてくれ。名は……まぁそのうち適当に考えるから、とりあえず今は『洋』と呼んでくれるか?」
玲馨と梅は思わず顔を見合わせる。
「じゃあ遠慮なく」
「私は、しばらく人前では癖が出てしまうかと」
「あ、オレは風蘭って呼んでくれよな! 洋兄さん!」
玲馨はさておき他二名は何の抵抗もなく態度を変えるので、戊陽は苦笑するしかない。
高い壁に囲まれた狭い隘路をずっと行くと、やがて汀彩城で最も小さい北門が見えてくる。門衛は案の定東江の兵が二名つけられており、事情を知る二人は無表情のまま四人が通るのを黙って見過ごした。
門を抜けたらいよいよ汀彩城、それから紫沈との別れである。最後に市井の様子を見ていけないのは、戊陽にとっては心残りだろう。だが、彼は思いの外すっきりとした面持ちで、城の威容を見上げた。
「戊陽」
「何だろうな。ずっと城の中に居たおかげで、改めて外から見たところでさほど思うところはないようだ」
そう言われてみれば玲馨も汀彩城の外観にはあまり馴染みがない。中には人の皮を被った悪鬼羅刹が跋扈する城も、外から見上げる景観は実に荘厳で嘘のように美しい。陽光を照り返す黄釉琉璃瓦は金に輝き皇帝の威光を示すかのようだ。
しばらく城を眺めていると、梅が「おい」とやや緊張ぎみに二人を呼んだ。声のした方を振り返って、玲馨を目を疑う。
「四郎」
戊陽が茫然としたように名前を呼ぶ。四郎と一緒に何故か于雨までもがついてきている事に気付きぎょっとする。
「于雨! お前……」
「玲馨先輩!!」
初めて聞く于雨の大きな声にたじろぐと、于雨が駆け寄ってくる。
「今日発たれると聞いて、私も最後にお話しをしたいとお願いしました」
最後に話したのは于雨がまだ療養の身だった頃だ。ちゃんと言葉を交わした日となると数ヶ月も前の事になる。これくらいの歳の頃の子供はたくさん見て来たが、成長が早く日ごとに様子が変わっていくものだ。于雨もまた背が伸びた上に、どことなく大人っぽい顔付きをするようになっていた。
「あの、私はまだあまり自分の力がよく分かっていないのですが、私の力はあわいを消すのにお役に立てるそうなのです」
「そうなのか? いや、地脈を操るのだものな」
「はい。けれど一度生まれたあわいをすっかり消してしまうには、長い時が必要なのだそうです。私はこの力を、良い事に使おうと思います」
「……そうか」
ふ、と玲馨が頬を緩めて于雨の頭を撫でると、于雨もまた嬉しそうに口元を綻ばせる。同室だった頃、こうして頭を撫でてやった事はあったろうか。あったとしても片手で足りるほどだった。もっときちんとこの子と向き合うべきだったと、于雨の笑顔を見て思う。
一方、四郎と相対した戊陽の表情は実にぎこちなく、四郎もまた固い空気を解すような芸当が出来る人ではない。
「四郎、お前は俺に恨みはないのか?」
「恨みですか。何故です?」
「お前の兄の仇のようなものだろう」
会話の内容も実に物騒なもので、後ろで聞いていた梅と風蘭が関わるまいと遠くに離れていく。
「寧ろあなたこそ私に恨みがあるのでは? 私はあなたが生まれた頃より間諜だったのですから」
二人の間に幻影の頑丈で巨大な壁が見えるようだ。于雨には是非とも清い心のまま育ってほしいので耳を塞ぐべきか悩んだ。
「はー……。やめておこう。お前の事は最後までよく分からないままだったが、それでも俺は四郎に助けられてきた。それなりに情もある」
「はい、私は、あなたの事を弟のように思っておりました」
「そう、弟……」
「弟!?」
思わず玲馨が反応すると、戊陽と四郎から同時に見つめられて小声で謝罪した。
「私の妹はちょうどあなたがお生まれになった年と同じくして生まれました。顔どころか話した事さえありませんが、自分の下に弟妹が居たらこういうものかと思って接しておりました」
玲馨も戊陽も絶句する。于雨でさえも驚きを隠しきれていなかった。
「そうか、それは、分からなかったなぁ」
四郎にその自覚は無いのだろう。どこかきょとんとしたような無垢な表情で戊陽の言葉を聞いていた。
最後の最後まで教本通りの拱手をする四郎と、宦官着がようやっと板についてきた于雨に見送られて紫沈を発つ。
先頭を行く梅と風蘭に対して、玲馨と戊陽の口数は少なかった。胸に去来する思いは複雑で、筆舌に尽くしがたい。
不安はある。それでも、隣を見た時そこに戊陽がいる。それは生まれも育ちも卑しい玲馨にとっては果報の身分であった。
*
東江の領都からは遠く外れた鄙びたその村は、まだ蘇氏が分家だった頃の領地だという。完全な自給自足の土地でよそ者は当然歓迎されない。蘇氏の屋敷に新たに人がやってくるという噂はたちまち広がり、玲馨たち一行を見る目はとてもよそよそしく冷たいものだった。
──が、「住人たちと仲を深めていくのはこれからの事だ。時間だけはあるのだから、ゆっくりと交流を進めれば良い」とは戊陽の言葉だ。いっときは自死の事で頭がいっぱいだったとは思えないほどの前向きさには驚かされる。
東江の領都で買い込んできた最低限の日用品を片付けて、埃だらけの新居を掃除するので丸一日が過ぎていった。翌日には監視役である東江の遣いがやってきたが、終始面倒そうに挨拶だけしていった。そして更に翌日には梅と風蘭が村を発った。二人はしばらくの間、東江を旅して回るという。名目は互いの護衛なのでおかしな話だが。
突然二人きりになった事で、屋敷の中が広く感じた。普通の人間が暮らすには大きいくらいの家だが、黄麟宮を筆頭に戊陽が住んできた殿舎を思い出すとここが豚小屋だと言われても信じるくらいだ。
「厨と居間と寝所が全部一繋ぎになっているのは不思議な感覚だな」
「慣れていかないといけませんね」
「お前もな」
「あ……」
どちらかと言わず戊陽に対しては丁寧な言葉の方が話しやすい上に「洋」という呼び方にもなかなか慣れられそうにない。
「洋も、まだどこかの貴族みたいな話し方をしているけどな」
「む……そうなのか?」
「梅のように……は私が嫌だから、ここの村の人間と話しながら覚えていくといいかも知れない」
「そうだな」
寒村の夜の静寂は、物音ひとつ立てただけで村中に伝わるのではないかと思うほどである。扉に隙間があるのか外から虫の鳴く声が聞こえてくるだけだ。
窓、と言っても穴を開けて木戸で蓋をしただけのそこにも同じように隙間があいていて、遅い食事を終えて一息ついていた二人の間に一筋の月明かりが差し込んでいた。
「玲馨、その……」
じ、と見つめてくる戊陽の顔は朧気にしか見えていない。けれど、その声音ともぞりと動く気配とで、何を言いたいかが分かってしまった。
「じ、準備するから、待ってほしい」
「俺がやる!」
「それは無理だ!」
暗闇でもむ、と唇をへの字に曲げているのが想像出来る。準備とは、単に体を洗って終わりではない。どんなに対等な立場になったからと言っても、あんな事を戊陽にさせる訳にはいかなかった。
「こ、こればかりは嫌です!」
「何故だ?」
「は、恥ずかしいからに決まってるでしょう!」
「……仕方ない。待っているから、早くしてくれ」
と、どうにかごねる戊陽を説得したまでは良かった。
ここは寒村の小さな屋敷である。厠は外で、城のように沐浴のための部屋がある訳でもない。考えに考えた末、戊陽を部屋の端っこに追いやって、玲馨はその反対側にある大きな水瓶に身を隠すようにして準備をする事にした。
実のところ、戊陽とこういった行為に及んだ数はさほど多くない。片手で足りる。それに、戊陽が即位してからはそんな雰囲気になる余裕などなかった。今年の春頃には戊陽が政務に慣れてきた事や宮廷での振る舞い方を覚えたおかげで心にもゆとりが出たようで、戊陽の方からそんな様な雰囲気を感じることがぽつぽつあったというだけだ。
それにしても数年ぶりの行為に体がついていくはずもない。自分の指で解して洗うだけでも、苦しさにふうと呼気が漏れていく。
「まだか?」
「わっ!?」
突然後ろから声を掛けられて、手巾を桶の中に取り落としてしまう。パシャンと水の跳ねる音の後、玲馨は「もう!」と戊陽を叱る。
「待ってて欲しいとあれだけ頼んだのに!」
しゃがみこみ、股の間から腕を通して尻を洗う姿など誰が見せたいものか。しかし間抜けな格好をしている玲馨の事など何も気にしていないようで、戊陽は後ろから玲馨の腕を取る。
「大体で構わない。俺が解すからな」
「何を言って、ちょっと、うわぁっ!!」
衣を半端に寛げた間抜けな格好のまま戊陽に腕を引っ張られ、そのまま強引に部屋の奥、寝床として使っている場所まで連れていかれる。寝台の上にそっと押されて尻もちをつくと、股を割りながら戊陽が伸し掛かってきた。
「も、焦りすぎです」
「俺がどれだけ待っていたと……。まぁいい。その体で全部感じてくれ」
「なん──んんっ」
覆いかぶさられて唇を押し当てられると逃げ場をなくしてただ受け入れるしかなくなる。
「ん、んぅっ、はぁ……ん、ふ……っ」
角度を変えて何度も何度も口付けられる間に戊陽の手は衣を脱がせにかかっていた。緩んだ帯は簡単に取り払われて、腿を晒されると肌が生温い外気に触れる。
戊陽の汗ばんだ手の平が腿を割り開き、躊躇いなく秘部へと触れた。
「っ!」
「痛むか?」
痛みはない。痛みはないが、やはり未だにそこを他人に触れるとどうしても体は身構えてしまうらしい。問題無い事を伝えて意識的に体の力を抜くようにする。
戊陽は指にたっぷりと香油を取り、それを後孔に塗り付けていく。香油なんてものが普通に売られているものなんだなと余所事をしているうちにまず一本差し込まれた。
中でぐにぐにと蠢く感触に「ああやっぱり」という思いが過る。しばらく使ってこなかった尻の感覚は以前より鈍くなっており、中で動いているという実感がそこにあるだけだ。
解す合間にしつこいくらいに繰り返される口付けは心地よい。呼吸が間に合わないくらい激しく貪られ、頭の奥が少しずつ朦朧としてくる。
絡められる舌に精一杯になっているうちに指が増えていた。玲馨自身に快感がある必要はない。そこが拡がりさえすれば戊陽の物を受け入れる事は出来るので、後孔に引き攣れたようなあの痛みが無いのは幸いだった。
戊陽は後ろをとても念入りに解した。三本が中でバラバラに動いても苦しさを感じないくらいになると、玲馨は「戊陽」と彼の真名を呼ぶ。
「駄目だ。もう少し我慢してくれ」
「ん……」
眉が下がりくったりと力の無い表情で頷く玲馨を、まるで子供をあやすようにして頬に唇が押し当てられる。ここまで戊陽に対して何もしてあげられていないのだが、玲馨が体を起こそうとしたり、手を伸ばそうとしたりすると「待て待て」と必ず止められた。
こうなるともう納得がいくまでやめる人ではないので、頃良く羞恥も消え始めていた玲馨は、己の体をすっかり戊陽に明け渡した。
しかし、それからしばらくのうちに玲馨は後悔する事になる。
指は三本。そこから増える気配は無いが、戊陽の前戯が終わる気配も無い。
「う、戊陽」
「うん、もう少し」
「でもっ……」
「うん」
もはや玲馨の言葉を聞いていない。
熱で溶けて液体のようになってしまった香油がぬち、と粘度のある音を立てる。執拗に弄られたそこはきっと真っ赤になっているに違いない。寝台に零れるほど惜しげなく香油を使われているので痛みは無いが、十分に拡がっても戊陽は指を抜こうとしない。
一体何故、と不安になり始めると、不意に戊陽の指がある場所を掠め、「んぁっ」と思わず鼻に掛かった甘い嬌声が抜けていった。
ぱっと顔を上げた戊陽がまた唇を合わせながら言う。「ひゃっほは」
「ん……っ、ふ、んんっ、あっ、あぁー……っ」
足の指が勝手にぎゅっと曲がって寝台を引っ掻いた。戊陽の指が同じ所を押したり捏ねたりするごとに、声が我慢出来なくなっていく。
眠っていた感覚が戊陽のしつこい前戯のおかげで呼び覚まされたのだ。
「あんっ、あ、声っ、が出るからぁっ」
寝入った村人たちのもとに自分の嬌声が響くかと思うととてつもなく恥ずかしいのに、段々とそうした事に意識が回らなくなっていく。
「安心した。前にあんなに善がってみせたのは演技だったのかと思ったぞ」
「違っあっ」
「うん、寂しい思いをさせたから、鈍ってしまっただけなんだな」
何だか妙に恥ずかしい言い回しをされた気がして下からじとっと睨みつけるも、後孔からせり上がってくる快感がすぐにその目をとろりと撓ませる。
気持ち的に余裕が出たのか、戊陽は変わらず下を弄りながら余った手で胸を撫で始める。そちらも同じく最初は反応を示さなかったのだが、捏ねて吸って噛んでとされているうちに、尻の感覚と結びつくようにして腹の奥を疼かせた。
「もっ……や、ぁっ、戊陽っ、戊陽っ」
まだ物を入れられた訳でもないのにやりどころの無い性感の波に、イヤイヤと玲馨は頭を振り乱す。喘ぎにも泣きが混じり始めた。乱れる玲馨を見下ろして、戊陽は至極満足そうな笑みを湛える。
「腰が揺れているぞ玲馨」
「だって、あんっ、ぅ……っ、んんっ」
気持ち良い、気持ち良い──。頭がいっぱいになるのに戊陽は決して玲馨が極めてしまわないように加減をしていた。せめて出すものがあれば勝手に解放されたろうに、後ろで達するしか出来ない事がこんなにも焦れったく感じたのは初めての事だ。
半ば泣きじゃくるようにして戊陽を呼び続けると、やっと気が済んだのかぬるりと指が引き抜かれていく。半端に弄ばれた熱はしっかりと腹奥で熾火のように燻り、玲馨の意識とは関係なく後孔がひくひくと開閉する。
気が遠くなるほど長い前戯だったにも関わらず戊陽の陰茎はぴんと天井を向いていた。ぶるんと震えるほど屹立したそれは、記憶の中より些か増している。縦も、横も。前戯に時間を掛けた理由が分かると同時、玲馨の喉が鳴った。
──期待、しているのか。あれを突き入れてほしいと、私が……?
性行為を自ら求めた事など未だ嘗てなかった玲馨は、自分の体の変化が信じられない。いや、変わったのは心かも知れない。
ともあれ硬く太く、そしてきっと熱いだろうそれから視線を外す事は出来なくて、自ら微かに腰を持ち上げた。
ふ──と小さく笑ったような呼吸の音がしたかと思うやいなや、ずんっ、と質量が穿たれる。
「──うっ、ふぅぅっ、は、おっ、きい……っ」
「くぅっ、煽るな、玲馨」
恐ろしい事にがちがちに勃起を保ち続けながら戊陽が根気強く柔らかくしたそこは、香油のぬめりを借りてもみちみちと孔をめいっぱい塞いでいく。腹の中の空気が押し上がってくるような圧迫感。しかし玲馨の体は何もかもをすっかり忘れた訳ではなかった。玲馨は上手に力を抜きつつ戊陽の陰茎を奥へ奥へと誘っていく。戊陽の表情に一瞬複雑なものが過ぎった気がしたが、慎重に腰を進める事に集中する。
ごわごわとした下生えの感触が尻に当たると、玲馨はたまらず息を吐き出した。
まるで一仕事終えたかのような充足感がある。動かなくても繋がっているだけで心が満ちているのがよく分かった。
「玲馨」
顔の横に投げ出されていた玲馨の手を、戊陽が杭を打つように寝台に縫い付ける。その手をしっかりと握り返すと、戊陽が幸せそうに目を細めるのだ。
「好きだ」
気持ちが溢れて声に出てしまう。自分でびっくりして、じわじわ照れがのぼってきて、目を逸らそうとしたが戊陽の顔が降りてきて接吻で阻止される。それからすぐに顔を上げると、そこには甘く溶けた中にも切なるものが混じった戊陽の表情があった。
「愛している」
戊陽のあたたかで、感情が直に伝わるような声音に鼻の奥にツンとした痛みが走る。今泣いてしまうのは違うだろうと思った。けれど堪え切れなかった一筋が頬を伝って耳元に落ちていった。
「ああっ、ンッ、んっ、んぅッ」
始めは気遣うようだった動きも、玲馨の顔付きが誤魔化せないほど淫らに蕩ければ、戊陽は律動を速めていった。
先端の括れは出し入れするたび腹側のしこりを引っ掻いて、奥まで突き上げられると腹の奥がひくひくと蠢く。未だ両手はしっかりと戊陽に押さえつけられているので、普段の凛とした姿からは想像も及ばないような玲馨のあられもない声が闇夜に響き渡った。
「だ、めっ、もぅっ、くる……っ」
「ああ、いいぞ。好きなだけ、達してくれ」
「──っひぁぁっ、やぁっ、ああっ!」
玲馨の訴えに、戊陽の突き上げの角度が変わる。腹の中で生まれた泣きたくなるような快感に、戊陽の手をぐっと握り締めて果てた。
閉じた瞼の奥で何か白いものがチカっと瞬き、はぁはぁと荒い息が止まらない。余韻にまで小さく鳴いていた玲馨だったが、しかしすぐにまた戊陽の動きが再開されて目を見開いた。
「待って、い、今はまだ」
「待てないと、何度、言ったら分かるん、だっ」
「ああっ、なん……っ、う、やんっ」
少し落ちつくまで待ってほしいと必死に目で訴えても戊陽は止まらない。達した余韻にひくひくと痙攣する中を、未だ一度も果てていない肉の塊が容赦なく擦りあげ、玲馨は背を弓なり反らせて喘いだ。
戊陽が手を放したかと思うとその手は玲馨の胸に伸び、ぷっくりと存在を主張する乳首を土を捏ねるようにして指の腹で刺激してくる。既に嘗ての性感は取り戻された。乳首の刺激にも玲馨は悩ましげに眉を潜めて胸を跳ねさせる。
「ふ……本当にっ、愛らしいな」
美しい、可愛らしい、そんな美辞麗句は聞き飽きたはずなのに、真っ直ぐに降りてくる戊陽の心底愛しげな眼差しの前には玲馨の頬もかあっと上気していく。尻は無自覚に孔を締め付けて、戊陽が苦しげに眉根を寄せた。
「玲馨、善いか?」
そんな事、顔を見れば一目瞭然だというのに。今の戊陽はとても意地の悪い顔をしている。答えずにいるとわざと律動を緩めて「玲馨」と急かしてくるので、ふいっとそっぽを向いて「善くないはず、ない」と言うと、満足げな笑い声の後に耳元に口付けされる。
「ひっ、ん」
ちゅっ、と水音が耳の間近でする感覚に玲馨が首を竦めると、それを見逃さなかった戊陽が耳たぶを食み、わざとちゅうちゅうと音を立てるように耳をしゃぶってくる。そんな所を責め立てられるのは初めてで、くすぐったいような気持ち良いような奇妙な感覚に玲馨は「あっあっ」と素直に声を上げた。
「も、しつこっ、い」
「じゃあやはり、こちらが好きか?」
訊ねながら戊陽の唇が首筋から鎖骨を通って胸の飾りに触れる。柔らかな唇で吸い付きながら尖端を舌で擦られると甘く痺れるような感覚が背骨を走り抜けていく。
律動そのものは緩くなっているが、戊陽の硬さは失われていない。下から上に向かってゆっくり、玲馨の善い所を圧迫するように押し付けてくる。先程までの激しい突き上げと打って変わってじわじわと追い詰められていくような感覚に、同調するように玲馨の腰も揺れた。
「……このまま、ずっと繋がっていたいくらいだ」
そんな事されては玲馨の尻が壊れてしまうと一瞬真剣に考えたが、そういう意味ではないと分かって「私も」と答えた。
「けど、そろそろ、俺も限界だ」
「出して、戊陽」
ぐ、と尻に力を入れて戊陽の陰茎を締め付けると、戊陽はたまらないような息を吐き出す。そのまま少しずつ速度が上がり始めれば、再び玲馨にも込み上がってくるものがあった。
戊陽のものがいっそう腹の中で硬くなり、間もなく射精するという時戊陽は玲馨を力いっぱい抱き締めた。加減なく潰されるような苦しさに、得も言われぬ幸福を感じながら、玲馨も二度目の絶頂を迎えるのだった。
行為の後はもう指先一つ動かせないと思うほど疲労を感じていたが、どうしても香油のぬめり気が気になって、戊陽の手を借りて身を清めた。他人から世話をされても、他人の世話などした事のない戊陽の手付きは実にぎこちなく、「必ず上達するから」と神妙に言うので笑ってしまった。
暮らし始めてまだ三日の家の中、暗闇を手探りで進むと、玲馨の先を歩いていた戊陽の足元からカコンという軽くて固い音が響いてくる。
「何か指に当たったな」
戊陽が拾い上げるとそれは玲馨の荷を入れていた袋だった。麻で織った目の粗い袋に残っていた物は箱だ。舶来の品で、黒光りのする艶々とした表面に螺鈿の飾りと、金の文様が蒔いてある。于雨に手紙を渡すのに使った鍵付きの箱であり、戊陽からの勅命を記した紙を保管し、そして返事を書けなかった戊陽からの手紙を後生大事に取っておいた思い出深い品だ。そも、この箱自体、戊陽から贈られた物である。
「踏んでしまうような所に置いて申しわけ、ご、ごめん、戊陽」
「……これ、ここまで持ってきてくれたんだな」
「それは、私にとって大事な物だから」
「そうか……」
この箱をくれた事を覚えていてくれたのかと思うと温かく、そして懐かしい気持ちになる。
しばし蓋を眺めていた戊陽は表面を手で撫でてから「開けていいか?」と訊ねてくるのでうんと答えた。
「紙ばっかりだな」
「全部あなたから貰った物だけど」
「俺?」
首を傾げながら窓に寄っていくと、木戸をずらして月明かりに中身を照らしてみる。
「これは勅命の……」
勅命の証である印璽だけが押された白紙を持ち上げて戊陽は笑う。その寂しげな横顔は玲馨の胸を刺した。その痛みは生涯玲馨が抱え続けていかなくてはならないものだ。痛むけれど、そのおかげで今があると思えば苦ではない。
「皮肉だな。最早この紙には何の力もなくなった」
「そうでもない。私にとっては、軽くて……何より重たい物だった」
于雨への手紙を隠すのに箱を使った時、白紙の紙のやりどころに困った玲馨はそれを懐に忍ばせて東江への旅路についた。戊陽からの手紙も同様に持ち歩いていたのだ。あの時はまさか最後はこれを手にして死ぬのだとは思わなかったし、助かる事も想像していなかった。
白紙の下から昔に自分で書いた手紙を見つけると、戊陽は手で顔を覆って嘆息する。
「いや嬉しいんだ。お前がこれを取っておいてくれた事は、箱の事も含めてな。だが、いかんせん昔の俺の詩作があまりに拙すぎる」
正直今もさほど変わらないどころか詩など数年単位で触れていないのでその才は昔より衰えているかもしれない、とは彼の矜持のために言わずに黙っておく。
手紙の方は再び綺麗に畳んで箱にしまうと、白紙の方を月光に透かしながら戊陽は思案する。
「何か気になる事でも?」
「これをこのまま捨ててしまうのは惜しいような気がしてな」
或いは玉座への未練があるのかと思ったがそんな様子ではない。いや、表に出さないだけで、皇帝への未練は完全に捨てきれてはいないだろう。彼は彼なりにやれる事を必死にこなしてきたのだから、何もかもを成し遂げられずに紫沈を離れるのは心残りだったはずだ。
玲馨は戊陽の隣に立ち白紙を覗き込む。
白紙。そう、今二人の人生は白紙になったも同然だ。皇帝は死に、その影武者として一人の宦官が死んだ。
「お互いへの命令でも書きましょうか?」
「命令?」
「そう、もう二度と裏切らない、とか」
冗談のつもりだったが「自罰的なのは良くない」と叱られてしまう。
「だったら誓いを書こう。生涯守り抜く誓いだ。別に破ったって良い。その時はまた新たな誓いを立てるのだ」
「それでは誓いとは言わないような」
「良いんだ、何でも。ただし絶対に諦めない。間違っても失敗しても必ず二人で考えるんだ、どうすれば上手くいくのか。俺もお前も一人で考え込むとよくない事を招く事が分かったからな」
仕方ないような慈しむような戊陽の笑みがどうしようもなく柔らかく、玲馨の目に涙が滲み視線がさまよった。すると戊陽は面白がって覗き込もうとするので肩を押しやって逃げる。
「さて一体何に誓ったものか。印璽もある事だし皇帝か? いや黄龍でもいいな」
「やはりお互いというのは? 私はあなたに、あなたは私に」
目の端を拭って振り返ると呆けたような顔があり、すぐにおかしくてたまらないと笑い出す。
「は、ははっ、いいな。いい! 自由な考え方で、俺は好きだ。よし誓おう、俺は玲馨に誓う」
「ええ私も……ところで、何を?」
「ん? んー……色々だなぁ。嘘を吐かない、一人にしない、寂しくさせない、夜はいっぱい愛する」
「では、私も同じものを、同じだけ。あなたに誓います」
あなたが嘗て与えてくれた自由な心で、生涯あなただけを愛すると。
私はもう、あわいの宦官ではないのだから。
終幕
もはや二度と見る事は叶わないと思っていた。優に十年は過ごしたはずの慣れ親しんだ汀彩城の風景を見渡して、今度こそ最後の別れを胸の裡で告げる。それから後宮の最奥へと歩を進める。
黄麟宮──。それは沈の皇帝が住まう宮殿。紫沈を守護する黄金の龍から名をとったその場所は、この国の持てる最高の技で造り上げた格別の居所である。宮女も宦官もここに仕える事は至高であり、生え抜きの者だけが皇帝を世話する役目を仰せつかる事が叶う。
しかし現在、この宮殿はもぬけの殻である。同様に後宮からも全ての人が去っていた。
先日ここ紫沈は、戦禍に見舞われた。建物は壊され民にも死者が出て、お膳立てなどなくとも皇帝の信頼は地に落ちていった。
およそ十日に及んだ戦乱は、皇帝の死を以て決着となる。そうして主のいなくなった黄麟宮からは、宮女も宦官も全てが追い出されて無人となったのだった。
無人となった後、東江の大男、関虎が一人で黄麟宮へと続く門を守るようになった。それが蘇智望の命である事も、その目的も訊ねずとも理解出来た。
門を通る時、互いに短く礼をするだけで言葉は交わさない。今日、ここ黄麟宮へ人が来る事は、彼の耳にも伝わっていたようだ。
庭の景色に荒んだ様子はなかった。無人になっても人の手は入っているようで、池の水面は透き通り、短く刈られた下草は歩行の邪魔にはならない。
扉を開ける時にわざわざ中へ声を掛ける必要も最早ない。重い扉を無言で開けば、人が消えた寂しげな広間が出迎える。皇帝は仕事をする時ここを執務室として使い、奥の間は寝所とした。
黄麟宮にはさほど振り返りたい思い出はない。それどころか辛く苦しい過去ばかりが蘇る。
黄昌の死から始まった過酷な日々は、日常にあった大切な何かを一息に壊していった。壊れたものを拾い集めて繋ぎ合わせ、どうにか体裁だけでも取り戻したように見えて、どこまでも昔とは違ってしまった。後宮を無邪気に駆け回っていたあの頃の姿は、もうきっと取り返せはしなかったのだ。
梅と風蘭の二人は門の外に残してきた。先程まで姦しかった彼らの声から離れると、静寂に耳が痛むようだ。
執務用の机の脇には使い込んだ香炉がそのままになっていた。近くを通るとほんの僅かに香の残り香が嗅覚を刺激する。
桃の淡い匂い──。それを知覚した瞬間に、ふっ、と息が漏れていった。
コツ、コツ、と自分の足音だけが響く違和感に慣れ始めた頃、寝所が視界に入る。二年の間に何度となく通った部屋の窓際に、人影があった。皇帝が死に、侍従たちが追い出された黄麟宮は、隠すのにはうってつけだったとそういう事だ。世話する者のない宮殿でひっそりと隠され過ごしてきた姿に、最早皇帝らしい威光はない。長い髪は無造作に下ろされ、衣は着るのが楽な簡素なもの。それから、記憶より少し痩せていた。
「戊陽」
思いの外掠れた声が出て、初めて喉がからからに乾いている事に気付く。
窓の外を眺めていた人影──戊陽は、振り返るなりあんぐりと口を開けてまるで幽霊でも見ているような顔をした。
「……玲馨」
戊陽は何もないところで躓きそうになりながらふらふらと近付いてくる。漸く互いが手を伸ばせば届く所までくると、玲馨はその距離を詰めさせないために右手に抱えていた物を突き出した。
「それは……何のつもりだ、玲馨」
右手に持った物。それは剣だ。
玲馨は剣を持ち替えて両手で戊陽に柄の方を向けて差し出す。その場に跪き、首を見せるようにして頭を垂れた。
「りんし──」
「私はあなたの思いを踏みにじった」
牢の中で枯れるほど泣いたはずなのに、じわりと熱くなった眦からぼとぼとと涙が溢れてくる。
「私は、私のためだけにあなたを裏切った」
抑えようとしても声は震え、喉が熱くてたまらなくなる。同情を買うようで嫌だと思うのに、思えば思うほどに視界は滲んでいった。
「どうか、あなたの手で殺してください」
それ以上言葉は必要ないだろう。
玲馨が握っていた剣が、戊陽によって引き抜かれる。鞘から抜けていく擦れる音を聞きながらぎゅっと目を瞑り、静かにその時を待った。
カラン、カラン……、と余韻を残しながら何か硬い物が床を滑って遠ざかっていく。視界の端に音の正体を捉えて玲馨はたまらず顔を上げた。
「なぜっ」
「歯を食い縛れ」
言うが早いかバチンという音が左から鳴って視界が大きく左右に揺さぶられた。遅れて頬を張られたのだと気付く。
死を覚悟したこんな時にでさえ大人の男に強い力で暴力を振るわれるという状況に、言葉にならない恐怖が襲いくる。しかし、戊陽の顔に涙の筋を見つけると、嘘のように恐怖は消えていった。
戊陽はただ無言で玲馨の体を抱き締めた。玲馨の肩に顔を埋めて、戊陽は泣き声を噛み殺している。それでも漏れてくる乱れた呼吸には誤魔化しきれない涙の気配があって、再び玲馨の頬にも同じものが零れていった。
しばらくの間、互いの熱を感じ呼吸を聞くだけの時間が続いた。やがて落ち着くと、戊陽がそっと肩を掴んで体を離す。
「ふっ……ははっ、酷い顔だ」
玲馨は戊陽のようには笑えなかった。
「俺は、死ぬんだと思っていた」
「私は」
玲馨が言い掛けると、戊陽が首を左右に振って言葉を遮る。
「俺は俺の事を言っている。俺はお前が死ぬと分かったら、俺も死ぬんだと思ったんだ」
大袈裟に言っているのではないのだと、戊陽の顔を見れば分かった。
「何もかもが全部どうでもよくなった。腹も減らなくなったんだ。それでも死ねなかったのは、最初のうちは刃物が全部ここから取り上げられたからだ。でもそのうち、運ばれてくる食事の皿を割ってでも凶器は作り出せると気付いた」
戊陽は訥々と語る。
「今日は居ないがいつもは知らぬ女が俺の給仕をしていた。毎日一切手をつけないのに女は必ず食事を運んでくる。それを断るのも億劫で暫く放っておいたが、その日は俺から食事を部屋に運んでほしいと頼んだ。それで気付かれたんだろうな。驚くほど勘の良い女だったよ。死ぬのに失敗して、後はもう餓死するのを待つくらいしか出来ないと思った時、蘇智望が黄麟宮に現れた」
玲馨の肩に置かれていた手に力が入るのが分かった。きっと無意識なのだろう。
「生きろと言ってきたんだ。信じられるか? 激昂して、俺は蘇智望を殺そうと掴みかかったが、食事を取っていない体はまるで言うことを聞いてくれなくて、簡単にあしらわれた。玲馨を死に追いやった男を殺す事さえ俺は出来ないんだ。この手は救いたい人を救えず、殺したい奴を殺せない」
玲馨から手を放し体を起こすと、戊陽は窓際に戻っていく。話しながらその時の感情がぶり返したのだろう、固い壁を拳で殴る。強い力ではなかった。溢れてくるものをどうにかいなすような、苦し気な拳が壁をもう一度鳴らす。
「情けなく床に倒れていた俺に、蘇智望はまず無理矢理水を飲ませた。咳き込むのも構わずに粥を流し込まれて、俺はそこで料理の味がしない事に気付くんだ。またか、と思った。お前にも話さなかったが、実は兄上が亡くなられた時も少しの間味が分からなくなっていた事がある。とうとう体まで生きる事を諦めたんだと思ったら、蘇智望はまた言うんだ『生きろ』と」
蘇智望が戊陽を生かそうとした理由を、玲馨は知っている。蘇智望は戊陽のために生きろと言ったのではない。ましてや玲馨のためなどあろうはずもない。蘇智望の想い人のためだ。
「あの男の俺を見る目には憎しみが込められていた。俺の顔を見たくないと心底から思っているくせに、時々ここへ現れては生きろの繰り返し。最初ほどではないにせよ、食事も無理矢理口に入れられた。そうして命を長らえて、刑が執行された当日だ。玲馨は生きていると教えられた。玲馨を身代わりにさせた元凶で、自分を恨んでいる男の言葉の何を信用出来るかと思ったのに、俺はその日情けないくらい泣いたんだ。食事も自ら食べた」
窓から差し込む陽光を背に振り返った戊陽の瞳は揺れていた。微かにきらめく黄金の虹彩が、玲馨を呼ぶ。
「俺の言いたい事が分かるか?」
分かってくれと切なる眼差しを向けられるほどに、彼の言葉を己に都合よく解釈しそうになる。どんなに必要とされようとも従者として主を裏切ったその報いは必ず受けなくてはならない、その覚悟を決めて蘇智望についていったのだ。
だから、だから──。
「玲馨」
呼ばれていた。視線で、声で、ここへ来いと呼ばれていた。
紐で引かれるように右、左と動き出した玲馨の足は戊陽に向かって進み、目の前に来たところで迎えるように両手を広げられる。結局、自分からその腕の中に飛び込む事は出来なくて、察した戊陽が困ったように笑って互いの間の距離を消した。
「お前と居たい」
背中に回された腕が、息が苦しくなるほどきつく締められる。
「頼む。玲馨に望んでほしいんだ。俺と同じように、共にありたいと」
ああ戊陽だ、という至極当たり前の事が過る。皇子とは結局どこまでも人の上に立つ者としての傲慢さを隠し切れないのだ。お前の嫌がる事はしないと言いながら、彼はいつだって彼自身の欲望を溢れさせていた。何でどうしてと戸惑う気持ちさえ掻き消されてしまうほど分かりやすく求められ続け、彼の気持ちを疑う隙などどこにも無かった。
今だって戊陽を疑うから迷うのではない。
「私も……私だって、ずっと」
立場、身分、性別。色々なものが戊陽との間には横たわっていた。どれだけ彼の事を愛しても決して自分だけのものにはならないと分かっていたから、自分は分を弁えられる理性的な人間だと言い聞かせ続けてきたのだ。
「玲馨」
「あなたに、どれだけ惹かれていた事か……」
玲馨が言い終わる前に性急に唇を重ねられ、歯と歯が小さくぶつかった。痛みはないが、戊陽にやめる気配はない。
互いに泣き過ぎて腫れぼったくなった唇は驚くほど熱くて、口付けの合間に漏れていく吐息も熱病に罹ったかのようだ。
「ん、ふぁ……っ」
小さく開いた唇の隙間から舌が入り込んでくると、己の舌を夢中で絡めた。
「……はぁ、駄目だ。ここでは、駄目だ。用意がない。刃物だけじゃなくて、何もかも取り上げられてしまったからな」
どちらともなく唇を離して開口一番、戊陽は心底残念そうに言うので、思わず玲馨が力なく笑う。と、戊陽は一度まじまじと玲馨の顔を見つめてから、ほっとしたように笑顔になるのだった。
*
「ちゃんと仲直り出来た?」
黄麟宮を出て門に戻るとくありと大きな欠伸をしながら風蘭が訊ねてくる。仲直りという表現をされると何とも言えない据わりの悪さを覚える。玲馨たちにとっては生きるか死ぬかが懸かっていたというのに、他人から見ればせいぜい子供の喧嘩くらいの事だったのだ。「まぁ」と視線が定まらぬまま玲馨が答えると、風蘭は「良かったじゃん」と言ってくれるのに対して梅はにやりと口角を吊り上げた。
「俺ぁもう少し出てくるのが遅くなるかと思ってたんすけどねぇ?」
「それならもう少し長く居たら良かったな。せっかく気を遣って早く出てきてやったというに。なぁ、玲馨」
「私に振らないで下さい」
現在、黄麟宮にはもう守衛は必要なくなるので門番をしていた関虎が一行を先導し、北門に向かって移動しているところだ。世間的には生きていてはいけない人間が混ざっている割にはやんやと喧しく会話を弾ませながら、ふと戊陽が「それでな」と切り出した。
「梅と玲馨は、その言葉遣いを改めてくれ。名は……まぁそのうち適当に考えるから、とりあえず今は『洋』と呼んでくれるか?」
玲馨と梅は思わず顔を見合わせる。
「じゃあ遠慮なく」
「私は、しばらく人前では癖が出てしまうかと」
「あ、オレは風蘭って呼んでくれよな! 洋兄さん!」
玲馨はさておき他二名は何の抵抗もなく態度を変えるので、戊陽は苦笑するしかない。
高い壁に囲まれた狭い隘路をずっと行くと、やがて汀彩城で最も小さい北門が見えてくる。門衛は案の定東江の兵が二名つけられており、事情を知る二人は無表情のまま四人が通るのを黙って見過ごした。
門を抜けたらいよいよ汀彩城、それから紫沈との別れである。最後に市井の様子を見ていけないのは、戊陽にとっては心残りだろう。だが、彼は思いの外すっきりとした面持ちで、城の威容を見上げた。
「戊陽」
「何だろうな。ずっと城の中に居たおかげで、改めて外から見たところでさほど思うところはないようだ」
そう言われてみれば玲馨も汀彩城の外観にはあまり馴染みがない。中には人の皮を被った悪鬼羅刹が跋扈する城も、外から見上げる景観は実に荘厳で嘘のように美しい。陽光を照り返す黄釉琉璃瓦は金に輝き皇帝の威光を示すかのようだ。
しばらく城を眺めていると、梅が「おい」とやや緊張ぎみに二人を呼んだ。声のした方を振り返って、玲馨を目を疑う。
「四郎」
戊陽が茫然としたように名前を呼ぶ。四郎と一緒に何故か于雨までもがついてきている事に気付きぎょっとする。
「于雨! お前……」
「玲馨先輩!!」
初めて聞く于雨の大きな声にたじろぐと、于雨が駆け寄ってくる。
「今日発たれると聞いて、私も最後にお話しをしたいとお願いしました」
最後に話したのは于雨がまだ療養の身だった頃だ。ちゃんと言葉を交わした日となると数ヶ月も前の事になる。これくらいの歳の頃の子供はたくさん見て来たが、成長が早く日ごとに様子が変わっていくものだ。于雨もまた背が伸びた上に、どことなく大人っぽい顔付きをするようになっていた。
「あの、私はまだあまり自分の力がよく分かっていないのですが、私の力はあわいを消すのにお役に立てるそうなのです」
「そうなのか? いや、地脈を操るのだものな」
「はい。けれど一度生まれたあわいをすっかり消してしまうには、長い時が必要なのだそうです。私はこの力を、良い事に使おうと思います」
「……そうか」
ふ、と玲馨が頬を緩めて于雨の頭を撫でると、于雨もまた嬉しそうに口元を綻ばせる。同室だった頃、こうして頭を撫でてやった事はあったろうか。あったとしても片手で足りるほどだった。もっときちんとこの子と向き合うべきだったと、于雨の笑顔を見て思う。
一方、四郎と相対した戊陽の表情は実にぎこちなく、四郎もまた固い空気を解すような芸当が出来る人ではない。
「四郎、お前は俺に恨みはないのか?」
「恨みですか。何故です?」
「お前の兄の仇のようなものだろう」
会話の内容も実に物騒なもので、後ろで聞いていた梅と風蘭が関わるまいと遠くに離れていく。
「寧ろあなたこそ私に恨みがあるのでは? 私はあなたが生まれた頃より間諜だったのですから」
二人の間に幻影の頑丈で巨大な壁が見えるようだ。于雨には是非とも清い心のまま育ってほしいので耳を塞ぐべきか悩んだ。
「はー……。やめておこう。お前の事は最後までよく分からないままだったが、それでも俺は四郎に助けられてきた。それなりに情もある」
「はい、私は、あなたの事を弟のように思っておりました」
「そう、弟……」
「弟!?」
思わず玲馨が反応すると、戊陽と四郎から同時に見つめられて小声で謝罪した。
「私の妹はちょうどあなたがお生まれになった年と同じくして生まれました。顔どころか話した事さえありませんが、自分の下に弟妹が居たらこういうものかと思って接しておりました」
玲馨も戊陽も絶句する。于雨でさえも驚きを隠しきれていなかった。
「そうか、それは、分からなかったなぁ」
四郎にその自覚は無いのだろう。どこかきょとんとしたような無垢な表情で戊陽の言葉を聞いていた。
最後の最後まで教本通りの拱手をする四郎と、宦官着がようやっと板についてきた于雨に見送られて紫沈を発つ。
先頭を行く梅と風蘭に対して、玲馨と戊陽の口数は少なかった。胸に去来する思いは複雑で、筆舌に尽くしがたい。
不安はある。それでも、隣を見た時そこに戊陽がいる。それは生まれも育ちも卑しい玲馨にとっては果報の身分であった。
*
東江の領都からは遠く外れた鄙びたその村は、まだ蘇氏が分家だった頃の領地だという。完全な自給自足の土地でよそ者は当然歓迎されない。蘇氏の屋敷に新たに人がやってくるという噂はたちまち広がり、玲馨たち一行を見る目はとてもよそよそしく冷たいものだった。
──が、「住人たちと仲を深めていくのはこれからの事だ。時間だけはあるのだから、ゆっくりと交流を進めれば良い」とは戊陽の言葉だ。いっときは自死の事で頭がいっぱいだったとは思えないほどの前向きさには驚かされる。
東江の領都で買い込んできた最低限の日用品を片付けて、埃だらけの新居を掃除するので丸一日が過ぎていった。翌日には監視役である東江の遣いがやってきたが、終始面倒そうに挨拶だけしていった。そして更に翌日には梅と風蘭が村を発った。二人はしばらくの間、東江を旅して回るという。名目は互いの護衛なのでおかしな話だが。
突然二人きりになった事で、屋敷の中が広く感じた。普通の人間が暮らすには大きいくらいの家だが、黄麟宮を筆頭に戊陽が住んできた殿舎を思い出すとここが豚小屋だと言われても信じるくらいだ。
「厨と居間と寝所が全部一繋ぎになっているのは不思議な感覚だな」
「慣れていかないといけませんね」
「お前もな」
「あ……」
どちらかと言わず戊陽に対しては丁寧な言葉の方が話しやすい上に「洋」という呼び方にもなかなか慣れられそうにない。
「洋も、まだどこかの貴族みたいな話し方をしているけどな」
「む……そうなのか?」
「梅のように……は私が嫌だから、ここの村の人間と話しながら覚えていくといいかも知れない」
「そうだな」
寒村の夜の静寂は、物音ひとつ立てただけで村中に伝わるのではないかと思うほどである。扉に隙間があるのか外から虫の鳴く声が聞こえてくるだけだ。
窓、と言っても穴を開けて木戸で蓋をしただけのそこにも同じように隙間があいていて、遅い食事を終えて一息ついていた二人の間に一筋の月明かりが差し込んでいた。
「玲馨、その……」
じ、と見つめてくる戊陽の顔は朧気にしか見えていない。けれど、その声音ともぞりと動く気配とで、何を言いたいかが分かってしまった。
「じ、準備するから、待ってほしい」
「俺がやる!」
「それは無理だ!」
暗闇でもむ、と唇をへの字に曲げているのが想像出来る。準備とは、単に体を洗って終わりではない。どんなに対等な立場になったからと言っても、あんな事を戊陽にさせる訳にはいかなかった。
「こ、こればかりは嫌です!」
「何故だ?」
「は、恥ずかしいからに決まってるでしょう!」
「……仕方ない。待っているから、早くしてくれ」
と、どうにかごねる戊陽を説得したまでは良かった。
ここは寒村の小さな屋敷である。厠は外で、城のように沐浴のための部屋がある訳でもない。考えに考えた末、戊陽を部屋の端っこに追いやって、玲馨はその反対側にある大きな水瓶に身を隠すようにして準備をする事にした。
実のところ、戊陽とこういった行為に及んだ数はさほど多くない。片手で足りる。それに、戊陽が即位してからはそんな雰囲気になる余裕などなかった。今年の春頃には戊陽が政務に慣れてきた事や宮廷での振る舞い方を覚えたおかげで心にもゆとりが出たようで、戊陽の方からそんな様な雰囲気を感じることがぽつぽつあったというだけだ。
それにしても数年ぶりの行為に体がついていくはずもない。自分の指で解して洗うだけでも、苦しさにふうと呼気が漏れていく。
「まだか?」
「わっ!?」
突然後ろから声を掛けられて、手巾を桶の中に取り落としてしまう。パシャンと水の跳ねる音の後、玲馨は「もう!」と戊陽を叱る。
「待ってて欲しいとあれだけ頼んだのに!」
しゃがみこみ、股の間から腕を通して尻を洗う姿など誰が見せたいものか。しかし間抜けな格好をしている玲馨の事など何も気にしていないようで、戊陽は後ろから玲馨の腕を取る。
「大体で構わない。俺が解すからな」
「何を言って、ちょっと、うわぁっ!!」
衣を半端に寛げた間抜けな格好のまま戊陽に腕を引っ張られ、そのまま強引に部屋の奥、寝床として使っている場所まで連れていかれる。寝台の上にそっと押されて尻もちをつくと、股を割りながら戊陽が伸し掛かってきた。
「も、焦りすぎです」
「俺がどれだけ待っていたと……。まぁいい。その体で全部感じてくれ」
「なん──んんっ」
覆いかぶさられて唇を押し当てられると逃げ場をなくしてただ受け入れるしかなくなる。
「ん、んぅっ、はぁ……ん、ふ……っ」
角度を変えて何度も何度も口付けられる間に戊陽の手は衣を脱がせにかかっていた。緩んだ帯は簡単に取り払われて、腿を晒されると肌が生温い外気に触れる。
戊陽の汗ばんだ手の平が腿を割り開き、躊躇いなく秘部へと触れた。
「っ!」
「痛むか?」
痛みはない。痛みはないが、やはり未だにそこを他人に触れるとどうしても体は身構えてしまうらしい。問題無い事を伝えて意識的に体の力を抜くようにする。
戊陽は指にたっぷりと香油を取り、それを後孔に塗り付けていく。香油なんてものが普通に売られているものなんだなと余所事をしているうちにまず一本差し込まれた。
中でぐにぐにと蠢く感触に「ああやっぱり」という思いが過る。しばらく使ってこなかった尻の感覚は以前より鈍くなっており、中で動いているという実感がそこにあるだけだ。
解す合間にしつこいくらいに繰り返される口付けは心地よい。呼吸が間に合わないくらい激しく貪られ、頭の奥が少しずつ朦朧としてくる。
絡められる舌に精一杯になっているうちに指が増えていた。玲馨自身に快感がある必要はない。そこが拡がりさえすれば戊陽の物を受け入れる事は出来るので、後孔に引き攣れたようなあの痛みが無いのは幸いだった。
戊陽は後ろをとても念入りに解した。三本が中でバラバラに動いても苦しさを感じないくらいになると、玲馨は「戊陽」と彼の真名を呼ぶ。
「駄目だ。もう少し我慢してくれ」
「ん……」
眉が下がりくったりと力の無い表情で頷く玲馨を、まるで子供をあやすようにして頬に唇が押し当てられる。ここまで戊陽に対して何もしてあげられていないのだが、玲馨が体を起こそうとしたり、手を伸ばそうとしたりすると「待て待て」と必ず止められた。
こうなるともう納得がいくまでやめる人ではないので、頃良く羞恥も消え始めていた玲馨は、己の体をすっかり戊陽に明け渡した。
しかし、それからしばらくのうちに玲馨は後悔する事になる。
指は三本。そこから増える気配は無いが、戊陽の前戯が終わる気配も無い。
「う、戊陽」
「うん、もう少し」
「でもっ……」
「うん」
もはや玲馨の言葉を聞いていない。
熱で溶けて液体のようになってしまった香油がぬち、と粘度のある音を立てる。執拗に弄られたそこはきっと真っ赤になっているに違いない。寝台に零れるほど惜しげなく香油を使われているので痛みは無いが、十分に拡がっても戊陽は指を抜こうとしない。
一体何故、と不安になり始めると、不意に戊陽の指がある場所を掠め、「んぁっ」と思わず鼻に掛かった甘い嬌声が抜けていった。
ぱっと顔を上げた戊陽がまた唇を合わせながら言う。「ひゃっほは」
「ん……っ、ふ、んんっ、あっ、あぁー……っ」
足の指が勝手にぎゅっと曲がって寝台を引っ掻いた。戊陽の指が同じ所を押したり捏ねたりするごとに、声が我慢出来なくなっていく。
眠っていた感覚が戊陽のしつこい前戯のおかげで呼び覚まされたのだ。
「あんっ、あ、声っ、が出るからぁっ」
寝入った村人たちのもとに自分の嬌声が響くかと思うととてつもなく恥ずかしいのに、段々とそうした事に意識が回らなくなっていく。
「安心した。前にあんなに善がってみせたのは演技だったのかと思ったぞ」
「違っあっ」
「うん、寂しい思いをさせたから、鈍ってしまっただけなんだな」
何だか妙に恥ずかしい言い回しをされた気がして下からじとっと睨みつけるも、後孔からせり上がってくる快感がすぐにその目をとろりと撓ませる。
気持ち的に余裕が出たのか、戊陽は変わらず下を弄りながら余った手で胸を撫で始める。そちらも同じく最初は反応を示さなかったのだが、捏ねて吸って噛んでとされているうちに、尻の感覚と結びつくようにして腹の奥を疼かせた。
「もっ……や、ぁっ、戊陽っ、戊陽っ」
まだ物を入れられた訳でもないのにやりどころの無い性感の波に、イヤイヤと玲馨は頭を振り乱す。喘ぎにも泣きが混じり始めた。乱れる玲馨を見下ろして、戊陽は至極満足そうな笑みを湛える。
「腰が揺れているぞ玲馨」
「だって、あんっ、ぅ……っ、んんっ」
気持ち良い、気持ち良い──。頭がいっぱいになるのに戊陽は決して玲馨が極めてしまわないように加減をしていた。せめて出すものがあれば勝手に解放されたろうに、後ろで達するしか出来ない事がこんなにも焦れったく感じたのは初めての事だ。
半ば泣きじゃくるようにして戊陽を呼び続けると、やっと気が済んだのかぬるりと指が引き抜かれていく。半端に弄ばれた熱はしっかりと腹奥で熾火のように燻り、玲馨の意識とは関係なく後孔がひくひくと開閉する。
気が遠くなるほど長い前戯だったにも関わらず戊陽の陰茎はぴんと天井を向いていた。ぶるんと震えるほど屹立したそれは、記憶の中より些か増している。縦も、横も。前戯に時間を掛けた理由が分かると同時、玲馨の喉が鳴った。
──期待、しているのか。あれを突き入れてほしいと、私が……?
性行為を自ら求めた事など未だ嘗てなかった玲馨は、自分の体の変化が信じられない。いや、変わったのは心かも知れない。
ともあれ硬く太く、そしてきっと熱いだろうそれから視線を外す事は出来なくて、自ら微かに腰を持ち上げた。
ふ──と小さく笑ったような呼吸の音がしたかと思うやいなや、ずんっ、と質量が穿たれる。
「──うっ、ふぅぅっ、は、おっ、きい……っ」
「くぅっ、煽るな、玲馨」
恐ろしい事にがちがちに勃起を保ち続けながら戊陽が根気強く柔らかくしたそこは、香油のぬめりを借りてもみちみちと孔をめいっぱい塞いでいく。腹の中の空気が押し上がってくるような圧迫感。しかし玲馨の体は何もかもをすっかり忘れた訳ではなかった。玲馨は上手に力を抜きつつ戊陽の陰茎を奥へ奥へと誘っていく。戊陽の表情に一瞬複雑なものが過ぎった気がしたが、慎重に腰を進める事に集中する。
ごわごわとした下生えの感触が尻に当たると、玲馨はたまらず息を吐き出した。
まるで一仕事終えたかのような充足感がある。動かなくても繋がっているだけで心が満ちているのがよく分かった。
「玲馨」
顔の横に投げ出されていた玲馨の手を、戊陽が杭を打つように寝台に縫い付ける。その手をしっかりと握り返すと、戊陽が幸せそうに目を細めるのだ。
「好きだ」
気持ちが溢れて声に出てしまう。自分でびっくりして、じわじわ照れがのぼってきて、目を逸らそうとしたが戊陽の顔が降りてきて接吻で阻止される。それからすぐに顔を上げると、そこには甘く溶けた中にも切なるものが混じった戊陽の表情があった。
「愛している」
戊陽のあたたかで、感情が直に伝わるような声音に鼻の奥にツンとした痛みが走る。今泣いてしまうのは違うだろうと思った。けれど堪え切れなかった一筋が頬を伝って耳元に落ちていった。
「ああっ、ンッ、んっ、んぅッ」
始めは気遣うようだった動きも、玲馨の顔付きが誤魔化せないほど淫らに蕩ければ、戊陽は律動を速めていった。
先端の括れは出し入れするたび腹側のしこりを引っ掻いて、奥まで突き上げられると腹の奥がひくひくと蠢く。未だ両手はしっかりと戊陽に押さえつけられているので、普段の凛とした姿からは想像も及ばないような玲馨のあられもない声が闇夜に響き渡った。
「だ、めっ、もぅっ、くる……っ」
「ああ、いいぞ。好きなだけ、達してくれ」
「──っひぁぁっ、やぁっ、ああっ!」
玲馨の訴えに、戊陽の突き上げの角度が変わる。腹の中で生まれた泣きたくなるような快感に、戊陽の手をぐっと握り締めて果てた。
閉じた瞼の奥で何か白いものがチカっと瞬き、はぁはぁと荒い息が止まらない。余韻にまで小さく鳴いていた玲馨だったが、しかしすぐにまた戊陽の動きが再開されて目を見開いた。
「待って、い、今はまだ」
「待てないと、何度、言ったら分かるん、だっ」
「ああっ、なん……っ、う、やんっ」
少し落ちつくまで待ってほしいと必死に目で訴えても戊陽は止まらない。達した余韻にひくひくと痙攣する中を、未だ一度も果てていない肉の塊が容赦なく擦りあげ、玲馨は背を弓なり反らせて喘いだ。
戊陽が手を放したかと思うとその手は玲馨の胸に伸び、ぷっくりと存在を主張する乳首を土を捏ねるようにして指の腹で刺激してくる。既に嘗ての性感は取り戻された。乳首の刺激にも玲馨は悩ましげに眉を潜めて胸を跳ねさせる。
「ふ……本当にっ、愛らしいな」
美しい、可愛らしい、そんな美辞麗句は聞き飽きたはずなのに、真っ直ぐに降りてくる戊陽の心底愛しげな眼差しの前には玲馨の頬もかあっと上気していく。尻は無自覚に孔を締め付けて、戊陽が苦しげに眉根を寄せた。
「玲馨、善いか?」
そんな事、顔を見れば一目瞭然だというのに。今の戊陽はとても意地の悪い顔をしている。答えずにいるとわざと律動を緩めて「玲馨」と急かしてくるので、ふいっとそっぽを向いて「善くないはず、ない」と言うと、満足げな笑い声の後に耳元に口付けされる。
「ひっ、ん」
ちゅっ、と水音が耳の間近でする感覚に玲馨が首を竦めると、それを見逃さなかった戊陽が耳たぶを食み、わざとちゅうちゅうと音を立てるように耳をしゃぶってくる。そんな所を責め立てられるのは初めてで、くすぐったいような気持ち良いような奇妙な感覚に玲馨は「あっあっ」と素直に声を上げた。
「も、しつこっ、い」
「じゃあやはり、こちらが好きか?」
訊ねながら戊陽の唇が首筋から鎖骨を通って胸の飾りに触れる。柔らかな唇で吸い付きながら尖端を舌で擦られると甘く痺れるような感覚が背骨を走り抜けていく。
律動そのものは緩くなっているが、戊陽の硬さは失われていない。下から上に向かってゆっくり、玲馨の善い所を圧迫するように押し付けてくる。先程までの激しい突き上げと打って変わってじわじわと追い詰められていくような感覚に、同調するように玲馨の腰も揺れた。
「……このまま、ずっと繋がっていたいくらいだ」
そんな事されては玲馨の尻が壊れてしまうと一瞬真剣に考えたが、そういう意味ではないと分かって「私も」と答えた。
「けど、そろそろ、俺も限界だ」
「出して、戊陽」
ぐ、と尻に力を入れて戊陽の陰茎を締め付けると、戊陽はたまらないような息を吐き出す。そのまま少しずつ速度が上がり始めれば、再び玲馨にも込み上がってくるものがあった。
戊陽のものがいっそう腹の中で硬くなり、間もなく射精するという時戊陽は玲馨を力いっぱい抱き締めた。加減なく潰されるような苦しさに、得も言われぬ幸福を感じながら、玲馨も二度目の絶頂を迎えるのだった。
行為の後はもう指先一つ動かせないと思うほど疲労を感じていたが、どうしても香油のぬめり気が気になって、戊陽の手を借りて身を清めた。他人から世話をされても、他人の世話などした事のない戊陽の手付きは実にぎこちなく、「必ず上達するから」と神妙に言うので笑ってしまった。
暮らし始めてまだ三日の家の中、暗闇を手探りで進むと、玲馨の先を歩いていた戊陽の足元からカコンという軽くて固い音が響いてくる。
「何か指に当たったな」
戊陽が拾い上げるとそれは玲馨の荷を入れていた袋だった。麻で織った目の粗い袋に残っていた物は箱だ。舶来の品で、黒光りのする艶々とした表面に螺鈿の飾りと、金の文様が蒔いてある。于雨に手紙を渡すのに使った鍵付きの箱であり、戊陽からの勅命を記した紙を保管し、そして返事を書けなかった戊陽からの手紙を後生大事に取っておいた思い出深い品だ。そも、この箱自体、戊陽から贈られた物である。
「踏んでしまうような所に置いて申しわけ、ご、ごめん、戊陽」
「……これ、ここまで持ってきてくれたんだな」
「それは、私にとって大事な物だから」
「そうか……」
この箱をくれた事を覚えていてくれたのかと思うと温かく、そして懐かしい気持ちになる。
しばし蓋を眺めていた戊陽は表面を手で撫でてから「開けていいか?」と訊ねてくるのでうんと答えた。
「紙ばっかりだな」
「全部あなたから貰った物だけど」
「俺?」
首を傾げながら窓に寄っていくと、木戸をずらして月明かりに中身を照らしてみる。
「これは勅命の……」
勅命の証である印璽だけが押された白紙を持ち上げて戊陽は笑う。その寂しげな横顔は玲馨の胸を刺した。その痛みは生涯玲馨が抱え続けていかなくてはならないものだ。痛むけれど、そのおかげで今があると思えば苦ではない。
「皮肉だな。最早この紙には何の力もなくなった」
「そうでもない。私にとっては、軽くて……何より重たい物だった」
于雨への手紙を隠すのに箱を使った時、白紙の紙のやりどころに困った玲馨はそれを懐に忍ばせて東江への旅路についた。戊陽からの手紙も同様に持ち歩いていたのだ。あの時はまさか最後はこれを手にして死ぬのだとは思わなかったし、助かる事も想像していなかった。
白紙の下から昔に自分で書いた手紙を見つけると、戊陽は手で顔を覆って嘆息する。
「いや嬉しいんだ。お前がこれを取っておいてくれた事は、箱の事も含めてな。だが、いかんせん昔の俺の詩作があまりに拙すぎる」
正直今もさほど変わらないどころか詩など数年単位で触れていないのでその才は昔より衰えているかもしれない、とは彼の矜持のために言わずに黙っておく。
手紙の方は再び綺麗に畳んで箱にしまうと、白紙の方を月光に透かしながら戊陽は思案する。
「何か気になる事でも?」
「これをこのまま捨ててしまうのは惜しいような気がしてな」
或いは玉座への未練があるのかと思ったがそんな様子ではない。いや、表に出さないだけで、皇帝への未練は完全に捨てきれてはいないだろう。彼は彼なりにやれる事を必死にこなしてきたのだから、何もかもを成し遂げられずに紫沈を離れるのは心残りだったはずだ。
玲馨は戊陽の隣に立ち白紙を覗き込む。
白紙。そう、今二人の人生は白紙になったも同然だ。皇帝は死に、その影武者として一人の宦官が死んだ。
「お互いへの命令でも書きましょうか?」
「命令?」
「そう、もう二度と裏切らない、とか」
冗談のつもりだったが「自罰的なのは良くない」と叱られてしまう。
「だったら誓いを書こう。生涯守り抜く誓いだ。別に破ったって良い。その時はまた新たな誓いを立てるのだ」
「それでは誓いとは言わないような」
「良いんだ、何でも。ただし絶対に諦めない。間違っても失敗しても必ず二人で考えるんだ、どうすれば上手くいくのか。俺もお前も一人で考え込むとよくない事を招く事が分かったからな」
仕方ないような慈しむような戊陽の笑みがどうしようもなく柔らかく、玲馨の目に涙が滲み視線がさまよった。すると戊陽は面白がって覗き込もうとするので肩を押しやって逃げる。
「さて一体何に誓ったものか。印璽もある事だし皇帝か? いや黄龍でもいいな」
「やはりお互いというのは? 私はあなたに、あなたは私に」
目の端を拭って振り返ると呆けたような顔があり、すぐにおかしくてたまらないと笑い出す。
「は、ははっ、いいな。いい! 自由な考え方で、俺は好きだ。よし誓おう、俺は玲馨に誓う」
「ええ私も……ところで、何を?」
「ん? んー……色々だなぁ。嘘を吐かない、一人にしない、寂しくさせない、夜はいっぱい愛する」
「では、私も同じものを、同じだけ。あなたに誓います」
あなたが嘗て与えてくれた自由な心で、生涯あなただけを愛すると。
私はもう、あわいの宦官ではないのだから。
終幕
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
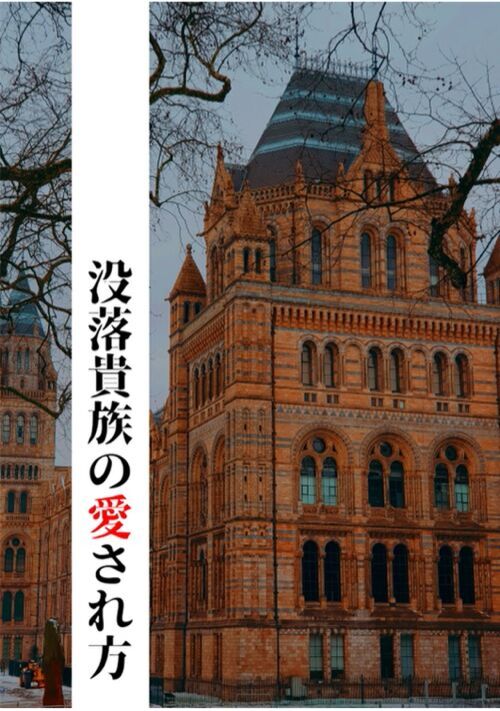
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















